消化器病学の過去,現在,そして未来へ!
日本消化器病学会創立100周年に寄せて
新春鼎談
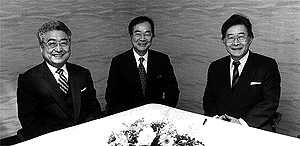 | ||
| 青木照明氏 東京慈恵会医科大学教授 第2外科 日本消化器病学会 創立100周年記念事業 準備委員会委員長 | 佐藤信紘氏(司会) 順天堂大学教授 消化器内科 日本消化器病学会 創立100周年記念事業 準備委員会副委員長 |
石井裕正氏 慶應義塾大学教授 消化器内科 |


草創期の消化器病学:その原点を探る
学際的な性格を持って発会したきわめて稀な学会
佐藤(司会) 日本消化器病学会はアメリカ消化器病学会(AGA)に遅れること1年後の1898年,長與稱吉胃腸病院院長の発案に呼応して創設され,今年は創立100周年を迎えます。そこで本日はこれを機に,これまでの消化器病学の100年を振り返り,また現状を分析するとともに,将来の展望について21世紀のわが国の消化器病学をリードする方々からお話をお聞かせいただきたいと思います。私どもが「創立100周年記念事業準備委員会」の委員を仰せつかり,100年史の編纂をさせていただきましたが,発会当時の状況を簡単にお話しいたしますと,東京で開かれた発会式には,北里柴三郎先生,山極勝三郎先生,三浦謹之助先生ら錚々たる方々が参集いたしました。
発会式の顔ぶれを拝見しますと,当初から細菌学の先生を始めとして,腫瘍病理学や栄養代謝学などの泰斗の方々がお集まりになっています。
通常,学会は身近な有志の研究者が集って創設されるものですが,日本消化器病学会は創立時にすでに,現代風に言えば,さしづめ「学際的」とも評すべき性格を持っていました。これは,きわめて稀な例と言えましょうし,同時に消化器病学の多様性を示唆しているものと思われます。
すでに話題にのぼっていた4方向:癌,生理機能,感染症,栄養
佐藤 また発会式に行なわれた4題の特別講演は,今日の消化器病学の状況を暗示するのに十分な内容でした。まず第1席が山極勝三郎先生の「病理上胃腸及他臓器トノ関係」と題する講演で,当時から大問題になっていた癌が取り上げられていました。
次いで第2席が三浦謹之助先生の「胃病ノ沿革及他ノ内科諸病トノ関係」という講演で,消化液の分泌など消化器の生理機能に関する基礎的な問題を取り扱っています。
続いて,第3席が北里柴三郎先生による講演「消化機器ニ於ケル伝染病ニ就テ」で,感染症を扱っています。主に急性感染症でしたが,腸チフスやコレラなどです。
そして腸管感染症,ことに急性感染症に罹患すると栄養の摂取が悪くなります。そこで,下痢を含めた消化・吸収・栄養の問題が取り上げられました。第4席の長與稱吉会長の講演「胃病患者ノ食餌ニ就テ」がそれです。
つまり消化器の分野の中でも,癌,生理機能,感染症,栄養という問題が当時も話題になっていたわけで,すでに今日われわれが直面している問題を議論されておられていた事実に,私は大変深い感銘を受けました。
青木先生は今年の100周年の記念大会の会長を務められるご予定で,大変ご苦労が多いと思いますが,これまでの100年を振り返って,ご意見をいただけますか。
“消化”“吸収”“栄養”
 青木 ご指摘のように,急性感染症の結果,栄養状態が悪くなるということが昔から話題になっていました。
青木 ご指摘のように,急性感染症の結果,栄養状態が悪くなるということが昔から話題になっていました。
どのような栄養素を摂り,どのように体調を整えるかが,消化器病という学問以前の,消化器そのものの重要な役割であり,課題でもあるわけで,いわば人間の存在の最も基本的な部分は栄養の問題によって決まると言っても過言ではありません。そして特にここ10数年間の研究によって,栄養素の役割,特に免疫との関連が明らかになってきました。
また一方では,慢性感染症における栄養状態が,免疫との相互関係やさまざまな機能性疾患との関係を左右している基本的な問題であると言っても過言ではないと思います。わが国の疾病構成の疫学的変動は,欧米に遅れること20年から30年,場合によると50年はあるわけですが,栄養状態がよくなるにしたがって,その疾病分布や疾病概念が変化しています。
そこで私は,今回100周年を迎えたのを機に,消化器の役割や消化器疾患を考えていく上で,最も基本的かつ根本的な問題としての「栄養の問題」を取り上げたいと思いまして,記念大会においては「Pharmacological Nutrition」,あるいは「Nutritional Therapy」をメインテーマに掲げようと思っています。
佐藤 申し上げるまでもありませんが,消化器病学という学問は機能的には消化吸収という形で捉えられます。したがって,ただいま青木先生からご指摘があったように,栄養との関係が最も重要なポイントになるでしょう。
そして,栄養の問題には当然代謝の問題が絡んできますから,代謝の研究が大変盛んに進められました。そういうこともあって,代謝学は内科だけでなく,青木先生の ご専門である外科の領域でも著しく進歩して,術後の管理や高カロリー輸液療法へと発展してきました。
“栄養”そのものに積極的な意義を持たせて
佐藤 ところで,石井先生は内科をご専門とする立場から,この栄養という問題についてどのように考えておられますか。石井 いま青木先生が「“栄養”という観点から100周年記念大会をとらえ直した」とおっしゃいましたが,私は大変素晴らしい発想だと思いました。
と申しますのも,温故知新,古きものをたずねて新しきを知ると言いますか,新しい観点から栄養を学び直すことは,換言すればいわゆる病態栄養,つまり疾患の発症機序における栄養学的なファクターを位置づけることになると思います。そして,青木先生は「Pharmacological Nutrition」とおっしゃいましたが,これからは薬剤と同じように,栄養そのものに積極的な意義を持たせることが大変に重要なテーマになると思います。
そういう傾向の一端が,現在の Hyperalimentation(高カロリー栄養法)ということに結実しているわけです。また逆に,それがさまざまな病態に取り入れられることによって,今度は過剰な面,つまりOver Nutriotionの面も出てきまして,これに伴って起こる肝障害もあります。
しかし,そういう形を通して,栄養という問題はあらゆる疾患の病態発生,それから治療などすべてのレベルに関与しているにも関わらず,1つのまとまった概念として抽出しにくいのが現状です。ですから,「医食同源」とよく言われますが,まさに食事・栄養というのは医療の根幹である,という否定できない厳然たる事実があるように思います。
ましてや,消化器病を専門とする学会なのですから,「食物の摂取」「消化・吸収」「排泄」を通して必要なエネルギーを得るという過程の中で,「栄養」が担う基本的な重要性があることになります。
消化器病学のその後の進歩:100年を鳥瞰する
「消化器」,「免疫」,「栄養」という切り離せない3要素
 佐藤 それからもう1点,消化・吸収や栄養の問題と同時に,この100年間の消化器病学の領域における研究の進歩として特筆すべきことは,「免疫」の問題ではないかと思います。
佐藤 それからもう1点,消化・吸収や栄養の問題と同時に,この100年間の消化器病学の領域における研究の進歩として特筆すべきことは,「免疫」の問題ではないかと思います。
石井先生,この問題についてご意見をいただけますか。
石井 ご指摘のように,免疫学の研究の進歩と相まって,「免疫と栄養」という問題が近年大変注目されてきています。
特にさまざまな免疫異常の根幹には消化管が存在することが明らかになって,特に小腸の「Peyer patch(パイエル板)」や「GALT Gut associated lymphoid tissue(消化管リンパ組織)」などの役割が大きくクローズアップされてきています。
長期間「Malnutrition(栄養失調)」が続くと免疫機能が著明に落ちることはよく知られていますし,また逆に,長期間高カロリー栄養法を施行しすぎるとGALTが非常に萎縮してきて,免疫機能にも影響を及ぼしてきます。そのようなことことからも,本来は「消化器・免疫・栄養」という3つの要素は,切っても切れない関係にあるのですが,ようやくそうした現代の研究の結果,その重要性が再認識され始めたと言えるのではないかと思います。
そういう点からも,これからはそれぞれの切り口で病態の解明と治療法を創造することによって,栄養学を受け身の形ではなく,さらに「積極的かつ能動的な栄養学」と考える時代に入っていくのではないでしょうか。
佐藤 そうですね。その昔は点滴だけで何十日も生命を維持させることは大変難しいことでした。ところが現在は,高カロリー輸液療法の導入で,そういうことが可能になりました。それだけでも100年前と比較すると大きな進歩と言えるでしょう。
青木 そのお話をさらに一歩話を進めますと,ストレスが起因となる良性疾患と言われる状態が続くと,免疫力が落ちてくることは科学的にほぼ証明されています。ですから,その問題を辿っていくとやはり栄養と免疫の問題になります。
石井先生が言われたように,積極的に疾患の予防や治療に栄養がどのように関わってくるかがわかりつつあるわけですが,その基礎となるものは栄養にありますから,必然的に消化器病学と密接に関わることになりますね。
嗜好品(アルコール)の問題:デベロッピングプロセスを反映する
佐藤 ところで石井先生にお聞きしたいのですが,食物摂取や栄養という問題の一方では,アルコールとか喫煙というような問題があります。これまでの歴史を振り返ってみても,こういう嗜好品は今後もわれわれの生活に密着し続けることでしょう。喫煙については,直接的には肺のみならず,消化器,特に頭脛部,食道に深い関わりがあると思います。石井先生のところでは,昨今増加傾向にある食道癌との関係をかなり大がかりに科学的に証明されておりましたが,こういう問題についてはどのようにお考えですか。
石井 そうですね。ご指摘のように,いわゆる嗜好品と医学との関係は非常に古くからある話です。
ウイルスにしろバクテリアにしろ,あまたある疾患を形成する原因の中でも,それらはすべて自分の意思とは関係なく外から入ってくるものです。ところが,アルコールや煙草は害と思われるものであっても,自分の意思で積極的に取り込んでいるわけです。つまり,同じ害的なものを取り込むにしても,そこに積極的な自分の意思が働いて病気を形成する原因を作るわけです。
そういう意味ではまさに現代病の1つの典型例が,アルコールや喫煙に代表されているのだろうと思います。これは,いわゆるストレスと言われているものを解消する意味で取り入れているにも関わらず,あまりにも過剰なために,それがまた新たな別のストレッサーとなって病態を形成することになってしまうわけです。
ただこういう問題は,例えば,西太平洋とか東南アジアにおいて論じろと言われても難しい問題です。まだ感染症との闘いの真っ只中にいる世界ですから,アルコールを常習的に過飲していても,それが実際に疾病と関係があるかどうかというレベルで論じるまでにはいきません。要するに,その国のデベロッピングプロセスを反映していると思われます。
文明病的な側面も
 石井 しかし,最近この点で明らかな変化が生じているようで,西太平洋地域においてもアルコール関連問題が増加しており,昨年9月に第1回のアジア太平洋アルコール医学生物学会議が東京で開催されました。WHOのHam事務局長も参加され,今後定期的に集会を開催していこうということになりました。
石井 しかし,最近この点で明らかな変化が生じているようで,西太平洋地域においてもアルコール関連問題が増加しており,昨年9月に第1回のアジア太平洋アルコール医学生物学会議が東京で開催されました。WHOのHam事務局長も参加され,今後定期的に集会を開催していこうということになりました。
そういう意味でアルコールや喫煙というのは文明病的な側面もあります。欧米では,特にアルコールの障害は肝臓だけではなく,食道や膵臓にしても,病因的な位置づけが大きな議論の対象になっています。
先ほど,日本の疾病概念や疾病構造は,欧米より20年から30年ほど遅れてキャッチアップしている,というお話がありましたが,その代表と言ってもいいのがアルコールではないかと思います。
現に欧米ではそういう状況を十分に認識していまして,特にイタリアやフランス,ポルトガルなど,主にワインを飲んでいるいわゆるカトリック教国のアルコール消費量は,かつてはわが国に比べて桁違いに多かったのですが,ここ5年から10年で明らかに減っています。
しかし,日本人の約半分が酵素欠損によってアルコールが遺伝的に弱い民族であるにもかかわらず,わが国では全体のアルコール消費量はいまだに増え続けているのが現実ですね。
多臓器を巻き込むアルコール障害:ウイルスや細菌との相互作用
石井 それから,これからも長い年月をかけてウイルスや感染症をさらに検証し続ける必要があるでしょうが,その結果,相対的にアルコールの問題は大きな課題になると思います。例えば,アルコールそのものの臓器障害性に加えて,ウイルスや細菌との相互関係です。肝炎ウイルスのことはこれからお話に出てくるでしょうが,肝炎ウイルスとアルコールとの関連性は今後の大きな研究テーマになるでしょう。また,食道や胃におけるアルコールの問題も同様です。
そしてこれも後ほどお話になるでしょうが,特に最近注目されているHelicobacter pyloriとアルコールとの関連性はもっと認知していかなければいけないと思います。
そういう意味でも,一見地味ではあるけれども,無視できない重要な研究分野ではないかという気がいたします。
佐藤 アルコールは肝臓病だけでなく,最近は膵臓病など全身に関係が広がってきました。一方はウイルスで,かたや化学物質ですが,生体内では似たような炎症反応を起こしているのですね。
石井 そうですね。まさに多臓器を巻き込んでいます。
わが国においては,アルコールが肝障害に占める率は,肝硬変という1つの完成された肝障害を考えた場合にも,平均的に言えば2割ぐらいを形成します。
また他の臓器に関しては,特に慢性膵炎の成因は6-7割がアルコールです。さらに食道癌などはアルコールとの関連がきわめて強いことは明白です。しかも,それは遺伝的にALDH(アルデヒド脱水素酵素)2型のヘテロ欠損と強い関連を持っていることがわかってきました。21世紀に向けてさらに研究が盛んになることが予想される分野の1つに分子疫学がありますが,こういうことなどもその流れにある研究成果と言えると思います。
そういう点からも,アルコールに関わる問題は肝臓という臓器だけを対象として考えていたら駄目で,もっと広く多くの臓器の,しかも癌をはじめとする炎症性疾患や機能的な疾患まで含めて考えるべきです。これはまさに21世紀の疾患につながるものではないかという気がいたします。
H2ブロッカーの開発:まさに革命的デビュー
佐藤 話題が少し跳びますが,消化器病学の発展・進歩を考える際に見落としてはならないことの1つに薬剤の開発があると思います。その中でも,特にH2ブロッカーは1970年代初頭に開発され,わが国でも80年代の初めから使われだしました。これは消化性潰瘍の症状を見事に抑え,多くは1-2か月で潰瘍が治癒するようになりました。
しかし,これは後ほど触れることになると思いますが,その後明らかになった驚くべきことは,潰瘍の根本原因はHelicobacter pylori菌の感染ではないかということです。つまり,酸はただの増殖因子ではないかというわけです。しかしながら,こういう薬剤の開発が大事なことは洋の東西を問いません。その結果,酸分泌機構に関わる研究が進歩し,受容体の構造解析が可能となり,アンタゴニストとか,あるいは分泌に関わる酵素を阻害することによって酸の分泌を100%抑えることも可能な時代になりました。
しかし,潰瘍の原因が本当に酵素異常であるのかということは,分子遺伝学的に証明されていません。酵素異常あるいは受容体異常という,遺伝子疾患ということになれば,酵素や受容体を修飾すればいいわけですが,どうもそうではなさそうです。そう考えますと,現在行なわれている治療は,今後どのような方向に行くべきなのでしょうか。
石井 おっしゃるように,なぜ胃潰瘍になるのかという原因説については,150年前に胃酸分泌亢進における自律神経説が提出されてから今日まで数多くの学説が出されました。そして,いまお話があった最新のHelicobacter pylori説に至っているわけですが,胃潰瘍の病態の中核をなしている胃酸分泌機序に直接作用して治療するH2ブロッカーの登場は,治療薬としてまさに革命的デビューと言っても過言ではないと思います。
つまり,H2ブロッカーの登場以後,胃潰瘍は外科領域から,内科が対象とする疾患へと変化したわけであり,その一方では,外科領域はQOLを追求するプロセスにおいて,minimum invasive surgeryとしての腹腔鏡下の手術へと進展していったと言えると思います。
根本原因はいったい何かを常に考慮しながら
佐藤 疾患の根本的な原因が明確になるまでは,疾患の進展プロセスのどこかを抑えていくことによって治療が成り立つのでしょうね。しかし究極的には,原因に至るところにアプローチしなければいけないのは当然です。根本原因が一体何かということを常に考慮しながら,自分たちが行なっている医療や薬の投与がどういう役割を担っているかを考えなければいけないと思います。
つまり逆に言えば,症状は取ったけれども癌化は逆に進んでしまったという事態が生じることもあり得るわけですね。
青木 そういう可能性はいつも考えておかなければいけないですね。
佐藤 特に消化器領域においては癌を対象とすることが多いですから,症状を抑えていると思っても,他の部位で異なる反応が生じる可能性もあります。
われわれは常にそういうことに留意しなければいけないと思います。
青木 また反対に,良性疾患をコントロールできる薬でも,あるいは発癌を促進していくのかもしれないということをいつも考えておく必要があると思いますね。
佐藤 そうですね。分子生物学などの顕著な進歩などによって,発癌機構が徐々に明らかになってきた今日,根本原因を考えることは,私ども医師が常にとるべき姿勢だと思います。
青木 薬物でコントロールできることは,大変よいことだと思うのですが,それでこと足れりというのはいけません。特に消化器関係の薬物療法にはそういう要素が大きいのではないかと思いますね。
石井 切れ味のよい薬を使用し,患者が一見治癒したかのごとく思って長期的に薬を飲み続けている間に,胃癌が進行している例もありますね。
消化器病学の現在:疾病概念の変遷
感染と癌化について:肝炎ウイルスと癌
佐藤 ところで感染症の話に戻りますが,消化器領域の急性感染はかなり克服されてきましたが,慢性感染症がまだたくさん存在します。かつては感染症は癌と結びついてはいませんでしたが,肝炎ウイルスについては,HBV(B型肝炎ウイルス)自身がオンコジン(癌遺伝子)を持っており,p53を攪乱させること,またC型肝炎は炎症を繰り返すことによって肝機能の再生・増殖をきたし,その間に増殖に関わる遺伝子が変異すると考えられています。
そういう分子遺伝子レベルの研究の進歩の結果,先ほどのお話にもありましたように,慢性ウイルス感染症からの発癌のプロセスが次第に判明してきたわけですが,石井先生,感染と癌化の問題についてご意見をうかがえますか。
石井 ご存じのように肝炎ウイルスと癌との関係が特に問題になっています。
先ほどアルコールとの関係で肝炎ウイルスのことが話に出ましたが,HBVに関してはヒトの遺伝子にも組み込まれるというインテグレーションによって癌化の理論的な背景が出ています。
しかし,HCV(C型肝炎ウイルス)に関してはまだ非常に曖昧模糊としています。長期間にわたる持続的な炎症の繰り返しが発癌につながるのですが,どうしてHCVで発癌するかという点は明確な解答はなされていません。HCVは肝炎ウイルスではあるけれども肝臓だけにとどまらず,もっとシステミックに臓器障害を発現するウイルスであるということが大変注目されているわけです。
HCVは肝細胞親和性のあるウイルスであると同時に,末梢血の単核球,あるいはリンパ球に非常に親和性があります。そこで,長期間の感染によって起こる「悪性リンパ腫」とHCVとの関係が注目されてきているのですが,それに加えて口腔内癌とHCVとの関係も関心の的になっています。特に前癌状態とされるleukoplakia(白斑症)やlichen planus(扁平苔癬〔たいせん〕)では,その組織レベルにおいてもHCVが高頻度に見られるので,肝炎ウイルスの中でHCVは広く悪性リンパ腫,あるいは口腔内癌ということも含めて,肝外病変との関連についても今後一層注意を払う必要があります。
佐藤 肥大型心筋症にも関係があるという報告もありましたね。
石井 そうですね。
Helicobacter pylori感染症
石井 感染と癌化については胃疾患について論じますと,まず胃悪性リンパ腫ではそのメカニズムは不明ですが,先ほどのお話にもありましたHelicobacter pylori感染がその発生に関与していることが知られており,その除菌が治療法の1つとして位置づけられています。胃癌に関しましては,1994年にWHOが「Helicobacter pyloriはdefinite carcinogenである」と結論づけましたが,まだ直接的証明はなされていません。その点,厚生省の「がん克服新10か年戦略事業」に一環として企画されているprospectiveな除菌治療は重要な意義を持っていると思われます。
疾病の予防という観点から考えますと,21世紀に向けてHelicobacter pylori菌と癌化の問題に真剣に取り組まなければならないことは言うまでもありません。
Helicobacter pyloriと胃癌発生の因果関係を証明するために必要なことは,まずHelicobacter pyloriに感染可能な実験動物系の確立と,それによる発癌実験でしょう。Mongolian gerbilを用いた実験は期待の持てるものです。
臨床的には,Helicobacter pylori除菌による胃癌増殖の抑制効果の確認と長期にわたる丹念な臨床治験をprospectiveに行なうことだと思います。
佐藤 これは疾病概念の変遷という話題に関連するのですが,ウイルスの話が出ましたが,石井先生もご指摘なさいましたように,現在は胃炎・胃潰瘍と癌がHelicobacter pylori感染症でつながり始めましたね。これまでは潰瘍と癌はあまり関係ない,まして胃炎と癌とはまったく関係ないと思われていました。
また一方では,食道癌も逆流性食道炎や食道炎がベースになって起こるバレット上皮と関係があります。これまで癌とは関係ないと思われていたものが相当な割合で癌化することがわかりました。
UC(潰瘍性大腸炎:ulcerative colitis)やCD(クローン病:Crohn disease)などのIBD(炎症性腸疾患:inflammatory bowel disease)もそうです。これらは長期間にわたる内科的治療ができるようになってきたけれども,癌化という観点から患者さんのQOLを考えると,早めに外科的切除をしたほうがよいのではないかということも言われるようになりましたね。
良性の器質的疾患
佐藤 そのように考えますと,癌化と関連があるウイルスやバクテリアなどの感染源の検索がこれから大きな問題になるのでしょうね。21世紀にはそれらがさらに,またかつ急速に解明される時代になると思います。この点について,青木先生,何かご意見はございますか。
青木 そうですね。先ほど少し申し上げたのは,癌の予防と早期治療という問題を考えていく場合,どうしても慢性感染症の成り立ちを考えなければなりません。つまり,免疫力や栄養との関係で申し上げましたけれども,実際はそういう従来良性疾患であって,癌と関係のない器質的疾患と言われてきたものが,実は発癌のfields carcinogenesis のような形で発癌と非常に大きな関連を持っていることがわかってきました。そういう器質的な良性疾患も実は慢性の感染症の成り立ちの中で存在しているということは大きな問題ですが,ほぼわかりつつあります。
そして,さらに一歩進めると,ストレスや器質的な疾患が認められない,例えば上部消化管で言えばNUD(non-ulcer dyspepsia)と言われるような疾患ですね。そこには慢性胃炎や逆流性食道炎や運動異常といったような疾患も入ってきます。そしてそこには,それらの環境を作っている人間の自律神経系の問題などの機能的なものと切っても切り離せないものが残ってくるわけです。それで,器質的な良性疾患と言われてきたものも長期にわたれば発癌の母地になるということもほぼ解明されつつあります。
佐藤 ええ。同じことがIBS(過敏性腸症候群:irritable bowel syndrome)についても言えますね。
青木 そうですね。ですから,機能性疾患と言われているものがどの程度,またどのような理由で機能異常を起こしているのか。ストレスによる良性疾患と言われるものも,ある状況でストレスが慢性的に続くと免疫力が落ちますから,やはりそこを辿っていくと栄養と免疫の問題に行き着くことになります。
それから「生活習慣病」と申しますか,人間の個体としての精神状態の社会的な存在としての反応性の問題,そういうところに行き着いてあまり科学的ではないような話になってしまいますが(笑)。
栄養の問題というのは,そういうとらえられ方をしてきたわけです。
ところが,最近になってどの栄養素がどのように疾患と関わっているか。また,石井先生が先ほど言われたように,疾患の予防や治療に特定栄養素が積極的にどのように関わってくるかが明らかになりつつあります。その基礎になるのはやはり栄養ですから,消化器病学の領域になりますね。
慢性感染症と免疫・栄養
佐藤 青木先生,外科のお立場からは慢性感染症についてはいかがでしょうか。青木 そうですね,時には「内科」とか「外科」という垣根を越えて考えることも必要だと思いますので,消化器病学全体としてとらえてみますと,やはり慢性感染症の成り立ちには,先ほど申し上げたような栄養・免疫,そして慢性感染症を成り立たせる感染源,その3つの関わりがあります。
そして,その3つの関わり合いの中にいて,さまざまな遺伝子異常などが加わることによって,発癌の問題が発生してきます。そういうことを背景にして,早期発見や早期治療,例えばミリ単位の肝癌の診断や治療という問題が出てくるわけです。
それから,私が強調したいことは胃癌の成り立ちについてです。特に日本人の胃癌の成り立ちのかなりの部分は,いま言った慢性の感染,創傷治癒の繰り返しの中で発生したものです。
これは明らかに欧米人とは異なっていて,栄養素の摂取,つまり脂質の摂取量の違いなどに起因するものが多いと考えられます。
佐藤 ビタミンの関与も考えられますね。
青木 ええ。ビタミンの関与もあります。そのような明らかな栄養状態の違い,ホスト側の免疫力の違いなどの中で成り立っていくわけです。
大腸癌についても,「adenoma-carcinoma sequence(腺腫-癌連鎖)」と言っても,それはやはりホスト側の免疫力の違いとかDNAの損傷の修復力の違い,そういうところからきているわけですね。それさえも栄養素の補給の仕方,ビタミンの取り方によって修復がきちんとできるのではないかという意見も出てきています。
くり返しになるようですが,先ほど石井先生が言われたように,これからは栄養や代謝との関係の中で免疫力がどのように変化するか,という問題を消化器との関わりにおいて,研究を積極的に進めていくべきだと思います。それがまた癌の予防や癌の早期治療に関わってくると思います。
現に,胃癌の中でも特に日本人に多い腸型の癌などの治療概念は一変しました。早期治療の場合は,内視鏡的な治療や局所治療でよいことなど,広がり方の違いもわかってきました。慢性感染症がどういう形で確立されるかが治療の選択の判断につながってきます。
もし,そういうことによって21世紀に早期治療が可能になってくるとすれば,「癌大国」という日本の汚名は,1世代が交代する30年ぐらいの間に,ガラッと変わってしまうのではないかと思います。
栄養と免疫ネットワーク
佐藤 子どもの頃の感染,あるいは垂直感染など,免疫機能がまだ十分に成立していない時の肝炎ウイルス感染が慢性化し,それが癌化へとつながっていくことが明らかになりました。ということは,免疫力というのは年齢の発達とともに強くなり,栄養が低下すれば喪失することになりますが,それでは何によって規制されているのかという問題が出てきます。現在は,ワクチンの開発で感染を断ち切るという方向に進んでいますが,先ほども少し話にでましたが,「免疫力を高める栄養」の問題については,石井先生,いかがでしょうか。
石井 栄養は経口的ルートで補給される場合と,TPN(total parenteral nutrition:完全静脈栄養)などの非経口的ルートで行なう場合とでは免疫ネットワークへ与える影響に大きな差異が生じます。
TPNは食事摂取の不十分な患者の栄養管理に広く応用されていますが,その結果腸管粘膜萎縮を来たし,さらに感染への抵抗力を減少させたり,bacterial translocationを来たしやすいことがわかっています。長期間TPNでラットを飼育すると,T細胞数の減少を伴うパイエル板の減少がが顕著に見られます。これは経口摂取の刺激がGALTの機能と形態を維持するのにいかに重要かを示唆しています。
その点,elementary dietは腸管免疫系への影響も少なく,過剰な炎症・免疫系のネットワークをコントロールできる可能性があります。
21世紀に向けた消化器病学:未来を眺望する
低侵襲治療が持つ二面性
 佐藤 さて,駆け足で消化器病学の100年を振り返るとともに,現状を総覧してみました。もちろん短時間ですべてを網羅することはできませんが,時間も迫ってきましたので,このへんで将来への展望という話題に移りたいと思います。
佐藤 さて,駆け足で消化器病学の100年を振り返るとともに,現状を総覧してみました。もちろん短時間ですべてを網羅することはできませんが,時間も迫ってきましたので,このへんで将来への展望という話題に移りたいと思います。
青木先生,先ほど石井先生から低侵襲手術というお話が出ましたが,外科手術において最近低侵襲治療ということが盛んに言われています。この治療方法は,次の時代はどういう方向に向かっていくとお考えでしょうか。
青木 手術と言いますと,患者さんがイメージすることはまず,「痛い,恐ろしい!」ということでしょうね。これは本能的なものだと思います。
そういう点からも,低侵襲手術という治療方法は,傷を小さくすることがまず第1の条件です。というのも,病巣がどこにあるかが術前にわかっていても,そこに到達するために健全な表皮やその外を覆っているところを切り開かざるを得ません。これが外科治療の最大のネックです。それを最小にするために,例えば血管をルートする方法や小さな穴から到達する方法,あるいは消化管や内視鏡を通じたルートを利用して,侵襲そのものを小さくするわけです。
しかし,そうは言っても,一例を上げれば,皮膚を5㎝ほど切るにしても,そこにはさまざまなサイトカインが作動して,全身的な反応を起こします。また内分泌的な防御機構が動員されて,ただ単に「痛い!」ということだけではなく,体の侵襲に対する反応が起こってくるわけです。そのような現象をミニマムにすることが,現在のテクノロジーの進歩によって可能になってきたわけです。
また例えば,表皮の侵襲をいかに小さくしても,臓器の一部を取り除くという侵襲は必然的にあります。それに対して,脊髄の交感神経あるいは知覚神経を創傷治癒が完成するまでの間,中からブロックしておくことによって,あたかも体の中の一部を隔離したような形で積極的に侵襲をブロックする。そういう意味での低侵襲という考え方が2つ目にあります。
つまり,低侵襲手術という概念には,到達するためのルートを工夫することによる低侵襲という意味と,与えられる侵襲を積極的にブロックするという意味の両面があります。わかりやすく言えば痛くない手術ですね。
佐藤 ご指摘のように,侵襲に対する反応をいかに小さくするかという研究がこれから進められていくと思います。
外科手術というのを一歩裏返してみれば,侵襲に対する反応をいかに上手く抑えるかという問題にもなります。こういう問題を解決することが,次の世代には必要な課題になるのでしょうね。
青木 与える侵襲を少なくすることがまず第1の目的ですが,もう1つは与えられた侵襲に対して生体の反応をどうコントロールするかという問題があります。この二面性を低侵襲手術は持っているわけです。
特に後者の面についての研究がかなり進歩してきました。
佐藤 最近,外科の先生方が青木先生がおっしゃられた外科に関連した生体の動きをよく研究され,遺伝子のレベルまで検索されていますね。
先ほど,青木先生は「外科と内科の垣根を越えて考える」と言われましたが,そういう点では,外科医も内科医と同じ立場に立って研究する必要があるのでしょう。やはり,そういう低侵襲外科手術に対する生体の反応をきめ細やかに検討していくということも,これからの外科医に求められるのでしょうね。
青木 そうだと思います。
佐藤 石井先生のご意見はいかがですか。
石井 ご存じのように,1990年に腹腔鏡下胆嚢摘出術がわが国に導入されて以来,低侵襲手術の代表として内視鏡下手術が急速に普及しましたが,青木先生がご指摘なさったような,低侵襲手術が持つ二面性を十分に認識することが必要だと思います。 そしてまた21世紀に向けて,今後その適応を拡大し,より安全に,かつより容易に行なうためには,新しい技術を開発して導入していくことも必要だと思います。
臓器移植について:外科医の立場から
佐藤 それから,昨年秋に「臓器移植法案」が成立いたしました。消化器病学に関連する事項としては,特に肝移植が注目されるところですが,将来展望も含めて外科医のお立場から青木先生のご意見をお伺いしたいのですが。
 青木 外科医の立場からしますと,臓器移植は疾病(臓器単位)の究極の治療であり,外傷の治療と並んで21世紀に残される外科の大問題と考えています。
青木 外科医の立場からしますと,臓器移植は疾病(臓器単位)の究極の治療であり,外傷の治療と並んで21世紀に残される外科の大問題と考えています。
しかし,臓器そのものの移植にはドナーが必要で,1個体の治療のために他に1個体の消滅が必要であり,そうした意味ではいずれ倫理的に行き詰まる可能性を考えておかねばいけないと思います。
そして次の段階として考えられることは,人工臓器の開発になると思います。現在よりもさらに生体に近い状態で,機能を「移植」できる方法としては,細胞培養のテクノロジーの進歩とともに,「細胞移植」が夢を与えてくれます。
しかしこれを実現するためには当然,遺伝子治療による「細胞」に不死化,しかも機能温存と非腫瘍化,さらにまた免疫制御が条件となります。
佐藤 臓器移植は人工的な代替臓器ができるまでは,相当幅広く行なわれるでしょうね。しかし,究極的なことは人工臓器の開発研究ではないかと私も考えています。
もう1つ,臓器移植医療の大事な側面は,免疫というこれまた重要かつ進歩の著しい研究の発展に貢献することでしょうね。そういう面では,臓器移植の問題はまだこれから膨らむでしょう。
ロボティックスを用いた遠隔操作
佐藤 それから,先ほど石井先生からもご指摘がありましたが,最近は内視鏡などを用いて,画像を駆使した手術がかなり施行され始めてきました。そしてそれに加えて,将来はロボットを用いた手術も可能になるかもしれません。青木先生,見通しはいかがでしょうか。青木 すでに特定の手術ではロボット工学のテクニックが取り入れられています。
アプローチする場所をわずか0.1㎜単位の正確さで捉えていくようなことは,脳神経外科の分野でも行なわれています。その他の分野においても,ロボティックの技術が外科手術に応用され始めていますから,この技術が普及するのも時間の問題だと思います。
佐藤 そうなってくると,遠隔操作なども可能になってくるのでしょうね。
青木 ええ。1つの器具を通じての遠隔操作ですけれども,いまや胸腔鏡や腹腔鏡下で行なわれています。
これがもっと正確にコンピュータライズされて,まさにロボットと同様に,入力して何100分の1㎜のところを切れというようなことまでも可能になる時代がやってくると思います。
石井 私も同感です。内視鏡下手術において,縫合などで物理的に不自由を感じる手術操作に対し,ロボティックスの応用が期待されると思います。実際に腹腔鏡をロボットに操作させて手術者自身が足スイッチで操作するシステムを臨床応用されていると聞いてますが,期待される分野ですね。
私が特に今後期待すべきものとしては,3次元ハイヴィジョン映像,ロボティックス,そしていまご指摘のあった遠隔操作を用いたテレサージャリーなどがあります。これらの新しい技術を駆使することによって,外科手術の変化は想像以上に急速に進展することが予想されます。
疾患の予防
佐藤 消化器医,Gastroenterologistとして,明るい展望が開けてきました。青木 しかし,そのような新しい技術の導入は最終選択肢であって,しかも十分に精確性が保証されていることが必須です。
手術をしなければ治らない,という結論になる過程をもっと突き詰めて考えるべきでしょう。疾患があるから治療するのではなく,疾患の予防にもさらに大きな努力を払うべきでしょう。
佐藤 予防という話になりますと,現在の保険診療のもとでは,薬剤の使用から始まって大変制約が強いですね。
これは行政側とも相談しながら進めないといけませんが,新しい医療を導入することによって費用効果がこれだけ改善されるという具体的なデータを示すことも必要でしょう。
 石井 そうですね。疾病の本態が明らかになるにつれて,それまで1つの線で結べなかった独立した疾患がお互いに関連し合って,最終的に癌に至るような場合,その連鎖を断ち切るには早期からのinterventionが必要になってくるわけです。
石井 そうですね。疾病の本態が明らかになるにつれて,それまで1つの線で結べなかった独立した疾患がお互いに関連し合って,最終的に癌に至るような場合,その連鎖を断ち切るには早期からのinterventionが必要になってくるわけです。
その点,現在の保険診療下の医療システムでは満足のいく診療は困難かもしれませんが,1つひとつ解決していく方法しかないと思います。
青木 くり返すようですけれども,良性疾患があるプロセスを経て悪性疾患の成立に関係があることがわかってきているのですから,予防措置を講じさせないのは医療制度に問題点があるわけです。
先生がおっしゃる通り,それができるように,考え方を根本的に見直していく必要があるのではないかと思います。
佐藤 21世紀には,消化器疾患に限らずすべての疾患の診断・治療・予防において,費用効果のみならず,QOLの向上をめざした国民医療が進むとよいですね。
今日はお忙しいところをどうもありがとうございました。
