医学生・研修医版[8]1997. OCT.
座談会 がん診療におけるmedical oncology
 | |||
| 福岡正博氏 | 渡辺 亨氏(司会) | 勝俣範之氏 | 小野裕之氏 |
| (近畿大教授・第4内科) | (国立がんセンター中央病院・内科医長) | (国立がんセンター中央病院・内科) | (国立がんセンター中央病院・消化器科) |


「内科腫瘍学」とは何か
日本のがん診療の現状と問題
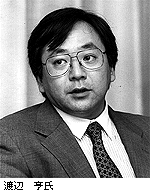 渡辺 日本のがん診療において,欧米ではその中心的な役割を果たしているmedical oncology(以下,「内科腫瘍学」)は存在しないという声も聞かれますが,今日お集まりの先生方は,「内科腫瘍学」をすでに日本で実践されている方々です。まず最初に,この「内科腫瘍学」とは何かを考えたいと思います。福岡先生,この「内科腫瘍学」とはどのようなものなのでしょうか。
渡辺 日本のがん診療において,欧米ではその中心的な役割を果たしているmedical oncology(以下,「内科腫瘍学」)は存在しないという声も聞かれますが,今日お集まりの先生方は,「内科腫瘍学」をすでに日本で実践されている方々です。まず最初に,この「内科腫瘍学」とは何かを考えたいと思います。福岡先生,この「内科腫瘍学」とはどのようなものなのでしょうか。
福岡 「内科腫瘍学」は,最近よく使われますが,日本では確立されていません。私が考えているのは,「薬物療法を中心とした戦略でがん治療を行なうこと」だと思っています。がんの診療には,治療だけでなく病態や疾患そのものの把握,そして緩和医療などの領域も含めた理解が必要です。一方,わが国では現在,臓器専門の医師,例えば大腸がんや乳がんは外科,卵巣がんは婦人科でがんの化学療法が行なわれています。しかし,メディカル・オンコロジスト(腫瘍内科医)という場合には,すべての臓器のがんについてある程度の理解が必要であり,特に薬物療法に付随した種々の問題に十分対処できるトレーニングを受け,臓器という枠組みから独立したものであるべきと思います。
渡辺 小野先生はいかがですか。
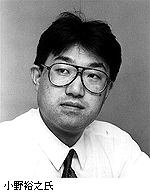 小野 いま福岡先生がおっしゃったように,臓器に関係なく薬物療法中心というのが,今の「内科腫瘍学」の定義だと思います。逆に言うと,それも薬物中心の1つのセクションになりかねない部分があると考えられます。ですから,横の広がりとして,他科を含めた全体のがんに対する薬物療法そのものを押さえておく必要があると思います。
小野 いま福岡先生がおっしゃったように,臓器に関係なく薬物療法中心というのが,今の「内科腫瘍学」の定義だと思います。逆に言うと,それも薬物中心の1つのセクションになりかねない部分があると考えられます。ですから,横の広がりとして,他科を含めた全体のがんに対する薬物療法そのものを押さえておく必要があると思います。
もう1つは,サブスペシャリティとして胃がんや大腸がんなどに対する診断から,早期のものには内視鏡治療を行ない,なおかつ進行がんには薬物療法も行なうという,縦と横がある程度組み合わさったものが必要ではないかと考えています。
渡辺 勝俣先生はどのようにお考えですか。
勝俣 「内科腫瘍学」とは,内科学の中でも比較的新しい概念の学問体系だと思うのです。抗がん剤が開発される以前は,外科医がメインにがん治療を行なっていました。しかし抗がん剤の種類が増え,また社会的にもインフォームド・コンセントや,ターミナルケアへの関心が高まるようになってきました。そこで,内科医ががん患者を診る機会も増え,世間のニーズというか学問的なニーズから「内科腫瘍学」が生まれてきたのではないかと思います。
日本も今,移行期の段階にあると思います。近年,多彩な作用機序を持った抗がん剤も開発され,抗がん剤の使い方が非常に難しくなり,そこから「内科腫瘍学」といった専門的な知識を持った人が必要になってきたと思うのです。
がん診療の縦と横の広がり
渡辺 3人のお話を整理すると,「内科腫瘍学」とは,内科学の一分野であり,治療学を重視した領域であることがまず1つのポイントで,その意味合いが大きいということですね。私は大学を卒業してから15年ほどになりますが,当時に習ったことを思い出しても診断学や病態生理の講義が中心で,ポリクリやベッドサイドトレーニングでも治療学はほとんどありませんでした。ですから医師になり,国立がんセンターで初めてがんの治療学を系統立てて勉強したのです。
治療学の観点で見ると,「内科腫瘍学」は抗がん剤を主体とした治療となります。同時に病態生理を把握した上で,疼痛,全身倦怠,呼吸困難,食欲不振など,がん患者に現れる様々な症状に対する治療,すなわち緩和医療(palliative medicine)も腫瘍内科医の守備範囲であると思います。一方,腫瘍内科医の対象疾患は何かと考えた場合,2番目のポイントとして,横の広がりと縦の広がりというX軸,Y軸の考え方が重要となります。つまり横の広がりとは,例えば抗がん剤治療のようなモダリティですね。治療学,診断学,それから基礎的なところで病態や疾患の把握,そして患者を知ること,これらは,すべてのがんに共通するのです。この点については「内科腫瘍学」の基礎的な部分として,ある程度の素養を持たないといけません。そこで,直交する軸,つまり縦の広がりとしてそれぞれの臓器があります。1人の医師がどれくらいの疾患を対象として診療するかということについては,病院の規模や性格により異なると思います。例えば,国立がんセンターのようながん専門病院では,ある程度のサブスペシャリティが確立していて,主に乳がんを担当するとか,悪性リンパ腫の専門家という色分けができています。
そうすると,いろいろながんを対象としているということだけでなく,病態や疾患の把握,治療手段である抗がん剤の特性の把握をしなくてはいけない点が,腫瘍内科医として要求されるものだと思います。
勝俣 今までは,例えば呼吸器内科医が肺がんを,消化器内科医が消化器がんを診るという,がんを専門とする医師は臓器別に縦割りされた内科の各分野の中では少数派グループなんですね。
福岡 疾患としては一番多いですよ(笑)。
小野 縦糸と横糸の話ではないですが,今までは各臓器別の専門医師が,がんも治療していました。しかし,これからはそうではなく,腫瘍内科医が臓器がんをある程度専門に診ることが必要だと思います。
「内科腫瘍学」を実践するには,ターミナルケアの薬の使い方やインフォームド・コンセント,臨床研究の立て方など様々なことを知った上で,腫瘍内科医がある程度限られた臓器がんを診ていくのが理想的だと思います。
福岡 僕はよく言うのですが,肺がんとはたまたま肺にできた“がん”であり,呼吸器疾患の1つではあるけれど,異なるカテゴリーのものだという認識が必要です。呼吸器科の人が肺がんも治療する,婦人科の先生がお産をしながらもう片方でがんの治療をするのでは,片手落ちになってしまうということです。
例えば,どんな抗がん剤を使っても肺臓炎が起きるでしょう。ところが肺臓炎が起こると,呼吸器科へ紹介せざるを得ないのが現状です。そこで腫瘍内科医である以上,薬剤性の肺臓炎が起こればきちんと対処することが,今の日本ではできていないのです。
渡辺 従来の内科の細分類でみると,福岡先生もおっしゃいましたが,同じ呼吸器の専門家として,ぜんそくと肺がんを両方診るのが当たり前のように言われています。しかし,必ずしも必然性があるわけではありません。
福岡 まったく違う病気ですからね。
渡辺 例えば,肺がんと乳がんと消化器がんを「抗がん剤治療」という枠でカバーできる人がいるほうが,必然性があるということです。
そうすると,なんとなく「内科腫瘍学」の実際の姿,われわれがめざすところが見えてきたと思います。がんという病気の治療は,今まであまりにも外科偏重でした。白血病はまた別ですが,固形がんは外科偏重で,腫瘍の生物学に関係なく,丸いものを四角く切り取って治療するという考え方がいまだに幅をきかせているのです。
国立がんセンター中央病院(以下がんセンター)でも総ベッド数550のうち内科はわずか130足らずで,あとは全部外科なんですね。いかに今まで早期発見,早期外科切除が唯一の治療のパラダイムであったかがわかります。しかし今後は,腫瘍の生物学によっては,きわめて早期でも悪性度の高いものは,最初から全身疾患としてとらえる必要が出てきます。そうすると外科だけではなく,内科の中からがんをもっと一所懸命診る人が出てこなくてはいけないですね。
インフォームド・コンセントの問題
渡辺 今まで世間でそれほどがんの専門家が必要とされていなかったのは,患者さんはがんと告知をされていなければ,特別にがんの専門家を求めないというのも,1つの原因ではないかと思います。しかし,がんであると告知された場合,患者さんはその専門家に診てもらいたいというモチベーションが働くと思います。その点と「内科腫瘍学」に対する社会的ニーズの増大とは無関係ではないと思います。小野 私が一般病院にいた5年間,告知をしたことがありませんでした。実際に周囲の医師もしないし,肺がんを「胸膜中皮腫」といって治療していました。
しかしがんセンターに来て,逆に「告知をして当然」の雰囲気があり,自分もするようになって,それで初めて患者さんのリアクションがわかったところがあります。結局,告知しない所はいつまでもできなくて,誰もどうすればいいのかわからないのです。
勝俣 それを教えてくれる人がいないんですよ。
小野 だから実際に告知ができるような状況を作ることが大事なのだろうと考えています。
告知についてはいろいろな考え方があり,ケース・バイ・ケースであるとか,家族との関係などがありますが,私ががんセンターに来て「俺たち医者は神じゃない。だから,この人には告知をしてよくて,この人にいけないとは,俺たちが決められるわけがない。それは傲慢だ」と言われました。本当にその通りだと思います。
勝俣 「末期医療に関するケアの在り方の検討会報告書」の中の告知をしてよい条件として,「患者に受容能力があること」とありますが,それを私たちが決められるかどうか。また,告知をしないということは,放射線や抗がん剤に関しても説明されずに治療が行なわれてしまうことになり,治療を受けるか受けないかという患者の選択する権利も奪ってしまうことになりかねません。
小野 そういう患者の自己決定権を私たちが勝手に奪ってしまうことは許されないのではないかと思うのです。
福岡 1つは,「腫瘍内科医」である以上,抗がん剤を使いますが,告知していなければ,これは抗がん剤だとは患者さんに言えません。しかし,抗がん剤と言わずに抗がん剤を使うことは,非常に大きな問題です。ですから,告知をしなければ治療はできないのです。そこを理解しないといけません。でも,われわれも以前から実行していたわけじゃなく,最近になって自覚しているのですが。
渡辺 抗がん剤治療の場合,特に適応と限界がはっきりしています。ある疾患は抗がん剤で完全に治すこともできますが,一方でまったく効かない場合も確かにあるのです。インフォームド・コンセントや,患者さんに状況を正しく説明することが重要になってきます。今まで,そういうことを見きわめた説明がなされてなかったので,社会的問題にもなった,これまでのがん治療に対する批判が出る背景もあるわけです。今までがんの非専門家が行なってきたことに対して反省する時期であるという社会的な動きとも一致して,腫瘍内科医を養成していくことが必要となってきたのです。
がん診療の世界的な動き
渡辺 日本のがん診療の問題点をいろいろお話いただきましたが,ここで世界の動向や,「内科腫瘍学」が海外ではどういう形で定着しているのか,欧米との対比において日本はどうかを考えたいと思います。よく日本は遅れていると言われていますが,必ずしもそうでもなく,素晴らしい論文が次々に出ているように,ある面では日本がリードしている場もあります。しかし,総体として見た場合にどうなのでしょうか。
福岡 やはり遅れていると思います。欧米では腫瘍内科医が,婦人科がんであろうが悪性リンパ腫や肺がんであろうが治療できます。ただし,各々サブスペシャリティ分野がありますが,腫瘍内科医という点では共通してすべての教育を受けています。日本はどちらかといえば,外科医のほうが化学療法を行なうケースが多い分野もあるという点が大きな違いです。
それから,肺がんのように手術で治りにくい分野では,日本でも内科医の活躍する場が出てきましたが,手術が第一選択になる腫瘍では,まだ内科の力は弱いというのが,日本の腫瘍学の現状ではないですか。
渡辺 そうですね。臓器ごとの話題が出ましたが,日本では,内科の教科書に肺がんや消化器がんなどは出てきますが,乳がんなどは名前すら出てこないですね。日本では乳がんは外科疾患と認識されていて,もちろん手術は外科が行ないますが,手術後の化学療法や,再発後の薬物療法,終末期医療なども全部外科医が担当しているのです。
外科医が担当して悪いということはないと思います。しかし,例えば「転移性乳がん」を治療することを考えると,抗がん剤やホルモン剤などに関する知識もさることながら,内分泌的な知識や電解質異常,感染症など,まさに内科学の基本的な見識が要求されます。内科的,外科的という区別は手術をするかしないかという点だけではなく,内科医はもとより,生物学的な考え方をする,外科医は機械的な考え方をする,そういった目でみると,全身に影響を及ぼすような病態である転移性がんは内科的な考え方,アプローチがより適していると思うのです。
私は日本では数少ない乳がん専門の内科医ですが,乳がんを「内科腫瘍学」の切り口で,その他の疾患も担当することができ,乳がんも診療できる若い医師が育ってきていますので,その点では,今は欧米に遅れているかもしれないが,だんだんとあるべき方向に向かっているのではないかと思います。
腫瘍内科医になるために
研修医のためのがん診療のマニュアル
渡辺 いままでお話いただいたような状況に対応すべく,小野先生,勝俣先生,また山本信之先生(現近畿大・内科)ら,がんセンターのレジデントが中心となって執筆した『がん診療レジデントマニュアル』(医学書院刊)が出版されました。どのような経緯で本書の作成にいたったのかをお話ください。小野 1つには,臨床の現場ですぐに使えるような実践的なマニュアルが欲しかったことです。今までの抗がん剤の説明は薬剤が並べてあるだけで,実際にどうすればよいのかがさっぱりわからりませんでしたし,あるいは胃がん,大腸がんにいろいろな多剤併用療法を行ない,その有効率だけが書かれてあったりという具合でした。
勝俣 化学療法のマニュアルというのがよくありますが,ただ薬が並べてあって,どれをファーストチョイスにするのかよくわからなかったということがありますね。
小野 有効率が書いてあるから,一番高いのでいいのかなと,医師になって1年目の時に使って,はまってしまったことがありました。あるステージのがんの患者さんが来たときにこうするんだということが,実際に読むだけでプラクティカルにできるようにとしたつもりです。
勝俣 本書を作った目的は,今は一般病院でも内科の研修医や医師ががんを診る機会が多くなってきたので,一般病院でも使えるようなものにしたかったことでもあります。
自分も研修医の時にがんの患者さんを診たのですが,誰も疼痛コントロールやインフォームド・コンセントについて教えてくれないし,抗がん剤の使い方も知っている人は非常に少なかったのです。ターミナルケアも自前では経験があるけど,学問的に経験のある人はほとんどいなかったので,日本にこのような専門家はいないのかなと思ったんですね。それで欧米にはそういう専門医がいることを知り,自分も腫瘍内科医をめざそうと思うようになりました。
本書では,各臓器の抗がん剤の使い方に固執するわけでなく,疫学からがんの診断,治療までを書いてあります。化学療法だけでなく,腫瘍内科医は最低限の知識として,がんの診断,外科治療,放射線治療まで一通りは知っておかなければならないと思います。
小野 がんの背景を学んで,なおかつどのような治療をするかは,できるかぎり「evidence‐based medicine」(後述)の概念を使って書いたつもりです。
勝俣 そうです。evidenceがないものは削除するか,何らかの注釈を加えるようにしました。また,抗がん剤の使い方だけでなく,インフォームドコンセント,疼痛コントロール,緩和医療などについても実践的な内容にするように力を入れました。
小野 そういう意味では,例えば疼痛のコントロールでは,実際にはどう使ったらいいのかはわからないことが多いでしょうから,モルヒネの換算など細かく書いたつもりです。
渡辺 実際的に役立つもので,主にがんセンターで実際にトレーニングした内容を基に書いているということですね。福岡先生,これをご覧になっていかがですか。
福岡 臨床腫瘍学の教科書が日本にないと言われて,最近はそれを作る努力がなされているのですが,教科書は分厚くて,持ち運びに不便であり,絶えずベッドサイドに持っていきひもとくというわけにもいきません。本書を見せていただいて,いままでになかったものができたと感銘を受けています。
まず最初に,がんの治療学ということで,その基本となるインフォームド・コンセントから入っているのは非常によいのではないかと思います。また,先ほど言われたように,治療薬を並べるだけでなく,そこにいくにはどのような薬物,化学療法の概念や基本を理解する必要があるかが書かれています。あるいは臨床試験の重要性も理解できるようにされており,手軽にそれをひもとくことができる点で,今までにはないものです。本書は,研修を受ける人にとっては大変有用ではないかなと感じています。
evidence-based medicine
渡辺 最近では「evidence-based medicine」や「evidence-based decision making」が1つのキーワードとして臨床医学の中で使われていますね。「内科腫瘍学」におけるevidenceがどういう形で得られるかは,臨床試験を通じて得られたもので,これに基づいて日常診療のdicision makingが行なわれていくことが重要なポイントです。勝俣 「evidence-based medicine」は,evidence,つまり臨床試験の結果をもとにしてできています。現在最も臨床試験が発達しているのは,内科の中では循環器学と腫瘍学です。腫瘍内科医はそうしたevidenceをもとに抗がん剤の適応と限界を知りながら,日常診療に生かしていかなければなりません。常に標準的な治療は何か,ということを頭に入れておかなければなりませんが,腫瘍の領域は臨床試験が多いので,その日進月歩についていくのも大変です。NCI(アメリカ国立がん研究所)では,がんの標準的治療(state of arts)をインターネットで流していますが,その内容は3か月ごとに更新されるそうです。
大学での「内科腫瘍学」教育
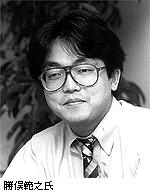 勝俣 今はまだ「内科腫瘍学」を志向する人が少ないですね。人材の養成については,1つは教育施設の問題と,あとは内科学の中に腫瘍学を確立することが一番大きな課題ではないかなと思います。
勝俣 今はまだ「内科腫瘍学」を志向する人が少ないですね。人材の養成については,1つは教育施設の問題と,あとは内科学の中に腫瘍学を確立することが一番大きな課題ではないかなと思います。
渡辺 そうですね。研修・教育という観点でいくと,まず大学での学部教育が重要となりますが,実際にはどうなっているかを,福岡先生,教えてください。
福岡 大学はそもそもが臓器中心の,臓器別の縦割の単位になっていますので,乳がんは外科,婦人科がんの化学療法は産婦人科,睾丸腫瘍の抗がん剤使用は泌尿器科というように,教える時点で区分けがなされていますから,教えられる学生も乳がんは外科の病気と,卒業するまで思い込んでいますね。
国家試験の問題も各臓器に分かれていて,腫瘍という独立した項目の問題はないのです。呼吸器の中から肺がんが出題されるように,大学の医学教育に関してはすべてがそうなっているのです。だから,学生は「内科腫瘍学」の存在すら教育されていないことになります。それをどうすればよいか,われわれもこれから考えていかなければならないと思っています。できるだけ他の時間を切り詰めて,臨床腫瘍学を導入しても,国家試験には出ませんから,大学ではどちらかと言えばあまり教えなくてもいい分野になってしまうところに大きな問題があるわけです。
渡辺 国家試験の問題ですが,私は看護婦さんの国家試験の問題作成委員を担当していますが,問題作成要綱に腫瘍学という領域はまったくないのです。問題を作成する際の問題数の割り振りの時点で,すでに循環器は何題,内分泌の数は何題となっています。ですから,私は割り振られた問題を全部がんの問題にしたのです。循環器でも内分泌でもすべてがんの問題を作成したら,看護婦さんの合格率が下がってしまった(笑)。そのように,学生の勉強のモチベーションは,国家試験でどれぐらい出題されるかという話です。一方で,がんを扱った問題が少ないことは,3.7人に1人ががんで死ぬ状況の中で,医学教育として不十分です。大学の先生方を中心に学会などにも何らかの働きかけをしていただきたいですね。
福岡 内科の教科書の中に,腫瘍という項目はないですから。
小野 がんの患者を診ない医師は少ないと思います。内科医になったらまず診るでしょう。それなのに講義や,国家試験の問題が少ないのは疑問です。
福岡 呼吸器科では病棟の6,7割は肺がんですからね。臨床実習に来るとがん患者ばかり診ているけれど,卒業試験や国家試験になると違ってしまい,矛盾したことが行なわれているわけです。
渡辺 そうですね。ある国立大学の先生に話を聞くと,その先生は白血病が専門で,腫瘍学を教えたいけれど,その先生の科では白血病と循環器,アレルギー,膠原病などを担当しなければならず,助手や講師を割り振ると,とても腫瘍学に割けないとおっしゃってました。そういう面からも何らかの改革が必要だろうと思いますね。
がん専門病院での研修
渡辺 大学での腫瘍学トレーニングが不十分ということもあって,日本ではなかなかそのような教育が受けられる場所がありません。ここで少し,がんセンターでの研修教育が実際にどのようなものかに話を移したいと思います。がんセンターでは,初期研修後の3年間でレジデントトレーニングを行ないます。レジデント数は毎年20人で,外科対内科の比率が3対1ぐらいです。ひどいときは15,6人が外科で3,4人が内科という感じです。しかし最近,少しずつ内科をめざしたレジデントが増えています。
小野 レジデント教育の具体的な内容を言うと,僕自身は最初の1年間は診断が主で,胸部X線や腹部CTの読み方,あるいはX線の撮り方を学びます。それから実際に消化器がんの病理を勉強して,基礎的なことを習得してから2年目以降に肺の内科を回り,その後消化器内科に戻り,内視鏡と消化器の化学療法を学びました。その前に胃の外科も回って,お腹の中を触らせてもらいました。
要するに,消化器内科だけではなく,診断的なものから他の内科の治療方法に加えて,実際の外科の考え方,すなわち治療して手術するまでの診断と,手術後の経過やどのようなデシジョンがなされているかを学んでから,もう一度自分のサブスペシャリティの分野に戻りました。このことにより,他の分野を知り,関連する内科だけでなく,外科あるいは診断というところまで理解し,患者さんを総合的に診る素地ができたことが,非常によかったと思っています。
勝俣 私は腫瘍内科医を志していましたが,腫瘍内科医ではまだ日本の現状では食べていけないだろうと考え,がんセンターではリンパ腫や白血病などの血液腫瘍学を学ぼうと思いました。1年目は診断系をローテートすると決められているので,血液病理や超音波,内視鏡も回りました。
2年目から臨床に入ったのですが,最初は消化器,肺がんをまわり,その後に乳がんをローテートしました。そうしているうちに,だんだん固形がんの化学療法に興味が湧いてきました。3年目は血液腫瘍のみをやりましたが,結局現在は,主に乳がんと婦人科のがんの化学療法をしています。当面の目標として志望したものとは違った道に入ったわけですが,結果的には腫瘍内科医らしい仕事ができるようになり,自分としてはこれでよかったかなと思っています。
小野 様々な分野を知った上で,いまの分野に進んだということですね。
渡辺 最初に病理や診断部門,それから外科や麻酔科を広くローテーションして,そのあとに内科の場合には内科各科をローテーションするのです。臨床トレーニングを主体とした3年間で,そのための病理の勉強や,研究所に出入りしたり,基礎的な研究を一時期することもありますが,あくまで臨床研修を主体としているということです。
内科腫瘍学の今後の展望
 福岡 日本で現在,そのような教育のできる場所が他にほとんどないんですね。一般的には研修を終了してから,どういう分野にいくのか,つまり受け皿にまだ問題があると思います。そのような教育,あるいは「内科腫瘍学」を日本で確立すると同時に,一般病院においてがん化学療法のディビジョンができてこないといけませんね。
福岡 日本で現在,そのような教育のできる場所が他にほとんどないんですね。一般的には研修を終了してから,どういう分野にいくのか,つまり受け皿にまだ問題があると思います。そのような教育,あるいは「内科腫瘍学」を日本で確立すると同時に,一般病院においてがん化学療法のディビジョンができてこないといけませんね。
勝俣 最近は一般病院でも腫瘍科の看板を出すところも少しずつ増えていますね。
福岡 それから,がんセンターでの3年間の研修はかなり内容の多いものという感じも受けます。しかし,今後はもう少しこれを横にも広げてほしい。全がん協(全国がん専門病院協議会)は26病院あるのですが,教育ができていないところが多いのではないかと思います。将来,一般病院あるいは大学にも,おそらく「内科腫瘍学」が必要になってくると思われます。その時には,卒後研修システムの確立をがんセンターが指導的に行なっていってほしいと思っています。
勝俣 全がん協はほとんどが大学病院の関連病院のようになっていて,レジデント卒業生がそこにいくルートは実際は確保されていません。結局,がんセンターで「内科腫瘍学」のトレーニングを受けても,大学病院の中の呼吸器科や消化器科に入ってしまい,なかなか活かせる場所がないことが問題になっています。
渡辺 医学生や研修医の皆さんは,将来のことを考えた場合,安定を求めるわけですね。大学の医局のローテーションや人事から離れて研修を受けると,それはもう飛び出してしまって糸の切れた凧のようなものになってしまうと考えて,それを恐れるあまり,大学から出たがらないケースが多くなってきたといいます。
がんセンターでトレーニングし,非常にいい人材を育てられれば大学や一般病院にも採用してもらえるのでしょうが,まだ日本では「内科腫瘍学」としての受け皿が一般には少ないのです。そのあたりが揃えばだんだんよくなっていくと思います。
今後は腫瘍学に限っていえば,臨床研究や臨床試験をきちんと自分で行ない,そのデータのもとに新しい治療方法の評価を行なうとことも,きちんとした臨床研究として市民権を得なければいけません。そういう意味で,今後は大学教育における内科腫瘍学の充実も期待されるところです。
今日は「内科腫瘍学」とは何かから始まって,レジデントの研修,医学部教育のトレーニングのことなどの話題が出ました。「内科腫瘍学」は臨床の学問としてはまだまだ新しい学問であるけれども,社会的な要請も高く,専門病院での教育や,大学教育も徐々に整いつつある状況で,大きく発展していく領域です。医学生や研修医の方々にとっても,おもしろく興味深い重要な領域だと思います。ぜひ腫瘍学のほうに目を向けてほしいと希望しています。
勝俣 アメリカでは,内科の中で人気のある科とは,循環器が1番で,2番が腫瘍学だそうです。そのくらいおもしろい学問ですので,どんどんめざしていってほしいなと思います。
渡辺 実際にがんを病む患者さんを対象としていますから,主治医が暗い顔をして回診していたのでは患者さんが滅入る一方です。がん患者さんは不治の病ではあるけれども,それなりに明るい側面があり,その明るい側面をなるべく見ていくようにと患者さんにも話しています。毎日の回診で患者さんと話す話題の9割は冗談になってしまうこともありますけれど。国立がんセンター総長の阿部薫先生も内科医なのですが,常々われわれに対して,患者さんに対する愛情,思いやりを持つこと,自分も患者さんと同じ「人間」であることを忘れてはいけないとおっしゃいます。これは腫瘍内科医としての基本だろうと思います。
――どうもありがとうございました。
