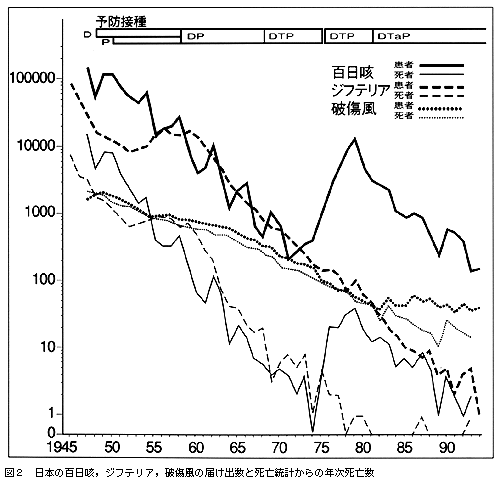連載
現代の感染症
2.百日咳,ジフテリア
堺 春美(東海大助教授・小児科学)百日咳,ジフテリアとも重症な疾患であるが,いずれもきわめて有効なワクチンがある。百日咳ワクチンにジフテリア,破傷風トキソイドを混合した百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT)は,世界でも日本でも小児の最も基本的なワクチンである。いずれの疾患も予防が最良の対策なので,定期の予防接種の機会を逃さないことが肝要である。
百日咳とジフテリアの疫学
現在,旧ソヴィエト連邦で,予防接種率の低下と社会的な混乱が相まって,ジフテリアが大流行している(図1)1)。日本でも第2次世界大戦末期から終戦後にかけて,社会的な混乱から,ジフテリアの大流行をみた。日本では,1948年にジフテリアトキソイドの接種が予防接種法によって義務づけられた。1949年には百日咳ワクチンの予防接種が開始され,1958年から百日咳ジフテリア混合ワクチンが使われるようになり,この頃からジフテリア,百日咳の患者がともに減少してきた。1960年になると破傷風トキソイドの製造が始められた。百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチンの基準が1964年に作られ,1968年から定期接種に使われるようになった2)。破傷風トキソイドは,DPTワクチンとして使用されるようになってから,急速に普及した。破傷風,ジフテリアの患者数,死亡者数ともに着々と減少し,ジフテリア患者数(死亡数)は,1992年4,93年5(1),94年1である。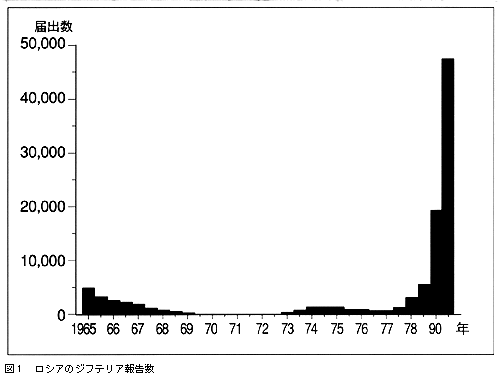
ワクチン接種率の低下
1960年代後半から予防接種事故が社会問題となった。それを契機に,国の予防接種事故救済制度が発足した。その申請例のうち,種痘に次いで百日咳ワクチンの副反応が目立ったことから,百日咳ワクチンがマスコミの批判の対象になった。そのため,1975年初頭,厚生省は乳児への百日咳ワクチン接種を中止し百日咳ワクチンを含むワクチンの接種開始年齢を2歳以上とした。このような状況にあって,百日咳ワクチン接種率は低下し,1979年を頂点とする全国的な百日咳の流行が起こった。
その後,百日咳菌の培養上清から感染防御に有効な抗原(感染防御抗原)を精製して作った無菌体百日咳ワクチンが開発され,1981年から定期接種に全面的に使用され始めた3)。その際,集団接種における百日咳ワクチンの接種年齢は2歳のままであった。1989年になって3か月から接種してもよいという指示が出され,1995年の予防接種法改正によって,3か月から12か月のDPTのI期初回接種を行なうのが標準的な接種法となった。1981年頃からわが国の百日咳患者も着々と減少し,1995年に至って,ようやく1970年代前半のレベルに下がった(図2)。1990年代前半では,百日咳患者の半分は,0歳児,1歳児が占めていたが,最近になり,ワクチン接種開始の年齢が下がるに伴い,ますます低年齢の百日咳患者の割合が増加する傾向にある(図3)。一方,年長児での発生もあるが,この中には,一部ワクチン歴のあるものがいる。
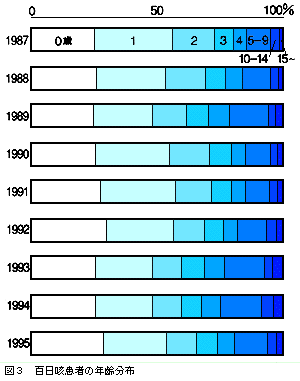
百日咳・ジフテリアが疑われた時
百日咳百日咳の臨床診断は,定型的痙咳発作*(特に夜間に多い),長期にわたる咳(通常4-5週間,その名の通り100日に及ぶこともある),咳に伴う嘔吐,百日咳様顔貌(上眼瞼が浮腫状),無呼吸発作,呼吸障害による。合併症がなければ発熱を認めない。乳児では,呼吸障害,肺炎の合併,あるいは脳症を起こして死亡することがある。
百日咳を疑ったら,できるだけ早く抗生物質を投与する。第1選択薬は,マクロライド系のエリスロマイシン(EM),クラリスロマイシン(CAM),あるいはロキシスロマイシン(RXM)である。対症的には,去痰剤,鎮咳剤(あまり強くないもの)を投与し,水分補給を十分にする。筆者は,これに気管支拡張剤(β2刺激剤)を併用している。
*コンコンコンコンと続く咳(スタッカート,Staccato),その直後にヒューと吸い込む音(フープ,whoop; whooping coughの語源)そしてそれ繰り返す(レプリーゼ,reprise)が特徴である。
ジフテリア
咽頭ジフテリアでは,発熱,咽頭痛,咽頭における偽膜形成が認められる。喉頭ジフテリアでは,発熱,クループが主要症状である。発症後7-10日に毒素によって心筋炎,心不全,あるいは軟口蓋,眼筋,四肢の麻痺を来たす。
吸収されてしまった毒素を中和するには,抗毒素血清を使用する以外に方法がない。ジフテリア抗毒素血清は,ワクチン製造所が管理保存しており,地方自治体から厚生省に連絡すれば即時入手可能である。ジフテリアを疑ったら,可及的速やかに抗毒素血清を手配する。抗血清は馬で作られているので,投与の際には,アナフィラキシー反応に注意する。
抗生物質は,菌を排除するために,できるだけ早く投与する。第1選択薬は,経口ペニシリン(PC)とエリスロマイシン(EM)である。
わが国の百日咳,ジフテリア対策
ポリオワクチンや麻疹ワクチンのような一部の限られた生ワクチンでは,ワクチンによって対象疾病を根絶することが可能である。しかし,百日咳ワクチン,ジフテリアトキソイドのような不活性化ワクチンでは,永続的に予防接種を行なうことによって対象疾病の流行を抑止することを目標としている。1986年に全国の衛生研究所の協力により,百日咳の疫学およびワクチンの有効性の評価に関する研究班(班長=東海大教授木村三生夫)が組織された。研究班では,臨床的に百日咳が疑われた患者2501例のうち,百日咳菌分離陽性は403例,パラ百日咳菌陽性が7例あったと報告している。菌分離によって診断を確定した94%(378/403人)はDPTワクチンを全く受けておらず,一方,確実なワクチン歴があったのは5%(21/403人)だけであった。残りの1%はワクチン歴不明,あるいは罹患直前,直後のワクチン接種例である。全国感染症サーベイランスでは,1996年の百日咳報告数は5696で,そのうち107例(1.9%)にDPTワクチン歴(1回以上)があった。これらのデータは,百日咳ワクチンがきわめて有効であることを示している。
百日咳あるいはジフテリアの感受性者は,DPTワクチン接種開始年齢前の乳児,ワクチン接種を受けていない乳幼児,学童,成人,そして,ワクチン歴があっても接種後年数を経て,免疫の度合いが低下した者(この場合は通常,軽症である)である。
流行抑止のための課題
対象疾病の流行抑止のためには,高い予防接種率を保ち,感受性者をできるだけ減らすことが鉄則である。わが国におけるDPTワクチンの接種率はI期3回目で80-90%と高く,ほぼ満足すべきレベルである。しかし,第II期(小学校6年のDPT)の接種率は従来80%あったが,1995年の予防接種法の改正に伴い,接種が原則として個別になり,大幅に低下してきた。不活化ワクチンによる免疫は,年を経ると低下するため,今後は年長児,成人の感受性者の蓄積が懸念される。第II期接種の接種率のリカバリーのためには,今後特別な配慮が必要である。
成人が百日咳に感染したために乳幼児の感染源となることがしばしばある。また,百日咳,ジフテリア,破傷風に対する成人女性の免疫度が高ければ,移行抗体のレベルも高まるので,新生児,乳児の感染症対策にもなる。これらのことを総合すると,成人についても百日咳,ジフテリア,破傷風の感染予防を行なうことが望ましい。成人への予防接種をどのようにして推進できるかは今後の課題である。
参考文献
1)Diphtheria Epidemic-New Independent States of the Former Soviet Union, 1990-1994. MMWR44(10);177-181, 1995
2)木村三生夫, 平山宗宏, 堺春美 : 予防接種の手びき, 第7版, 1995, pp.98-117,近代出版
3)木村三生夫 : 百日咳, 無菌体ワクチンの臨床的研究. モダンメディア 42(4): 154-161, 1996