質の高い退院をめざして
地域との連携を図る退院調整専門看護婦
済生会山口総合病院での試み
 済生会山口総合病院(藤井英雄院長,五十部八惠子看護部長,310床)では,全国の病院に先駆け,1994年9月から「退院調整専門看護婦」を病院の保健指導部に設置し,実働を開始している。医療者,患者・家族,そして地域を結ぶ役割を担い,入院初期から質の高い退院をめざしてかかわっている。これは退院の件数を上げるための導入ではなく,患者や家族にとり,また医療者にとっても満足できる退院を進めることを目的とした決断だった。しかし,結果として患者の入院期間の短縮,病床の稼働率が上がることにもつながった。もともと同病院の患者の平均在院日数はそう長くはなかったが,導入前の平均22.1日(脳神経外科病棟48.7日)から20.6日(同34.3日)へと減少した。
済生会山口総合病院(藤井英雄院長,五十部八惠子看護部長,310床)では,全国の病院に先駆け,1994年9月から「退院調整専門看護婦」を病院の保健指導部に設置し,実働を開始している。医療者,患者・家族,そして地域を結ぶ役割を担い,入院初期から質の高い退院をめざしてかかわっている。これは退院の件数を上げるための導入ではなく,患者や家族にとり,また医療者にとっても満足できる退院を進めることを目的とした決断だった。しかし,結果として患者の入院期間の短縮,病床の稼働率が上がることにもつながった。もともと同病院の患者の平均在院日数はそう長くはなかったが,導入前の平均22.1日(脳神経外科病棟48.7日)から20.6日(同34.3日)へと減少した。
本紙では,同病院での退院調整専門看護婦の誕生のきっかけとなったもの,そして導入後に病院はどう変わったのかを,退院調整専門看護婦の役割を中心に追ってみた。


医療者,患者・家族,地域の間で
退院調整看護婦誕生のきっかけ
「脳神経外科(以下脳外)病棟を中心に,長期にわたって入院されている患者さんがおり,効率的なベッド回転とは言えない状況でした。この実態を調査しようと,脳外病棟を退院した脳血管障害患者239人を対象にアンケートを実施しました。その結果,『突然退院と言われショックを受けた』『慣れぬ転院のために辛い思いをした』と患者さんは感じており,患者・家族にとっては不満足な退院となっていることがわかりました。このようなケースに対して,看護婦は何ができるのかを考えたところ,医療者,患者・家族,地域の間を取り持つことの必要性が導き出されました」と語るのは,同病院の五十部八惠子看護部長。患者にとっての不満足な退院は,看護職にとっても納得のできるものではなかった。そこで双方が納得するために,退院後の患者の環境を見据えて,入院初期から退院調整を図る専門看護婦を設置する必要性を訴えた。「“退院調整”をする看護婦の検討を,担当医や院長に話したところ,理解が得られすぐに取り組む体制ができました」
その結果,日本でおそらく初と言える「退院調整専門看護婦」のポストが誕生した。この任にあたることになったのが,同病院保健指導室婦長の倉田和枝さん。
倉田さんは,何をどう解決すれば患者にとって最もよい退院に結びつけられるかを,患者・家族や病院スタッフから情報を収集し,さらに福祉面に明るい在宅介護支援センターのケースワーカーと常時連携をとりながら,社会資源などの活用も考慮に入れ退院調整を図っている。
「自分の中にあるネットワークを使いながら患者さんの抱える問題を解決していき,退院に結びつけています。退院後の患者さんの環境や生活を見通す能力が,退院計画を進める看護婦には必要です」と語る倉田さん。相談があったケースについては,患者が退院した後も,保健指導室にいるもう1人の訪問看護婦と訪問看護を行なう。看護婦が,入院時から退院を見通した看護計画をたてることは,病棟のスタッフの意識にも影響を与えた。
同病院が“退院調整”に取り組んだねらいは,患者を施設から施設にたらい回しにするのではなく,患者が最も望んでいる場所への退院へとつなげることにある。
「何が何でも退院させるというのではなく,いい退院をしてもらうことが基本です。その結果として,長期でなかなか退院できなかった患者さんも在宅に移行できました」と五十部さん。いろいろと難しい状況を抱える家族の調整を図りながら,1つひとつケースを重ねていくことで,満足のいく退院になってきた。それでも最初から順風満帆のスタートではなかった。導入当初は“退院促進ナース”と捉えられ,スタッフからも「患者がいなくなったらどうするんだ」という意見もあったという。
前出の2人の他に,伊藤満子副看護部長,江藤京子脳外科病棟婦長からも話を聞いた。
退院調整の必要性
退院調整の取り組みは脳外病棟から始まった。「入院が長期となる場合が多い脳外病棟では,入院時に退院の話をするのは難しいために,今でも入院当初は病状説明だけですが,ある程度症状が落ちついてきた時に,入院の期間や,長期になるようでしたら転院もありえますとか,在宅療養の可能性についてというように,医師たちが早めに退院に向けた説明をされるようになりました」と,江藤婦長。
「退院は医師が決める,という感覚から自分自身が抜け出ていなかったように思います」とは,倉田さん。
医師の中には,退院の指示は医師が出すものという意識を持つ人もいる。特に慢性疾患患者を抱える内科医からは,早めに退院のことを聞いてもあいまいな言葉しか返ってこない場合が多かった。入院の時点で退院までの見通しを立てることは難しく,したがって看護計画もそれに合わせたものになってしまっていた。看護職も,退院後の慢性疾患患者がどのような生活環境におかれるのかという視点に欠けていた。
また,医療面からは退院できると考えられても,患者の持つ社会的背景から受け入れ難いこともあるために,退院後も継続してケアを受けられる環境設定が必要だ。そこに看護者のジレンマがあった。それを解消するためには,患者のことを熟知している看護婦による退院調整が望ましい。退院後の患者のことを考えると,訪問看護部門もまた大きなウエイトを占める。
同病院は,1993年に地域ケアセンターを設立し,在宅介護支援センター,訪問看護ステーションに加え,A型デイサービスなどを実施している。訪問看護事業を始めたのは今から12年前に遡る。
伊藤副看護部長は,「患者さんの受入れに必要なサービスを整えてから在宅に切り換えなければ,退院調整をしても無責任になってしまう」と語る。長期入院患者が在宅に移行した場合,介護が必要な患者だと家族に負担が集中してしまうことから,他施設へ転院するケースも多い。やはり病院や施設からの在宅フォローがなければ,退院後に在宅へと切り換えるのは難しい。同病院では,併設の在宅介護支援センターが山口市全体に対応しているために,退院後のフォロー体制はできていた。
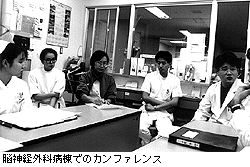
問題解決のために院外にも目を向けて
スムーズに他の施設へ移行するために
倉田さんが常駐する保健指導室で,退院調整の実際を見学した。退院調整は,各病棟から回ってくる保健指導依頼書によって行なわれる。患者のどういうところが問題なのかを病棟であげてもらい,それに基づいて情報収集をする。次いで患者・家族と面談をして,病棟婦長,受け持ち看護婦,主治医と相談しながら見えてきた問題点に対処する。
この日の依頼は,夫と2人ぐらしのKさん(71歳)のケース。大腿骨骨折の手術から回復し,院内でのリハビリテーションのゴールは見えたが,金銭的な問題などから在宅へスムーズに移行できずに,他施設への転院を考えている。
Kさんの場合は,特別養護老人ホームへ入所するのが望ましいと,倉田さんは考えているのだが,山口市の場合は入所までに100人待ちの状態だという。老人保健施設への入所も考えられるが,金銭的負担が大きいことがネックとなった。
倉田さんは,これまで築いてきたネットワークを活用し,ようやく減免制度を利用した社会福祉法人立施設への入所の可能性を見いだした。前日,その施設から相談員が病棟まで出向き,KさんのADL状態などを観察し,彼女の何が問題なのかも話しあった。
「患者さんにも納得をしてもらった上での転院や入所でなければ,相手側の施設にも迷惑をかけてしまう」と,倉田さんは双方の合意を原則に話しを進めている。現在,先方施設からの返答待ちだ。
病院からだけの支援には限りが
 こんなケースもあった。
こんなケースもあった。
山口市からは山1つ離れた地域で,前妻の息子と暮らしている老齢の患者は,家族関係がうまくいっていないことが問題になっている。病棟の看護婦たちも,この女性が家族に遠慮をしているのだと気づいているのだが,うまく在宅へと移行できないままでいる。
病院から遠くに住む患者の場合は,訪問に行きたくても時間がかかってしまうことからどうしても負担が大きくなり,自分たちで訪問看護を行なうことに無理が生じる。このような場合は,地域の保健センターの保健婦に情報提供をし,近医機関での訪問看護に切り換えている。その場合には,訪問看護依頼書と医師の指示書,患者の退院サマリーかデータベースをつけて依頼を行なう。
退院調整を行なう際には,他施設に移せばいいというだけでは根本的な解決にならないケースも多くあり,悩みの種となっていると倉田さんは言う。在宅療養をすることが金銭的には最も負担は軽いのだが,そうすると介護者の問題がつきまとう。在宅に切り換えられると考えても,主治医から「訪問看護婦にしても保健婦にしてもかかわれるのは昼間だけではないか」と指摘されたこともある。確かに訪問看護を展開する中で,看護婦が触れ合う時間はわずかにすぎない。それでも巡回型の訪問看護になれば,切り換えは可能かもしれないが,まだそのシステムはできていない。
「退院調整に介入すると,院内だけにとどまっていたのでは何もできません。地域にネットワークを広げていかないと解決できないケースが多いことに気づかされます。現実にはいろいろな問題を抱えながら患者さんが入院してきますが,金銭的な背景などよりも治療が最優先されます。入院治療をする中で,例えばどうして家族が見舞いにこないのだろうかなど,様々な問題が見えるようになりますね」と倉田さん。
この日,彼女は脳外病棟の合同カンファレンスにも参加した。今日のケースは,退院が可能になった難聴を伴う高血圧症のある患者。湧田幸雄脳外科部長を軸に,退院をして自宅で生活できるかを焦点に検討し,その結果,緊急通報装置の導入など,家族へ連絡をしてみてから,改めて再調整することになった。
退院調整専門看護婦は何をもたらしたか
医師を含めたスタッフの意識に変化
倉田さんが退院調整専門看護婦を名乗った当初は,病棟まで出向いていって患者さんを探していた。それが今では継続看護システム(下図参照)となり,病棟からの連絡を待って活動できるようになった。病棟の看護婦と医師の合同カンファレンスの中に家族も参加するケースも増えてきた。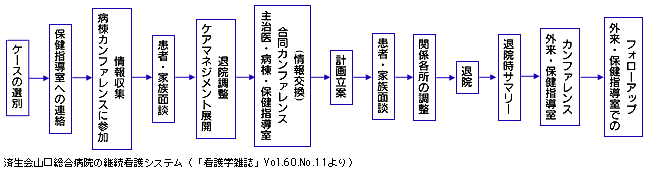
「インフォームドコンセントの時代と言われています。ケースによるのかもしれませんが,患者さんや家族を抜きにして第三者だけで退院調整のカンファレンスをするのではなく,どんどん患者さんたちを巻き込んで,彼らの意向や希望を聞きながらよりよい方向性を一緒に考えていくべきです」。倉田さんは,カンファレンスがその場で自分たちの思いを直接に患者や家族に伝えるいい機会でもあり,患者や家族の意見も聞ける場であることを強調し,「それが互いに不満なく進められる形なのではないか」と語った。
現場での看護婦の意識がどのように変わったのかを江藤さんに伺った。
「入院の時点から,スタッフが患者さんはどこに帰っていくのだろうか,サポートしてくれる人はいるのだろうかと,生活背景を考えるようになりました。今までは疾患,症状などの身体面しか見ていなかったように思いますが,入院当初より退院を見渡した思考に変わってきました。また医師の許可は必要ですが,外出,外泊の検討も家族と調整しながら,看護婦サイドでできるようになりましたし,医師との週1回のカンファレンスの中で,医師のほうからそろそろ在宅に切り換えては,という提案も出る雰囲気になりました」
施設に移転させたくても,一般の看護婦には,どのような施設かはパンフレットなどからの情報しかなく,家族に説明するには不十分であった。また医師に紹介状を書いてもらうまでには1~2時間がかかっていた。しかし,保健指導室に業務が移ることで1人の患者にかける時間が少なくなり,効率的になった。倉田さんは実際に施設へ出向き,様子も知っている。彼女らがかかわることで,家族の不安や「行ってみたらこんな所だった」という不満の解消にもつながった。
また,患者が外泊練習をする場合,病棟の看護婦が患者宅まで行って様子を見ることは時間的に難しい。倉田さんたちは外出や外泊の際に患者に同行し,家庭内での実際のADL状態や,家の構造を観察する。それらを踏まえ,病院での次のリハビリテーションや患者教育への示唆も与えている。倉田さんは,「病棟のスタッフたちも,私たちのノウハウを見ていますので,本当に大変になったケース以外は,ちょっとしたアドバイスで解決できるようになりました」とも語る。
「医師の認識もだいぶ変わりました。退院に向けて,患者さんにとって最もいい状況で帰られるならば任せてもらえるようになり,ケースの内容によっては看護サイドで調整をするようになりました。それまでによい退院につながった事例を提示していくこと,また1つひとつの事例を大切にし一緒に展開していくことにより,医師の理解も深まり,制度としての退院調整専門看護婦の役割が受け入れてもらえたのだと思います。最近では全科から依頼がくるようになりましたし,難しい患者さんの場合には事前に先生から相談を持ちかけられるようにもなりました」
それらの結果,ベッドの稼働率も回転率も上昇し,病院にとっても大きなメリットとなった。

地域との連携を基本に
倉田さんは,ケースワーカーとの連携がなければこの仕事は成り立たないと強調する。医療上のリスクや看護面からの視点と,生活ニーズがキャッチしやすく福祉面に明るい立場からの調整が,在宅療養を行なう上では必要なのである。倉田さんは,病院に併設する在宅介護支援センターに常駐するケースワーカーと常時連携を取りながら,退院調整を図っている。退院後に患者・家族からの苦情はない。退院調整をしただけでなく,後方施設へ,または在宅へとその後の患者の場が移っても,患者のフォローアップをきっちりとしているからだろう。
「退院した後も,訪問をしたり,電話をかけたりと,経過を追っています。そこでうまくいかなくなったら,再度調整をしていくという方法をとりながら,フォローしています」
自分たちの手が届かない場合には,保健センターの保健婦の力を借り,患者を定期的に見てもらっている。保健婦からも近況報告や指導要請がくる。そのような連携から,患者に対して早めの対応ができるようになった。また再入院になった時にも,まったく別の病棟に入院するのではなく,前と同じ病棟に戻り,継続看護をする方法をとっている。
「退院調整というかたちでかかわることで,病棟との行き来もしやすくなりました。受持ち看護婦に聞けば患者さんの様子が即座に返ってきますし,互いの情報交換が密になったように思います。病棟スタッフから退院に向けた視点で,『この患者さんの問題はここなのですが,どうでしょうか』という相談が気楽に入るようになりました。実際に病棟に出向くことが多くなりましたね」と倉田さん。その彼女に,今何を望んでいるかを尋ねた。
行政へ望むこと
「訪問医療を進める上で,年齢の問題がネックになっています。65歳以上であればほぼ問題はないのですが,40代,50代での脳疾患の患者さんが結構多いのです。これは山口市だけの問題ではないと思いますが,在宅になると負担が大きくなります。老人政策が先行していますが,もっと若い層の現状を行政は知ってほしいと思います。難病の患者さんはある程度負担が軽減しましたが,小児や癌患者さんの在宅も含め,厳しい現状があります。高齢者は資源活用ができますが,高齢との狭間にある人に,医療・介護用具の給付がありません。このことを民間レベルで考えるのは難しいことです。また高齢者の後方施設への入所の問題にしても,いつ入所できるかわからないという入所待ちの現状があり,これらのことは行政上の問題として考えていかなければならないだろうと思います」と語り,「なにかよい解決方法はありませんか?」と投げかけられた。さらに倉田さんは,「看護婦による療養指導料の枠を広げて,退院調整(指導)にも点数をつけてほしい」と要望している。
(1996年12月取材)
