死は医療のものか
イギリス,スウェーデンのターミナルケアに学ぶ
 高齢化の急速な進展や疾病構造の変化の中で新しいターミナルケアのあり方を探る「福祉のターミナルケア調査研究委員会」(委員長=千葉大助教授 広井良典氏)が,昨年10月,長寿社会開発センターに設置された。
高齢化の急速な進展や疾病構造の変化の中で新しいターミナルケアのあり方を探る「福祉のターミナルケア調査研究委員会」(委員長=千葉大助教授 広井良典氏)が,昨年10月,長寿社会開発センターに設置された。
同委員会では本年1月5日から15日まで,イギリス,スウェーデンでの海外調査を実施し,本紙はこの調査に同行し取材を行なった。本調査についての報告は別途なされるが,調査内容の一部は,広井氏が「看護学雑誌」(医学書院)に連載中の「ケアって何だろう」第4回(第61巻4号,1997年4月号)以降でも紹介の予定である。本紙では,いち早く両国のターミナルケア事情について報告する。
●「デイホスピス」というコンセプト
ホスピス発祥の国イギリスで見学した「セントオズワルド・ホスピス」は,「急性期ホスピス」と言いうるものであった。癌患者が主な対象であるが,死亡退所者は約半数で,残りの半数が自宅や他施設に移っていく(平均在所日数は約2週間)。自宅に帰った患者は,このホスピスが提供するデイケア,ショートステイ,外来診療,訪問看護などさまざまな通所・在宅サービスで支えられる。つまりこのホスピスは「死に場所」というより,これ以上の治癒が望めない患者の「在宅死を支える施設」なのである。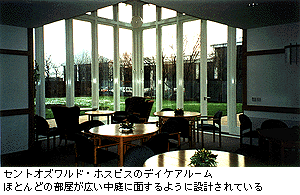
ホスピスによるデイケア,すなわち「デイホスピス」という新しいコンセプトは非常に興味深い。日本でも数分間の診察を受けるため数時間を病院の待合室でつぶす癌患者も多いというが,「疼痛管理を受けつつ仲間と静かに語らいながら日中を過ごす」機能に対する潜在的需要は高いはずだ。日本経済新聞(1月24日付朝刊)によれば,似たような試みとして地域医療に通じた開業医を中心に「通院型ホスピス」が試み始められているものの,診療報酬上の手当がほとんどなく,患者負担が重くなっているという。
デイホスピスであれ通院型ホスピスであれ,ターミナルケアに通所機能を付与する施策が必要な時期に来ているのではないだろうか。それは第1に,死までの期間を社会との接点を保ちつつ在宅で過ごすことができるという患者のQOL的視点から,第2に医療財政の効率化の視点から,そして第3に,老人ホームがデイサービスとショートステイによって社会に認知されたのと同様に,死にゆく場所として社会から隔絶されつつある日本のホスピスを「解放」するためにも有効な手段であると思われる。
●ソーシャルニーズにどう応えるか
ターミナルケアは医療の問題だけではなく,状況によってはむしろ「ノン・メディカル」あるいは「生活モデル」のターミナルケアがあってもよいのではないか。50歳の癌による死(メディカルニーズ中心)と,80歳以上の天寿を全うしたと言いうるような死(ソーシャルニーズ中心)とでは,ターミナルケアの様相は異なるのではないか。このような問題意識から本調査会は発足された。 今回の海外調査でいえば,例えばイギリスの急性期ホスピスが前者,スウェーデンのグループホームが後者であると概念的には分けられるだろうが,むしろ印象的だったのは,どこのホスピスでも死にゆく患者のソーシャルニーズ充足の重要性が盛んに指摘されたことだ。痛みの緩和と症状のコントロールさえできていれば,患者が求めているのは,死の前後の不安にカウンセリング的にかかわるという心理的援助のほか,家事の手伝い,話し相手,社会的関係づくりの手伝い,残される家族のケアなどの社会的な生活援助であり,これらをコーディネートするのがソーシャルワーカーの役割である。日本のターミナルケア論議は往々にして,医療とその対極としての宗教をめぐってのみ行なわれがちで,患者・家族の生活にとって切実な問題であるソーシャルニーズへの対応がすっぽりと抜け落ちているのではないかと考えさせられた。
またソーシャルワーカーは同時に,医療専門職が陥りやすい「指示的な対応」から患者・家族を守り彼らの立場を代弁する。ターミナル期においてはこのようなアドボカシー機能が不可欠であるが,この点を強調したホスピスが,治癒不可能な子どもとその家族のための「レインボートラスト・ホーム」である。医療に振り回されて疲れ切った家族の「病院でないところで休息をとりたい」という切実なニーズに応えるため,つまり「医療から子どもを守る」ことを目的に設立されたという。
この「ホーム」の主役はあくまでも患者とその家族であり,スタッフはそのサポート役に徹する。「与えるケア」ではなく自分でコントロールできるように環境を整えること,すなわち「エンパワメント」が強調される。したがって医療のみならず「専門家」という権威者は不要であり,むしろ対象者個々のニーズに合わせて動くことのできる,適応力のある人材が求められていた。ちなみに「チームアプローチ」と「フレキシビリティ」が強調されるのは,どのホスピスでも同じであった。
●在宅での死,福祉施設での死
スウェーデンでは,1979年の政府報告でホスピスは否定的に表現されている(「スウェーデンにホスピスはない」という神話はここから生まれた)。「ホスピスという特別な場で特別なケアを行なう必要はない。通常のケアの延長にターミナルケアがある」というのがその理由のようだが,実際には6~7か所のホスピスがある。しかしイギリスのように「在宅死を支えるためのデイホスピス」というようなコンセプトはまだ登場しておらず,日本と同様に死にゆく場所というイメージが強いように思われた。またイギリスでは「ターミナルケア」という用語は末期のみのかかわりと誤解されやすいことなどから「パリアティブ(緩和)ケア」が一般化しつつあるが,スウェーデンではまだアカデミックな用語と思われていると,ある看護婦は言っていた。とはいえ福祉の国らしく,例えばソレンツナにあるグループホームでは「ノン・メディカル」のターミナルケアが実践されている。ここでは死にゆく者への吸引や酸素吸入は無効であると認識されており,「自然な死」に導くことに力が注がれていた。興味を引いたのは,ターミナルケアにとって必要な教育は医療処置を覚えさせることではなく,死を必要以上に怖がらないようにさせることだと強調していた点だ。日本の特別養護老人ホームがターミナル患者を病院に送る理由として排痰や酸素吸入等の難しさがしばしばあげられるが,それらによる延命効果,さらに苦痛緩和の効果も再吟味する必要があるのではないだろうか。
朝日新聞では元日からの連載「いのち長き時代に-生と死と」で,医療から離れた死のあり方を模索している。一方,それに対抗するように毎日新聞では,本人の意思確認という観点から延命治療中止に批判的な記事を載せ始めている(例えば1月7日,27日付朝刊)。イギリスでもスウェーデンでも本人のQOLおよび財政上の要請から,病院外での死(在宅死と福祉施設での死)が強く推進されているが,日本でも今後大きな論議を呼ぶものと思われる。
