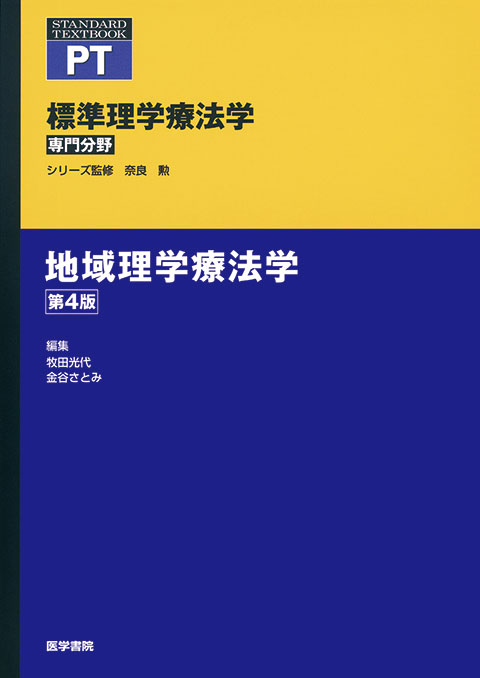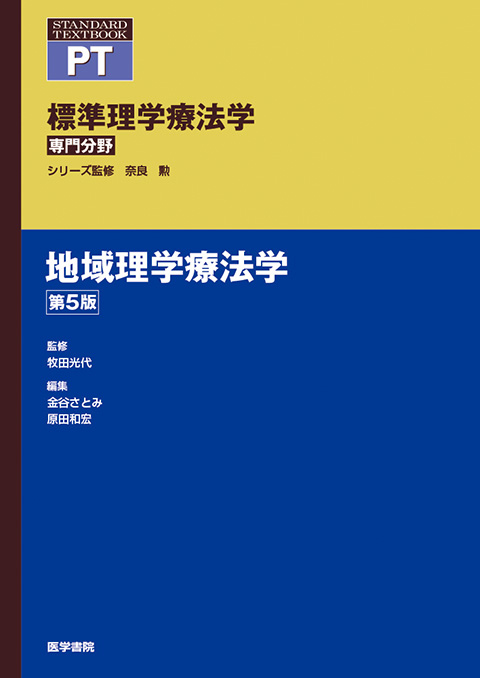地域理学療法学 第4版
定評ある学生向けテキストの最新版!
もっと見る
理学療法士養成課程における「地域理学療法学」のテキストとして最適の1冊。近年改められた関係法や制度の内容を更新するとともに、地域包括ケアシステムの現状と課題や施設および訪問時のリスクマネジメントなどについて加筆するなど、今の地域理学療法学の臨床に即した内容に改訂している。本書の重要箇所を太字で示すことで読者の学習の利便性を図るとともに、今版より全頁がカラー印刷となり、さらに見やすい紙面構成とした。
*「標準作業療法学」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 標準理学療法学 専門分野 |
|---|---|
| シリーズ監修 | 奈良 勲 |
| 編集 | 牧田 光代 / 金谷 さとみ |
| 発行 | 2017年02月判型:B5頁:296 |
| ISBN | 978-4-260-02851-6 |
| 定価 | 5,170円 (本体4,700円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第4版 序
2003年に本書初版が出版されたころは介護保険制度が導入されたばかりで,地域に参入する理学療法士もほんの一握りであった.あれから十数年で高齢化率は1割程度上昇し,それを補うように急ピッチで理学療法士養成校が増加したが,地域理学療法の重要性が高まりを見せ始める一方で,その教育に関しては長年の課題であった.
現在,高齢社会がもたらす医療費の高騰を懸念した制度改正が繰り返されている.リハビリテーションに関する医療費削減のあおりが他の診療と比べて遅くゆるやかだったのは,入院期間短縮などの医療費削減に直結するリハビリテーションの効果のほどを期待されていたことと,過去にリハビリテーション専門職の人員が少なかったためである.近年は,維持期リハビリテーションを介護保険へ移行する具体的な改定が繰り返されており,地域包括ケアシステムの推進,連携重視,早期退院,退院支援…という形で医療と介護は急接近しているといえよう.
特にリハビリテーションに関しては,外来の機能強化だけでなく,介護保険の通所の併設を促すような方向づけがなされており,医療機関であっても地域をさらに意識した活動が求められている.たとえば,入院早期から在宅生活のイメージを明確にした理学療法の提供,退院後における理学療法の必要性の明確化,在宅の通所や訪問の理学療法士などに対しての親密な連携などである.
一方,全国の理学療法士数は著しく増加し,地域によっては,養成校卒業後に臨床経験を積まない新卒者が地域に就職することも稀ではなくなった.医療と介護の親密な連携,医療から介護へ移行後の集中的な理学療法などの提供方法は示されているが,これからは地域理学療法の内容をさらに充実させ,質向上,効果判定,そして他職種間の連携強化とマネジメント力も身につけていく必要がある.また,生活者としての障害児・者にも目を向けなければならない.
それらに対処するために,学校教育においても地域理学療法学についての再構築がなされる必要がある.本書では理学療法の対象が予防から障害急性期,維持期そして終末期まで広がるなかでの業務のあり方,地域連携のあり方を述べている.医療技術者となる学生に対して,対象者を患者としてだけではなく,生活する主体者として捉えるかかわり方も提示している.地域での理学療法士としてのあり方を学ぶことにより,理学療法の可能性はさらに広がると思われる.
2016年11月
牧田 光代
金谷さとみ
2003年に本書初版が出版されたころは介護保険制度が導入されたばかりで,地域に参入する理学療法士もほんの一握りであった.あれから十数年で高齢化率は1割程度上昇し,それを補うように急ピッチで理学療法士養成校が増加したが,地域理学療法の重要性が高まりを見せ始める一方で,その教育に関しては長年の課題であった.
現在,高齢社会がもたらす医療費の高騰を懸念した制度改正が繰り返されている.リハビリテーションに関する医療費削減のあおりが他の診療と比べて遅くゆるやかだったのは,入院期間短縮などの医療費削減に直結するリハビリテーションの効果のほどを期待されていたことと,過去にリハビリテーション専門職の人員が少なかったためである.近年は,維持期リハビリテーションを介護保険へ移行する具体的な改定が繰り返されており,地域包括ケアシステムの推進,連携重視,早期退院,退院支援…という形で医療と介護は急接近しているといえよう.
特にリハビリテーションに関しては,外来の機能強化だけでなく,介護保険の通所の併設を促すような方向づけがなされており,医療機関であっても地域をさらに意識した活動が求められている.たとえば,入院早期から在宅生活のイメージを明確にした理学療法の提供,退院後における理学療法の必要性の明確化,在宅の通所や訪問の理学療法士などに対しての親密な連携などである.
一方,全国の理学療法士数は著しく増加し,地域によっては,養成校卒業後に臨床経験を積まない新卒者が地域に就職することも稀ではなくなった.医療と介護の親密な連携,医療から介護へ移行後の集中的な理学療法などの提供方法は示されているが,これからは地域理学療法の内容をさらに充実させ,質向上,効果判定,そして他職種間の連携強化とマネジメント力も身につけていく必要がある.また,生活者としての障害児・者にも目を向けなければならない.
それらに対処するために,学校教育においても地域理学療法学についての再構築がなされる必要がある.本書では理学療法の対象が予防から障害急性期,維持期そして終末期まで広がるなかでの業務のあり方,地域連携のあり方を述べている.医療技術者となる学生に対して,対象者を患者としてだけではなく,生活する主体者として捉えるかかわり方も提示している.地域での理学療法士としてのあり方を学ぶことにより,理学療法の可能性はさらに広がると思われる.
2016年11月
牧田 光代
金谷さとみ
目次
開く
I 地域理学療法の理念と背景
第1章 地域リハビリテーションの広がりとその社会的背景
第2章 障害児・者施策の推移(保護から自立へ)
第3章 地域包括ケアシステムと地域連携
第4章 生活者としての対象者
II 介護保険制度と理学療法
第1章 介護保険制度
第2章 介護保険サービスとその評価
III 地域理学療法の展開
第1章 行政における理学療法士の役割
第2章 介護予防の展開
第3章 介護保険下の入所サービスの展開
第4章 介護保険下の通所サービスの展開
第5章 訪問における理学療法の展開
第6章 集団への対応
第7章 入院・入所から在宅への準備
第8章 成人障害者支援施設の取り組み
第9章 小児施設の取り組み
IV 地域理学療法のリスクマネジメント
第1章 施設のリスクマネジメント
第2章 訪問のリスクマネジメント
第3章 体力増進とリスク管理
V 地域理学療法の実際
第1章 脳血管障害
第2章 骨折
第3章 慢性呼吸不全
第4章 神経変性疾患
第5章 脊髄損傷
第6章 成人脳性麻痺
第7章 認知症
第8章 終末期における在宅理学療法
VI QOLの増大に向けて
第1章 障害者とスポーツ
第2章 小児理学療法:乳幼児
第3章 小児理学療法:学齢期
第4章 地域における健康増進
第5章 自主グループ活動への支援
VII 生活環境の整備
第1章 住宅改修
第2章 福祉用具
第3章 社会資源
第4章 シーティング
索引
第1章 地域リハビリテーションの広がりとその社会的背景
第2章 障害児・者施策の推移(保護から自立へ)
第3章 地域包括ケアシステムと地域連携
第4章 生活者としての対象者
II 介護保険制度と理学療法
第1章 介護保険制度
第2章 介護保険サービスとその評価
III 地域理学療法の展開
第1章 行政における理学療法士の役割
第2章 介護予防の展開
第3章 介護保険下の入所サービスの展開
第4章 介護保険下の通所サービスの展開
第5章 訪問における理学療法の展開
第6章 集団への対応
第7章 入院・入所から在宅への準備
第8章 成人障害者支援施設の取り組み
第9章 小児施設の取り組み
IV 地域理学療法のリスクマネジメント
第1章 施設のリスクマネジメント
第2章 訪問のリスクマネジメント
第3章 体力増進とリスク管理
V 地域理学療法の実際
第1章 脳血管障害
第2章 骨折
第3章 慢性呼吸不全
第4章 神経変性疾患
第5章 脊髄損傷
第6章 成人脳性麻痺
第7章 認知症
第8章 終末期における在宅理学療法
VI QOLの増大に向けて
第1章 障害者とスポーツ
第2章 小児理学療法:乳幼児
第3章 小児理学療法:学齢期
第4章 地域における健康増進
第5章 自主グループ活動への支援
VII 生活環境の整備
第1章 住宅改修
第2章 福祉用具
第3章 社会資源
第4章 シーティング
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。