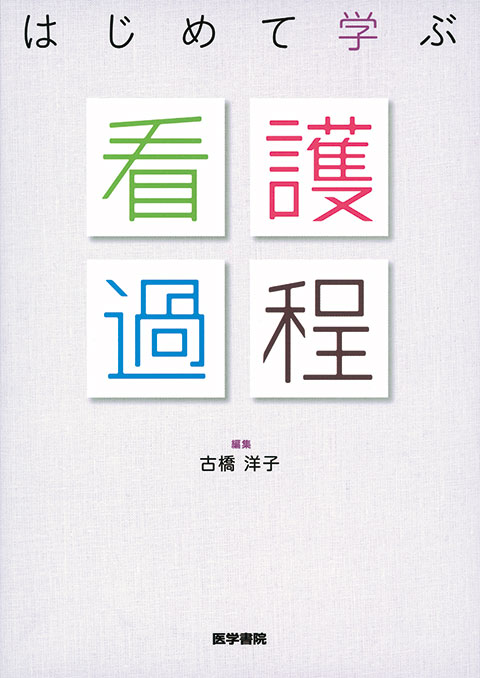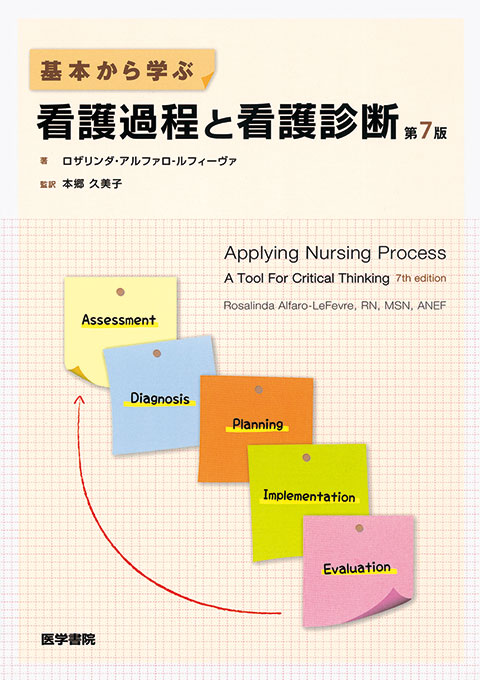はじめて学ぶ看護過程
看護師としての考え方を身につけよう
もっと見る
看護師がケアを行うときに頭の中で行われている思考の一連の流れ、それが「看護過程」である。看護の対象である患者・家族の状態やニーズを捉え、解決すべき問題とそのための方策を導き出していくには、繰り返しのトレーニングが必要となる。本書では、「看護過程」を進めるために必要な考え方、記録のまとめ方を、ステップを追ってていねいに解説する。
| 編集 | 古橋 洋子 |
|---|---|
| 発行 | 2017年01月判型:B5頁:120 |
| ISBN | 978-4-260-02867-7 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに INTRODUCTION
看護過程は難しい——みなさんはそんな印象を持っていませんか。
看護大学・専門学校では看護過程を必ず学びます。学校によって科目名が違うこともありますが,その内容に変わりはありません。講義では模擬患者(あるいはペーパーペイシェント)などを活用して,臨地実習では1人の患者を受け持ちながら,看護過程に必要な思考を養っていきます。学生が十分にその考え方を理解し修得できるよう,教員はさまざまな工夫を凝らしています。しかしながら,いつの時代の学生もこの思考を身につけることに苦しんでおり,「看護過程は難しい」という冒頭の印象を抱いているように思います。
看護過程は看護師が頭で考えて行動する源となる思考過程であり,看護師として臨床で働く上では欠くことができません。また,医療職全員に課されているものが記録(カルテ)であり,看護過程は,記録に必要となる情報を整理するための基本でもあります。
本書は,看護過程をはじめて学ぶ学生に少しでもわかりやすく,身につけやすい内容となることをめざして企画し,書かれています。
本書は,以下の4章で構成されています。
・第Ⅰ章 「看護過程とは」
本書を発行するにあたって,長年にわたり医学書院七尾清氏に動機づけをいただきました。また,企画化・編集面で北原拓也氏,近江友香氏に大変お世話になりました。この場を借り,改めて感謝申し上げます。
2017年1月
編集 古橋 洋子
看護過程は難しい——みなさんはそんな印象を持っていませんか。
看護大学・専門学校では看護過程を必ず学びます。学校によって科目名が違うこともありますが,その内容に変わりはありません。講義では模擬患者(あるいはペーパーペイシェント)などを活用して,臨地実習では1人の患者を受け持ちながら,看護過程に必要な思考を養っていきます。学生が十分にその考え方を理解し修得できるよう,教員はさまざまな工夫を凝らしています。しかしながら,いつの時代の学生もこの思考を身につけることに苦しんでおり,「看護過程は難しい」という冒頭の印象を抱いているように思います。
看護過程は看護師が頭で考えて行動する源となる思考過程であり,看護師として臨床で働く上では欠くことができません。また,医療職全員に課されているものが記録(カルテ)であり,看護過程は,記録に必要となる情報を整理するための基本でもあります。
本書は,看護過程をはじめて学ぶ学生に少しでもわかりやすく,身につけやすい内容となることをめざして企画し,書かれています。
本書は,以下の4章で構成されています。
・第Ⅰ章 「看護過程とは」
看護過程はなぜ必要なのか,日頃の生活に結び付けながら説明しています。
・第Ⅱ章 「看護過程の頭づくり」 看護過程は物事の考え方であることを述べるとともに,看護過程をどのように考えていくか,目で理解しやすい図式を用いて表す工夫をしました。看護の対象となる患者さんを理解するために役立つさまざまな看護の視点,発達段階についても解説しています。
・第Ⅲ章 「思考過程としての看護過程」 看護過程のプロセスを,アセスメント,問題の明確化,看護計画,実施,評価の5段階で解説しています。
・第Ⅳ章 「看護過程を事例で学ぶ」 事例を用い,より具体的に看護過程の考え方を説明しています。臨地実習も見すえて,病態関連図,患者関連図の活用,経過記録のまとめ方も解説しています。
本書を発行するにあたって,長年にわたり医学書院七尾清氏に動機づけをいただきました。また,企画化・編集面で北原拓也氏,近江友香氏に大変お世話になりました。この場を借り,改めて感謝申し上げます。
2017年1月
編集 古橋 洋子
目次
開く
Ⅰ 看護過程とは
看護過程を身につける理由
看護過程の考え方
1 一般的な考え方の道筋:問題解決の思考
2 看護師の考え方の道筋
3 看護師の頭のなか
4 看護の理論家の視点を使う
5 論理的思考を身につける
6 倫理的配慮について
Ⅱ 看護過程の頭づくり
「情報を収集する」とは
1 観察力を身につける
2 情報を収集する
3 観察したことを知識と結びつける
情報の統合
問題解決に向けた思考の流れ
Ⅲ 思考過程としての看護過程
看護過程のステップ
1 アセスメント
1 情報収集
2 情報の分類
3 患者関連図の作成:病態関連図に基づいた患者情報の整理
4 情報の分析と統合(統合アセスメント)
2 問題の明確化
1 優先順位の考え方
2 看護診断名を用いて問題を記述する方法
3 看護計画
1 患者目標(期待される結果)の設定
2 看護計画の立案
4 実施
1 実施内容の記録
2 記録記述時の留意点
5 評価
Ⅳ 看護過程を事例で学ぶ
事例1 ヘンダーソンの看護の視点に沿った看護過程
ステップ1 情報収集・アセスメント
ステップ2 問題の明確化
ステップ3 看護計画
ステップ4・5 実施・評価
事例2 オレムの看護の視点に沿った看護過程
ステップ1 情報収集・アセスメント
ステップ2 問題の明確化
ステップ3 看護計画
ステップ4・5 実施・評価
事例3 ロイの看護の視点に沿った看護過程
ステップ1 情報収集・アセスメント
ステップ2 問題の明確化
ステップ3 看護計画
ステップ4・5 実施・評価
索引
看護過程を身につける理由
看護過程の考え方
1 一般的な考え方の道筋:問題解決の思考
2 看護師の考え方の道筋
3 看護師の頭のなか
4 看護の理論家の視点を使う
5 論理的思考を身につける
6 倫理的配慮について
Ⅱ 看護過程の頭づくり
「情報を収集する」とは
1 観察力を身につける
2 情報を収集する
3 観察したことを知識と結びつける
情報の統合
問題解決に向けた思考の流れ
Ⅲ 思考過程としての看護過程
看護過程のステップ
1 アセスメント
1 情報収集
2 情報の分類
3 患者関連図の作成:病態関連図に基づいた患者情報の整理
4 情報の分析と統合(統合アセスメント)
2 問題の明確化
1 優先順位の考え方
2 看護診断名を用いて問題を記述する方法
3 看護計画
1 患者目標(期待される結果)の設定
2 看護計画の立案
4 実施
1 実施内容の記録
2 記録記述時の留意点
5 評価
Ⅳ 看護過程を事例で学ぶ
事例1 ヘンダーソンの看護の視点に沿った看護過程
ステップ1 情報収集・アセスメント
ステップ2 問題の明確化
ステップ3 看護計画
ステップ4・5 実施・評価
事例2 オレムの看護の視点に沿った看護過程
ステップ1 情報収集・アセスメント
ステップ2 問題の明確化
ステップ3 看護計画
ステップ4・5 実施・評価
事例3 ロイの看護の視点に沿った看護過程
ステップ1 情報収集・アセスメント
ステップ2 問題の明確化
ステップ3 看護計画
ステップ4・5 実施・評価
索引
書評
開く
看護過程の考え方を明快かつ具体的に解説
書評者: 今野 葉月 (埼玉医短大教授・看護学)
看護の醍醐味には“看護の対象の個別性を踏まえた看護の実践”があります。この個別性を踏まえた看護の実践には,看護理論と看護過程が不可欠であることは言うまでもありません。『はじめて学ぶ看護過程』というタイトルが示すとおり,本書は,看護実践に不可欠な要素である看護過程について解説している書籍です。看護過程の各ステップの解説はもちろん,情報収集の方法や記録の書き方などが,わかりやすく具体的に示されています。中でも,第2章の「看護過程の頭づくり」では,看護学生から「難しい」と常に声があがる「アセスメント」にポイントを絞って解説しています。
患者を理解するために,看護学生は事前学習として病態関連図などを作成します。本書でも,患者の病気と成長発達にかかわる一般的な内容を関連図にしていますが,その利用方法がとてもユニークです。それは,作成した病態関連図に患者の情報を重ねるようにしてまとめていく手法で,「積み上げ方式」と紹介されています。「積み上げ方式」でまとめていくと,患者の状態が関連図から浮かび上がって見えるため,患者から収集した情報のまとまりが一目でわかったり,不足している情報に気付いたりすることができるようです。
さらに,本書では情報収集の方法のみにとどまらず,“情報がうまくつながらない”場面を想定して,学生がセルフチェックできるように短い文章でポイントを示しています。思考過程を学ぶ学生が困難にぶつかったとき,乗り越えられる工夫が随所に散りばめられています。
また,看護過程をいくら学習しても,看護理論を活用しなければ患者の持つ健康上の問題を明確にすることはできません。本書では事例を用いて,「ヘンダーソン」「オレム」「ロイ」の看護の視点に沿った看護過程を紹介しています。「基礎看護学ではヘンダーソン看護論を使って看護過程も勉強したけれど,他の理論ではどうしたらよいのだろう?」と考える学生は少なくありません。どの看護理論を用いても“個別性のある看護”を導き出す力をつけるには,事例を通して,看護理論の特徴を踏まえた“アセスメント”や“看護診断”を学ぶことが,効果的と思われます。
本書は看護学生に向けて書かれていますが,教員や臨地実習指導者の立場で読み進めると,編者らが教育経験の中で培った指導方略を読み取ることができます。また,NANDA-NOC-NICの連動についても,事例を用いて具体的に示されていることから,電子カルテの運用にかかわる看護師にもお薦めできます。看護学生から看護師,教員まで,幅広く手に取っていただきたい一冊です。
実践のための看護過程を学ぶ/教える基本の一冊(雑誌『看護教育』より)
書評者: 中村 朝枝 (国家公務員共済組合連合会呉共済病院看護専門学校)
看護基礎教育では,ほとんどの学校が講義や演習,臨地実習などで「看護過程」を取り入れているのではないでしょうか。しかし,学生たちは,看護過程を学習すればするほど「苦手だ。難しい」と頭を抱えているような印象があります。また,「実習で患者さんに援助することはとても楽しい!記録(看護過程)がなければ……」という声をよく耳にします。学生は,看護を実践するとき,さまざまな情報をもとにしながら,思考をめぐらせますが,その内容を言語化することが難しく看護過程に苦手意識があるのではないでしょうか。また,教員も時間をかけて学生に一所懸命指導するのですが,お互いなかなか達成感が得られないことも少なくありません。
本書は全4章で構成されており,第I章「看護過程とは」では,看護過程の必要性や考え方を日頃の生活やマンガ『サザエさん』での場面を例に挙げ説明されています。看護が実践されるとき,見ることのできない看護師の思考過程が言語化されおり,看護実践に至るまでのプロセスがイメージしやすくなっています。
第II章「看護過程の頭づくり」では,情報を得るために必要な観察力や情報整理の仕方,問題点の優先度の考え方について説明されています。
本章では,解剖生理や病態生理について学習した内容を図式化し,それに自ら得た情報を加えながら患者の全体像をとらえる学習方法について説明されています。学生は解剖生理や病態生理の豆知識と,患者の状態を関連づけて考えることが苦手なため,実習前,実習中の学習に大いに役立つと思います。
第III章「思考過程としての看護過程」では,アセスメント,問題の明確化,看護計画,実施,評価の5段階で説明されています。各段階での考え方が具体的に記されているので,学生は実習でこのテキストを活用しながら,患者の看護を考えられるようになっています。
第IV章「看護過程を事例で学ぶ」では,ヘンダーソン,オレム,ロイの理論で3つの事例が紹介されています。それぞれの理論に基づいた看護の視点とアセスメントの枠組みを活用した観察の視点や方法は,学生が看護を考える道しるべになるのではないでしょうか。
看護過程の記録は,用紙を埋めるための書き方の学習ではなく,看護を実践するための考え方の学習であることを実感できる書籍です。
本書は学習方法やポイント,学習を振り返るためのセルフチェックなどが要所にあり,看護過程が苦手な学生が楽しく学べる書であり,また,教員や実習指導者には学生指導のヒントがたくさんつまっています。初学者から教員まで活用できる書籍としてお勧めいたします。
(『看護教育』2017年4月号掲載)
書評者: 今野 葉月 (埼玉医短大教授・看護学)
看護の醍醐味には“看護の対象の個別性を踏まえた看護の実践”があります。この個別性を踏まえた看護の実践には,看護理論と看護過程が不可欠であることは言うまでもありません。『はじめて学ぶ看護過程』というタイトルが示すとおり,本書は,看護実践に不可欠な要素である看護過程について解説している書籍です。看護過程の各ステップの解説はもちろん,情報収集の方法や記録の書き方などが,わかりやすく具体的に示されています。中でも,第2章の「看護過程の頭づくり」では,看護学生から「難しい」と常に声があがる「アセスメント」にポイントを絞って解説しています。
患者を理解するために,看護学生は事前学習として病態関連図などを作成します。本書でも,患者の病気と成長発達にかかわる一般的な内容を関連図にしていますが,その利用方法がとてもユニークです。それは,作成した病態関連図に患者の情報を重ねるようにしてまとめていく手法で,「積み上げ方式」と紹介されています。「積み上げ方式」でまとめていくと,患者の状態が関連図から浮かび上がって見えるため,患者から収集した情報のまとまりが一目でわかったり,不足している情報に気付いたりすることができるようです。
さらに,本書では情報収集の方法のみにとどまらず,“情報がうまくつながらない”場面を想定して,学生がセルフチェックできるように短い文章でポイントを示しています。思考過程を学ぶ学生が困難にぶつかったとき,乗り越えられる工夫が随所に散りばめられています。
また,看護過程をいくら学習しても,看護理論を活用しなければ患者の持つ健康上の問題を明確にすることはできません。本書では事例を用いて,「ヘンダーソン」「オレム」「ロイ」の看護の視点に沿った看護過程を紹介しています。「基礎看護学ではヘンダーソン看護論を使って看護過程も勉強したけれど,他の理論ではどうしたらよいのだろう?」と考える学生は少なくありません。どの看護理論を用いても“個別性のある看護”を導き出す力をつけるには,事例を通して,看護理論の特徴を踏まえた“アセスメント”や“看護診断”を学ぶことが,効果的と思われます。
本書は看護学生に向けて書かれていますが,教員や臨地実習指導者の立場で読み進めると,編者らが教育経験の中で培った指導方略を読み取ることができます。また,NANDA-NOC-NICの連動についても,事例を用いて具体的に示されていることから,電子カルテの運用にかかわる看護師にもお薦めできます。看護学生から看護師,教員まで,幅広く手に取っていただきたい一冊です。
実践のための看護過程を学ぶ/教える基本の一冊(雑誌『看護教育』より)
書評者: 中村 朝枝 (国家公務員共済組合連合会呉共済病院看護専門学校)
看護基礎教育では,ほとんどの学校が講義や演習,臨地実習などで「看護過程」を取り入れているのではないでしょうか。しかし,学生たちは,看護過程を学習すればするほど「苦手だ。難しい」と頭を抱えているような印象があります。また,「実習で患者さんに援助することはとても楽しい!記録(看護過程)がなければ……」という声をよく耳にします。学生は,看護を実践するとき,さまざまな情報をもとにしながら,思考をめぐらせますが,その内容を言語化することが難しく看護過程に苦手意識があるのではないでしょうか。また,教員も時間をかけて学生に一所懸命指導するのですが,お互いなかなか達成感が得られないことも少なくありません。
本書は全4章で構成されており,第I章「看護過程とは」では,看護過程の必要性や考え方を日頃の生活やマンガ『サザエさん』での場面を例に挙げ説明されています。看護が実践されるとき,見ることのできない看護師の思考過程が言語化されおり,看護実践に至るまでのプロセスがイメージしやすくなっています。
第II章「看護過程の頭づくり」では,情報を得るために必要な観察力や情報整理の仕方,問題点の優先度の考え方について説明されています。
本章では,解剖生理や病態生理について学習した内容を図式化し,それに自ら得た情報を加えながら患者の全体像をとらえる学習方法について説明されています。学生は解剖生理や病態生理の豆知識と,患者の状態を関連づけて考えることが苦手なため,実習前,実習中の学習に大いに役立つと思います。
第III章「思考過程としての看護過程」では,アセスメント,問題の明確化,看護計画,実施,評価の5段階で説明されています。各段階での考え方が具体的に記されているので,学生は実習でこのテキストを活用しながら,患者の看護を考えられるようになっています。
第IV章「看護過程を事例で学ぶ」では,ヘンダーソン,オレム,ロイの理論で3つの事例が紹介されています。それぞれの理論に基づいた看護の視点とアセスメントの枠組みを活用した観察の視点や方法は,学生が看護を考える道しるべになるのではないでしょうか。
看護過程の記録は,用紙を埋めるための書き方の学習ではなく,看護を実践するための考え方の学習であることを実感できる書籍です。
本書は学習方法やポイント,学習を振り返るためのセルフチェックなどが要所にあり,看護過程が苦手な学生が楽しく学べる書であり,また,教員や実習指導者には学生指導のヒントがたくさんつまっています。初学者から教員まで活用できる書籍としてお勧めいたします。
(『看護教育』2017年4月号掲載)