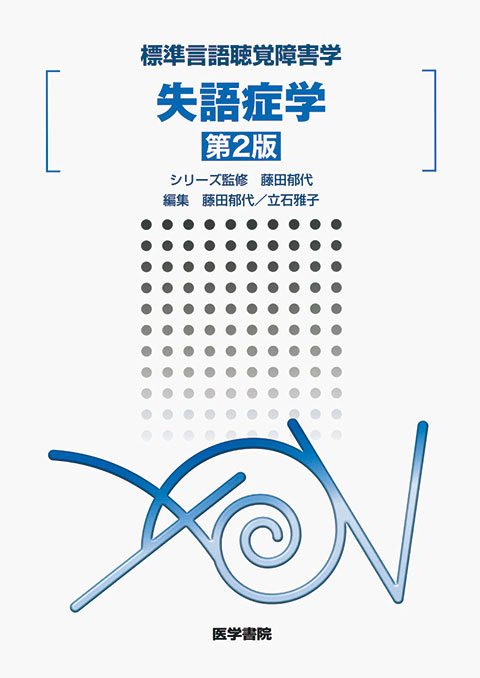失語症学 第2版
失語症学分野の理論・技術の進歩に応える待望の改訂。豊富な実践例は臨床家にも有用。
もっと見る
認知神経心理学的アプローチを中核とする刺激法と行動変容理論を組み合わせた機能訓練法の標準化、病院・施設から在宅・地域へ提供の場の拡がりなど、失語症学分野の理論・技術の進展は著しい。学生及び新たな知識を求める臨床家に、重要な概念、理論、技術、価値観、それを臨床に適用する方法論を体系的に理解させ、豊富な実践例で臨床思考力を向上させるための書。教科書の真価は、学生が臨床現場に出た時に役立つかで決まる。
*「標準言語聴覚障害学」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 標準言語聴覚障害学 |
|---|---|
| シリーズ監修 | 藤田 郁代 |
| 編集 | 藤田 郁代 / 立石 雅子 |
| 発行 | 2015年02月判型:B5頁:384 |
| ISBN | 978-4-260-02095-4 |
| 定価 | 5,500円 (本体5,000円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
第2版の序
初版の発行から6年が経過したが,この間の失語症学および近接する学問分野の理論・技術の進歩には目を見張るものがある.また少子高齢社会を迎えて医療福祉制度の改革が進み,病期別リハビリテーションが充実するとともに,言語聴覚療法を提供する場は病院・施設から在宅・地域へと拡がってきた.言語聴覚障害学は3年経つとその知識の半分が古くなるといわれるが,編集を通してそれを実感している.例えば失語症の機能訓練では刺激法が大きな位置を占めてきたが,現在では認知神経心理学的アプローチを中核として刺激法と行動変容理論を組み合わせた方法が国際的スタンダードとなっている.また失語症の問題を機能,活動,参加,背景因子の次元で捉え,総合的観点から言語治療を提供することが日常臨床の基本として定着し,さまざまな形態の職種間連携が求められるようなってきた.このような学問の進歩と臨床状況の変化を本書に反映すべき時期に来ているとの認識から,この度,第2版を刊行することになった.
本書は言語聴覚士を志す学生のテキストとして広く利用していただいているが,その真価は学生が言語聴覚士になって臨床現場に出たときに問われるだろう.そこで本書の作成に際しては,失語症学における重要な概念,理論,技術,価値観を体系的に学ぶことができるとともに,それを臨床に適用する方法論について深く理解できるよう心掛けた.本書に豊富に掲載されている評価診断や治療の実践例は臨床思考力を磨く材料として役立つものと思われる.
第2版ではかなりの章の内容を大幅に更新し,新しい理論・技術を取り入れたものになっている.特に次の章・項目は新たな執筆者を迎え,内容を刷新している;第1章「言語と脳」の3「言語の神経学的基盤」(26頁),第5章「失語症の症状」の1「言語症状」(74頁),第7章「評価・診断」(169頁),第8章「失語症の言語治療」の2「各期の言語治療」(208頁),3「言語治療の理論と技法」(214頁),3-F「実用的コミュニケーション訓練」(225頁),7-F「重度失語症の訓練」(316頁).また近年の臨床動向を受けて,「原発性進行性失語」(第6章-11,160頁),「社会的アプローチ」(第8章-3-G,230頁),「ニューロリハビリテーション」(第8章-3-J,239頁)について新しく項を設けて解説した.
編集においては標準テキストとしての正確性,客観性,総合性を保つよう留意したが,同時に言語聴覚障害学が発展し続けている若い学問であることを踏まえ,多様な理論・技法を偏りなく取り上げて網羅することに努めた.本書は,言語聴覚士を志す学生のテキストとなることを念頭において著されているが,基本的知識から最先端の理論までを含む豊富な内容は初学者のほか失語症学について新しい知識を得たいと思っている臨床家や各分野の専門家の興味や関心にも応えることができると思われる.本書が失語症臨床を深化する一助となり,読者の探求心を刺激することを期待したい.
本書の執筆者は失語症の臨床・研究の第1線で活躍されている先生方であり,豊かな経験をもとに難解な理論もわかりやすく解説していただいた.失語症臨床への科学的な眼差しと,熱い思いをもってご執筆いただいた方々に心から感謝申しあげる.
最後に,第2版の発刊にご尽力いただいた医学書院編集部の皆様に深く感謝申しあげる.
2015年1月
編集
藤田郁代
立石雅子
初版の発行から6年が経過したが,この間の失語症学および近接する学問分野の理論・技術の進歩には目を見張るものがある.また少子高齢社会を迎えて医療福祉制度の改革が進み,病期別リハビリテーションが充実するとともに,言語聴覚療法を提供する場は病院・施設から在宅・地域へと拡がってきた.言語聴覚障害学は3年経つとその知識の半分が古くなるといわれるが,編集を通してそれを実感している.例えば失語症の機能訓練では刺激法が大きな位置を占めてきたが,現在では認知神経心理学的アプローチを中核として刺激法と行動変容理論を組み合わせた方法が国際的スタンダードとなっている.また失語症の問題を機能,活動,参加,背景因子の次元で捉え,総合的観点から言語治療を提供することが日常臨床の基本として定着し,さまざまな形態の職種間連携が求められるようなってきた.このような学問の進歩と臨床状況の変化を本書に反映すべき時期に来ているとの認識から,この度,第2版を刊行することになった.
本書は言語聴覚士を志す学生のテキストとして広く利用していただいているが,その真価は学生が言語聴覚士になって臨床現場に出たときに問われるだろう.そこで本書の作成に際しては,失語症学における重要な概念,理論,技術,価値観を体系的に学ぶことができるとともに,それを臨床に適用する方法論について深く理解できるよう心掛けた.本書に豊富に掲載されている評価診断や治療の実践例は臨床思考力を磨く材料として役立つものと思われる.
第2版ではかなりの章の内容を大幅に更新し,新しい理論・技術を取り入れたものになっている.特に次の章・項目は新たな執筆者を迎え,内容を刷新している;第1章「言語と脳」の3「言語の神経学的基盤」(26頁),第5章「失語症の症状」の1「言語症状」(74頁),第7章「評価・診断」(169頁),第8章「失語症の言語治療」の2「各期の言語治療」(208頁),3「言語治療の理論と技法」(214頁),3-F「実用的コミュニケーション訓練」(225頁),7-F「重度失語症の訓練」(316頁).また近年の臨床動向を受けて,「原発性進行性失語」(第6章-11,160頁),「社会的アプローチ」(第8章-3-G,230頁),「ニューロリハビリテーション」(第8章-3-J,239頁)について新しく項を設けて解説した.
編集においては標準テキストとしての正確性,客観性,総合性を保つよう留意したが,同時に言語聴覚障害学が発展し続けている若い学問であることを踏まえ,多様な理論・技法を偏りなく取り上げて網羅することに努めた.本書は,言語聴覚士を志す学生のテキストとなることを念頭において著されているが,基本的知識から最先端の理論までを含む豊富な内容は初学者のほか失語症学について新しい知識を得たいと思っている臨床家や各分野の専門家の興味や関心にも応えることができると思われる.本書が失語症臨床を深化する一助となり,読者の探求心を刺激することを期待したい.
本書の執筆者は失語症の臨床・研究の第1線で活躍されている先生方であり,豊かな経験をもとに難解な理論もわかりやすく解説していただいた.失語症臨床への科学的な眼差しと,熱い思いをもってご執筆いただいた方々に心から感謝申しあげる.
最後に,第2版の発刊にご尽力いただいた医学書院編集部の皆様に深く感謝申しあげる.
2015年1月
編集
藤田郁代
立石雅子
目次
開く
第1章 言語と脳
1 言語の構造
A 言語の性質
B 音韻
C 語
D 文
E 談話
2 言語情報の処理過程
A 音声言語の生成と理解
B 文字言語の生成と理解
3 言語の神経学的基盤
A 左右の半球と脳梁
B 脳構造の成り立ちと認知機能との関係-大まかな原則
C 言語を支える神経基盤
D 言語機能や言語症状からみた神経基盤
E 血管支配と失語症候群
F 変性疾患の失語
第2章 失語症の定義
第3章 失語症研究史
A 失語症研究前史
B 古典論の成立
C 古典論に対する批判,知性論
D 失語症評価の歴史的展開
E 失語症治療介入法の歴史
F わが国の失語症研究の歴史
第4章 失語症の原因疾患
A 脳血管障害
B 頭部外傷
C 中枢神経の感染症
D 一過性脳虚血発作
E てんかん
F 脳腫瘍
G 前頭側頭葉変性症
第5章 失語症の症状
1 言語症状
A 発話面の障害
B 復唱および関連する症状
C 聴覚的理解の症状
D 読字の症状
E 書字の症状
F 数・計算の障害
2 近縁症状
A 無言
B 保続
C 語間代
D 反復言語
3 随伴しやすい障害
A 神経学的症状
B 失行
C 失認
D 失語症以外の言語障害
E 記憶障害
F 半側無視
第6章 失語症候群
1 症候群の成り立ち
A 古典論の成立
B ボストン学派による分類
C 古典分類の有用性と限界
2 ブローカ失語
3 ウェルニッケ失語
4 伝導失語
5 健忘失語(失名辞失語)
6 超皮質性失語
A 超皮質性運動失語
B 超皮質性感覚失語
C 語義失語
D 超皮質性混合性失語(言語野孤立症候群)
7 全失語
8 交叉性失語
9 皮質下性失語
10 純粋型
[1 純粋語聾]
[2 発語失行]
[3 純粋失読]
[4 純粋失書]
[5 失読失書]
[6 失語に伴う失読・失書]
A 古典的アプローチ
B 失読および失書への認知神経心理学的アプローチ
11 原発性進行性失語
A 基本概念・症状
B 病変部位と病理
C 評価・診断
D 訓練・指導・援助
E 社会参加
第7章 評価・診断
1 評価・診断の原則
A 評価・診断の原則
2 情報収集
A 言語面の情報
B 医学面の情報
C 関連行動面の情報
D 社会・生活面の情報
E 評価サマリーの作成
3 鑑別診断
A 鑑別診断の方法
B 関連障害との鑑別
第8章 失語症の言語治療
1 言語治療の原則
A 言語治療の枠組み
B 言語治療の提供体制
C 言語治療プロセス
D リハビリテーションにおける連携
2 各期の言語治療
A 急性期の言語治療
B 回復期の言語治療
C 維持期(生活期)の言語治療
3 言語治療の理論と技法
A 刺激法
B 機能再編成法
C 遮断除去法
D 認知神経心理学的アプローチ
E 行動変容法(プログラム学習)
F 実用的コミュニケーション訓練
G 社会的アプローチ
H 拡大・代替コミュニケーション
I メロディック・イントネーション・セラピー(MIT)
J ニューロリハビリテーション
K まとめ
4 失語症の回復
A 予後に関係する要因
B 言語機能の回復
C 神経機能画像からみた失語症の回復
5 言語治療計画の立て方
A 言語治療の適応
B 目標の設定
C 治療方針
D 期間・頻度
E 職種間連携
F 言語治療の効果
G 言語治療のアウトカムの測定方法
6 急性期の訓練・援助
A 急性期における言語聴覚療法の状況
B 急性期の評価
C 急性期の訓練・指導・援助3つの側面
D 急性期の安全管理
E まとめ
7 回復期の訓練・援助
A 語彙訓練
B 構文訓練
C 文字訓練
D 実用的コミュニケーション訓練
E 発語失行の治療
F 重度失語症の訓練
G 心理・社会的問題への対応
8 維持期(生活期)の訓練・援助
A 評価・訓練・指導・援助
9 社会復帰
A 社会復帰とは何か
B 社会適応に影響する要因
C 言語聴覚士の役割
第9章 後天性小児失語症
A 基本概念
B 原因と発生メカニズム
C 症状
D 評価・診断
E 訓練・指導・援助
F 社会参加
参考図書
索引
1 言語の構造
A 言語の性質
B 音韻
C 語
D 文
E 談話
2 言語情報の処理過程
A 音声言語の生成と理解
B 文字言語の生成と理解
3 言語の神経学的基盤
A 左右の半球と脳梁
B 脳構造の成り立ちと認知機能との関係-大まかな原則
C 言語を支える神経基盤
D 言語機能や言語症状からみた神経基盤
E 血管支配と失語症候群
F 変性疾患の失語
第2章 失語症の定義
第3章 失語症研究史
A 失語症研究前史
B 古典論の成立
C 古典論に対する批判,知性論
D 失語症評価の歴史的展開
E 失語症治療介入法の歴史
F わが国の失語症研究の歴史
第4章 失語症の原因疾患
A 脳血管障害
B 頭部外傷
C 中枢神経の感染症
D 一過性脳虚血発作
E てんかん
F 脳腫瘍
G 前頭側頭葉変性症
第5章 失語症の症状
1 言語症状
A 発話面の障害
B 復唱および関連する症状
C 聴覚的理解の症状
D 読字の症状
E 書字の症状
F 数・計算の障害
2 近縁症状
A 無言
B 保続
C 語間代
D 反復言語
3 随伴しやすい障害
A 神経学的症状
B 失行
C 失認
D 失語症以外の言語障害
E 記憶障害
F 半側無視
第6章 失語症候群
1 症候群の成り立ち
A 古典論の成立
B ボストン学派による分類
C 古典分類の有用性と限界
2 ブローカ失語
3 ウェルニッケ失語
4 伝導失語
5 健忘失語(失名辞失語)
6 超皮質性失語
A 超皮質性運動失語
B 超皮質性感覚失語
C 語義失語
D 超皮質性混合性失語(言語野孤立症候群)
7 全失語
8 交叉性失語
9 皮質下性失語
10 純粋型
[1 純粋語聾]
[2 発語失行]
[3 純粋失読]
[4 純粋失書]
[5 失読失書]
[6 失語に伴う失読・失書]
A 古典的アプローチ
B 失読および失書への認知神経心理学的アプローチ
11 原発性進行性失語
A 基本概念・症状
B 病変部位と病理
C 評価・診断
D 訓練・指導・援助
E 社会参加
第7章 評価・診断
1 評価・診断の原則
A 評価・診断の原則
2 情報収集
A 言語面の情報
B 医学面の情報
C 関連行動面の情報
D 社会・生活面の情報
E 評価サマリーの作成
3 鑑別診断
A 鑑別診断の方法
B 関連障害との鑑別
第8章 失語症の言語治療
1 言語治療の原則
A 言語治療の枠組み
B 言語治療の提供体制
C 言語治療プロセス
D リハビリテーションにおける連携
2 各期の言語治療
A 急性期の言語治療
B 回復期の言語治療
C 維持期(生活期)の言語治療
3 言語治療の理論と技法
A 刺激法
B 機能再編成法
C 遮断除去法
D 認知神経心理学的アプローチ
E 行動変容法(プログラム学習)
F 実用的コミュニケーション訓練
G 社会的アプローチ
H 拡大・代替コミュニケーション
I メロディック・イントネーション・セラピー(MIT)
J ニューロリハビリテーション
K まとめ
4 失語症の回復
A 予後に関係する要因
B 言語機能の回復
C 神経機能画像からみた失語症の回復
5 言語治療計画の立て方
A 言語治療の適応
B 目標の設定
C 治療方針
D 期間・頻度
E 職種間連携
F 言語治療の効果
G 言語治療のアウトカムの測定方法
6 急性期の訓練・援助
A 急性期における言語聴覚療法の状況
B 急性期の評価
C 急性期の訓練・指導・援助3つの側面
D 急性期の安全管理
E まとめ
7 回復期の訓練・援助
A 語彙訓練
B 構文訓練
C 文字訓練
D 実用的コミュニケーション訓練
E 発語失行の治療
F 重度失語症の訓練
G 心理・社会的問題への対応
8 維持期(生活期)の訓練・援助
A 評価・訓練・指導・援助
9 社会復帰
A 社会復帰とは何か
B 社会適応に影響する要因
C 言語聴覚士の役割
第9章 後天性小児失語症
A 基本概念
B 原因と発生メカニズム
C 症状
D 評価・診断
E 訓練・指導・援助
F 社会参加
参考図書
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。