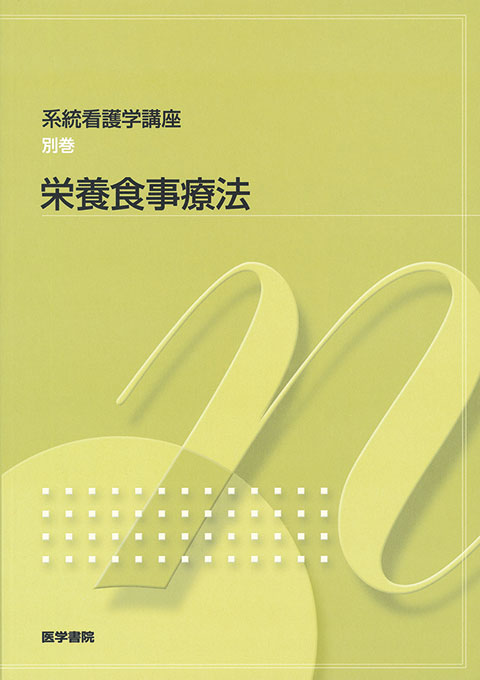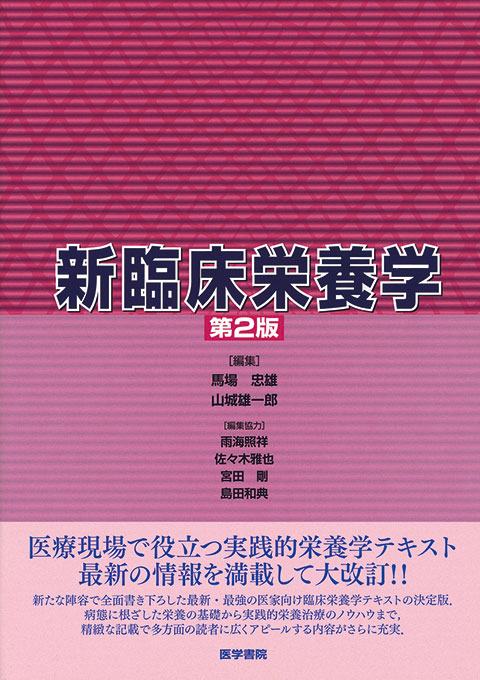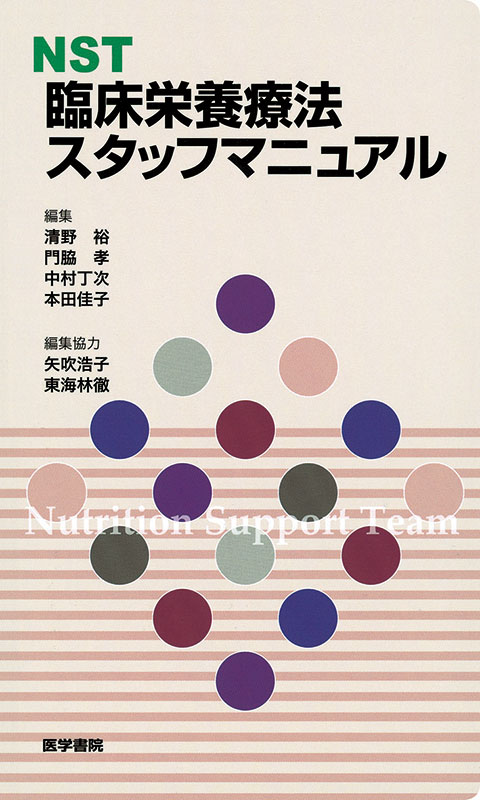栄養食事療法 第3版
本書の特長
もっと見る
●「日本人の食事摂取基準 2015年版」の最新データを反映させています。
●栄養食事療法の基礎から疾患ごとの栄養食事療法までを総合的に学習できる内容です。
●「第3章 症状を持つ患者の栄養食事療法」「第4章 呼吸器疾患患者の栄養食事療法」「第13章 がん患者の栄養食事療法」の章を新設し、一層の充実をはかりました。
● 『人体の構造と機能[3]栄養学』 で基礎を固め、本書で臨床場面に役だつ知識を学ぶことができます。臨地実習や卒後の参考資料としても役だつテキストです。
*「系統看護学講座」は2018年版より新デザインとなりました。
*「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
*「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 系統看護学講座 |
|---|---|
| 著 | 足立 香代子 / 可知 直子 / 川島 由起子 / 斎藤 恵子 / 齋藤 長徳 / 柴田 みち / 杉山 真規子 / 田中 弥生 / 寺本 房子 / 中村 丁次 / 松原 薫 |
| 発行 | 2015年01月判型:B5頁:268 |
| ISBN | 978-4-260-02006-0 |
| 定価 | 1,980円 (本体1,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はしがき
人間は,この世に生を受け,死を迎えるまで,生命活動に必要な物質を体外から補給しつづけなければならず,この必須成分を栄養素と名づけた。私たちは,自分たちが生存する環境のなかで獲得した食物から,この栄養素を補給し,生命を維持している。一方,人間は,火や道具を用いて食物を調理や加工し,さらに食物の栽培や飼育を行い,多様な食生活を発展させた。食物選択の内容は複雑で,個人や集団により特徴があり,ときとしてエネルギーや栄養素の摂取内容が,生体が必要とする内容とずれを生じることがある。すなわち,生体の必要量と食物からの摂取内容とが一致しないのであり,このずれが異常に大きくなり,さらに長期に及び,生体が持つ恒常性による調整能力をこえたときに,代謝に異常がおこり,疾病状態へと進展する。
このように,食習慣が誘因となって発症する慢性疾患を,とくに生活習慣病とよぶようになった。生活習慣病の予防には,できる限りずれが少ない適正な食習慣を形成することと,早期にこのずれを見いだし,食習慣を改善することが必要である。また,生活習慣病のような慢性疾患の多くは,不可逆的な疾患であるために,多くの場合,完治することが不可能で,治療の目標は増悪化を防止し,合併症の出現を防ぐことになる。食事療法が,慢性疾患の早期においては,薬物療法以上の効果があることもわかってきた。
医療・福祉の領域においては,傷病者・高齢者にみられる低栄養障害が重要な課題になってきている。とくに,エネルギー・タンパク質欠乏症やビタミン・ミネラル欠乏症を放置すると,免疫力が低下し,病気の回復が遅れ,合併症がおこりやすくなる。それによって薬物使用が多くなり,入院日数がのび,さらに医療費の増大などがおこる。
ところで,近年,体内への栄養素の補給法が進歩・多様化し,食物の経口摂取だけではなく,カテーテルを用いて栄養剤を消化管に投与する経管・経腸栄養,静脈に栄養剤を直接投与する経静脈栄養が利用されるようになった。投与されるものも日常的な食品だけではなく,病者用特別用途食品・経腸栄養食品・栄養剤・保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品)などの特殊な食品が利用される。栄養補給法がこのように多様化したために,食事療法は,栄養食事療法といわれるようになってきた。
栄養食事療法の目的は,傷病者に対して,健康状態や栄養状態をよりよい状態へ改善し,疾病の予防・治療・増悪化防止をし,さらにQOLを向上させることである。効果的な栄養食事療法を進めるためには,実行すべき手順をシステム化する必要があり,対象者の病態や栄養状態を評価・判定し,栄養食事療法の計画を立て,それに従って実施し,さらにその効果を評価するマネジメントが必要になる。そのためには,関連する職種が連携したチームケアが重要である。
看護師は,とくに管理栄養士・栄養士と連携し,患者個々に適正な食事が提供されているかをチェックし,摂食が困難な場合には食事介助をする。さらに,必要に応じて治療食の意義や特徴を指導し,摂食状況を観察・記録し,食環境を含めて,その状況が改善するように努めることになる。また,栄養食事療法を実践するには,食生活を医療の監視下におき,その管理を行うことが生涯にわたり必要で,患者はエネルギーおよび栄養素の摂取を調整するために,自由な食事が困難になる。この不自由さを生活のなかでどのように解決するかも重要な課題であり,看護師の役割は大きい。
改訂の趣旨
本書は,こうした栄養食事療法について学ぶための教科書として,2005年に初版が刊行された。このたびの改訂では,2014年に発表となった「日本人の食事摂取基準(2015年版)」の内容を反映させ,また,できる限り最新の知見を導入して内容の刷新をはかった。ご活用いただき,忌憚のないご意見をいただければ幸いである。
2014年12月
著者ら
人間は,この世に生を受け,死を迎えるまで,生命活動に必要な物質を体外から補給しつづけなければならず,この必須成分を栄養素と名づけた。私たちは,自分たちが生存する環境のなかで獲得した食物から,この栄養素を補給し,生命を維持している。一方,人間は,火や道具を用いて食物を調理や加工し,さらに食物の栽培や飼育を行い,多様な食生活を発展させた。食物選択の内容は複雑で,個人や集団により特徴があり,ときとしてエネルギーや栄養素の摂取内容が,生体が必要とする内容とずれを生じることがある。すなわち,生体の必要量と食物からの摂取内容とが一致しないのであり,このずれが異常に大きくなり,さらに長期に及び,生体が持つ恒常性による調整能力をこえたときに,代謝に異常がおこり,疾病状態へと進展する。
このように,食習慣が誘因となって発症する慢性疾患を,とくに生活習慣病とよぶようになった。生活習慣病の予防には,できる限りずれが少ない適正な食習慣を形成することと,早期にこのずれを見いだし,食習慣を改善することが必要である。また,生活習慣病のような慢性疾患の多くは,不可逆的な疾患であるために,多くの場合,完治することが不可能で,治療の目標は増悪化を防止し,合併症の出現を防ぐことになる。食事療法が,慢性疾患の早期においては,薬物療法以上の効果があることもわかってきた。
医療・福祉の領域においては,傷病者・高齢者にみられる低栄養障害が重要な課題になってきている。とくに,エネルギー・タンパク質欠乏症やビタミン・ミネラル欠乏症を放置すると,免疫力が低下し,病気の回復が遅れ,合併症がおこりやすくなる。それによって薬物使用が多くなり,入院日数がのび,さらに医療費の増大などがおこる。
ところで,近年,体内への栄養素の補給法が進歩・多様化し,食物の経口摂取だけではなく,カテーテルを用いて栄養剤を消化管に投与する経管・経腸栄養,静脈に栄養剤を直接投与する経静脈栄養が利用されるようになった。投与されるものも日常的な食品だけではなく,病者用特別用途食品・経腸栄養食品・栄養剤・保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品)などの特殊な食品が利用される。栄養補給法がこのように多様化したために,食事療法は,栄養食事療法といわれるようになってきた。
栄養食事療法の目的は,傷病者に対して,健康状態や栄養状態をよりよい状態へ改善し,疾病の予防・治療・増悪化防止をし,さらにQOLを向上させることである。効果的な栄養食事療法を進めるためには,実行すべき手順をシステム化する必要があり,対象者の病態や栄養状態を評価・判定し,栄養食事療法の計画を立て,それに従って実施し,さらにその効果を評価するマネジメントが必要になる。そのためには,関連する職種が連携したチームケアが重要である。
看護師は,とくに管理栄養士・栄養士と連携し,患者個々に適正な食事が提供されているかをチェックし,摂食が困難な場合には食事介助をする。さらに,必要に応じて治療食の意義や特徴を指導し,摂食状況を観察・記録し,食環境を含めて,その状況が改善するように努めることになる。また,栄養食事療法を実践するには,食生活を医療の監視下におき,その管理を行うことが生涯にわたり必要で,患者はエネルギーおよび栄養素の摂取を調整するために,自由な食事が困難になる。この不自由さを生活のなかでどのように解決するかも重要な課題であり,看護師の役割は大きい。
改訂の趣旨
本書は,こうした栄養食事療法について学ぶための教科書として,2005年に初版が刊行された。このたびの改訂では,2014年に発表となった「日本人の食事摂取基準(2015年版)」の内容を反映させ,また,できる限り最新の知見を導入して内容の刷新をはかった。ご活用いただき,忌憚のないご意見をいただければ幸いである。
2014年12月
著者ら
目次
開く
第1章 栄養食事療法とは (中村丁次)
A 栄養食事療法の概要
B 医療・福祉の場における栄養食事療法
第2章 栄養食事療法の実際 (中村丁次)
A 病人食の分類と特徴
B 栄養補給法
C 栄養アセスメントの基本
第3章 症状を持つ患者の栄養食事療法 (田中弥生・松原薫)
A ショック
B 発熱・低体温
C 脱水・浮腫
D やせ・過体重
E 便秘・下痢
F 摂食・嚥下障害
第4章 呼吸器疾患患者の栄養食事療法 (可知直子)
A 肺炎
B 急性呼吸不全
C 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
第5章 循環器疾患患者の栄養食事療法 (寺本房子)
A 高血圧症
B 動脈硬化症
C 虚血性心疾患
D うっ血性心不全
E 脳血管障害
第6章 消化器疾患患者の栄養食事療法 (斎藤恵子)
A 胃炎
B 胃・十二指腸潰瘍
C 機能性ディスペプシア
D 過敏性腸症候群
E クローン病
F 短腸症候群
G 人工肛門造設患者
H 潰瘍性大腸炎
I 吸収不良症候群
J タンパク漏出症候群
K 便秘
L 下痢
M 慢性肝炎
N 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)
O 肝硬変症
P 脂肪肝
Q 膵炎
R 胆石症・胆嚢炎
S 胃食道逆流症
第7章 腎・泌尿器疾患患者の栄養食事療法 (足立香代子)
A 腎疾患
B 泌尿器疾患
第8章 栄養代謝性疾患患者の栄養食事療法 (川島由起子)
A 肥満
B エネルギー・タンパク質欠乏症
C ビタミン・ミネラル欠乏症
D 糖尿病
E 脂質異常症
F 高尿酸血症・痛風
第9章 血液疾患患者の栄養食事療法 (寺本房子)
A 鉄欠乏性貧血
B 巨赤芽球性貧血
C 白血病
第10章 熱傷・褥瘡の栄養食事療法 (足立香代子)
A 熱傷
B 褥瘡
第11章 精神・神経疾患患者の栄養食事療法 (川島由起子)
A 摂食障害
B アルコール依存症
第12章 術前・術後の栄養管理 (足立香代子)
A 術前・術後の栄養管理の原則
B 胃の摘出手術
C 大腸がんの手術
D 食道がんの手術
E 循環器の手術
第13章 がん患者の栄養食事療法 (中村丁次・杉山真規子)
A がんの発症に関係する栄養食事療法
B がん患者と栄養
C がん治療における栄養食事療法
第14章 妊産婦・更年期の栄養食事療法 (斎藤恵子・柴田みち)
A 妊産婦の栄養と食事
B 更年期の栄養と食事
第15章 小児の栄養食事療法 (柴田みち)
A 小児の栄養管理の基本
B 低出生体重児
C 小児肥満
D 先天性代謝異常
E 食物アレルギー
F アトピー性皮膚炎
G 周期性嘔吐症(アセトン血性嘔吐症)
H 乳児下痢症
第16章 高齢者の栄養食事療法 (足立香代子)
A 高齢者の栄養管理の基本
B 骨粗鬆症
第17章 医療保険制度・介護保険制度と食事 (齋藤長徳)
A 医療保険と食事
B 介護保険と食事
索引
A 栄養食事療法の概要
B 医療・福祉の場における栄養食事療法
第2章 栄養食事療法の実際 (中村丁次)
A 病人食の分類と特徴
B 栄養補給法
C 栄養アセスメントの基本
第3章 症状を持つ患者の栄養食事療法 (田中弥生・松原薫)
A ショック
B 発熱・低体温
C 脱水・浮腫
D やせ・過体重
E 便秘・下痢
F 摂食・嚥下障害
第4章 呼吸器疾患患者の栄養食事療法 (可知直子)
A 肺炎
B 急性呼吸不全
C 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
第5章 循環器疾患患者の栄養食事療法 (寺本房子)
A 高血圧症
B 動脈硬化症
C 虚血性心疾患
D うっ血性心不全
E 脳血管障害
第6章 消化器疾患患者の栄養食事療法 (斎藤恵子)
A 胃炎
B 胃・十二指腸潰瘍
C 機能性ディスペプシア
D 過敏性腸症候群
E クローン病
F 短腸症候群
G 人工肛門造設患者
H 潰瘍性大腸炎
I 吸収不良症候群
J タンパク漏出症候群
K 便秘
L 下痢
M 慢性肝炎
N 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)
O 肝硬変症
P 脂肪肝
Q 膵炎
R 胆石症・胆嚢炎
S 胃食道逆流症
第7章 腎・泌尿器疾患患者の栄養食事療法 (足立香代子)
A 腎疾患
B 泌尿器疾患
第8章 栄養代謝性疾患患者の栄養食事療法 (川島由起子)
A 肥満
B エネルギー・タンパク質欠乏症
C ビタミン・ミネラル欠乏症
D 糖尿病
E 脂質異常症
F 高尿酸血症・痛風
第9章 血液疾患患者の栄養食事療法 (寺本房子)
A 鉄欠乏性貧血
B 巨赤芽球性貧血
C 白血病
第10章 熱傷・褥瘡の栄養食事療法 (足立香代子)
A 熱傷
B 褥瘡
第11章 精神・神経疾患患者の栄養食事療法 (川島由起子)
A 摂食障害
B アルコール依存症
第12章 術前・術後の栄養管理 (足立香代子)
A 術前・術後の栄養管理の原則
B 胃の摘出手術
C 大腸がんの手術
D 食道がんの手術
E 循環器の手術
第13章 がん患者の栄養食事療法 (中村丁次・杉山真規子)
A がんの発症に関係する栄養食事療法
B がん患者と栄養
C がん治療における栄養食事療法
第14章 妊産婦・更年期の栄養食事療法 (斎藤恵子・柴田みち)
A 妊産婦の栄養と食事
B 更年期の栄養と食事
第15章 小児の栄養食事療法 (柴田みち)
A 小児の栄養管理の基本
B 低出生体重児
C 小児肥満
D 先天性代謝異常
E 食物アレルギー
F アトピー性皮膚炎
G 周期性嘔吐症(アセトン血性嘔吐症)
H 乳児下痢症
第16章 高齢者の栄養食事療法 (足立香代子)
A 高齢者の栄養管理の基本
B 骨粗鬆症
第17章 医療保険制度・介護保険制度と食事 (齋藤長徳)
A 医療保険と食事
B 介護保険と食事
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。