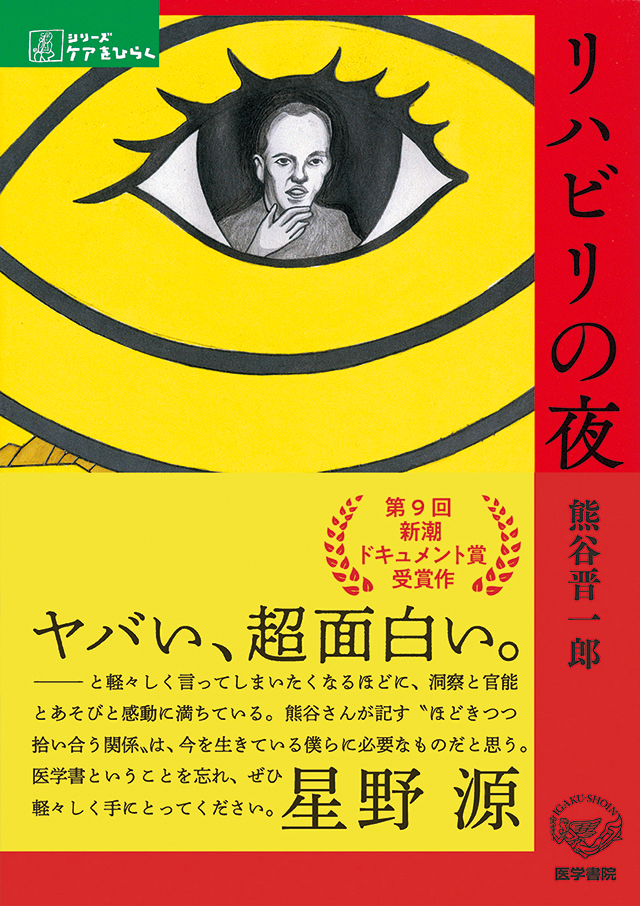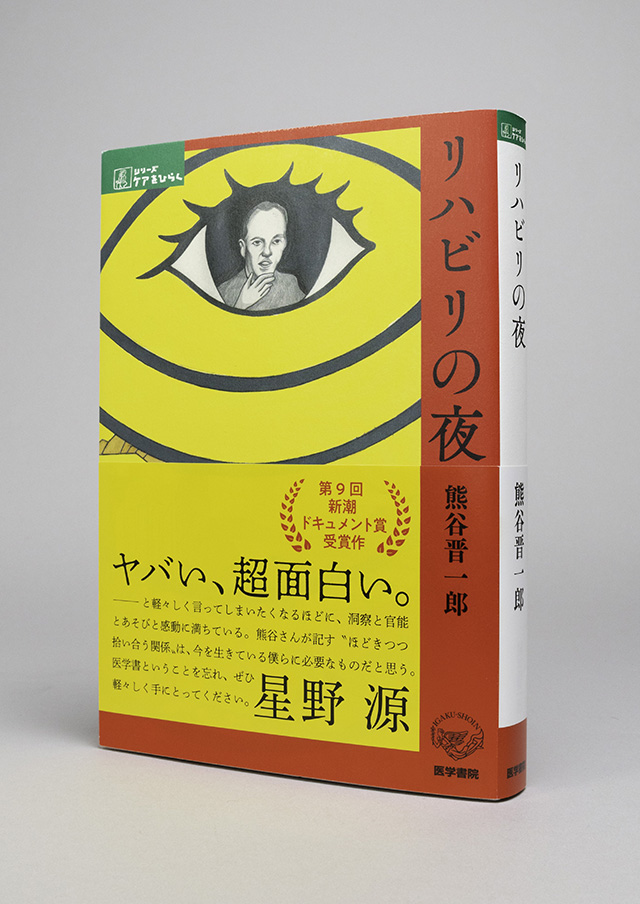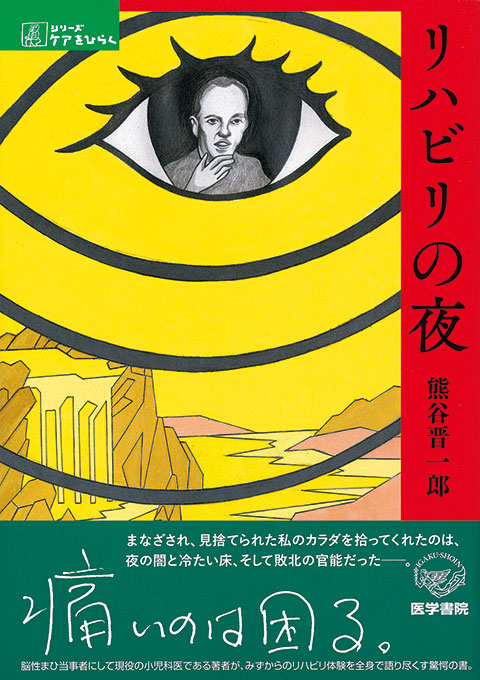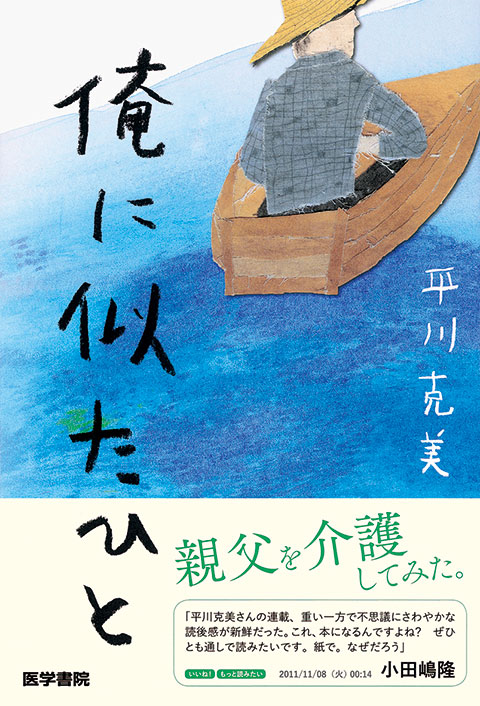リハビリの夜
痛いのは困る。気持ちいいのがいい。
もっと見る
現役の小児科医にして脳性まひ当事者である著者は、あるとき「健常な動き」を目指すリハビリを諦めた。そして、《他者》や《モノ》との身体接触をたよりに「官能的」にみずからの運動を立ち上げてきた。リハビリキャンプでの過酷で耽美な体験、初めて電動車いすに乗ったときのめくるめく感覚などを全身全霊で語り尽くし、リハビリテーションを根底から定義しなおす驚愕の書。
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 熊谷 晋一郎 |
| 発行 | 2009年12月判型:A5頁:264 |
| ISBN | 978-4-260-01004-7 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 序文
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
●本書が新潮ドキュメント賞を受賞!
第9回新潮ドキュメント賞(主催:財団法人新潮文芸振興会 発表誌:「新潮45」)が2010年8月26日に発表となり,本書が選出されました。同賞は,ジャーナリスティックな視点から現代社会と深く切り結び、その構成・表現において文学的にも良質と認められる作品に授与されるものです。同賞の詳細情報はこちら(新潮社「新潮ドキュメント賞」のページ)。
●動画配信中!
著者・熊谷晋一郎氏からのメッセージです。
序文
開く
今から三二年前に、私は生まれた。胎児と母体をつなぐ胎盤に異常があったせいで、出産時に酸欠になり、脳の中でも「随意的な運動」をつかさどる部分がダメージを受けたらしい。そして私の身体の状態は、「脳の損傷が原因で、イメージに沿った運動を繰り出すことができない状態」というような表現で、専門家によって説明されている。この通説に従えば、私の身に起こったことはとてもわかりやすく説明された気になる。
しかしこのような説明は、特にリハビリや療育の現場でさまざまな拡大解釈を生み出す可能性を持っている。たとえば、「脳には損傷があるが、それ以外の筋肉や骨には問題がない。これはつまり、乗り物には異常がないが、それを操縦する認知や行動といった過程に問題があるということだ。だから、注意の向け方、イメージの描き方、努力の仕方などに介入しなくてはならない」というような実践的な解釈がなされたりするのである。
むろん、そのような解釈は、間違いとは言えない。けれどもその解釈を聞いた当人やその家族は、また違った解釈をそこに付加していくことになる。つまり、「目に見える体の問題だったらあきらめるしかないが、努力や気の持ちようといった心の問題だというなら希望が持てる」などというように。こうして、「体の問題ではなく、心の問題」という解釈のもとで、目標設定は青天井に高められ、お手本どおりに動けない原因は「家族や本人の意思や努力の問題」に帰責させられやすくなる。
私自身、このようなリハビリを受けてきて、手本どおりにうまく体を操れない自分自身に苛立ちを覚え、劣等感を味わってきた。しかしその後、私の体に合ったオリジナルの運動イメージを、実際の暮らしの中でモノや人と交渉していくことで徐々に立ち上げてきた。
随意運動を手にするためには、既存の運動イメージに沿うような体の動かし方を練習するしかない、というのは間違いだ。それとは逆に、運動イメージのほうを体に合うようなものに書きかえるというやり方もある。私はこのような自分の経験を通して、規範的な運動イメージを押し付けられ、それを習得し切れなかった一人として、リハビリの現場のみならず、広く社会全体において暗黙のうちに前提とされている「規範的な体の動かし方」というものを、問いなおしていきたいと思っている。
本書ではまた、体に合わない規範を押し付けられたという体験が、私の体に刻み込んでいった独特の官能についても考察する。規範と身体とのあいだに生じる乖離のなかで、私の体は緊張と弛緩を繰り返す。そしてその反復は、強い官能を伴うものであると同時に、既存の運動イメージをほぐし、組み立てなおして、私にあった運動を新たに立ち上げる源でもあることを示していきたいと思う。
読者の中には、「規範的な体の動かし方」や「運動というもの一般」への問いなおしというテーマを論じるにあたって、「官能」を媒介とすることに、戸惑いを感じる方もおられるかもしれない。しかし私は、「運動に内在するはずの官能」というものに目を向けることが、このテーマにとって重要な論点だと考えている。
本書では、私の中で湧き上がる、「痛いのは困る、気持ちいいのがいい」という荒削りで弱々しい体の声を羅針盤にして論じていきたい。
目次
開く
序章 リハビリキャンプ
第一章 脳性まひという体験
1 脳内バーチャルリアリティ
2 緊張しやすい体
3 折りたたみナイフ現象の快楽
4 動きを取り込み、人をあやつる
第二章 トレイナーとトレイニー
1 ほどかれる体
2 まなざされる体
3 見捨てられる体
4 心への介入が体をこわばらせる
5 体への介入が暴力へと転じるとき
6 女子大生トレイナーとの「ランバダ」
第三章 リハビリの夜
1 夕暮れ
2 歩かない子の部屋
3 歩く子の部屋
4 女風呂
5 自慰にふける少年
第四章 耽り
1 対比に萌える
2 取り込めないセックス
3 規範・緊張・官能
4 打たれる少女
第五章 動きの誕生
1 モノと作り上げる動き
2 人と作り上げる動き
3 「大枠の目標設定」が重要な理由
4 世界に注ぐまなざしの共有
5 助け合いから暴力へ
第六章 隙間に「自由」が宿る-もうひとつの発達論
1 両生類と爬虫類の中間くらい?
2 便意という他者
3 身体に救われる
4 むすんでひらいてつながって
5 衰えに向けて
注
文献
あとがき
書評
開く
●新聞で紹介されました
《リハビリにとどまらず、体の「動き」の本質を問い直した。》
(著者来店:本よみうり堂:読売新聞(YOMIURI ONLINE)2010年3月14日より)
《客観的な記述に、これほど共感できたのは、長い間生きてきたつもりだが、はじめてだといってもいい。……いろいろな立場の人に本気で読んでほしい。しみじみそう思う。》――養老孟司(解剖学者)
(『毎日新聞』2010年3月7日朝刊・書評欄より)
《まさに読みながら、脳性まひを追体験しているような感覚を味わった。…渾身の一冊というのは、このような本のことをいうのだろう。》――緑慎也(ライター)
(『週刊読書人』2010年3月12日号・第2829号より)
《流体としての身体は、こんなにも世界と官能的に関わっていたのだ。》――河野哲也(立教大学教授・哲学)
(『北海道新聞』2010年2月14日朝刊・書評欄より)
●雑誌で紹介されました
《読めば読むほど、彼の物語にものすごく共感してしまったのである! 正月草々、目からウロコが落ちた気分だ。》――中村うさぎ氏(作家)
(『週刊文春』2010年1月21日号、1月28日号、2月4日号 連載コラム「さすらいの女王」にて3回連続で紹介されました)
●webで紹介されました
敗北の体験から会得できる官能(紀伊國屋書店「書評空間」より)
《熊谷(の文章)の魅力は、熊谷自身の体験と体験の概念化が織りなす説得力だ。たとえば、トイレと「つながれなかった」カレはいったん「便意」に敗北するが、「失禁」が快楽をもたらす他者として意識され、ドラマチックに展開されていく。》――川口 有美子(日本ALS協会理事)
(紀伊國屋書店「書評空間」:川口有美子の書評ブログ 2010年02月20日より)
《これはちょっとない、とてつもない著作である。すでに伏見の周辺では「驚くべき本」と評価が天井を突き抜けていて……》――伏見 憲明(作家)
(ポット出版 マガジンポット:伏見憲明の公式サイト 2010年1月4日付記事 「いただいたご本 『リハビリの夜』」より)
《すごい本に出合ったと思った。》――片岡 義博(記者)
(全国新聞ネット 47NEWS(よんななニュース)新刊レビュー「障害を超え、いかに世界とつながるか 『リハビリの夜』 熊谷晋一郎著」 2010年1月25日より)
衰えの悲しみから,つながっていく官能へ (雑誌『看護管理』より)
書評者:河村 圭子(梅花女子大学看護学部看護学科教授)
書評を見る閉じる
生きる切実さが迫るリハビリ体験
本書は,脳性まひの当事者で小児科医でもある著者が,自らのリハビリ体験を主軸に,幼少期から現在に至るまでの軌跡を綴ったものである。
脳性まひによる運動機能の障害は千差万別である。著者の場合は「随意的な運動をつかさどる部分がダメージ」を受けたことによって,「脳には損傷があるが筋肉や骨には問題がない。つまり,乗り物には異常がないが,それを操縦する認知や行動といった過程に問題がある。だから,注意の向け方,イメージの描き方,努力の仕方などに介入しなくてはならない」といった実践的解釈がなされてきた。そこから,目に見える体の問題だったらあきらめるしかないが,努力や気のもちようといった心の問題だというなら希望がもてるといった解釈が派生し,リハビリの目標は高められ,うまく動けない原因は家族や本人の意志や努力の問題であるとされた。著者にとって,このような現実にそぐわない,希望的観測に支えられただけのリハビリが負担であったことは想像に難くない。実際,本書で描かれた脳性まひとリハビリの体験は,淡々とした語り口とは裏腹に生きている切実さが迫ってくる。
体験者の言葉だからこそ,感覚的に“わかる”
まず,脳性まひという症状を,自らの体験というフィルターを通して私たちに解説してくれる。著者の表現は独特で,脳性まひの体験者でなければ描けなかった内実が伝わり,従来の脳性まひの知識によって理解するのではなく,感覚的に“わかる”のだ。また、自分の身体状態を冷徹に分析し記述する力,それは医師という職業と無縁ではないだろう。いったい著者は,どれくらいの困難を克服してきたのだろうか。その過程で自分の身体とその動きを見極め,限界を可能性に変えてきた意志と実行力は並大抵ではなかったと思われる。
次に,思春期を経て青年となった著者が,これまでのリハビリに懐疑的になると同時に思索的になり,自らが生きることの困難や性に目覚めていく過程が綴られている。さらに,トレイナーとトレイニー(障がいをもたない者ともつ者)の関係を「ほどきつつ拾いあう関係」「まなざし/まなざされる関係」「加害者/被害者関係」に分けて説明している。これらの関係性においては,リハビリにおける身体への物理的な介入が虐待へと転じることさえあるという。これほどまでに明確な告発と解説を,私は他に知らない。
最後に,衰えていく自身について語っている。できたことができなくなっていくことは痛みを伴うが,同時に許しでもあり,周囲とのつながりの回復でもある。衰えは不安や悲しみだけではなく,身体が開かれ,つながっていくような官能を伴うものになるという。施設の高い窓から見た夕日に労われ許され,泣きそうになったという述懐とともに,私たち読み手は静かに本を閉じることになる。これからも続く著者の日々の営みと,看護者としてリハビリの現場に立つ責務に思いをはせながら。
(『看護管理』2011年1月号掲載)
医療専門家でありながら、脳性マヒ者としての自分の身体の声を拾っている (『けんこう通信』より)
書評者:小佐野 彰(脳性マヒ当事者・NPO法人「自立の家」代表)
書評を見る閉じる
今回は、2009年12月に出版された『リハビリの夜』(熊谷晋一郎著、医学書院)を紹介します。この本は紛れもなく労作で、著者の障害当事者として「健常者の動きを習得すること」を課題とされたリハビリテーションを受け続け、ついに「健常者の動きを習得することができなかった」体験を振り返り、私たち読者にモノや他者との関係を通して世界とのつながりを考えさせる物語です。全編にわたって鋭い洞察と機知に富む内容となっています。なにせ、私が仕事以外に真面目に読んだ小説以外の数少ない作品なので、記念すべき名著といえます。そこで本の内容に触れる前に、著者の紹介と私との出会いについて若干告白するところから始めたいと思います。
*
熊谷晋一郎さんは脳性マヒ者(痙直型)で、電動車イスを使用しながら小児科医として臨床現場で活躍しています。それとともに東京大学先端科学技術研究センターの特任講師として「バリアフリー」や「リハビリテーション」や「全身に障害のある人の二次障害」等の課題に取り組んでいます。そんな紹介をするといかにもエリート然とした厳めしい姿が思い浮かぶかもしれませんが、私が言うと失礼にあたりますが、見方によってはとても愛くるしい顔をしていて、子ども好きで妙に人懐っこいムードを醸し出す不思議な人です。それでいて冴えた論理的な面と哲学的な思考を併せ持ち、現在の私にとっては敬愛する友人の一人なのですが、最初からこのような親しみを感じる関係になれたわけではありませんでした。
私が熊谷さんと初めてお会いしたのは、今から約13年前にさかのぼります。当時、彼は東京大学に入学され、マスコミ等から脚光を浴びる存在でした。私は、縁あって同大学の学生サークルに出入りしていた関係で彼の存在は知っていましたが、私が勝手に抱いていた「障害者エリート」のイメージのために、はっきり言って好感が持てる対象ではありませんでした。それが様々ないきさつを経て彼も私が関係していた学生サークルに入ることになり、その後そのサークル主催の花火大会にともに参加することになりました。そして私が生まれて初めて見る打ち上げ花火に熱中していると、いつの間にか彼がニコニコしながら一升瓶を抱え「一緒に飲みましょう」と言いながら隣にいたのです。そこでつい釣り込まれて一緒に飲むことになり、私の彼に対するイメージが「面白い奴」に変わりました。彼の笑顔はとても印象的なものでした。
それから彼が私の家にちょくちょく遊びに来るようになり、サークルの合宿や飲み会等の様々な場面を一緒に体験しました。その頃、私は彼と会って一緒に飲むたびに「電動車イスに乗っている姿と、床に降りて寝たきりの姿のどちらが本当のお前なんだ? どうやってその二つの姿をつなげていくんだ?」という問答を吹っかけていました。その度に彼から冗談とも本気ともつかずに「またいじめる」と言われたのを思い出します。私としては勿論「彼をいじめる」ためにそんな問答を吹っかけていたわけではなく、私自身が若い頃から「分裂した自分の頭と身体」をつなげるためにもがいてきた体験を振り返り、一緒に仲間として考えていけたらと思っていました。
社会や周囲の人々にとって「ただ黙って車イスに座っている姿」は、一般的な障害のある人のイメージとして受け入れやすいものだと思います。また、本人にとっても周囲に受け入れてもらえるという意味で、安心して自己受容できる姿でもあります。もちろんそれで自らの障害からくる周囲との異質性が消えるわけではありませんが、私の中には幼い頃から「激しい緊張や不随意運動を隠しておけさえすれば、健常者に近づくために懸命な努力を重ねる『障害者エリート』として周囲に受けいれられることで他の重い障害のある人から一線を画す存在になれる」という哀しい意識がありました。しかし、そんな自分がひとたび車イスから降りれば、激しい不随意運動とともにむき出しの障害者存在になってしまうという現実の中で、私はいつも自分の頭と身体の分裂感(喪失感)にもがいてきました。
そんな私と似た部分を彼の置かれた状況に感じていたのかもしれません。そして私の勝手な思い込みなのですが、今回の『リハビリの夜』という本の内容は、熊谷さんからの私への答えだと感じています。
*
前置きはさておき、書籍紹介としての本筋に戻りたいと思います。先ず何よりも『リハビリの夜』の内容の凄いところは、医療専門家でありながら最初から最後まで自分の脳性マヒ者としての身体の声を拾い続けようとしたところにあります。「痛いのは困る。気持ちいいのがいい」という身体の声を羅針盤に「リハビリテーション論」や「障害当事者論」を越え、読者に世界とのつながりを考えさせる壮大な物語です。彼は医療専門家の立場から「脳科学」等の成果を縦横無尽に例として引きながら、あくまでも障害当事者の視点を大切に「健常者の動きを習得すること」を課題とされたリハビリテーション(支配/被支配の関係あるいは「まなざし/まなざされる関係」)を受け続けた結果、自らの身体の動きが何者にも拾われずに瓦解していく過程を冷静に分析していきます。
著者は、理学療法士が身体をほぐすためにリハビリを施す時にその人の手が緊張した体幹や手足に触れることで「ほどきつつ拾い合う関係」が築かれ、安心感とともに緊張が抜けていく状況を「折りたたみナイフ現象」として説明していますが、それは脳性マヒ者であれば、リハビリテーション以外の場面でも体験しているのではないでしょうか?
例えば採血やレントゲン撮影をされる時に、動くまいと思うことで余計に緊張してしまう手足に看護師が手を触れることで、すーっと身体の力が抜けていく不思議な状態。著者はそれを「官能」という言葉で表現しています。けれども同じリハビリでも、理学療法士によって意識的に「健常者の動きを習得すること」が課題とされた場合は、気持ちよさに代わって「痛み」と「恐怖」を強く感じてしまい、焦りと敗北感の中で自分の動きがどんどん「健常者の動きを習得すること」から離れてしまう。そのようなリハビリテーションの過程で、理学療法士と著者との関係が支配/被支配の関係あるいは「まなざし/まなざされる関係」に変質してしまう様を切なく描いています。
著者はそのようなリハビリテーションに対する絶望感の中で、地域での自分なりの生活を実現していく過程を通し、脳性マヒ者としての自らの動きを見つめ直し、自分が生きる上で必要とする床やトイレ、電動車イスを始めとするモノや介助者(他者)に身を預け「官能」を感じながら「協同関係」あるいは「ほどきつつ拾い合う関係」を築いていくことに未来の可能性を見出していきます。ですから『リハビリの夜』は読者に世界とのつながりを考えさせるとともに、彼自身の自立に向けた物語であると言えます。
また、著者は物語の後半でリハビリテーションのみに視点を注ぐのではなく、人間にとっての「自由」についても考察します。「健常者と同様に自分で動けるようになることが自由なのか?」ということを突き詰めた結果、モノや他者とつながり、「ほどきつつ拾い合う関係」を持つことこそが、人間としての自由であるということに行きつきます。そしてその「ほどきつつ拾い合う関係」が介助をする/されるという立場を介すことで、容易に「支配/被支配の関係」や「加害/被害の関係」に代わりうる現実も冷静に見つめていきます。
さらに、最終章で他者との関係に生じる「隙間」の大切さについて述べています。例えば、介助者との関係を通して自分の意志や行動を実現したいがために相手を身体化しようと思っても、介助者が独立した他者であるためにどうしようもなく生じてしまう「隙間」こそが、お互いの関係を豊かにしていくことにつながるという洞察はまさに圧巻といえます。障害のあるなしに関わらず、人生はいったん固定化してしまった「ほどきつつ拾い合う関係(支配/被支配の関係に変わりうる)」を敢えてほどき、結び直していくことを通して営まれるという指摘は真実であり、障害のある人の運動における「当事者主権」を越える重要な問題提議だと思います。
*
最後に、私は著者が提起する「共同体的自己決定」とでも表現する様な考え方には共感しますし、自分もひとりの脳性マヒ者としてそのような生活や生き方を目指してきました。しかし『リハビリの夜』を読む中で、敢えて問い直したい課題を感じました。それは「ほどきつつ拾い合う関係」が成立する前提条件とは何かという問題です。
残念ながら障害のある人が「支配/被支配の関係」あるいは「まなざし/まなざされる関係」に置かれているのは、リハビリテーションの場面だけではありません。障害のある人は健常者の日常生活や社会関係に適応しきれず、障害が重いほど絶えず介助を必要とすることで、ものを考えたり行動しようとするといつも「周囲から問われたり、頑張りという見返りを求められてしまう存在」になりがちです。そのために他者との関係の中でまるで「裁きを受けているような感覚」を持ってしまう場合があると思います。
その心の傷をどうすれば拭い去ることが出来るのか? これが重要な課題だと思うのです。
もちろん当たり前ですが、日常生活や社会関係の中で障害のある人が一方的な被害者というわけではありません。例えば介助という場面を考えても、自らの障害を武器に障害のある人の方が介助者に対して支配的な関係になることがあり得ると思います。しかし、そういうことを踏まえてもなお健常者の優位性が保たれる社会構造があると思います。
私も他人ごとではありませんが、健常者と障害のある人の社会経験の差異が問題にされたり、健常者が「介助の大変さ」を語ったりした時に、素直に受け止める余裕がなくて「おびえて逃げてしまう」多くの障害当事者の心のありよう(本音)をどう開いていけるかが、重要なのではないでしょうか。私は「ほどきつつ拾い合う関係」を深めていくためには、健常者と障害のある人がお互いの本音や体験を素直に語り合える条件が必要だと思いますし、当面はそのお互いの語りを蓄積していくしかないと考えています。「共同体的自己決定」は素敵な関係だと思いつつ、そんなことを考えてしまいました。
『リハビリの夜』は、私にもそのようなことを考えさせる素晴らしい本なので、是非とも皆さんお読み下さい。
(障害者医療問題全国ネットワーク発行『けんこう通信』第25号より転載)
透徹した目で語る「動きの誕生」
書評者:岩崎 清隆(群馬大学医学部保健学科准教授・作業療法士)
書評を見る閉じる
本書の著者は,脳性まひを抱えた小児科医である。本書には,著者の幼少時からの運動学習,モノや人への働きかけの学習のプロセスがある種の感慨をもって描かれている。感慨と言っても独りよがりな情緒論に陥ることなく,全体が透徹した公平な視点で貫かれている。適切な内容に,それに見合う適切な言葉が用意周到に選ばれているので,味わい深いと同時にその描写がとても美しくも感じられる。
きらりと光る表現
本書のコンセプトの一つに,セクシュアリティがある。「官能」「快楽」などドキッとするような表現があるが,「敗北の官能」など,「そうとしか表現できないだろうな」と思われるようなきらりと光る表現が随所にみられる。
非日常的な次元にわれわれの視点を向けるのに本書のイラストも有効である。はじめは少し不気味な気持ちを抱かせるようなイラストであるが,透徹した論理とともに軽みと遊びも同時にそこに用意されている。
脳の障害に由来する運動障害が,「身体内・身体外協調構造」という概念から説明されているが,著者の体験に裏打ちされた理解なので,とてもわかりやすい。感覚・運動コントロールシステムの最新の知見も踏まえて書かれているが,それらの紹介が巻末の注などにほどよく整理されているので,冗長にならず,文章の流れを遮ることはない。
人間関係の在り方が動作を決める
リハビリの体験と,トイレ動作,注射の動作など新しい動作の学習のプロセスの記述は圧巻である。
著者は,これらの学習が促進されるかどうかの背景としての人間関係の在り方を指摘している。人が「ほどきつつ拾い合う関係」にあるときにのみ,運動学習が良き循環の中に進行していくという指摘は,著者でなければできない指摘であろう。反対に悪意はなかったとしても,運動学習が健常の規範に同化させるような,著者の言う「まなざし/まなざされる関係」の中で行われると,決していい効果を生まないばかりか,治療者/被治療者関係が容易に「加害/被害関係」に移行しうる危険性が容易に想像される。これらの指摘は,発達障害の医療・教育・福祉に携わるすべての人々に有益である。
著者は「あとがき」の中で,2次障害を診察してくれた整形外科医の対応について触れている。これを読むとすべての医療・教育・福祉関係職種は,それを手がかりに,自らの臨床の場に患者,生徒との「ほどきつつ拾い合う関係」がどのように実現されているか吟味したくなるのではないだろうか。
多元的な視点が動きをひらく
「動きの誕生」の章では,脳性まひを抱えた人のモノや人との出会いと適応には,彼自身が健常者と自分自身の二つの異なる運動イメージを持つ必要があったことが述べられている。すべての医療・教育・福祉関係職種にとっても,そういう多元的な視点の獲得こそが,対象者との「ほどきつつ拾い合う関係」を築きあげる手がかりと思われる。
この著作からは,著者の透徹した目を感じると同時に,著者の人と世界に対しての信頼と,生きる上でのしぶとさ,粘り強さが感じ取れる。本著のタイトルが『リハビリの夜』とあるように,リハビリを受けた夜に感じた「敗北の官能」が,著者の学習の原動力になってきたからであろう。
ここに描かれている敗北,悲哀,希望は,運動障害を持った一人の医師の学習過程にとどまらず,人間の生き方の普遍的なモデルの一つのように見えてくる。
「健常な身体」という不自由から解放されるために
書評者:宮地 尚子(一橋大学大学院教授・精神医学)
書評を見る閉じる
また名著が生まれた!
当事者性を重視した「障害学」という面白い学問がある。そこに、また名著が生まれた。著者の熊谷さんは、車いすに乗った脳性まひの小児科医である。本人は言われたくないかもしれないが、東大医学部卒という超エリートでもある。
自分の思いどおりに動かない身体。意識的にめざせばめざすほど、こわばる身体。健常者に近づけるべく、まなざされる身体。訓練され、規律を教え込まれる身体。つたなさに見捨てられる身体。ほどけ、ゆるみ、ひらき、ふたたびつながる身体。そんな自分の身体と周囲とのつきあいを、熊谷さんは時には論理的に、時には詩的に描く。マックス・エルンストにちょっと似た画風の笹部紀成氏による挿絵が随所にあって、読者の理解を助けるとともに、独特の雰囲気をこの本に与えている。
地上10センチの果てしない旅
熊谷さんが小さいころ毎年参加させられたリハビリキャンプの経験が痛々しい。けれどもそれが今の彼の一部を形成していることも事実であり、その中には「快楽」をも含んでいて興味深い。だから従来のリハビリのあり方の全否定といった簡単な結論にはならない。
しかし、彼が大学生になり自立生活を試して初めて自分の「身体の輪郭が見えてきた」というのは、やはり衝撃的である。
自分からモノに働きかけ、介助者に働きかけ、失敗し、まさに試行錯誤するなかで、形づくられていく「自立生活」。周囲の物や人との相互性のなかでこそ生まれてくる「自分の身体」。誰もいないときに転倒し、地上10センチの二次元の世界に浸る、果てしない時間。それは「失敗」だが、彼の生に、身体に、深みを与える豊かな時間でもある。
この本は障害論であり、介助論であり、リハビリ論であり、身体論であり、生命論であり、発達論である。同時に、マイノリティ論であり、セクシュアリティ論であり、他者論でもある。実際にリハビリや障害児のケアにあたる人たちに今日から役立つ本であるとともに、身体による/をめぐる哲学的な思考の果てしない旅にも誘ってくれる。
善意が暴力に変わるとき
私はこの本を、年末、実家に戻り、心身の衰えが進みつつある父のそばで読んだ。本を読みながら、当事者の視点や経験を尊重することの大切さを、しみじみと感じる。病いや老い、障害や弱さをかかえた当事者から見える世界、感じる世界が、どれほど「健常者」のそれと異なっているのか。その違いを認識しない医療者やリハビリ関係者の善意が、いかに簡単に暴力になり、当事者の尊厳を奪ってしまうのか。
けれども目の前にいる父に対し、つい治療者の介入モードになってアドバイスをしてしまう私がいる。このままでは転倒しやすいから、こうすれば身体への負担が楽になるから、こうすれば薬の飲み忘れがないからと。長期的には「正しい」それらの介入が、父を苛立たせる。父のゆっくりしたテンポや、気持ちの動き、それなりの論理、そしてプライドに、合わせきれない自分が残る。
正しさを求めるのではなく、より良さを求めるのではなく、いったん降りて、寄り添う。時間をかけて、ほどける。自然にリズムが合わさっていくのを待つ。健常者に近づくのではなく、その人がその人なりに、生き甲斐を感じながら、楽な形で生きていくことをともにめざす。
それはリハビリだけでなく、メンタルヘルスなどあらゆる領域で重要なはずなのに。近代医療の根源にある健常者の「ものさし」、そのものさしにあわせた改良の思想。その作用から自分を解放することの難しさを感じながら、本を読み進める。
熊谷さん、書いてくれてありがとう
熊谷さんは、セクシュアリティという、生きていく上でものすごく大切なのに、医療やリハビリ現場で無視されがちなテーマにも、率直に言及している。
「敗北の官能」やマゾヒズムについては、まだまだ解釈を深める必要があると思うし、女性に投影するのはどうなんだろう、女性の障害者だとまた別の解釈がありそうだとも思ったが、内容はとても興味深かった。健康で「ノーマル」でヘテロ(異性愛)指向の男性はこういうのを読んでどう感じるんだろう。不快なのか、ピンとこないのか、案外共感するのだろうか。
熊谷さん、書いてくれてありがとう。この本を読んで、健康な医療従事者たちが、健常な身体の不自由さから少しでも解放されるといいなと思う。
身体と向き合うことの切実さ
書評者:甲野 善紀(武術研究者)
書評を見る閉じる
この本の書評を書いてほしいと依頼を受け、本書を読みはじめたものの、著者である熊谷晋一郎氏の身体のありようなど、とても我々に想像のつくものではないと思い、一度は断ろうかと考えた。
それでも、折角の御依頼でもあるので、本書を少し拾い読みしてみたものの、やはり想像していたとおり、人間が生きるということに本質的に備わっている苛烈さ、そして目も眩むような複雑さが、脳性マヒという不自由な身体を持たれていることによって、より凄まじい形であぶり出されてきており、とてもじっくりと通読することさえ苦しくなってくるほどの困難さを感じた。しかし、同時にノンフィクションのみが持つ迫力に打たれて、「もう少し、もう少し」と読み進めていくうちに、人間というのは、さまざまな過酷な状況にさらされても、自分が生き続けようという意欲を持つために、当事者以外は想像もつかないような工夫をするものだということをあらためて教えられている気がして、ついついページを繰る手が止まらなくなっていた。
そして、「もし健常者の常識を押しつけるようなことを止めて、例えば温水プールを基盤とした水辺の町のような環境をつくり、それぞれに適った暮らし方、過ごし方をしてもらい、そこから気づいた道具の工夫や思想、文学などを社会に還元してもらったら、現代の常識として固定化している人間の幸福感などが根底から変わってくるような、新しい価値観が生まれるのではないか」などという夢想も拡がった。
ここまで書いて、私の文章がとても「ある本についての印象を読者に伝える」という書評の体をなしていないのではないかという気もするのだが、本書『リハビリの夜』の持つきわめて詳細な客観的観察に基づく記述が、その冷静で詳細な分、いっそうリアルでナマナマしい迫真力を持っており、読んでいるとそれに打ちのめされてしまって上手くこの本の感想を伝えられない自分を自覚せざるを得ないのである。そのため、中途半端であるが、このような文章での、本書の紹介を御容赦いただきたい。
個人的には、私自身の技がかつての武術の名人達人に比べて遥かにレベルが低いということを常日頃から口にしていながら、その事実に対する認識が甘かったことを、あらためて痛感させられた。健常者の身体が基準とされる世界において、脳性マヒの身体と向き合い続ける熊谷氏の生き様を思うと、「必要は発明の母」というが、すべての学びの成否は「いかにしてそれを学ぶことに切実さを持たせるか」ということにあるのだということをあらためて思い知らされた気がしている。
より多くの分野の方々に本書を読んでいただき、どう思われたか、その感想を聞かせていただきたいと思う。
夜の語り手(雑誌『精神看護』より)
書評者:藤山 直樹(精神分析家・精神科医)
書評を見る閉じる
私の読書はとても場当たり的なものだ。
世の中の知的な動向に絶えず気を配っている人からすると、相当にずっこけている。どんな本が売れていて評判になっているのかにとても疎い。だから世の中の人たちが評価しつくした頃に、ふと手に取ってみて、これは凄い本だ、などと声を出すと、いまごろ何言ってるんだよ、みたいな声が返ってくるという経験をよくする。あるいは、一度読んで感銘を受けたのにしばらく忘れていて、後になって誰かがその本のことを言及したり世間で評判になったりしているのを聞き、ほお、面白そうな本だな、と思って手に取ると、それは以前自分が凄いと思って読んだ本だった、というようなこともある。毎日患者と会うことに忙しくて、たまたまふと出くわした泉で渇きを潤すというような按配で読書をしているせいだろう。この本で頻出する表現で言うなら、本のほうで私を拾ってくれるときしか本を読んでいないのだ。
熊谷さん(書評を書くときにいつも困るのは、著者をどう呼ぶかということである。純粋な学術書を同じ領域の研究者として書評するときは、呼び捨てにするのが正しいような気がしているが、この本の場合、著者の熊谷晋一郎氏とは何度かお目にかかっていて、一方的に親しみを覚えている人なので、ちょっと呼び捨てが難しい。この一文では熊谷さんで通させていただく)の『リハビリの夜』も、たまたま誰かが面白いと言っていたので手に取ってみたら、驚き、唖然とし、凄い本だと思った。だがそれは、すでにこの本が世間に評価されて賞まで取ってから数年経ってからのことだった。
それからもう6~7年経ってしまった。だがこの本は、何度読んでもそのたびに、別の角度からこの本と対話している自分、この本に魅せられている自分を自覚させてくれる。稀有な本である。そういうわけで、この本は私のオフィスのデスクの上の、手の届くところに置いてある。ときどきふと、この本のところどころを無性に読みたくなるからだ。そんな本が私には何冊かある。
精神分析家のウィルフレッド・ビオンという人が書いた『注意と解釈』という無味乾燥なタイトルの本も私にとってそんな本で、その本の原書と訳書が私の机上にはいつもある。とはいうものの、そのふたつの書物はかなり趣が違う。乾いて硬い『注意と解釈』と湿潤で柔らかい『リハビリの夜』。だが私を惹きつけるものは突き詰めれば共通しているようにも思う。粗雑な言いかたに聞こえるかもしれないが、それはこのふたつの本が帯びている真実の感覚だ。なまの事実というものは豊かな解釈の可能性を持っている。その二冊はまさになまの事実のような生々しさを帯びている。何度読んでも何かを考えるように私を誘ってくるのだ。
「さもしい分析家」を惹きつけるもの
毎日患者と会って暮らしている精神分析家なので、どんな本を読んでいても、どうしてもその視線がせり出してくる。しかも、この本には、人が変化し、進展していく過程、そしてそれを助けようとする人物が頻出する。だから、いやが上にもその傾向は強まる。人が人と援助的に交流することがどういうことなのか、そして援助されるということが援助する側の思惑によって、あるいは思惑にもかかわらず、どのように達成されあるいは失敗するのか、そうしたことに引き寄せて読んでしまいがちになるのだ。
それはそれでやむを得ないだろう。どうしたって私は精神分析家であって、それ以外ではないからだ。ほかの職業でもそうなのかもしれないが、精神分析はとりわけそういう職業だ。精神分析家は自分のプライベートなこころを差し出して訓練される。つまり、自分自身が精神分析を受ける。このことは、パーソナルな自分が取り返しのつかない形で変わってしまう可能性を前提として、職業訓練に入るということだ。パーソナルな自分が維持された上でスキルや知識を身に付ける、というのとは根本的に違う。私はもはや、何もかも精神分析のレンズを通して見たり聞いたりするしかできなくなっている。その私がこの本を読むと、ある種の実用書として役立てたくなる私がどうしても出てきてしまう。さもしい話だ。
さもしい分析家としての私がこの本から拾い上げるものはたくさんある。熊谷さんが生きた体験から抽出して、名前を付けた多くの興味深い概念である。
たとえば、「ほどきつつ拾う関係」「まなざし/まなざされる関係」「加害/被害関係」という三つの関係性のモデルがある。このあたりは当然、分析家として患者と一緒にいるときの患者と私のあいだに起きていることと即座につなげて読んでしまうことになる。母子関係的で無媒介的な二者関係のなかに、「法」「基準」「父」というものが導入されて三者関係が生まれる。それは精神分析の営みのなかで日々私が体験している、もしくは体験することに失敗しているなりゆきである。
その私の視点からすると、熊谷さんの描き出したなりゆきは、あまりに強引に第三者性、もしくは「基準」が突きつけられてしまったために、きわめて不毛で反復的な迫害的世界に閉じ込められる過程である。私たち分析家が「言語」という第三者を持ち込む手続き、解釈の供給という介入をあまりに性急におこなったときのありさまを彷彿とさせる。どのような援助の局面でも、援助者側の固有の何かが、あまりに早くあまりに強くそこに持ち出されれば、同じようなことが起こるのだろう。それは援助される側の存在の連続性を壊して断片化に導く。その様子を熊谷さんは、体の言葉でビビッドに描き出している。
あるいは、「折りたたみナイフ現象」から「敗北の官能」に至る受身的なゆだねる快の考察にも、さもしい分析家は惹きつけられる。トレイナーがある緊張を維持しながら脳性麻痺の人の関節を伸展させるべく力を入れる。なかなかうまくいかないにもかかわらずそれを持ちこたえていると、そのある種のパワーゲームがクライマックスに達したときに、突然、脳性麻痺の人の緊張が消え去り、関節はストンと伸びてしまう。そのときに彼にはある種の快が生じる。
これは私たち分析家と患者とのやりとりでの行き詰まりがあるクライマックスに到達したときに、そこで起きているできごとそのものに双方が降伏する局面と似ている。事態が不連続に転換し、変化と進展と安堵が生まれるというなじみ深いできごとである。過程そのものにゆだねること、降伏すること、ということの持つ生産性とある種の快。それは「目標」というものが過程のなかで官能的動因へと脱構築されていくことで実効性を生むという逆説のあらわれだ。こうしたことも熊谷さんはきわめてビビッドな体の言葉で語っている。
このように、分析家としての私の営みにとって、この本はとても有用な示唆を与えてくれる。だが、そんなふうにこの本を概念や要旨に還元することは、さもしく実用主義的に読みたい私の部分を喜ばせるだけだ。私のなかのそうでない部分が面白いと思っているのは、そんなこととは関係ない。それははっきり感じられる。この本を読むという体験は、そのようなさもしさを満たす体験をはるかに超えた何かなのである。そんな節穴のような狭い視野では、この本の面白さの中核にたどり着くことはできない。
とにかく、私がオフィスでこの本をときどき手に取って楽しんでいるのは、そういうさもしい動機からではない。それはまちがいない。
体験したことのないことが私に生きたまま伝わる
この本は脳性麻痺という事態の当事者が自身の体験を語っている本である。熊谷さんが脳性麻痺というありかたを抱えてこの世に生まれ、その障害を生きてこられたおかげで、私たちはこの本が読めている。その事実こそがこの本の面白さの中核にある。この本の面白さを考えるとしたら、まずこのあたりまえのところを出発点にするべきだろう。
もちろん、脳性麻痺を抱えた人たちは過去にも現在にもおびただしくおられる。だがそうした人たちはこの本を書かなかった。書きたいとも思わなかっただろう。だが、何より熊谷さんのようには書けなかったのではないか。
私は脳性麻痺になったことはない。「折りたたみナイフ現象」を経験したことがない。だが、この本を読むと私はそれをいきいきと実感的に思い描ける感じがしてくる。この本を読む前にはとんと想像もできなかった、脳性麻痺になっているという体験がどんな体験なのか、わかる気さえする。なじみ深いとさえ感じる。
体験を体験としての生気を失わない形で言葉にして伝える。熊谷さんはそれに成功している。そのおかげで私たちは、まだ体験したことのない脳性麻痺を生きる体験を、こころのなかで微かにでも生きることができる。体験をその生気を維持して伝えうるように言葉を用いる。それが途方もなく困難な課題だということは、どれほど強調してもしすぎることはない。その大きなハードルを越えて彼は書いてくれた。このことがまず、なんと言っても重要だ。
体験というものは言葉にはできない。これはあたりまえのことだ。体験という言葉を純粋に使用するなら、言葉を受け取るという体験は、単に声の音波を聞いたりインクの濃淡を見たりすることでしかない。言葉の意味は体験とは違う。どれほど私が言葉を連ねて、旬の鳥貝の甘み、西瓜に似た香り、酢飯と混然となるときのうっとりする感覚について語ったとしても、けっして私が鳥貝の鮨を食べる体験そのものを読者に伝えることはできない。体験は言葉を超えたものだ。だが、にもかかわらず、体験が生気を失わないで言葉になっていると感じられるときがある。書き手の書く体験が具体的に伝わってきたと感じられるときがある。
言葉は体験そのものを描き出せない。したがって体験を伝達することもできない。言葉は体験そのものでないが、体験の帯びる生気を受け手のなかに生み出すことができる。ひからびた生気のない形での伝達と、生気を保持した伝達、その違いは何なのだろう。おそらく、生気を保持した伝達においては、私たちの内部の何か、おそらく記憶のなかの何かが喚起されるのだろう。体験そのものは伝わってこなくても、その体験をとりまく感じ、雰囲気が、その言葉によって読者にきわめてミクロではあっても喚起される。おそらくそうした「感じ」や「雰囲気」は私たちの記憶のなかにすでに蓄えられているものなのだ。「感じ」「雰囲気」が喚起されたとき、書き手の持った体験、言葉にできなかった体験と相似な、私たちの無意識的記憶のなかの体験が、やはりきわめてミクロに動き始める。
体験そのものを言葉が伝えることがなくても、その体験とつながる、受け手にとってなじみ深い何かがこころのどこかで動く。そのとき私たちは体験が生気を保持した形で言葉で「伝えられた」と感じるのだろう。熊谷さんの言葉は私にとってそれを可能にした。そういう力を持っていた。それはなぜなのだろう。
夜でつながる
思うにそれは、熊谷さんのことがとても身近に感じられるからだ。身近、という言葉の文字通りの意味、身体的近接感のようなもの、熊谷さんの体温さえ感じられる感覚が、この本を読む体験のなかで私に瞬間瞬間に生まれてくるからだ。そんなことが起きるのはおそらく、私が熊谷さんと大きな共通基盤の上にいるという感覚を持てるからだと思う。
人が眠っているとき、みんな誰もが眠っている人だ。みんな夢見る人だ。個人と個人とのあいだの差異は溶けて流れ去り、眠り夢見る同じような人間になる。熊谷さんは自分がふつうに歩いている夢を見ると書いている。逆に私は、夢のなかで自分が手足を動かせず溺れてしまう夢を見ることがある。夜はすべての人を同じ場所に立たせやすい。たとえば、精神科病棟で昼間の患者はそれぞれに病気によって特徴的なふるまい、思考、感情を示してくる。彼らはそれぞれに、まだ退院できない程度に私たちの気を揉ませる人たちだ。しかし、夜が来て彼らが眠ってしまえば、彼らはみんな普通の眠っている人になる。それは、体の病気の人が眠っていてもあいかわらず体の病気を持つ人で、当直医が絶えず気を揉ませられていることとは対照的だ。精神科の当直医は要するに、昼の患者を夜の患者に変えればいい。眠ってもらえばいい。
熊谷さんは昼間、脳性麻痺の人としてリハビリを受けていた。しかし夜の彼を必ずしも脳性麻痺の人であると考える必要はない。夜、たいていの人は彼と同じように「二次元の世界」に憩うのだし、そこで思い描く空想や想起には官能がつきまとっている。熊谷さんも私たちも、昼間のことを思い出したりしながら、官能的な世界に入り込んでいく。
熊谷さんの書く言葉には「色気」がある。「官能的」と言ってもいい。それは絶えず昼の体験を裏打ちしている夜の体験を意識しているからだ。彼はたぐいまれな夜の語り手である。たとえば、「ほどきつつ拾う関係」という、リハビリの進展促進的な関係体験を語るとき、彼はそこが非対称の場であると語り、そこで大きな存在に自分をゆだねることが生む、ある種の「官能的」体験を描き出す。それは「敗北の官能」だ。この「敗北の官能」が熊谷さんにとっては、こころ慰められる、憩いと安堵に満ちた体験であり、進展の基盤を作るものだということは、この本で何度も語られている。この「敗北の官能」こそ、リハビリの「夜」のもっとも中心的で建設的な側面なのだ。そしてその夜の側面こそ、熊谷さんと私の共通基盤なのだ。
豊かな太腿に「敗北の官能」が……
私は脳性麻痺の体験を持てない。そして、リハビリを受ける体験も持てない。つまり、昼のリハビリ体験を持つことができない。だが、ちょっと思い起こせば、リハビリの「夜」の体験、援助されるときの「敗北の官能」を自分が体験していたことが思い出せる気がする。
小児喘息を克服できないまま思春期を迎えた私は、高校生になると親元を離れて進学校である男子校に進んだ。官能などというもの入り込む余地が微塵もない殺伐とした環境で暮らしながら、ときどき発作を起こしては医院に駆け込んだものだった。
点滴をされ吸入を受ける。ベッドに横たわっていると、自分がとても無力な存在だという気がしてくる。そこにつかつかと若い看護婦さん(この当時は看護師という言葉はなく、看護婦さんだった)が近付いてくる。私には白いストッキングの脚が見えるだけだ。看護婦さんはいつもは華奢に見える割に、太腿はとても肉付きがよい。その太腿に頬ずりしたいような、頬ずりしたまま泣いてしまいたいような気持ちになる。そんなことはできない。でも何か懐かしいような気持ちだ。そのままじっとしていると、徐々に体が楽になり、同時に自分が何か大きなものに降伏してしまったような気分になり、わけもなくうっとりする。しばらくうとうとする。
そうしたことを私は一年に何度も繰り返した。看護婦さんと言葉を交わしたことはほとんどない。彼女はひとりの人間というより、私より大きな何かの一部であり、しいて言うなら豊かな太腿だった。それに私は決定的に降伏するしかない、ゆだねるしかないと高校生の私は感じていた。
別のことも思い出す。私はしばしばモノをなくす。失くし物をするという体験は、確信を持ってそこにあると考えていた場所からモノが消えてしまうという体験だ。当然驚く。そして自分というものがあてにならないことに、ひとことでいえばバカであることに傷つくことになる。毎日三回くらいは探し物をしているので、いい加減慣れそうなものだが、そうはいかない。毎回毎回私は傷つき、自分を罵る。その繰り返しだ。
ある日タクシーから降りて家に着いたら財布がない。激しく動揺する。例によって自分をこころのなかで罵倒する。絶望的によるべなく悲しい。領収書をたよりに翌日電話してみる。財布は届いており、営業所に行けば財布は返ってくるということがわかる。ほっとして胸をなでおろす。緊張が緩んで涙ぐみそうになる。行ってみると営業所は祖師ヶ谷大蔵にある。私が五十年近く前大学1年生のときから2年間暮らした町だ。私鉄を降りて営業所に行き、財布をもらってそのあたりを歩く。微かに自分が住んでいたあたりの街並みが同定できる。なにかものすごく懐かしくなる。同時にとてもかなわないという気持ちがしてくる。
自分がモノをなくしてばかりのどうしようもない人間なのに、この世の中は財布を戻してくれただけでなく、自分をこんなに懐かしい甘美な気持ちにもしてくれた。ほんとにかなわない。自分はちっぽけなダメな奴なのに。降参するしかない。
こうした私の体験はおそらく、熊谷さんの言う「敗北の官能」の体験と同質の体験と言えるだろう。熊谷さんと私が昼間体験していることは大きく違う。だが夜の側面は共通しているということだ。私がたまたま喘息だったり、注意欠陥があったりしたからこうした共通基盤が生まれたのだろうか。私はそうは思わない。私たちは誰もが小さく無力な、自分では何もできない存在としてこの世に生まれてくるからだ。
最早期に私たちが私という意識をもたないまま、思い通りのものが環境から手に入るという状況にいるとしたら、そこには他者はいないから、他者というものが必要な「官能」は存在する余地はない。だが、いったん、「私」という意識に乳児が目覚めれば、自分を世話してくれる、大きな圧倒的な他者を意識しないわけにはいかない。その他者に自分をゆだねることでもたらされる安堵と幸福感は、大きな他者に圧倒される感覚とないまぜになって、「敗北の官能」に結実する。他者が出現したとたん私たちは「官能」あるいは「性愛」にからめとられてしまうのだ。
私たちは「夜」を語れるか
他者としての母親への官能的体験を乳幼児が持つという想定は、精神分析の基本的想定である。そうした想定は人間の夜の側面が絶えず活動しているという想定と同義である。そうした想定を十分に身をもって納得するために私たち分析家は、自分自身が精神分析を受ける体験を持つと言えるだろう。精神分析を受けるなかで大きな他者をもう一度体験する機会を集約的に持つことによって、精神分析家は自分のなかの、ひいては人間ひとりひとりのなかの夜の側面の力を知るのである。
そうした訓練とは無縁な熊谷さんが、どうしてこれほど率直に正直に、かついきいきとした生気を保持したままで、リハビリの夜の側面を語れるのか、私には謎だ。それはおそらく子どもの頃から何度もリハビリという形で「大きな他者」にさらされ、「敗北の官能」を経験したことと無関係ではない。だがそれだけでこのような言葉が語れるわけでないことは、他の脳性麻痺の人たちと比べてみればわかる。
この本が面白いのは、夜を語る存在、たぐいまれな夜の語り手である熊谷さんを近くに感じることにもとづいている。そのことによって、読者の私たち自身もわずかでも夜を語れるようになるかもしれない。私たちは熊谷さんの助けを借りて、官能にからめとられている自分のこころ、からめとられてこそ構築される自分のこころを、認識し、深く受け入れることができるかもしれない。
(『精神看護』2021年3月号掲載)
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。