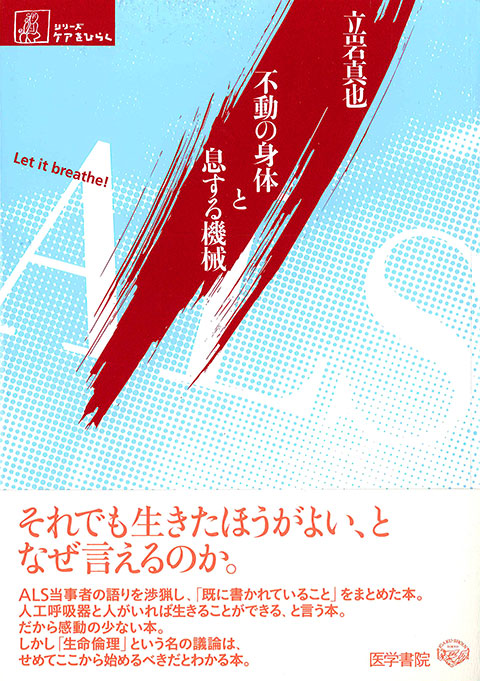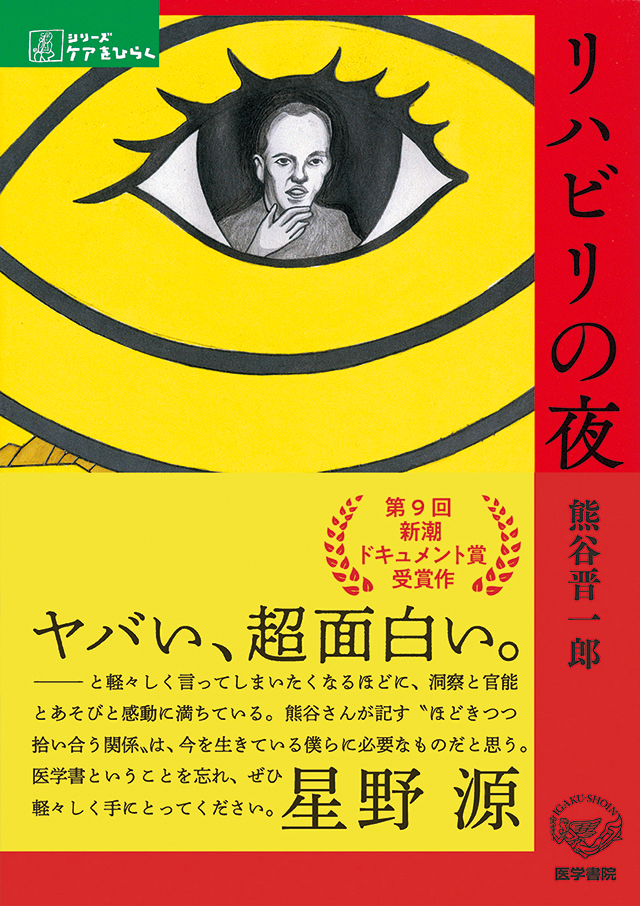逝かない身体
ALS的日常を生きる
究極の身体ケア
もっと見る
言葉と動きを封じられたALS患者の意思は、身体から探るしかない。ロックトインシンドロームを経て亡くなった著者の母を支えたのは、「同情より人工呼吸器」「傾聴より身体の微調整」という即物的な身体ケアだった。 かつてない微細なレンズでケアの世界を写し取った著者は、重力に抗して生き続けた母の「植物的な生」を身体ごと肯定する。
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 川口 有美子 |
| 発行 | 2009年12月判型:A5頁:276 |
| ISBN | 978-4-260-01003-0 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 序文
- 書評
TOPICS
開く
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
●本書が大宅壮一ノンフィクション賞を受賞!
第41回大宅壮一ノンフィクション賞(日本文学振興会主催)が2010年4月5日に発表となり,本書が選出されました。同賞は,大宅壮一氏の半世紀にわたるマスコミ活動を記念して制定されたもので,過去には沢木耕太郎著『テロルの決算』,猪瀬直樹著『ミカドの肖像』などが受賞しています。
●動画配信中!
著者・川口有美子氏からのメッセージです。
序文
開く
日本の金融機関に勤めていた夫がロンドン支社勤務になり、一九九三年の春から私たちは家族そろって二度目の海外生活を送っていた。けれども、翌九四年の春に母は乳房ごとがんの摘出手術を受けることになり、私は一歳と五歳の二人の子どもを両腕に抱えて、一時帰国することになったのだ。
それは、不穏な予感に苛まれる日々のはじまりだった。
母によれば、初めて乳房の辺りにごりんとした感触を見つけたのは、友人と訪れた信州の温泉に入ったときだった。湯煙の向こうに三人の尼僧の剃髪した頭が霞んでみえた。ただそう聞けば夢のような優しい光景だが、母には不吉な予感がしたという。
「背中にもときどき痛みが走っていたから、たぶんこれはもう、初期ではないと思う……」
日本でもようやく患者主体の医療とかインフォームド・コンセントなどという言葉が聞かれるようになり、がんも告知される時代になっていた。母も大学病院の外科医から、それはていねいな説明を受けていて、闘病の心構えもできていた。
このときは、病気の本人が家中でもっともしっかり病気を受け止めていたし、万事において自分で采配を振るっていた。手術の段取りも母は医師と相談をして決めていたから、家族には事後報告で済んでいた。手術当日は持病の狭心症に慎重すぎるほどの対応がなされたため、術後もなかなか目覚めないほどに麻酔が効いてしまったのだが、そうとは知らない父と妹はただおろおろと廊下で気を揉んでいたという。
母は術後二週間ほどで退院してきた。だから一時帰国のお見舞いといっても名目ばかりで、私にとってはのんびりできる里帰りに変わりなかった。母も久しぶりに会う孫の成長に目を細めて、リハビリと称しては台所に立ち、得意の煮物をつくってくれた。しかし実際には母の予想したとおり早期発見とはいえない進行がんだったから、温存療法どころではなく念には念を入れた処置がなされていた。
「どれどれ」と胸を開いて手術痕を見せてもらうと、脇の下のリンパ腺も大きくえぐりとられ、筋肉を剥がされたような左の胸は、肋骨が皮膚の下に透けて見えた。その胸の傷は、母の陽気な振る舞いとは裏腹に、手術の侵襲性と深刻な現実を物語っていたのである。私の動揺を見て、母はため息まじりに寂しそうに笑った。
「これじゃあ、もう温泉には入れないわよね」
そしてぽつりとこう続けた。
「パパがわたしのことを、かたわになったなんて言うのよ」
そういう言い方でしか自分のショックを誤魔化せない父なのだ。
乳房を失った妻。女性としての自信も失った母を慰めることもできない。そんな反応も父らしいといえば父らしかった。しかし後になって振り返れば、このときは母はまだ、片方の乳房を失った「だけ」だったのだ。
(第1章「静まりゆく人」より)
書評
開く
●新聞で紹介されました
《目が離せなくなり、読み終えたときには世界が一変していた。》――佐藤幹夫氏(ジャーナリスト)
(『東京新聞』2010年5月23日朝刊「BOOKナビ」より)
《『逝かない身体』で大宅壮一ノンフィクション賞を受けた川口有美子さん》
(『朝日新聞』2010年4月19日「ひと」より)
《母の介護体験書き大宅壮一ノンフィクション賞を受賞》
(『東京新聞』2010年4月9日、中日新聞2010年4月13日「この人」より)
《殺させないために何ができるか 病人の「生」が軽んじられる社会であってはならない――川口有美子氏に聞く『逝かない身体』》
(『図書新聞』2010年3月27日より)
《「マイヘルパー」養成に取り組む日本ALS協会理事 川口有美子さん》
(『読売新聞』2010年3月2日「顔」より)
《最後のページをゆっくり閉じて、まとまりきらない思いをしばらく胸中に漂わせなければ、落ち着かない本だった。》――西川勝(大阪大学特任准教授)
(『信濃毎日新聞』2010年2月21日ほかより)
《人間のQOLについての普遍的な問題提起に溢れている。》――松田良一(東京大学大学院准教授・生物学)
(『週刊読書人』2010年2月26日号・第2827号より)
●雑誌で紹介されました
《壮絶な記録としか言いようがない。同時に、極めて解像度の高い、科学的な記録でもある。文藝春秋誌(2010年5月号)に掲載された大宅賞選考委員の絶賛ぶりもあわせて一読すべきである。》――福岡伸一氏(分子生物学者・青山学院大学教授)
(『ミセス』2010年8月号「BooK」より)
《《「ピンピンコロリで死ぬのがいいと言われますが、本当にそうなんでしょうか」》
(『クロワッサン』2010年8月10日号「著者インタビュー」より)
《ここに展開された介護の状況と「生と死」をめぐる考察の深さには、脱帽するばかりだ。》――柳田邦男氏(ノンフィクション作家)
(『暮らしの手帖』2010年8月号「心を聴く」より)
《一冊の感動的な文学になっている。……この作品の出現でサナトロジー(死生学)に新しいジャンルが生まれた。》――藤原作弥氏(元日本銀行副総裁)
(『経済界』2010年7月6日号「BOOKS REVIEW」より)
《まず文章がすばらしい。奥行きのある理知的な文体で、私は冒頭から惹き込まれた。》――野村進氏(ノンフィクションライター)
(『週刊現代』2010年6月5日号「リレー読書日記」より)
《ことばが詩の域に達している。頁を繰る手が、何度も止まった。》――上野千鶴子(東京大学大学院教授・社会学)
(『みすず』2010年1・2月号(第579号)より)
●webで紹介されました
技術は人を救う、難病や末期であればなおのこと
《難病や末期を思想的にあるいは心理的に語る本は多い。生命倫理と呼ばれる学問もある。しかし、本書に含まれる「即物的なこと」はあまり語られてこなかったのではないか。店頭には並びにくいかもしれない本だが、もっと知られてよい、と思った。》――松野享一(紀伊國屋書店洋書部)
(紀伊國屋書店スタッフによる書評的空間 2010年02月15日より)
エスノグラフィーに触発される気づき――ALSのコミュニケーション論
《《ALSの人を交えたやりとりは、私たちが「コミュニケーション」について偏ったイメージを抱きがちであることに気づかせてくれます。ひとつひとつの出来事の微細な描写からそうした気づきが触発されるところが、まさにエスノグラフィーの醍醐味なのだろうと思います。》――伊藤智樹(富山大学人文学部准教授)
(紀伊國屋書店「書評空間」:富山大学・伊藤智樹の書評ブログ 2010年01月29日より)
難病患者は生きるのに忙しい
《川口さんは母親がALSを発病したことを知って、夫の赴任先の英国から二児をつれて帰国。24時間不眠不休の介護生活がスタート。そして母が亡くなるまでの壮絶な記録です。そしてひとりの主婦が、生と死について考え尽くしたひとつの回答の書です。》――石井政之(ジャーナリスト、評論家)
(紀伊國屋書店「書評空間」:ジャーナリスト・石井政之の書評ブログ 2009年12月24日より)
押しつぶされそうになる心に,一筋の希望の光 (雑誌『看護管理』より)
書評者:野田 洋子(株式会社マイケア代表取締役,アムナス博多訪問看護ステーション所長)
書評を見る閉じる
死の淵から戻ってきた彼は「もう少し頑張れそうです」と言った
私が本書の著者,川口有美子さんの名前を知ったのは,TLS(totally locked in state 完全な閉じ込め状態)について調べているときだった。その頃,筆者の訪問看護ステーションでは,ALS(筋萎縮性側索硬化症)の利用者が何度も呼吸停止の状態に陥っていた。数回目の呼吸停止のとき,主治医をはじめ誰もが「これで最後か」と思った。しかし,彼は意識を取り戻した。驚く家族と医療職に向かって,携帯型意思伝達装置である“レッツチャット”で「もう少し頑張れそうです」と言ったという。
生死の狭間から奇跡的に生還したものの,彼の病状では鼻マスク式人工呼吸の限界にあった。医師から気管切開の意思確認がなされたが,答えは「NO」。もともと,彼はALSの診断を受けたときから,「気管切開はしない」と決めていたらしい。その後も幾度となく意思確認が繰り返されたが決心は変わらなかった。そして,今回の“事件”の後も,やはり気管切開はしないと言ったのだ。理由は「TLSになることが怖い。それに,自分はまだ若いので気管切開して長く生きれば看てくれる人がいなくなってしまう」ということだった。
両親も「本人の意思だから呼吸が止まったときが運命」と覚悟を決めておられた。しかし,筆者には,常に呼吸苦と闘い,死の恐怖と背中合わせの日々を送っていた彼が死の淵から戻ってきたとき,「もう少し頑張る」と言ったことが,“生きたい”という強い意思の表われに思えてならなかった。そして,考えに考え抜いたのであろう本人や両親の「気管切開はしない」という決断に,私は「ほんとうにこれでいいのだろうか?」と思い悩んでいた。この出口のない迷路のなかで「他のTLSの方はどうしているのだろう。何か方策はないのだろうか」とインターネットで情報を探していたとき,川口有美子さんのサイトに出合ったのだ。そこには,ALSの母の介護の記録として川口さんの気付きや思いが語られていた。そこで,筆者は一筋の光を見出した。それから約1年半後,彼は気管切開し自宅で一人暮らしをめざして力強く生きている。
“いのち”“生きるということ”とは
本書は,家族による単なる介護の記録を超え,瞬く間に病状が進行し,数年で目も動かすことができずに外界との意思疎通を遮断されてしまったALSの母の身体状況や感情,言動を通して,著者自身の気持ち,考えの変化が詳細に描かれている。その著者の考え,気づき,視点は,私がそうであったように,多くのALS患者と家族,そのケアに関わる人たちが必ずぶつかる壁,そして次々に襲いかかる過酷な状況に押しつぶされそうになる心に,一筋の希望の光を投げかけてくれる。
同時に,私たち医療職こそが謙虚で真摯に向き合わなければならない“いのち”や“生きるということ”について,何と表層的で安易な考えをしているかにも反省させられるのである。
(『看護管理』2010年10月号掲載)
【特別寄稿】川口有美子著『逝かない身体──ALS的日常を生きる』を読む 沈黙の身体が語る存在の重み─介護で見いだした逆転の生命観(『週刊医学界新聞』より)
書評者:柳田 邦男(ノンフィクション作家・評論家)
書評を見る閉じる
《凄い記録だ》――私はこの本を読み進めるうちに率直にそう感じ,「生と死」をめぐる著者・川口有美子さんの思索の展開と,次々に登場する既成概念を打ち砕く数々の言葉に,ぐいぐいと引きこまれていった。
難病ALSの母を介護した12年間の記録だ。症状の進行がはやく,大半は言語表現力を失った沈黙の状態に陥っていた。
ALSは随意筋を司る神経細胞が死滅していく病気だ。手足が動かなくなるだけでなく,呼吸する肺の筋肉も動かなくなるので,人工呼吸器をつけないと生きられない。唇も動かなくなるから,発語ができなくなる。最近は技術の発達により,頬などに残されたわずかに動かせる場所にセンサーを取りつけて,YESかNOかの意思表示ができるようになった。
例えば介護者が50音表の文字盤を示し,「あかさたな……」と発音しながら指でたどっていく。「あ」と言った時に,患者が頬の筋肉を動かすと,センサーがピッと鳴る。次は「あいうえお」と1語ずつ読んでいく。「う」のところでピッと鳴ると,患者が言おうとする言葉の第1語が「う」であることがわかり,パソコンに記録させる。同じようにして,次の1語を探すと,「た」であることがわかり,患者は「うた(歌)を聴きたい」と言っているのだと汲み取り,好きな歌をCDでかけてあげる。患者とのコミュニケーションは,こうやって時間をかけて可能になったのだ。
ALSが他の病気と違う最も大きな特質は,五感と脳は生きているという点だ。ALSが進行すると,頬かどこかに最後まで残っていた筋のわずかな動きも消えてしまう。そうなると,センサーは何も感知できないから,患者は意思表示の手段を失う。目蓋も動かせなくなる。たいていは乾き目を避けて,閉じたままにする。患者は光もなく何の意思表示もできない中で生き続けるのだが,聴覚も思考力もあるのだから,ただひたすら耐えるだけという過酷な日々を送ることになる。そういう状態をTLS(Totally Locked-in State)と言う。
私は30年以上にわたって,がんが進行した人々の生き方と死の迎え方について学びを重ね,人間が「生きる」意味と「尊厳ある死」とは何かについて,自分なりにたどり着いた考えを持てたつもりでいた。しかし,最近,何人もの進行したALSの患者・家族にお会いして,その「生と死」への様々な向き合い方を見るにつれて,ALSの場合,「生きる意味」や「尊厳ある生」の問題は,がんの場合とかなり異質な面があり,もっともっと思索を深めなければ本質に迫れないなと,立ちすくむ状態になっていた。
そのさなかに,川口さんの『逝かない身体』に出会ったのだ。
この手記は,個人的な介護のドキュメントなのだが,母の言葉,心理,身体の様子などについてのとらえ方が実にきめ細かく,それらの一つひとつを通して,「生きる意味」や「生きるのを支える条件」についてどんどん思索を深め,自分を変えていく。しかも,医学の用語や既製の概念などにとらわれない平易な言葉と文章で表現している。それらは,一般的に考えられている難病患者の「いのち」をめぐる通念を180度逆転させるような,極めてドラマティックな気づきを含むので,私は川口さんが到達したそうした気づきの文章に出会う度に,心を揺さぶられ,「目から鱗」の気持ちになった。それらは,「生きる意味」「生きることを支える条件」の新たな発見と言ってもよいものだ。
特に注目すべき気づきを紹介したい。
*
川口さんは,はじめのうちは,死よりほかに母を楽にする方法はないだろうと考えていた。慈悲殺の考えだ。しかし,ある日,母が早めに書いてあった遺書をこっそり読むと,そこには家族に対し,「いっぱいお世話かけてごめんね でもうれしかった ありがとう」と書かれていた。そして,続く文章からは,最後まで娘たちに介護されて,自分も娘たちもハッピーエンドを迎えたいという意思が伝わってきて,ハッとなった。安楽死は,そういう母の最後の人生計画と言うべきものを台無しにするものではないか。川口さんが母の寝顔を見ると,母は娘に否定されそうになっている命を全身全霊で守ろうとしているかのように,すやすやと眠っている。他者が手を出すのを拒否する安らかさ! 究極のオーラと言おうか。
川口さんのいのちを見る眼が,突然逆転する。コペルニクス的転回だ。
《「閉じこめる」(=ロックトイン:筆者註)という言葉も患者の実態をうまく表現できていない。むしろ草木の精霊のごとく魂は軽やかに放たれて,私たちと共に存在することだけにその本能が集中しているというふうに考えることだってできるのだ。すると,美しい一輪のカサブランカになった母のイメージが私の脳裏に像を結ぶようになり,母の命は身体に留まりながらも,すでにあらゆる煩悩から自由になっていると信じられたのである。(中略)患者を一方的に哀れむのはやめて,ただ一緒にいられることを尊び,その魂の器である身体を温室に見立てて,蘭の花を育てるように大事に守ればよいのである。》(『逝かない身体――ALS的日常を生きる』200ページより引用)
川口さんは,母がロックトインの状態になってからも,顔色などから母の心情を読み取っていた。顔の肌がさらっと涼しげな時は,リラックスしているのだとわかるし,発汗にしても,汗や肌の微妙な違いを見分ければ,身体のどこかに痛みがあるためか,焦りやストレスのためかの区別がついたという。身体は硬直したままであっても,皮膚の下の毛細血管は母の心情を反映して,恥ずかしければ顔が赤くなるし,具合が悪ければ青白くなり緑色っぽくもなる。
そして,川口さんは母の身体から,「あなたたちといたいから,別れたくないから生きている」という声を聞く。
言葉は発しなくても,全身全霊で向き合っていた母と娘との間には,密度の濃いコミュニケーションが成立していたのだ。私は25歳だった息子が脳死状態に陥った時,ベッドサイドで同じことを経験したので,そういう「瞬間々々の真実」を信じることができる。
そうした魂レベルの会話は,受け手の側の感受性が問われるものであることに,川口さんは気づく。
こうして川口さんは,「ただ寝かされているだけ」と言う医療者がいようが,重病人を辛いままに「生かしている」と批判する人がいようが,そうした言葉に動かされることなく,母を生の側に引き留めるだけ引き留めて,12年間の介護を全うしたのだ。
「生きる意味」は,病者が自らは見いだせなくなっても,「他者」によって見いだされうるものであろうという川口さんの気づきも重要だ。社会的な理解も支援も遅れているがゆえに,自己肯定感を持てない患者が多いこの国において,刺激的な命題と言えるだろう。
死と生に関する表面的なスピリチュアリティ論でなく,いのちを支えるリアリティに満ちた鮮烈な言葉が連打される問題提起の手記だ。
(『週刊医学界新聞』第2873号 2010年3月29日に【特別寄稿】として掲載)
『逝かない身体』 (雑誌『看護教育』 連載「医療と社会ブックガイド」より)
書評者:立岩 真也(立命館大学大学院総合学術研究科教授)
書評を見る閉じる
どんないきさつで始まったのかもう覚えていないのだが、この連載、9年も書いてしまった。今回は最終回。紹介すべき本はもちろんいくらもあるが、それを拾っていくのは到底無理だから、今年はひらきなおり、徹頭徹尾、私や私が関係する企画に関わる本だけを紹介してきた。最後のこの回は少し違う、ただ関係はあることを。
「ケアをひらく」というシリーズが医学書院にある。担当の編集者の白石正明さんに、シリーズの一冊でもある『ALS』(2004)でお世話になった。たまに話をした。本のことを知らせてもらった。
第18・19回で浦河べてるの家『べてるの家の「非」援助論』(2002)、第38回で石川准『見えないものと見えるもの――社交とアシストの障害学』(2004)、第44回で『ALS』、第61・62回で小澤勲編『ケアってなんだろう』(2006)、第90・91回で上野千鶴子・中西正司編『ニーズ中心の福祉社会へ――当事者主権の次世代福祉戦略』(2008)を紹介した。他にもたくさんある。今さら個々の紹介は無理だ。ここではもっと漠然としたことを。いったいこのシリーズは何なのか。編集者の好み・偏りがあり、販売戦略・戦術があり、出そうと思ったものを出しているというのが一つの答ではあるが、もうすこし。
ときに、こんな本たちが他の国で出版されることがあるだろうかと思う。世界の出版事情を知らないから、憶測でしかないのだが、ないような気がする。
どこの国にも、専門書・学術書があり、ハウツー本があり、ノンフィクション・小説がある。中には「本人」が書いたものもある。そのいくつかは紹介してきた。他国と比べ、実際に調べて書かれた厚みのある学術書がこの国には少ないことに不平も述べてきた。
ただ、この国には、これらのいずれでもないような本の群れもあって、それにはよいところもあるように思う。つまり、理論・学問を知らないではないのだが、心底信じているわけではなく、ある距離感を置くという態度がある。関係して、普遍的なことというより、個別のことやその細部を大切にしようという傾きがある。割り切れないことは割り切れないのだという開き直りがある。原理を「建て前」と捉え、それをあまり信用しないところがある。言葉にできないといったことにあまり引け目を感じない。そしてもう一つ、言ってならないことになっていることも言えばよいではないかといった気持ちがある。そんな場から書かれるものがある。
それはなにか素人っぽい営みでもあるのだが、知った(つもりになった)上で、斜めから、あるいは後ろから、見るという態度でもある。「目利き」という人たちがいて、その人たちが「これはしぶい」とか「あれはつまらない」とか言う。小林秀雄が晩酌に使っていた徳利はやはりよい、とかそんな感じだ。爛熟という言葉を使えそうなところがある。江戸もアニメも、そんな流れのものだ。
もちろん「ケアをひらく」シリーズの本の多くは普通の素直な本である。ただ同時に、とりわけ本を数見てきた編集者の方に、「そんなの飽きてしまったよ」という倦怠感と、「おもしろがることにした」みたいな好奇心というか邪心というか、そんなものがある。
医療社会学なら医療社会学の作法がある。看護学にもある。他もそうだろう。「ナラティヴ」もそうだし「ライフ・ヒストリー」もそうかもしれない。そこそこにおもしろいが、それを決まったものとして繰り返してもつまらない。
そして例えば「体制側」にしても「反体制側」にしても、「これはふれないでおこう」という部分があるのだが、そういうことを気にしないことにする。例えば、暴力をふるう患者は現にいる。となれば、それにどう対抗するかはやはり大切ではないか。こうなる。
それに対して私は、まず図式主義者であり原理主義者であると、すくなくともありたいと思ってきた。「現場は複雑」なのは当たり前で、それで話を終わらせてしまうのが嫌いだ。また自分自身がどうかは別に、建て前は建て前として大切で、人権主義者である、あるしかなかろうと思ってきた。
だから、私の建て前はこのシリーズのやんちゃなスタンスと同じではないと思う。ただ、流行を紹介したり決まった単純なお話を再唱したりはつまらないと思ってきた。そして、『ケアってなんだろう』の紹介の時にも述べたように、理屈じゃないんだと(例えば故・小澤勲が)言うしかないような部分にこそ理屈がある、原理があると言いたいとも考えてきた。だから、このシリーズのものはこれからも気にしようと思っている。
*
その最新作が川口有美子の『逝かない身体』。拙著『ALS』もALSの本だったが、それは書かれたことを並べた本だ。多くの人は字を書かないし、また、やがて書かなくなったり話さなくなったりする。しかしではそこになにもないかいえば、むろん、まったくそんなことはない。そのことを想像はできる。だが私は椅子にすわって字を書いているだけだ。
対して、こちらの大学院の大学院生でもある川口は、その母がALSになって、それ以来、介護の生活があり、様々があり、やがて自ら事業所を始める。ALS協会の活動もあり、各地を日々駆けずりまわっている。
第1章にその母親が発症してからの話があり、昨年に亡くなられる前後の話が第4章にある。その間に2つの章がある。
第2章「湿った身体の記録」は、こんなことを書いても(書いたら)よいのだと言われたりしないと、たぶん本にならなかったと思う。闘病記や家族の記録はかなりたくさんあるが、摘便のことや涎(よだれ)のことが、在宅介護の技術指南というわけではなく、書かれることは、そうはない。
さて「それでどうした?」ということにはなる。身体観だとか羞恥だとかいった「主題」につなげられなくはない。ただその前に、介護の苦労話は山ほどあることを知った上で、ここを書いてもらったらおもしろかろうと編集者は考えたと思う。その趣向をどう評価するか、読んでみてください。
普通におもしろいのは、第3章「送信から受信へ」だろう。口が動かなくなり、だんだん伝えにくくなる。動くには動くが「超」ゆっくりになる。すると「通訳」する人は代弁者のようにもなる。それはよくない、か。たいていよくない。けれどいつもそうか。また、やがてその方法もとれなくなる。しかしその人に伝えたり、その人から何かが伝わったりすると感じる。すると、前者は無駄だとか、後者は想像にすぎないとも言われる。前者の非難はもちろん間違っている。受信しているのだから無駄ではない。では後者はどうか。送信があると思うのはたんなる思い込みではないと本では示されている。その記述になるほどと思うか。次にそれと別に、想像に「すぎない」として、それではいけないのか。そんな話にもつながる。
ただここでも、そんなことの前に、様々が微妙に微細になっていく様子・過程が詳細に――というほとでは、今度の本はないのだが、しかしそもそも書けることかとも思う――書かれることがなかった。私は、幾人かから聞き知って、なんだか驚かなくなってしまっているところがあり、どう受け取られるか予想できないところがあるのだが、知らない人は知ってみたらよいと思う。他方に「現場」にいて知っている人もいる。でもその人は近すぎたり、慣れすぎたり、疲れすぎたりしている人でもある。この本の著者はいくつかのきっかけもあって、すこし距離をとることができた。すると書けることがある。またそれを読んで、知っているつもりの人が新たに知ることがでてくる。ときに「学」はそんな距離を得ることを助けることができる、こともある。
それにしても、約10年の、長くない時間に、しかし長くもある時間に、かくもいろいろなことが起こる。この本では記述が抑制されているが政治方面も慌ただしかった。動かない状態を生きる人も、関わってしまうと慌ただしかった。ではそれらから離れた人は、たしかに忙しくはなかったとして、時間は無限に続く単調な時間だったろうか。たぶんそうではない、それは私たちの妄想に近い。そのことがこの本で示されている。
(『看護教育』2009年12月号掲載)
「どのような状況であれ,ともに生きる」という生命観 (雑誌『訪問看護と介護』より)
書評者:真部 昌子(前看護教員)
書評を見る閉じる
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は徐々に全身の筋肉が動かなくなる難病で,発症割合は10万人に1人程度。有効な治療法はなく,病状の最終段階では,呼吸困難が起こり,人工呼吸器を装着するのかどうかという選択が患者と家族に迫られる。患者数は2008年3月現在で約8000人といわれているので,読者の中には在宅療養の患者に関わった経験がある方も少なくないと思う。
私は,臨床実習指導で十数年間にわたり神経内科病棟へ行っていた。しかし,学生には一度もALSの患者を受け持たせたことはない。それは短期間の実習では,学生が患者を理解し,看護を実施することが難しいだろうという,病棟側の判断があったからである。
この本の著者である川口有美子さんの母親がALSに罹患したのは1995年6月だった。当時,川口さんは夫の転勤でロンドンにいた。8歳と3歳の二人の子どもの教育やイギリスでの生活がようやく軌道に乗りかけていた矢先,母親から「がんの再発(一年前に乳がんの摘出手術を受けていたため)なのかもしれない。歩きにくくて,しゃべりにくい」という国際電話を受ける。それがALSの始まりだとは,その時点では誰も予想だにしないことだった。
その後,都立病院で「筋萎縮性側索硬化症」の診断を受けた母親の身体機能は急速に悪化していった。川口さんは急遽二人の子どもを連れ帰国することになる。その時の状況を彼女は「滞在中のたった3週間のあいだに,母は毎朝使っていた愛用のみそ汁用の小鍋や菜っ葉包丁が持てなくなった。料理は予想以上に早くできなくなった。これこそ家族も予期しなかったことだった。もう母の手料理を二度と食べられなくなったのである。それは同居の妹が母に代わって毎日,父のために料理しなければならないということでもあった」と表現しているが,この文の中には健康な時の母親の日常生活が刻々と侵されていくという深刻さ,同居家族が役割の変化を余儀なくされること,そして母親の作る手料理を食べられなくなってしまったという悲しみが込められている。
ALSという病名からは,神経難病,人工呼吸器装着や尊厳死,ヘルパーによる吸引の可否など重い問題がイメージされるが,川口さんの母親の場合も例外ではなかった。家族だけではとてもなし得ない介護にはヘルパー,ボランティアや在宅医療の医師,看護師,保健師などの支援が欠かせない。多くの支援者に支えられながら,川口さんは12年に渡り母親の介護をするのである。彼女が病気になった自分の子どもの受診もできないという家族との関わりにジレンマを抱き,自分の身体の限界などを感じていたことは事実である。しかし,読んでいてある種の爽快感が感じられるのは彼女のしなやかな生きる哲学によるのだと思う。本の中で,イギリスでの生活や風景,イギリス人の大家さんとの関わりが瑞々しく描かれており,読む側にとって正直なところほっとする。また,病に冒された小さな猫を拾ってその生命をも救おうとする行為そのものが著者の「どのような状況であれ,ともに生きるという生命観」なのだと納得させられる。
母親が逝ってしまった後で,著者自身が母親の使っていたベッドの上に身を横たえてみる。そこで聞こえる音,感じられる空気,見えるものすべてを見るという体験を試みたのだ。母親はこの状態で12年間も過ごしたのだという感慨が彼女にわき起こる。この母親を追体験する場面に,私は深い感動を覚えたのだ。
(『訪問看護と介護』2010年3月号掲載)