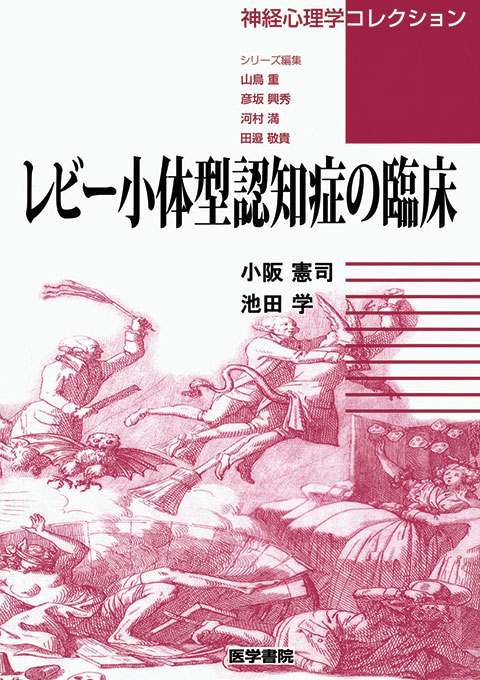レビー小体型認知症の臨床
発見者が語りつくすレビー小体型認知症の病理と臨床
もっと見る
変性性認知症としてはアルツハイマー型に続いて発症頻度が高いといわれるレビー小体型認知症(DLB)。本疾患の発見者が、病理学的発見の経緯から、DLBの臨床上の特徴である行動心理学的症状(BPSD)をはじめとした症状、診断、治療、介護に至るまで、同じく認知症の臨床に詳しい精神科医を聞き手に語り尽くす。神経心理学コレクション『トーク 認知症』に連なる貴重な対談。
*「神経心理学コレクション」は株式会社医学書院の登録商標です。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
レビー小体型認知症(DLB)は現在アルツハイマー病に次いで二番目に多く,血管性認知症を含めてこれらは三大認知症と呼ばれるようになった。DLBという名称が世に出てわずか十数年で国際的によく知られるようになり,臨床診断も可能になり,精神医学的にも神経学的にも神経病理学的にも注目されるようになってきた。また,頻度も高く,最近では一般の医師や一般の人たちにも知られるようになってきている。しかし,初期には精神症状が出現しやすいためDLBは臨床的に誤診されていることが少なくなく,またBPSD(行動心理学的症状)が初期から起こり,パーキンソン症状や自律神経症状も出やすく,ケアが最も大変な認知症である。したがって,早期に診断して適切な治療や介入を行うことが重要である。
DLBはもともと1976年以降の私の一連の報告により国際的に知られるようになった「びまん性レビー小体病(DLBD)」を基礎として発展してきた認知症であり,1980年以来,私が主張してきたように,DLB,DLBD,パーキンソン病,認知症を伴うパーキンソン病を「レビー小体病(Lewy body disease)」のspectrumでとらえるという考えが,国際的にも最近やっと受け入れられるようになった。DLBはまさに日本で発見された重大な認知症であると言っても過言ではない。
以前から,DLBについてあちこちで講演した際に,本を書いてほしいという要望があったし,私も書きたいと思っていた。時間的余裕がなく実現しなかったが,このたび熊本大学の池田学教授の協力を得て,対話形式でこの本を発刊することになった。この本は,主に私や私のグループの研究報告を中心に,歴史的な観点も含めて具体的に紹介したものである。発刊に当たっては,医学書院の方々の多大なご協力を得た。心より深謝します。
2010年4月吉日
小阪憲司
レビー小体型認知症(DLB)は現在アルツハイマー病に次いで二番目に多く,血管性認知症を含めてこれらは三大認知症と呼ばれるようになった。DLBという名称が世に出てわずか十数年で国際的によく知られるようになり,臨床診断も可能になり,精神医学的にも神経学的にも神経病理学的にも注目されるようになってきた。また,頻度も高く,最近では一般の医師や一般の人たちにも知られるようになってきている。しかし,初期には精神症状が出現しやすいためDLBは臨床的に誤診されていることが少なくなく,またBPSD(行動心理学的症状)が初期から起こり,パーキンソン症状や自律神経症状も出やすく,ケアが最も大変な認知症である。したがって,早期に診断して適切な治療や介入を行うことが重要である。
DLBはもともと1976年以降の私の一連の報告により国際的に知られるようになった「びまん性レビー小体病(DLBD)」を基礎として発展してきた認知症であり,1980年以来,私が主張してきたように,DLB,DLBD,パーキンソン病,認知症を伴うパーキンソン病を「レビー小体病(Lewy body disease)」のspectrumでとらえるという考えが,国際的にも最近やっと受け入れられるようになった。DLBはまさに日本で発見された重大な認知症であると言っても過言ではない。
以前から,DLBについてあちこちで講演した際に,本を書いてほしいという要望があったし,私も書きたいと思っていた。時間的余裕がなく実現しなかったが,このたび熊本大学の池田学教授の協力を得て,対話形式でこの本を発刊することになった。この本は,主に私や私のグループの研究報告を中心に,歴史的な観点も含めて具体的に紹介したものである。発刊に当たっては,医学書院の方々の多大なご協力を得た。心より深謝します。
2010年4月吉日
小阪憲司
目次
開く
序
第1章 歴史
パーキンソン病とレビー
レビー小体の発見
エコノモ脳炎
パーキンソン病の神経病理学の確立
パーキンソン病と認知症
見逃されていた大脳皮質のレビー小体
レビー小体病・びまん性レビー小体病の発見
びまん性レビー小体病の最初の症例
レビー小体病の提唱
びまん性レビー小体病の提唱
レビー小体型認知症の命名
第2章 発見・概念
最初の症例
レビー小体病の概念
びまん性レビー小体病(DLBD)の概念
DLBと認知症を伴うパーキンソン病(PDD)は同じ
純粋型の症例から始まったレビー小体の研究
DLBDの日本人例・欧米人例の比較
DLBDの神経病理診断基準
レビー小体病におけるレビー小体の進展
ATD type
PDDとは何か
第3章 診断と課題・疫学
DLBの診断基準
診断マーカーの開発
DLB診断の難しさ
疫学
第4章 臨床症状(BPSDを中心に)
BPSDの概要
DLBに特徴的なBPSD
患者への対応
REM睡眠行動障害
うつ病
抗精神病薬への過敏性
パーキンソン病との関連性
幻聴,妄想
BPSDの臨床
第5章 早期発見・治療・介護
DLBと軽度認知障害(MCI)
薬剤への過敏性
心筋シンチグラフィ
薬物治療
介護
第6章 病理・病態
レビー小体の病理像の特徴
大脳皮質のレビー小体
α-synuclein免疫染色
α-synucleinの遺伝子異常の発見
扁桃核
海馬の病変
視領野の病変
レビー小体病の概念
DLBのアルツハイマー病変
アミロイド仮説
経内嗅皮質の海綿状態
トランスジェニックマウスによる実験
病理と臨床からわかる疾患のspectrum
索引
第1章 歴史
パーキンソン病とレビー
レビー小体の発見
エコノモ脳炎
パーキンソン病の神経病理学の確立
パーキンソン病と認知症
見逃されていた大脳皮質のレビー小体
レビー小体病・びまん性レビー小体病の発見
びまん性レビー小体病の最初の症例
レビー小体病の提唱
びまん性レビー小体病の提唱
レビー小体型認知症の命名
第2章 発見・概念
最初の症例
レビー小体病の概念
びまん性レビー小体病(DLBD)の概念
DLBと認知症を伴うパーキンソン病(PDD)は同じ
純粋型の症例から始まったレビー小体の研究
DLBDの日本人例・欧米人例の比較
DLBDの神経病理診断基準
レビー小体病におけるレビー小体の進展
ATD type
PDDとは何か
第3章 診断と課題・疫学
DLBの診断基準
診断マーカーの開発
DLB診断の難しさ
疫学
第4章 臨床症状(BPSDを中心に)
BPSDの概要
DLBに特徴的なBPSD
患者への対応
REM睡眠行動障害
うつ病
抗精神病薬への過敏性
パーキンソン病との関連性
幻聴,妄想
BPSDの臨床
第5章 早期発見・治療・介護
DLBと軽度認知障害(MCI)
薬剤への過敏性
心筋シンチグラフィ
薬物治療
介護
第6章 病理・病態
レビー小体の病理像の特徴
大脳皮質のレビー小体
α-synuclein免疫染色
α-synucleinの遺伝子異常の発見
扁桃核
海馬の病変
視領野の病変
レビー小体病の概念
DLBのアルツハイマー病変
アミロイド仮説
経内嗅皮質の海綿状態
トランスジェニックマウスによる実験
病理と臨床からわかる疾患のspectrum
索引
書評
開く
興味の尽きない疾患
書評者: 朝田 隆 (筑波大教授・精神医学)
他の診療科の医師からは変わり者集団だとさえ言われる精神科医だが,実は二分できる。見分ける質問は,「認知症を診るのが好きですか?」。イエスならオーガニック派,ノーならメンタル派の精神科医である。暴論するなら,治療について,前者は薬物が,後者は精神療法がより重要だと思っている。ところがいずれも,「幻覚・妄想」という言葉には弱い。たやすく,「何々?」と身を乗り出してくる。
本書の二著者はもとより,私もオーガニック派精神科医である。メンタル派精神科医と神経内科医のはざまに位置するだけにそれぞれに対して引け目を感じることが,少なくとも私にはある。
そんなわれわれだから,レビー小体型認知症は興味が尽きない疾患である。そもそも認知症として最多のアルツハイマー病と変性神経疾患で最も多いパーキンソン病が一緒に起こっているのである。しかも大好物の「幻覚・妄想」が付いている。しばしば観察されるカプグラ症候群も精神病理学的には見逃せないテーマである。その一方で,これらもまた本症の中核をなすレム睡眠関連行動異常,意識の変動,視覚認知障害などは,今日の脳科学の最重要テーマだろう。
精神や神経を扱う医者にとって,興味の尽きない本疾患の全容を適切なスピード感とともに順次明らかにしていくのが本書である。本書の醍醐味の一つは,臨床所見と病理所見とをつき合わせて意味付けしてゆくプロセスの記述にある。
例えば本症の幻視は有名だが,視領野にはLewy pathologyがない。なのに「見える」背景が記されている。まず一次よりも二次視覚野のLewy pathologyが重度なので形態や色彩の認知に影響する。これがより傷害の酷い扁桃体の視覚路への影響と相まって幻視が生じるという説明である。
今更だが,小阪先生はレビー小体研究の中興の祖である。言うまでもなく疾患概念とは固有の臨床経過と病理所見のセットである。先生の最大の業績は,レビー小体にかかわる諸病態をスペクトラムとしてとらえ,それを疾患概念群というレベルでまとめられたことだと思う。
何ゆえに祖に成り得たのか? 後進である池田学先生も私もこの点に興味がある。まず患者さんの臨床を主治医としてしっかりと診られたこと,その上で顕微鏡下に普通には見えないもの(レビー小体)が見えてくる不断の努力があったことが行間に読めた。「田舎の学問,京の昼寝」という表現がある。その反対で,池田研二先生,井関栄三先生など諸先生との切磋琢磨もうかがえてなんともうらやましい。一連の研究成果を出し続けられる日常を伝聞するに「京の猛勉」状態にあられたと思われる。
さて昔から精神病理学的論議の的となる幾つかの概念や症候群がある。実態的意識性,遅発性統合失調症などは横綱級,コタール症候群にも老舗の風情がある。実はこうしたものが,レビー小体型認知症ではしばしば認められる。メンタル派の先生も本書をご一読あれ。これらの概念を再考させる知見がたくさんに盛られた本書は,必ずや温故知新の体験をもたらすはずだから。
偉大な観察者が示す臨床医学の方法論
書評者: 岩田 誠 (女子医大名誉教授/メディカルクリニック柿の木坂院長)
臨床家にとって最もやりがいのある仕事は,それまで誰も気付いていなかった病気や病態に世界で初めて気付き,それを世に知らしめることである。最初は,自分の小さな気付きがそれほど大きな意味を持つとも思わず,単に多少の興味を惹かれた事実を記載するだけである。それが大発見であるというようなことには,世間一般だけでなく,発見者当人もまだ気付いていない。当然のことながら,その記載は世の中に大きな反響を呼ぶほどのものにはならず,小数の臨床家の記憶の隅にしまわれるだけである。
しかし,時間が事の重大さを明らかにしていく。世の中の人々が,同じ事に気付きだすと,その最初の記載が大きくクローズアップされる。そして世間は,その発見が日常の臨床の場での,緻密ではあるがごく日常的な観察に始まったことを知る。
臨床家が毎日飽きもせず患者に接しているその営みの中から大きな発見がなされ,医学の歴史の新しいページが開かれていく時,いつも繰り返されるこのプロセスは,現在最も注目を浴びている変性性デメンチアのひとつであるレビー小体型デメンチアにおいても然りであった。この書物は,その発見者である小阪憲司先生が,後輩である池田学先生にその気付きのプロセスを語っていく書物である。これを読む人は皆,臨床家の観察というものが,いかに大きな発見につながっていくかを知り,感動を覚える。聞き手の池田先生も,臨床の場において次々と大きな発見を成し遂げてこられた方であるだけに,お二人の対談は,そういう臨床の場における発見の意義を生き生きと示す興味深い読み物となっており,ワクワクしながらこの病気の発見史を辿っていくことができる。
真の観察者は,患者の臨床症状であれ,その病理所見であれ,それらを単なるデータとして観察することはない。アルゴリズム的な考え方に従って,観察すべき所見の有無を記入したり,検査に頼ってどこそこの血流量がどのくらい減少しているかを測定したりするだけの行為は,単なるデータの収集であって観察とは言えないのである。小阪先生が大脳皮質の神経細胞の細胞体中に何か不思議な構造物を見つけても,その患者の示していた特異な臨床像を見ていなかったら,この病気の発見はもっと遅かったに違いない。臨床家としての観察力と,神経病理学者としての観察力が見事に合体した結果が,この発見につながった。
したがって,評者はこれを,単に一つの病気の臨床像や病理像に関する最新の知見を教えてくれるだけの書物とは思わない。確かに,この本を読めば,レビー小体型デメンチアに関する知識を余すことなく知ることができるのは事実であるが,この病気の発見者が,本書を通じて読者に伝えたかった真のメッセージは,臨床医学の方法論だったのではないかと思う。小阪先生の観察方法は,決して今日的なハイテク技術を駆使したものではない。それは古典的な地味な方法論に基づくものではあるが,大発見につながったのはその徹底的な観察であった。大脳皮質の神経細胞の中にレビー小体を見いだすことは,それがあることがわかっている症例においてさえ容易ではなかったと,池田先生が述べておられるが,そのような実体験を経ることによって,小阪先生の偉業が真に理解できる。この書物は,臨床医学における観察の意味とその重要性を示す,偉大な観察者のかけがえのない言葉に溢れている。
書評者: 朝田 隆 (筑波大教授・精神医学)
他の診療科の医師からは変わり者集団だとさえ言われる精神科医だが,実は二分できる。見分ける質問は,「認知症を診るのが好きですか?」。イエスならオーガニック派,ノーならメンタル派の精神科医である。暴論するなら,治療について,前者は薬物が,後者は精神療法がより重要だと思っている。ところがいずれも,「幻覚・妄想」という言葉には弱い。たやすく,「何々?」と身を乗り出してくる。
本書の二著者はもとより,私もオーガニック派精神科医である。メンタル派精神科医と神経内科医のはざまに位置するだけにそれぞれに対して引け目を感じることが,少なくとも私にはある。
そんなわれわれだから,レビー小体型認知症は興味が尽きない疾患である。そもそも認知症として最多のアルツハイマー病と変性神経疾患で最も多いパーキンソン病が一緒に起こっているのである。しかも大好物の「幻覚・妄想」が付いている。しばしば観察されるカプグラ症候群も精神病理学的には見逃せないテーマである。その一方で,これらもまた本症の中核をなすレム睡眠関連行動異常,意識の変動,視覚認知障害などは,今日の脳科学の最重要テーマだろう。
精神や神経を扱う医者にとって,興味の尽きない本疾患の全容を適切なスピード感とともに順次明らかにしていくのが本書である。本書の醍醐味の一つは,臨床所見と病理所見とをつき合わせて意味付けしてゆくプロセスの記述にある。
例えば本症の幻視は有名だが,視領野にはLewy pathologyがない。なのに「見える」背景が記されている。まず一次よりも二次視覚野のLewy pathologyが重度なので形態や色彩の認知に影響する。これがより傷害の酷い扁桃体の視覚路への影響と相まって幻視が生じるという説明である。
今更だが,小阪先生はレビー小体研究の中興の祖である。言うまでもなく疾患概念とは固有の臨床経過と病理所見のセットである。先生の最大の業績は,レビー小体にかかわる諸病態をスペクトラムとしてとらえ,それを疾患概念群というレベルでまとめられたことだと思う。
何ゆえに祖に成り得たのか? 後進である池田学先生も私もこの点に興味がある。まず患者さんの臨床を主治医としてしっかりと診られたこと,その上で顕微鏡下に普通には見えないもの(レビー小体)が見えてくる不断の努力があったことが行間に読めた。「田舎の学問,京の昼寝」という表現がある。その反対で,池田研二先生,井関栄三先生など諸先生との切磋琢磨もうかがえてなんともうらやましい。一連の研究成果を出し続けられる日常を伝聞するに「京の猛勉」状態にあられたと思われる。
さて昔から精神病理学的論議の的となる幾つかの概念や症候群がある。実態的意識性,遅発性統合失調症などは横綱級,コタール症候群にも老舗の風情がある。実はこうしたものが,レビー小体型認知症ではしばしば認められる。メンタル派の先生も本書をご一読あれ。これらの概念を再考させる知見がたくさんに盛られた本書は,必ずや温故知新の体験をもたらすはずだから。
偉大な観察者が示す臨床医学の方法論
書評者: 岩田 誠 (女子医大名誉教授/メディカルクリニック柿の木坂院長)
臨床家にとって最もやりがいのある仕事は,それまで誰も気付いていなかった病気や病態に世界で初めて気付き,それを世に知らしめることである。最初は,自分の小さな気付きがそれほど大きな意味を持つとも思わず,単に多少の興味を惹かれた事実を記載するだけである。それが大発見であるというようなことには,世間一般だけでなく,発見者当人もまだ気付いていない。当然のことながら,その記載は世の中に大きな反響を呼ぶほどのものにはならず,小数の臨床家の記憶の隅にしまわれるだけである。
しかし,時間が事の重大さを明らかにしていく。世の中の人々が,同じ事に気付きだすと,その最初の記載が大きくクローズアップされる。そして世間は,その発見が日常の臨床の場での,緻密ではあるがごく日常的な観察に始まったことを知る。
臨床家が毎日飽きもせず患者に接しているその営みの中から大きな発見がなされ,医学の歴史の新しいページが開かれていく時,いつも繰り返されるこのプロセスは,現在最も注目を浴びている変性性デメンチアのひとつであるレビー小体型デメンチアにおいても然りであった。この書物は,その発見者である小阪憲司先生が,後輩である池田学先生にその気付きのプロセスを語っていく書物である。これを読む人は皆,臨床家の観察というものが,いかに大きな発見につながっていくかを知り,感動を覚える。聞き手の池田先生も,臨床の場において次々と大きな発見を成し遂げてこられた方であるだけに,お二人の対談は,そういう臨床の場における発見の意義を生き生きと示す興味深い読み物となっており,ワクワクしながらこの病気の発見史を辿っていくことができる。
真の観察者は,患者の臨床症状であれ,その病理所見であれ,それらを単なるデータとして観察することはない。アルゴリズム的な考え方に従って,観察すべき所見の有無を記入したり,検査に頼ってどこそこの血流量がどのくらい減少しているかを測定したりするだけの行為は,単なるデータの収集であって観察とは言えないのである。小阪先生が大脳皮質の神経細胞の細胞体中に何か不思議な構造物を見つけても,その患者の示していた特異な臨床像を見ていなかったら,この病気の発見はもっと遅かったに違いない。臨床家としての観察力と,神経病理学者としての観察力が見事に合体した結果が,この発見につながった。
したがって,評者はこれを,単に一つの病気の臨床像や病理像に関する最新の知見を教えてくれるだけの書物とは思わない。確かに,この本を読めば,レビー小体型デメンチアに関する知識を余すことなく知ることができるのは事実であるが,この病気の発見者が,本書を通じて読者に伝えたかった真のメッセージは,臨床医学の方法論だったのではないかと思う。小阪先生の観察方法は,決して今日的なハイテク技術を駆使したものではない。それは古典的な地味な方法論に基づくものではあるが,大発見につながったのはその徹底的な観察であった。大脳皮質の神経細胞の中にレビー小体を見いだすことは,それがあることがわかっている症例においてさえ容易ではなかったと,池田先生が述べておられるが,そのような実体験を経ることによって,小阪先生の偉業が真に理解できる。この書物は,臨床医学における観察の意味とその重要性を示す,偉大な観察者のかけがえのない言葉に溢れている。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。