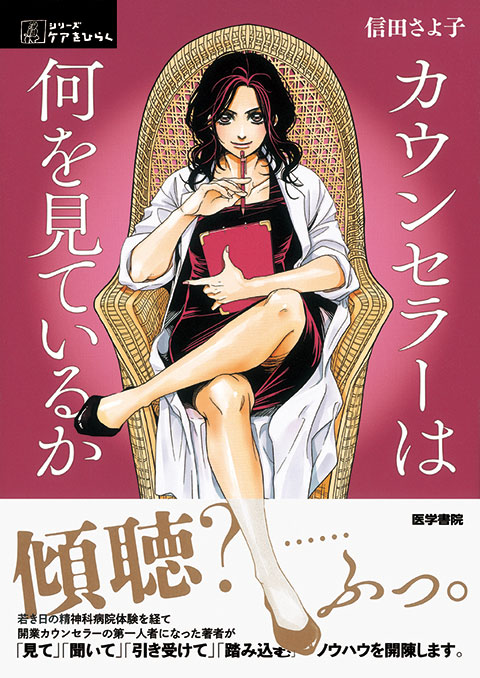アディクションアプローチ
もうひとつの家族援助論
「家族」が見える,「私」が変わる
もっと見る
なぜ家族が見えないのか。どうすれば家族に巻き込まれずにすむのか。「家族」が看護の中心課題になったいま、アディクション(依存症)へのアプローチ法が大きな注目を浴びている。「非援助の援助論」ともいうべき逆説とスリリングな発想に満ちた本書は、多くの看護職を悩ませている家族問題の理解に新しい視点をひらくだろう。
| 著 | 信田 さよ子 |
|---|---|
| 発行 | 1999年06月判型:A5頁:224 |
| ISBN | 978-4-260-33002-2 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
序章 ある日の午前=看護婦Nが相談室にやってきた
1章 家族は変わった
2章 アディクションアプローチとは何か
3章 家族をどうみたらよいか
4章 「援助」とは何か=アディクションアプローチからみなおす医療という場の特殊性
5章 自己理解のためのキーワード=アダルトチルドレンと共依存
終章 ある日の午後=援助者が「私」に戻るとき
1章 家族は変わった
2章 アディクションアプローチとは何か
3章 家族をどうみたらよいか
4章 「援助」とは何か=アディクションアプローチからみなおす医療という場の特殊性
5章 自己理解のためのキーワード=アダルトチルドレンと共依存
終章 ある日の午後=援助者が「私」に戻るとき
書評
開く
援助における支配性と物語による癒し-介護保険中毒者が読んだ援助職論
書評者: 池田 省三 (龍谷大社会学助教授)
小林秀雄風にいえば,私は5年前に介護保険という「事件」に巻き込まれた。そして,いまも「事件」の渦中にいる。いわば介護保険アディクション(嗜癖)に陥った者である。本書は臨床心理士によって書かれた書であるが,介護保険を考える私にも多くを教えてくれた。
◆「援助の価値」を疑う
信田氏は,「愛情とは支配のことなのだろうか。支配の『支』の字は支えると読めるではないか」と述べている。これは,私にとって1つの発見である。これまでの高齢者介護施策は何か。行政が,扶養関係と所得を勘案して,要介護高齢者に介護という支えを配給する制度だったではないか。まさに「支え」を「配る」制度,つまり支配の構造そのものであり,私はこれに対する嫌悪感から出発し,介護保険にのめり込んでいったのだ。
援助者と被援助者は,意識されようと,されまいと,支配と従属の関係に入り込む。これに対して,信田氏は「援助者と被援助者の等価性をどのように保障していくか」という観点を対置する。援助職にとって,愛情,献身,奉仕などという「援助の価値」を取り去り,逃れられない支配性は必要悪として自覚に至る作業が必要である。援助行為の報酬として「金銭」の支払いが介在することにより,最終的に等価性が保障される。信田氏のこうした指摘は,社会的な介護システムが,社会扶助制度から社会保険に転換し,サービスが「商品」として流通する意味を的確に描き出していると言える。
さらに,家族という密室の中で,支配-被支配のパワーゲームが展開するという観点も,きわめて重要なものである。痴呆性高齢者のケアにあたって,家族は最も不適切な介護者であることが多い。例えば,夫が痴呆となれば,妻との支配-被支配の関係は逆転するが,夫の問題行動の拡大という展開でさらに逆転する。そして,シーソーゲームの果てに,収拾のつかない状態を生み出してしまう。本書では,痴呆性高齢者への援助が書かれているわけではないが,応用すれば,「適切なケア」とは何かが発見できるのではなかろうか。
◆関係性の再構築としての「物語」
もう1つのキーワードは「物語」である。信田氏は,「私とは『私についての物語である』」という。専門外の私にとって,この「物語モデル」を説明するのは困難であるが,おそらくそれは関係性の再構築という作業のことを指すのだろう。他者から規定された関係性,自分が陥ってしまった関係性は虚妄であるとし,新しく創り上げる物語は虚妄でありながら,自己の位置を移動させるが故に真実に転換する。そのような関係性の創造と意思の変化は聴き手を必要とする。だから,断酒会のような自助グループが専門家のカウンセリングを超えた効果を示すことが起きる。介護にひきつけて考えれば,要介護者に対して,それがどんな小さなものであれ,自己表現,自己実現への契機を引き出し,これを展開していくことがきわめて重要な自立支援方策である。「物語モデル」もまた,そうした意味合いにおいて,高齢者介護のあり方に何らかの発見ができるはずである。
本書は,人間のdignity(尊厳)というものを,思い入れなしで教えてくれる。その点から,看護・介護職とりわけケアマネジャーにぜひとも一読してほしい本である。援助者の「愛情や献身」が支配欲を満足させるものであったり,依存や反抗も従属の形態であるということを,看護・介護職は知らねばならない。あらゆる局面で自立を支援するとは,常に本人が主人公なのだという立場に立つ必要がある。
私事であるが,信田氏は高校の同級生である。本書の最後に「ポストではなく,モダンそのものに首まで漬かっている」,「普遍に近づきたい」と記されているが,その思いは,私にもまったく共通する。ポストモダンに魅入られつつも,介護保険という「事件」の中で,結局は,私もプリモダンと闘うモダンの子だったからである。
初心者にこそ薦めたい,現代性に満ちたテキスト
書評者: 宮本 真巳 (横浜市大看護短大部・精神看護学)
アディクションアプローチという簡潔な題名は,本書の内容をよく言い表している。そして,精神保健に限らず,保健医療領域で仕事をする看護職やそれ以外の専門家にとって,本書は格好なテキストとなるだろう。ただし,おそらく読まれ方は多様で,本書の内容に抵抗を覚える専門家も少なくないと思う。
◆イネーブリングという逆説
本書のキーワードである「アディクション」とその訳語である「嗜癖」という概念は,少しずつ世に知られるようになってきたが,医療の世界で必ずしも共有されてはいない。一昔前のように,アルコール依存症や薬物依存症を中毒に見立てるのではなく,依存症として捉えることまでは医学の常識となった。しかし,飲酒のほかに賭博,浪費,暴力,摂食障害など,社会生活を脅かす執拗な繰り返し行動をアディクションとして包括的に捉える発想と,それに基づく専門的な援助方法が,臨床の現場に十分根づいたとは言えない。
アディクションアプローチの浸透しにくさを代表しているのが,「イネーブリング」という概念だろう。アディクションアプローチでは,嗜癖患者への援助よりも,問題を持ち込んだ家族への援助に重点を置く。ただし,援助の内容は家族が患者の世話から手を引くよう勧め,手を出さずにいられる方法を一緒に考えることである。それは,嗜癖患者のためを思う家族の行動が病気を支えてしまうという理由からであり,専門家もまた同じ理由から,患者の回復を遅らせてしまう。
◆思わず保護に走ってしまう援助者自身の問題
そこで筆者は,悩み多き若手訪問看護婦を登場させ,カウンセラーならではの共感を示しながら,専門職がイネーブリングにはまっていく道筋と,そこから脱けだす方策について懇切丁寧に説いている。
一方で筆者は,心理臨床家の立場から,看護職,とりわけ訪問看護の担い手に寄せる期待について,若干の危惧を交えながら語っている。看護職は,人の命を守るという大儀名分により,身体性とプライヴァシーの壁を突破できる。さらに,訪問活動を通じて家族の閉鎖性に風穴を開け,“ホームナース”の役割を果たす可能性も秘めている。しかし,看護職が,他の援助職にはないこうした“特権”を乱用すれば,患者や家族の自己決定を妨げ,まさにイネーブリングにはまり込むことになる。
アディクションアプローチの要点は,専門家が患者や家族への余計なお世話をやめて患者の問題は患者に,家族の問題は家に返すことである。それが看護者にとって簡単なようで難しいのは,患者の個人的な精神病理に眼を奪われてきたからだろう。アディクションを家族背景や生活状況から切り離して個人病理と見る限り,患者の保護という役割から降りられない。病人には何よりも保護が大切だという固定観念と,思わず保護に走ってしまう援助者自身の問題に気づくことの重要性を筆者は指摘している。
◆セルフケアを促進する方法論として
「キュア」から「ケア」へという最近よく耳にする標語は,医学偏重への警鐘にはなるが保護の偏重を助長する危険もはらむ。今求められているのは,他律的ケアから自律的ケア,すなわちセルフケアに向かう流れを作り出すことだろう。看護界でもセルフケアの重要性が指摘されて久しいが,医師や看護者の指示通りに行動することがセルフケアだという誤解も根強い。患者の自己決定を尊重した対等の話し合いが根づくまでには時間がかかりそうだが,アディクションアプローチが,これを促進する方法論であることは間違いない。
本書は,保健医療の現状に染まった人には抵抗があっても,初学者にとっては,日常的な人間関係と専門的な援助関係の関連を解きあかすわかりやすい本だと思う。旧世代の試行錯誤と悪戦苦闘の跡が滲み出た本書を出発点にした人たちが,この先どこまで行けるか見届けていきたい。
書評者: 池田 省三 (龍谷大社会学助教授)
小林秀雄風にいえば,私は5年前に介護保険という「事件」に巻き込まれた。そして,いまも「事件」の渦中にいる。いわば介護保険アディクション(嗜癖)に陥った者である。本書は臨床心理士によって書かれた書であるが,介護保険を考える私にも多くを教えてくれた。
◆「援助の価値」を疑う
信田氏は,「愛情とは支配のことなのだろうか。支配の『支』の字は支えると読めるではないか」と述べている。これは,私にとって1つの発見である。これまでの高齢者介護施策は何か。行政が,扶養関係と所得を勘案して,要介護高齢者に介護という支えを配給する制度だったではないか。まさに「支え」を「配る」制度,つまり支配の構造そのものであり,私はこれに対する嫌悪感から出発し,介護保険にのめり込んでいったのだ。
援助者と被援助者は,意識されようと,されまいと,支配と従属の関係に入り込む。これに対して,信田氏は「援助者と被援助者の等価性をどのように保障していくか」という観点を対置する。援助職にとって,愛情,献身,奉仕などという「援助の価値」を取り去り,逃れられない支配性は必要悪として自覚に至る作業が必要である。援助行為の報酬として「金銭」の支払いが介在することにより,最終的に等価性が保障される。信田氏のこうした指摘は,社会的な介護システムが,社会扶助制度から社会保険に転換し,サービスが「商品」として流通する意味を的確に描き出していると言える。
さらに,家族という密室の中で,支配-被支配のパワーゲームが展開するという観点も,きわめて重要なものである。痴呆性高齢者のケアにあたって,家族は最も不適切な介護者であることが多い。例えば,夫が痴呆となれば,妻との支配-被支配の関係は逆転するが,夫の問題行動の拡大という展開でさらに逆転する。そして,シーソーゲームの果てに,収拾のつかない状態を生み出してしまう。本書では,痴呆性高齢者への援助が書かれているわけではないが,応用すれば,「適切なケア」とは何かが発見できるのではなかろうか。
◆関係性の再構築としての「物語」
もう1つのキーワードは「物語」である。信田氏は,「私とは『私についての物語である』」という。専門外の私にとって,この「物語モデル」を説明するのは困難であるが,おそらくそれは関係性の再構築という作業のことを指すのだろう。他者から規定された関係性,自分が陥ってしまった関係性は虚妄であるとし,新しく創り上げる物語は虚妄でありながら,自己の位置を移動させるが故に真実に転換する。そのような関係性の創造と意思の変化は聴き手を必要とする。だから,断酒会のような自助グループが専門家のカウンセリングを超えた効果を示すことが起きる。介護にひきつけて考えれば,要介護者に対して,それがどんな小さなものであれ,自己表現,自己実現への契機を引き出し,これを展開していくことがきわめて重要な自立支援方策である。「物語モデル」もまた,そうした意味合いにおいて,高齢者介護のあり方に何らかの発見ができるはずである。
本書は,人間のdignity(尊厳)というものを,思い入れなしで教えてくれる。その点から,看護・介護職とりわけケアマネジャーにぜひとも一読してほしい本である。援助者の「愛情や献身」が支配欲を満足させるものであったり,依存や反抗も従属の形態であるということを,看護・介護職は知らねばならない。あらゆる局面で自立を支援するとは,常に本人が主人公なのだという立場に立つ必要がある。
私事であるが,信田氏は高校の同級生である。本書の最後に「ポストではなく,モダンそのものに首まで漬かっている」,「普遍に近づきたい」と記されているが,その思いは,私にもまったく共通する。ポストモダンに魅入られつつも,介護保険という「事件」の中で,結局は,私もプリモダンと闘うモダンの子だったからである。
初心者にこそ薦めたい,現代性に満ちたテキスト
書評者: 宮本 真巳 (横浜市大看護短大部・精神看護学)
アディクションアプローチという簡潔な題名は,本書の内容をよく言い表している。そして,精神保健に限らず,保健医療領域で仕事をする看護職やそれ以外の専門家にとって,本書は格好なテキストとなるだろう。ただし,おそらく読まれ方は多様で,本書の内容に抵抗を覚える専門家も少なくないと思う。
◆イネーブリングという逆説
本書のキーワードである「アディクション」とその訳語である「嗜癖」という概念は,少しずつ世に知られるようになってきたが,医療の世界で必ずしも共有されてはいない。一昔前のように,アルコール依存症や薬物依存症を中毒に見立てるのではなく,依存症として捉えることまでは医学の常識となった。しかし,飲酒のほかに賭博,浪費,暴力,摂食障害など,社会生活を脅かす執拗な繰り返し行動をアディクションとして包括的に捉える発想と,それに基づく専門的な援助方法が,臨床の現場に十分根づいたとは言えない。
アディクションアプローチの浸透しにくさを代表しているのが,「イネーブリング」という概念だろう。アディクションアプローチでは,嗜癖患者への援助よりも,問題を持ち込んだ家族への援助に重点を置く。ただし,援助の内容は家族が患者の世話から手を引くよう勧め,手を出さずにいられる方法を一緒に考えることである。それは,嗜癖患者のためを思う家族の行動が病気を支えてしまうという理由からであり,専門家もまた同じ理由から,患者の回復を遅らせてしまう。
◆思わず保護に走ってしまう援助者自身の問題
そこで筆者は,悩み多き若手訪問看護婦を登場させ,カウンセラーならではの共感を示しながら,専門職がイネーブリングにはまっていく道筋と,そこから脱けだす方策について懇切丁寧に説いている。
一方で筆者は,心理臨床家の立場から,看護職,とりわけ訪問看護の担い手に寄せる期待について,若干の危惧を交えながら語っている。看護職は,人の命を守るという大儀名分により,身体性とプライヴァシーの壁を突破できる。さらに,訪問活動を通じて家族の閉鎖性に風穴を開け,“ホームナース”の役割を果たす可能性も秘めている。しかし,看護職が,他の援助職にはないこうした“特権”を乱用すれば,患者や家族の自己決定を妨げ,まさにイネーブリングにはまり込むことになる。
アディクションアプローチの要点は,専門家が患者や家族への余計なお世話をやめて患者の問題は患者に,家族の問題は家に返すことである。それが看護者にとって簡単なようで難しいのは,患者の個人的な精神病理に眼を奪われてきたからだろう。アディクションを家族背景や生活状況から切り離して個人病理と見る限り,患者の保護という役割から降りられない。病人には何よりも保護が大切だという固定観念と,思わず保護に走ってしまう援助者自身の問題に気づくことの重要性を筆者は指摘している。
◆セルフケアを促進する方法論として
「キュア」から「ケア」へという最近よく耳にする標語は,医学偏重への警鐘にはなるが保護の偏重を助長する危険もはらむ。今求められているのは,他律的ケアから自律的ケア,すなわちセルフケアに向かう流れを作り出すことだろう。看護界でもセルフケアの重要性が指摘されて久しいが,医師や看護者の指示通りに行動することがセルフケアだという誤解も根強い。患者の自己決定を尊重した対等の話し合いが根づくまでには時間がかかりそうだが,アディクションアプローチが,これを促進する方法論であることは間違いない。
本書は,保健医療の現状に染まった人には抵抗があっても,初学者にとっては,日常的な人間関係と専門的な援助関係の関連を解きあかすわかりやすい本だと思う。旧世代の試行錯誤と悪戦苦闘の跡が滲み出た本書を出発点にした人たちが,この先どこまで行けるか見届けていきたい。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。