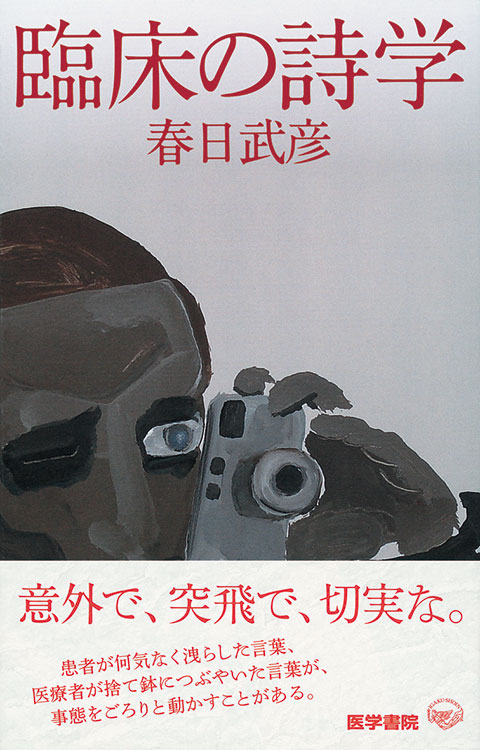臨床で書く
精神科看護のエスノグラフィー
途方に暮れながら引き受ける人びとの記録
もっと見る
たとえば看護師は、どのような成り行きで患者を拘束したりしなかったりするのか。会話の成立しない患者との間に“通路”が生じたきっかけは何か――臨床で働く看護師なら誰もが知っている「そのこと」を、看護師自身のフィールドワークによって炙り出す。POS記録を一次資料に「そこにあったはずの何か」を描き切った、質的研究の画期的成果!
| 著 | 松澤 和正 |
|---|---|
| 発行 | 2008年03月判型:A5頁:360 |
| ISBN | 978-4-260-00569-2 |
| 定価 | 2,860円 (本体2,600円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
プロローグ 私たちの現実はどこにあるのか?
ある日保護室で
その日、私は深夜勤務明けで、朝の病棟ミーティングでの申し送りも終えたところだった。書き残した看護記録をそそくさと書き上げ、帰り支度をしてナースステーションを出たのだが、なぜかふとある患者の保護室に足が向いていた。
ちょっと挨拶だけでもしていこうか、という軽い気持ちに過ぎなかった。ただし彼は、私の受け持ち患者(入院から退院まで責任を持つ)の一人であったし、依然かなりむずかしい病状を抱えたままだった。私自身も、彼のために日々めまぐるしく対応に追われ、かなり消耗していたことも事実だった。それでもとにかく私は、帰り際の挨拶をしようと彼の部屋を訪ねていた。
ところが、彼は、私の顔を見るなり突然泣きくずれ、激しく叫びはじめたのだった。しかも、とんでもない激しさというかほとんど爆発するかのように。「おれはもう死ぬ。生きていても仕方ないんだ。死、死ぬよ、死ぬんだよ!」などと叫びながら……。
私は、当然ながら驚いた。しかも腰が抜けそうなほどに。ただし彼の希死念慮とその訴えはほとんど常にあったから、それ自体に驚いたわけではなかった。今回は、その声も振る舞いもいままでにない格別なものだったからだ。彼は大声で叫びながら、まさにベッドの上で飛び跳ねんばかりだった。
私は一瞬ほとんど凍りついていた。いまにも彼はベッドの上から身を投げるのではないかとさえ思った。すぐに誰かに助けを求めなければと思うほどだった。けれど、そこは保護室ゾーンの最深部にあり、容易に声が届く場所ではなかった。それ以上に、彼の切迫しきった叫び声が私をたじろがせ、さらに不用意な私の反応がさらなるエスカレートを生みそうな気がした。私は、出しかけた声をのみ込んでしまった。「おれは生きていても仕方ないんだよ! 死ねって言ってるよ。もうだめなんだよ。おれは!」
数か月前、彼がこの病棟に運ばれてきたとき、彼はストレッチャー(搬送台車)上に簀巻き状態で固定され厳重に身体拘束されていた。彼は統合失調症で、思春期に発症していたが、ある特別な家庭の事情から長い無治療の時期などを経過して、すでに40歳を超える年齢になっていた。そして最近になって、不幸にも、本人と二人で同居していた母に対して重大な事件を起こし、今回の入院となったというわけだった。当然のことながら、入院当初から彼の病状は重かった。しかもそれはかなり特徴的なものだった。
「おれは神なんだ、メシアなんだ、天使なんだ」「ほら、いま降りてきたよそこに、神が」「おれは何だってできるんだよ」というように、おもに妄想的な世界に「浸っている」時期が長く続くと、次は「悲しいよ。寂しいよ。つらくてだめだ」「もう生きていても仕方ない。もう死ぬんだ。死ぬんだよ」とひっきりなしに悲嘆や死ぬことばかりを口にする時期がやってくる。そして、それが過ぎるとまた再び妄想の世界へ。
もちろん、その繰り返しのあり方は、それほどはっきり周期的なものと言い切れるわけではなかった。その日のうちにも、また次の瞬間にも入れ替わるし、一気にごちゃごちゃになって押し寄せて来たりもした。ただ大きく見ると、やはりそのような一群の波が、交互に入れ替わりながら押し寄せつづけているように私には思えた。しかし、冒頭で述べた出来事が起きたのは、それまでの激しい波の振れも間合いもごくわずかだが落ち着きはじめ、波と波との境もかなり不明瞭なものになってきたのではないか、そんな個人的な印象を抱きはじめていた矢先のことだった。
それだけに私には、半狂乱のような目の前の現実が、ほとんど信じがたく理解しがたいものに映ったのも事実だった。しかし、事態はそんな安穏とした理解や判断にとどまっていることなど許さなかった。私は当初、ほとんど彼の前に金縛りのようになって立っていた。ともかくも、あわてふためく自分も恐れおののく自分もなんとか抑えながら、「どうしたの? 急に……」と困惑しながら声をかけるのがやっとだった。
「話してみてよ。どうしたの?」「何がどうしたっていうの?」等々、思いつく限りの声かけを続けたが、彼の興奮と叫びはいっこうに収まる気配はなかった。それどころかますますエスカレートして、私全体を巻き込み、飲み込んでしまうかのような激しさとただならぬ切迫感を募らせていた。
私はその異常な圧力に耐えながら、つとめて冷静さを保とうとしていたものの、それさえ不可能になっていた。私は、しばしば、自分自身のこの判断(いまだ、ただ一人で対応していること)の誤りを感じながらも、しだいに冷静さを失い、上気し語気を強めていく自分を感じていた。その声のトーンは、ほとんど彼のそれに近いものになっていたような気がする。私は、彼の激しい悲嘆と自殺企図へのおそれや不安から、なんとかこの事態を収拾しようと焦りほとんど我を失っていた。
そんなとき、私の口から、自分でも信じがたい言葉が飛び出してきた。
「ねえ、○○さん、私にも見えるよ、あなたのお母さんが。それに、聞こえるよ、あなたのお母さんの言葉が」
「そこにいるじゃないの、あなたを見て」
「そう、私にははっきり見えるよ。そして、言ってるじゃないの、死ぬなって。○○さん、あなたには聞こえないの!」
「私のぶんまで生きてって、そう言ってるじゃないの!」
私は夢中だった。ただ、自分の言っていることが、専門職としての妄想への「標準的な態度」から大きく逸脱していることに気づかないわけではなかった。というより、そうしている自分に驚き、たいへんな間違いをしているのではないかという思いにとらわれもした。しかし私はそれ以上に真剣だったのだ。そのうちに私は、ほとんど彼の母親になりかわっている自分にさえ気づいた。
「お前のことはもう許すから、もう許しているから、…だから決して死んではいけない」
「お母さんのぶんまで生きるのよ」
私は立ちながら、膝をつきながら、床にべったりと腰を下ろしながら、また立ち上がって、延々と彼に向き合いつづけていた。私は最初、たしかに彼の担当看護師だったのだが、その後なかば幻覚の見える患者本人となり、さらになかば亡くなった彼の母親本人にもなっていた。私は上気し汗だくになっていた。彼ももちろんそうだった。彼は激しく泣いて涙さえ枯れてしまっていた。
私たちは、互いに逃げることも避けることもできない現実と妄想の狭間に巻き込まれながら、尋常ならざる「劇」を演じていた。私は、そのことの持つ意味やそれがもたらすかもしれない有害さについてまったく意識できないわけではなかった。ただそれは、自然と必然とによってうながされたかのような、この切実な「劇」をやめる力にはならなかった。
そして、彼はようやく落ち着きを取り戻し始めた。私の前で叫ぶことをやめ力なく肩を落としていた。すでに1時間半をゆうに超える時間が経過していたことに、そのとき私はようやく気づいた。
その後のこと
彼はその後の日々も、一進一退を繰り返していた。病状の執拗な波は、気まぐれな自然の波のように押し寄せては消え、押し寄せては消えることを繰り返した。ただ、あの出来事の後の波は、それまでの荒波とはどこか違っているように思えてならなかった。あえていえばその波の感触というか伝わり方というか、そうした類のものに過ぎなかったのだが。実際、そうこうするうちに波の力、つまり病状そのものの力も、しだいに弱まっていく方向へと確実に向かいはじめたのだった。
しかし、私にとって忘れがたいあの出来事は、いまとなってはおそらくいかようにも語りうる、多くの不確定さや可能性を持った対象であるに違いない。回復への途上の重要な契機としてとらえることもできれば、たまたま大事に至らなかった看護師の誤判断事例ともいえれば、あるいは偶然にも大波にさらわれかけた不運な看護師物語に過ぎなかったのかもしれない。ただ、それでも一つだけいえることは、少なくともあのとき彼は、私を「必要としていた」ということではないだろうか。
彼は、絶望して泣き叫び、幻覚と妄想の世界を行きかってはいたが、それはあくまでも、彼を訪れた私の目の前で起きた(あるいは起きる必要のあった?)出来事だった。しかも、たじろぎ驚きながら立っている私を否応なく巻き込みながら。
彼はおそらくそのような私を必要としていたのだろう。まさに自分自身と見まがうほどの私の姿を。実際、彼にはそういう時期がきていたのかもしれない。幻想と現実と悲嘆とを、なんとか一つの像に近づけようとするときの耐えがたい苦痛や恐れを感じ取りながら、それでも何かにしがみつき立ち上がろうとする時期に。
そんなときに出くわしてしまった私は、教科書よろしく「中立的に」「肯定も否定もせずに」現実や安全へと導くことなど、やろうとしてもできなかっただけだった。たとえそのとき、この事態をさほど危険性のないある種のカタルシスのようなものと理解していたとしても、私はけっきょく同様な対応を余儀なくされていたような気がする[★1]。
それほど彼は、私という人間の「杖」を必要としていたように思えたから。ただもちろん当時の私は、彼の病状やそれに伴うさまざまな出来事について、十分な理解や把握をしていたわけでは決してなかった。ともかくも当時私は、このような現実を経験しながら、多くの驚きや恐れや学びや疑問のなかにいた。そこには、いまだ経験したことも記述されたことも議論されたこともないであろう、多くの臨床の現実が横たわっているように私には思えた。
あの日、ようやく彼との長く切迫した時間から解放された私は、ほとんどへとへとになりながら同僚たちのいる看護室にたどりついていた。私は大きく息をつきながら、なかば高揚しなかば脱力したまま、つい先ほどまでのたいへんな出来事と経験を周囲に吐き出していた。同僚たちは一様に驚き私をなぐさめはしたものの、まもなくそれぞれの業務に追い立てられるかのように出て行ってしまった。私はそれから、閑散とした看護室で、興奮を静めながらいままさに経験してきたばかりの異様な出来事を、ずいぶんと丹念に記録しつづけた覚えがある。
そして、理解も評価も判然とせぬまま書いた記録ではあれ、その当日から、ケアや治療のための重要な情報として利用される。そうやって日々のケアや治療は続けられ、さらにカルテには、同種の困難な記述やエピソードの数々が積み重ねられていく。そのうちに、多くの患者たちは回復を果たし、また一部は長く膠着することにもなる。この彼の場合は、幸いにもしだいに小康を得て、数か月後には私たちの病棟から慢性期病棟へと転棟していったのだが。
臨床の現実はどこにあるのか
いま、彼の入院記録を記したあの膨大なカルテはどこにあるのだろう。もし彼が退院してしまっているとしたら、その分厚い記録の束は地下の文書倉庫の片隅に、埃をかぶって眠っているに違いない。おそらくその階上の病棟では、また同じように困難な現実が何度となく繰り返され、患者も看護師も同じような苦しみや恐れや懐疑のただなかにいるのではないだろうか。
もちろん看護師の営みとは、専門的な知識や経験、判断等をもとにして行なわれるものである。ただしそれらは、複雑で個別的な臨床事例に向き合う道具として、ただちに十全なものとなりうるわけではない。実際には、冒頭で示した事例のように、その現実に圧倒されながらも、わずかにみずからの知識や経験を支えとして、なんとか向き合いしのいでいる場合も多いに違いない。
こうした状況下では、なぜ患者はこんなにも変わってしまったのか、なぜこうも落ち着いてしまったのか、あるいはなぜ事態は長く停滞したままなのかなど、幾多の問いはほとんど日常的に生じうるものだろう。にもかかわらず、(特に急性期病棟の)多くの看護師は、この種の問いに十分向き合ういとまもなく、新たな入院患者を受け入れつづける日常を生きている。毎日のほとんどは、目の前にある差し迫った問題への対処や繁忙なルーチン業務に追われて過ぎていく。
しかし、こうした現実のなかにこそ、看護師や患者を苦しめつづける真に臨床的な問題が存在しているのだ。
しかも、そこにあるはずの問題とは、時とともに過ぎ去り、意識や記憶からも速やかに消え去っていくとらえがたい対象である。それらの多くは、新人の看護師がどんなに眼を凝らしても見えず、どんなにすぐれた研究者が短期滞在したくらいでは見ることのできない、臨床の深部に位置する困難かつ複雑な臨床現象なのである。また、その場合の臨床現象とは、それにかかわる当事者(患者、看護師、医師、その他スタッフや研究者等々)の認知、思考、経験、かかわりのあり方や深さなどによって、いかようにも(したがっていくつもの)像を結ぶことができる相互的なリアリティの一つに過ぎない。
臨床にいる看護師は、こうした現実の深みで仕事を続けている。さまざまな汗を伴うケアと、日々の膨大な経過記録やケアプランやカンファレンスの数々を残しながら……。ただしそれらの多くは、法的保存期限を待つ記録と同様閉ざされたまま、全体像の発掘に向けて再度見直されることは稀である。もちろん、ときに研究の対象となって新たな知見が見出されることもあり、現にそうやって臨床知は少しずつ蓄積されてきたに違いない。それに、なにより必要なのは患者を支えうる「ケアそのもの」なのであって、常にそのケアを正当化する理屈や理論の存在が必須であるわけでもない。むしろ、予期できないほどの現実に対しても、(本事例のように現状理解もままならぬまま)ともかくも向き合い同伴することが、看護の基本的な役割でありある種の本質でもあるのだから。
だとしても、先にも述べたように、いま私たちが向き合っている臨床の現実とは、そこにたしかに存在しながらも、つかもうとしてはすり抜け、拾い上げた断片からだけではほとんど復元不可能な、関係者相互的で不定形のモザイクに似たあり方をしている。その意味ではいまだ看護師は、臨床にある「現実」にたどり着くことさえできていないのではないか、という素朴な疑問を抱く。しかも、そこにたどり着いたとしても、その現実のいくぶんかは、すでに医学や看護学さらにはその他多くのコメディカルの強い専門性志向のなかで、なかばつくり出されたものに過ぎないかもしれない。
ここで、ほぼ25年余も前に遡る、臨床看護研究の白眉ともいうべき「事例検討」を実践しかつ論じた外口の発言[外口1981:37]を、やや我田引水だが以下に引用したいと思う。
「看護の理念が盛んに謳われ追求されている昨今ですが、私は、行なわれている実践を表現しえていないこと、そのための方法を発見していないことが現代の看護領域における問題と考えています」
私たちが日々行なっている看護実践とは何か、それを表現するとは何か、その方法とは何なのか。
すでに四半世紀も前の切実な問いであるが、振り返って私たちの時代にこの問いの回答が用意されているとはまったくいいがたい。というよりこの問いは、人間を対象とする科学すなわち人間科学全般にも敷衍できる(しかも、いままさに存在する)重く大きな方法論的問いであるようにも思える。ところが現在、私たちの看護(臨床においても研究においても)は、臨床の現実を丹念に写しとり表現し吟味しようとする問題意識よりも、むしろそれらを数値や記号やチャートや概念のなかに削り込み、あるいは看護行為の入口や出口だけを注視するような標準化や効率化の時代へと突き進みつつあるように思える。そのようななかでは、先の外口の問いはますます遠くなっていくように思えてならない[★2]。
その意味でも本書は、だいぶ反時代的で流行はやらないものと見なされるかもしれない。けれど私の願いは、依然この流行らない問いとともにある比較的素朴なものである。つまり、当初まったくの新人から、しだいに臨床看護師としてより深くかかわることで向き合うことになった問題群をともかくも描き出し、それら問題の持つ複雑で多様な意味やあり様を一つひとつ問おうとしたものである。
そして、なによりもそのことによって、精神医療に従事する当事者の臨床的あり方をとらえつつ再考し、さらに支持し、最終的には有効で確かな患者支援へとつながっていくであろう、臨床の知恵を積み重ねようとするわずかな試みを示したいと思う。
[★1]臨床実践において、教科書的な妄想への態度、たとえば「肯定も否定もしない」「中立的な」態度というものほど不親切なものもない。その気持ちも根拠もある程度理解できるが、患者の前では無力に近い。現実には「そうなんですね。ただ……」などと答えることが多いのではと思われるが、その場合、「そうなんですね」では患者の主観的な事実としての妄想を「肯定的」に受け止め、「ただ……」では、客観的な事実とは違う妄想に対してやや「否定的」に距離を置いている。その意味ではむしろ「肯定も否定もしている」ということになる。
しかし、このような対応はこと妄想への対応に限られるものではないと私は思う。患者へのケアにおいては、まず患者の経験世界を(たとえそれがどのようなものであれ)「彼自身にとっての事実」として受け止めることなくして、患者へと近づくことはまず期待できない。それは妄想を強化させる云々以前の問題意識である。その後に、ようやく看護師は患者の傍らに行くことができ、さらにはともに歩くこと、つまりやや現実的な方向づけという働きかけやケアが可能となるのである。
[★2]さらに羽山[2004]は、急激な大学改革等に伴うなかば政策的な研究実績志向が、研究そのものの幅を狭め、より本質的な看護課題探索への流れが滞ることを危惧している。
ある日保護室で
その日、私は深夜勤務明けで、朝の病棟ミーティングでの申し送りも終えたところだった。書き残した看護記録をそそくさと書き上げ、帰り支度をしてナースステーションを出たのだが、なぜかふとある患者の保護室に足が向いていた。
ちょっと挨拶だけでもしていこうか、という軽い気持ちに過ぎなかった。ただし彼は、私の受け持ち患者(入院から退院まで責任を持つ)の一人であったし、依然かなりむずかしい病状を抱えたままだった。私自身も、彼のために日々めまぐるしく対応に追われ、かなり消耗していたことも事実だった。それでもとにかく私は、帰り際の挨拶をしようと彼の部屋を訪ねていた。
ところが、彼は、私の顔を見るなり突然泣きくずれ、激しく叫びはじめたのだった。しかも、とんでもない激しさというかほとんど爆発するかのように。「おれはもう死ぬ。生きていても仕方ないんだ。死、死ぬよ、死ぬんだよ!」などと叫びながら……。
私は、当然ながら驚いた。しかも腰が抜けそうなほどに。ただし彼の希死念慮とその訴えはほとんど常にあったから、それ自体に驚いたわけではなかった。今回は、その声も振る舞いもいままでにない格別なものだったからだ。彼は大声で叫びながら、まさにベッドの上で飛び跳ねんばかりだった。
私は一瞬ほとんど凍りついていた。いまにも彼はベッドの上から身を投げるのではないかとさえ思った。すぐに誰かに助けを求めなければと思うほどだった。けれど、そこは保護室ゾーンの最深部にあり、容易に声が届く場所ではなかった。それ以上に、彼の切迫しきった叫び声が私をたじろがせ、さらに不用意な私の反応がさらなるエスカレートを生みそうな気がした。私は、出しかけた声をのみ込んでしまった。「おれは生きていても仕方ないんだよ! 死ねって言ってるよ。もうだめなんだよ。おれは!」
数か月前、彼がこの病棟に運ばれてきたとき、彼はストレッチャー(搬送台車)上に簀巻き状態で固定され厳重に身体拘束されていた。彼は統合失調症で、思春期に発症していたが、ある特別な家庭の事情から長い無治療の時期などを経過して、すでに40歳を超える年齢になっていた。そして最近になって、不幸にも、本人と二人で同居していた母に対して重大な事件を起こし、今回の入院となったというわけだった。当然のことながら、入院当初から彼の病状は重かった。しかもそれはかなり特徴的なものだった。
「おれは神なんだ、メシアなんだ、天使なんだ」「ほら、いま降りてきたよそこに、神が」「おれは何だってできるんだよ」というように、おもに妄想的な世界に「浸っている」時期が長く続くと、次は「悲しいよ。寂しいよ。つらくてだめだ」「もう生きていても仕方ない。もう死ぬんだ。死ぬんだよ」とひっきりなしに悲嘆や死ぬことばかりを口にする時期がやってくる。そして、それが過ぎるとまた再び妄想の世界へ。
もちろん、その繰り返しのあり方は、それほどはっきり周期的なものと言い切れるわけではなかった。その日のうちにも、また次の瞬間にも入れ替わるし、一気にごちゃごちゃになって押し寄せて来たりもした。ただ大きく見ると、やはりそのような一群の波が、交互に入れ替わりながら押し寄せつづけているように私には思えた。しかし、冒頭で述べた出来事が起きたのは、それまでの激しい波の振れも間合いもごくわずかだが落ち着きはじめ、波と波との境もかなり不明瞭なものになってきたのではないか、そんな個人的な印象を抱きはじめていた矢先のことだった。
それだけに私には、半狂乱のような目の前の現実が、ほとんど信じがたく理解しがたいものに映ったのも事実だった。しかし、事態はそんな安穏とした理解や判断にとどまっていることなど許さなかった。私は当初、ほとんど彼の前に金縛りのようになって立っていた。ともかくも、あわてふためく自分も恐れおののく自分もなんとか抑えながら、「どうしたの? 急に……」と困惑しながら声をかけるのがやっとだった。
「話してみてよ。どうしたの?」「何がどうしたっていうの?」等々、思いつく限りの声かけを続けたが、彼の興奮と叫びはいっこうに収まる気配はなかった。それどころかますますエスカレートして、私全体を巻き込み、飲み込んでしまうかのような激しさとただならぬ切迫感を募らせていた。
私はその異常な圧力に耐えながら、つとめて冷静さを保とうとしていたものの、それさえ不可能になっていた。私は、しばしば、自分自身のこの判断(いまだ、ただ一人で対応していること)の誤りを感じながらも、しだいに冷静さを失い、上気し語気を強めていく自分を感じていた。その声のトーンは、ほとんど彼のそれに近いものになっていたような気がする。私は、彼の激しい悲嘆と自殺企図へのおそれや不安から、なんとかこの事態を収拾しようと焦りほとんど我を失っていた。
そんなとき、私の口から、自分でも信じがたい言葉が飛び出してきた。
「ねえ、○○さん、私にも見えるよ、あなたのお母さんが。それに、聞こえるよ、あなたのお母さんの言葉が」
「そこにいるじゃないの、あなたを見て」
「そう、私にははっきり見えるよ。そして、言ってるじゃないの、死ぬなって。○○さん、あなたには聞こえないの!」
「私のぶんまで生きてって、そう言ってるじゃないの!」
私は夢中だった。ただ、自分の言っていることが、専門職としての妄想への「標準的な態度」から大きく逸脱していることに気づかないわけではなかった。というより、そうしている自分に驚き、たいへんな間違いをしているのではないかという思いにとらわれもした。しかし私はそれ以上に真剣だったのだ。そのうちに私は、ほとんど彼の母親になりかわっている自分にさえ気づいた。
「お前のことはもう許すから、もう許しているから、…だから決して死んではいけない」
「お母さんのぶんまで生きるのよ」
私は立ちながら、膝をつきながら、床にべったりと腰を下ろしながら、また立ち上がって、延々と彼に向き合いつづけていた。私は最初、たしかに彼の担当看護師だったのだが、その後なかば幻覚の見える患者本人となり、さらになかば亡くなった彼の母親本人にもなっていた。私は上気し汗だくになっていた。彼ももちろんそうだった。彼は激しく泣いて涙さえ枯れてしまっていた。
私たちは、互いに逃げることも避けることもできない現実と妄想の狭間に巻き込まれながら、尋常ならざる「劇」を演じていた。私は、そのことの持つ意味やそれがもたらすかもしれない有害さについてまったく意識できないわけではなかった。ただそれは、自然と必然とによってうながされたかのような、この切実な「劇」をやめる力にはならなかった。
そして、彼はようやく落ち着きを取り戻し始めた。私の前で叫ぶことをやめ力なく肩を落としていた。すでに1時間半をゆうに超える時間が経過していたことに、そのとき私はようやく気づいた。
その後のこと
彼はその後の日々も、一進一退を繰り返していた。病状の執拗な波は、気まぐれな自然の波のように押し寄せては消え、押し寄せては消えることを繰り返した。ただ、あの出来事の後の波は、それまでの荒波とはどこか違っているように思えてならなかった。あえていえばその波の感触というか伝わり方というか、そうした類のものに過ぎなかったのだが。実際、そうこうするうちに波の力、つまり病状そのものの力も、しだいに弱まっていく方向へと確実に向かいはじめたのだった。
しかし、私にとって忘れがたいあの出来事は、いまとなってはおそらくいかようにも語りうる、多くの不確定さや可能性を持った対象であるに違いない。回復への途上の重要な契機としてとらえることもできれば、たまたま大事に至らなかった看護師の誤判断事例ともいえれば、あるいは偶然にも大波にさらわれかけた不運な看護師物語に過ぎなかったのかもしれない。ただ、それでも一つだけいえることは、少なくともあのとき彼は、私を「必要としていた」ということではないだろうか。
彼は、絶望して泣き叫び、幻覚と妄想の世界を行きかってはいたが、それはあくまでも、彼を訪れた私の目の前で起きた(あるいは起きる必要のあった?)出来事だった。しかも、たじろぎ驚きながら立っている私を否応なく巻き込みながら。
彼はおそらくそのような私を必要としていたのだろう。まさに自分自身と見まがうほどの私の姿を。実際、彼にはそういう時期がきていたのかもしれない。幻想と現実と悲嘆とを、なんとか一つの像に近づけようとするときの耐えがたい苦痛や恐れを感じ取りながら、それでも何かにしがみつき立ち上がろうとする時期に。
そんなときに出くわしてしまった私は、教科書よろしく「中立的に」「肯定も否定もせずに」現実や安全へと導くことなど、やろうとしてもできなかっただけだった。たとえそのとき、この事態をさほど危険性のないある種のカタルシスのようなものと理解していたとしても、私はけっきょく同様な対応を余儀なくされていたような気がする[★1]。
それほど彼は、私という人間の「杖」を必要としていたように思えたから。ただもちろん当時の私は、彼の病状やそれに伴うさまざまな出来事について、十分な理解や把握をしていたわけでは決してなかった。ともかくも当時私は、このような現実を経験しながら、多くの驚きや恐れや学びや疑問のなかにいた。そこには、いまだ経験したことも記述されたことも議論されたこともないであろう、多くの臨床の現実が横たわっているように私には思えた。
あの日、ようやく彼との長く切迫した時間から解放された私は、ほとんどへとへとになりながら同僚たちのいる看護室にたどりついていた。私は大きく息をつきながら、なかば高揚しなかば脱力したまま、つい先ほどまでのたいへんな出来事と経験を周囲に吐き出していた。同僚たちは一様に驚き私をなぐさめはしたものの、まもなくそれぞれの業務に追い立てられるかのように出て行ってしまった。私はそれから、閑散とした看護室で、興奮を静めながらいままさに経験してきたばかりの異様な出来事を、ずいぶんと丹念に記録しつづけた覚えがある。
そして、理解も評価も判然とせぬまま書いた記録ではあれ、その当日から、ケアや治療のための重要な情報として利用される。そうやって日々のケアや治療は続けられ、さらにカルテには、同種の困難な記述やエピソードの数々が積み重ねられていく。そのうちに、多くの患者たちは回復を果たし、また一部は長く膠着することにもなる。この彼の場合は、幸いにもしだいに小康を得て、数か月後には私たちの病棟から慢性期病棟へと転棟していったのだが。
臨床の現実はどこにあるのか
いま、彼の入院記録を記したあの膨大なカルテはどこにあるのだろう。もし彼が退院してしまっているとしたら、その分厚い記録の束は地下の文書倉庫の片隅に、埃をかぶって眠っているに違いない。おそらくその階上の病棟では、また同じように困難な現実が何度となく繰り返され、患者も看護師も同じような苦しみや恐れや懐疑のただなかにいるのではないだろうか。
もちろん看護師の営みとは、専門的な知識や経験、判断等をもとにして行なわれるものである。ただしそれらは、複雑で個別的な臨床事例に向き合う道具として、ただちに十全なものとなりうるわけではない。実際には、冒頭で示した事例のように、その現実に圧倒されながらも、わずかにみずからの知識や経験を支えとして、なんとか向き合いしのいでいる場合も多いに違いない。
こうした状況下では、なぜ患者はこんなにも変わってしまったのか、なぜこうも落ち着いてしまったのか、あるいはなぜ事態は長く停滞したままなのかなど、幾多の問いはほとんど日常的に生じうるものだろう。にもかかわらず、(特に急性期病棟の)多くの看護師は、この種の問いに十分向き合ういとまもなく、新たな入院患者を受け入れつづける日常を生きている。毎日のほとんどは、目の前にある差し迫った問題への対処や繁忙なルーチン業務に追われて過ぎていく。
しかし、こうした現実のなかにこそ、看護師や患者を苦しめつづける真に臨床的な問題が存在しているのだ。
しかも、そこにあるはずの問題とは、時とともに過ぎ去り、意識や記憶からも速やかに消え去っていくとらえがたい対象である。それらの多くは、新人の看護師がどんなに眼を凝らしても見えず、どんなにすぐれた研究者が短期滞在したくらいでは見ることのできない、臨床の深部に位置する困難かつ複雑な臨床現象なのである。また、その場合の臨床現象とは、それにかかわる当事者(患者、看護師、医師、その他スタッフや研究者等々)の認知、思考、経験、かかわりのあり方や深さなどによって、いかようにも(したがっていくつもの)像を結ぶことができる相互的なリアリティの一つに過ぎない。
臨床にいる看護師は、こうした現実の深みで仕事を続けている。さまざまな汗を伴うケアと、日々の膨大な経過記録やケアプランやカンファレンスの数々を残しながら……。ただしそれらの多くは、法的保存期限を待つ記録と同様閉ざされたまま、全体像の発掘に向けて再度見直されることは稀である。もちろん、ときに研究の対象となって新たな知見が見出されることもあり、現にそうやって臨床知は少しずつ蓄積されてきたに違いない。それに、なにより必要なのは患者を支えうる「ケアそのもの」なのであって、常にそのケアを正当化する理屈や理論の存在が必須であるわけでもない。むしろ、予期できないほどの現実に対しても、(本事例のように現状理解もままならぬまま)ともかくも向き合い同伴することが、看護の基本的な役割でありある種の本質でもあるのだから。
だとしても、先にも述べたように、いま私たちが向き合っている臨床の現実とは、そこにたしかに存在しながらも、つかもうとしてはすり抜け、拾い上げた断片からだけではほとんど復元不可能な、関係者相互的で不定形のモザイクに似たあり方をしている。その意味ではいまだ看護師は、臨床にある「現実」にたどり着くことさえできていないのではないか、という素朴な疑問を抱く。しかも、そこにたどり着いたとしても、その現実のいくぶんかは、すでに医学や看護学さらにはその他多くのコメディカルの強い専門性志向のなかで、なかばつくり出されたものに過ぎないかもしれない。
ここで、ほぼ25年余も前に遡る、臨床看護研究の白眉ともいうべき「事例検討」を実践しかつ論じた外口の発言[外口1981:37]を、やや我田引水だが以下に引用したいと思う。
「看護の理念が盛んに謳われ追求されている昨今ですが、私は、行なわれている実践を表現しえていないこと、そのための方法を発見していないことが現代の看護領域における問題と考えています」
私たちが日々行なっている看護実践とは何か、それを表現するとは何か、その方法とは何なのか。
すでに四半世紀も前の切実な問いであるが、振り返って私たちの時代にこの問いの回答が用意されているとはまったくいいがたい。というよりこの問いは、人間を対象とする科学すなわち人間科学全般にも敷衍できる(しかも、いままさに存在する)重く大きな方法論的問いであるようにも思える。ところが現在、私たちの看護(臨床においても研究においても)は、臨床の現実を丹念に写しとり表現し吟味しようとする問題意識よりも、むしろそれらを数値や記号やチャートや概念のなかに削り込み、あるいは看護行為の入口や出口だけを注視するような標準化や効率化の時代へと突き進みつつあるように思える。そのようななかでは、先の外口の問いはますます遠くなっていくように思えてならない[★2]。
その意味でも本書は、だいぶ反時代的で流行はやらないものと見なされるかもしれない。けれど私の願いは、依然この流行らない問いとともにある比較的素朴なものである。つまり、当初まったくの新人から、しだいに臨床看護師としてより深くかかわることで向き合うことになった問題群をともかくも描き出し、それら問題の持つ複雑で多様な意味やあり様を一つひとつ問おうとしたものである。
そして、なによりもそのことによって、精神医療に従事する当事者の臨床的あり方をとらえつつ再考し、さらに支持し、最終的には有効で確かな患者支援へとつながっていくであろう、臨床の知恵を積み重ねようとするわずかな試みを示したいと思う。
[★1]臨床実践において、教科書的な妄想への態度、たとえば「肯定も否定もしない」「中立的な」態度というものほど不親切なものもない。その気持ちも根拠もある程度理解できるが、患者の前では無力に近い。現実には「そうなんですね。ただ……」などと答えることが多いのではと思われるが、その場合、「そうなんですね」では患者の主観的な事実としての妄想を「肯定的」に受け止め、「ただ……」では、客観的な事実とは違う妄想に対してやや「否定的」に距離を置いている。その意味ではむしろ「肯定も否定もしている」ということになる。
しかし、このような対応はこと妄想への対応に限られるものではないと私は思う。患者へのケアにおいては、まず患者の経験世界を(たとえそれがどのようなものであれ)「彼自身にとっての事実」として受け止めることなくして、患者へと近づくことはまず期待できない。それは妄想を強化させる云々以前の問題意識である。その後に、ようやく看護師は患者の傍らに行くことができ、さらにはともに歩くこと、つまりやや現実的な方向づけという働きかけやケアが可能となるのである。
[★2]さらに羽山[2004]は、急激な大学改革等に伴うなかば政策的な研究実績志向が、研究そのものの幅を狭め、より本質的な看護課題探索への流れが滞ることを危惧している。
目次
開く
プロローグ 私たちの現実はどこにあるのか?
第1章 「帰れない」エスノグラファー…臨床看護師のための研究方法をめぐって
1-1 エスノグラフィーという方法
1-2 臨床をどう記述するか
第2章 病院の入り口で
2-1 入院という出来事
2-2 治療・看護との遭遇
第3章 介入と回復
3-1 薬物療法による変容と精神病後抑うつ
3-2 隔離あるいは身体的拘束
3-3 回復過程における依存と強迫をめぐって
第4章 反復と語り
4-1 経験の用法としての言語と臨床の詩学
4-2 語りはなぜ可能なのか
第5章 新たな病棟文化の構築に向けて
5-1 何がケアを支えるのか
5-2 病棟文化というもう一つのケア…人、組織、制度
5-3 農耕的なるものへの夢
エピローグ 「感じる看護」はどこへ行くのか
補遺 精神科病棟の構造と機能
文献
初出一覧
あとがき(謝辞)
第1章 「帰れない」エスノグラファー…臨床看護師のための研究方法をめぐって
1-1 エスノグラフィーという方法
1-2 臨床をどう記述するか
第2章 病院の入り口で
2-1 入院という出来事
2-2 治療・看護との遭遇
第3章 介入と回復
3-1 薬物療法による変容と精神病後抑うつ
3-2 隔離あるいは身体的拘束
3-3 回復過程における依存と強迫をめぐって
第4章 反復と語り
4-1 経験の用法としての言語と臨床の詩学
4-2 語りはなぜ可能なのか
第5章 新たな病棟文化の構築に向けて
5-1 何がケアを支えるのか
5-2 病棟文化というもう一つのケア…人、組織、制度
5-3 農耕的なるものへの夢
エピローグ 「感じる看護」はどこへ行くのか
補遺 精神科病棟の構造と機能
文献
初出一覧
あとがき(謝辞)
書評
開く
精神医療の現場伝える (『読売新聞』掲載)
書評者: 春日 武彦 (精神科医)
(『読売新聞』2008年3月17日「本よみうり堂」に上記書評が掲載されました)
書評――臨床で書く (『臨床心理学』掲載)
書評者: 森岡 正芳 (神戸大学大学院)
(『臨床心理学』2008年8巻5号(9月号)に上記書評が掲載されました)
ほんとの対話 (『こころの科学』掲載)
書評者: 江口 重幸 (東京武蔵野病院・精神科医)
(『こころの科学』2008年7月第140号に上記書評が掲載されました)
“果敢なる弱さ”から来ている本書がもつ圧倒的な力―感情的な反応をより深い臨床理解へと転換させる作業 (『図書新聞』掲載)
書評者: 橋本 明 (愛知県立大学教授・ 精神医療史・精神保健福祉論)
(『図書新聞』2008年5月17日2869号に上記書評が掲載されました)
臨床民族誌としての看護の可能性―患者の個別的生活世界に寄り添って (『週刊読書人』掲載)
書評者: 山田 富秋 (松山大学教授・社会学)
(『週刊読書人』2008年5月23日2739号に上記書評が掲載されました)
書評 (雑誌『精神看護』より)
書評者: 大西 香代子 (三重大学医学部看護学科・教授)
◆よみがえる記憶――あの患者たちのこと
「時間が経たないんだよ。それで、タバコをすうと、タバコが短くなった分だけ、時間が過ぎ去ったことが見えるんだ」。
それは、「どうしてそんなにタバコばかりすっているの?」という無邪気にして残酷な質問に対する答えだった。私は看護師になったばかりで、彼は私の初めての受け持ち患者だった。散歩をしながらそんな会話をして1時間も経たないうちに、彼は無断離院した。翌日、車で2時間ほどかかる彼の自宅に先輩の看護師と彼を迎えに行ったことを思い出す。新人の私には、彼がそのときどうしようもない焦燥感に苦しんでいたことがわからなかった。
同じ頃、初回入院となった青年は、精悍な身のこなしで他患者の世話を焼いていたが、まもなく錐体外路症状が現れてきた。「見てくれよ! 俺、前はあんなに速く走れたのに、今は歩くのだってこんなになってしまって」と言われ、私には何も答えることができなかった。そしてその半年後、彼はビルの屋上から虚空へと身を躍らせた……。
忘れることのできない患者の姿、言葉の数々が、20年以上の時を経て、突然鮮やかに蘇ってきた。その原因は、紛れもなくこの本、松澤和正氏の筆になる『臨床で書く 精神科看護のエスノグラフィー』にある。これまで、精神科の臨床がこれほど活き活きと描き出されたことがあっただろうか。
◆精神科の臨床を活写したい欲望に、私たちは身を焼いてきた
そして、気づかなかった、というより、「みずから眺めることも困難なほど現実に馴化してしまって」いた問題があぶりだされていることに衝撃を受けた。今まで、私たち看護師は、客観的に記述することが正しいと教えられ、そう信じながらも、目の前の患者やその患者と看護師、あるいは他の患者たちとの間で生じていることを表現するにはあまりに味気ない「看護診断」のラベルにも違和感を禁じえなかった。
この『臨床で書く 精神科看護のエスノグラフィー』は、臨床で看護師たちが感じていた違和感の大切さをも教えてくれた。例えば、患者「様」という呼称を用いるときの、どこかうしろめたいような心のなかのざらつき。その違和感を追求すると、患者との距離感や患者に対する自らの姿勢が見えてくる。また例えば、患者の状態を医師に報告するときの看護師の微妙なニュアンスの違い。そこからは、隔離や拘束に関する精神保健福祉法の規定も吹っ飛ぶような現実が明らかとなる。そしてまた、「看護室症候群」という命名によって見えてくる患者の病態。質の高いエスノグラフィーは、良質の読み物でもある。
◆臨床で迷子になってしまったあなたへ
本当のことを言えば、この本の書評だけは書きたくなかった。看護・精神医学だけでなく、臨床人類学、社会学、哲学などの幅広く深い素養を背景にした、どこか中井久夫を思い起こさせるような味わいの文の前には、どのような書評も無力である。それでも書いてしまったのは、無名のまま忘れられようとしている人々の存在を書くことでとどめたいとの思いを、『臨床で書く 精神科看護のエスノグラフィー』が触発したからだった。きっと松澤氏も同じような思いを抱いていたのではないか、と推測している。
いつのまにか、私も「行ったきりのフィールドワーカー」から「帰還」を果たそうとしはじめたのかもしれない。そして、臨床というフィールドで迷子になってしまったあなたにも、きっと道が見えてくるだろう。
「自由」であるための自覚とこだわり
書評者: 萱間 真美 (聖路加看護大学教授)
本書『臨床で書く』は360ページの大作であり,あたかも『ハリー・ポッター』とか『終わりのない物語』のように重厚な装丁に仕上がり,見知らぬ世界を予感させる。読み始めても,中身は期待を裏切らない。精神科看護の経験がないひとにとって,繰り広げられる日々の真実はきっと「精神科看護は楽だ」というようなステレオタイプの見方をひっくり返すことだろう。
また,巻末にある「精神科病棟の構造と機能」も,部屋の配置,人員配置,勤務体制,入院治療の流れ,看護の流れ,患者の日常生活など,精神科病棟のさまざまな要素が客観的に解説されており,精神科を知らない人への手引きとしても秀逸である。
◆臨床の「苦い思い」に向かい合う
急性期の重篤な精神症状を持ち,自我の機能が極端に弱体化した状態の患者を受け入れ,手厚い治療と看護を提供する病院の看護師として,著者の松澤氏が遭遇した事例は多様で,リアルだ。
入院を拒否しながらなぜ病棟に入って行くのか――
看護師を求めてドアを激しく叩く患者を横目に,尊敬する温厚な看護師がなぜ平静でいるのか――
なぜ行動制限が必要な患者を前に看護師は回避的な態度をとるのか――
精神科の急性期病棟で働く看護師なら疑問をもたなかった者はいないと思われる出来事。しかし,向かい合うことなしに走り過ぎてしまっていながら,心のどこかにずっと残っている苦い思い。松澤氏はこれらに対して驚くほど自覚的であり,走り過ぎることなしに再構成し,そのときの看護師のあり方に,気持ちに,向かい合う。
◆「臨床をいかに記録し再現するか」という問い
松澤氏は,SOAP形式で記録された看護記録の「S(患者の主観的データ)」と「O(看護師が観察したこと)」を中心に看護場面を記録から切り取り,そこで起こった看護師と患者の相互作用と,主に看護師側のこころのあり方に関して考察を加えている。看護師と患者に起こった「事実」に軸足をしっかりすえるこの姿勢は,情緒的な思い入れを排したうえで,精神科の臨床で起こっているさまざまな事件を,具体性を失わないレベルで,しかも動的に捉えており,中途半端に抽象的ではない。
このような研究活動の目的を氏は,《意識的に看護そのものを対象化すること》であり,そのことによって《ようやく目の前にある問題や患者の現実がとらえられるようになった》と述べている。事件を経験している当事者の「意識・経験レベル」を捉えるために,「臨床現象をいかに記録し再現するか」という氏の問いは,現実と離れることを目指すのではなく,むしろそうすることによって初めて現実と向かい合えるのだという。
◆「文系×寄り道」vs.「理系×一直線」
私たちの活動する精神科看護の領域には,「寄り道」をした経験のある人材がたくさんいる。松澤氏は「寄り道」と呼ぶのがはばかられるほど,文学における博士課程の研究を行いながら精神科看護に従事していた方である。
私自身は,「文系」と「寄り道」の2つに対して,コンプレックスをもちながら精神科看護の領域で関わってきた。それは,自分自身が「理系」で「寄り道なし」にここにいるからである。前者の経歴や知識背景をもつ人たちは,いつもどこか臨床でのどろどろした体験から離れたところに自分をおき,その中の具体のテーマに日々あくせくしている臨床看護師たちを,哲学に視座をおきながら冷ややかに見つめているかのような,独特の距離を感じてきたためかもしれない。
実際,360ページに及ぶ論考の末にすえられたテーマは,「農業としての看護へ」である。《土地を耕し,種をまき,水をやり,あとは自然の営みのなかで芽吹き成長するのを日々見守りながら待ち続ける,そのような遅々とした営み》が精神科看護だという。
それだったら,内省しなくても臨床の看護師たちは最初から自分たちの活動にはそうした素朴さをもっているではないか。だからこそ精神科急性期病棟のようなところにずっと身をおいていられるのだ。「なんだかまどろっこしい」という人もいるであろう。寄り道をして看護にきた人たちに感じる距離感は,彼らのこのような現実への向かい合い方による部分があるかもしれない。内省しつくさなければ素朴な向かい合いすらできないなんて,しんどすぎる。窮屈すぎる。そんなことばかりしていたら身動きがとれなくなる。看護はもっと本能的な営みなのではないか。
しかし,本当にそうなのだろうか。
◆素朴なだけでは自由になれない
松澤氏は《看護師の感情もその表出のあり方も,その目的に適うケアの一部として絶えずその妥当性や無危害性が問われなければならない》という。無自覚に,ただ素朴なだけでは他者に精神科看護の活動は理解されないのだ。確かにそうかもしれない。
「私は一生懸命やっているのだからわかるでしょう。わからないのはそっちが悪い」という論理を看護師にときどき見かけ,そして私は自分の活動に絶望しそうになるが,それでは議論もできない。他職種に向かって機能を主張することもできない。
私は看護の「理系」の研究者として,精神科看護を誰からも見える「形」にして正当に評価したいと願って活動してきた。こてこての「文系」の研究である本書とまったく作業のプロセスは異なるが,奇しくも同じ主張にたどりついている。無自覚であることと,自由であることは決定的に違う。自覚し,形にして初めて得られることもとても多いのだと思う。
良かった。意味もなく「文系」にコンプレックスをもち続けなくてもよさそうだ。
日ごろ何とも思わずに関わり,走り抜けている日々の出来事に,徹底的にこだわり,考察しつくす筆者の思索を通じて,精神科看護のあり方を,自分自身のあり方をふと立ち止まって見つめる豊かな時間を,この本と一緒にすごすのはきっと贅沢なことである。
書評者: 春日 武彦 (精神科医)
(『読売新聞』2008年3月17日「本よみうり堂」に上記書評が掲載されました)
書評――臨床で書く (『臨床心理学』掲載)
書評者: 森岡 正芳 (神戸大学大学院)
(『臨床心理学』2008年8巻5号(9月号)に上記書評が掲載されました)
ほんとの対話 (『こころの科学』掲載)
書評者: 江口 重幸 (東京武蔵野病院・精神科医)
(『こころの科学』2008年7月第140号に上記書評が掲載されました)
“果敢なる弱さ”から来ている本書がもつ圧倒的な力―感情的な反応をより深い臨床理解へと転換させる作業 (『図書新聞』掲載)
書評者: 橋本 明 (愛知県立大学教授・ 精神医療史・精神保健福祉論)
(『図書新聞』2008年5月17日2869号に上記書評が掲載されました)
臨床民族誌としての看護の可能性―患者の個別的生活世界に寄り添って (『週刊読書人』掲載)
書評者: 山田 富秋 (松山大学教授・社会学)
(『週刊読書人』2008年5月23日2739号に上記書評が掲載されました)
書評 (雑誌『精神看護』より)
書評者: 大西 香代子 (三重大学医学部看護学科・教授)
◆よみがえる記憶――あの患者たちのこと
「時間が経たないんだよ。それで、タバコをすうと、タバコが短くなった分だけ、時間が過ぎ去ったことが見えるんだ」。
それは、「どうしてそんなにタバコばかりすっているの?」という無邪気にして残酷な質問に対する答えだった。私は看護師になったばかりで、彼は私の初めての受け持ち患者だった。散歩をしながらそんな会話をして1時間も経たないうちに、彼は無断離院した。翌日、車で2時間ほどかかる彼の自宅に先輩の看護師と彼を迎えに行ったことを思い出す。新人の私には、彼がそのときどうしようもない焦燥感に苦しんでいたことがわからなかった。
同じ頃、初回入院となった青年は、精悍な身のこなしで他患者の世話を焼いていたが、まもなく錐体外路症状が現れてきた。「見てくれよ! 俺、前はあんなに速く走れたのに、今は歩くのだってこんなになってしまって」と言われ、私には何も答えることができなかった。そしてその半年後、彼はビルの屋上から虚空へと身を躍らせた……。
忘れることのできない患者の姿、言葉の数々が、20年以上の時を経て、突然鮮やかに蘇ってきた。その原因は、紛れもなくこの本、松澤和正氏の筆になる『臨床で書く 精神科看護のエスノグラフィー』にある。これまで、精神科の臨床がこれほど活き活きと描き出されたことがあっただろうか。
◆精神科の臨床を活写したい欲望に、私たちは身を焼いてきた
そして、気づかなかった、というより、「みずから眺めることも困難なほど現実に馴化してしまって」いた問題があぶりだされていることに衝撃を受けた。今まで、私たち看護師は、客観的に記述することが正しいと教えられ、そう信じながらも、目の前の患者やその患者と看護師、あるいは他の患者たちとの間で生じていることを表現するにはあまりに味気ない「看護診断」のラベルにも違和感を禁じえなかった。
この『臨床で書く 精神科看護のエスノグラフィー』は、臨床で看護師たちが感じていた違和感の大切さをも教えてくれた。例えば、患者「様」という呼称を用いるときの、どこかうしろめたいような心のなかのざらつき。その違和感を追求すると、患者との距離感や患者に対する自らの姿勢が見えてくる。また例えば、患者の状態を医師に報告するときの看護師の微妙なニュアンスの違い。そこからは、隔離や拘束に関する精神保健福祉法の規定も吹っ飛ぶような現実が明らかとなる。そしてまた、「看護室症候群」という命名によって見えてくる患者の病態。質の高いエスノグラフィーは、良質の読み物でもある。
◆臨床で迷子になってしまったあなたへ
本当のことを言えば、この本の書評だけは書きたくなかった。看護・精神医学だけでなく、臨床人類学、社会学、哲学などの幅広く深い素養を背景にした、どこか中井久夫を思い起こさせるような味わいの文の前には、どのような書評も無力である。それでも書いてしまったのは、無名のまま忘れられようとしている人々の存在を書くことでとどめたいとの思いを、『臨床で書く 精神科看護のエスノグラフィー』が触発したからだった。きっと松澤氏も同じような思いを抱いていたのではないか、と推測している。
いつのまにか、私も「行ったきりのフィールドワーカー」から「帰還」を果たそうとしはじめたのかもしれない。そして、臨床というフィールドで迷子になってしまったあなたにも、きっと道が見えてくるだろう。
「自由」であるための自覚とこだわり
書評者: 萱間 真美 (聖路加看護大学教授)
本書『臨床で書く』は360ページの大作であり,あたかも『ハリー・ポッター』とか『終わりのない物語』のように重厚な装丁に仕上がり,見知らぬ世界を予感させる。読み始めても,中身は期待を裏切らない。精神科看護の経験がないひとにとって,繰り広げられる日々の真実はきっと「精神科看護は楽だ」というようなステレオタイプの見方をひっくり返すことだろう。
また,巻末にある「精神科病棟の構造と機能」も,部屋の配置,人員配置,勤務体制,入院治療の流れ,看護の流れ,患者の日常生活など,精神科病棟のさまざまな要素が客観的に解説されており,精神科を知らない人への手引きとしても秀逸である。
◆臨床の「苦い思い」に向かい合う
急性期の重篤な精神症状を持ち,自我の機能が極端に弱体化した状態の患者を受け入れ,手厚い治療と看護を提供する病院の看護師として,著者の松澤氏が遭遇した事例は多様で,リアルだ。
入院を拒否しながらなぜ病棟に入って行くのか――
看護師を求めてドアを激しく叩く患者を横目に,尊敬する温厚な看護師がなぜ平静でいるのか――
なぜ行動制限が必要な患者を前に看護師は回避的な態度をとるのか――
精神科の急性期病棟で働く看護師なら疑問をもたなかった者はいないと思われる出来事。しかし,向かい合うことなしに走り過ぎてしまっていながら,心のどこかにずっと残っている苦い思い。松澤氏はこれらに対して驚くほど自覚的であり,走り過ぎることなしに再構成し,そのときの看護師のあり方に,気持ちに,向かい合う。
◆「臨床をいかに記録し再現するか」という問い
松澤氏は,SOAP形式で記録された看護記録の「S(患者の主観的データ)」と「O(看護師が観察したこと)」を中心に看護場面を記録から切り取り,そこで起こった看護師と患者の相互作用と,主に看護師側のこころのあり方に関して考察を加えている。看護師と患者に起こった「事実」に軸足をしっかりすえるこの姿勢は,情緒的な思い入れを排したうえで,精神科の臨床で起こっているさまざまな事件を,具体性を失わないレベルで,しかも動的に捉えており,中途半端に抽象的ではない。
このような研究活動の目的を氏は,《意識的に看護そのものを対象化すること》であり,そのことによって《ようやく目の前にある問題や患者の現実がとらえられるようになった》と述べている。事件を経験している当事者の「意識・経験レベル」を捉えるために,「臨床現象をいかに記録し再現するか」という氏の問いは,現実と離れることを目指すのではなく,むしろそうすることによって初めて現実と向かい合えるのだという。
◆「文系×寄り道」vs.「理系×一直線」
私たちの活動する精神科看護の領域には,「寄り道」をした経験のある人材がたくさんいる。松澤氏は「寄り道」と呼ぶのがはばかられるほど,文学における博士課程の研究を行いながら精神科看護に従事していた方である。
私自身は,「文系」と「寄り道」の2つに対して,コンプレックスをもちながら精神科看護の領域で関わってきた。それは,自分自身が「理系」で「寄り道なし」にここにいるからである。前者の経歴や知識背景をもつ人たちは,いつもどこか臨床でのどろどろした体験から離れたところに自分をおき,その中の具体のテーマに日々あくせくしている臨床看護師たちを,哲学に視座をおきながら冷ややかに見つめているかのような,独特の距離を感じてきたためかもしれない。
実際,360ページに及ぶ論考の末にすえられたテーマは,「農業としての看護へ」である。《土地を耕し,種をまき,水をやり,あとは自然の営みのなかで芽吹き成長するのを日々見守りながら待ち続ける,そのような遅々とした営み》が精神科看護だという。
それだったら,内省しなくても臨床の看護師たちは最初から自分たちの活動にはそうした素朴さをもっているではないか。だからこそ精神科急性期病棟のようなところにずっと身をおいていられるのだ。「なんだかまどろっこしい」という人もいるであろう。寄り道をして看護にきた人たちに感じる距離感は,彼らのこのような現実への向かい合い方による部分があるかもしれない。内省しつくさなければ素朴な向かい合いすらできないなんて,しんどすぎる。窮屈すぎる。そんなことばかりしていたら身動きがとれなくなる。看護はもっと本能的な営みなのではないか。
しかし,本当にそうなのだろうか。
◆素朴なだけでは自由になれない
松澤氏は《看護師の感情もその表出のあり方も,その目的に適うケアの一部として絶えずその妥当性や無危害性が問われなければならない》という。無自覚に,ただ素朴なだけでは他者に精神科看護の活動は理解されないのだ。確かにそうかもしれない。
「私は一生懸命やっているのだからわかるでしょう。わからないのはそっちが悪い」という論理を看護師にときどき見かけ,そして私は自分の活動に絶望しそうになるが,それでは議論もできない。他職種に向かって機能を主張することもできない。
私は看護の「理系」の研究者として,精神科看護を誰からも見える「形」にして正当に評価したいと願って活動してきた。こてこての「文系」の研究である本書とまったく作業のプロセスは異なるが,奇しくも同じ主張にたどりついている。無自覚であることと,自由であることは決定的に違う。自覚し,形にして初めて得られることもとても多いのだと思う。
良かった。意味もなく「文系」にコンプレックスをもち続けなくてもよさそうだ。
日ごろ何とも思わずに関わり,走り抜けている日々の出来事に,徹底的にこだわり,考察しつくす筆者の思索を通じて,精神科看護のあり方を,自分自身のあり方をふと立ち止まって見つめる豊かな時間を,この本と一緒にすごすのはきっと贅沢なことである。