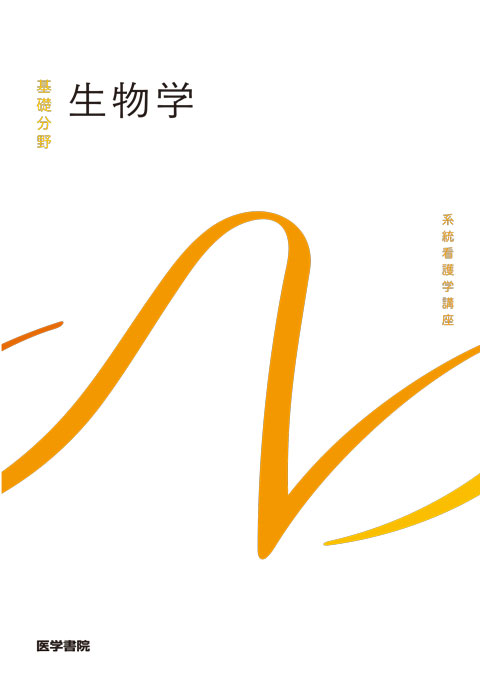生物学 第10版
もっと見る
- 生物の個体レベルから分子レベルまで、カラーの美しい図版により生物学への興味を引き出します。
- 写真を随所に配置し、視覚的にも興味をもたせられる紙面構成にしました。
- 学生のつまずきやすい代謝について、より学生が理解しやすい構成にしています。
- 分子生物学の進展に伴うトピックスも取り上げ、わかりやすく掲載しています。
- 生物の進化と種の多様性を、ストーリーをもたせた展開で説明をしています。
- 巻末資料として、生物学を学ぶにあたって必要となる物理・化学の基礎知識をまとめています。
- 「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 系統看護学講座-基礎分野 |
|---|---|
| 執筆 | 高畑 雅一 / 増田 隆一 / 北田 一博 |
| 発行 | 2019年02月判型:B5頁:356 |
| ISBN | 978-4-260-03189-9 |
| 定価 | 2,640円 (本体2,400円+税) |
- 2026年春改訂予定
- 改訂情報
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はしがき
科学の諸分野のなかで,生物学ほど研究の進展が速い分野はない。それは,生物学が包含する専門的な学問領域が,分子生物学から環境生物学にいたる広大なものであり,研究・解析のレベルも分子から細胞・個体を経て地球にいたる多くの階層から構成されるからである。それぞれの専門分野,解析レベルでの研究が日進月歩で進み,新たな発見が毎週のように報告されている。
もとより一般教育のための教科書がこれらにふりまわされる必要はない。むしろ教科書としては,生物学の基幹をなす古典的概念や考え方が新しい知見に対しても有効であることを検証し,これらを学ぶ者に伝えていかねばならない。もしも旧来の概念・考え方が否定され,それにかわるものが提唱されたときは,その根拠と展望を伝えていかねばならない。これまで不明であったことが明らかにされたのであれば,その研究手法的な背景も含めて伝えていかねばならない。学問分野が極度に細分化された今日,新たな知見を見すえながら生物学を1つの科目として教科書にまとめるには非常な困難があるが,まさにそれゆえにこそ,一般教育のための生物学教科書の使命には大切なものがあると考える。
今日,医療の現場と基礎的な生物学の知識・概念は,かつてないほどに近づいている。がんやエイズといった病気を理解するためにはもちろんのこと,再生医療や生殖医療といった先端的な医療を正しく理解してこれに携わるためには,高度の生物学的な訓練が必要となろう。それは,単に断片的な知識を集めればよいということではなく,生物学を体系的に学ぶ必要があるということでもある。
本書は看護学教育の基礎課程を対象とする教科書として,1969年発行の初版以来,生物学の進展を取り入れながら版を重ねてきた。第10版となる今回の改訂では,とくに進展の著しい分子遺伝学分野について,iPS細胞を用いた再生医療やゲノム編集に関するコラムを新たに加えて従来の記述を増強するとともに,環境生物学分野では新たに多数の写真を添えることで,読者の直感的な理解を促すよう工夫した。また生体エネルギー論や電気生理学に関する記述をできる限りわかりやすく書きあらため,予備知識なしでも理解できるよう,平易な表現を心がけた。
生物が示す形態や機能は,進化の過程でそれぞれの種の生息環境に適応して多様化してきた。ヒトの生命機能も例外ではない。進化は学問としての生物学の中心命題であり,生物学を生理学,生化学などその関連領域と区別する最大の特徴である。本書では,これまでの版での比較生物学的な方針を継承し,本書で学ぶ学生の皆さんが,ヒトを含む生命現象について,広く生物学的視野の中でその理解を深められるように配慮した。著者の意図がどこまで実現できているかは,本書で学び,また,本書で教えられる諸賢の判断にゆだねられる。ご批判,ご提言を頂くことを心から期待する所以である。
なお,本書で用いる学術用語は原則として『生物教育用語集』(日本動物学会/日本植物学会,東京大学出版会,1998年)に準拠,統一した。医学用語とは異なる学術用語については,適宜括弧内などに併記し,必要に応じて英語を示した。
2019年1月
著者一同
科学の諸分野のなかで,生物学ほど研究の進展が速い分野はない。それは,生物学が包含する専門的な学問領域が,分子生物学から環境生物学にいたる広大なものであり,研究・解析のレベルも分子から細胞・個体を経て地球にいたる多くの階層から構成されるからである。それぞれの専門分野,解析レベルでの研究が日進月歩で進み,新たな発見が毎週のように報告されている。
もとより一般教育のための教科書がこれらにふりまわされる必要はない。むしろ教科書としては,生物学の基幹をなす古典的概念や考え方が新しい知見に対しても有効であることを検証し,これらを学ぶ者に伝えていかねばならない。もしも旧来の概念・考え方が否定され,それにかわるものが提唱されたときは,その根拠と展望を伝えていかねばならない。これまで不明であったことが明らかにされたのであれば,その研究手法的な背景も含めて伝えていかねばならない。学問分野が極度に細分化された今日,新たな知見を見すえながら生物学を1つの科目として教科書にまとめるには非常な困難があるが,まさにそれゆえにこそ,一般教育のための生物学教科書の使命には大切なものがあると考える。
今日,医療の現場と基礎的な生物学の知識・概念は,かつてないほどに近づいている。がんやエイズといった病気を理解するためにはもちろんのこと,再生医療や生殖医療といった先端的な医療を正しく理解してこれに携わるためには,高度の生物学的な訓練が必要となろう。それは,単に断片的な知識を集めればよいということではなく,生物学を体系的に学ぶ必要があるということでもある。
本書は看護学教育の基礎課程を対象とする教科書として,1969年発行の初版以来,生物学の進展を取り入れながら版を重ねてきた。第10版となる今回の改訂では,とくに進展の著しい分子遺伝学分野について,iPS細胞を用いた再生医療やゲノム編集に関するコラムを新たに加えて従来の記述を増強するとともに,環境生物学分野では新たに多数の写真を添えることで,読者の直感的な理解を促すよう工夫した。また生体エネルギー論や電気生理学に関する記述をできる限りわかりやすく書きあらため,予備知識なしでも理解できるよう,平易な表現を心がけた。
生物が示す形態や機能は,進化の過程でそれぞれの種の生息環境に適応して多様化してきた。ヒトの生命機能も例外ではない。進化は学問としての生物学の中心命題であり,生物学を生理学,生化学などその関連領域と区別する最大の特徴である。本書では,これまでの版での比較生物学的な方針を継承し,本書で学ぶ学生の皆さんが,ヒトを含む生命現象について,広く生物学的視野の中でその理解を深められるように配慮した。著者の意図がどこまで実現できているかは,本書で学び,また,本書で教えられる諸賢の判断にゆだねられる。ご批判,ご提言を頂くことを心から期待する所以である。
なお,本書で用いる学術用語は原則として『生物教育用語集』(日本動物学会/日本植物学会,東京大学出版会,1998年)に準拠,統一した。医学用語とは異なる学術用語については,適宜括弧内などに併記し,必要に応じて英語を示した。
2019年1月
著者一同
目次
開く
序章 生物学を学ぶにあたって(高畑雅一)
A 生命観とその変遷
1 生物とはなにか,生命とはなにか
2 生命観の変遷
3 生物学と生命観
B 生命と生物学
1 生命の特徴
2 生物学と生命科学
C 看護・医学の基礎科学としての生物学
第1章 生命体のつくりとはたらき(高畑雅一)
A 生物学における構造と機能
1 生命現象の2つのとらえ方──形態学と生理学
2 生命現象研究のための技術
3 生命現象の研究方法
B 細胞とその構造
1 真核細胞と原核細胞
2 真核細胞の構造
C 細胞の化学成分
1 水
2 タンパク質
3 核酸
4 脂質
5 炭水化物(糖質)
6 無機塩類
D 細胞膜の輸送
1 細胞膜の透過性
2 受動輸送
3 能動輸送
4 エンドサイトーシスとエクソサイトーシス
5 オートファジー
E 細菌とウイルス
1 真正細菌と古細菌
2 ウイルス
第2章 生体維持のエネルギー(高畑雅一)
A 生体内の化学反応
1 自由エネルギーと化学反応
2 下り坂反応と上り坂反応との共役
3 エネルギーの変換とATP
4 酵素とそのはたらき
B ATPの生合成
1 光合成
2 解糖系──基質レベルのリン酸化
3 好気的過程──酸化的リン酸化
第3章 細胞の増殖とからだのなりたち(北田一博)
A 細胞分裂
1 真核生物の染色体とDNA
2 体細胞分裂
3 細胞分裂の周期
4 減数分裂
B 細胞の分化と個体のなりたち
1 単細胞生物から多細胞生物へ
2 組織と器官
C 細胞の老化
第4章 遺伝情報とその伝達・発現のしくみ(北田一博)
A 遺伝の法則と染色体
1 メンデルの法則
2 染色体と遺伝子
3 連鎖と乗換え
B 遺伝情報の担い手──DNA
1 核酸の発見
2 核酸の構造
3 DNAは遺伝物質である
4 DNAの二重らせん構造
C DNAの複製
1 ワトソンとクリックによるDNA複製モデル
2 酵素によるDNAの複製
3 DNA複製の分子機構
D 遺伝情報の伝達──RNA
1 遺伝情報の伝達の流れとRNAの役割
2 RNAの合成(転写)
E タンパク質の合成──翻訳
1 タンパク質の構成単位と構造
2 tRNA
3 リボソーム
4 遺伝暗号
5 タンパク質合成の過程
6 遺伝子発現の調節機構
F 遺伝子組換え技術とゲノムの構造解析法
1 DNAクローニング
2 ゲル電気泳動法とサザン-ハイブリダイゼーション
3 DNA塩基配列の解析法
G 変異
1 染色体変異
2 遺伝子変異
H ヒトの遺伝
1 ヒトの遺伝学
2 先天性異常
I 遺伝子組換えの応用
第5章 生殖と発生(高畑雅一)
A 無性生殖と有性生殖
1 無性生殖
2 有性生殖
B 動物の受精と発生
1 配偶子形成
2 受精
3 卵割から胞胚への発生
4 原腸胚と胚葉の形成
5 胚葉と器官の形成
6 動物の発生分化
C 哺乳類の発生
1 性ホルモン
2 性周期
3 精子の形成
4 胚発生
5 人工受精(人工授精)
第6章 個体の調節(高畑雅一)
A ホメオスタシス
1 負のフィードバックの例──体温調節の場合
2 産熱と放熱の生理機構
B 各器官系のはたらき
1 呼吸系──酸素の取り込みと二酸化炭素の排出
2 消化系──栄養物質と水の吸収
3 循環系──体液とその循環
4 免疫系──異物特異的反応と排除のしくみ
5 排出系──代謝老廃物の排出と浸透圧調節
C 神経性相関
1 自律神経系のはたらき
2 自律神経系の配置
D 液性相関
1 内分泌腺
2 ホルモンの作用
3 内分泌系とホルモン
4 その他のホルモン
E 無脊椎動物のホルモン
1 節足動物のホルモン
2 無脊椎動物の神経ペプチド
第7章 刺激の受容と行動(高畑雅一)
A 神経系における情報処理の特徴──電気信号
1 細胞間の情報伝達
2 興奮性細胞
3 膜電位
4 活動電位
5 生物電気現象の記録
B 環境の情報とその受容
1 受容器電位と感覚情報の伝達
2 刺激の種類と受容器
C 神経系の情報伝達
1 神経細胞(ニューロン)
2 活動電位の伝導
3 興奮の伝達
4 神経系の構成
D 神経系の系統的発達
1 神経節神経系
2 管状神経系
E 効果器のはたらき
1 細胞運動とそのしくみ
2 生物発光
F 行動
1 走性
2 本能行動
3 個体間の情報の伝達
4 学習
5 記憶
第8章 生命の進化と多様性(増田隆一)
A 化学進化と生命の起源
1 原始地球での低分子有機物の合成
2 原始地球での高分子有機物の合成
3 コアセルベートの形成と自己増殖能の出現
B 生物の多様化と絶滅の歴史
1 地質年代と生物の化石
2 先カンブリア代
3 古生代
4 中生代
5 新生代
C 生物の分類と系統
1 分類と命名
2 生物の3ドメインと6界説
3 植物界の系統関係
4 動物界の系統関係
D ヒトの起源と進化
1 霊長類の進化
2 ヒトの起源
3 ヒトの身体的変化
4 ホモ-サピエンスの単一起源説
5 日本人の起源
6 現生人類の進化
E 進化のしくみ
1 ダーウィン以前の進化論
2 ダーウィンの進化論とその後の論争
3 集団遺伝学に基づく進化の総合説
4 分子進化
5 現代の進化学
6 種が進化する要因
第9章 生物と環境のかかわり(増田隆一)
A 生物の集団
1 個体群とその成長
2 個体群密度の変動
3 個体間の関係
B 動物の社会
1 なわばり
2 社会階級
3 昆虫の社会
C 生態系の経済
1 生産者・消費者・分解者
2 生態ピラミッド・食物連鎖
3 生態系の生産力
4 生態系のエネルギーの流れ
D 生態系の物質循環
1 炭素の循環
2 窒素の循環
3 塩類の循環
第10章 地球環境とヒトとの共存(増田隆一)
A 人間活動による環境への影響
1 人口の増加と食糧問題
2 エネルギーの消費
3 消える森林と進行する砂漠化
4 大気汚染と酸性雨
5 地球温暖化
6 環境汚染物質と生物濃縮
B 生物多様性の保全
1 絶滅の危機にある動植物
2 遺伝的多様性の維持
3 外来種と環境問題
巻末資料 生命科学を学ぶための物理・化学の基礎知識(高畑雅一)
索引
A 生命観とその変遷
1 生物とはなにか,生命とはなにか
2 生命観の変遷
3 生物学と生命観
B 生命と生物学
1 生命の特徴
2 生物学と生命科学
C 看護・医学の基礎科学としての生物学
第1章 生命体のつくりとはたらき(高畑雅一)
A 生物学における構造と機能
1 生命現象の2つのとらえ方──形態学と生理学
2 生命現象研究のための技術
3 生命現象の研究方法
B 細胞とその構造
1 真核細胞と原核細胞
2 真核細胞の構造
C 細胞の化学成分
1 水
2 タンパク質
3 核酸
4 脂質
5 炭水化物(糖質)
6 無機塩類
D 細胞膜の輸送
1 細胞膜の透過性
2 受動輸送
3 能動輸送
4 エンドサイトーシスとエクソサイトーシス
5 オートファジー
E 細菌とウイルス
1 真正細菌と古細菌
2 ウイルス
第2章 生体維持のエネルギー(高畑雅一)
A 生体内の化学反応
1 自由エネルギーと化学反応
2 下り坂反応と上り坂反応との共役
3 エネルギーの変換とATP
4 酵素とそのはたらき
B ATPの生合成
1 光合成
2 解糖系──基質レベルのリン酸化
3 好気的過程──酸化的リン酸化
第3章 細胞の増殖とからだのなりたち(北田一博)
A 細胞分裂
1 真核生物の染色体とDNA
2 体細胞分裂
3 細胞分裂の周期
4 減数分裂
B 細胞の分化と個体のなりたち
1 単細胞生物から多細胞生物へ
2 組織と器官
C 細胞の老化
第4章 遺伝情報とその伝達・発現のしくみ(北田一博)
A 遺伝の法則と染色体
1 メンデルの法則
2 染色体と遺伝子
3 連鎖と乗換え
B 遺伝情報の担い手──DNA
1 核酸の発見
2 核酸の構造
3 DNAは遺伝物質である
4 DNAの二重らせん構造
C DNAの複製
1 ワトソンとクリックによるDNA複製モデル
2 酵素によるDNAの複製
3 DNA複製の分子機構
D 遺伝情報の伝達──RNA
1 遺伝情報の伝達の流れとRNAの役割
2 RNAの合成(転写)
E タンパク質の合成──翻訳
1 タンパク質の構成単位と構造
2 tRNA
3 リボソーム
4 遺伝暗号
5 タンパク質合成の過程
6 遺伝子発現の調節機構
F 遺伝子組換え技術とゲノムの構造解析法
1 DNAクローニング
2 ゲル電気泳動法とサザン-ハイブリダイゼーション
3 DNA塩基配列の解析法
G 変異
1 染色体変異
2 遺伝子変異
H ヒトの遺伝
1 ヒトの遺伝学
2 先天性異常
I 遺伝子組換えの応用
第5章 生殖と発生(高畑雅一)
A 無性生殖と有性生殖
1 無性生殖
2 有性生殖
B 動物の受精と発生
1 配偶子形成
2 受精
3 卵割から胞胚への発生
4 原腸胚と胚葉の形成
5 胚葉と器官の形成
6 動物の発生分化
C 哺乳類の発生
1 性ホルモン
2 性周期
3 精子の形成
4 胚発生
5 人工受精(人工授精)
第6章 個体の調節(高畑雅一)
A ホメオスタシス
1 負のフィードバックの例──体温調節の場合
2 産熱と放熱の生理機構
B 各器官系のはたらき
1 呼吸系──酸素の取り込みと二酸化炭素の排出
2 消化系──栄養物質と水の吸収
3 循環系──体液とその循環
4 免疫系──異物特異的反応と排除のしくみ
5 排出系──代謝老廃物の排出と浸透圧調節
C 神経性相関
1 自律神経系のはたらき
2 自律神経系の配置
D 液性相関
1 内分泌腺
2 ホルモンの作用
3 内分泌系とホルモン
4 その他のホルモン
E 無脊椎動物のホルモン
1 節足動物のホルモン
2 無脊椎動物の神経ペプチド
第7章 刺激の受容と行動(高畑雅一)
A 神経系における情報処理の特徴──電気信号
1 細胞間の情報伝達
2 興奮性細胞
3 膜電位
4 活動電位
5 生物電気現象の記録
B 環境の情報とその受容
1 受容器電位と感覚情報の伝達
2 刺激の種類と受容器
C 神経系の情報伝達
1 神経細胞(ニューロン)
2 活動電位の伝導
3 興奮の伝達
4 神経系の構成
D 神経系の系統的発達
1 神経節神経系
2 管状神経系
E 効果器のはたらき
1 細胞運動とそのしくみ
2 生物発光
F 行動
1 走性
2 本能行動
3 個体間の情報の伝達
4 学習
5 記憶
第8章 生命の進化と多様性(増田隆一)
A 化学進化と生命の起源
1 原始地球での低分子有機物の合成
2 原始地球での高分子有機物の合成
3 コアセルベートの形成と自己増殖能の出現
B 生物の多様化と絶滅の歴史
1 地質年代と生物の化石
2 先カンブリア代
3 古生代
4 中生代
5 新生代
C 生物の分類と系統
1 分類と命名
2 生物の3ドメインと6界説
3 植物界の系統関係
4 動物界の系統関係
D ヒトの起源と進化
1 霊長類の進化
2 ヒトの起源
3 ヒトの身体的変化
4 ホモ-サピエンスの単一起源説
5 日本人の起源
6 現生人類の進化
E 進化のしくみ
1 ダーウィン以前の進化論
2 ダーウィンの進化論とその後の論争
3 集団遺伝学に基づく進化の総合説
4 分子進化
5 現代の進化学
6 種が進化する要因
第9章 生物と環境のかかわり(増田隆一)
A 生物の集団
1 個体群とその成長
2 個体群密度の変動
3 個体間の関係
B 動物の社会
1 なわばり
2 社会階級
3 昆虫の社会
C 生態系の経済
1 生産者・消費者・分解者
2 生態ピラミッド・食物連鎖
3 生態系の生産力
4 生態系のエネルギーの流れ
D 生態系の物質循環
1 炭素の循環
2 窒素の循環
3 塩類の循環
第10章 地球環境とヒトとの共存(増田隆一)
A 人間活動による環境への影響
1 人口の増加と食糧問題
2 エネルギーの消費
3 消える森林と進行する砂漠化
4 大気汚染と酸性雨
5 地球温暖化
6 環境汚染物質と生物濃縮
B 生物多様性の保全
1 絶滅の危機にある動植物
2 遺伝的多様性の維持
3 外来種と環境問題
巻末資料 生命科学を学ぶための物理・化学の基礎知識(高畑雅一)
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。