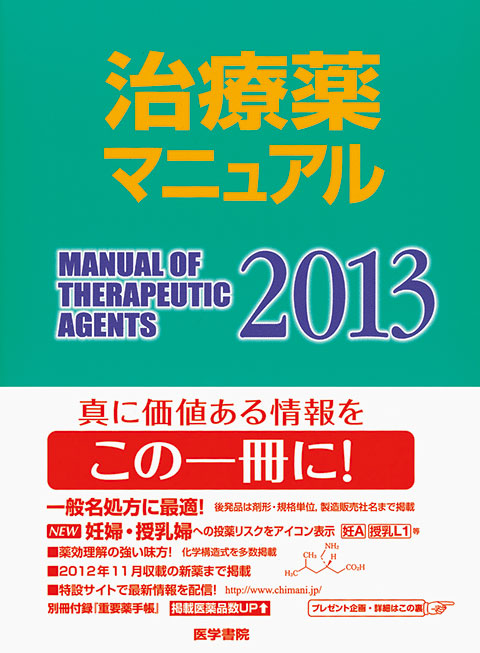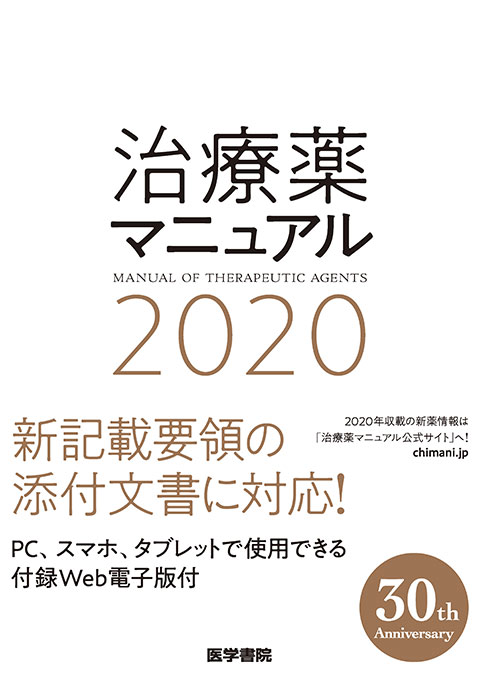治療薬マニュアル 2013
真に価値ある情報をこの一冊に!! 最も網羅性に優れた『治療薬年鑑』
もっと見る
本書の特徴 ■各領域の専門医による総論解説、最新の動向を各章に掲載 ■2,200成分、16,000品目の医薬品情報を約2,600頁に収録 ■使用目的や使用法、適応外使用など、臨床解説が充実 ■重要薬、重要処方情報をポケットサイズにまとめた別冊付録「重要薬手帳」
2013年版の特徴 【NEW!】 妊産婦・授乳婦への投薬リスクをアイコン表示! 【一般名処方に最適!】 後発品は剤形、規格単位、製造販売社まで掲載 【新薬情報】 2012年に薬価収載された新薬を収録
この書籍には最新版があります。詳しくは治療薬マニュアル特設サイトをご覧ください。
| 監修 | 高久 史麿 / 矢崎 義雄 |
|---|---|
| 編集 | 北原 光夫 / 上野 文昭 / 越前 宏俊 |
| 発行 | 2013年01月判型:B6頁:2724 |
| ISBN | 978-4-260-01677-3 |
| 定価 | 5,500円 (本体5,000円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
2013年版の序
24年前に「治療薬マニュアル」がはじめて出版されて,ほぼ四半世紀にならんとしている.当時の「治療薬マニュアル」の厚さに比較してみると,現在のマニュアルは2倍近い厚さへと拡大している.この厚さは次々とマーケットにあらわれた新しい抗腫瘍薬あるいは抗自己免疫疾患薬としての分子標的薬,経口糖尿病薬の追加,新抗凝固薬などを加えた情報量の多さによる.また,すでに十分利用されていることであるが,後発品全てについて,それらの商品名,製薬会社名,剤形,規格単位を網羅してある.この点は一般名処方を考慮している医療機関に対して,十分な役割を果たしていると思う.後発品がこのマニュアルにのっているので,他院からの患者がどのような後発薬を使用しているか知ることができ,誤投薬をさけることにも一翼を担っていると信じている.
さて「治療薬マニュアル2013」でも,新たな要素が加わっている.妊婦および授乳婦への投薬リスクをアイコン形式で掲載するようにした.胎児あるいは乳児への薬物リスクは常に頭を悩ませる問題である.妊婦への投薬リスクはオーストラリア医薬品評価委員会からのデータを利用している.また,授乳婦への投薬リスクはHaleによる「Medications and Mothers' Milk 2012」を参考にしている.ここにあげた2資料のデータは世界的に評価されており,わが国においても十分に利用できるものである.
本書はわが国で使われているほぼ全ての薬物を掲載しており,書籍形態によるだけでなく, 「今日の診療DVD-ROM・WEB版・イントラネット版」でも幅広く活用されている.これらのマニュアルの使用方法は利用者の仕事場,年齢などによって,異なるであろうが,各セクションの最初にかかげられたように薬物の特徴,あるいは主たる疾患に対する薬物の投与方法あるいは病態による薬物選択の違いなども配慮されており,利用しやすく工夫されている.
医療に携わる医師にとっては「今日の治療指針」との相互レファレンスにより,よりよい医療がおこなえると考える.また,教育制度の改正により,6年制となった薬学を志す学生諸君はもとより,現場で処方に関与する薬剤師の方々の要望には対応できていると自負している.
最後に,このマニュアルの進歩発展に尽力された執筆者の方々と医学書院編集担当諸氏に心より感謝したい.
2012年10月
北原光夫
24年前に「治療薬マニュアル」がはじめて出版されて,ほぼ四半世紀にならんとしている.当時の「治療薬マニュアル」の厚さに比較してみると,現在のマニュアルは2倍近い厚さへと拡大している.この厚さは次々とマーケットにあらわれた新しい抗腫瘍薬あるいは抗自己免疫疾患薬としての分子標的薬,経口糖尿病薬の追加,新抗凝固薬などを加えた情報量の多さによる.また,すでに十分利用されていることであるが,後発品全てについて,それらの商品名,製薬会社名,剤形,規格単位を網羅してある.この点は一般名処方を考慮している医療機関に対して,十分な役割を果たしていると思う.後発品がこのマニュアルにのっているので,他院からの患者がどのような後発薬を使用しているか知ることができ,誤投薬をさけることにも一翼を担っていると信じている.
さて「治療薬マニュアル2013」でも,新たな要素が加わっている.妊婦および授乳婦への投薬リスクをアイコン形式で掲載するようにした.胎児あるいは乳児への薬物リスクは常に頭を悩ませる問題である.妊婦への投薬リスクはオーストラリア医薬品評価委員会からのデータを利用している.また,授乳婦への投薬リスクはHaleによる「Medications and Mothers' Milk 2012」を参考にしている.ここにあげた2資料のデータは世界的に評価されており,わが国においても十分に利用できるものである.
本書はわが国で使われているほぼ全ての薬物を掲載しており,書籍形態によるだけでなく, 「今日の診療DVD-ROM・WEB版・イントラネット版」でも幅広く活用されている.これらのマニュアルの使用方法は利用者の仕事場,年齢などによって,異なるであろうが,各セクションの最初にかかげられたように薬物の特徴,あるいは主たる疾患に対する薬物の投与方法あるいは病態による薬物選択の違いなども配慮されており,利用しやすく工夫されている.
医療に携わる医師にとっては「今日の治療指針」との相互レファレンスにより,よりよい医療がおこなえると考える.また,教育制度の改正により,6年制となった薬学を志す学生諸君はもとより,現場で処方に関与する薬剤師の方々の要望には対応できていると自負している.
最後に,このマニュアルの進歩発展に尽力された執筆者の方々と医学書院編集担当諸氏に心より感謝したい.
2012年10月
北原光夫
目次
開く
薬物療法の基本的注意
図解 薬理作用
添付文書情報と臨床解説
01 解熱・鎮痛・抗炎症薬
02 片頭痛治療薬
03 抗リウマチ薬
04 痛風・高尿酸血症治療薬
05 催眠・鎮静薬
06 抗不安薬
07 抗精神病薬
08 抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬
09 抗てんかん薬
10 パーキンソン病/症候群治療薬
11 脳循環代謝改善薬
12 筋弛緩薬
13 自律神経系作用薬
14 抗めまい薬
15 その他の神経系用薬
16 強心薬
17 抗狭心症薬
18 β遮断薬
19 Ca拮抗薬
20 抗不整脈薬
21 利尿薬
22 降圧薬
23 末梢循環障害治療薬
24 脂質異常症用薬
25 昇圧薬
26 アレルギー治療薬
27 気管支拡張薬・喘息治療薬
28 鎮咳薬
29 去痰薬
30 その他の呼吸器用薬
31 消化性潰瘍治療薬
32 健胃・消化薬
33 下剤
34 止痢・整腸薬
35 その他の消化器用薬
36 糖尿病用薬
37 下垂体ホルモン製剤
38 副腎皮質ホルモン製剤
39 性ホルモン製剤
40 その他のホルモン製剤
41 子宮用薬
42 骨粗鬆症・骨代謝改善薬
43 ビタミン製剤
44 造血と血液凝固関係製剤
45 輸液・栄養製剤
46 電解質製剤
47 灌流用剤
48 解毒薬・中毒治療薬
49 抗菌薬
50 抗真菌薬
51 抗ウイルス薬
52 寄生虫・原虫用薬
53 抗癌剤
54 免疫抑制薬
55 眼科用薬
56 耳鼻咽喉科用薬
57 口腔用薬
58 泌尿・生殖器用薬
59 痔治療薬
60 皮膚用薬
61 酵素製剤
62 血液製剤類
63 ワクチン・トキソイド
64 麻薬
65 麻酔薬
66 生活改善薬
67 その他の治療薬
68 検査・診断用薬
69 造影剤
70 放射性医薬品
71 消毒剤
72 歯科用薬
73 漢方薬
新薬
付録
重大な有害反応(副作用)の症状と,原因となる代表的な医薬品
医療用医薬品添付文書および添付文書情報の見方
医薬品添付文書以外の重要な医薬品情報源とその見方
後発医薬品に関する情報と医薬品選択上の留意点
処方せんの書き方
錠剤・カプセルの粉砕・開封可否の基準
疾患別禁忌薬・注意薬一覧
血液製剤の使用指針(概要)
基本的薬物動態用語
薬物血中濃度モニタリング(TDM)の対象となる薬物とその有効・中毒濃度範囲
薬物と飲食物・嗜好品との相互作用
名称類似によるヒヤリ・ハット事例が報告されている薬剤一覧
薬剤の影響を受ける臨床検査一覧
投与期間の上限が設けられている医薬品
薬効分類番号一覧(4桁)
製薬企業の略称及び連絡先一覧
索引
図解 薬理作用
添付文書情報と臨床解説
01 解熱・鎮痛・抗炎症薬
02 片頭痛治療薬
03 抗リウマチ薬
04 痛風・高尿酸血症治療薬
05 催眠・鎮静薬
06 抗不安薬
07 抗精神病薬
08 抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬
09 抗てんかん薬
10 パーキンソン病/症候群治療薬
11 脳循環代謝改善薬
12 筋弛緩薬
13 自律神経系作用薬
14 抗めまい薬
15 その他の神経系用薬
16 強心薬
17 抗狭心症薬
18 β遮断薬
19 Ca拮抗薬
20 抗不整脈薬
21 利尿薬
22 降圧薬
23 末梢循環障害治療薬
24 脂質異常症用薬
25 昇圧薬
26 アレルギー治療薬
27 気管支拡張薬・喘息治療薬
28 鎮咳薬
29 去痰薬
30 その他の呼吸器用薬
31 消化性潰瘍治療薬
32 健胃・消化薬
33 下剤
34 止痢・整腸薬
35 その他の消化器用薬
36 糖尿病用薬
37 下垂体ホルモン製剤
38 副腎皮質ホルモン製剤
39 性ホルモン製剤
40 その他のホルモン製剤
41 子宮用薬
42 骨粗鬆症・骨代謝改善薬
43 ビタミン製剤
44 造血と血液凝固関係製剤
45 輸液・栄養製剤
46 電解質製剤
47 灌流用剤
48 解毒薬・中毒治療薬
49 抗菌薬
50 抗真菌薬
51 抗ウイルス薬
52 寄生虫・原虫用薬
53 抗癌剤
54 免疫抑制薬
55 眼科用薬
56 耳鼻咽喉科用薬
57 口腔用薬
58 泌尿・生殖器用薬
59 痔治療薬
60 皮膚用薬
61 酵素製剤
62 血液製剤類
63 ワクチン・トキソイド
64 麻薬
65 麻酔薬
66 生活改善薬
67 その他の治療薬
68 検査・診断用薬
69 造影剤
70 放射性医薬品
71 消毒剤
72 歯科用薬
73 漢方薬
新薬
付録
重大な有害反応(副作用)の症状と,原因となる代表的な医薬品
医療用医薬品添付文書および添付文書情報の見方
医薬品添付文書以外の重要な医薬品情報源とその見方
後発医薬品に関する情報と医薬品選択上の留意点
処方せんの書き方
錠剤・カプセルの粉砕・開封可否の基準
疾患別禁忌薬・注意薬一覧
血液製剤の使用指針(概要)
基本的薬物動態用語
薬物血中濃度モニタリング(TDM)の対象となる薬物とその有効・中毒濃度範囲
薬物と飲食物・嗜好品との相互作用
名称類似によるヒヤリ・ハット事例が報告されている薬剤一覧
薬剤の影響を受ける臨床検査一覧
投与期間の上限が設けられている医薬品
薬効分類番号一覧(4桁)
製薬企業の略称及び連絡先一覧
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。