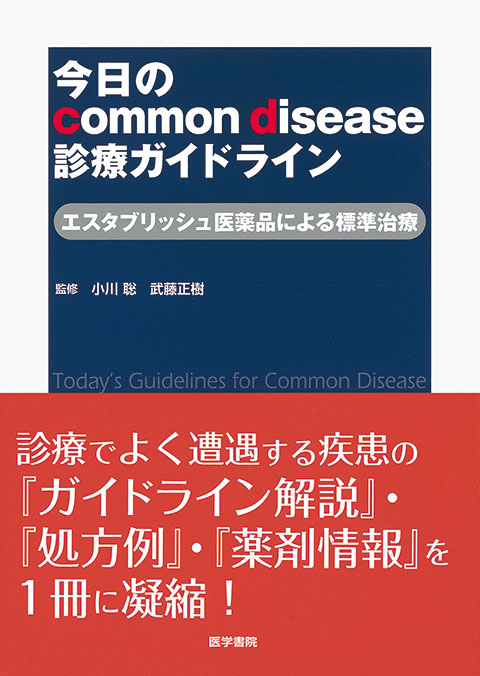今日の common disease 診療ガイドライン
エスタブリッシュ医薬品による標準治療
ガイドライン解説・処方例・薬剤情報を1冊に凝縮!
もっと見る
common disease59疾患の『ガイドライン解説』と『処方例』、処方薬の基本情報を『薬剤一覧』にまとめた、全医療従事者必携のクイック・リファレンスブック。各疾患解説中の「処方例」と巻末の「薬剤一覧」は、相互参照できるユニークな構成となっている。本書では、エビデンスに基づく診療ガイドラインに収載されるような標準的治療薬で、しかも費用対効果の優れた医薬品を「エスタブリッシュ医薬品」と位置づけ、それらの薬剤を中心にとりあげた。common disease情報のアップデートに、患者説明・服薬指導に、薬剤銘柄選択に…あらゆるシチュエーションにおいて、多忙な現場をサポートする1冊。
■疾患解説(59項目)
重要事項が把握しやすく、見やすいレイアウト
►各項目冒頭に[Point]・[診療チャート]を掲載
►随所に見出しとなるアイコンを配置
わかりやすい「処方例」
►商品名、剤形、用量・用法を具体的に記載
►単剤使用/他剤併用もできる限り明示
►登場薬剤に[薬剤一覧]での掲載ページを表示
►「処方のコツ」も適宜紹介
■薬剤一覧(約350成分)
「処方例」薬剤の基本情報をその場で確認可能
►一般名・代表的な商品名・禁忌・重大な副作用等のほか、薬価幅(最低~最高)も収載〔2012年度新薬価基準に準拠〕
►[薬剤一覧]の各薬剤に「処方例」掲載ページを表示
さらに詳しい紹介・サンプルページはこちら(GIF 445KB)
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
序
ここ20年ほどの間に,わが国においても,さまざまな疾患で診療ガイドラインの整備・普及が進んだ.これは適正かつ質の高い医療を広く提供するうえで大いに歓迎すべきことであろう.ただ,多忙な日々を送る医療関係者にとって,自身の専門領域のみならず,専門外のガイドラインの概要を把握しておくことは容易なことではない.そこで本書では,日常臨床でよく遭遇する59の日常疾患(common disease)を取り上げ,その診療ガイドラインと特にその薬物治療に重点を置き解説を試みた.日常診療に役立つよう,薬剤商品名による具体的な処方例も記載している.
ところでその薬物治療の際,われわれはどのようなことを念頭に置いて薬剤の選択を行うべきだろうか.さまざまな考え方があると思うが,診療ガイドラインの存在する疾患については,まず“診療ガイドラインに収載されている薬剤であること”が1つの基準となるだろう.また,少子高齢社会を迎えたわが国では,今後ますます医療財政が逼迫することが見込まれるため,“費用対効果に優れた薬剤であること”も薬剤選択の重要な要素であるといえる.特に,生活習慣病薬のように長期にわたって服用する医薬品には,患者自己負担の面からも経済性が考慮されなくてはならない.
このような観点から選ばれる医薬品を,最近では「エスタブリッシュ医薬品」と呼んでいる.つまり,エスタブリッシュ医薬品とは,エビデンスに基づく診療ガイドラインに収載されるような標準的治療薬で,しかも費用対効果の優れた医薬品のことである.ちなみに,「エスタブリッシュ」とは「確立した」という意味である.また,その多くは薬剤有効成分の特許期間が満了していて,特許期間中の新薬に比べて安価である.なお,わが国の処方薬の種類はおおよそ1万6千品目,その半分は特許期間がすでに満了した長期収載品や後発医薬品によって占められている.
さて本書では,こうしたエスタブリッシュ医薬品の臨床における普及を意識して,以下の工夫をした.まず各疾患の処方例に登場した薬剤の基本情報は,巻末の薬剤一覧にまとめて収載し,「後発医薬品の有無」および「同一有効成分をもつ薬剤の薬価幅(最低~最高)」についてもそれぞれ掲載した.これは読者諸氏に,薬剤の銘柄選択の際,各薬剤の経済性を意識していただくための工夫の一環でもある.
なお,本書は国際医療福祉大学グループの専門医が総力をあげて執筆した.企画趣旨を理解し,ご協力いただいた専門医の諸氏に,この場を借りて感謝したい.
本書が日常疾患の診断治療に日々携わる医師・薬剤師の皆さんや,外来で日常疾患の診断治療を学ぶ臨床研修医の皆さんなど,広く医療関係者のお役に立てば,執筆者一同の喜びとするところです.
2012年6月吉日
小川 聡
武藤正樹
ここ20年ほどの間に,わが国においても,さまざまな疾患で診療ガイドラインの整備・普及が進んだ.これは適正かつ質の高い医療を広く提供するうえで大いに歓迎すべきことであろう.ただ,多忙な日々を送る医療関係者にとって,自身の専門領域のみならず,専門外のガイドラインの概要を把握しておくことは容易なことではない.そこで本書では,日常臨床でよく遭遇する59の日常疾患(common disease)を取り上げ,その診療ガイドラインと特にその薬物治療に重点を置き解説を試みた.日常診療に役立つよう,薬剤商品名による具体的な処方例も記載している.
ところでその薬物治療の際,われわれはどのようなことを念頭に置いて薬剤の選択を行うべきだろうか.さまざまな考え方があると思うが,診療ガイドラインの存在する疾患については,まず“診療ガイドラインに収載されている薬剤であること”が1つの基準となるだろう.また,少子高齢社会を迎えたわが国では,今後ますます医療財政が逼迫することが見込まれるため,“費用対効果に優れた薬剤であること”も薬剤選択の重要な要素であるといえる.特に,生活習慣病薬のように長期にわたって服用する医薬品には,患者自己負担の面からも経済性が考慮されなくてはならない.
このような観点から選ばれる医薬品を,最近では「エスタブリッシュ医薬品」と呼んでいる.つまり,エスタブリッシュ医薬品とは,エビデンスに基づく診療ガイドラインに収載されるような標準的治療薬で,しかも費用対効果の優れた医薬品のことである.ちなみに,「エスタブリッシュ」とは「確立した」という意味である.また,その多くは薬剤有効成分の特許期間が満了していて,特許期間中の新薬に比べて安価である.なお,わが国の処方薬の種類はおおよそ1万6千品目,その半分は特許期間がすでに満了した長期収載品や後発医薬品によって占められている.
さて本書では,こうしたエスタブリッシュ医薬品の臨床における普及を意識して,以下の工夫をした.まず各疾患の処方例に登場した薬剤の基本情報は,巻末の薬剤一覧にまとめて収載し,「後発医薬品の有無」および「同一有効成分をもつ薬剤の薬価幅(最低~最高)」についてもそれぞれ掲載した.これは読者諸氏に,薬剤の銘柄選択の際,各薬剤の経済性を意識していただくための工夫の一環でもある.
なお,本書は国際医療福祉大学グループの専門医が総力をあげて執筆した.企画趣旨を理解し,ご協力いただいた専門医の諸氏に,この場を借りて感謝したい.
本書が日常疾患の診断治療に日々携わる医師・薬剤師の皆さんや,外来で日常疾患の診断治療を学ぶ臨床研修医の皆さんなど,広く医療関係者のお役に立てば,執筆者一同の喜びとするところです.
2012年6月吉日
小川 聡
武藤正樹
目次
開く
総論
1 診療ガイドラインの活用のポイント
2 エスタブリッシュ医薬品とは
3 処方せんの記載のありかた
各論
1章 呼吸器疾患
1 禁煙
2 インフルエンザ
3 小児上気道炎
4 市中肺炎
5 結核
6 気管支喘息
7 小児気管支喘息
8 COPD(慢性閉塞性肺疾患)
2章 循環器疾患
9 不整脈
10 高血圧
11 心筋梗塞
12 冠攣縮性狭心症
13 急性心不全
14 慢性心不全
15 弁膜症・感染性心内膜炎
16 肺塞栓症
17 大動脈瘤・大動脈解離
18 下肢閉塞性動脈硬化症
3章 消化器疾患
19 胃食道逆流症(GERD)
20 消化性潰瘍
21 過敏性腸症候群(IBS)
22 慢性肝炎
23 肝硬変
24 胆石症
25 急性膵炎
26 慢性膵炎
4章 血液・免疫疾患
27 鉄欠乏性貧血
28 関節リウマチ
5章 代謝・内分泌疾患
29 糖尿病
30 脂質異常症
31 痛風・高尿酸血症
32 甲状腺機能異常症
33 骨粗鬆症
6章 精神・神経疾患
34 認知症
35 気分障害
36 パニック障害
37 てんかん
38 脳卒中
39 パーキンソン病
40 頭痛
7章 腎・泌尿器・生殖器疾患
41 慢性腎臓病(CKD)
42 尿路結石
43 過活動膀胱(OAB)
44 男性下部尿路症状
45 尿失禁
46 夜間頻尿
47 性感染症(男性)
48 性感染症(女性)
8章 皮膚科疾患
49 アトピー性皮膚炎
50 接触皮膚炎
51 蕁麻疹
52 皮膚真菌症
53 ざ瘡
54 褥瘡
9章 感覚器疾患
55 アレルギー性結膜炎
56 急性鼻副鼻腔炎
57 アレルギー性鼻炎・花粉症
58 小児急性中耳炎
10章 緩和・疼痛
59 癌疼痛
薬剤一覧
解熱・鎮痛・抗炎症薬
片頭痛治療薬
抗リウマチ薬
痛風・高尿酸血症治療薬
精神科用薬
催眠・鎮静薬
抗不安薬
抗精神病薬
抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬
神経科用薬
抗てんかん薬
パーキンソン病/症候群治療薬
脳循環代謝改善薬
筋弛緩薬
自律神経系作用薬
その他の神経系用薬
循環器用薬
強心薬
抗狭心症薬
β遮断薬
Ca拮抗薬
抗不整脈薬
利尿薬
降圧薬
脂質異常症用薬
アレルギー治療薬
呼吸器用薬
気管支拡張薬・喘息治療薬
去痰薬
消化器用薬
消化性潰瘍治療薬
健胃・消化薬
下剤
止痢・整腸薬
その他の消化器用薬
糖尿病用薬
ホルモン製剤
下垂体ホルモン製剤
副腎皮質ホルモン製剤
その他のホルモン製剤
骨粗鬆症・骨代謝改善薬
ビタミン製剤
造血と血液凝固関係製剤
輸液・栄養製剤
電解質製剤
抗菌薬
化学療法剤
抗真菌薬
抗ウイルス薬
寄生虫・原虫用薬
免疫抑制薬
インターフェロン・インターロイキン製剤
眼科用薬
耳鼻咽喉科用薬
泌尿・生殖器用薬
皮膚用薬
生物学的製剤
麻薬
生活改善薬
漢方薬
索引
事項索引(欧文・和文)
薬剤索引
1 診療ガイドラインの活用のポイント
2 エスタブリッシュ医薬品とは
3 処方せんの記載のありかた
各論
1章 呼吸器疾患
1 禁煙
2 インフルエンザ
3 小児上気道炎
4 市中肺炎
5 結核
6 気管支喘息
7 小児気管支喘息
8 COPD(慢性閉塞性肺疾患)
2章 循環器疾患
9 不整脈
10 高血圧
11 心筋梗塞
12 冠攣縮性狭心症
13 急性心不全
14 慢性心不全
15 弁膜症・感染性心内膜炎
16 肺塞栓症
17 大動脈瘤・大動脈解離
18 下肢閉塞性動脈硬化症
3章 消化器疾患
19 胃食道逆流症(GERD)
20 消化性潰瘍
21 過敏性腸症候群(IBS)
22 慢性肝炎
23 肝硬変
24 胆石症
25 急性膵炎
26 慢性膵炎
4章 血液・免疫疾患
27 鉄欠乏性貧血
28 関節リウマチ
5章 代謝・内分泌疾患
29 糖尿病
30 脂質異常症
31 痛風・高尿酸血症
32 甲状腺機能異常症
33 骨粗鬆症
6章 精神・神経疾患
34 認知症
35 気分障害
36 パニック障害
37 てんかん
38 脳卒中
39 パーキンソン病
40 頭痛
7章 腎・泌尿器・生殖器疾患
41 慢性腎臓病(CKD)
42 尿路結石
43 過活動膀胱(OAB)
44 男性下部尿路症状
45 尿失禁
46 夜間頻尿
47 性感染症(男性)
48 性感染症(女性)
8章 皮膚科疾患
49 アトピー性皮膚炎
50 接触皮膚炎
51 蕁麻疹
52 皮膚真菌症
53 ざ瘡
54 褥瘡
9章 感覚器疾患
55 アレルギー性結膜炎
56 急性鼻副鼻腔炎
57 アレルギー性鼻炎・花粉症
58 小児急性中耳炎
10章 緩和・疼痛
59 癌疼痛
薬剤一覧
解熱・鎮痛・抗炎症薬
片頭痛治療薬
抗リウマチ薬
痛風・高尿酸血症治療薬
精神科用薬
催眠・鎮静薬
抗不安薬
抗精神病薬
抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬
神経科用薬
抗てんかん薬
パーキンソン病/症候群治療薬
脳循環代謝改善薬
筋弛緩薬
自律神経系作用薬
その他の神経系用薬
循環器用薬
強心薬
抗狭心症薬
β遮断薬
Ca拮抗薬
抗不整脈薬
利尿薬
降圧薬
脂質異常症用薬
アレルギー治療薬
呼吸器用薬
気管支拡張薬・喘息治療薬
去痰薬
消化器用薬
消化性潰瘍治療薬
健胃・消化薬
下剤
止痢・整腸薬
その他の消化器用薬
糖尿病用薬
ホルモン製剤
下垂体ホルモン製剤
副腎皮質ホルモン製剤
その他のホルモン製剤
骨粗鬆症・骨代謝改善薬
ビタミン製剤
造血と血液凝固関係製剤
輸液・栄養製剤
電解質製剤
抗菌薬
化学療法剤
抗真菌薬
抗ウイルス薬
寄生虫・原虫用薬
免疫抑制薬
インターフェロン・インターロイキン製剤
眼科用薬
耳鼻咽喉科用薬
泌尿・生殖器用薬
皮膚用薬
生物学的製剤
麻薬
生活改善薬
漢方薬
索引
事項索引(欧文・和文)
薬剤索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。