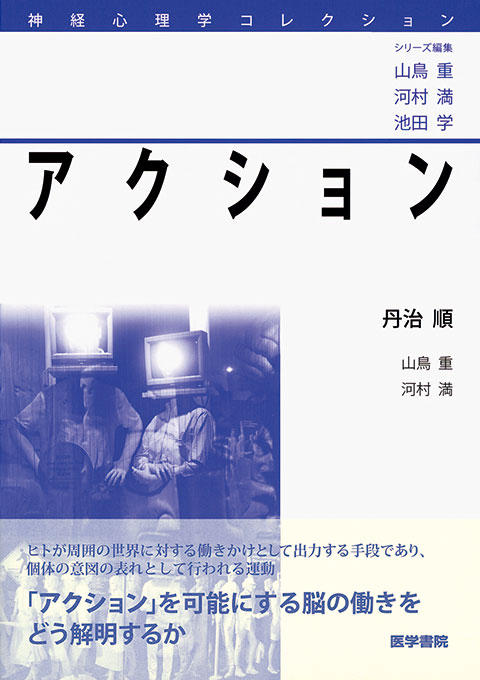アクション
「アクション」を可能にする脳の働きをどう解明するか
もっと見る
ヒトが周囲の世界に対する働きかけとして出力する手段であり、個体の意図の表れとして行われる運動である「アクション」。脳はそれをどのようにして実現しているのか。その解明に向け、大脳を文字通り縦横無尽に駆け巡るがごとく行われてきた実験・研究の成果から、アクションの大脳生理学的背景を探る。神経心理学の臨床家のサジェスチョンを受けつつ、大脳生理学研究の第一人者が行ったスリリングな講義を余すところなく収録。
*「神経心理学コレクション」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 神経心理学コレクション |
|---|---|
| 著 | 丹治 順 / 山鳥 重 / 河村 満 |
| シリーズ編集 | 山鳥 重 / 河村 満 / 池田 学 |
| 発行 | 2011年09月判型:A5頁:184 |
| ISBN | 978-4-260-01034-4 |
| 定価 | 3,740円 (本体3,400円+税) |
- 販売終了
- 電子版を購入( 医書.jp )
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
私達の人生において大切なものは数多くあるとはいっても,何よりも大切なことは何かをするということ,アクションではないでしょうか。生きているという実感は,身体を動かし,アクションをするときに生まれてきます。私達の存在意義,あるいはアイデンティティーを確かなものにすることができるのは,自己の表現以外にないならば,その手段としてのアクションの意味はとてつもなく大きいと言わざるを得ません。どんなに博学で知識にたけ,あるいは明晰な判断力と知謀に卓越していても,それらを表現し,世に表すことができなければ,せっかくの知の存在が埋もれたままに終わってしまうでしょう。
アクションの内容がいかに厖大であり,その実態がどれほど複雑多岐にわたるかは説明するまでもありませんが,常に移り変わる外界の条件や状況にしっかりと対応し,意味のある動作を行って意図した目的を果たすという,アクション本来のありようを考えるとき,それを可能にする脳の働きがいかにすぐれたものであるかについては,その奥の深さがはかり知れないとも思えてきます。しかしそのような脳の働きのメカニズムを解き明かすことは,人類に与えられた深遠な課題であり,知性に課されたきわめて魅力的なチャレンジでもあります。
アクションを可能にする脳の働きについて,脳科学はその解明に向けてどのようにメスを入れ,どこまで理解を進めているのでしょうか。そういう問題提起を基本に据えながら,本書では大脳皮質の運動関連領野の働きについて,大脳生理学研究者の観点から考察を進めていきます。
まず最初に,大脳の一次運動野の働きを考えてみます。手足や躯幹のどこを,どのように動かすかを決める主役が一次運動野であることは,損傷されたときの麻痺症状から明らかですし,一次運動野と脊髄や脳幹の解剖学的な関係についての詳細な知識の集積をもとに考えると,当然とも思われます。しかし,運動が実際に行われるときに,一次運動野を構成するどの種類の細胞が,どのように働いて,運動の時空間パターンを形成するのでしょうか。また,一次運動野の機能的な構成原理を考える基本となる,要素的な基本単位は何でしょうか。大脳の一次視覚野における機能円柱のような構造はあるのでしょうか。そのように問い始め,理解を深めようとすると,一次運動野の機能をもたらす仕組みがいかに複雑であるかが見えてきます。それとともに,まだ解っていないこと,これから明らかにするべき疑問点が多いことも明確になってきます。
次に高次運動野,つまり一次運動野以外の大脳運動野の働きを考えます。高次運動野は多数存在しますが,それぞれ細胞構築や脳に占める位地だけでなく,脳の中で形成される神経回路が異なっているので,一つひとつの領域の働きには特徴があると考えるのが自然です。むろん各領野の機能には共通部分があるとしても,そして複数の領野の共同作業によって初めて機能が達成される面はあっても,なおかつそれぞれの機能的な存在意義はあると考えざるを得ません。個々の高次運動野を特徴づける存在意義は何でしょうか。
大脳の外側にある高次運動野は運動前野です。ここでは,認知された感覚情報を活用して,意味のある動作をもたらすという働きが重要です。これまでの運動前野研究では,2つの概念が重要とされてきました。ひとつは感覚情報による動作の誘導,もうひとつは感覚情報と動作選択の連合ということです。まずはこれらについて,これまでの研究の成果をふまえて検討します。次にもうひとつの機能的側面,つまり抽象レベルでのアクションプランを,具体性をもった動作のプランに変換する過程を担う,運動前野の働きについて考察します。
一方,大脳の内側には,3領域の高次運動野が存在します。補足運動野,前補足運動野,帯状皮質運動野です。補足運動野と前補足運動野の働きを考えるとき,キーとなるのは,自発性ということと,脳内情報にもとづいた動作制御ということ,そして動作の時間的・時系列的制御ということです。むろん極論は禁物で,内側の高次運動野はそれ以外の働きもないわけではなく,例えば感覚情報にもとづいた動作制御にも参加はしますが,しかし特徴的で不可欠という観点からは,self-initiation(自己開始性),internalized action selection(脳内情報による動作選択),そしてtemporal coding(動作の時間制御)という制御の要点を担っている領域であることに間違いはないと言えます。他方,帯状皮質運動野は帯状溝の内部を占める広い領域で,その機能の本格的な研究はこれからと言えますが,その要点のひとつは,大脳辺縁系と高次運動野の接点として機能しているところにあると言えそうです。報酬情報による動作選択の切り替えなどはその機能の一端と言えるでしょう。
最後に,前頭前野が登場します。ここでは外側前頭前野に限定しますが,それでもなお前頭前野の働きは極めて多岐にわたります。従来の研究は認知情報の処理機構に焦点が合わされることが多かったのですが,前頭葉の要所を占める領域ですから,行動の統合的制御機構としての機能は枢要とみなされます。その観点から,前頭前野の機能動態を細胞レベルで検討することで,アクションの総括的な制御の様子を浮き彫りにすることを試みます。
聞き手の山鳥先生と河村先生には,随所に鋭い質問と興味深いコメントをいただきました。本質的な問題提起に,生理学者としての至らなさを新たな角度から認識させていただいたところもありましたが,適切なフィードバックと幅の広い話題の拡充をしていただいたおかげで,読者諸氏にも内容理解が深まるところが多かったと感ずる次第です。この場をお借りして,厚くお礼を申し上げます。
2011年8月
丹治 順
私達の人生において大切なものは数多くあるとはいっても,何よりも大切なことは何かをするということ,アクションではないでしょうか。生きているという実感は,身体を動かし,アクションをするときに生まれてきます。私達の存在意義,あるいはアイデンティティーを確かなものにすることができるのは,自己の表現以外にないならば,その手段としてのアクションの意味はとてつもなく大きいと言わざるを得ません。どんなに博学で知識にたけ,あるいは明晰な判断力と知謀に卓越していても,それらを表現し,世に表すことができなければ,せっかくの知の存在が埋もれたままに終わってしまうでしょう。
アクションの内容がいかに厖大であり,その実態がどれほど複雑多岐にわたるかは説明するまでもありませんが,常に移り変わる外界の条件や状況にしっかりと対応し,意味のある動作を行って意図した目的を果たすという,アクション本来のありようを考えるとき,それを可能にする脳の働きがいかにすぐれたものであるかについては,その奥の深さがはかり知れないとも思えてきます。しかしそのような脳の働きのメカニズムを解き明かすことは,人類に与えられた深遠な課題であり,知性に課されたきわめて魅力的なチャレンジでもあります。
アクションを可能にする脳の働きについて,脳科学はその解明に向けてどのようにメスを入れ,どこまで理解を進めているのでしょうか。そういう問題提起を基本に据えながら,本書では大脳皮質の運動関連領野の働きについて,大脳生理学研究者の観点から考察を進めていきます。
まず最初に,大脳の一次運動野の働きを考えてみます。手足や躯幹のどこを,どのように動かすかを決める主役が一次運動野であることは,損傷されたときの麻痺症状から明らかですし,一次運動野と脊髄や脳幹の解剖学的な関係についての詳細な知識の集積をもとに考えると,当然とも思われます。しかし,運動が実際に行われるときに,一次運動野を構成するどの種類の細胞が,どのように働いて,運動の時空間パターンを形成するのでしょうか。また,一次運動野の機能的な構成原理を考える基本となる,要素的な基本単位は何でしょうか。大脳の一次視覚野における機能円柱のような構造はあるのでしょうか。そのように問い始め,理解を深めようとすると,一次運動野の機能をもたらす仕組みがいかに複雑であるかが見えてきます。それとともに,まだ解っていないこと,これから明らかにするべき疑問点が多いことも明確になってきます。
次に高次運動野,つまり一次運動野以外の大脳運動野の働きを考えます。高次運動野は多数存在しますが,それぞれ細胞構築や脳に占める位地だけでなく,脳の中で形成される神経回路が異なっているので,一つひとつの領域の働きには特徴があると考えるのが自然です。むろん各領野の機能には共通部分があるとしても,そして複数の領野の共同作業によって初めて機能が達成される面はあっても,なおかつそれぞれの機能的な存在意義はあると考えざるを得ません。個々の高次運動野を特徴づける存在意義は何でしょうか。
大脳の外側にある高次運動野は運動前野です。ここでは,認知された感覚情報を活用して,意味のある動作をもたらすという働きが重要です。これまでの運動前野研究では,2つの概念が重要とされてきました。ひとつは感覚情報による動作の誘導,もうひとつは感覚情報と動作選択の連合ということです。まずはこれらについて,これまでの研究の成果をふまえて検討します。次にもうひとつの機能的側面,つまり抽象レベルでのアクションプランを,具体性をもった動作のプランに変換する過程を担う,運動前野の働きについて考察します。
一方,大脳の内側には,3領域の高次運動野が存在します。補足運動野,前補足運動野,帯状皮質運動野です。補足運動野と前補足運動野の働きを考えるとき,キーとなるのは,自発性ということと,脳内情報にもとづいた動作制御ということ,そして動作の時間的・時系列的制御ということです。むろん極論は禁物で,内側の高次運動野はそれ以外の働きもないわけではなく,例えば感覚情報にもとづいた動作制御にも参加はしますが,しかし特徴的で不可欠という観点からは,self-initiation(自己開始性),internalized action selection(脳内情報による動作選択),そしてtemporal coding(動作の時間制御)という制御の要点を担っている領域であることに間違いはないと言えます。他方,帯状皮質運動野は帯状溝の内部を占める広い領域で,その機能の本格的な研究はこれからと言えますが,その要点のひとつは,大脳辺縁系と高次運動野の接点として機能しているところにあると言えそうです。報酬情報による動作選択の切り替えなどはその機能の一端と言えるでしょう。
最後に,前頭前野が登場します。ここでは外側前頭前野に限定しますが,それでもなお前頭前野の働きは極めて多岐にわたります。従来の研究は認知情報の処理機構に焦点が合わされることが多かったのですが,前頭葉の要所を占める領域ですから,行動の統合的制御機構としての機能は枢要とみなされます。その観点から,前頭前野の機能動態を細胞レベルで検討することで,アクションの総括的な制御の様子を浮き彫りにすることを試みます。
聞き手の山鳥先生と河村先生には,随所に鋭い質問と興味深いコメントをいただきました。本質的な問題提起に,生理学者としての至らなさを新たな角度から認識させていただいたところもありましたが,適切なフィードバックと幅の広い話題の拡充をしていただいたおかげで,読者諸氏にも内容理解が深まるところが多かったと感ずる次第です。この場をお借りして,厚くお礼を申し上げます。
2011年8月
丹治 順
目次
開く
第1章 大脳皮質の一次運動野
1.大脳運動野研究の背景ときっかけ
2.一次運動野のつくりと働きを探る
3.運動野の機能単位
4.運動準備への関与
5.一次運動野と一次感覚野の関係
6.「アクション」という用語について
7.Penfieldの地図の意味
8.機能地図の可塑的な変化
第2章 高次運動野
1.高次運動野はどこに,いくつあるか
2.高次運動野の定義
第3章 運動前野
1.運動前野の二大機能
2.動作の空間的誘導
3.新たな機能仮説の紹介
4.ミラーニューロン仮説
5.視覚情報と動作情報の連合
6.抽象的な動作プランから具体的動作プランへの変換
7.運動前野の働きのまとめ
第4章 補足運動野と前補足運動野
1.大脳半球内側の高次運動野
2.左右の手の使い分け
3.Ecclesと二元論
4.補足運動野の機能仮説
5.複数動作の順序制御
6.前補足運動野の特性
7.動作の時間制御への関与
8.細胞活動による時間表現
9.補足運動野の機能脱落
10.失行との関係性
第5章 帯状皮質運動野
1.帯状皮質運動野はどこにある
2.帯状皮質運動野と脳の回路
3.帯状皮質運動野の使われ方
4.報酬情報に依拠した動作選択
5.帯状皮質運動野機能の別の側面
6.系統発生という視点からの考察
7.細胞活動の意味を考察する
8.体性局在について
9.前頭眼野と補足眼野
第6章 前頭前野
1.前頭前野の働きを概説する
2.working memory仮説
3.行動の抑制
4.行動の制御系としての前頭前野の働き
5.行動のカテゴリー化
6.行動の先読み
7.未来を予測し,イメージする能力
8.前頭前野の面白さ
索引
1.大脳運動野研究の背景ときっかけ
2.一次運動野のつくりと働きを探る
3.運動野の機能単位
4.運動準備への関与
5.一次運動野と一次感覚野の関係
6.「アクション」という用語について
7.Penfieldの地図の意味
8.機能地図の可塑的な変化
第2章 高次運動野
1.高次運動野はどこに,いくつあるか
2.高次運動野の定義
第3章 運動前野
1.運動前野の二大機能
2.動作の空間的誘導
3.新たな機能仮説の紹介
4.ミラーニューロン仮説
5.視覚情報と動作情報の連合
6.抽象的な動作プランから具体的動作プランへの変換
7.運動前野の働きのまとめ
第4章 補足運動野と前補足運動野
1.大脳半球内側の高次運動野
2.左右の手の使い分け
3.Ecclesと二元論
4.補足運動野の機能仮説
5.複数動作の順序制御
6.前補足運動野の特性
7.動作の時間制御への関与
8.細胞活動による時間表現
9.補足運動野の機能脱落
10.失行との関係性
第5章 帯状皮質運動野
1.帯状皮質運動野はどこにある
2.帯状皮質運動野と脳の回路
3.帯状皮質運動野の使われ方
4.報酬情報に依拠した動作選択
5.帯状皮質運動野機能の別の側面
6.系統発生という視点からの考察
7.細胞活動の意味を考察する
8.体性局在について
9.前頭眼野と補足眼野
第6章 前頭前野
1.前頭前野の働きを概説する
2.working memory仮説
3.行動の抑制
4.行動の制御系としての前頭前野の働き
5.行動のカテゴリー化
6.行動の先読み
7.未来を予測し,イメージする能力
8.前頭前野の面白さ
索引
書評
開く
心とつながる意図的運動の機序を科学的データに基づいて解明
書評者: 糸山 泰人 (国立精神・神経医療研究センター病院院長)
私は神経内科の臨床医であるが,幸いなことに世界的な神経生理学者の丹治順先生とNIHから東北大学時代にわたり長いお付き合いをさせていただいている。それは共同研究というよりもむしろアフター5のスコッチのグラスを交わしながらのお付き合いで,私の勝手な神経学の疑問を先生に投げかけ,それに対して世界的神経生理学者のお答えを聞けるという誠にぜいたくなものである。その丹治先生から,私の退官時に重要な宿題ともいうべき議論のテーマをいただいた。それは「上位運動ニューロンなるものとは何か,そのようなものは存在しない」というショッキングなものであった。実際のところ大脳運動野の細胞のほとんどは脊髄運動神経細胞以外の細胞に出力を送っていて,脊髄運動神経細胞に対して直接出力を送っているのは極めて限られていることが知られている。私ども神経内科医が何の疑問もなく用いている下位運動ニューロンに対する「上位運動ニューロン」の概念に根本的な問題を突き付けられたわけである。この問題提起というか警告は極めて重要なものであり,本書『アクション』を世に出す動機,すなわち心とつながる意図的運動(アクション)の機序解明と深くかかわっている。
この『アクション』を読んで感銘を受けたことは多々あるが,中でも「心とつながる意図的運動の機序の解明」を理論や推論で解説するのではなく,丹治先生自らが企画したサルを用いての決して容易ではない実験系を介して得たデータを基に論理を展開されていることにある。内なる心というものから外界に働きかける合目的アクションに至る過程が科学的データに基づいて明解に示されていることに感心するとともに感動を覚える。
本書『アクション』は運動総体の神経機構の総論に始まり,一次運動野から各高次運動野の機能分担が述べられている。私ども臨床医にとっては一次運動野はPenfield WGによるホムンクルスの体性局在マッピング,muscle representationのイメージの影響が根強くあるが,むしろ今はmovement representationの考え方で研究が進んでいることを知らされた。また,一次運動野におけるほとんどの細胞は上位運動ニューロンとしての脊髄運動ニューロンには出力を送っておらず,むしろ多くは橋を介して小脳へ,また視床や線条体,それに体性感覚野や高次運動野へ出力を送り,未知なるネットワーク形成に使われていることに驚かされる。
高次運動野とはそこを刺激すると運動が誘発され,かつ一次運動野に出力を送る領域である。それらは心に近い前頭前野から運動前野および補足運動野,前補足運動野それに帯状皮質運動野であり,おのおのの高次運動野の関与と調節を得て最終的に一次運動野にてアクションの指令がなされている。
運動前野においては,大きく分けて二つの運動に関するプロセスが働いている。それらは,認知された感覚情報を活用して意味のある動作をもたらすプロセス,それに加えて抽象レベルでのアクションプランを具体性を持った動作のプランに変換するプロセスである。
また,補足運動野においては左右の運動の協調的な側面を考えさせる多くの知見が実験データを示しながら解説されている。さらに,前頭前野においては時間的な関係が加わることも示されているが,個々の貴重なデータと論理の展開,それらの解説はぜひ本書をお読みいただきたい。
本書に書かれている一次運動野や高次運動野に関する最新の知見や論理は臨床医にとって多くの重要な情報を与えてくれる。本書を読むにつけ私ども神経内科医は今まで運動を上位ニューロン,下位ニューロンというレベルで思考停止してきたのではないかと大いに反省させられる。いずれにしろ本書は脳の中における心というものの存在,そしてそこから発する運動のアクションというものへのつながりを科学的データに基づいて解説した本であり,実に多くを勉強させていただいた。神経内科,脳神経外科およびリハビリテーションなど神経にかかわる方々には,ぜひともこの本を一読されることをお勧めする。
最後にこのシリーズの企画者でもあり,本書の共著者でもある山鳥重先生および河村満先生の深い知識に感心するとともにお二人と丹治先生との鼎談〈ていだん〉がこの『アクション』の内容を深めたことに敬意を表したい。
“アクション”の作動原理を解き明かす前頭葉レビューの傑作
書評者: 高田 昌彦 (京大霊長類研究所教授)
本書を初めて手にし,いつものようにまず「序」に目を通した。残りは時間のあるときにと思っていたが,まるで評判の推理小説を読むかのように,そのまま時間を忘れて一気に読み切ってしまった。
私は著者の丹治順先生と以前から懇意であり,また,著者と著者の研究グループが長年にわたって展開してきたさまざまな大脳研究の中身をかなりよく知っている一人ではあるが,あらためて読み進めてみると,本書はまさに40年以上におよぶ大脳生理学者としての著者自身のヒストリーがつづられた“読み物”であった。最も驚くべきは,この“読み物”のシナリオ全体がほとんど著者自身の研究のみで描かれていることである。
本書では,“アクション”をヒトが周囲の世界に対する働きかけとして出力する手段であり,個体の意図の表れとして行われる運動であると定義しており,まず大脳前頭葉に分布する運動関連領野の概念にアップデートを迫るところから始まる。そこには,基本的な共通理解を確立することで,現存する教科書や入門書には系統的な解説がないという状況を変えたいという著者の強い願いが込められている。さらに,現在一般的に広まっている知識には誤りと理解不足が多いという問題点を明確にすることに力点を置いている。このため,一次運動野に始まり,運動前野,補足運動野などの高次運動野,そして前頭前野に至るまで,サルを使った神経生理学の研究成果を提供し,それぞれの機能について考察を進めるという形をとっている。特に,最後に登場する前頭前野については,その機能を行動の統合的司令塔として捉えており,これこそ著者の前頭葉研究を総括する考え方である。本書を通して,著者は“アクション”を可能にする大脳の働きを明快に説明するとともに,未解明の事象に関する本質的な問題提起を行い,さらに今後の前頭葉研究に関する的確な指針を与えている。
昨今の脳神経科学の研究分野は,数多の研究者による実験データが氾濫しており,情報のアップデートを頻繁に行う必要がある反面,脳の構成原則や作動原理に迫るような確かな情報を選び出すことが極めて厄介(しかし重要)な作業になっている。優れた教科書がない(特に日本語では)状況で,著者のように高い見識を持った大脳生理学者が体系的な知識と学問の正しい方向性を提示した本書が,とりわけ若手研究者にとって貴重なバイブルとなることに疑いの余地はない。
本書は,著者(先生)と,聞き手(生徒)であり神経内科学の権威でもある山鳥重先生,河村満先生との軽快なやりとりで構成されており,随所に両先生からの鋭い突っ込みや臨床から見た興味深いコメントと,それらに対する著者の適切なレスポンスが絶妙の間合いとなっているので大変読みやすい。このような構成によって,単なる研究内容の解説にとどまらず,複眼的な視点が常に示されており,読者一人一人が主体的に理解を進めることができる。また,脳神経科学の基礎および臨床研究に携わっている人たちだけでなく,さまざまな臨床医学,看護やリハビリテーションなどのコメディカルに従事している人たち,さらには人文社会科学系の研究者までをも対象として,意識的に平易な語調でまとめられている。
本書のおかげで,このように幅広い読者層を横断して,“アクション”の担い手としての大脳前頭葉の役割に関する理解が格段に深まるであろう。本書は,“アクション”の作動原理を解き明かす前頭葉レビューの傑作である。
書評者: 糸山 泰人 (国立精神・神経医療研究センター病院院長)
私は神経内科の臨床医であるが,幸いなことに世界的な神経生理学者の丹治順先生とNIHから東北大学時代にわたり長いお付き合いをさせていただいている。それは共同研究というよりもむしろアフター5のスコッチのグラスを交わしながらのお付き合いで,私の勝手な神経学の疑問を先生に投げかけ,それに対して世界的神経生理学者のお答えを聞けるという誠にぜいたくなものである。その丹治先生から,私の退官時に重要な宿題ともいうべき議論のテーマをいただいた。それは「上位運動ニューロンなるものとは何か,そのようなものは存在しない」というショッキングなものであった。実際のところ大脳運動野の細胞のほとんどは脊髄運動神経細胞以外の細胞に出力を送っていて,脊髄運動神経細胞に対して直接出力を送っているのは極めて限られていることが知られている。私ども神経内科医が何の疑問もなく用いている下位運動ニューロンに対する「上位運動ニューロン」の概念に根本的な問題を突き付けられたわけである。この問題提起というか警告は極めて重要なものであり,本書『アクション』を世に出す動機,すなわち心とつながる意図的運動(アクション)の機序解明と深くかかわっている。
この『アクション』を読んで感銘を受けたことは多々あるが,中でも「心とつながる意図的運動の機序の解明」を理論や推論で解説するのではなく,丹治先生自らが企画したサルを用いての決して容易ではない実験系を介して得たデータを基に論理を展開されていることにある。内なる心というものから外界に働きかける合目的アクションに至る過程が科学的データに基づいて明解に示されていることに感心するとともに感動を覚える。
本書『アクション』は運動総体の神経機構の総論に始まり,一次運動野から各高次運動野の機能分担が述べられている。私ども臨床医にとっては一次運動野はPenfield WGによるホムンクルスの体性局在マッピング,muscle representationのイメージの影響が根強くあるが,むしろ今はmovement representationの考え方で研究が進んでいることを知らされた。また,一次運動野におけるほとんどの細胞は上位運動ニューロンとしての脊髄運動ニューロンには出力を送っておらず,むしろ多くは橋を介して小脳へ,また視床や線条体,それに体性感覚野や高次運動野へ出力を送り,未知なるネットワーク形成に使われていることに驚かされる。
高次運動野とはそこを刺激すると運動が誘発され,かつ一次運動野に出力を送る領域である。それらは心に近い前頭前野から運動前野および補足運動野,前補足運動野それに帯状皮質運動野であり,おのおのの高次運動野の関与と調節を得て最終的に一次運動野にてアクションの指令がなされている。
運動前野においては,大きく分けて二つの運動に関するプロセスが働いている。それらは,認知された感覚情報を活用して意味のある動作をもたらすプロセス,それに加えて抽象レベルでのアクションプランを具体性を持った動作のプランに変換するプロセスである。
また,補足運動野においては左右の運動の協調的な側面を考えさせる多くの知見が実験データを示しながら解説されている。さらに,前頭前野においては時間的な関係が加わることも示されているが,個々の貴重なデータと論理の展開,それらの解説はぜひ本書をお読みいただきたい。
本書に書かれている一次運動野や高次運動野に関する最新の知見や論理は臨床医にとって多くの重要な情報を与えてくれる。本書を読むにつけ私ども神経内科医は今まで運動を上位ニューロン,下位ニューロンというレベルで思考停止してきたのではないかと大いに反省させられる。いずれにしろ本書は脳の中における心というものの存在,そしてそこから発する運動のアクションというものへのつながりを科学的データに基づいて解説した本であり,実に多くを勉強させていただいた。神経内科,脳神経外科およびリハビリテーションなど神経にかかわる方々には,ぜひともこの本を一読されることをお勧めする。
最後にこのシリーズの企画者でもあり,本書の共著者でもある山鳥重先生および河村満先生の深い知識に感心するとともにお二人と丹治先生との鼎談〈ていだん〉がこの『アクション』の内容を深めたことに敬意を表したい。
“アクション”の作動原理を解き明かす前頭葉レビューの傑作
書評者: 高田 昌彦 (京大霊長類研究所教授)
本書を初めて手にし,いつものようにまず「序」に目を通した。残りは時間のあるときにと思っていたが,まるで評判の推理小説を読むかのように,そのまま時間を忘れて一気に読み切ってしまった。
私は著者の丹治順先生と以前から懇意であり,また,著者と著者の研究グループが長年にわたって展開してきたさまざまな大脳研究の中身をかなりよく知っている一人ではあるが,あらためて読み進めてみると,本書はまさに40年以上におよぶ大脳生理学者としての著者自身のヒストリーがつづられた“読み物”であった。最も驚くべきは,この“読み物”のシナリオ全体がほとんど著者自身の研究のみで描かれていることである。
本書では,“アクション”をヒトが周囲の世界に対する働きかけとして出力する手段であり,個体の意図の表れとして行われる運動であると定義しており,まず大脳前頭葉に分布する運動関連領野の概念にアップデートを迫るところから始まる。そこには,基本的な共通理解を確立することで,現存する教科書や入門書には系統的な解説がないという状況を変えたいという著者の強い願いが込められている。さらに,現在一般的に広まっている知識には誤りと理解不足が多いという問題点を明確にすることに力点を置いている。このため,一次運動野に始まり,運動前野,補足運動野などの高次運動野,そして前頭前野に至るまで,サルを使った神経生理学の研究成果を提供し,それぞれの機能について考察を進めるという形をとっている。特に,最後に登場する前頭前野については,その機能を行動の統合的司令塔として捉えており,これこそ著者の前頭葉研究を総括する考え方である。本書を通して,著者は“アクション”を可能にする大脳の働きを明快に説明するとともに,未解明の事象に関する本質的な問題提起を行い,さらに今後の前頭葉研究に関する的確な指針を与えている。
昨今の脳神経科学の研究分野は,数多の研究者による実験データが氾濫しており,情報のアップデートを頻繁に行う必要がある反面,脳の構成原則や作動原理に迫るような確かな情報を選び出すことが極めて厄介(しかし重要)な作業になっている。優れた教科書がない(特に日本語では)状況で,著者のように高い見識を持った大脳生理学者が体系的な知識と学問の正しい方向性を提示した本書が,とりわけ若手研究者にとって貴重なバイブルとなることに疑いの余地はない。
本書は,著者(先生)と,聞き手(生徒)であり神経内科学の権威でもある山鳥重先生,河村満先生との軽快なやりとりで構成されており,随所に両先生からの鋭い突っ込みや臨床から見た興味深いコメントと,それらに対する著者の適切なレスポンスが絶妙の間合いとなっているので大変読みやすい。このような構成によって,単なる研究内容の解説にとどまらず,複眼的な視点が常に示されており,読者一人一人が主体的に理解を進めることができる。また,脳神経科学の基礎および臨床研究に携わっている人たちだけでなく,さまざまな臨床医学,看護やリハビリテーションなどのコメディカルに従事している人たち,さらには人文社会科学系の研究者までをも対象として,意識的に平易な語調でまとめられている。
本書のおかげで,このように幅広い読者層を横断して,“アクション”の担い手としての大脳前頭葉の役割に関する理解が格段に深まるであろう。本書は,“アクション”の作動原理を解き明かす前頭葉レビューの傑作である。