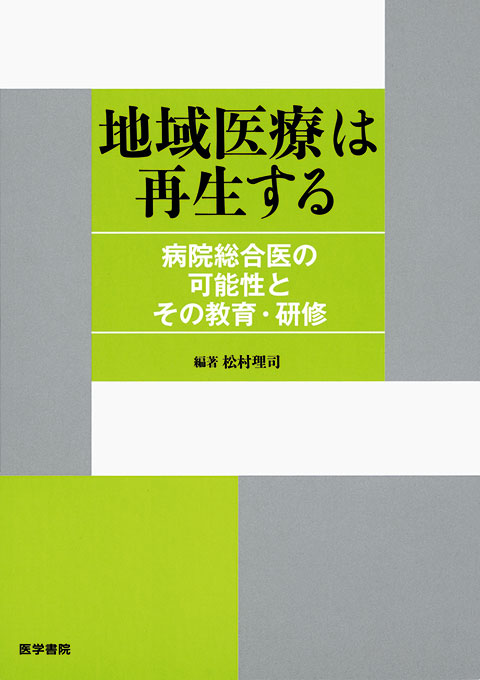地域医療は再生する
病院総合医の可能性とその教育・研修
力量のある病院総合医が地域医療を救う!
もっと見る
多くの勤務医が専門医である日本の病院は、常に「非互換性の無駄」が付きまとう。また国民に対して「断らない救急医療」を質高く恒常的に展開することも難しい。しかしながら間口が広いだけでは、一人前の総合医ではない。当然、奥行きが必要なのである。地域医療崩壊の危機を前に、期待されるべき病院総合医の可能性と彼らの育成について、大リーガー医でも知られる音羽病院ほかの実践を詳述。
| 編著 | 松村 理司 |
|---|---|
| 発行 | 2010年06月判型:A5頁:304 |
| ISBN | 978-4-260-01054-2 |
| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
日本の医療にも光と影があるが,近年は綻びばかりが照射される.「医療崩壊」という言葉もすっかり耳に馴染むようになったが,開業医・診療所は比較的無傷なので,「病院崩壊」という言葉を使うほうが実相に近い.その最大の理由は,勤務医が病院から撤退するからである.2004年春の新医師臨床研修制度の開始に備えて,あちこちの地域病院への勤務医の派遣中止やそこからの引き揚げが大学医局によって行われたが,これが確かに悪さした.直撃を受けた中小病院もある.しかし,理由はそれだけではない.勤務医が疲労困憊したあげくに,「地域医療に邁進しよう」といった気概もあまりなく,開業してゆく傾向が目立つようになったのだ.これは『立ち去り型サボタージュ』という業界用語を生み,広く社会に知られるようになった.
こういう事態を背景に,医学生定員増が国策として打ち出され,2009年度から若干増(約700人)として開始された.医師事務作業補助体制への診療報酬上での配慮が,少しは払われるようになった.医師・病院バッシングが常態化していたメディア報道にも,偏向の少ない地道な記事が散見されるようになった.開業医にもっと活躍してもらおうとする案もある.勤務医は入院患者の診療や手術に特化し,外来患者や一次の救急患者をもっと多く開業医に振ろうとする厚生労働省の構想である.「総合医としての開業医」を拡大させる路線である.良質の家庭医を養成する専門医制度が構築されつつある現状だが,大きく結実すれば相当に強固な解決策の1つになるだろう.しかしこれらの策の中には,効果が出るまでに時間のかかるものも多い.
病院内を見渡すと,別の解決策があるように思われる.日本の勤務医のほとんどは専門医とその卵だが,力量のある病院総合医(ホスピタリスト)を大量育成するのである.そして,専門医はもっと「専門」に従事してもらい,その代わりに「非専門」を病院総合医に任せるわけである.「専門性の希釈」とでもいうべき事態は,できるだけ回避したい.例えば日替わりメニューで専門医が救急当直をし,一次救急に駆り出され,ふだん経験しない「非専門」に四苦八苦する愚は,そろそろ避けたいものである.こういう「各診療科(各当直医)相乗り型救急」を墨守するのではなく,病院の一次救急を,ER型救急専属医や彼・彼女らと連携する総合診療医にできるだけ任せるのである.こういった「病院における総合医と専門医の握手」は,少し違った角度から眺めることもできる.専門医の仕事は,各診療科間の取り替えがきかない.つまり,互換性がない.内科系専門医たちは,手が空いていても,手術の助手になれない.外科系専門医たちは,手術のキャンセルで暇ができても,忙しい内科系外来を手伝えない.いやそれどころではない.日本の平均的な地域病院での慢性患者外来は,それほど専門特化していないものもあるはずなのに,内科系諸科間での外来業務の互換性が想像すらされていない.開業すれば,たちまちにこういった患者群のかかりつけ医になることも往々あるはずなのにである.病院総合医の大量育成は,この現状に楔を打つ試みといえよう.
私が勤める洛和会音羽病院は588床のケアミックスの病院であり,一般病床428床(ICU/CCU 12床を含む),医療療養型病床50床,回復期リハビリテーション病床50床,認知症病床60床からなっている.総合診療科は34診療科の中で最大の診療科であり,年間入院患者数も約1,100名と最多である.同科入院患者の約75%がERからであり,それはER全体からみると約25%にあたる.所長(副院長兼務)1名,部長1名,医長3名,医員11名,後期研修医12名の所帯だが,枠外の存在である医学教育センター所長(副院長兼務)や院長の私も,たまたま総合診療出身である.
院内最大勢力の総合診療科は,さまざまな「雑務」をこなさざるをえない.「出前」とも称しており,「院内出前」と「院外出前」に分けられる.「院内出前」の最大のものは,8名の救急専属医(後期研修医2名を含む)と連携したうえでのER型救急医療現場への主体的関与である.当院は「救急を断らない民間病院」として最近何度かメディアにも取り上げられたが,年間救急搬送依頼約5,000件に対する応需率は99.9%ときわめて高い.「院外出前」の最大のものは,内科系医師の絶対的欠乏に悩む当院の姉妹病院(洛和会丸太町病院,170床)への継続的複数(6~7名)医師派遣であった.総合医は,本来「非特異的」に患者を診察・治療する(つまり,“What can I do for you?”「何がお困りですか?」と,どんな患者のどんな症状・病態・病気にも対応する)ものだが,以上の多岐にわたる活動を「雑務」と感じたりせず,またidentity crisisに陥らないためには,やはり多数の総合医が必要である.
病院総合医の育て方に固有のものはないが,私たちは,「診断推論や臨床推論の徹底した訓練」と「治療のEBM」と「チーム医療下での屋根瓦方式教育指導体制」をとりわけ重視している.いずれの軸も,総合診療科の間口の広さを利用して成り立つものであり,そのうえで奥行きを構築しようとするものである.当院の総合診療科の面々が,毎早朝に昼に夜に,カンファレンス室や病室や廊下や医局で,侃々諤々,ときにはひっそりと議論し合うのも,早急に正診にたどり着き,治療をできるだけ根拠立て,意見を調整し,異論に耳を傾け,倫理的課題にも最大公約数的納得を得ようとする努力にほかならない.各診療科の専門医療にうまく溶け込むには,かかわる病院総合医の臨床的実力が必須である.
このように当院の総合診療科がかなり巨大で,けっこう多機能であるのが広域に知られてきたためか,私のところに,全国の地域病院や,ときには大学や行政組織から「総合診療の指導医を派遣してもらえないだろうか」という依頼がやってくる.「総合診療のマグネットホスピタル」を目指している立場としては誠に面映ゆい次第なのだが,何せ歴史も浅く,期待にほとんど応えることができない.とりあえずはごく数日間の「院外出前」で間に合わせてもらっているが,こういった真摯な要求にせめて文章上で応えたいというのが,本書の執筆動機である.
ところで前述した洛和会丸太町病院の170床という規模こそ,当院のような専門医の多い規模の病院よりも,かえって病院総合医が活躍できる場であることは,双方の病院で働いたことのある洛和会総合医の共通の認識である.丸太町病院の「自前化」は最近になってみるみる進み,当院の最大の「院外出前」の対象とは全く言えなくなってきたのは,誠に嬉しい「誤算」である.私の教え子や仲間の中には,その程度の比較的小さな規模の地域病院の総合医として孤軍奮闘したり,病院崩壊を食い止めたり,後輩を育成したりしている者も散見されるので,その肉声を書いてもらうことにした.
さらに,病院総合医の出自であり,大学などで臨床研究や教育研究にかかわっている教え子や仲間たちにも,活躍の現状を書いてもらうことにした.
残暑の中での2009年の衆議院選挙は,自民党の惨敗・民主党の大勝利に終わり,政権が交代することになった.数多くのマニフェストが乱舞したが,医療に関するものはあまり多くなかった.医師臨床研修制度の見直しに関していうと,大学医局による医師派遣機能の復活を目指した自民党に対して,民主党のホームページの「INDEX2009医療政策〈詳細版〉」では,「見直しは大変な誤り」とある.しかし,その後の鳩山首相や小沢幹事長の「政治とカネ」問題,さらには「米軍普天間基地移設」問題などに表面的にはかき消されたためなのか,この方面での具体的な進展は聞こえてこない.
本書の主眼は,従来から指摘されている「診療科偏在の是正」を「専門医と総合医の協調・協働」の角度から切り取ったものである.病院再生や,広く地域医療再生の旗手が総合医だけであると言っているわけでは決してない.専門医がたとえ少数であっても,その本分を果たすためには,裾野をしっかりと支える総合医が不可欠であることを強調したいだけである.専門医(特に臓器別専門内科医)の守備範囲の拡大も,病院再生にはもちろん有効であろうが,既存の勢力にはなかなか望みにくい.また卒後初期研修制度に関して敷衍すると,基本的臨床能力のどっしりとした構築は,総合医(病院総合医から家庭医まで)を志す研修医にとってだけでなく,専門医としての将来の先端医療分野での開花にとっても貴重な財産になりうるものであると提言したい.ともあれ,医師不足の地域病院にとって何らかの参考になれば,誠に幸いである.
2010年 新緑
松村理司
日本の医療にも光と影があるが,近年は綻びばかりが照射される.「医療崩壊」という言葉もすっかり耳に馴染むようになったが,開業医・診療所は比較的無傷なので,「病院崩壊」という言葉を使うほうが実相に近い.その最大の理由は,勤務医が病院から撤退するからである.2004年春の新医師臨床研修制度の開始に備えて,あちこちの地域病院への勤務医の派遣中止やそこからの引き揚げが大学医局によって行われたが,これが確かに悪さした.直撃を受けた中小病院もある.しかし,理由はそれだけではない.勤務医が疲労困憊したあげくに,「地域医療に邁進しよう」といった気概もあまりなく,開業してゆく傾向が目立つようになったのだ.これは『立ち去り型サボタージュ』という業界用語を生み,広く社会に知られるようになった.
こういう事態を背景に,医学生定員増が国策として打ち出され,2009年度から若干増(約700人)として開始された.医師事務作業補助体制への診療報酬上での配慮が,少しは払われるようになった.医師・病院バッシングが常態化していたメディア報道にも,偏向の少ない地道な記事が散見されるようになった.開業医にもっと活躍してもらおうとする案もある.勤務医は入院患者の診療や手術に特化し,外来患者や一次の救急患者をもっと多く開業医に振ろうとする厚生労働省の構想である.「総合医としての開業医」を拡大させる路線である.良質の家庭医を養成する専門医制度が構築されつつある現状だが,大きく結実すれば相当に強固な解決策の1つになるだろう.しかしこれらの策の中には,効果が出るまでに時間のかかるものも多い.
病院内を見渡すと,別の解決策があるように思われる.日本の勤務医のほとんどは専門医とその卵だが,力量のある病院総合医(ホスピタリスト)を大量育成するのである.そして,専門医はもっと「専門」に従事してもらい,その代わりに「非専門」を病院総合医に任せるわけである.「専門性の希釈」とでもいうべき事態は,できるだけ回避したい.例えば日替わりメニューで専門医が救急当直をし,一次救急に駆り出され,ふだん経験しない「非専門」に四苦八苦する愚は,そろそろ避けたいものである.こういう「各診療科(各当直医)相乗り型救急」を墨守するのではなく,病院の一次救急を,ER型救急専属医や彼・彼女らと連携する総合診療医にできるだけ任せるのである.こういった「病院における総合医と専門医の握手」は,少し違った角度から眺めることもできる.専門医の仕事は,各診療科間の取り替えがきかない.つまり,互換性がない.内科系専門医たちは,手が空いていても,手術の助手になれない.外科系専門医たちは,手術のキャンセルで暇ができても,忙しい内科系外来を手伝えない.いやそれどころではない.日本の平均的な地域病院での慢性患者外来は,それほど専門特化していないものもあるはずなのに,内科系諸科間での外来業務の互換性が想像すらされていない.開業すれば,たちまちにこういった患者群のかかりつけ医になることも往々あるはずなのにである.病院総合医の大量育成は,この現状に楔を打つ試みといえよう.
私が勤める洛和会音羽病院は588床のケアミックスの病院であり,一般病床428床(ICU/CCU 12床を含む),医療療養型病床50床,回復期リハビリテーション病床50床,認知症病床60床からなっている.総合診療科は34診療科の中で最大の診療科であり,年間入院患者数も約1,100名と最多である.同科入院患者の約75%がERからであり,それはER全体からみると約25%にあたる.所長(副院長兼務)1名,部長1名,医長3名,医員11名,後期研修医12名の所帯だが,枠外の存在である医学教育センター所長(副院長兼務)や院長の私も,たまたま総合診療出身である.
院内最大勢力の総合診療科は,さまざまな「雑務」をこなさざるをえない.「出前」とも称しており,「院内出前」と「院外出前」に分けられる.「院内出前」の最大のものは,8名の救急専属医(後期研修医2名を含む)と連携したうえでのER型救急医療現場への主体的関与である.当院は「救急を断らない民間病院」として最近何度かメディアにも取り上げられたが,年間救急搬送依頼約5,000件に対する応需率は99.9%ときわめて高い.「院外出前」の最大のものは,内科系医師の絶対的欠乏に悩む当院の姉妹病院(洛和会丸太町病院,170床)への継続的複数(6~7名)医師派遣であった.総合医は,本来「非特異的」に患者を診察・治療する(つまり,“What can I do for you?”「何がお困りですか?」と,どんな患者のどんな症状・病態・病気にも対応する)ものだが,以上の多岐にわたる活動を「雑務」と感じたりせず,またidentity crisisに陥らないためには,やはり多数の総合医が必要である.
病院総合医の育て方に固有のものはないが,私たちは,「診断推論や臨床推論の徹底した訓練」と「治療のEBM」と「チーム医療下での屋根瓦方式教育指導体制」をとりわけ重視している.いずれの軸も,総合診療科の間口の広さを利用して成り立つものであり,そのうえで奥行きを構築しようとするものである.当院の総合診療科の面々が,毎早朝に昼に夜に,カンファレンス室や病室や廊下や医局で,侃々諤々,ときにはひっそりと議論し合うのも,早急に正診にたどり着き,治療をできるだけ根拠立て,意見を調整し,異論に耳を傾け,倫理的課題にも最大公約数的納得を得ようとする努力にほかならない.各診療科の専門医療にうまく溶け込むには,かかわる病院総合医の臨床的実力が必須である.
このように当院の総合診療科がかなり巨大で,けっこう多機能であるのが広域に知られてきたためか,私のところに,全国の地域病院や,ときには大学や行政組織から「総合診療の指導医を派遣してもらえないだろうか」という依頼がやってくる.「総合診療のマグネットホスピタル」を目指している立場としては誠に面映ゆい次第なのだが,何せ歴史も浅く,期待にほとんど応えることができない.とりあえずはごく数日間の「院外出前」で間に合わせてもらっているが,こういった真摯な要求にせめて文章上で応えたいというのが,本書の執筆動機である.
ところで前述した洛和会丸太町病院の170床という規模こそ,当院のような専門医の多い規模の病院よりも,かえって病院総合医が活躍できる場であることは,双方の病院で働いたことのある洛和会総合医の共通の認識である.丸太町病院の「自前化」は最近になってみるみる進み,当院の最大の「院外出前」の対象とは全く言えなくなってきたのは,誠に嬉しい「誤算」である.私の教え子や仲間の中には,その程度の比較的小さな規模の地域病院の総合医として孤軍奮闘したり,病院崩壊を食い止めたり,後輩を育成したりしている者も散見されるので,その肉声を書いてもらうことにした.
さらに,病院総合医の出自であり,大学などで臨床研究や教育研究にかかわっている教え子や仲間たちにも,活躍の現状を書いてもらうことにした.
残暑の中での2009年の衆議院選挙は,自民党の惨敗・民主党の大勝利に終わり,政権が交代することになった.数多くのマニフェストが乱舞したが,医療に関するものはあまり多くなかった.医師臨床研修制度の見直しに関していうと,大学医局による医師派遣機能の復活を目指した自民党に対して,民主党のホームページの「INDEX2009医療政策〈詳細版〉」では,「見直しは大変な誤り」とある.しかし,その後の鳩山首相や小沢幹事長の「政治とカネ」問題,さらには「米軍普天間基地移設」問題などに表面的にはかき消されたためなのか,この方面での具体的な進展は聞こえてこない.
本書の主眼は,従来から指摘されている「診療科偏在の是正」を「専門医と総合医の協調・協働」の角度から切り取ったものである.病院再生や,広く地域医療再生の旗手が総合医だけであると言っているわけでは決してない.専門医がたとえ少数であっても,その本分を果たすためには,裾野をしっかりと支える総合医が不可欠であることを強調したいだけである.専門医(特に臓器別専門内科医)の守備範囲の拡大も,病院再生にはもちろん有効であろうが,既存の勢力にはなかなか望みにくい.また卒後初期研修制度に関して敷衍すると,基本的臨床能力のどっしりとした構築は,総合医(病院総合医から家庭医まで)を志す研修医にとってだけでなく,専門医としての将来の先端医療分野での開花にとっても貴重な財産になりうるものであると提言したい.ともあれ,医師不足の地域病院にとって何らかの参考になれば,誠に幸いである.
2010年 新緑
松村理司
目次
開く
I 市立舞鶴市民病院辞職のてんまつ
1 個人史を語るわけ
2 うわさの真相
3 抽出できる普遍的意味
II 病院崩壊の時代
1 新医師臨床研修制度の影響
2 その他の理由
3 歴史的俯瞰
4 吉本隆明氏と岡本祐三先生の表現より
5 医師臨床研修制度の見直し
III 病院崩壊の打開策
1 医学部定員の増員
2 メディカルスクール構想
3 医師事務作業補助体制の充実
4 チーム医療下でのスキルミックスの推進
5 ナース・プラクティショナーやNurse anesthetistなどの育成
6 「総合医としての開業医」の拡充
7 女性医師対策
8 「医療安全調査委員会」の設置
9 無過失補償制度
10 偏向のないメディア報道
11 低医療費政策・医療費抑制政策の抜本的改革
12 国民・市民(消費者)の理解・納得-低負担・低福祉から中負担・中福祉へ
13 院長の出番
14 医師側の反省
IV 病院総合医(ホスピタリスト)の立場から
1 総合医の定義─家庭医から病院総合医まで
2 “大リーガー医”とは
3 日本版ホスピタリストとは
4 総合医と専門医の握手
5 日本の中小病院の勤務医
6 専門医の非互換性・目線の高さ
V 「1つ上の段階の総合医」を目指して
1 診断推論・臨床推論の訓練
2 治療のEBM
3 チーム医療下での屋根瓦方式教育指導体制の構築
4 「総合する専門医」
5 専門医認定制度の構築
6 画像診断や手技の訓練
VI 洛和会音羽病院の医局と総合診療科
1 沿革と現状
2 総合医局
3 総合診療科の陣容と教育内容
4 総合診療科とDPC
5 総合診療科の出前(“雑務”)
6 総合診療科の玉手箱より-狂犬病騒動
7 “大リーガー医”招聘
8 総合診療科のアクションプラン
9 洛和会京都医学教育センターからの発信
VII いくつかの地域病院における総合診療
A 洛和会丸太町病院
1 はじめに
2 洛和会丸太町病院の特徴
3 洛和会音羽病院の特徴
4 丸太町病院に総合内科医が常駐するようになった背景
5 総合内科医の質を向上させるために
6 地域貢献を願う心
B 江別市立病院
1 はじめに
2 研修の特徴
3 研修の詳細
4 病棟研修の内容
5 週間スケジュール
6 おわりに
C 諏訪中央病院
1 はじめに
2 諏訪中央病院の現状
3 諏訪中央病院,内科/総合診療部
4 なぜ内科/総合診療部が成立するか
5 総合診療は卒後1~5年目の世代が支える?
VIII 臨床研究をめぐって
A 総合診療と臨床研究
1 臨床研究について-歴史とこれから
2 音羽病院での臨床研究-現状・問題点
3 総合診療と臨床研究の今後
4 臨床研究や疫学を学ぶ
5 推薦図書
IX 教育研究をめぐって
A ジェネラリストが担う教育研究
1 はじめに
2 臨床実習のあり方
3 医療安全教育
4 ケースメソッド授業の導入
5 指導医講習会の開発
6 医師向けの臨床研究スキル教育(狭義の医学教育研究も含む)
7 まとめ
B ジェネラリストのアカデミックキャリア
1 はじめに
2 市立舞鶴市民病院内科における卒後初期臨床研修
3 市立舞鶴市民病院内科の卒業生の共通した行動
4 医学教育に関する疑問-社会政策と社会科学の間で
5 医学教育学という学問の存在
6 医学教育学研究
7 医学教育学という専門をもつ総合医
8 おわりに
X 展望
1 中小病院と総合診療
2 高齢社会と総合診療
3 専門医認定制度と総合診療
4 マッチングと総合診療
5 医療安全と総合診療
あとがき
索引
1 個人史を語るわけ
2 うわさの真相
3 抽出できる普遍的意味
II 病院崩壊の時代
1 新医師臨床研修制度の影響
2 その他の理由
3 歴史的俯瞰
4 吉本隆明氏と岡本祐三先生の表現より
5 医師臨床研修制度の見直し
III 病院崩壊の打開策
1 医学部定員の増員
2 メディカルスクール構想
3 医師事務作業補助体制の充実
4 チーム医療下でのスキルミックスの推進
5 ナース・プラクティショナーやNurse anesthetistなどの育成
6 「総合医としての開業医」の拡充
7 女性医師対策
8 「医療安全調査委員会」の設置
9 無過失補償制度
10 偏向のないメディア報道
11 低医療費政策・医療費抑制政策の抜本的改革
12 国民・市民(消費者)の理解・納得-低負担・低福祉から中負担・中福祉へ
13 院長の出番
14 医師側の反省
IV 病院総合医(ホスピタリスト)の立場から
1 総合医の定義─家庭医から病院総合医まで
2 “大リーガー医”とは
3 日本版ホスピタリストとは
4 総合医と専門医の握手
5 日本の中小病院の勤務医
6 専門医の非互換性・目線の高さ
V 「1つ上の段階の総合医」を目指して
1 診断推論・臨床推論の訓練
2 治療のEBM
3 チーム医療下での屋根瓦方式教育指導体制の構築
4 「総合する専門医」
5 専門医認定制度の構築
6 画像診断や手技の訓練
VI 洛和会音羽病院の医局と総合診療科
1 沿革と現状
2 総合医局
3 総合診療科の陣容と教育内容
4 総合診療科とDPC
5 総合診療科の出前(“雑務”)
6 総合診療科の玉手箱より-狂犬病騒動
7 “大リーガー医”招聘
8 総合診療科のアクションプラン
9 洛和会京都医学教育センターからの発信
VII いくつかの地域病院における総合診療
A 洛和会丸太町病院
1 はじめに
2 洛和会丸太町病院の特徴
3 洛和会音羽病院の特徴
4 丸太町病院に総合内科医が常駐するようになった背景
5 総合内科医の質を向上させるために
6 地域貢献を願う心
B 江別市立病院
1 はじめに
2 研修の特徴
3 研修の詳細
4 病棟研修の内容
5 週間スケジュール
6 おわりに
C 諏訪中央病院
1 はじめに
2 諏訪中央病院の現状
3 諏訪中央病院,内科/総合診療部
4 なぜ内科/総合診療部が成立するか
5 総合診療は卒後1~5年目の世代が支える?
VIII 臨床研究をめぐって
A 総合診療と臨床研究
1 臨床研究について-歴史とこれから
2 音羽病院での臨床研究-現状・問題点
3 総合診療と臨床研究の今後
4 臨床研究や疫学を学ぶ
5 推薦図書
IX 教育研究をめぐって
A ジェネラリストが担う教育研究
1 はじめに
2 臨床実習のあり方
3 医療安全教育
4 ケースメソッド授業の導入
5 指導医講習会の開発
6 医師向けの臨床研究スキル教育(狭義の医学教育研究も含む)
7 まとめ
B ジェネラリストのアカデミックキャリア
1 はじめに
2 市立舞鶴市民病院内科における卒後初期臨床研修
3 市立舞鶴市民病院内科の卒業生の共通した行動
4 医学教育に関する疑問-社会政策と社会科学の間で
5 医学教育学という学問の存在
6 医学教育学研究
7 医学教育学という専門をもつ総合医
8 おわりに
X 展望
1 中小病院と総合診療
2 高齢社会と総合診療
3 専門医認定制度と総合診療
4 マッチングと総合診療
5 医療安全と総合診療
あとがき
索引
書評
開く
地域医療再生のための処方箋
書評者: 堺 常雄 (日本病院会会長/聖隷浜松病院院長)
私が勤務する聖隷浜松病院では,過去10数年の間に各科の専門分化が進み診療の内容も高度化し先進的な医療にも対応ができてきた。それにもかかわらず,数年前から現在の診療体制はこれでよいのだろうかという漠然とした疑問が浮かんできている。例えば救急の場面で専門医が呼ばれ,「これはうちではないよ」という事例を散見するようになったからである。彼(彼女)自身からすればその通りなのかもしれないが,困るのは患者,看護師,初期対応の医師である。この時点では診療プロセスの中で何ら問題が解決されていないのである。
このような状況を改善し,診療の基礎となる部門の充実と総合的な診療の質の保証をめざして考えたのが「診療部門3階建」構想である。1階部分が総合診療内科と救急科よりなるGeneral Medicine(総合診療部門),2階部分がSpecialties(専門各科),3階部分がSuper-specialtiesという構造である。縦,横の連携の充実が図れればと願っている。まだ完成してはいないがこれから1-2年のうちに構築しようと考えている。
このような考えをもっているときに読んだのが本書『地域医療は再生する―病院総合医の可能性とその教育・研修』であり,まさに目から鱗が落ちた感じであった。この本は松村理司先生の36年にわたる経験をもとに書かれたもので現場の医療を知り尽くした上で地域医療再生のための処方箋を示されたものである。医療者が医療崩壊などといっている場合ではなく,現場から医療を再構築しようという熱い心が込もった,しかも実現可能な提言である。
IからVIまでは松村先生がご自分の経験,具体的な提言を述べられ,VIIからIXは松村門下の先生が現場からの考えを述べられている。ここで感心したのは日常診療の忙しい中で臨床研究,教育研究の重要性に言及されていることである。普通ならば「そんなことは無理」との一言で無視されそうな,しかしながら大切な点に触れていただき,まさにその通りと思った。研究心を失ったら進歩はおぼつかないのである。最後のXでは松村先生が「展望」を担当され,管理者の目で日本の医療全般の問題点について独自の考えを述べておられる。
「医療崩壊」がいわれ,病院の勤務医は疲れ切っている。すべてを政治のせいにするのは簡単であるが,現在の政治状況を考えると,残念ながら明るい展望は描けない。それではそのままでよいかといえばそうではなく,医療に携わる一人一人が自分にできることを実直に行っていく必要があるだろう。「誰かがやってくれる」ではなくて「自分たちがやらなければ何も起こらない」のである。その意味で本書は読者に何をやるべきかを示し,夢と希望を与えてくれるものとなっており,すべての医療人必読の書といえる。多くの読者がこの本から刺激を受け,自分のやるべき方向性を見いだし,さらに前進することを切に願うものである。
ボトムアップな地域医療再生総合医を育てる魂の一冊
書評者: 岩田 健太郎 (神戸大教授・感染治療学/神戸大病院感染症内科診療科長)
本書の編著者である松村理司先生は一貫して優れた総合医であることをめざし,優れた総合医を育てることに尽力してきた。そして,疲弊の激しい中小病院の勤務医が優れた病院総合医であれば,現在の「医療崩壊」(松村先生的に表現するならば「病院崩壊」)の問題は解決に向かうのではないかと主張している。本書の主旨である。
医療の質という面では病院勤務医はまだまだうまく機能できてはいない。検査過剰,「木を見て森を見ない」と称されるマイクロな医療をぐるぐる回しても,超高齢化社会を迎え,患者の様相が複雑化し,また診療の目的すら明確でなくなる日本の医療に明瞭なヴィジョンを持ち得ないだろう。そのヴィジョンを個々の優れた病院総合医が持てば診療の質は高まり,それがひいては病院という組織の,そして国の医療のあり方の改善につながっていく。松村先生は本書で数々の医療政策に対する提言を行うが,「国がこうすればよいのだ」というトップダウンの,「おかみ丸投げ」ではない。徹底してボトムアップの思想である。そしてそれを具現化しているのが洛和会音羽病院である。
音羽病院は卒後臨床研修環境において日本で最も優れた環境を持っている(International Journal of Medical Education. 2010; 1: 10-14)。ちなみに上位10施設中,大学病院は弘前大学病院ただ一つだけである。大学病院から人が出ていったのは初期臨床研修「制度」のせいではない。大学病院が研修医を引きつけるだけのリソースと魅力を持っていないからなのである。制度はただ,それを顕在化させただけなのである。
優れたシステムもすべては「ひと」からなる。形式だけ整えても構成員個々の能力や意欲が伴わなければ絵に描いた餅である。古典的な日本の医療システムにおける「美点」(例えばフリーアクセス)も,それは個人の,特に勤務医の過剰な献身によるぎりぎりの綱渡りな状態がもたらしたものであった。それが限界を迎え,「立ち去る」状態になる。「医療崩壊」という言葉が生まれる。
日本医療の質はよいか? このような「イエス・ノー」的な回答を促す問いは子どもじみている。アメリカと日本のどちらの医療が「まし」か? これも大人げない議論である。他者との比較でしか自己を規定できない人は哀れである。(他国はさておき)「日本の医療のどこに問題点があり,さらなる改善点があるか?」こそが問われるべき大人の命題だ。そして病院診療における改善点は山のようにある。我々は毎日毎日,日本の病院診療の欠点を見せつけられている。
本書は重層的に,多角的に日本の病院総合診療のあり方を,そして病院診療のあり方を提言する。提言は実に具体的でマイクロなものだ。カンファレンスのあり方,診断プロセスのあり方,女性医師のあり方に始まり,労務管理や給与の問題,果ては音羽病院における狂犬病診断の顛末から脚気の「森-高木論争」に至るまで,実に多彩な議論が展開される。その根底には一貫して,優れた総合医とは何か,育てる手段はいかに,という問いが流れている。著者の魂がこもっており,読者の魂も揺さぶられる。
間口を広く,かつ深いバイブル的地域診療の解説書
書評者: 邉見 公雄 (社団法人全国自治体病院協議会会長)
「地域医療は再生する」のだろうか? この本のタイトルを見たときに,再生してほしいという当事者としての強い願望と,どんどん悪い方向に流れる現実との狭間で,少しわだかまりのようなものがあった。それを可能にするのは総合医である,というのが編著者・松村理司氏の持論である。総合医を“間口を広く,かつ深い”領域と述べているが,この本もそれを地で言っている内容である。
かつて小生も,大学病院研究室から片道3時間をかけ毎週水曜日に手術応援に通っていた舞鶴市民病院での氏の総合医としてのご経験,音羽病院での院長としての御苦労が本書のレベルを高め,広くて深いバイブル的地域医療の解説書に仕上げられている。森鴎外と高木兼寛の論争が専門医と総合医のルーツ的なものというのも目から鱗,大学と市中病院に置き換えるのも可能であろう。スキルミックスやメディカルアシスタントも,米国での経験から説得力がある。50年,半世紀遅れになってしまっても,まだ追いつくチャンスはわずかに残っているとはかない希望も抱かせてくれる優しさもある。
小生は,女性医師の“3H”はWarm Heart,Cool Head,Skill(Good) Handのことかと一瞬思ったが,予想外でかつ納得,参ってしまった。最も感心したのは,職員を守るためには筋を通して理不尽なクレーム・訴訟に院長が先頭に立ち門前払い。言うはやすいがなかなかできることではない。これにも私は参った,参った。本書を読んでからは先輩面ができなくなってしまった(実は,編著者は小生の大学の6年後輩である)。特に61ページの遺族に対する慰謝料御免,お断りの文章は腰越状以上の名文で,院長など病院管理者の心を打つ。複写して院長室に掲げておきたい。
診断学の基本とも言うべき診断推論や臨床推論,そのために招いた大リーガー医,またチーム医療下での屋根瓦方式教育指導,専門医志向から家庭医の重要性,病院死から在宅死へ,そのための地域総合診療医。メディカルスクールや地域枠と医師の育成にも付言している。DPCと病院医療,わが国特有の中小病院における勤務医の実状,足利事件とDNA鑑定など,著者が四方にアンテナを高く上げているのがよくわかる。さらには,総合医の行う臨床研究,臨床疫学など同僚の若手医師も筆を奮っている。この本を読んだ院長や副院長,部長の先生方は必ずや自院の医師に短期研修,出前回診をお願いしたくなること請け合いである。
小生は卒後40余年,大学周辺で研究していた数年を除き生粋のジェネラリストと思い,またそこそこやれる院長と思っていた。しかし,この著書を読んで私の自負は木端微塵,寝苦しい夜が続いている。地域医療に自信のある方は,ぜひとも御一読を。また自信のない人も,私の故郷の阿波踊りのお囃子「よしこの 」風に言えば“読まなきゃ損,損”。
書評者: 堺 常雄 (日本病院会会長/聖隷浜松病院院長)
私が勤務する聖隷浜松病院では,過去10数年の間に各科の専門分化が進み診療の内容も高度化し先進的な医療にも対応ができてきた。それにもかかわらず,数年前から現在の診療体制はこれでよいのだろうかという漠然とした疑問が浮かんできている。例えば救急の場面で専門医が呼ばれ,「これはうちではないよ」という事例を散見するようになったからである。彼(彼女)自身からすればその通りなのかもしれないが,困るのは患者,看護師,初期対応の医師である。この時点では診療プロセスの中で何ら問題が解決されていないのである。
このような状況を改善し,診療の基礎となる部門の充実と総合的な診療の質の保証をめざして考えたのが「診療部門3階建」構想である。1階部分が総合診療内科と救急科よりなるGeneral Medicine(総合診療部門),2階部分がSpecialties(専門各科),3階部分がSuper-specialtiesという構造である。縦,横の連携の充実が図れればと願っている。まだ完成してはいないがこれから1-2年のうちに構築しようと考えている。
このような考えをもっているときに読んだのが本書『地域医療は再生する―病院総合医の可能性とその教育・研修』であり,まさに目から鱗が落ちた感じであった。この本は松村理司先生の36年にわたる経験をもとに書かれたもので現場の医療を知り尽くした上で地域医療再生のための処方箋を示されたものである。医療者が医療崩壊などといっている場合ではなく,現場から医療を再構築しようという熱い心が込もった,しかも実現可能な提言である。
IからVIまでは松村先生がご自分の経験,具体的な提言を述べられ,VIIからIXは松村門下の先生が現場からの考えを述べられている。ここで感心したのは日常診療の忙しい中で臨床研究,教育研究の重要性に言及されていることである。普通ならば「そんなことは無理」との一言で無視されそうな,しかしながら大切な点に触れていただき,まさにその通りと思った。研究心を失ったら進歩はおぼつかないのである。最後のXでは松村先生が「展望」を担当され,管理者の目で日本の医療全般の問題点について独自の考えを述べておられる。
「医療崩壊」がいわれ,病院の勤務医は疲れ切っている。すべてを政治のせいにするのは簡単であるが,現在の政治状況を考えると,残念ながら明るい展望は描けない。それではそのままでよいかといえばそうではなく,医療に携わる一人一人が自分にできることを実直に行っていく必要があるだろう。「誰かがやってくれる」ではなくて「自分たちがやらなければ何も起こらない」のである。その意味で本書は読者に何をやるべきかを示し,夢と希望を与えてくれるものとなっており,すべての医療人必読の書といえる。多くの読者がこの本から刺激を受け,自分のやるべき方向性を見いだし,さらに前進することを切に願うものである。
ボトムアップな地域医療再生総合医を育てる魂の一冊
書評者: 岩田 健太郎 (神戸大教授・感染治療学/神戸大病院感染症内科診療科長)
本書の編著者である松村理司先生は一貫して優れた総合医であることをめざし,優れた総合医を育てることに尽力してきた。そして,疲弊の激しい中小病院の勤務医が優れた病院総合医であれば,現在の「医療崩壊」(松村先生的に表現するならば「病院崩壊」)の問題は解決に向かうのではないかと主張している。本書の主旨である。
医療の質という面では病院勤務医はまだまだうまく機能できてはいない。検査過剰,「木を見て森を見ない」と称されるマイクロな医療をぐるぐる回しても,超高齢化社会を迎え,患者の様相が複雑化し,また診療の目的すら明確でなくなる日本の医療に明瞭なヴィジョンを持ち得ないだろう。そのヴィジョンを個々の優れた病院総合医が持てば診療の質は高まり,それがひいては病院という組織の,そして国の医療のあり方の改善につながっていく。松村先生は本書で数々の医療政策に対する提言を行うが,「国がこうすればよいのだ」というトップダウンの,「おかみ丸投げ」ではない。徹底してボトムアップの思想である。そしてそれを具現化しているのが洛和会音羽病院である。
音羽病院は卒後臨床研修環境において日本で最も優れた環境を持っている(International Journal of Medical Education. 2010; 1: 10-14)。ちなみに上位10施設中,大学病院は弘前大学病院ただ一つだけである。大学病院から人が出ていったのは初期臨床研修「制度」のせいではない。大学病院が研修医を引きつけるだけのリソースと魅力を持っていないからなのである。制度はただ,それを顕在化させただけなのである。
優れたシステムもすべては「ひと」からなる。形式だけ整えても構成員個々の能力や意欲が伴わなければ絵に描いた餅である。古典的な日本の医療システムにおける「美点」(例えばフリーアクセス)も,それは個人の,特に勤務医の過剰な献身によるぎりぎりの綱渡りな状態がもたらしたものであった。それが限界を迎え,「立ち去る」状態になる。「医療崩壊」という言葉が生まれる。
日本医療の質はよいか? このような「イエス・ノー」的な回答を促す問いは子どもじみている。アメリカと日本のどちらの医療が「まし」か? これも大人げない議論である。他者との比較でしか自己を規定できない人は哀れである。(他国はさておき)「日本の医療のどこに問題点があり,さらなる改善点があるか?」こそが問われるべき大人の命題だ。そして病院診療における改善点は山のようにある。我々は毎日毎日,日本の病院診療の欠点を見せつけられている。
本書は重層的に,多角的に日本の病院総合診療のあり方を,そして病院診療のあり方を提言する。提言は実に具体的でマイクロなものだ。カンファレンスのあり方,診断プロセスのあり方,女性医師のあり方に始まり,労務管理や給与の問題,果ては音羽病院における狂犬病診断の顛末から脚気の「森-高木論争」に至るまで,実に多彩な議論が展開される。その根底には一貫して,優れた総合医とは何か,育てる手段はいかに,という問いが流れている。著者の魂がこもっており,読者の魂も揺さぶられる。
間口を広く,かつ深いバイブル的地域診療の解説書
書評者: 邉見 公雄 (社団法人全国自治体病院協議会会長)
「地域医療は再生する」のだろうか? この本のタイトルを見たときに,再生してほしいという当事者としての強い願望と,どんどん悪い方向に流れる現実との狭間で,少しわだかまりのようなものがあった。それを可能にするのは総合医である,というのが編著者・松村理司氏の持論である。総合医を“間口を広く,かつ深い”領域と述べているが,この本もそれを地で言っている内容である。
かつて小生も,大学病院研究室から片道3時間をかけ毎週水曜日に手術応援に通っていた舞鶴市民病院での氏の総合医としてのご経験,音羽病院での院長としての御苦労が本書のレベルを高め,広くて深いバイブル的地域医療の解説書に仕上げられている。森鴎外と高木兼寛の論争が専門医と総合医のルーツ的なものというのも目から鱗,大学と市中病院に置き換えるのも可能であろう。スキルミックスやメディカルアシスタントも,米国での経験から説得力がある。50年,半世紀遅れになってしまっても,まだ追いつくチャンスはわずかに残っているとはかない希望も抱かせてくれる優しさもある。
小生は,女性医師の“3H”はWarm Heart,Cool Head,Skill(Good) Handのことかと一瞬思ったが,予想外でかつ納得,参ってしまった。最も感心したのは,職員を守るためには筋を通して理不尽なクレーム・訴訟に院長が先頭に立ち門前払い。言うはやすいがなかなかできることではない。これにも私は参った,参った。本書を読んでからは先輩面ができなくなってしまった(実は,編著者は小生の大学の6年後輩である)。特に61ページの遺族に対する慰謝料御免,お断りの文章は腰越状以上の名文で,院長など病院管理者の心を打つ。複写して院長室に掲げておきたい。
診断学の基本とも言うべき診断推論や臨床推論,そのために招いた大リーガー医,またチーム医療下での屋根瓦方式教育指導,専門医志向から家庭医の重要性,病院死から在宅死へ,そのための地域総合診療医。メディカルスクールや地域枠と医師の育成にも付言している。DPCと病院医療,わが国特有の中小病院における勤務医の実状,足利事件とDNA鑑定など,著者が四方にアンテナを高く上げているのがよくわかる。さらには,総合医の行う臨床研究,臨床疫学など同僚の若手医師も筆を奮っている。この本を読んだ院長や副院長,部長の先生方は必ずや自院の医師に短期研修,出前回診をお願いしたくなること請け合いである。
小生は卒後40余年,大学周辺で研究していた数年を除き生粋のジェネラリストと思い,またそこそこやれる院長と思っていた。しかし,この著書を読んで私の自負は木端微塵,寝苦しい夜が続いている。地域医療に自信のある方は,ぜひとも御一読を。また自信のない人も,私の故郷の阿波踊りのお囃子「よしこの 」風に言えば“読まなきゃ損,損”。