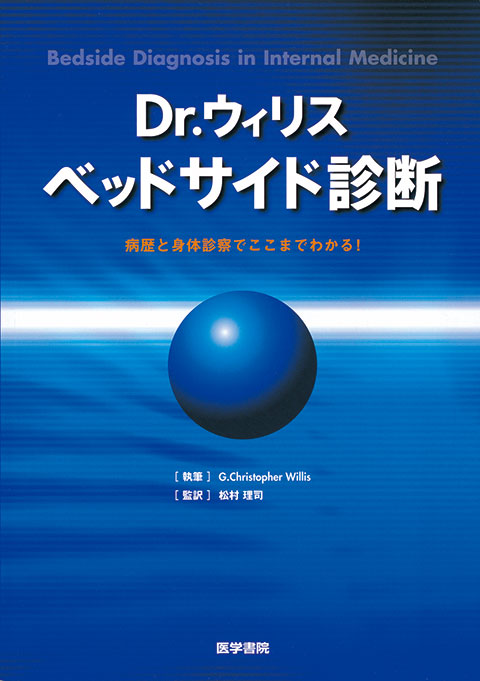Dr.ウィリス ベッドサイド診断
病歴と身体診察でここまでわかる!
私は病歴聴取と身体診察だけで90%のケースを正しく診断できる―G. C. Willis
もっと見る
あの伝説のウィリスノート全訳。ウィリス先生が日本の医学生や若い医師に臨床診断学を教えるためにまとめたとされる書。患者の訴える症状、病歴・身体診察から種々の情報を集めて鑑別診断を行い、ベッドサイドで最終診断にいたるまでのプロセスが詳述されており、本書を読めば、本来、もっと驚くべき正確さ、速さ、そして少ないコストで診断に到達できることが理解されよう。決して時代遅れになることのないベッドサイドの診断技術を、すべての臨床医に。
| 執筆 | G. Christopher Willis |
|---|---|
| 監訳 | 松村 理司 |
| 発行 | 2008年04月判型:B5頁:720 |
| ISBN | 978-4-260-00033-8 |
| 定価 | 7,150円 (本体6,500円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
この本は,かつて私が医学生や若い医師に臨床診断学を教えるために作ったノートをまとめたものである。ここには私のほぼ50年に及ぶ臨床医としての経験が凝縮されているといってよい。私はこれまで長年にわたって後進の指導にあたり,彼らに多くの技術を教えてきたが,そのほとんどは私個人の発明ではなく,私自身が優れた能力をもつ指導者や,その残した書物から学んできたものであった。この本では専門分野にこだわらず,広く内科一般の患者に対して,「ベッドサイドで何がわかるか」ということが解説してある。ただ,その対象とする範囲があまりに広いため,個々の項目について,出典や参考文献をすべて記すことは不可能であった。そこでここにそれらの技術や知識を残してくれた人たちに対する深い感謝と尊敬の念を表し,出典の明示に代えさせていただきたい。私はこの本が医学教育にかけた先人の熱意を少しでも読者に伝えてくれることを祈っている。
この本で私は病歴と身体所見に基づく臨床診断の重要性を強調しているが,これは私自身の経験がそうさせるのである。私はこれまで臨床医として,かつて英領北ボルネオと呼ばれた地方の粗末な診療所から,アジア・北米・イギリス・アフリカにおける最も近代的な大病院に至るまで,実に様々な条件下で診療にあたってきた。ベッドサイドでの診断技術は,厚いコンクリートの壁に囲まれた近代的病院よりも,むしろボルネオ僻地の小さな診療所において,その真の価値を発揮した。そこでは病理組織標本に基づく疾患分類はほとんど意味をもたない。医師は患者の訴えを聞き,自ら適切な質問をし,身体診察を行って,その場で正しい診断を下さなければならないのである。ベッドサイドの所見だけで最終診断に到達するためには,あらゆるケースにおいて適切な鑑別診断ができるだけの膨大な数の臨床症候を知っておく必要がある。この本ではこのスタイルにのっとり,患者の訴える症状から始まって,身体診察によって種々の情報や証拠を集めて鑑別診断を行い,ベッドサイドで最終診断に至るプロセスが詳しく説明してある。
また,私は上述の近代的医学設備が使えない状況下で診療を続けるうちに,患者を目の前にして医師自身が2~3分の短時間で行う簡単な臨床化学検査が,安いコストの割に非常に大きな診断的有用性をもつということを学んだ。これらの簡易検査についてはすでに1冊の本にまとめて医学書院から出版したので(G.C.ウィリス著,宮城征四郎・平安山英達訳「救急室で役立つ臨床検査の実際」1981年刊,すでに絶版),興味のある読者はそちらを参照されたい。
ベッドサイドでの診断技術は決して時代遅れになることはない。基礎医学の進歩に伴い,医療も診断学もこれまで大きな変化発展を遂げてきたし,またこれからも変化し続けるであろうが,華々しい最新技術はある日突然現れるものではなく,遠い昔から先人たちがベッドサイドで発見してきた真理の上に積み重ねられるものなのである。
この本では具体的な鑑別診断に入る前に,できるだけ生体の正常機能とその破綻について病態生理学的な記述を加えるよう心がけた。これは病態生理学の知識が種々のデータの解釈に役立ち,さらに多くの煩雑な知識を整理しながら覚える上で非常に有用だと考えるからである。また各章の末尾には,主訴から始まって,病歴,種々の臨床所見,簡易検査をもとに鑑別診断を行い,最終診断に至るフローチャートがつけてある。これらのチャートは,臨床家が診療現場で診断の迷路に迷い込んだ時に,そこから脱出する助けとなるであろう。
この本は,最新の医療設備や検査機器を利用できる医師にとっても決して無価値ではない。彼らはその最新設備を有効に使って,ベッドサイドにおける診断技術をさらに磨くことができる。すなわちまずベッドサイドで診断をつけておき,それを後から生化学検査や画像診断などの結果と比較してみれば,臨床診断の精度をさらに上げられるのである。しかしやがて読者は,こうした診断機器の助けなしでも,ベッドサイドで病歴や身体所見を詳しく分析すれば,それだけで驚くべき正確さ,速さ,そして少ない金銭的コストで診断に到達できるということを理解するであろう。実際ある種の疾患に対しては今なお最新の診断機器もまったく無力であり,依然としてベッドサイドの情報だけが唯一の診断手段なのである。
この本を発表するにあたって,まず,枝 雅俊先生に感謝の意を表したい。彼は私のノートを本の形にして発表するよう勧めてくれ,また英語の原稿を日本語に翻訳してくれた。翻訳上の疑問点については,数多くの手紙のやりとりによって解決が得られたと信じている。また市立舞鶴市民病院での私の生徒であり,仲間でもあった木村雅英先生や池川雅哉先生の努力がなければ,この本は出版には至らなかっただろう。この本のもととなるノートは,私がかつて参加した市立舞鶴市民病院における臨床研修プログラムのために準備された。この臨床研修プログラムは同病院にいらした松村理司先生の企画立案によるものである。
また私は沖縄県とハワイ大学にも賛辞を呈する。彼らの協力により沖縄県立中部病院で実施された若手医師に対する卒後臨床研修プログラムは,その後日本各地で採用された同種の研修システムの先駆けであった。私はかつてそのプログラムに参加し,宮里不二彦先生,宮城征四郎先生,喜舎場朝和先生,西平竹夫先生,豊永一隆先生といった優秀な同僚と,数年間ともに働けたことを大きな名誉とするものである。
最後に,日本で最も高名な臨床医の一人である日野原重明先生による,非常に多方面にわたる支持と助力に感謝したい。日野原先生はSir. William Oslerの熱心な信奉者であり,日本において一人でも多くの医師にOsler博士の臨床スタイルを広めるため,献身的な努力をしておられる。
2008年3月
G. Christopher Willis
この本は,かつて私が医学生や若い医師に臨床診断学を教えるために作ったノートをまとめたものである。ここには私のほぼ50年に及ぶ臨床医としての経験が凝縮されているといってよい。私はこれまで長年にわたって後進の指導にあたり,彼らに多くの技術を教えてきたが,そのほとんどは私個人の発明ではなく,私自身が優れた能力をもつ指導者や,その残した書物から学んできたものであった。この本では専門分野にこだわらず,広く内科一般の患者に対して,「ベッドサイドで何がわかるか」ということが解説してある。ただ,その対象とする範囲があまりに広いため,個々の項目について,出典や参考文献をすべて記すことは不可能であった。そこでここにそれらの技術や知識を残してくれた人たちに対する深い感謝と尊敬の念を表し,出典の明示に代えさせていただきたい。私はこの本が医学教育にかけた先人の熱意を少しでも読者に伝えてくれることを祈っている。
この本で私は病歴と身体所見に基づく臨床診断の重要性を強調しているが,これは私自身の経験がそうさせるのである。私はこれまで臨床医として,かつて英領北ボルネオと呼ばれた地方の粗末な診療所から,アジア・北米・イギリス・アフリカにおける最も近代的な大病院に至るまで,実に様々な条件下で診療にあたってきた。ベッドサイドでの診断技術は,厚いコンクリートの壁に囲まれた近代的病院よりも,むしろボルネオ僻地の小さな診療所において,その真の価値を発揮した。そこでは病理組織標本に基づく疾患分類はほとんど意味をもたない。医師は患者の訴えを聞き,自ら適切な質問をし,身体診察を行って,その場で正しい診断を下さなければならないのである。ベッドサイドの所見だけで最終診断に到達するためには,あらゆるケースにおいて適切な鑑別診断ができるだけの膨大な数の臨床症候を知っておく必要がある。この本ではこのスタイルにのっとり,患者の訴える症状から始まって,身体診察によって種々の情報や証拠を集めて鑑別診断を行い,ベッドサイドで最終診断に至るプロセスが詳しく説明してある。
また,私は上述の近代的医学設備が使えない状況下で診療を続けるうちに,患者を目の前にして医師自身が2~3分の短時間で行う簡単な臨床化学検査が,安いコストの割に非常に大きな診断的有用性をもつということを学んだ。これらの簡易検査についてはすでに1冊の本にまとめて医学書院から出版したので(G.C.ウィリス著,宮城征四郎・平安山英達訳「救急室で役立つ臨床検査の実際」1981年刊,すでに絶版),興味のある読者はそちらを参照されたい。
ベッドサイドでの診断技術は決して時代遅れになることはない。基礎医学の進歩に伴い,医療も診断学もこれまで大きな変化発展を遂げてきたし,またこれからも変化し続けるであろうが,華々しい最新技術はある日突然現れるものではなく,遠い昔から先人たちがベッドサイドで発見してきた真理の上に積み重ねられるものなのである。
この本では具体的な鑑別診断に入る前に,できるだけ生体の正常機能とその破綻について病態生理学的な記述を加えるよう心がけた。これは病態生理学の知識が種々のデータの解釈に役立ち,さらに多くの煩雑な知識を整理しながら覚える上で非常に有用だと考えるからである。また各章の末尾には,主訴から始まって,病歴,種々の臨床所見,簡易検査をもとに鑑別診断を行い,最終診断に至るフローチャートがつけてある。これらのチャートは,臨床家が診療現場で診断の迷路に迷い込んだ時に,そこから脱出する助けとなるであろう。
この本は,最新の医療設備や検査機器を利用できる医師にとっても決して無価値ではない。彼らはその最新設備を有効に使って,ベッドサイドにおける診断技術をさらに磨くことができる。すなわちまずベッドサイドで診断をつけておき,それを後から生化学検査や画像診断などの結果と比較してみれば,臨床診断の精度をさらに上げられるのである。しかしやがて読者は,こうした診断機器の助けなしでも,ベッドサイドで病歴や身体所見を詳しく分析すれば,それだけで驚くべき正確さ,速さ,そして少ない金銭的コストで診断に到達できるということを理解するであろう。実際ある種の疾患に対しては今なお最新の診断機器もまったく無力であり,依然としてベッドサイドの情報だけが唯一の診断手段なのである。
この本を発表するにあたって,まず,枝 雅俊先生に感謝の意を表したい。彼は私のノートを本の形にして発表するよう勧めてくれ,また英語の原稿を日本語に翻訳してくれた。翻訳上の疑問点については,数多くの手紙のやりとりによって解決が得られたと信じている。また市立舞鶴市民病院での私の生徒であり,仲間でもあった木村雅英先生や池川雅哉先生の努力がなければ,この本は出版には至らなかっただろう。この本のもととなるノートは,私がかつて参加した市立舞鶴市民病院における臨床研修プログラムのために準備された。この臨床研修プログラムは同病院にいらした松村理司先生の企画立案によるものである。
また私は沖縄県とハワイ大学にも賛辞を呈する。彼らの協力により沖縄県立中部病院で実施された若手医師に対する卒後臨床研修プログラムは,その後日本各地で採用された同種の研修システムの先駆けであった。私はかつてそのプログラムに参加し,宮里不二彦先生,宮城征四郎先生,喜舎場朝和先生,西平竹夫先生,豊永一隆先生といった優秀な同僚と,数年間ともに働けたことを大きな名誉とするものである。
最後に,日本で最も高名な臨床医の一人である日野原重明先生による,非常に多方面にわたる支持と助力に感謝したい。日野原先生はSir. William Oslerの熱心な信奉者であり,日本において一人でも多くの医師にOsler博士の臨床スタイルを広めるため,献身的な努力をしておられる。
2008年3月
G. Christopher Willis
目次
開く
序
監訳者 序
翻訳にあたって
呼吸器
第1章 呼吸のパターン
第2章 呼吸器症状と胸部の視診
第3章 胸部の触診と打診
第4章 呼吸器系の聴診
第5章 肺機能
循環器
第6章 胸部の痛みや不快感
第7章 血圧と脈
第8章 頸静脈波のパターン
第9章 前胸部の拍動と振戦
第10章 心音
第11章 心雑音
第12章 心臓病学における問題解決法
神経
第13章 神経学的診断についての基本概念
第14章 運動・感覚・反射の検査
第15章 大脳病変でみられる症状徴候
第16章 小脳・運動失調・歩行障害
第17章 脊髄
第18章 神経学的視力障害
第19章 神経学的眼球運動障害
第20章 三叉(V)神経と顔面(VII)神経
第21章 内耳(VIII)神経:難聴・耳鳴・めまい
第22章 嗅(I)神経・舌咽(IX)神経・迷走(X)神経・副(XI)神経・舌下(XII)神経
第23章 単神経障害と多発性単神経障害
第24章 多発性神経障害
第25章 意識障害
第26章 頭痛
第27章 失神
第28章 てんかん発作
第29章 認知症
第30章 神経因性膀胱と神経因性排便障害
第31章 神経疾患と間違われやすい症状徴候
第32章 脳卒中
第33章 ミオパチー
第34章 筋ジストロフィーと代謝性筋疾患
第35章 神経筋接合部疾患と周期性四肢麻痺
消化器
第36章 腹痛
第37章 消化管出血
第38章 食欲不振・嘔気・嘔吐・呑気症
第39章 腹部診察時の身体所見
第40章 食道と嚥下に関する障害
第41章 下痢(総論)
第42章 下痢(各論)
第43章 膵臓の非内分泌性疾患
第44章 肝臓の身体所見
第45章 黄疸
第46章 ベッドサイドでの肝機能評価
第47章 胆道系
内分泌
第48章 甲状腺
第49章 副腎皮質と副腎皮質機能不全
第50章 副腎と高血圧
第51章 視床下部と下垂体
第52章 男性性腺機能の臨床的評価
第53章 卵巣
筋骨格
第54章 関節の診察
第55章 関節炎
第56章 背部痛
皮膚
第57章 皮膚科診断学の基礎
第58章 表皮の異常
第59章 真皮と皮下脂肪組織の異常
血液
第60章 脾臓
第61章 リンパ節
第62章 出血の異常
第63章 血小板異常による出血
第64章 血管性紫斑病
第65章 凝固異常による出血
体液・電解質など
第66章 体液・電解質・酸塩基平衡の異常
第67章 浮腫
第68章 ビタミン欠乏症とビタミン中毒
身体所見チャート
索引
監訳者 序
翻訳にあたって
呼吸器
第1章 呼吸のパターン
第2章 呼吸器症状と胸部の視診
第3章 胸部の触診と打診
第4章 呼吸器系の聴診
第5章 肺機能
循環器
第6章 胸部の痛みや不快感
第7章 血圧と脈
第8章 頸静脈波のパターン
第9章 前胸部の拍動と振戦
第10章 心音
第11章 心雑音
第12章 心臓病学における問題解決法
神経
第13章 神経学的診断についての基本概念
第14章 運動・感覚・反射の検査
第15章 大脳病変でみられる症状徴候
第16章 小脳・運動失調・歩行障害
第17章 脊髄
第18章 神経学的視力障害
第19章 神経学的眼球運動障害
第20章 三叉(V)神経と顔面(VII)神経
第21章 内耳(VIII)神経:難聴・耳鳴・めまい
第22章 嗅(I)神経・舌咽(IX)神経・迷走(X)神経・副(XI)神経・舌下(XII)神経
第23章 単神経障害と多発性単神経障害
第24章 多発性神経障害
第25章 意識障害
第26章 頭痛
第27章 失神
第28章 てんかん発作
第29章 認知症
第30章 神経因性膀胱と神経因性排便障害
第31章 神経疾患と間違われやすい症状徴候
第32章 脳卒中
第33章 ミオパチー
第34章 筋ジストロフィーと代謝性筋疾患
第35章 神経筋接合部疾患と周期性四肢麻痺
消化器
第36章 腹痛
第37章 消化管出血
第38章 食欲不振・嘔気・嘔吐・呑気症
第39章 腹部診察時の身体所見
第40章 食道と嚥下に関する障害
第41章 下痢(総論)
第42章 下痢(各論)
第43章 膵臓の非内分泌性疾患
第44章 肝臓の身体所見
第45章 黄疸
第46章 ベッドサイドでの肝機能評価
第47章 胆道系
内分泌
第48章 甲状腺
第49章 副腎皮質と副腎皮質機能不全
第50章 副腎と高血圧
第51章 視床下部と下垂体
第52章 男性性腺機能の臨床的評価
第53章 卵巣
筋骨格
第54章 関節の診察
第55章 関節炎
第56章 背部痛
皮膚
第57章 皮膚科診断学の基礎
第58章 表皮の異常
第59章 真皮と皮下脂肪組織の異常
血液
第60章 脾臓
第61章 リンパ節
第62章 出血の異常
第63章 血小板異常による出血
第64章 血管性紫斑病
第65章 凝固異常による出血
体液・電解質など
第66章 体液・電解質・酸塩基平衡の異常
第67章 浮腫
第68章 ビタミン欠乏症とビタミン中毒
身体所見チャート
索引
書評
開く
臨床医学の天才によるジェネラリスト必読の書
書評者: 宮城 征四郎 (群星沖縄臨床研修センター長)
このたび,医学書院から『Dr.ウィリス ベッドサイド診断』という臨床医学書が出版された。監訳は京都の洛和会音羽病院院長の松村理司先生が担当し,実際には若い医師たちが関わって翻訳に汗を流した力作である。最後の索引欄まで合わせると実に700ページに迫る,すぐにベッドサイドで役立つ臨床本である。
Dr. Willisは知る人ぞ知る臨床医学の天才である。評者の45年余りの医師人生の中でも,彼のような臨床の天才にめぐり合えたことは誠に幸せと思う。評者は,沖縄県立中部病院時代,内科指導医としてカナダから赴任してきた彼と30代の頃に5年間,共に過ごした経験がある。彼はそのころ,既に40代半ばであった。ボルネオのジャングルで開業した経験もあるらしい。
実は彼は医師であると共にキリスト教の伝道師でもある。伝道の傍ら医学を勉強したという経歴の持ち主である。世界のどこにでも出かけ,伝道の傍ら医学を教育する毎日であったという。共に過ごした5年の後,彼はロックフェラー医療団の一員としてエチオピア大学に赴任し,臨床を指導していたと聞く。
その後,当時舞鶴市民病院で教育指導に当たっていた松村先生のたっての願いを聞き入れて,再び日本に来たわけである。松村先生とは5年ほど共に過ごしたと聞いている。そういうご縁もあって,彼の個人的な臨床指導書が松村先生一派によってこのたび翻訳の運びとなり,出版されたのが本書である。
その原書がかつて出版されたという話を筆者は聞いたことはない。したがって,日本語になった本書こそが,日の目を見ることになったおそらく最初であろう。
評者は,沖縄県立中部病院時代は呼吸器疾患を中心とした臨床に携わっていたので,当時,彼の指導書に触れたのは呼吸器疾患に限られていたのであるが,ここに記されている内容を見ると呼吸器,循環器,神経,消化器,内分泌,筋骨格,皮膚,血液,体液・電解質すべてに及び,記載がないのは免疫,感染症,腎臓・膠原病などごくわずかな項目のみである。
しかし,これらの項目についての記載がないからといって,彼がこの分野について不得手であったわけではないと思う。常々彼は筆者に免疫部門だけは新しい学問なので十分にはまだ追いついていないと,口癖のように言っていたことを思い出す。そういう意味では彼は本当の今で言う「ジェネラリスト」であり,彼が記載している各項目に目を通してみると,われわれ日本で専門家と自認している医師にとって驚くべき内容が記載されているのを見出す。例えばバイタルの解釈では血圧だけの数値症例を10ほど述べているが,それだけから臨床診断が成されていて,生理学を究めていなければ,到底,われわれには思いつかない診断名が挙げられている。
専門家各自が自分の分野の項目に目を通すだけで,彼の臨床家としての天才ぶりが分かるはずだし,また,勉強を通じて1人の医師が,その人生において,これだけ広い分野の知識と技術を習得できることのモデルとして,この本を読むことには大きな意味がある。
ことに内科のジェネラリストを目指している若い人々には必読の書である。筆者は自信をもってここに推薦する。
超一流臨床医学教育者の教えをすべての臨床医に
書評者: 伴 信太郎 (名大教授・総合診療部)
ウィリス先生(Dr. G. Christopher Willis)のご高名には,本書の監訳者である松村理司氏の興味深い逸話の紹介を通して10年以上前から接していた。そのウィリス先生が「医学生や若い医師に臨床診断を教えるために作ったノートをまとめたもの」(「 」は著書からの引用)が本書である。ウィリス先生のことを少しでも知っている人(評者のように直接お会いしたことはないが評判は聞いていたという人がおそらく多いと思う)にとっては,垂涎の書といってよい。
本書は,外来のテーブルにおいて症候に応じた鑑別診断を探したり,一冊を始めから終わりまで読み通したりするタイプの本ではない。一例をじっくり症例検討する時に,本書の関連箇所を開くと,ウィリス先生の「ほぼ50年に及ぶ臨床医としての経験が凝集されている」アドバイスに接することができる。少し時間的余裕がある時でないと読みこなせない深さがある。
本書を魅力ある書に仕上げているのは,訳者の並々ならぬ努力によるところも大きい。通称ウィリスノートを原本として日本語訳を終えた後にウィリス先生と連絡を取ったら,「先生が引退後も独りでコツコツと原稿の改訂作業を続けておられたことが判明したため,最終版の原稿を入手して翻訳を全面的にやり直した」という。さらには非常に詳しい脚注が付けてある。本文だけでは高度に過ぎる内容だが,この脚注のために本書が医学生や研修医にも役立つものとなっている。評者が知らなかった症候も,ほとんど脚注で補われていた。
「地位にも名誉にも全く興味はない」超一流の臨床医学教育者の教えを,日本全国の多くの臨床医が受けることが可能になったことを心から喜ぶとともに,訳者の皆さんの努力に対して深い敬意を表する。
医学生から,ベテランの医師まで,ウィリス先生のことを知らなかった人にも,ぜひ手にとってほしい書である。息の長いベストセラーになる本だと思う。
日常診療で広く活用できる名著
書評者: 日野原 重明 (聖路加国際病院名誉院長・理事長)
今般,医学書院から『Dr.ウィリス ベッドサイド診断――病歴と身体診察でここまでわかる!』という非常に魅力のある内科書,あるいは総合医学書ともいうべき書が出版された。著者ウィリス先生は長年カナダはマギル大学医学部の救急医療部の教授を務められた方であるが,日本が非常に好きで,日本の医学生や研修医の卒後研修に非常に興味を持ち,1986年,私の勧めにより舞鶴市民病院で研修医教育を引き受けられた,いわば日本の卒後教育のモデルを作った人である。
ウィリス先生は一時沖縄県立中部病院の指導医として勤めていたが,ちょうどその頃,私の息子が慶応義塾大学医学部卒業後に中部病院でインターンをしており,彼の患者中心の医療とその人格に非常に大きな影響を受けたようである。
ウィリス先生は日本での医学教育,特にプライマリ・ケアや外来受診時の診察のコツや患者への接し方を舞鶴市民病院で身をもって教えられたのであり,毎日の早朝のカンファレンスで医のサイエンスとアートとを教えられたのであった。つまり,やはりマギル大学医学部の出身で,後にジョンズ・ホプキンズ大学病院の内科主任教授となったWilliam Oslerとそっくりの臨床指導をウィリス先生はされたのであった。
本書の監訳をされたのは,長年同じ病院で働いた,当時内科医長であった松村理司医師である。本書は,呼吸器,循環器,その他の各系統について,診断学のABC,または診療術が極めて詳しく,しかも要領よく解説されており,医学生や研修医にとっては何よりもよい手引きとなる教科書である。
各系統についての診察の解説とともに主な病気の診察術や主な症状についての解説もされている。さらにまた体液電解質についての章もあり,浮腫やビタミン欠乏などについても解説されている。脚注には病名や症状や薬剤検査値についての解説が書かれている。特にほとんどすべての疾患についての解説が脚注の欄にも書かれていることは,編集の努力によるものと思う。
医学生,研修医ならびに第一線で開業する臨床医や救命救急センターで働く医師に,広くその日常の診療上活用される名著であることを述べておきたい。
一読三嘆,噛みしめるほどに味が出る
書評者: 野口 善令 (名古屋第二赤十字病院救急・総合内科部長)
20年以上も前,評者が市中病院から大学医局に帰局して,臨床医としての生き方に悩んでいた頃,舞鶴にDr.ウィリスというすごい先生がいるといううわさを聞いた。結局は,噂を聞いただけで舞鶴に出向くこともなく,Dr.ウィリスにお会いすることもなく終わってしまった。一期一会というが,会いたいと思った人には会っておくものだと後で後悔した。
このたび,医学書院から,『Dr.ウィリス ベッドサイド診断――病歴と身体診察でここまでわかる!』が松村理司先生の監訳で上梓された。本書は,Dr.ウィリスが,医学生や若い医師に教えるために作った秘蔵のウィリスノートを編集・翻訳したものである。Dr.ウィリスにお会いすることはかなわなかったが,松村先生らのご尽力でこうしてDr.ウィリスの余香を拝することができるようになったのはありがたいことである。
手にとって読んでみると,緻密な観察と鋭い洞察力によって得られたclinical pearlがあちこちにちりばめられて光っている。「そうだったのか」「そうだよな」という発見が随所にある。
たとえば,黄疸について「痒みの発生する原因は,皮膚に胆汁酸塩が蓄積するためだと考えられている。胆汁酸塩は肝臓で合成されるがそのためにはある程度の(良好な)肝機能が必要である。つまり,痒みは,患者の肝機能が胆汁酸塩の合成が可能な程度には保たれており,主たる問題は胆汁うっ滞にある,ということを示しているのである」と書かれている。「なるほど,だから,肝硬変の黄疸は痒くないのか」と納得する。
臨床的問題に対する体系的なアプローチについても,多発性神経障害の項目にこう書いてある。
1.患者を大きな5つのグループのどれかにあてはめる。
*遺伝性神経障害
*重金属・毒素・産業化学物質・アルコールへの曝露
*薬剤性神経障害
*種々の基礎疾患に伴う多発性神経障害
*急性(ギラン―バレー症候群)または慢性の炎症性脱髄性多発神経根障害
2.臨床症候の時間的経過を調べる。
3.運動・感覚・運動感覚混合性・自律神経性の神経症候を探し,その分布パターンを確認する。
4.細い線維主体の障害か? 太い線維主体の障害か? それとも混合性か?
5.軸索障害か? 髄鞘障害か? 神経細胞障害か?
本文の内容は各項目の最後に分かりやすくフローチャートにしてまとめられている。しびれの診断は,専門外のほとんどの臨床医にとって苦手なものであるが,この内容に従って話を聞いて診察するのみで見当がついてしまうだろう。あまりに細かすぎず,特殊検査を乱発せずにすむという点も,筆者のように総合内科と称して診療を行っている人間にはありがたい。
一読三嘆,非常に面白く読ませていただいたが,何回読んでも新しい発見があるだろう。病歴と身体診察について,噛みしめるほどに味の出る1冊である。
最後に,蛇足であるが,sensitivity鋭敏度,specificity特異性と訳されているが,これは感度・特異度の方がとおりがよいだろう。
書評者: 宮城 征四郎 (群星沖縄臨床研修センター長)
このたび,医学書院から『Dr.ウィリス ベッドサイド診断』という臨床医学書が出版された。監訳は京都の洛和会音羽病院院長の松村理司先生が担当し,実際には若い医師たちが関わって翻訳に汗を流した力作である。最後の索引欄まで合わせると実に700ページに迫る,すぐにベッドサイドで役立つ臨床本である。
Dr. Willisは知る人ぞ知る臨床医学の天才である。評者の45年余りの医師人生の中でも,彼のような臨床の天才にめぐり合えたことは誠に幸せと思う。評者は,沖縄県立中部病院時代,内科指導医としてカナダから赴任してきた彼と30代の頃に5年間,共に過ごした経験がある。彼はそのころ,既に40代半ばであった。ボルネオのジャングルで開業した経験もあるらしい。
実は彼は医師であると共にキリスト教の伝道師でもある。伝道の傍ら医学を勉強したという経歴の持ち主である。世界のどこにでも出かけ,伝道の傍ら医学を教育する毎日であったという。共に過ごした5年の後,彼はロックフェラー医療団の一員としてエチオピア大学に赴任し,臨床を指導していたと聞く。
その後,当時舞鶴市民病院で教育指導に当たっていた松村先生のたっての願いを聞き入れて,再び日本に来たわけである。松村先生とは5年ほど共に過ごしたと聞いている。そういうご縁もあって,彼の個人的な臨床指導書が松村先生一派によってこのたび翻訳の運びとなり,出版されたのが本書である。
その原書がかつて出版されたという話を筆者は聞いたことはない。したがって,日本語になった本書こそが,日の目を見ることになったおそらく最初であろう。
評者は,沖縄県立中部病院時代は呼吸器疾患を中心とした臨床に携わっていたので,当時,彼の指導書に触れたのは呼吸器疾患に限られていたのであるが,ここに記されている内容を見ると呼吸器,循環器,神経,消化器,内分泌,筋骨格,皮膚,血液,体液・電解質すべてに及び,記載がないのは免疫,感染症,腎臓・膠原病などごくわずかな項目のみである。
しかし,これらの項目についての記載がないからといって,彼がこの分野について不得手であったわけではないと思う。常々彼は筆者に免疫部門だけは新しい学問なので十分にはまだ追いついていないと,口癖のように言っていたことを思い出す。そういう意味では彼は本当の今で言う「ジェネラリスト」であり,彼が記載している各項目に目を通してみると,われわれ日本で専門家と自認している医師にとって驚くべき内容が記載されているのを見出す。例えばバイタルの解釈では血圧だけの数値症例を10ほど述べているが,それだけから臨床診断が成されていて,生理学を究めていなければ,到底,われわれには思いつかない診断名が挙げられている。
専門家各自が自分の分野の項目に目を通すだけで,彼の臨床家としての天才ぶりが分かるはずだし,また,勉強を通じて1人の医師が,その人生において,これだけ広い分野の知識と技術を習得できることのモデルとして,この本を読むことには大きな意味がある。
ことに内科のジェネラリストを目指している若い人々には必読の書である。筆者は自信をもってここに推薦する。
超一流臨床医学教育者の教えをすべての臨床医に
書評者: 伴 信太郎 (名大教授・総合診療部)
ウィリス先生(Dr. G. Christopher Willis)のご高名には,本書の監訳者である松村理司氏の興味深い逸話の紹介を通して10年以上前から接していた。そのウィリス先生が「医学生や若い医師に臨床診断を教えるために作ったノートをまとめたもの」(「 」は著書からの引用)が本書である。ウィリス先生のことを少しでも知っている人(評者のように直接お会いしたことはないが評判は聞いていたという人がおそらく多いと思う)にとっては,垂涎の書といってよい。
本書は,外来のテーブルにおいて症候に応じた鑑別診断を探したり,一冊を始めから終わりまで読み通したりするタイプの本ではない。一例をじっくり症例検討する時に,本書の関連箇所を開くと,ウィリス先生の「ほぼ50年に及ぶ臨床医としての経験が凝集されている」アドバイスに接することができる。少し時間的余裕がある時でないと読みこなせない深さがある。
本書を魅力ある書に仕上げているのは,訳者の並々ならぬ努力によるところも大きい。通称ウィリスノートを原本として日本語訳を終えた後にウィリス先生と連絡を取ったら,「先生が引退後も独りでコツコツと原稿の改訂作業を続けておられたことが判明したため,最終版の原稿を入手して翻訳を全面的にやり直した」という。さらには非常に詳しい脚注が付けてある。本文だけでは高度に過ぎる内容だが,この脚注のために本書が医学生や研修医にも役立つものとなっている。評者が知らなかった症候も,ほとんど脚注で補われていた。
「地位にも名誉にも全く興味はない」超一流の臨床医学教育者の教えを,日本全国の多くの臨床医が受けることが可能になったことを心から喜ぶとともに,訳者の皆さんの努力に対して深い敬意を表する。
医学生から,ベテランの医師まで,ウィリス先生のことを知らなかった人にも,ぜひ手にとってほしい書である。息の長いベストセラーになる本だと思う。
日常診療で広く活用できる名著
書評者: 日野原 重明 (聖路加国際病院名誉院長・理事長)
今般,医学書院から『Dr.ウィリス ベッドサイド診断――病歴と身体診察でここまでわかる!』という非常に魅力のある内科書,あるいは総合医学書ともいうべき書が出版された。著者ウィリス先生は長年カナダはマギル大学医学部の救急医療部の教授を務められた方であるが,日本が非常に好きで,日本の医学生や研修医の卒後研修に非常に興味を持ち,1986年,私の勧めにより舞鶴市民病院で研修医教育を引き受けられた,いわば日本の卒後教育のモデルを作った人である。
ウィリス先生は一時沖縄県立中部病院の指導医として勤めていたが,ちょうどその頃,私の息子が慶応義塾大学医学部卒業後に中部病院でインターンをしており,彼の患者中心の医療とその人格に非常に大きな影響を受けたようである。
ウィリス先生は日本での医学教育,特にプライマリ・ケアや外来受診時の診察のコツや患者への接し方を舞鶴市民病院で身をもって教えられたのであり,毎日の早朝のカンファレンスで医のサイエンスとアートとを教えられたのであった。つまり,やはりマギル大学医学部の出身で,後にジョンズ・ホプキンズ大学病院の内科主任教授となったWilliam Oslerとそっくりの臨床指導をウィリス先生はされたのであった。
本書の監訳をされたのは,長年同じ病院で働いた,当時内科医長であった松村理司医師である。本書は,呼吸器,循環器,その他の各系統について,診断学のABC,または診療術が極めて詳しく,しかも要領よく解説されており,医学生や研修医にとっては何よりもよい手引きとなる教科書である。
各系統についての診察の解説とともに主な病気の診察術や主な症状についての解説もされている。さらにまた体液電解質についての章もあり,浮腫やビタミン欠乏などについても解説されている。脚注には病名や症状や薬剤検査値についての解説が書かれている。特にほとんどすべての疾患についての解説が脚注の欄にも書かれていることは,編集の努力によるものと思う。
医学生,研修医ならびに第一線で開業する臨床医や救命救急センターで働く医師に,広くその日常の診療上活用される名著であることを述べておきたい。
一読三嘆,噛みしめるほどに味が出る
書評者: 野口 善令 (名古屋第二赤十字病院救急・総合内科部長)
20年以上も前,評者が市中病院から大学医局に帰局して,臨床医としての生き方に悩んでいた頃,舞鶴にDr.ウィリスというすごい先生がいるといううわさを聞いた。結局は,噂を聞いただけで舞鶴に出向くこともなく,Dr.ウィリスにお会いすることもなく終わってしまった。一期一会というが,会いたいと思った人には会っておくものだと後で後悔した。
このたび,医学書院から,『Dr.ウィリス ベッドサイド診断――病歴と身体診察でここまでわかる!』が松村理司先生の監訳で上梓された。本書は,Dr.ウィリスが,医学生や若い医師に教えるために作った秘蔵のウィリスノートを編集・翻訳したものである。Dr.ウィリスにお会いすることはかなわなかったが,松村先生らのご尽力でこうしてDr.ウィリスの余香を拝することができるようになったのはありがたいことである。
手にとって読んでみると,緻密な観察と鋭い洞察力によって得られたclinical pearlがあちこちにちりばめられて光っている。「そうだったのか」「そうだよな」という発見が随所にある。
たとえば,黄疸について「痒みの発生する原因は,皮膚に胆汁酸塩が蓄積するためだと考えられている。胆汁酸塩は肝臓で合成されるがそのためにはある程度の(良好な)肝機能が必要である。つまり,痒みは,患者の肝機能が胆汁酸塩の合成が可能な程度には保たれており,主たる問題は胆汁うっ滞にある,ということを示しているのである」と書かれている。「なるほど,だから,肝硬変の黄疸は痒くないのか」と納得する。
臨床的問題に対する体系的なアプローチについても,多発性神経障害の項目にこう書いてある。
1.患者を大きな5つのグループのどれかにあてはめる。
*遺伝性神経障害
*重金属・毒素・産業化学物質・アルコールへの曝露
*薬剤性神経障害
*種々の基礎疾患に伴う多発性神経障害
*急性(ギラン―バレー症候群)または慢性の炎症性脱髄性多発神経根障害
2.臨床症候の時間的経過を調べる。
3.運動・感覚・運動感覚混合性・自律神経性の神経症候を探し,その分布パターンを確認する。
4.細い線維主体の障害か? 太い線維主体の障害か? それとも混合性か?
5.軸索障害か? 髄鞘障害か? 神経細胞障害か?
本文の内容は各項目の最後に分かりやすくフローチャートにしてまとめられている。しびれの診断は,専門外のほとんどの臨床医にとって苦手なものであるが,この内容に従って話を聞いて診察するのみで見当がついてしまうだろう。あまりに細かすぎず,特殊検査を乱発せずにすむという点も,筆者のように総合内科と称して診療を行っている人間にはありがたい。
一読三嘆,非常に面白く読ませていただいたが,何回読んでも新しい発見があるだろう。病歴と身体診察について,噛みしめるほどに味の出る1冊である。
最後に,蛇足であるが,sensitivity鋭敏度,specificity特異性と訳されているが,これは感度・特異度の方がとおりがよいだろう。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。