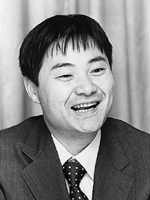| ●しりあす・とーく | |||||||||
第17回テーマ
内科ローテーションで何を学ぶか?
(前号よりつづく)
鳥居 まず産婦人科・精神科についてですが,選択科としてはとてもいい研修になるものの,必修科としての意義に疑問を感じていた人が大半を占めていたように思います。それはその2つの科,特に産婦人科は中でも専門性が特化された部分がかなり強いためであり,正常分娩ひとつとってもしっかりとした対処ができるようになるのは1カ月ではかなり厳しいと思いました。若い女性の腹痛のプライマリケアということに関していえばとても重要なことだと思いましたが,総じて回ったことで自分でできるようになることというのは,他の科と比べて少ないのではないかと思います。また,指導医側からしても1カ月間という短い期間のなかでこの専門性の高い分野での指導はとても大変ではないかと思います。この点でいえば,産婦人科を選択科の一つとしてしまい,自分の学びたい選択科の期間を長めに設定するのもいいのではないかと思いました。 次に精神科についてですが,回る前は,「なぜ精神科を必修科として回らなくてはいけないのか」というのが本音で,精神科を必修化にした意味が私もよくわかりませんでした。しかし,実際に回ってみて,うちの病院(横浜市立市民病院)が精神科の研修に力を入れてくださっていたことが幸いしていたのですが,内科一般での患者さんのアプローチの仕方として染みついていたものと違って,心理面からのアプローチに接することができ,「こういうアプローチもあるんだ」と驚き,また,すごく勉強になり必修科にした意味がよくわかりました。 最後に小児科ですが,いわずもがな小児はどこの科でも必ず接しますし,短期間でプライマリケアを習得しやすいため必修科で全く異論はなく,皆技術や知識を習得するのに非常にモチベーションは高かったように思いました。 上記3科を必修科として比較してみた場合,研修の必修科に必要な要素は内容だけではなく,「プライマリケアを限られた短期間で自分ができるように習得することができる科目」といった要素も兼ね備えている必要があると感じました。 学びが多かった精神科での研修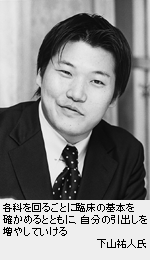 前野 具体的に,どういうところが勉強になったのですか。 前野 具体的に,どういうところが勉強になったのですか。
鳥居 例えば,精神科では話の聞き方から違いました。精神的にまいってしまっている人の場合,家族から話を聞くのか,本人から話を聞くのかという,根本的なところからスタートしているところが内科と違っていました。内科でも高齢者の方では,家族から聞いたほうが早いということがあるのですが,精神科の場合は,年齢が若くても本人からは客観的な病歴聴取ができないということが多いため家族からまずは話を聞いてみる,といったほかの科とは少し異なるアプローチの仕方をしなくてはなりません。年齢にかかわらず,まず家族か本人のどちらから話を聞くべきかということから考えなくてはなりません。 それに,最初はどういうことを話していったらいいのか,どんなことを言ってはいけないのかという詳細がわからず,何かちょっと言ったことに対しても問題が起きるのではないかといった不安もありました。これはやはり学生実習の頃にはなかったことだと思います。そういう意味で,精神科研修でのすべてが新鮮でした。 普段出会わない患者さんを診る 前野 下山先生はどうですか。 前野 下山先生はどうですか。
下山 やはりこれらのローテーションに共通して特徴的なのは,普段出会わない人たちと出会う場所であるということで,それは鳥居先生のおっしゃるとおりだと思います。 湘南鎌倉総合病院の小児科の場合ですと,働く場所が3つありまして,1つ目は産科の新生児室で,新生児の診察と採血の係,そして小児ERといって,朝から晩までERにくる子どもを診る係,それとは別に小児科外来があって,小児の病棟番という役割があります。うちの小児科にはNICUもないし,重症の場合は近隣の医療機関に送ることになります。普段は5~6人,冬でも10人ぐらいの小規模な病棟です。その3つの場所を,3人ぐらいの研修医が必ず2か月間回ります。 小児科というのは,子どもと遊べて,可愛らしさに癒されるような現場だけでなくて,時として,症状が激変してしまうようなこともあって,自分ではなくて,もっと実力のある人だったらなんとかなるのではないかというような葛藤を感じたこともありました。 産婦人科の場合に特徴的なのは,アクティブバースといって,好きな格好で産むというお産で,天井から綱が下がっていて,それにぶら下がって立って産む人もいれば,四つんばいで産む人もいるし,基本的には布団の上で産むんです。ですから,お産のときは「暗い」「見えない」といって,汗をかきながらほんとうに大変な思いをするわけです(笑)。 臨床の基本を学ぶ,職業人としての基本を学ぶ 下山 そのなかで――すべての科にいえることですが――,早く現場で働けるように,悪く言えば兵隊になることが要求されるので,皆,基本的なことを早く学ぼう,危ないことを拾うようにしようと勉強するわけです。最初は指導医にくっついていますが,2~3週間で難しい症例でなければ1人でやってみて,「何かあったら呼びなさい」という形式です。 下山 そのなかで――すべての科にいえることですが――,早く現場で働けるように,悪く言えば兵隊になることが要求されるので,皆,基本的なことを早く学ぼう,危ないことを拾うようにしようと勉強するわけです。最初は指導医にくっついていますが,2~3週間で難しい症例でなければ1人でやってみて,「何かあったら呼びなさい」という形式です。
それぞれの科に特徴的なことがいろいろあると思うのですけれども,私の場合は,臨床の基本を2年目で語るのはおかしいかもしれませんが,どの科に行っても臨床の基本というのは共通していて,詳細なアナムネとphysical examinationで決まって,そこから鑑別疾患を考えていくものだと思いました。治療のアプローチは,やはり患者とよく向かい合ったところで生まれてくるものではないかということが,すべての科で共通していたと思います。あとは,各科で,早くそこの職業人になろうという姿勢で取りくんでいければなんとかなると…。 ですから,臨床の基本を確認することと,その場での職業人になる,自分がそこでのコマにどうなるかということも考える必要がある。また,ローテーション中に,その科での自分の目標をもつことも大切だと思います。小児科だったら,川崎病を論じるところまではいけないだろうけれども,最低でも川崎病の診断や小児の脳炎や肺炎の鑑別については語れるようになる。産婦人科だったら,正常分娩の入り口ぐらいまでは語れるようになるということです。 (つづきは本誌をご覧ください)
|
 前野 新医師臨床研修制度では,小児科,産婦人科,精神科,そして,地域・保健医療が必修科目としてローテーションのなかに位置づけられました。そこで何をどう学んだか,また,その研修の中身はどうあるべきかということについてうかがいたいと思います。まず,小児科,産婦人科,精神科についていかがでしょうか?
前野 新医師臨床研修制度では,小児科,産婦人科,精神科,そして,地域・保健医療が必修科目としてローテーションのなかに位置づけられました。そこで何をどう学んだか,また,その研修の中身はどうあるべきかということについてうかがいたいと思います。まず,小児科,産婦人科,精神科についていかがでしょうか?