| ●日常診療の質を高める口腔の知識 | |
|
第4回 歯垢はバイオフィルム 岸本裕充(兵庫医科大学歯科口腔外科学) 口内炎,ドライマウス,歯肉出血と,口腔に生じやすいトラブルについてお話を進めてきました。今月は,むし歯・歯周病の原因となり,さらに誤嚥性肺炎との関連も注目されている「歯垢」についてのお話です。 ■むし歯・歯周病の原因となる歯垢とは内科領域でプラークと言えば,「冠動脈の『プラーク』に破綻をきたし」などと,動脈硬化を起こした血管における「粥腫」・「粥状硬化巣」が頭に浮かぶと思いますが,歯科領域では「歯垢」・「デンタルプラーク(dental plaque)」のことを指します。最近はテレビの歯ブラシや歯磨剤のCMでも「プラークコント-ル」という表現が使われるようになり,すっかり市民権を得た印象があります。本稿では,特に断わりのない限り,歯科領域での習慣に従って,歯垢あるいはデンタルプラークを単に「プラーク」と略させていただきます。
プラークは乳白色で,歯に似た色調であることから,見落とされがちです。しかし,歯垢染色液を用いると,特別な器具も必要なく簡単に明示できます(図1)。むし歯菌・歯周病菌などを含め,多種・多量の菌を含んでいます。その濃度は「1gあたり1011(1,000億)」のオーダーで,糞便に匹敵するレベルです。 ■バイオフィルムとはバイオフィルムをご存じでしょうか? 直訳して「生物膜」とするとますます意味不明ですが,簡単に説明しますと,「あらゆるものの表面に,菌が排泄するスライム(ネバネバ成分)によって層をなして堆積している状態」と定義できます。浴槽のヌルヌルはまさにバイオフィルムの代表です。菌を培養するためのフラスコ内では,菌は浮遊状態でバラバラですが,生体も含め自然界では,大部分の菌がバイオフィルムの形で「共同体」を形成して棲息しているのです。 バイオフィルムのネバネバへの吸着を応用し,水質の改善など「有益」に作用することもありますが,医療の現場ではバイオフィルムは「悪者」になることが多く,主に2つのパターンで問題になります。1つは人工物表面に形成されることで,そしてもう1つは難治性慢性疾患の原因としてです。前者の代表が中心静脈カテーテルであり,後者ではびまん性汎細気管支炎(diffuse panbronchiolitis:DPB)や慢性骨髄炎,慢性副鼻腔炎などを挙げることができます。 ■プラークはバイオフィルムバイオフィルムについてのイメージが湧いてきたと思いますが,プラークもバイオフィルムそのものなのです。プラークを例に,バイオフィルムの性質を整理し,その対策も含めて考えてみましょう。。。(つづきは本誌をご覧ください)
|
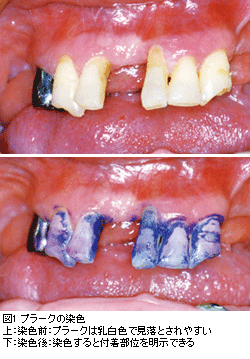 「むし歯・歯周病の原因はプラークである」という事実,そして「プラークコントール(狭義には歯みがきによるプラークの除去)で,むし歯・歯周病の予防が可能である」ということについても,誰も驚かれないと思います。しかし,「むし歯・歯周病の原因菌はそれぞれ異なる」,さらに「歯みがきの方法も異なる」という話となると,みなさんが毎日している歯みがきであるにもかかわらず,かなり怪しくなってくるのではないでしょうか? これについては後述します。
「むし歯・歯周病の原因はプラークである」という事実,そして「プラークコントール(狭義には歯みがきによるプラークの除去)で,むし歯・歯周病の予防が可能である」ということについても,誰も驚かれないと思います。しかし,「むし歯・歯周病の原因菌はそれぞれ異なる」,さらに「歯みがきの方法も異なる」という話となると,みなさんが毎日している歯みがきであるにもかかわらず,かなり怪しくなってくるのではないでしょうか? これについては後述します。