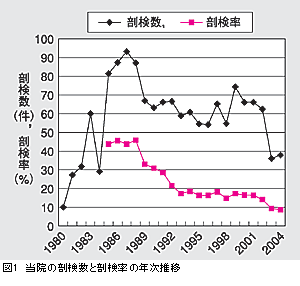| ●病理との付き合い方 病理医からのメッセージ | |||
第2回テーマ
森永正二郎氏(元 東京都済生会中央病院病理科,現 北里研究所病院病理科)が大衆月刊誌に『誰も知らない「病理医」の話』を発表して以来,もう10年以上になるが,いまだに病理医と聞いても料理(?)医と首をかしげたり,病院で何をしている医師(?科)なのかについて知らない人が多いことを実感する。ところが50年近く前にすでに,病理医(病理学者)を主人公としたアーサー・ヘイリー作の小説『最後の診断』(永井 淳訳,新潮文庫,1975年,残念ながら絶版)が発表されている。あらためて読み返してみると,日本の病理医を取り巻く現状とほとんど変わっていないことに気づく。前回の『医療のなかの病理学』で説明されたように,病理医は患者の病理診断を下すことが最も重要な務めである。そして,多くの病理医は組織標本を見ながらいつも患者のことを思い浮かべつつ診断している。ところが,目の前にその患者がいないので,患者のために病理診断を行ったと言っていても,本当は実感が乏しいことも否定はできない。もしも,患者から病理診断の説明を病理医に求められることが一般化すれば,「われわれ病理医は患者のためにいったい何ができるのか」を今以上に親身になって考えるのではなかろうか。それがひいては病理部門が臨床標榜科につながっていくものと信じている。本稿では,他の執筆者の内容とあまり重複しないように,日常の一般病院での病理医の姿を通して病理医の現状を説明し,病理と病理医の魅力について述べてみたい。 ■病理医の定義と現状1. 病理医とは病理医(pathologist)とはその名の通り,「病理学」を専門にする医師である。病理医も大学の医学部を卒業し,医師国家試験に合格して医師免許証をもち,患者に医療行為を施すことが法的に許されている。一方,病理学(pathology)とは,「病気で異常になったところ(病変部という)を目で見て(肉眼的観察),顕微鏡でさらに詳しく見て(顕微鏡的観察),どういう状態なのかを論理的に記述する学問」である。この手法を形態学(morphology)ともいう。つまり,病理医は病変部の形態学的異常を見つけて,病気の診断(病理診断)をする医師である。もしも何科の医師かと聞かれれば,内科や外科といったおなじみの科ではないけれども,近い将来「病理診断科(仮)」と胸を張っていえるときが来ることを心待ちにしている。具体的な形態学的診断手法については,次回から詳しく述べられるのでここでは省略する。その形態学的診断手法を用いて病理医が正しい病理診断をするためには,その病気の原因,診断,検査,経過,治療,予後,予防などにも幅広く理解を深めていることが必要である。しかし,一人の医師が全科領域の最先端をすべて理解することは日進月歩の著しい医学,医療の世界においてとても不可能である。そうはいっても,いろいろな病気についてある程度総合的に理解することは,病理医には可能であると考えている。なぜかというと,病理医は全科の病理検体(注1)を扱い,剖検で全身の病態診断を組み立てることに慣れているからである。 2. 病理医の現状次に,病理医のマンパワー(人員)の現状をみてみたい。全国で1,901名(2005年1月現在)の病理専門医がいるなかで,大学の病理学教室や大学病院病理部,国立がんセンターや国立循環器病センターなどの高度先進医療が可能な施設では病理医が10人前後雇われているところもあるが,地域の一般総合病院では500床を超えても1~2人(当院は527床で病理医2名)しかいないところも決して少なくない。いわゆる「一人病理医」が質の高い病理診断を行うためにぎりぎりのところで孤軍奮闘している施設も多いというわけだ。■病理診断の3つの柱病理医の仕事は病理診断と述べたが,それには,(1)病理解剖(剖検),(2)生検標本や手術摘出標本の病理組織診断(組織診),(3)細胞診断(細胞診)の3つの大きな柱がある。当院の現状を示しながら,順に述べる。1. 病理解剖(剖検;autopsy)「系統解剖」,「司法解剖」,「病理解剖」の3種類ある解剖の一つである病理解剖は,死体解剖保存法によって,死体解剖資格認定を受けた者に許可されている。無許可で勝手に死体にメスを入れると死体損壊罪に問われる。病理解剖すると,臨床科と病理部門間で討論会をすることも一般に行われている。これを臨床病理カンファレンス(clinico-pathological conference:CPC)という。生前の臨床診断や治療が適切であったかどうかを病理解剖で検証することが目的であり,病理診断が「最後の診断」と言われてきたゆえんである。ただし,最近は診断技術が進歩し,両者の診断が大きく食い違うことはほとんどなくなり,剖検数や剖検率が低下してきたことの大きな理由の一つにもなっている。当院でもその傾向が現れている(図1)。しかし,病理解剖の意義が決して薄れてきたわけではない。岡崎悦夫氏(立川メディカルセンター立川綜合病院病理・臨床検査科)は病院のリスクマネジメント対策に病理医も積極的に参加すべきと主張して,表1のように剖検を実施すべき場合の項目をいくつか挙げている2)。2004(平成16年)度からは新卒医師には臨床研修が必修化となり,CPCレポートの提出が義務づけられたことも病理解剖の重要性がいっそう深まったとみるべきであろう。
(つづきは本誌をご覧ください) 注1:病理検体とは,病理診断(剖検,組織診,細胞診)のために患者から採取された臓器,組織,細胞(細胞が含まれる液状物を含む),異物のことである。 |