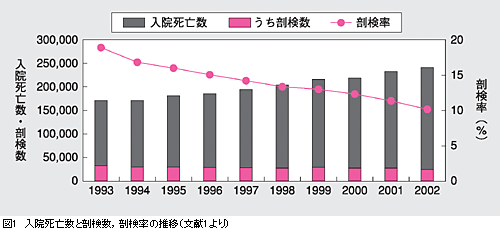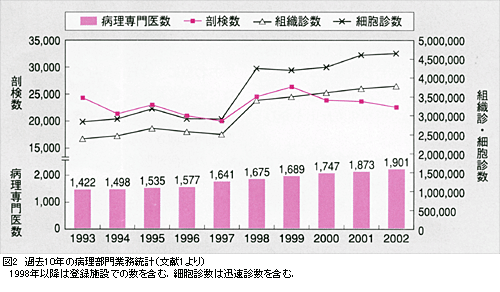| ●病理との付き合い方 病理医からのメッセージ | ||
第1回テーマ
本連載は,第一線で診断業務にあたる病理医から,臨床医,特に研修医の方々へ,病理検査について知っておいてほしいこと,病理検査の上手な使い方やレポートの読み方などを伝えることを目的にしている。前半は総論的な事項,後半は臓器別の情報を提供する予定である。
本連載が多くの読者の目に触れ,正しい診断根拠に基づく医療が臨床医と病理医の連携のもとに行われることを期待する。 診断学の要としての病理学日本人の死因統計が厚生労働省から毎年発表されるが,その第一位は悪性新生物,すなわち「がん」である。がんの診療がどのように組み立てられているかを考えてみよう。がん発見の契機は,症状を自覚しての受診と健康診断がある。自覚症状のある場合には進行がんの場合が少なくない。一方,健康診断は早期がんの発見,それに続く治療が目的である。 診断の過程では,肉眼的な腫瘍性病変の存在を確認して,病変の一部より組織あるいは細胞を採取してその性状を顕微鏡的に観察することが行われている。そして,「がん」と確認されたうえで治療の方法が検討されることになる。すなわち,「がん」の診断においては,組織学的あるいは細胞学的検索はなくてはならないものなのである。 病理学の歴史を眺めたとき,病理解剖といわれる解剖がその中心的な役割であった時代が長く続いた。そして,解剖で得られた情報をもとに病理組織学の体系が確立されてきた。すなわち,現時点の疾患と闘うために病理学が活用されたのではなく,疾患の「焼け跡」を検証することが病理学の役割だった。しかし近年になり,先に述べたように,病理学は現時点の疾患とどのように対峙するかを指し示す重要な情報を提供する分野になり,医療の後衛ではなく,前衛の一翼としての役割が求められるようになったのである。病理医の診断が「最後の診断=final diagnosis」といわれる所以はここにある。 死因統計と剖検輯報現在,世界各国で死因統計がとられており,日本でも死亡診断書・検案書をもとに統計がとられている。しかし,その正確性はどの程度のものであろうか。「心不全」「呼吸不全」などの状態像は死因には用いないようにマニュアルでは示されているが,はっきりした死因病名が臨床情報のみでは記載できない場合も少なくない。死亡順位を左右するようなことはないと考えられるが,どこまで正確なものか,バイアスは加わっていないかについては十分検討する必要がある。病理解剖による臓器の病理組織学的検索は,死因を明らかにする方法の一つである。もちろん,病理解剖(剖検,注1)をすればすべてが明らかになるものではない。しかし,より真実に近づく可能性が増すことは確かである。病理解剖は,死体解剖保存法に基づく解剖医の資格を得た医師が行うものと保健所長の許可により行われるものがある。通常は前者であり,その任務を遂行しているのが病理医である(注2)。 注1:病理解剖は「剖検」とも呼ばれる。厳密にいえば系統解剖,法医(行政・司法)解剖も剖検に含まれるが,病理解剖に比して圧倒的に数が少ないので,一般的には「剖検=病理解剖」とされる。注2:死体解剖には,病理,系統,法医解剖があり,厚生労働大臣に解剖資格を申請する際にいずれを主に行うかを届け出る必要がある。病理専門医は病理解剖の死体解剖資格を受けた後,日本病理学会の認定を受ける。 そして,病理解剖が行われた症例の詳細なデータが収載された資料が剖検輯報である。これには,全国の大学,大学関連医療機関,日本病理学会認定病院・登録施設の剖検症例が集められている。基本的なデータの登録は,各施設の病理医のボランティア的な努力によって行われており,資金的には学術振興会科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の支援を受けている。第1輯の発刊は1960年であり,2005年4月現在,第45輯までは発行されている。 国民の総死亡数は年間100万人であるが,そのうち剖検輯報に登録されているのは,その1/4にあたる入院死亡者のうち解剖が実施できた約10%のものであり,総死亡数のなかの2~3%である。入院死亡数は年々増加しているが,剖検数は減少し,結果として剖検率は低下している(図1)。
総死亡数を母数とすれば非常に少ない数ではあるが,最も正確な死因統計であり,40年以上も資料が集積しているという点でみれば,日本の保健・医療を考えるうえで非常に貴重な統計資料であるといえる。 剖検率の国際比較では,欧州では20~30%,米国では10%である。英国は剖検そのものが公衆衛生事業として位置づけられ,費用は公費で賄われており,正確な死因統計に基づいた政策作りの基礎資料となっている。欧州各国もこれに習い,高い剖検率を保っている。一方,米国では剖検費用が病院負担であり,医療施設評価合同委員会(Joint Communication on Accreditation of Healthcare Organization:JCAHO)が1971年に施設の認定基準から剖検率20%の項目を削除したこともあり,その後は激減してきた。その結果,米国では,剖検の目的と意義を明快かつ思慮深く示す技術が臨床医から失われ,患者家族が剖検同意書への署名を拒否したとされたケースの46%は,こうしたトレーニングを受けなかった医師がきちんとした説明もない(おそらくできない)まま,独断でキャンセルしていたものであったというような報告もなされており,この問題に関しては,米国病理学会が臨床医向けに教育的な指針を作成している(http://www.cap.org)。〔医学書院発行 医学界新聞第2593号(2004年7月19日),投稿「この国の剖検の行方」伊藤康太 参照〕 日本でも,病理解剖は基本的には病院負担(一体当たり25万円)である。日本内科学会認定医の研修病院における剖検率や剖検数の規定,また日本病理学会の認定病院の認定に対して,ある水準の剖検率,剖検数が数年前までは決められていた。しかし,剖検数が減ってきた事情もあり,これらの基準は次第に「緩和」されてきている。また,2004年度より実施された新医師臨床研修制度では,各研修医に対してCPC(clinico-pathological conference,clinical pathologic conference)レポートが義務化されたが,施設の剖検数あるいは剖検率に関しては特に言及していないために,剖検数の減少には歯止めはかからないと考えられる。すべての研修医が剖検例を通して学ぶ機会をもつということは,今後の医療のあり方や医学のあり方に大きな影響を及ぼす可能性を秘めており,病理医として積極的に協力していきたいと考えているが,公的な財政的支援も今後の発展のためにも重要と思われる。 病理の位置づけ歴史的にみれば,病理学は病気の本態を究明する基礎的な学問であるが,臨床医学から情報や材料を得ながら発展してきた。一方,見かたを変えれば,免疫学,血液学,感染症学,遺伝学,腫瘍学は,病理学を基盤にして発展してきた学問体系といえる。このような存在である病理学は「基礎か臨床か」という問いがある。病理学のなかでも人体病理学に基礎を置いた外科病理学・診断病理学の分野は,まさに臨床医学であり,診断の要として存在している。病院に「病理部」という部署が確立する理由がここにある。一方,病気の本態を解明するという点では,基礎的病理研究を行う実験病理の分野も重要である。この2つの分野をもつ病理部門のあり方について,診断病理の部門(病院病理部)と実験病理の部門を分離させる方式をとる大学と統合させる方式をとる大学がでてきている。いずれの方式がよいかは今後検討される事項であるが,いずれにしてもプロスペクティブに臨床医学に貢献する分野であることは間違いない。 専門分化次に,診断病理の分野における「専門分化」を考えてみる。現在,診断病理に携わる医師の資格として,日本病理学会病理専門医がある。2005年1月時点で1,901名の専門医が認定されている。病理専門医制度規定によれば,本認定を受けるためには資格試験に合格する必要があるが,受験資格を得るためには,著しく片寄らない剖検症例の執刀と診断書作成50例以上,著しく片寄らない病理組織学的診断5,000例(迅速診断50例を含む)などを経験しなければならない。きわめて広い見識を求められる資格であり,この点からみれば,病理医は「総合医」である。第一線の医療分野では,あらゆる臓器について「総合医である病理医」が診断に関与している。しかし,各臓器領域における知見の深まりもあり,総合的な研修のみでは対応が難しい分野が出てきている。 特殊な診療領域では,歯科医師の資格として口腔病理専門医がある。また,特別な資格制度はないものの,神経内科専門医,脳外科専門医あるいは皮膚科専門医の制度のなかでは,病理組織学的な素養も求められており,神経病理や皮膚病理の分野では臨床医と病理医が協力しながら運営する学会や研究会が開催されている。このような情勢のなかで,病理専門医のなかでのサブスペシャリティのあり方が日本病理学会のなかで議論されるようになってきている。 病理の業務量とマンパワー図2は過去10年の日本剖検輯報より集計した病理部門の業務統計である。剖検数は減少してきているが,生検数(組織診+細胞診)や細胞診数は大幅に増加してきている。このことは,先に述べたように病理の役割が変化していることの反映であると考えられる。
一方,ここで示した検体数は,病理医が常勤で業務をしていることが前提の施設の検体数である。矢野経済研究所の資料2)によれば,2002年度の組織検査では,総額983億5,500万円で,検査点数880点で換算すると1,118万件となる。すなわち日本全体の病理組織検査数のうち,常勤病理医の管理下で行われているのはなんと全体の20%余りで,80%は検査センターと呼ばれる衛生検査所で行われているのが実情である。病理組織検査の臨床現場への広がりを意味する指標としては意義あるものと考えるが,臨床と病理の連携が重要な医療の精度管理という点では,いろいろと問題の残る指標と思われる。 剖検輯報の業務統計資料を基礎データとして利用すると,病理医1人当たり年間,生検1,200件,細胞診1,800件,剖検12体の検体を処理していることになる。これを日本病理学会が1987年に示した病理医の業務量の指標(表1)にあてはめると,ほぼ妥当な数となっている。
一方,矢野経済研究所の資料2)によれば,病理医1人当たり,生検6,000件,細胞診7,000件となり,必要病理医数は3倍になる。すなわち,検査センターに提出されるものも含めて考えると,求められる医療内容に比して病理医数はきわめて少ないという実態がわかる。 業務量として認定病院の病理医数は妥当であるという結果が出たが,算定式には,病理の診断業務にかかるもののみしか含まれていない。実際には認定病院の病理医の役割として,カンファランスや各種管理的な会議への参加が期待されている。さらに新医師臨床研修制度では,研修医に対するCPCレポートの指導も必要になってきた。この点を考えると,一見足りているようにみられる認定病院の病理医の数も決して十分とはいえず,また,いわゆる「ひとり病理医」に対する種々のバックアップ態勢も課題になってきている。 病理のストラテジーの変遷病理組織学的検索で最も古典的な方法は組織の薄切標本のヘマトキシリンエオジン(HE)染色である。組織構造や細胞の特徴を観察し病変を解析していく方法である。これに加えて,粘液,顆粒,線維成分などを染め分ける特殊染色が行われてきた。次いで電子顕微鏡の開発・普及により,細胞内小器官の観察,細胞同士の結合の観察なども,診断の際に用いられてきた。また,免疫組織化学の進歩により,種々の細胞の性質が免疫反応を介して可視化できるようになってきた。 これらの方法論の進歩は,例えば乳癌においてHer2蛋白の存在の有無で抗がん剤ハーセプチンの使用の可否を判断するように,直接的に診療行為を左右するような結果をもたらしている。さらに,悪性リンパ腫においては,表面マーカーの免疫組織学的検索,遺伝子検索が必須になってきており,この情報が予後,治療に決定的に重要な意味をもつ状況になっている。 一方,Helicobacter pyloriの「発見」に象徴されるように,これまでHE標本で見えていたもののその病的意義がはっきりしていなかったものが,細菌学的な方法論の発展のなかで明らかになってきている。 病理組織学,種々の臨床検査医学,そして,臨床医学の情報が結合したなかでよりよい医療が実践できるようになってきたといえる。 ■おわりに今日,病理組織学的診断は疾患の治療において基礎となるものである。さまざまな臨床場面において細胞や組織が採取され,診断の専門部門に回される。そこで,診断業務に携わっているのが病理医である。一片の組織だけで診断がつくわけではなく,臨床経過をはじめとする臨床情報,肉眼所見は,正しい診断をするうえできわめて重要である。病理医は組織の先に患者像を描きながら診断を行っている。臨床各科の医師は,正しい診断を受け取り根拠に基づく医療が実践できるように,十分に病理との情報交換をしてもらいたい。 文献1) 日本病理学会(編):日本病理剖検輯報第36~45輯,日本病理剖検輯報刊行会,1995~2004 |