ICUから始める早期離床(讃井將満,長谷川隆一,高橋哲也,宇都宮明美)
対談・座談会
2013.09.02
【座談会】退院後の生活を見据えてチームで取り組むICUから始める早期離床 |
|
 |
|
|
近年,ICU患者が術後早期からリハビリテーション(以下,リハビリ)等を行う“早期離床”の取り組みが注目を集めている。早期離床が人工呼吸器離脱までの期間を短縮する等のエビデンスも明らかにされ,米国ではすでに多くの施設で推奨されているが,日本で導入に至っている施設はいまだ少ない。
本紙では,早期離床の重要性にいち早く着目して第一線で活躍するICUの医師・看護師・理学療法士の方々を迎え,チームとしてICU患者の早期離床を実践するために必要なことは何か,具体的な取り組みとともにお話しいただいた。
讃井 私がICUにおける早期離床の取り組みに注目したきっかけは,米国でICUのフェローをしていたときのことでした。気管挿管下の人工呼吸器装着中の患者が,呼吸療法士と看護師に付き添われながら廊下を歩いているのを見て,「この状態からリハビリを始められるんだ」と大きな衝撃を受けました(関連写真)。
近年の研究では,急性呼吸窮迫症候群(ARDS)から回復し退院した患者は,肺機能自体は回復しているのに,身体的能力や社会的・心理的な充足度が健常人より劣ることが示されました1)。そうしたなか,早期のリハビリによって人工呼吸患者のせん妄発生率や呼吸器装着時間が減少し,日常生活機能が早く回復することも,多施設ランダム化比較試験2)をはじめとする複数の研究で支持されています(図1)。また,深い鎮静が患者予後へ与える悪影響や,せん妄が遠隔期死亡の独立危険因子であること3)等も認識され始め,人工呼吸患者に対して「できるだけ覚醒させて早期にリハビリを」という考え方が広まりつつあります。
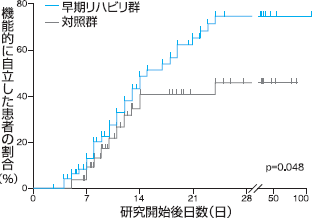 |
| 図1 日常生活機能の回復率(文献2より) |
| 早期リハビリ群のほうが対照群よりも早期に機能的に自立したことが示された。 |
「安静が一番」は正しい?
長谷川 一昔前まで,離床に向けた取り組みを始めるのはICUを退室してからでした。そのころには四肢筋力の低下など身体機能がかなり落ちてしまっていて,リハビリで体を動かすことに苦労される患者を多く見てきました。最近になって,早期離床の有効性を示すエビデンスや米国ICUにおける早期離床の取り組みなどの情報が日本にも入ってきていますが,ICU在室中から早期離床に取り組んでいる病院はいまだ少なく,呼吸器やカテーテルを装着している患者を動かすことへのタブー意識も残っています。
讃井 日本と米国では,重症患者に対する医療者の考え方が違うように感じました。米国には,「できる,頑張れ」と患者を叱咤激励して,離床への意欲を高める積極的な医療者が多いのですが,日本の医療者には,患者が少しでも苦しそうな顔をしていると気の毒な気持ちになってしまい,手が緩んでしまう方が多いのではないでしょうか。
高橋 私が留学していた豪州と日本とでは,早期離床に対する患者自身の受け止め方にも違いがあるように思います。豪州の方は自分自身で身の回りのことを行うのを重んじるようで,心臓手術をした患者もその日から体を起こすなど早期のリハビリに自ら積極的に取り組んでいました。一方,日本のICU患者は“重症患者らしく”おとなしく,動かないようにする方が少なくないように思います。
宇都宮 確かに日本には「安静が一番」という社会通念がありますね。患者の安楽を重視するのは大切ですが,予後を見据えたリスク管理の観点からすると「全身状態が良くなるまでじっと動かずにいる」のは誤りでしょう。動かないことがもたらす弊害や術後のリスクと離床の効果を医療者が患者や家族に正しく説明し,「積極的に体を動かすのは患者自身の役割である」ことを理解してもらう必要があると思います。
讃井 早期離床には日本人になじみにくい面もあるようですが,すでに取り組んでいる施設ではその効果が実感されていることと思います。ここからは,実際に取り組むために大切なポイントを共有していきましょう。
十分な鎮痛のもと,鎮静は浅く
宇都宮 早期離床に当たって非常に悩ましいのが,患者の疼痛・せん妄をどうコントロールするかですね。痛みをうまく制御できない患者は早期離床を拒否してしまいますし,せん妄患者は医療者の指示を理解できません。また,深く鎮静させてしまうと,患者は起き上がることすらできず,早期離床には取り組めないでしょう。
讃井 私が医師になった1990年代のICUでは,患者を深く鎮静して休ませるのが一般的でした。しかし2000年以降,過剰鎮静による呼吸器装着時間やICU滞在日数の延長,長期予後の悪化などのデメリットが明らかにされ4),“1日1回の鎮静中断”または“できるだけ浅い鎮静”が浸透しつつあります。その背景には,“十分な鎮痛が得られていれば鎮静は必要ない”という,鎮痛と鎮静を分けてとらえる考え方5)が普及したことが大きいでしょう。
長谷川 それらの知見を集約して,米国集中治療医学会(Society of Critical Care Medicine;以下,SCCM)が作成に携わり,今春発表された「成人患者の鎮静管理のためのガイドライン」6)では,“浅いレベルでの鎮静”や“鎮静よりも鎮痛の優先”が推奨され,集中治療の世界に大きなインパクトを与えました。
讃井 早期離床を達成するには,患者が覚めていて,痛みもなく落ち着き,理解力がある状態――ひと言でいえば“良質な覚醒状態”が求められます。つまり,十分な鎮痛のもとに鎮静を最低限に抑えることが,早期離床に取り組むための第一歩と言えますね。
せん妄モニタリングの感度を上げるコツは“継続性”
長谷川 鎮静を浅くすることで問題になることの一つは安全面です。2007年に日本呼吸療法医学会で「人工呼吸中の鎮静のためのガイドライン」7)を作成した際にも「鎮静の中断」を盛り込むことを検討したのですが,「患者の自己(事故)抜管が増えて看護師たちが困るのではないか」という慎重な意見が出たので見送りました。実際,鎮静しないことによって離床は進むが自己抜管が増えるという研究結果もあるため5),看護師に鎮静中断を勧めるには抵抗があったのです。
宇都宮 自己抜管などのインシデントの多くは,過活動型せん妄の患者が起こすと考えられがちですが,実は低活動型せん妄の患者によることも少なくありません。活動が激しく目立つ患者には看護師が意識的に注意を払うため重大な事故に至ることが少ないのですが,おとなしい患者の場合,看護師が気付いたときには事故になっていることが多いのです。こうした事故を防ぐには,患者の認知状況をあらかじめ把握しておき,積極的にモニタリングすることが有用でしょう。
認知状況の把握には,CAM-ICU(Confusion Assessment Method for the ICU;ICUにおける混乱評価法)やICDSC(Intensive Care Delirium Screening Checklist;ICUにおけるせん妄スクリーニングチェックリスト)など,せん妄のアセスメントツールを用います。すべての患者を毎日モニタリングするのは難しいので,判定スコアが高い患者に対してのみ継続的なモニタリングを実施し,せん妄が疑われた場合には薬物指導や生活指導などの介入を行うのがよいのではないでしょうか。
讃井 CAM-ICUとICDSCは,SCCMのガイドラインでも信頼性と妥当性が高いツールとされていますが,感度がやや低い点が課題ですね。
宇都宮 ええ。しかし,どんなツールも100%ではありませんから,症例数を重ねながら医療者のアセスメント力を高めていかなければなりません。
長谷川 継続性は重要ですね。当院の看護師もCAM-ICUを用いているのですが,使い続けるうちにCAM-ICUで「せん妄なし」と判断された患者についても「様子が少し気になるので早めに対応しましょう」と積極的に提案するようになり,とても驚きました。恐らくCAM-ICUが現場に根付いて,看護師たちの見極めが良くなってきたのでしょう。ツールの欠点を経験で補えるようになれば,検査の精度はますます高くなっていくと思います。
患者の状態に合わせた柔軟なリハビリ進行を
讃井 せん妄の発生予防に現在唯一有効だと考えられているのが,早期離床です2)。SCCMのガイドライン6)でも推奨されています。
高橋 せん妄は,敗血症など全身の炎症に伴って起こる急性の脳機能障害だと現在考えられています。リハビリで全身を動かすことによる刺激が,脳に何らかの良い影響を与えているのかもしれません。また,リハビリを介した定期的なコミュニケーションは「自分はいま最悪の状態から快方に向かっている」という前向きな意識を患者に持たせることができます。このようなポジティブな気持ちが早期離床を促進させ,せん妄に奏効しているとも考えられます。
讃井 早期離床に向けたリハビリは,どのように開始すればよいのでしょう。
高橋 まずはできることから取り組むのが良いと思います。早期離床は,ベッドから離れて歩くことだけを指すと思われがちですが,ベッドから離れるためには準備段階も必要です。ベッド上で,下肢の抗重力筋を働かせやすい環境を整えることも,早期離床の一つと言えるのです。
讃井 具体的にはどのような目標を設定し,どの程度のペースで行っているのでしょうか。
高橋 残念ながら,すべての患者にピタリと当てはまるリハビリ進行表は存在しないので,一概には言えません。例えば「重症者ほど少量頻回」といった“原則”はあるのですが,同じ病名・術後日数でも患者によって重症度や侵襲度が大きく異なるため,リハビリ進行の判断も難しくなります。特にICUに在室している患者の状態は刻々と変化しますから,日々の様子を観察しながら,その人に応じた進行度を決めていくしかありません。
長谷川 とはいえ,到達目標がまったくなかったり低すぎたりしても,患者や医療者のモチベーションを維持できませんよね。
高橋 ええ。逆に,目標を安易に高く設定してしまっても,患者の状態に柔軟に対応することができません。そこで私は,到達目標を“領域”で設定する方法を提案しています(図2)。これまでの臨床データから推定される大まかな到達度を領域で示し,その範囲に収まるように医療者も患者も努力する。皆の目標を統一する上では非常に有効で,患者の状態に合わせて柔軟にリハビリを進めることができます。
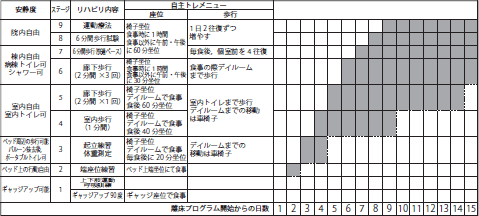 |
| 図2 心不全患者のリハビリ到達目標の設定例(田附興風会医学研究所北野病院の例) |
| 縦軸に到達度,横軸に経過日数を取り,到達目標を領域(色部分)で示すことで,患者に合わせた柔軟な離床プログラムの遂行をめざす。 |
長谷川 リハビリを行う適切なタイミングや適切な強度を判断するためのエビデンスや指針はあるのでしょうか。
というのも,当院のような一般病院ではマンパワーが少ないため,一人の患者に費やせる時間が多くありません。もし,せん妄や予後改善に効果的なタイミングや強度がわかれば,効果が期待される患者に集中的に人員を割いて高い強度のリハビリ介入を行ったり,エビデンスを提示することで離床の取り組みに診療報酬加算をつけたりすることも可能になるかもしれません。
高橋 理学療法による入院期間の短縮やADL向上などの事例は少しずつ報告されていますが,タイミングや強度の違いが最終的な予後にもたらす影響等についてはまだまだデータ不足です。早期離床に理学療法士がかかわる意義を理解してもらうためにも,きちんと根拠を提示していくことが今後必須だろうと思います。
讃井 早期離床に関するエビデンスに,日本発のものがほとんどない点も課題です。日本よりマンパワーがあり,医療スタッフの体格や男女比率,前述した積極性が異なる海外のデータでは,参考にはなりますが,単純に適用するのは難しいでしょう。
多様なスペシャリティで知恵を出し合う
讃井 限られたマンパワーで早期離床を実現していくためには,多職種の連携が欠かせません。宇都宮先生は以前いらした兵庫医大で,多職種が参加するウォーキングカンファレンスを導入されたそうですね。
宇都宮 当時は,医師は医師,看護師は看護師で申し送りをしていたのですが,それでは看護師が医師の治療方針などを十分理解できないという問題がありました。そこで患者のベッドサイドを一緒に回るウォーキングカンファレンスを始めたところ,医師と看護師だけでなく理学療法士,薬剤師,感染制御チームも参加するようになり,大所帯になりつつも職種間の意思疎通が図れるようになったのです。早期離床という目標を皆が共有でき,一丸となって取り組むことができました。
讃井 多職種チームによるラウンドは欧米でも文化として根付いています。
宇都宮 多職種チームで取り組むと,それぞれの専門的な知恵を出し合えるところが素晴らしいです。それを実感できたのは,人工呼吸器と透析器を付けた患者の事例でした。
われわれ看護師はその患者に座位をとらせて換気効率を上げたかったのですが,透析中であるために難しいと感じていました。そのことをウォーキングカンファレンスの際に皆で話し合ったところ,医師が「2-3時間なら透析を中断しても大丈夫」と意見を述べ,そうすると臨床工学技士からも「では,機械を空回ししましょう」と具体的な案が出されました。さらに,患者が座位をとる条件が整うと,理学療法士から「その時間,呼吸補助のリハビリに来ます」と提案され,たった2時間ではありますが,患者の早期離床に向けた取り組みを実現できたのです。多職種がそれぞれ自分の専門性を発揮しながら 1つのゴールをめざしていく。「これがチーム医療なのだ」とすごく感心しました。
高橋 医師からの指示を待つのではなく,チームの一員として各職種が専門性を発揮し,リハビリ計画をまとめていく。このプロセスは,われわれ医師以外の医療スタッフの成長にも,非常に重要だと思います。
理学療法士のなかには,いまだに後療法的なリハビリが自分の役割だと考えている人もいて,患者の予後を良くするためのリハビリをしている自覚がある人は少ないのが現状です。ICU専属の理学療法士が増え,予後改善を目的とした介入が積極的に行われるようになれば,急性期病院にいる理学療法士の役割も変わってくると期待しています。
共通言語を持ち,チーム内の相互理解を促す
讃井 ただ多職種が集まれば,チーム医療になるわけではありません。全員のモチベーションが高ければいいのですがすべてのスタッフがそうとも限らない。チームをどうマネジメントしていくのかが今後の課題でしょうね。
長谷川 当院では看護師に,自発呼吸試験(spontaneous breathing trial:以下,SBT)に取り組んでもらっています。すでに米国では,呼吸療法士や訓練を受けた看護師主導で行われているのですが,日本では医師主導だったり,そもそもSBTの認知度もあまり高くありません。
当院で最初に提案した際も,看護師からは「それは医師の仕事でしょう」「私たちが呼吸器離脱の判断をするなんて」と一度拒否されましたが,米国での取り組みなどを理解してもらい,ひとまず医師と看護師の判断に差があるかどうかを検証する看護研究として始めてもらうことになりました。そうして,ICUに入室した気管挿管患者96人(評価回数347回)を対象に「SBTを実施できるか否かの判断」と「SBTを実施し,抜管できるか否かの最終判断」のそれぞれにおける医師と看護師の一致率を前向きに検討したところ,医師と看護師の判断は,いずれの場合においても87%の高い割合で一致していることがわかったのです。また,SBTの評価項目については,100%一致していることが示されました8)。
宇都宮 実際に取り組んでみたことで,看護師にも自信が生まれたのではないでしょうか。
長谷川 ええ。実は医師と看護師の判断の一致率を検証する傍らで,看護師のSBTに対する不安感についても調査していました。すると,SBT導入前はほぼ全員が自分たちの判断に不安を感じていたのですが,調査の過程で自分たちも医師と同レベルの判断ができるとわかってきたのでしょう。導入4か月後には,SBTへの不安を持つ看護師が少なくなっていました8)。
讃井 新しいものを取り入れて,それを定着させるためには,理屈だけではうまくいきません。医療者も人間ですから,自信を持つことが大切ですよね。
長谷川 そうですね。この一連の取り組みによって,看護師と医師がSBTという共通言語を持つことができ,より質の高い医療を提供したいというモチベーションにもつながりました。
高橋 共通言語を持ってコミュニケーションをとることは,チーム医療における非常に重要なポイントだと思います。各自が果たすべき役割を自覚するだけでなく,互いの役割を理解し,尊重できる。その結果,高いパフォーマンスを発揮できるチームに成長するのではないでしょうか。
宇都宮 多職種が不安なく早期離床にかかわるためには,導入・中止の基準を明確にすることも大切です。例えば,開心術後の患者の場合,「心係数が2.1以下」であれば早期離床の導入は見送られるでしょうし,離床中の患者の「収縮期血圧が20 mmHg以上低下」すれば中断すべきでしょう。こうした基準があることによって,患者の安全を守るだけではなく,医療者も心理的負担が軽減され早期離床に取り組みやすくなると思います。
讃井 早期離床は,まだまだ日本のなかでは新しい分野ですので,定着には時間がかかりますが,決して難しいことではありません。少しずつバリアを減らしていくことで,多職種がかかわりやすい土壌は必ず作れると思います。
ICUから病棟・外来まで,シームレスな取り組みを
讃井 ここまでさまざまな取り組みを紹介してきましたが,ICU内だけで終えては意味がありません。ICUから病棟,そして外来まで切れ目なく患者をみる視点が必要になります。
宇都宮 一度病棟に移った患者が呼吸器合併症等でICUに戻って来てしまうケースを経験した方もいるでしょう。ICUはICU,病棟は病棟と区別するのではなく,治療をスタートした時点から目標に向けてできることを一貫してやっていくことが非常に重要だと思います。
長谷川 呼吸療法を必要としている患者には,呼吸ケアサポートチーム(respiratory care support team;以下,RST)がICU退室後も継続してかかわりを持てるのではないでしょうか。日本のRSTは直接患者のケアをするというよりも,ラウンドで病棟スタッフと話し合う形での介入がほとんど。病棟の様子を把握できるRSTだからこそ,ICUからシームレスに患者を見ていく上で重要な役割を果たすと思うのです。
讃井 ラウンド型のRSTを持つ日本の病院ならではのかかわり方ですね。
長谷川 特に,多くのRSTメンバーには臨床工学技士と理学療法士がいます。院内で横断的に動けるこの二職種の方だけは,患者がどこの病棟に行っても追いかけることができるのです。
高橋 そうですね。ICUから外来まで広くかかわることができる立場だからこそ,医師や看護師と患者をつなぐ役割を担えるでしょう。ICU退室後も,病棟や外来で患者が今どうなっているかをわれわれがICUスタッフにフィードバックできれば,ICUの医療チームが自分たちの治療を振り返る良い機会を持てるのではないかと思います。
宇都宮 RSTが病院内のハブ的な存在になるといいですね。平時からRSTが院内の情報にアンテナを張り,各病棟とのつながりを築いていれば,いざ病棟患者の呼吸状態が悪くなったときにもすぐICUと情報交換できるでしょう。院内のネットワークを形成する上で,欠かせない役割だと思います。
讃井 ICUスタッフが患者の長期予後の改善という目標を持って,チームとして鎮痛,鎮静,せん妄管理,理学療法に取り組む時代がやって来たと言えるでしょう。本座談会のような何でも言い合える風通しの良いチームが作れるとよいですね。
(了)
文献
1) Herridge MS, et al. Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2011; 364 (14): 1293-304.
2) Schweickert WD, et al. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. Lancet. 2009; 373 (9678): 1874-82.
3) Ely EW, et al. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA. 2004; 291 (14): 1753-62.
4) Girard TD, et al. Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for mechanically ventilated patients in intensive care (Awakening and Breathing Controlled trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2008; 371 (9607): 126-34.
5) Strøm T, et al. A protocol of no sedation for critically ill patients receiving mechanical ventilation: a randomised trial. Lancet. 2010; 375 (9713): 475-80.
6) Barr J, et al. Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit. s.l. : Crit Care Med. 2013; 41 (1): 263-306.
7) 「人工呼吸中の鎮静のためのガイドライン」
8) 植村佳絵,他.自発呼吸トライアルにおける医師と看護師の判断の差異についての検討.日本集中治療医学会雑誌.2013; 20(suppl.): 467.
9) 高橋哲也.冠動脈バイパス術後に呼吸理学療法は必要か?――早期呼吸理学療法導入の効果.理学療法学.2001; 28 (2): 31-7.
 |
讃井將満氏 1993年旭川医大卒。飯塚病院等で研修後,99年に渡米。米マイアミ大にて麻酔科レジデント,臓器移植麻酔フェロー,集中治療医学フェローを務め,2006年より自治医大さいたま医療センター講師。慈恵医大准教授を経て,13年より現職。日本集中治療医学会専門医,日本麻酔科学会指導医。米国での臨床経験に基づき,世界標準の集中治療の普及と若手の教育・研究に力を注ぐ。 |
 |
長谷川隆一氏 1990年東北大卒。同大病院麻酔科,医療安全推進室を経て,2003年より公立陶生病院呼吸器・アレルギー内科, 05年より現職。日本集中治療医学会専門医,日本麻酔科学会専門医。呼吸不全患者への全人的なケアの必要性に着目し,呼吸ケアサポートチームと協力したICUでの早期離床を開始。現在はICU専従医2人と看護師,理学療法士,臨床工学技士,薬剤師が常駐するチーム体制を院内に整えている。 |
| 高橋哲也氏 1989年国立仙台病院附属リハビリテーション学院卒。聖マリアンナ医大病院,豪州留学後,群馬県立心臓血管センターを経て,2007年より兵庫医療大教授。12年より現職。日本心臓リハビリテーション学会副理事長。早期の理学療法介入が呼吸機能の回復に及ぼす効果を検証したランダム化比較試験9)等,研究活動にも尽力。13年7月に日本心臓リハビリテーション学会第10回木村登賞受賞。 |
 |
| 宇都宮明美氏 2004年大阪府立看護大(現・大阪府立大)大学院博士前期課程修了。同年より兵庫医大病院に勤め,ICU師長,看護次長を経て,11年より現職。日本集中治療医学会理事。大学院時代に早期離床が患者にもたらすメリットを学び,兵庫医大では急性・重症患者看護専門看護師として,医師・看護師・理学療法士等多職種の協力を得ながらICU患者への早期離床に取り組んできた。 |
 |
いま話題の記事
-
忙しい研修医のためのAIツールを活用したタイパ・コスパ重視の文献検索・管理法
寄稿 2023.09.11
-
人工呼吸器の使いかた(2) 初期設定と人工呼吸器モード(大野博司)
連載 2010.11.08
-
連載 2010.09.06
-
事例で学ぶくすりの落とし穴
[第7回] 薬物血中濃度モニタリングのタイミング連載 2021.01.25
-
寄稿 2016.03.07
最新の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]脆弱性骨盤骨折
『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第3回]わかりやすく2つの軸で分類して考えてみましょう
『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第1回]平坦な病変 (1)色調の変化があるもの
『内視鏡所見のよみ方と鑑別診断——上部消化管 第3版』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください
『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第1回]バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO)
『IVRマニュアル 第3版』より2024.04.26
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
