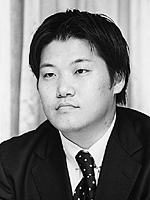| ●しりあす・とーく | |||||||||
第15回テーマ
スーパーローテーションの功罪
新制度の下,第一回目の研修修了者が誕生前野 スーパーローテーションを基本とする新医師臨床研修制度が実施されて2年が経ちました。本日は,新しい制度のもとで第一回目の研修修了者となった2人の先生をお迎えし,研修医・指導医の双方から,新制度の検証をしていきたいと思います。まず,自己紹介からですが,私は,筑波大学を卒業し,河北総合病院で3年間内科の初期研修,さらに,筑波大学の総合医コースで4年間総合診療の研修を行い,川崎医大の総合診療部,筑波メディカルセンター病院の総合診療科を経て,筑波大学に移りました。筑波大学では,卒後を中心とした臨床研修のコーディネートの実務と卒前の臨床教育をやっています。臨床では,総合診療科で,選択研修で回ってくる研修医と後期研修医の指導をしています。
鳥居 私は,2年前に大学を卒業して,2年間,横浜市立市民病院で研修をしました。もともと,医学部に入った動機が,眼科で研究をしたいということでしたので,母校へ戻り,いま慶應義塾大学病院の眼科で後期研修を始めたばかりです。 下山 私は,湘南鎌倉総合病院で臨床研修を行い,いま最後の離島研修を奄美大島の名瀬徳洲会病院で行い,研修の仕上げをしているところです(編集室注:本座談会は4月15日に収録された)。 もともと心臓外科医になろうかと思っていたのですが,ローテーションをしているうちに,循環器全般,虚血だけではなくて循環器内科をやりたいと心境が変化し,5月から大学病院で専門科研修をすることになっています。 スーパーローテーションを終えて前野 では,さっそく本題に入りたいと思います。まず,スーパーローテーション研修を終えたばかりのお2人から,全体的な感想を聞かせていただいて,そこから話を展開していきたいと思います。
先輩たちは,大学病院のなかの内科の1番,2番,3番というふうに順々に回って,人によっては外科を回ったり,眼科を回ったりということで,自分の行きたい科をわりと自由に選んでいるという印象をもっていましたが,私の研修先が市中病院ということもあり,どちらかというと研修をしながら病院の人手としての役割を果たすという,そのようなニーズを感じながらローテーションを回りました。 心の師匠との出会い下山 個人的な感想ですが,いろいろな科を回っていくと,それぞれの先生について「この人のこういうところは尊敬できる」「こういうやり方を盗もう,習おう」と思ったり,いろいろなところで,自分の心の師匠になるような先生たちとの出会いがあって,それがスーパーローテーションの隠れたおもしろさなのかなと思いました。例えば産婦人科では,お産を50人取って,そのなかの5人については最初から最後までケアをさせていただきましたが,たぶん,この先,循環器科の医師になるとお産を取り上げることはまずないと思います。でも,そこで,産婦人科の先生がどんなにきつい立場で仕事をされているかということを知って,産婦人科医の生きざま,助産師さんとの仕事の分担など,感じるところがたくさんありました。私が,人足として十分に働けたかどうかわからないけれども,実りある経験ができたと感じています。 前野 今,研修制度のメリットを挙げていただいたと思います。逆に,何か欠点はありませんでしたか。 下山 例えば,私が最初から猛烈に循環器内科に行きたいと考えていたとしたら,精神科の研修をしたり,わざわざ奄美大島に行って研修をする必要はないのではないかというふうに,きっと苛立ちを覚えたと思います。以前から言われている点ですけれども,専門医に早くなりたい人にとっては,2年遅れるわけで,それが欠点になるのではないかと思います。 あとは,どんどん人が変わっていくので,神様みたいな人ばかりではないと思うので,その職場との相性というものがあると思います。それぞれの科でうまくやっていくことが求められるのですが,受け入れる職場と,入っていく研修医と,それを見ていく上級のドクターと,それぞれが,ローテーションで人が動いていくということに馴染んでいかないと,軋轢を生むこともあるのではないかと思いました。最初は,「やっていけるんだろうか」と危惧しました。 前野 実際にやってみてどうでしたか。周りに馴染めなかったり,ネガティブな面が強く出てしまった人はいましたか。 下山 おそらく,先輩方が経験された割合とほぼ同じではないかと思いますけれども,研修医の10%ぐらいは,どこの科へいっても「あいつがきた」と言われながら,問題を起こしながら各科を回っていました。一方で,熱心で,横から見ていてもちゃんと患者の話も聴くし,問題点についてとことん追究しようという姿勢をもっている人は,尊敬されながら回っていくように思いました。 医者である以上やっておきたいこと前野 鳥居先生はいかがですか。
今回スーパーローテーションがあってよかったなと思うのはその点です。大学病院での研修という選択肢もあったのですが,一般的な頻度の高い疾患についても,治療を身につけたいと考えて,市中病院での研修を選びました。 スーパーローテーションで得たもの鳥居 研修をした横浜市立市民病院の研修委員長の大生定義先生は非常にすばらしい先生で,私は救急をメインにしながら2年間各科ローテートしたのですが,EBM・臨床倫理という観点もふまえ総合的な視野で疾患を見ることができるようになったと実感し感謝しています。また各科を回るときのモチベーションの維持については,将来の科として眼科に絞っている面もあったので,眼科と関連する点を追究しながら各科を回るというスタンスを取っていました。例えば精神科を回っていたときには,目が見えなくなっていく視野狭窄の患者さんについて,精神科的にはどのようにアプローチしていくのかというようなことを,常に上の先生とディスカッションしながら回ることができました。ただ,産婦人科と眼科とはあまり関連性がないので,ただ一生懸命やるという感じで終わってしまいました(笑)。 あと,小児科では,ルートを取るなどの基本的なことはほぼ確実にできるようになったので,いま,大学病院に子どもが入院してきても点滴のルートを取るのに困りませんし,いわゆるcommon diseaseに対しても困ることはあまりありません。そういう点も含めて,やっぱりスーパーローテーションはよかったなと思っています。 ネガティブな側面鳥居 ネガティブな面は,1つは,眼科のsurgeonとしてのスタートが遅れるということ。やはり下山先生が言われたような苛立ちはありました。それを解消させる目的で,1か月に1~2回,ブタの眼を使った豚眼実習を実際にやらせていただくことによって,なんとかそのストレスを解消することはできました。
鳥居 いえ,市民病院の眼科の先生(慶應出身)がやってくださいました。1年目は必修の科を回るので,うちの病院の場合は,眼科は2年目からしか回れないのですが,2年目は選択が可能で,しかも時期も選ぶことができるというので,とにかくモチベーションの高いものをいちばん最初にもってきて,2年目の4月から3カ月間,眼科を選択しました。そのときに,市民病院の眼科の宮田博先生・市川有穂先生にセッティングしていただいて,レンズ会社の方とコンタクトをとりながら実習させていただきました。 前野 うまくネガティブなところを消す努力をされましたね。 鳥居 そうですね。本当に周囲の先生方の御協力があったからこそできたことだと思っています。 前野 選択研修は,全部で何カ月されたんですか。 鳥居 トータルで6カ月で,眼科は3カ月です。最初は,眼科を6カ月とも考えたんですが,眼科医になったら,それ以外のことはやらないし,ここでしか回れないところを回りたいという気持ちがあり,初期治療に参加でき,外傷系を含め全科を学べる救急部を選択しました。 (つづきは本誌をご覧ください)
|
 石丸 私は,大学を卒業後,天理よろづ相談所病院で初期研修をしました。当時は,いまほどのローテーションではなくて,内科・外科を含めて1年半,そして麻酔科の研修を受けました。後期研修では,同じ病院の内科をローテートするコースで,専門内科研修を半年ずつ行い,その後,総合診療教育部というところで,総合内科医の仕事と研修医教育をする医師として採用され,その後ずっと同じ病院に勤めています。医者の経歴では,勤務先が変わることが多いのですが,私は同じ病院に勤めていますので定点観測的な感じで見ています。
石丸 私は,大学を卒業後,天理よろづ相談所病院で初期研修をしました。当時は,いまほどのローテーションではなくて,内科・外科を含めて1年半,そして麻酔科の研修を受けました。後期研修では,同じ病院の内科をローテートするコースで,専門内科研修を半年ずつ行い,その後,総合診療教育部というところで,総合内科医の仕事と研修医教育をする医師として採用され,その後ずっと同じ病院に勤めています。医者の経歴では,勤務先が変わることが多いのですが,私は同じ病院に勤めていますので定点観測的な感じで見ています。
 下山 すでに私が研修を始める2~3年前から大学病院でもスーパーローテーション研修が実施されていたので,あまり違和感はありませんでした。むしろ研修というものはいろいろな科を回っていくものなのかなと思っていました。
下山 すでに私が研修を始める2~3年前から大学病院でもスーパーローテーション研修が実施されていたので,あまり違和感はありませんでした。むしろ研修というものはいろいろな科を回っていくものなのかなと思っていました。
 鳥居 私は,中学生の頃から眼科で特に近視に関する研究をしてみたいと思い医師になりましたので,医学部時代から眼科の研究室に出入りさせてもらったりしていました。ただ,学年が進むにしたがって,行く先が眼科だけということに少し抵抗感をもつようにもなりました。つまり,医者である以上,人の生命を救い健康を守るという医療の中心部分に携わりたいという気持ちが出てきて,いきなり眼科に入ってしまうことに抵抗を感じたわけです。ところが,そこへこのスーパーローテーションが始まると聞いたものですから,自分にとってはよい機会でしたし,逆にそのことで「俺は将来眼科に行こう」と確信したところがあります。
鳥居 私は,中学生の頃から眼科で特に近視に関する研究をしてみたいと思い医師になりましたので,医学部時代から眼科の研究室に出入りさせてもらったりしていました。ただ,学年が進むにしたがって,行く先が眼科だけということに少し抵抗感をもつようにもなりました。つまり,医者である以上,人の生命を救い健康を守るという医療の中心部分に携わりたいという気持ちが出てきて,いきなり眼科に入ってしまうことに抵抗を感じたわけです。ところが,そこへこのスーパーローテーションが始まると聞いたものですから,自分にとってはよい機会でしたし,逆にそのことで「俺は将来眼科に行こう」と確信したところがあります。
 前野 そのブタの眼を使った実習というのは,慶應の眼科の先生の計らいで?
前野 そのブタの眼を使った実習というのは,慶應の眼科の先生の計らいで?