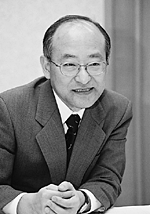| ●しりあす・とーく | |||||||
第9回テーマ
いま本当に必要な医療改革とは何か?
李 本日は,お忙しいところをありがとうございます。郡先生には,天理よろづ相談所病院総合診療教育部部長として,研修医の教育に当たっておられる立場と,勤務医として長い間のご経験をお持ちの立場の両面からご発言いただき,大西先生には,プライマリケアの第一線を担う開業医の視線から日本の医療についてお話しいただきたいと思います。 ■医療はどう変わったか?医療不信李 テーマは「医療改革」ということですが,私が外(米国)から見ていて,日本の医療でいちばん深刻だと思うのは,医療不信の問題です。大西先生と私とは,天理よろづ相談所病院(以下,天理病院)で,総合診療部の草分けの時代に同じレジデント仲間でしたし,郡先生は,私たちよりも3年先輩で,25年ほど前からご指導いただいてきましたが,25年前と,いまの日本の医療とは,大きく変わってきています。それは,ただ技術が進歩したというだけでなく,医療不信が,昔からは考えられないほど深化してしまったのではないかと思うのです。そのあたりの実感というか,実像というか,先生方がお感じになっておられるところから,本日の話を進めたいと思います。郡先生,いかがですか。郡 医療のあり方の変化という意味では,やはり情報が増えて,患者さんが,病気についてのいろいろな知識をもったというのは大きいと思います。「かくあるべきだ」というのを,患者さんなりにイメージされているものだから,その通りにいかないと「おや?」ということになるのでしょう。 わかってもらいにくい医療の不確実性郡 医療者側にかなり悪い点はあると思いますが,患者さんにもぜひ考えていただきたいのは,医療というのは不確実性の科学なので,同じことをやっても,必ず同じ結果が再現されるわけではないということです。そのことをぜひわかってほしいんです。しかし,よくいわれるように,3時間待ってもらって,3分間の診察時間しかないなかで,医療の不確実性を説明して,理解してもらうということは,ほとんど不可能です。そこが昔と変わらずそのまま残っているものだから,患者さんの理解も進んでいません。つまり,「結果も同じでないといけない」と思ってるわけです。機会は均等に与えられるけど,結果まで均等,均一には絶対になりません。しかし,そこがなかなかわかってもらえません。 李 例えば癌の治療にしても,奏功率50%の抗癌剤といった場合には,50%にはまったく効かないということです。また,副作用が5%という場合,その5%に自分があたってしまう,あるいは家族があたってしまうと,「医療事故だ」ということになったり……。何パーセントまでいったら医療事故かというと,これはわからないです。50%しか奏功しませんよといって,効かなかった50%に入ったという場合には,おそらく誰も医療事故だなどと言わないと思います。ところが,2%の割合で起こる副作用が起こったとすると,これは医療事故だと思われる方は多いのではないかと思います。 医療者に求められる説明の努力李 アメリカ科学アカデミーは,「プランどおりにいかなかったこと」,「誤った情報をもとに誤ったプランをつくった場合」を,医療事故と定義しています。ですから,仮に5%の確率でこういう副作用が起きますよということを説明していて,そういった可能性も十分に考慮して治療のプランを立てていて,副作用が起きた場合には,これこれこういう対策を講じておりますと,説明がしてあれば,プランどおりに起こったことだから,私は,事故とはいえないと思います。ただ,患者さんの実感としては,それを理解すること,つまり医療情報を科学的に受けとめることは難しいと思います。 しかし,情報を正確にアセスメントできないからといって,情報を与える努力を放棄してしまってはいけません。インフォームドコンセントに関連して,「患者に説明しても理解していない」という例が,けっこう論文になったりしていますが,だから説明しなくていいのかというと,それはまた別問題です。説明の仕方に工夫を加えたりするなど,どう受け取っていただくかということへの努力は放棄してはいけません。 もし,「わかっていただけない」ということで諦めてしまったら,医療不信はそのままです。 大西先生,いかがですか。日常の臨床の場で,医療不信というものをひしひしと感じられるような事例はありますか。 ■患者との信頼関係医療不信はマスコミのつくった虚像?大西 世の中でいわれているような医療不信というのは,あまり感じません。2年ほど前に,日医総研が医療機関にかかっている患者さんに,「あなたは,現在あなたが受けている医療に対して満足しているか」というアンケートを出したんですね。そのときに「満足している」と答えた人が,80%を超えたんです。それが記事に載ったのは,その日に私は確認したんですけど,日本経済新聞だけでした。私も,その記事がほかのところになぜ載らなかったのか,非常に不思議だったんですが,日医総研の方にその話をしたら,そういう話をマスコミに載せるように話しても,ほとんど記事にしてくれないとおっしゃっていました。 私は,日本の医療不信といわれているのは,マスメディアがつくった虚像ではないかと思っています。私の患者さんに,いろいろなところで医療不信をもっているかと聞くと,そのようなものをもっている様子の方はほとんどいません。 リウマチの薬は副作用が多いんですが,うちで副作用が出たときに,「こういう可能性がありますよ」と説明すると,皆さん,冷静に,受けとめられます。 李 事前に説明しているからですね? 大西 はい。非難されるようなことはないですね。それで患者さんが来なくなるというようなことも,ほとんどないです。 だから,臨床の現場では,医師が努力をしており,患者さんとの信頼関係が築かれている場合には,医療不信はあまりないのではないかと思います。 李 いまの時代の風潮の中で,先生が言われたようにマスコミが医療不信を煽る。その煽り方というのが,例えばこれは民放テレビ局のある記者が,ある場所に書いていたことですが,医療部門に配属されて,最初に先輩から習ったのは,「日本医師会の言うことは必ず間違っているから,日本医師会が言うことと反対の記事を作れば,正しい記事が自動的にできあがる」ということだったというのです。 確かに,マスメディアが煽るという側面はあると思います。ただ一方で,日本医師会の発言や方針のなかにも医療不信を煽るようなものがあった時期もあったように思います。 急性期医療における患者との信頼関係李 大西先生のところのように患者さんと信頼関係が築けている場合には問題は起こらないと思います。継続的に長期間,患者さんとお付き合いがある開業医の場合には,信頼関係を築く時間も努力によって確保できる。これは非常に大切なことだと思います。しかし,急性期の場合ですと,たかだか1週間しか入院されない方と信頼関係をとり結ぶのは,非常に難しいものがあるようにも思います。勤務医として,普段,外来でお付き合いのある方が入院された場合には,信頼関係をとり結びやすいと思います。しかし,例えば天理病院ですと,突然地方から来られた方が入院されることは,日常的にあることですよね。見知らぬ患者さんと信頼関係を結ぶときに,どういったことを心がけておられるのか。あるいは若い先生方を指導するときに,どういったことを心がけておられるかということを,お聞かせ願えますか。 ■「説明と同意」ではなく「安心と納得」郡 インフォームドコンセントが非常に大事ですが,私がキーワードだと思っているのは,「説明と同意」ではなく,「安心と納得」ということです。説明を聞いて,患者さんが安心し,納得しないと,説明したことにはならないと思っています。本当に大切なのは「達意」郡 研修医と患者さんとのあいだでトラブルが起こったときに,研修医に聞くと「私はちゃんと時間をかけて説明しました」と言うのです。では,「相手はちゃんとわかったのか,それは確認したのか」と聞くと,そこがあやふやなんです。結局,相手にはわかっていない。説明するというのは,いわば初歩的なことで,本当に大事なのは「達意」だと思うんです。「意」が伝わっているかどうかです。達意までいかないとダメだということです。だから,若い先生には,「君が三流の臨床医としてやっていくんだったら,単に説明しただけでいい。でも,一流の臨床医を目指すんだったら,達意の段階までいかないといけない。君はまだ,そこまでできていないからそうなるんだ」というふうに言っています。 インフォームドコンセントとは共同でプランをつくるプロセス李 インフォームドコンセントの定義というのは,「患者と治療のゴールを共有して,そのゴールを達成するために,共同でプランをつくるプロセス」です。同意を得ること,あるいは得た書式というのがインフォームドコンセントではないわけで,共同でプランを作成するというプロセスそのものがいちばん大事です。だから,インフォームドコンセントというのは,患者さんとかかわるときに初めから最後まで貫き通される原則でなければなりません。いつも共同でやっているのだと認識しておくことが大切です。口で言うのはたやすいことですが……。 「安心と納得」というのも,患者さんと一緒に,了解し合いながらやっていくことの大切さに根ざしているのではないかと思います。 (つづきは本誌をご覧ください)
|