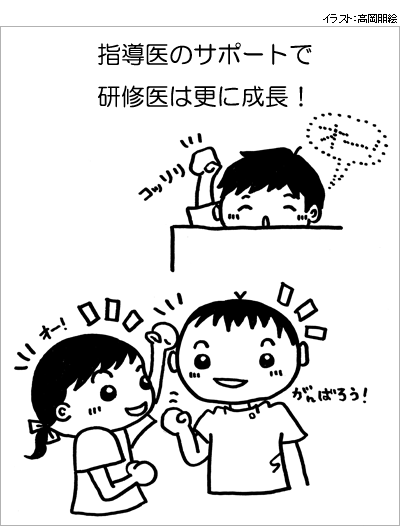第8回テーマ
上達への道
――鍛え方~指導医へ~
川島篤志(市立堺病院・総合内科)
例
|
◆プレゼンテーションについて,研修医同士での雑談
研修医A:せっかくプレゼンテーションの勉強したのに,「ダメだし」ばっかりされるし……かといって,(後期研修医の)X先生のプレゼンも上手じゃないように思えるんだよね。
研修医B:でもAくんのプレゼンテーション,聞いていてすごくわかりやすかったよ。確か,消化管出血の症例って初めて担当するんだよね。
研修医A:ありがとう! 前,Bくんが発表してたのと,指導医の先生からのフィードバックを聞いていて,なるほど,ってメモっておいたんだ。眠かったけど,Bくんの発表って声も大きくて,惹きつけられるから,しっかり聞けたよ。
研修医B:来年からは手本にならないといけないし,僕らが指導医になるときには,後輩のプレゼンテーションをきっちり聞いて,指導しないと日本はダメになっちゃうな。
◆難しい英語のテキストを基にした,初期研修医だけの早朝のカンファレンスで
研修医A:ここの部分は,どうなっているの?
研修医B:えーっと……ゴメン,昨日忙しくて準備しきれなかった。資料,わかりにくいよね……。
研修医A:じゃぁ,ここの部分,わかる人っている?
研修医C:……(寝ている)。
研修医B:答えがわからないと,いまいち盛り上がらないよね,ゴメン。(指導医の)Y先生なら知ってるかなぁ……。
研修医A:うーん……。
研修医D:(ガチャ)あーゴメン,遅刻しちゃった……布団から出るのがきつくって……。
研修医一同:もう,やめよっか。このカンファ……。
|
前回までは,内容,伝え方などのことの理論をお話ししました。理論について理解すれば,あとはいかに上達するか……というところになります。この上達法にもコツがありますので,今回はそのコツについてお話させていただきます。
さらにそのコツには指導医やシステムの協力が必要なことが多いので,「指導医へ」というサブタイトルもつけさせて頂きます。
■研修医アンケートに見るプレゼンテーション上達のポイント
まず2005年に当院の研修医からとったアンケートから,ポイントと思われる点を表1に挙げてみます(頻度順)。
表1 プレゼンテーション上達のポイント
・理論を理解すれば,あとは上達に向けて訓練しましょう
・訓練にもコツがありますので,上手に上達して下さい
・カンファレンスは「無理なく」チャレンジしましょう。上手くいかなかったら潰してしまって,また始めればいいだけです
・指導医の助けがあれば,上達速度は倍増です |
(1)実践を繰り返す,慣れる(得票数8)
当院の研修医がトップに挙げたことは,「とにかく実践を繰り返す・慣れる」ということでした。
とても当たり前のような気がしますが……この実践が行われている環境が日本にどれだけあるのか?ということです。第2話の「現在ないもの」でお話したように,このプレゼンテーションが必要・重要であるという認識や環境を整えるのは,指導医の役目です。
もし環境が整っていれば,実践を繰り返すことが大切ですので,失敗を恐れずに積極的に練習して下さい。
(8)スタンダードなプレゼンテーションを理解する(得票数2)
下位に挙げられていた「スタンダードなプレゼンテーションを理解する」,というのは,今までに話してきた内容を理解するということです。手前味噌かもしれませんが,当院の研修医は日々の臨床のなかで,スタンダードなフォーマットを理解しているので,あまり上位に挙げられなかったのかもしれません。しかし,これはきわめて大切なことです。繰り返し話していますが,フォーマットを理解しないと,オーラル・プレゼンテーションは成り立ちません。現在ではプレゼンテーションに関する書物も増えてきていますし,本連載もその助けになれれば嬉しいことです。
その「スタンダードな」プレゼンテーションが,その施設でのスタンダードになっているかどうかが問題です。せっかく,スタンダードを理解しても,利用できなければ全く意味がありません。ここも指導医の腕の見せ所です。
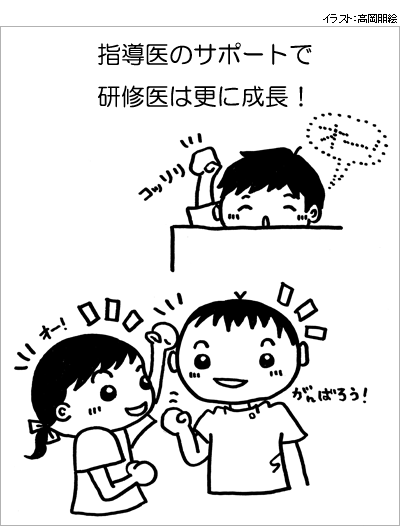
(つづきは本誌をご覧ください)
川島篤志
1997年筑波大学卒。京都大学医学部附属病院,市立舞鶴市民病院にて研修。2001年より米国Johns Hopkins大学公衆衛生大学院に入学し,MPH取得。2002年秋より現職。院内での総合内科の充実を目指すとともに,全国規模で,研修病院としての「経験の共有」,総合内科/総合診療/家庭医療/プライマリ・ケアの「横のつながり」を意識しながら,この分野を発展させていきたいと強く感じている。
本連載へのお問い合わせはkawashima-a@city.sakai.osaka.jpまで。 |
|