| ●できる医師のプレゼンテーション-臨床能力を倍増するために | ||
第3回テーマ
■プレゼンテーションの準備前回も話に出てきたように,プレゼンテーションするためには,とにかく情報を集めて,患者さんを把握することが必要です。さらに,「必要最低限」の情報を含めた,どの情報が有用なのかを判断するためには病態の理解が求められています。その必要な情報を整理したうえで,他の人に伝えることによって,プレゼンテーションが成立します。患者さんの把握患者さんの把握のためには,多くの情報を正確に,適切に集めることが求められます。その情報源はどこにあるか? 患者さん本人だけでなく,家人や周囲の方,以前入院・通院していた医療機関,現在の医療機関の過去の記録などさまざまです。少なすぎる情報では,適切な判断は下せませんし,不必要に多い情報では,混乱が生じます。何が必要最低限なのか,このあたりを常に意識しておくことが大切です(この「必要最低限」については後述します)。 研修医を含めて,経験の浅いうちは多くの情報を集めてくる訓練をしなければいけません。経験を積んでくると情報の取捨選択は上手になってくると同時に,面倒さや時間的な制約から多くの情報をとろうとしなくなってくることが多いかもしれません。研修医のうちは時間があるはず(入院患者さんが主体,他のDutyなどがない)なので,面倒がらずに情報収集をする習慣をつけたいものです。 前号にも記載しましたが,恥かしながら筆者の研修医時代に,予約入院患者さんにおいて,入院前=患者さんに会う前に現病歴を作成した経験があります。この時の情報源は何だったでしょうか? 過去の入院カルテ・外来カルテからの作成でした。効率はいいかもしれませんが,本当に患者さんを把握しているとは到底言えませんし,何のトレーニングにもなりません。
実際,当院の研修医に伝えていることの1つは,
こういった問題点を見つけるには,ROS(Review of systems;詳しくは次号)を含めた病歴をしっかりと取る訓練を地道に続けることが必要です。身体所見も同様で,「頭の先から爪の先まで」チェックする習慣をまず身につけることが大切です。知識や経験がついたときに初めて,少し省略した所見でも対応可能になると思います。 さらに大切なことは,病歴聴取や身体所見を取ることは決して1回で終わるわけではではないことを認識することです。報告や回診などでの発表の機会までは緊張して頑張るのですが,そのプレゼンテーションが良かったにしろ,悪かったにしろ,そこで終わりにしてしまっていることが多いのではないでしょうか。経験が浅いうちは,1回ですべての情報を得ることは不可能でしょう。しかし繰り返し,繰り返し情報を集め,整理することによって,プレゼンテーションに値するものに変化していくものです。研修医はこの繰り返す姿勢をさぼらずに自分自身で身につけること,一方,指導医は繰り返すことを促すこと,改善を評価する機会をつくることが必要です。 (つづきは本誌をご覧ください)
|
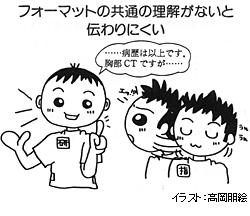 病歴をカルテ中心に取っているようであれば,主治医チームが捉えている医学的な問題点に主眼が置かれると思います。しかし,患者さんには他の臓器の問題点がある可能性もありますし,社会的な側面の問題もあるかもしれません。それを見つけるのが,医師として,主治医としての責任だと思います。
病歴をカルテ中心に取っているようであれば,主治医チームが捉えている医学的な問題点に主眼が置かれると思います。しかし,患者さんには他の臓器の問題点がある可能性もありますし,社会的な側面の問題もあるかもしれません。それを見つけるのが,医師として,主治医としての責任だと思います。