| ●できる医師のプレゼンテーション-臨床能力を倍増するために | |||
第2回テーマ
■ないない尽くしのPresentation前回,お話したように,プレゼンテーション能力は,臨床能力を反映すると考えられます。それにもかかわらず,「プレゼンテーションに自信がない」「うちの研修医のプレゼンテーションは駄目だ」ということをよく耳にします。言葉を置き換えると,「臨床能力に自信がない」「うちの研修医の臨床能力は駄目だ」ということです。とても残念なことですが,どうしてプレゼンテーション能力が伸びていかないのでしょう?私見ですが,研修医個人だけの問題ではなく,多くの要因(表1)が関係していると思います。あまりにも「悪いもの=ないもの」が多過ぎるので,ちょっとやそっとの改善では上達しないのかもしれません(上達のコツは第7・8話でお話します)。今回はそれぞれについての問題点・改善点を検討していきます。
■卒前教育?:プレゼンテーションについての教育がない自分自身が学生であったときには,プレゼンテーションのフォームを正式に教わったという記憶がありません(単に自分自身が不真面目であっただけかもしれませんが)。実際,2005年に当院の研修医24名(1/2年目15人,3/4年目9人:2005年度)に取ったアンケートでは,卒前教育でプレゼンテーションの教育を受けていないと答えたのは22名で,受けたと答えた人はわずかに2名でした。 プレゼンテーションの仕方,というものを授業で教わる,というのは難しいかもしれません。やはり臨床実習のなかで,継続したプレゼンテーションの機会が設けられることによって,訓練されていくものではないかと思います。現在の縦割りの科の中では,研修医に対する共通の継続した教育は難しいのかもしれませんが,臨床実習として,学生を主体とした発表の場を用意することは,まだ可能ではないでしょうか? ■研修医?:病歴・身体所見が十分に取れない,病態と結びつけられない,プレゼンテーションのフォーマットを知らないプレゼンテーションを行うには,事前の情報収集が大切となります(詳細は次号)。例は極端かもしれませんが,研修医では,病歴や身体所見と病態を結びつける知識と経験が不足しています。
身体所見も同様です。どういった所見が重症度・鑑別疾患を判断するのに必要なのか,ということが理解できていない場合もあります。 一方,すでに「誰か」によって指示された華やかで客観的な検査所見の解釈は,日を重ねるごとに上手になっていきます。各検査の感度/特異度や特殊検査の解釈は習得していくかもしれませんが,なぜその検査が必要なのか,病歴・身体所見から得られた検査前確率はどうなのか,といった思考について検討される機会は少ないのかもしれません。 プレゼンテーションのフォーマットを知らないことも問題です。現在ではプレゼンテーションに関する書籍も増えてきていますが,施設として共通のフォーマットを研修医に手渡しているところは,まだ少ないのではないかと思います。今回の連載も医学生だけでなく,初期研修医や後期研修医,さらにはスタッフの先生方にもお役に立てれば……と思います。 (つづきは本誌をご覧ください)
|
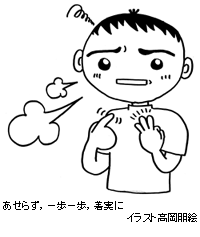 「詳細な」病歴聴取と,「適切な」病歴聴取は異なります。単なる記録のための病歴聴取となっている可能性もあります。Review of Systemsを含めて,鑑別疾患を念頭に置いた病歴聴取が,目の前の症例だけでなく,今後出会う症例に対応するのに大きく役立つことを覚えておいてほしいです。
「詳細な」病歴聴取と,「適切な」病歴聴取は異なります。単なる記録のための病歴聴取となっている可能性もあります。Review of Systemsを含めて,鑑別疾患を念頭に置いた病歴聴取が,目の前の症例だけでなく,今後出会う症例に対応するのに大きく役立つことを覚えておいてほしいです。