| ●病理との付き合い方 明日から使える病理の基本【実践編】 | ||||||
第5回テーマ リンパ節 加留部謙之輔(久留米大学医学部医学科病理学) 血液内科領域においても,病理とかかわる機会は,特にリンパ節病変の際などにおいてしばしば認められると思う。しかし,生検など臨床とのかかわりの深い病理の分野が「外科病理」といわれることだけあって,現在は,病理は主に外科とのつながりが深い科になっている。そのため,外科における病理経験者の割合に対し,内科,特に血液内科医におけるそれは低い傾向にある。そのこともあって,リンパ節,骨髄の病理診断の現場は,多くの血液臨床医にとってブラックボックスになっていると思われる。しかし,病理診断はしばしば病気の診断という医療行為の根幹をなす部分であり,確度の高い病理診断を得るためには病理医のみならず臨床医がかかわる部分が多い。本稿では,リンパ節の病気,特に悪性リンパ腫の確実な診断のために臨床医サイドで大切なことを述べていきたい。 ■どのようなときに病理検査を行うべきかどのような疾患に病理検査が有効かについて,表1に記した。まず重要なのは,悪性リンパ腫である。この疾患群は,病理診断抜きで診断が確定することはありえない。また,結核,サルコイドーシスをはじめとした特殊な反応性病変も病理検査で診断がつく場合が多い。それに対し,せっかく組織を採取しても,それだけでは診断が確定できない疾患もある。特に感染症や膠原病などは,ある程度個々の傾向はあるものの非特異的な炎症像であるので,病理組織だけでは確定診断には至らない。これらの病気は,臨床症状からみた診断基準や,培養検査などのほうがより“強い”検査である。しかし,病理診断は,それの補助診断としては活用できる。
■生検か細胞診か細胞診は侵襲の少ない検査であり,確定診断にまでは至ることは少ないものの,スクリーニング検査として,特に婦人科領域や呼吸器領域などで頻用されている。リンパ節においても,悪性リンパ腫のsubtypeの確定については困難であるが,癌の転移や肉腫との鑑別などは可能であり,そのような場合は,不必要な生検が避けられることがある。最近は,細胞診を飛ばして直接生検されることが多くなる傾向にあるが,基本的には細胞診→生検というのが本来の流れである(経過が急で診断を急ぐ場合は別)。■生検における注意点1. 針生検か手術か肝臓や前立腺など,針生検の対象臓器は侵襲が少ないこともあって広がっており,リンパ節に対してもしばしば行われる。しかし,リンパ節は,その最も普遍的な診断基準である新WHO分類1) が非常に複雑な分類になっており,針生検からの情報だけでは正確なsubtypeまで診断が不可能なことがある。やはり基本は手術のうえ,腫脹しているリンパ節全体を採取するのが望ましい。2. どのリンパ節を採取すべきか腫大しているリンパ節が一つの場合は迷うことは少ないが,多数認められる場合は,どこを採取するかの選択に迫られる。そこで優先順位があるとすれば,以下のようである。1)最も腫大しているリンパ節,2)体表面リンパ節,3)鼠経リンパ節以外。
2) 体表面のリンパ節
3) 鼠径リンパ節以外
このように単純に述べたが,実際はさまざまなジレンマがある。例えば,腸間膜リンパ節が最大に腫脹しているが,頚部にも優位な腫大があり,開腹生検は診断には有用だろうが,頚部で診断がつけば侵襲は少なくてすむものの,診断がつかなかった場合,二重に手術してしまうことになる,といった場合である。最終的には患者としっかり話し合って決めていくしかないであろう。 (つづきは本誌をご覧ください) 文献
|
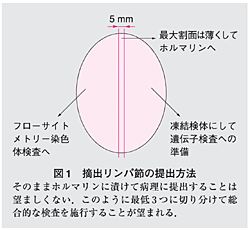 1) 最も腫大しているリンパ節
1) 最も腫大しているリンパ節