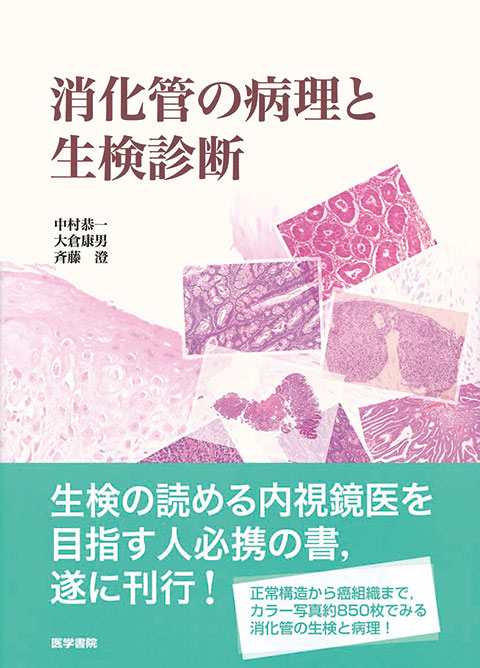消化管の病理と生検診断
消化管内視鏡医必読! 生検組織診断のエッセンスを専門家の解説で学ぶ
もっと見る
今日、消化管疾患の診断には内視鏡的生検による組織診断が不可欠のものとなっている。特に、食道癌、胃癌、大腸癌などの消化管癌の診断において、生検組織診断は決定的な役割を果たしており、治療法の選択にも直結する情報を提供する。本書は、極めて重要な腫瘍性病変の良悪性の鑑別を中心に、経験豊かな病理医が生検組織診断のエッセンスを解説する。消化管内視鏡医必読の書である。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序にかえて
日本における消化管生検診断の短い歴史と本書
本書は消化管生検診断の実際において,直接的間接的に役立つことを目的としています.そのため,本書では各臓器ごとに簡単な解剖組織学をはじめに記載し,続いて生検診断において必要な,それがよって立つところの基礎的な外科病理組織学を記述し,その後に生検診断について記述するという形をとりました.
さて,この外科病理学と消化管の生検組織診断は,現在の日本においては一般的となっていますが,これが日本で始められたのは,そう遠い過去のことではありません.消化管癌の早期診断に欠かすことのできないファイバースコープによる直視下胃生検法が開発され,胃生検組織診断がなされるようになったのはつい最近のことです(1964年).その後,胃の生検診断が日本において急速に進歩して,この分野では世界をリードするまでになりました.この外科病理学と消化管生検組織診断の始まりである胃生検組織診断の短い歴史を描いてみます.
1960年以前の日本の病理学は,病理解剖診断とそれを対象とした研究および実験病理が主流であった時代でした.生前の病気の診断に直接携わる生検組織診断,および外科病理学的研究はあまりなされてはいませんでした.このような時期に,筆者の恩師である故・太田邦夫教授は,1951年(昭和26年)ニューヨークのMemorial Hospitalで外科病理学の権威Dr. Stewartのもとで外科病理学の研鑽を積み,そして日本でその外科病理診断学の教育と普及に尽力されました.この外科病理診断学の黎明期における消化管生検,特に胃生検の病理組織診断はというと,当時はまっすぐの鉄管あるいはその鉄管の1,2か所に関節のあるいわゆる硬性胃鏡で胃内を観察していました.その時に,粘膜組織片を採取して病理組織診断が試みられてはいましたが,実用にはほど遠い検査で,その検査法は試験段階で稀にしか行われていませんでした.
1958年,Hirschowitz1)によってグラスファイバーを用いた軟式胃内視鏡が開発され,白壁・市川らによって確立されたX線二重造影法2)とによって,早期胃癌の術前の発見・診断がなされるようになりました.しかし,それらの検査はまだ一部の施設で行われているに過ぎず,早期胃癌と診断される症例の数は少ない状態がしばらく続きました.
筆者はこのような時期に,1962年から癌研究会癌研究所病理部で勉強することになり,生検組織と手術標本の病理組織診断に携わっていました.ある時から,マッチ棒の頭くらいの大きさの胃粘膜組織片が日常の生検診断の俎上に載るようになってきました.癌研究会付属病院外科の高木国夫先生が,ファイバースコープの横に細いチューブをセロテープで固定し,そのチューブの中に鉗子を入れて内視鏡直視下で胃の病変部の組織を採取し,それを顕微鏡で診断するという“内視鏡的直視下胃生検診断”を世界に先駆けて始めたのです.胃生検症例は徐々に数を増し,そして,高木らは1964年に“ファイバースコープによる直視下胃生検法”を発表しました3).これが私にとって胃生検組織に接した始まりであり,胃生検組織診断をした始まりでした.1965年には,症例数は少ないのですが胃生検組織とその切除胃組織との対比を行った論文4)を書いてみたりもしました.この時期においては消化管病変の生検はほとんどなされていなかった時代であり,よい参考書もなく診断に困ったことを今でも思い出すことがあります.
徐々に直視下胃生検法が普及するとともに,生検組織診断が問題となってきました.癌であるにもかかわらず生検組織で癌と診断されない症例,あるいはその逆の症例があったりしていたからです.胃生検組織診断は一時期混乱状態にありました.外科病理がやっと普及し始めた時期でもあり,多くの病理医は小さな組織をもって診断する生検組織診断の経験がないか,あるいは不慣れであったためでしょう.そこで,1971年に胃癌研究会は胃生検組織診断のための一つの指針としての“胃生検組織診断基準─Group分類(委員長・故・長与健夫)”5)を発表しました.この診断基準は多少の改訂が加えられて現在に至っていますが,Group分類発表後は胃癌生検組織診断に関するばらつきはかなり狭められ,以前のような極端な誤診例は少なくなりました.
胃生検組織診断は以上のような変遷を経て現在に至っていますが,1977年には大腸癌研究会が大腸癌生検組織診断基準を発表しました.また,西沢護先生らは胃内視鏡検査の終了した後に,内視鏡を引き抜く帰りに食道の観察を行い微小発赤あるいはびらんがあった場合に生検組織を採取し,また,ルゴール染色を施して不染帯から生検組織を採取して,食道上皮内癌を多数発見して発表しました6).その生検組織診断を,本書の著者の一人である大倉康男先生が担当していました.
消化管の直視下内視鏡生検法が普及しはじめた1980年に,筆者は太田教授門下の故・喜納勇先生(浜松医科大学病理学教授)と共著で,本書の前身である『消化管の病理と生検組織診断』を出版しました7).
日本は早期胃癌の診断については世界をリードしていました.それはX線二重造影検査,内視鏡検査,そして内視鏡的直視下生検と切除標本について,消化管疾患を専門とする内科医,外科医,そして病理医が一体となって診断するという,いわば学際的体制がもたらした成果でもあります8).
1972年,故・村上忠重教授(東京医科歯科大学医学部外科)および故・白壁彦夫教授(順天堂大学内科)は,国際協力事業団の協力のもとに,世界各国の臨床医を対象として毎年“外国医師のための早期胃癌診断”の研修会を主催しました.この研修会では,約3か月の期間をもって早期胃癌診断のためのX線二重造影法読影,内視鏡診断および早期胃癌の病理の講義,そして各施設における実習が行われました.この研修会は毎年開催され,それは31回にも及びました.この研修会に参加した外国の医師は,現在ではそれぞれの国で指導的立場にあって活躍しています.
この研修に参加した医師が帰国してX線・内視鏡的に早期癌を発見し,欣喜雀躍したのも束の間,病理医が生検組織あるいは切除胃の標本を癌と診断してくれないという事例が数多くあることを聞くに及び,消化管の早期癌の病理,特に早期胃癌の病理とその生検診断の研修会が必要であることに気がつきました.
そこで,1983年,日本の消化管病理を専門としている諸先生の協力のもとに筑波大学で第1回外国病理医のための消化管早期癌の病理とその生検診断の研修会『国際消化管癌病理研修会International Advanced Course of Gastrointestinal Tumor Pathology』を国際協力事業団の協力のもとに3か月の期間をもって開催しました.この研修会では日本の消化管病理学を専門としている諸先生に講義と診断実習,特に生検診断についての指導をお願いしました.この研修会は毎年1回筑波大学で,続いて東京医科歯科大学で開催しました.この研修会は16回にも及びました.本書の共著者である国際医療センター病理故・斉藤澄博士および杏林医科大学病理学教授・大倉康男先生は,筑波大学および東京医科歯科大学の研修会で協力してくれた同僚であり,研修会を通じて消化管早期癌診断および生検組織診断の講義・実習に尽力され,日本の消化管病理学を世界に広く知らしめました.鹿鳴館思想の消えやらぬ分野がいまだ残存している9)日本ではありますが,消化管癌の早期診断学は日本で確立され,それは世界で受け入れられています.
以上が日本における消化管早期癌と生検組織診断に関する始めから現在に至るまでの簡単な歴史です.筆者は,上述したように,高木国夫博士の本邦初の胃生検標本を検鏡して以来,今日,重要な診断ツールとして日常診療に欠かせないものとなるまでの消化管生検組織診断の進歩・発展の姿をつぶさにみてきました.この経過の途中には,胃微小癌,胃異型上皮巣,さらには大腸癌の組織診断基準などをめぐるいろいろな問題が生起し,さまざまな議論が交わされました.こうした先人の労苦の集積のうえに到達した現在の消化管病理と生検組織診断の全体像をここに提示したつもりです.消化管疾患の診療を日々担っている読者諸兄姉の参考となれば幸いです.
2010年6月
中村恭一
【文献】
1) Hirschowitz IB, Curtiss LE, Peters CW, et al : Demonstration of new gastroscope, the “Fiberscope”. Gastroenterology 35 : 50-53, 1958
2) 三輪清三,白壁彦夫:胃ポリープのX線診断.臨床消化器病学4 : 325, 335, 1956
3) 黒川利雄,淵上在弥,高木国夫,他:ファイバースコープによる直視下胃生検法.消化器病の臨床6:927-934,1964
4) 中村恭一:生検による胃癌の早期診断:直視下胃生検材料とその手術胃の病理組織学的比較.癌の臨床別冊:癌・早期診断.pp153-159,医歯薬出版,1965
5) 胃癌研究会(編):胃癌取扱い規約,改訂8版.金原出版,1971
6) 西沢 護,細井董三,牧野哲也:早期食道癌の診断.医学書院,1988
7) 中村恭一・喜納 勇:消化管の病理と生検組織診断.医学書院,1980
8) 胃癌研究会(編):日本の胃癌.金原出版,1996
9) 岡田節人:鹿鳴館時代が続いている.産経新聞1996年5月12日付 第11面
【国際研修会】
・1972~2000年:第1~31回外国人医師早期胃がん診断セミナー
・1981~1995年:El Curso Internacional de Avances en Gastroenterolog・a, en Santiago de Chile
・1983~1999年:第1~16回国際消化管病理学研修会 筑波大学,東京医科歯科大学
日本における消化管生検診断の短い歴史と本書
本書は消化管生検診断の実際において,直接的間接的に役立つことを目的としています.そのため,本書では各臓器ごとに簡単な解剖組織学をはじめに記載し,続いて生検診断において必要な,それがよって立つところの基礎的な外科病理組織学を記述し,その後に生検診断について記述するという形をとりました.
さて,この外科病理学と消化管の生検組織診断は,現在の日本においては一般的となっていますが,これが日本で始められたのは,そう遠い過去のことではありません.消化管癌の早期診断に欠かすことのできないファイバースコープによる直視下胃生検法が開発され,胃生検組織診断がなされるようになったのはつい最近のことです(1964年).その後,胃の生検診断が日本において急速に進歩して,この分野では世界をリードするまでになりました.この外科病理学と消化管生検組織診断の始まりである胃生検組織診断の短い歴史を描いてみます.
1960年以前の日本の病理学は,病理解剖診断とそれを対象とした研究および実験病理が主流であった時代でした.生前の病気の診断に直接携わる生検組織診断,および外科病理学的研究はあまりなされてはいませんでした.このような時期に,筆者の恩師である故・太田邦夫教授は,1951年(昭和26年)ニューヨークのMemorial Hospitalで外科病理学の権威Dr. Stewartのもとで外科病理学の研鑽を積み,そして日本でその外科病理診断学の教育と普及に尽力されました.この外科病理診断学の黎明期における消化管生検,特に胃生検の病理組織診断はというと,当時はまっすぐの鉄管あるいはその鉄管の1,2か所に関節のあるいわゆる硬性胃鏡で胃内を観察していました.その時に,粘膜組織片を採取して病理組織診断が試みられてはいましたが,実用にはほど遠い検査で,その検査法は試験段階で稀にしか行われていませんでした.
1958年,Hirschowitz1)によってグラスファイバーを用いた軟式胃内視鏡が開発され,白壁・市川らによって確立されたX線二重造影法2)とによって,早期胃癌の術前の発見・診断がなされるようになりました.しかし,それらの検査はまだ一部の施設で行われているに過ぎず,早期胃癌と診断される症例の数は少ない状態がしばらく続きました.
筆者はこのような時期に,1962年から癌研究会癌研究所病理部で勉強することになり,生検組織と手術標本の病理組織診断に携わっていました.ある時から,マッチ棒の頭くらいの大きさの胃粘膜組織片が日常の生検診断の俎上に載るようになってきました.癌研究会付属病院外科の高木国夫先生が,ファイバースコープの横に細いチューブをセロテープで固定し,そのチューブの中に鉗子を入れて内視鏡直視下で胃の病変部の組織を採取し,それを顕微鏡で診断するという“内視鏡的直視下胃生検診断”を世界に先駆けて始めたのです.胃生検症例は徐々に数を増し,そして,高木らは1964年に“ファイバースコープによる直視下胃生検法”を発表しました3).これが私にとって胃生検組織に接した始まりであり,胃生検組織診断をした始まりでした.1965年には,症例数は少ないのですが胃生検組織とその切除胃組織との対比を行った論文4)を書いてみたりもしました.この時期においては消化管病変の生検はほとんどなされていなかった時代であり,よい参考書もなく診断に困ったことを今でも思い出すことがあります.
徐々に直視下胃生検法が普及するとともに,生検組織診断が問題となってきました.癌であるにもかかわらず生検組織で癌と診断されない症例,あるいはその逆の症例があったりしていたからです.胃生検組織診断は一時期混乱状態にありました.外科病理がやっと普及し始めた時期でもあり,多くの病理医は小さな組織をもって診断する生検組織診断の経験がないか,あるいは不慣れであったためでしょう.そこで,1971年に胃癌研究会は胃生検組織診断のための一つの指針としての“胃生検組織診断基準─Group分類(委員長・故・長与健夫)”5)を発表しました.この診断基準は多少の改訂が加えられて現在に至っていますが,Group分類発表後は胃癌生検組織診断に関するばらつきはかなり狭められ,以前のような極端な誤診例は少なくなりました.
胃生検組織診断は以上のような変遷を経て現在に至っていますが,1977年には大腸癌研究会が大腸癌生検組織診断基準を発表しました.また,西沢護先生らは胃内視鏡検査の終了した後に,内視鏡を引き抜く帰りに食道の観察を行い微小発赤あるいはびらんがあった場合に生検組織を採取し,また,ルゴール染色を施して不染帯から生検組織を採取して,食道上皮内癌を多数発見して発表しました6).その生検組織診断を,本書の著者の一人である大倉康男先生が担当していました.
消化管の直視下内視鏡生検法が普及しはじめた1980年に,筆者は太田教授門下の故・喜納勇先生(浜松医科大学病理学教授)と共著で,本書の前身である『消化管の病理と生検組織診断』を出版しました7).
日本は早期胃癌の診断については世界をリードしていました.それはX線二重造影検査,内視鏡検査,そして内視鏡的直視下生検と切除標本について,消化管疾患を専門とする内科医,外科医,そして病理医が一体となって診断するという,いわば学際的体制がもたらした成果でもあります8).
1972年,故・村上忠重教授(東京医科歯科大学医学部外科)および故・白壁彦夫教授(順天堂大学内科)は,国際協力事業団の協力のもとに,世界各国の臨床医を対象として毎年“外国医師のための早期胃癌診断”の研修会を主催しました.この研修会では,約3か月の期間をもって早期胃癌診断のためのX線二重造影法読影,内視鏡診断および早期胃癌の病理の講義,そして各施設における実習が行われました.この研修会は毎年開催され,それは31回にも及びました.この研修会に参加した外国の医師は,現在ではそれぞれの国で指導的立場にあって活躍しています.
この研修に参加した医師が帰国してX線・内視鏡的に早期癌を発見し,欣喜雀躍したのも束の間,病理医が生検組織あるいは切除胃の標本を癌と診断してくれないという事例が数多くあることを聞くに及び,消化管の早期癌の病理,特に早期胃癌の病理とその生検診断の研修会が必要であることに気がつきました.
そこで,1983年,日本の消化管病理を専門としている諸先生の協力のもとに筑波大学で第1回外国病理医のための消化管早期癌の病理とその生検診断の研修会『国際消化管癌病理研修会International Advanced Course of Gastrointestinal Tumor Pathology』を国際協力事業団の協力のもとに3か月の期間をもって開催しました.この研修会では日本の消化管病理学を専門としている諸先生に講義と診断実習,特に生検診断についての指導をお願いしました.この研修会は毎年1回筑波大学で,続いて東京医科歯科大学で開催しました.この研修会は16回にも及びました.本書の共著者である国際医療センター病理故・斉藤澄博士および杏林医科大学病理学教授・大倉康男先生は,筑波大学および東京医科歯科大学の研修会で協力してくれた同僚であり,研修会を通じて消化管早期癌診断および生検組織診断の講義・実習に尽力され,日本の消化管病理学を世界に広く知らしめました.鹿鳴館思想の消えやらぬ分野がいまだ残存している9)日本ではありますが,消化管癌の早期診断学は日本で確立され,それは世界で受け入れられています.
以上が日本における消化管早期癌と生検組織診断に関する始めから現在に至るまでの簡単な歴史です.筆者は,上述したように,高木国夫博士の本邦初の胃生検標本を検鏡して以来,今日,重要な診断ツールとして日常診療に欠かせないものとなるまでの消化管生検組織診断の進歩・発展の姿をつぶさにみてきました.この経過の途中には,胃微小癌,胃異型上皮巣,さらには大腸癌の組織診断基準などをめぐるいろいろな問題が生起し,さまざまな議論が交わされました.こうした先人の労苦の集積のうえに到達した現在の消化管病理と生検組織診断の全体像をここに提示したつもりです.消化管疾患の診療を日々担っている読者諸兄姉の参考となれば幸いです.
2010年6月
中村恭一
【文献】
1) Hirschowitz IB, Curtiss LE, Peters CW, et al : Demonstration of new gastroscope, the “Fiberscope”. Gastroenterology 35 : 50-53, 1958
2) 三輪清三,白壁彦夫:胃ポリープのX線診断.臨床消化器病学4 : 325, 335, 1956
3) 黒川利雄,淵上在弥,高木国夫,他:ファイバースコープによる直視下胃生検法.消化器病の臨床6:927-934,1964
4) 中村恭一:生検による胃癌の早期診断:直視下胃生検材料とその手術胃の病理組織学的比較.癌の臨床別冊:癌・早期診断.pp153-159,医歯薬出版,1965
5) 胃癌研究会(編):胃癌取扱い規約,改訂8版.金原出版,1971
6) 西沢 護,細井董三,牧野哲也:早期食道癌の診断.医学書院,1988
7) 中村恭一・喜納 勇:消化管の病理と生検組織診断.医学書院,1980
8) 胃癌研究会(編):日本の胃癌.金原出版,1996
9) 岡田節人:鹿鳴館時代が続いている.産経新聞1996年5月12日付 第11面
【国際研修会】
・1972~2000年:第1~31回外国人医師早期胃がん診断セミナー
・1981~1995年:El Curso Internacional de Avances en Gastroenterolog・a, en Santiago de Chile
・1983~1999年:第1~16回国際消化管病理学研修会 筑波大学,東京医科歯科大学
目次
開く
第 I 部 食道疾患の病理と生検診断
A 食道の正常構造
1.解剖学的位置
2.正常組織構造
B 食道の生検標本
C 形成異常
1.異所性胃粘膜
2.異所性皮脂腺
3.メラノーシス
D アカラシア
E 食道炎と食道潰瘍
1.食道炎
2.食道びらん・潰瘍
3.感染性食道炎
F Barrett食道
1.食道胃接合部の定義
2.食道胃接合部の組織所見
3.食道胃接合部領域
4.Barrett食道
5.Barrett腺癌
G 良性上皮性病変
1.糖原過形成
2.乳頭腫
3.腺腫
H 食道癌
1.扁平上皮癌
2.類基底細胞(扁平上皮)癌
3.癌肉腫
4.腺癌
5.腺扁平上皮癌
6.粘表皮癌
7.腺様嚢胞癌
8.内分泌細胞癌
9.未分化癌
10.悪性黒色腫
I 長期経過観察された食道粘膜癌の生検診断
J 上皮内腫瘍
1.異形成から上皮内腫瘍への移行
2.組織標本における上皮内腫瘍の実態
3.上皮内腫瘍の問題点
4.上皮内腫瘍の取り扱い方
K 良悪性の鑑別診断
L 非上皮性腫瘍
1.平滑筋腫
2.顆粒細胞腫
3.その他の非上皮性腫瘍
M 全身性疾患の食道病変
第 II 部 胃疾患の病理と生検診断
A 胃の正常組織構造
1.胃の組織像
2.生検胃粘膜組織の観察
B 腸上皮化生
1.腸上皮化生粘膜の組織所見
2.F境界線の定義と型分類
3.F境界線の加齢に伴う移動
4.F境界線からみた腸上皮化生の原因
5.腸上皮化生粘膜の生検診断
C 胃潰瘍
1.胃潰瘍の病理
2.胃潰瘍の治癒
3.胃潰瘍の発生機序
4.胃潰瘍の生検診断
D 胃の上皮性隆起性病変 過形成性ポリープ,腺腫,癌腫,そして異型上皮巣
1.上皮性ポリープの組織学的分類
2.限局性上皮性隆起性病変の組織所見と頻度
3.胃の広義の異型上皮巣についての歴史と考え方の変遷
E 胃癌組織発生とそれからみた胃癌の臨床病理
1.胃癌の肉眼形態
2.胃癌組織発生の概観
3.胃癌の組織型分類
4.胃癌組織発生の観点からの癌組織型分類,その臨床病理学的意義
F 胃癌と上皮性ポリープの生検診断
1.胃内視鏡的生検とGroup分類の目的
2.Group分類と異型度パターン認識
3.異型度パターン認識と病変の質とGroup分類と
4.胃癌組織発生別にみた生検診断とGroup分類
5.癌か良性病変か紛らわしい生検組織の診断
G 内分泌細胞由来の腫瘍
H 胃炎
1.胃炎の分類
2.通常型胃炎
3.特殊型胃炎
I 胃悪性リンパ腫とその類縁疾患
1.胃悪性リンパ腫の概略
2.胃悪性リンパ腫各論
3.胃悪性リンパ腫の生検診断
J 粘膜下腫瘍と腫瘍様病変
K アミロイドーシス
第 III 部 十二指腸・小腸・虫垂疾患の病理と生検診断
1.十二指腸の疾患
2.小腸の疾患
3.虫垂の疾患
第 IV 部 大腸疾患の病理と生検診断
A 大腸の正常構造
B 大腸癌組織発生とそれからみた大腸癌の臨床病理
1.大腸癌組織発生をめぐる現代史
2.腺腫・癌の異型度と分化度について
3.確率的に良性悪性を振り分ける判別式に基づく
大腸癌の構造,その概略:組織診断基準,組織発生,生物学的振る舞い
4.大腸癌取扱い規約による大腸の腺腫と癌の組織型分類
5.腫瘍病理組織学の大前提に基づく大腸癌組織型分類
6.癌組織診断にまつわる問題
7.大腸上皮性腫瘍の異型度による生検組織分類と組織診断
C その他の大腸病変
D 大腸の炎症性疾患
1.潰瘍性大腸炎
2.Crohn病
3.腸結核
4.その他の炎症性大腸病変
E 大腸の発育異常・奇形・機械的障害および循環障害
第 V 部 肛門管疾患の病理と生検診断
1.肛門管の正常構造
2.肛門管の病変
索引
A 食道の正常構造
1.解剖学的位置
2.正常組織構造
B 食道の生検標本
C 形成異常
1.異所性胃粘膜
2.異所性皮脂腺
3.メラノーシス
D アカラシア
E 食道炎と食道潰瘍
1.食道炎
2.食道びらん・潰瘍
3.感染性食道炎
F Barrett食道
1.食道胃接合部の定義
2.食道胃接合部の組織所見
3.食道胃接合部領域
4.Barrett食道
5.Barrett腺癌
G 良性上皮性病変
1.糖原過形成
2.乳頭腫
3.腺腫
H 食道癌
1.扁平上皮癌
2.類基底細胞(扁平上皮)癌
3.癌肉腫
4.腺癌
5.腺扁平上皮癌
6.粘表皮癌
7.腺様嚢胞癌
8.内分泌細胞癌
9.未分化癌
10.悪性黒色腫
I 長期経過観察された食道粘膜癌の生検診断
J 上皮内腫瘍
1.異形成から上皮内腫瘍への移行
2.組織標本における上皮内腫瘍の実態
3.上皮内腫瘍の問題点
4.上皮内腫瘍の取り扱い方
K 良悪性の鑑別診断
L 非上皮性腫瘍
1.平滑筋腫
2.顆粒細胞腫
3.その他の非上皮性腫瘍
M 全身性疾患の食道病変
第 II 部 胃疾患の病理と生検診断
A 胃の正常組織構造
1.胃の組織像
2.生検胃粘膜組織の観察
B 腸上皮化生
1.腸上皮化生粘膜の組織所見
2.F境界線の定義と型分類
3.F境界線の加齢に伴う移動
4.F境界線からみた腸上皮化生の原因
5.腸上皮化生粘膜の生検診断
C 胃潰瘍
1.胃潰瘍の病理
2.胃潰瘍の治癒
3.胃潰瘍の発生機序
4.胃潰瘍の生検診断
D 胃の上皮性隆起性病変 過形成性ポリープ,腺腫,癌腫,そして異型上皮巣
1.上皮性ポリープの組織学的分類
2.限局性上皮性隆起性病変の組織所見と頻度
3.胃の広義の異型上皮巣についての歴史と考え方の変遷
E 胃癌組織発生とそれからみた胃癌の臨床病理
1.胃癌の肉眼形態
2.胃癌組織発生の概観
3.胃癌の組織型分類
4.胃癌組織発生の観点からの癌組織型分類,その臨床病理学的意義
F 胃癌と上皮性ポリープの生検診断
1.胃内視鏡的生検とGroup分類の目的
2.Group分類と異型度パターン認識
3.異型度パターン認識と病変の質とGroup分類と
4.胃癌組織発生別にみた生検診断とGroup分類
5.癌か良性病変か紛らわしい生検組織の診断
G 内分泌細胞由来の腫瘍
H 胃炎
1.胃炎の分類
2.通常型胃炎
3.特殊型胃炎
I 胃悪性リンパ腫とその類縁疾患
1.胃悪性リンパ腫の概略
2.胃悪性リンパ腫各論
3.胃悪性リンパ腫の生検診断
J 粘膜下腫瘍と腫瘍様病変
K アミロイドーシス
第 III 部 十二指腸・小腸・虫垂疾患の病理と生検診断
1.十二指腸の疾患
2.小腸の疾患
3.虫垂の疾患
第 IV 部 大腸疾患の病理と生検診断
A 大腸の正常構造
B 大腸癌組織発生とそれからみた大腸癌の臨床病理
1.大腸癌組織発生をめぐる現代史
2.腺腫・癌の異型度と分化度について
3.確率的に良性悪性を振り分ける判別式に基づく
大腸癌の構造,その概略:組織診断基準,組織発生,生物学的振る舞い
4.大腸癌取扱い規約による大腸の腺腫と癌の組織型分類
5.腫瘍病理組織学の大前提に基づく大腸癌組織型分類
6.癌組織診断にまつわる問題
7.大腸上皮性腫瘍の異型度による生検組織分類と組織診断
C その他の大腸病変
D 大腸の炎症性疾患
1.潰瘍性大腸炎
2.Crohn病
3.腸結核
4.その他の炎症性大腸病変
E 大腸の発育異常・奇形・機械的障害および循環障害
第 V 部 肛門管疾患の病理と生検診断
1.肛門管の正常構造
2.肛門管の病変
索引
書評
開く
消化器にかかわる医師の必読書
書評者: 柳澤 昭夫 (京府医大大学院教授・人体病理学)
生検の組織診断は,非常に小さい検体を顕微鏡的に行うが,誤らずに診断するためには,検体に含まれている病変の病理を正確に把握することが要求される。そのためには,観察している検体が含んでいる病変の情報のみならず,その病変が発生した環境・病態も十分理解しておく必要がある。本書は,まさに,生検を正しく診断するために書かれた教科書であり専門書である。
本書は30年前,わが国初の本格的な消化管の生検病理診断書として出版され,長年にわたり病理医・臨床医のバイブルとして用いられてきた当時筑波大学教授・中村恭一先生,浜松医科大学教授故・喜納 勇先生により出版された『消化管の病理と生検組織診断』の流れをくむ専門書である。共著者には,筑波大学名誉教授・東京医科歯科大学名誉教授の中村恭一先生のほか,中村門下の杏林大学教授・大倉康男博士と国際医療センター病理・故斉藤 澄博士が当たっている。
本書の特徴は,前述したように,ただの生検診断書ではなく,豊富な材料を縦横に駆使して適切かつ簡明に病変を解説し,病変の病理を正確に把握した上で正確な生検診断を行えるように述べられている点である。このことは,病理医のみならず臨床医にとっても,肉眼像から病態を理解し,生検組織から病変を正確に診断するために有効な教科書となっている。
今日,消化管疾患の診断には内視鏡的生検による組織診断が不可欠のものであるが,胃の生検診断の歴史はそれほど古いものではない。胃生検診断が始まった当初は,病理医がそれまで経験がないようなマッチ棒の頭ぐらいの小さい組織で診断するため,その診断結果は,癌であるにもかかわらず癌と診断されないなど生検診断に混乱状態があったと,著者中村先生が冒頭で触れている。このような生検診断の混乱状態を経て,生検診断は消化管疾患の診断になくてはならない地位を確立してきたわけである。
著者らは,消化器の病理研究における第一人者であるとともに日常診断に従事しており,診断の難しさや犯しやすい間違いにも精通している。特に,中村先生は,生検組織検査が始められた当初から生検組織診断にかかわっており,この分野の先駆者である。本書は,生検診断に誤りがないように,診断に有用な解剖組織学,基礎的な外科病理組織学,その後の生検診断について記述する形をとっている。このことは,日常生検診断に従事している病理医が正確に病理診断するため,内視鏡検査を行っている内視鏡医が病態を理解するため,また,新たに消化器の病理や生検診断を学ぼうとしている臨床医・病理医のために有効である。すなわち,本書は,消化器に関与する医師にとっての入門書,専門書であり,必読書といえる。
消化器内視鏡医にとって最良の病理解説書
書評者: 鶴田 修 (久留米大教授・消化器内科学)
今から約25年前,故白壁彦夫教授が司会をされていた研究会に久留米大学からIIc型早期大腸癌症例を提示したことがあった。外科手術症例で標本の張り付け方が悪く,X線,内視鏡などの画像とマクロの対応が困難となってしまい,白壁教授からかなり強烈なお叱りを受けて立ち往生している時に,当時筑波大学教授であった本書著者の中村恭一先生から「病理学的には頭の中で切除標本を伸ばせば,マクロと画像そして病理組織像の対応は可能である」というお助けの言葉をいただき,その場をなんとか切り抜けることができた。先生のお優しさには今でも大変に感謝している。中村先生は臨床の疑問点を理解され,真摯に答えようとされる。先生の下で研修した多く医師が日本各地で消化管画像診断学のリーダーになっていることにも納得がいく次第である。
さて,共著者である杏林大学・大倉教授から「本書は1980年に中村先生と故喜納勇教授の共著で出版された『消化管の病理と生検組織診断』を時代に合わせて改訂し,足りない部分を補充したものだ」というお話を伺っていたが,実際読ませていただくと前書と比べてその内容の充実ぶりに驚かされた。全消化管(食道,胃,十二指腸・小腸・虫垂,大腸,肛門管)の解剖,形成異常,炎症性疾患,非腫瘍性疾患,腫瘍性疾患について,カラーのマクロ写真,切除標本・生検標本の病理組織写真,内視鏡写真,図表を駆使して漏れなく記載・解説されており,非常にわかりやすく,特に腫瘍の項などは中村先生の癌発生とその組織像・診断に関する哲学までも十分に感じることのできる内容となっている。
消化管の内視鏡診断を行うには,正常消化管組織像,疾患の概念,肉眼像,病理組織像を理解・記憶することは,少々苦痛ではあるが必須である。また,最初は苦痛であるが,少しの努力により疾患の理解,内視鏡所見の読影力がつきだすと,苦痛は次第に快感へと変わり,それに伴いどんどんと実力も向上していくものである。
これまでの消化器内視鏡医のための病理解説書は簡単過ぎたり,難し過ぎたりで,内視鏡医にとっては“帯に短し襷に長し”と感じるものが多かったが,本書は内視鏡医に必要と思われる項目について“痒いところまで手の届く”内容に仕上がっており,苦痛を最も少なくして多くの知識を系統的に理解できる最高の1冊である。
ここに消化器内視鏡医にとって最良の病理解説書が出版された。消化器内視鏡専門医をめざす医師にとっては必須の1冊である。
書評者: 柳澤 昭夫 (京府医大大学院教授・人体病理学)
生検の組織診断は,非常に小さい検体を顕微鏡的に行うが,誤らずに診断するためには,検体に含まれている病変の病理を正確に把握することが要求される。そのためには,観察している検体が含んでいる病変の情報のみならず,その病変が発生した環境・病態も十分理解しておく必要がある。本書は,まさに,生検を正しく診断するために書かれた教科書であり専門書である。
本書は30年前,わが国初の本格的な消化管の生検病理診断書として出版され,長年にわたり病理医・臨床医のバイブルとして用いられてきた当時筑波大学教授・中村恭一先生,浜松医科大学教授故・喜納 勇先生により出版された『消化管の病理と生検組織診断』の流れをくむ専門書である。共著者には,筑波大学名誉教授・東京医科歯科大学名誉教授の中村恭一先生のほか,中村門下の杏林大学教授・大倉康男博士と国際医療センター病理・故斉藤 澄博士が当たっている。
本書の特徴は,前述したように,ただの生検診断書ではなく,豊富な材料を縦横に駆使して適切かつ簡明に病変を解説し,病変の病理を正確に把握した上で正確な生検診断を行えるように述べられている点である。このことは,病理医のみならず臨床医にとっても,肉眼像から病態を理解し,生検組織から病変を正確に診断するために有効な教科書となっている。
今日,消化管疾患の診断には内視鏡的生検による組織診断が不可欠のものであるが,胃の生検診断の歴史はそれほど古いものではない。胃生検診断が始まった当初は,病理医がそれまで経験がないようなマッチ棒の頭ぐらいの小さい組織で診断するため,その診断結果は,癌であるにもかかわらず癌と診断されないなど生検診断に混乱状態があったと,著者中村先生が冒頭で触れている。このような生検診断の混乱状態を経て,生検診断は消化管疾患の診断になくてはならない地位を確立してきたわけである。
著者らは,消化器の病理研究における第一人者であるとともに日常診断に従事しており,診断の難しさや犯しやすい間違いにも精通している。特に,中村先生は,生検組織検査が始められた当初から生検組織診断にかかわっており,この分野の先駆者である。本書は,生検診断に誤りがないように,診断に有用な解剖組織学,基礎的な外科病理組織学,その後の生検診断について記述する形をとっている。このことは,日常生検診断に従事している病理医が正確に病理診断するため,内視鏡検査を行っている内視鏡医が病態を理解するため,また,新たに消化器の病理や生検診断を学ぼうとしている臨床医・病理医のために有効である。すなわち,本書は,消化器に関与する医師にとっての入門書,専門書であり,必読書といえる。
消化器内視鏡医にとって最良の病理解説書
書評者: 鶴田 修 (久留米大教授・消化器内科学)
今から約25年前,故白壁彦夫教授が司会をされていた研究会に久留米大学からIIc型早期大腸癌症例を提示したことがあった。外科手術症例で標本の張り付け方が悪く,X線,内視鏡などの画像とマクロの対応が困難となってしまい,白壁教授からかなり強烈なお叱りを受けて立ち往生している時に,当時筑波大学教授であった本書著者の中村恭一先生から「病理学的には頭の中で切除標本を伸ばせば,マクロと画像そして病理組織像の対応は可能である」というお助けの言葉をいただき,その場をなんとか切り抜けることができた。先生のお優しさには今でも大変に感謝している。中村先生は臨床の疑問点を理解され,真摯に答えようとされる。先生の下で研修した多く医師が日本各地で消化管画像診断学のリーダーになっていることにも納得がいく次第である。
さて,共著者である杏林大学・大倉教授から「本書は1980年に中村先生と故喜納勇教授の共著で出版された『消化管の病理と生検組織診断』を時代に合わせて改訂し,足りない部分を補充したものだ」というお話を伺っていたが,実際読ませていただくと前書と比べてその内容の充実ぶりに驚かされた。全消化管(食道,胃,十二指腸・小腸・虫垂,大腸,肛門管)の解剖,形成異常,炎症性疾患,非腫瘍性疾患,腫瘍性疾患について,カラーのマクロ写真,切除標本・生検標本の病理組織写真,内視鏡写真,図表を駆使して漏れなく記載・解説されており,非常にわかりやすく,特に腫瘍の項などは中村先生の癌発生とその組織像・診断に関する哲学までも十分に感じることのできる内容となっている。
消化管の内視鏡診断を行うには,正常消化管組織像,疾患の概念,肉眼像,病理組織像を理解・記憶することは,少々苦痛ではあるが必須である。また,最初は苦痛であるが,少しの努力により疾患の理解,内視鏡所見の読影力がつきだすと,苦痛は次第に快感へと変わり,それに伴いどんどんと実力も向上していくものである。
これまでの消化器内視鏡医のための病理解説書は簡単過ぎたり,難し過ぎたりで,内視鏡医にとっては“帯に短し襷に長し”と感じるものが多かったが,本書は内視鏡医に必要と思われる項目について“痒いところまで手の届く”内容に仕上がっており,苦痛を最も少なくして多くの知識を系統的に理解できる最高の1冊である。
ここに消化器内視鏡医にとって最良の病理解説書が出版された。消化器内視鏡専門医をめざす医師にとっては必須の1冊である。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。