♪In My Resident Life♪ 指導医10人が語る“アンチ武勇伝”(生坂政臣,中島伸,西野洋,林寛之,井村洋,田中まゆみ,勝俣範之,大生定義,郡義明,武田裕子)
寄稿
2007.01.15
新春企画
|
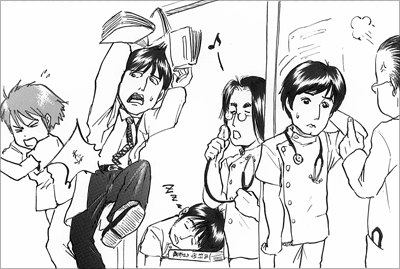 |
| ♪In My Resident Life♪ |
研修医のみなさん,あけましておめでとうございます。レジデント・ライフはいかがですか? たとえ病院選びで後悔したり,手技やコミュニケーションが苦手だったとしても,あきらめないでください。何十年に及ぶ医師としてのキャリアは,まだ始まったばかり。失敗に学びながら,生涯勉強を続け成長しましょう。
新春企画として贈る今回は,人気指導医の方々に研修医時代の失敗談,“アンチ武勇伝”を紹介してもらいます。2007年がよい一年となることを願って!
|
こんなことを聞いてみました。
(1)いま明かされる研修医時代の“アンチ武勇伝” (2)研修医時代の忘れえぬ出会い (3)あの頃にタイムスリップ!思い出の曲 (4)研修医・医学生へのメッセージ |
| 生坂政臣 中島 伸 西野 洋 林 寛之 井村 洋 |
田中まゆみ 勝俣範之 大生定義 郡 義明 武田裕子 |
第3希望の研修病院
生坂政臣(千葉大医学部教授・附属病院総合診療部長)
 (1)当時,卒業したら大学に残って研修するのが当然という風潮の中,田舎育ちの私は一度日本の中心から世の中を見てみたいとの思いから,2つの有名研修病院を受験した。しかし結果は不合格。やむなく第3希望だった都内の大学病院で研修を始めることになった。
(1)当時,卒業したら大学に残って研修するのが当然という風潮の中,田舎育ちの私は一度日本の中心から世の中を見てみたいとの思いから,2つの有名研修病院を受験した。しかし結果は不合格。やむなく第3希望だった都内の大学病院で研修を始めることになった。
研修医の大学離れが進む昨今では信じがたいが,この病院は医師であふれかえっていた。それゆえ病棟での受け持ち患者はひとり。手技は研修医同士の熾烈な戦いとなる。スワンガンツ(肺動脈カテーテル)挿入などのレアものはもちろん,膀胱洗浄(以下,膀洗)のようなありふれた手技も,仲間とあみだくじで決める有様であった。最初に膀洗を引き当てた同期の女医が,手袋を清潔操作で装着する姿をどれほどうらやましく思ったことか。たかが膀洗,されど膀洗。その後しばらくは膀洗病に取り憑かれ,自分が膀洗する“勇姿”を幾度も想像した。
でも,「こんな患者数じゃ力がつかない! もっと激しい研修をしたい!」との衝動にかられ,1年目の夏休みに野戦病院として名高い某施設をこっそり見学した。そこで目にしたのは,一足先に大学からその病院に研修先を鞍替えしていた同期生が,過労で入院している姿であった。ひるんだ私は研修施設の変更を諦め,現施設での最大限の努力を誓った。
まず自分に割り当てられた比較的楽な病棟当直を,夜間外来からICUまで担当する激務の救急当直に変えてもらう交渉を行った。睡眠時間ゼロの当直を歓迎しない研修医もいたので,この申し出は大いに感謝された。特に連休や正月は稼ぎ時であった。相変わらず受け持ち患者数は少なかったが,些細な問題点まですべて解決することを自分に課したため,帰宅はいつも深夜であった。数ではなく質で勝負しようと決めていた。また,休日でも病棟に張りついていれば何かが起こる。点滴漏れや経鼻チューブ交換,発熱,不眠などで呼ばれるごとに,主治医の代わりにカルテをみて診察をする。病棟の雑用を引き受けることにより,受け持ち以外の患者からも大いに学んだ。
 (2)経験してなんぼの医療の世界では,どんな先達にも学ぶべきものは必ずある。この病院にも私からみれば神同然の優れた医師がたくさんいた。しかし待っているだけでは何も起こらない。気持ちよく教えてもらうために,かばん持ちだろうが裸踊りだろうができることは何でもやった。そして多くのよき先輩に巡り会えた。
(2)経験してなんぼの医療の世界では,どんな先達にも学ぶべきものは必ずある。この病院にも私からみれば神同然の優れた医師がたくさんいた。しかし待っているだけでは何も起こらない。気持ちよく教えてもらうために,かばん持ちだろうが裸踊りだろうができることは何でもやった。そして多くのよき先輩に巡り会えた。
この2年間の初期研修で私の臨床の基礎が作られた。後に経験した米国臨床研修もすばらしかったが,ふり返ってみればここでの研修は別格であった。確かに第一希望の研修先ではなかった。しかし,もう一度学生に戻っても,迷うことなくこの病院を選ぶだろう。結局,どんな施設でもやり方次第で研修は実りあるものになる。そこに助けを必要とする患者がいる限り。
(4)手技経験の機会が少ないという研修医の悩みを耳にする。若いうちは手技に走りがちなので,友人が得意げに話す手技成功談に,後れを取った気分になるのも無理はない。しかし初期研修では臨床判断や診断プロセスなど,臨床の考え方をしっかり身につけてほしい。もちろん手技もできるに越したことはないし,ACLSなどの救命処置は体で覚えておく必要があるが,まずは大脳の鍛錬に主眼を置くべきである。
イチロー曰く,怖いのは年をとって筋肉が固くなることより,頭が固くなること。一流のアスリートが体でなく,考え方の硬直化を恐れているのである。研修指導の経験からも,一度染みついた考え方の軌道修正は,手技を正すよりはるかに難しい。最初に早いだけの雑な臨床に慣れると,深く柔軟に考える“面倒”な診療は倹約家の大脳が拒絶する。
懸命に修得した手技も,その多くはいつの間にか使わなくなっていくものである。しかし診療に携わっていく限り,日々の臨床判断から逃れることはできない。手技はあとづけできる。私自身,超音波や内視鏡検査を覚えたのは,卒後10年経ってからである。それで困ったことはない。
プロフェッショナルはどのみち一生勉強である。あとづけできるものは,必要に迫られた時に学べばよい。焦る必要はない。
「当たり前手術研究会」発足
中島 伸(国立病院機構大阪医療センター・脳神経外科医長) (1)先日,医学書院の『週刊医学界新聞』編集部から原稿の依頼がありました。
(1)先日,医学書院の『週刊医学界新聞』編集部から原稿の依頼がありました。
「全国には有名研修病院でバリバリ働く『勝ち組研修医』だけがいるのではありません。手技やコミュニケーションが苦手な研修医も大勢いらっしゃるはずです。そんな自称『落ちこぼれ研修医』を励ますために,大変失礼ではありますが先生自身の若い頃のトホホな経験談を披露してください」という趣旨のものでした。
研修医時代の失敗の数では誰にも負けない私に白羽の矢が立てられたわけですから,あまりにも的確な人選だと言えましょう。おそらく編集部の意図は「数多くの失敗をした研修医も今ではこんなに立派な指導医になっています」ということにあるのだと思います。ただ,私が現在も失敗続きの日々を送っていることまでは,編集部は見抜けていないようです。
それはさておき,研修医時代から少し経験を積み,自分の責任で手術をしはじめてからの体験を披露しましょう。大学の関連病院の集まりがあった時に,近くに勤務している者同士で「最先端の研究や難しい手術も結構だけど,脳外科医として普通の手術が当たり前にできるようになりたいよな」という話題で盛り上がりました。その勢いで,賛同者が集まって『当たり前手術研究会』というのをやることになったのです。自分たちのやった手術の未編集ビデオを見せ合い,お互いに「そんなもん,当たり前やないか」と批判し合うという趣旨です。この研究会では「当たり前にできる」ということがいちばん大切なので,「当たり前やないか!」と言われるのが最高の褒め言葉ということになります。
というわけで,早速5人で集まって『当たり前手術研究会』を始めました。しかし,当たり前にできるということの何と難しいことか! それよりも何よりも,自分の手術を人前に出して批判されることの恥ずかしさ,というのは言葉にできないものがありました。「先生,ここで血管が邪魔になったので焼灼凝固したのはわかりますが,どうしてすぐに切断しなかったのですか?」「前大脳動脈に沿ってアプローチする時に,脳と血管の間を剥離しておられますけど,穿通枝を引っこ抜いたりする危険性はないのでしょうか?」他のメンバーからの質問が紳士的であればあるほど,針のムシロです。当たり前が実行できていないことを思い知らされるわけですね。「外科医にとって,自分の手術を批判されることは,自分の人格を批判されるに等しい」と言った大先生がおられますが,まさにその通りでした。
しかし,ある程度,お互いの「立ち位置」がつかめてからは,私にとってきわめて有意義な研究会となりました。つまり,「自分が精一杯頑張った手術のビデオを提示する。お互いに感情的になることなく,ひたすら冷静に問題点を追究する。よいところはよい,改めるべきところは改める」という淡々とした作業の積み重ねが,自然に次の症例に生かされるようになったのです。
決して手先が不器用だとか,時間がかかるといって批判されることはありません。逆に,不適切な手術戦略や,理屈に合わない手術操作は容赦なく指摘されます。たとえ幸運に助けられてよい結果を得ることができたとしても,万一の時の安全策を講じていなかったら,これまた見逃してもらえません。
というわけで,メンバーが散り散りになるまで,月1回の『当たり前手術研究会』は和やかな雰囲気の中で2年近く続けられ,私にとっては一皮も二皮もむけるキッカケになりました。
後で考えてみれば,私よりも相当上手だった他の4人が私に合わせてくれていたのではないかという気もします。とはいえ,あれから何年も経った今でも,学会場などで他のメンバーと顔を合わせると「ぜひ『当たり前手術研究会』を再開しましょうよ!」という話が出るので,皆もけっこう楽しんでくれていたのかな,とも思う次第です。
(4)私自身,今でも知らないことだらけですが,「勉強こそ人生最大の道楽だ!」と自らを励ましつつ,毎日の診療をなるべく楽しむようにしています。
忘れえぬ見学旅行
西野 洋(亀田メディカルセンター 総合診療教育部長・卒後研修センター長) (1)私が医学部を卒業したのは1978年であるから,もう29年も前のことになる。四国の徳島で生まれ育ち,徳島大学に学んだ私は外の世界を知らなかった。卒業後の進路として,同級生の仲間たちの間では,大学の医局に残る人が圧倒的に多く,自分のふるさとにある徳島大学の医局に入るのが私にとっては自然な流れであった。しかし,外の世界に興味のあった私は,当時有名であった聖路加国際病院での研修に漠然とした憧れをいだいていた。東京で開業していた遠い親戚の医師の紹介で,聖路加の放射線科部長に会うことになった。
(1)私が医学部を卒業したのは1978年であるから,もう29年も前のことになる。四国の徳島で生まれ育ち,徳島大学に学んだ私は外の世界を知らなかった。卒業後の進路として,同級生の仲間たちの間では,大学の医局に残る人が圧倒的に多く,自分のふるさとにある徳島大学の医局に入るのが私にとっては自然な流れであった。しかし,外の世界に興味のあった私は,当時有名であった聖路加国際病院での研修に漠然とした憧れをいだいていた。東京で開業していた遠い親戚の医師の紹介で,聖路加の放射線科部長に会うことになった。
田舎から上京した私は,非常に緊張してドキドキしていたが,彼は非常に丁重に私を迎えてくれた。あの時に受けた質問の中で今でも忘れられないのは「大学の成績はクラスの中で,だいたいどのあたりですか?」というものであった。当時の私の医学部の試験成績は特別良くもなく悪くもなく,中の上といったところであったろう。私は正直に,「中の上くらいです」と答えた記憶がある。しかし,そう答えながら,田舎の徳島大学で,中の上くらいの成績では,とても聖路加では採用されないのだろうと自己嫌悪におちいった。
その後,病院内を案内していただいたが,研修医オフィスで出会った研修医たちは,非常にたくましく,賢く見えて,いよいよ私ではとても無理だと悟った。この見学旅行の結果,私は聖路加受験をあきらめ,徳島大学に残ることにした。しかし,いずれは外に出るという夢を持って,ECFMGの資格をとった。
(2)徳島大学で8年間の医局生活を経て,紆余曲折があり,1989年から93年までの間,メイヨークリニックでの神経内科レジデント生活を送ることとなった。この時に出会ったDr. Robert B Brown(愛称Bob)は今でも忘れられない医師である。Bobは私の2年先輩の神経内科レジデントで,どういう因縁からかローテーションで一緒になることが多かった。実は,Bobは車イスに乗ったレジデントである。聞いたところでは,高校生の時,ある朝目覚めたら,両足がまったく動かず,それ以来車イス生活となり,collegeさらにmedical schoolと進み,迷うことなく神経内科のレジデントになったらしい。
Bobは車イスではあるが,すさまじいスピードで病院内を駆け巡り,当直も苦もなくこなしていた。私は彼の疲れた顔を見たことがなく,彼が人の悪口や研修生活の文句などを口にするのを聞いたことが,ついぞ一度もなかった。Bobは,いつもpositiveで,神経内科に対する情熱を熱く語り,あらゆる点で,私が最も尊敬する先輩であった。
実は,昨年の春に,メイヨークリニックで神経内科・脳外科創立100周年記念行事があり,久しぶりにBobに会ったが,この時,彼が神経内科のchairmanに選出されたことを知り,新たな感激を覚えた。
(3)教会での賛美歌。私はクリスチャンではないが,教会で出会った純朴なアメリカ人と一緒に歌った賛美歌が,私の1週間の疲れを癒してくれた。
(4)清く高く大らかに
患者を診ずに痔を語るなかれ
林 寛之(福井県立病院・救命救急センター医長)(1)当時の福井県立病院・山崎信院長に「研修医時代の最初の2年間が医師としての人生の姿勢を決める」と教えられた。とにかく最初の2年だけは(?)必死に頑張れば,その後は慣性の法則のように医師の姿勢ができあがるものと思って頑張ったが,それは2年で解放されるわけではなく,「忙しいままの生活が当たり前のように感覚が麻痺するのだ」ということに気づいた時にはすでに遅し,workaholic病識欠如症候群になってしまった。目先の知識・技術はもちろん大事だが,医師としてのプロフェッショナリズム,そして自分の生活も大事だと思えるようになったのは,研修医が終わって少し余裕ができてからだったと思う。
episode I
初めての受け持ち患者さんは胆石症だった。とにかく最初の患者さんということで,鼻息もあらく勢い込み,患者さんの状態変化に敏感になるべしと,朝,昼,夕の1日3回回診を行った。医学知識もしょせん浅いのに,熱意だけで回診を続けたある日,患者さんが「あのぉ,何度も診察してもらえるのはありがたいのですが,私はそんなに悪い病気なんでしょうか?」とすごく心配そうに質問をされた。あまりに頻回に回診するもので,患者さんにいらぬ心配をかけてしまっていたのだった。
episode II
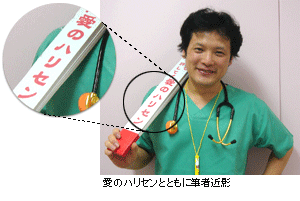 40歳台の患者さんが「痔ができて出血して困ってるんです」と言われた。教科書で痔は習ったことがあるものの,ろくに直腸診もしたことのない研修医だった私は,(これぞ痔を触わるいい機会だ)と思い,直腸診をした。(おぉ,これが痔かぁ)と感動し,「そうですね。痔ですね。ちゃんと治しましょうね」と知ったかぶりをしつつ,当直の外科医にコンサルトした。
40歳台の患者さんが「痔ができて出血して困ってるんです」と言われた。教科書で痔は習ったことがあるものの,ろくに直腸診もしたことのない研修医だった私は,(これぞ痔を触わるいい機会だ)と思い,直腸診をした。(おぉ,これが痔かぁ)と感動し,「そうですね。痔ですね。ちゃんと治しましょうね」と知ったかぶりをしつつ,当直の外科医にコンサルトした。
外科医が直腸診をするや否や,耳元でボソボソと「先生,これ,わかってるよね」と小声でささやいた。自慢そうにはっきりとした声で「ハイ,痔です」と言い切ったところ,「おい,これは直腸癌だよ。硬さが全然違うでしょ」と言われ,真っ赤になってしまった。外科の教科書ではその硬さや感触は伝わらない。確かに「実際の患者さんを診て勉強していかないとだめだぁぁぁ」と心から思った。
(2)当時は,「技は盗むもの」。研修医はとにかく上級医の言うことを,メモしまくり,自分のメモ帳こそどんなテキストよりも役に立つお宝メモ帳になったものだ。教科書や医学雑誌を読んでも臨床経験の少ない身にはピンと来ないことばかりで,実際に患者さんを目の前にして習う耳学問ほど役に立ったことはない。
徒弟制度全盛の研修医時代にも時代に逆らって積極的に教えてくれる希少価値の先生がいた。現福井大学附属病院副院長兼救急医学講座の寺澤秀一先生だ。なかなか積極的に教えてくれる先生がいない時代に寺澤先生というロールモデルに出会えたのは,私にとっても大きな幸運だった。知識・技術のみならず,態度面においても,血気盛んな研修医の自分が,小難しい患者さんを目の前にしても,「寺澤先生だったら……」と考えて態度を正すことも多かった。今では考えられないが,当時の同僚には患者さんとけんかをして飛び蹴りをした猛者もいた。結局は新興宗教? 『寺澤教』に入信することになり,今に至るようになったと考えている。
(3)ティナ・ターナー「Holding out for a Hero」。とにかくアドレナリンがぐっと出て,強気に攻める気分になれるのがいい。
(4)研修は口をあけて待っていてはいけない。積極的に教えを請う研修医には,多くの上級医は教えてくれるものだ。「貪欲になれ! 研修医! そして恩師を越えてこそ,恩を返せるのだ! 青は藍より出でて,藍よりも青し!」
進めない,研修もスケボーも
井村 洋(麻生飯塚病院・総合診療科部長) (1)当院の研修医にはしばしば吐露していますが,そもそも私が医師になった動機は,強くも深くもありません。親族に複数の医師が存在する生育環境のため自然のなりゆきというよりも,どこか強迫的に医学部進学を選択しました。強制されたわけではなく他の選択肢がないまま消去法で,というのが正直なところです。
(1)当院の研修医にはしばしば吐露していますが,そもそも私が医師になった動機は,強くも深くもありません。親族に複数の医師が存在する生育環境のため自然のなりゆきというよりも,どこか強迫的に医学部進学を選択しました。強制されたわけではなく他の選択肢がないまま消去法で,というのが正直なところです。
このため自分自身の目標も曖昧なまま大学附属病院での研修を開始しました。当時としては画期的な内科臓器別ローテーション研修でしたが,心のどこかで“いつか一般医として継承開業をするだろうな”という漠然とした予想があり,研修生活に慣れ始めた頃から,病棟専従の臓器内科別研修を続けることに疑問や不安を感じ始めました。「こんな細部にこだわる診療ばかりを続けても将来につながるのかしら。いっそ内科なんてあきらめて小児科や耳鼻科を専攻するほうが,将来の開業への道筋が容易かも?」と,中途半端に悩み始めました。
そんな煩悩に左右され続けた初期研修でしたので,自分の診療行為を振り返ることや,積極的に教科書やマニュアルを読もうなどという意欲は毛頭ありませんでした。だからといって,強い危機感を抱いて独自で学習しようなどという気迫もなく,周囲の医師も同様であることに安堵し,「こんな感じで続ければなんとかなるんだろうな」と長いものに巻かれている研修医でした。
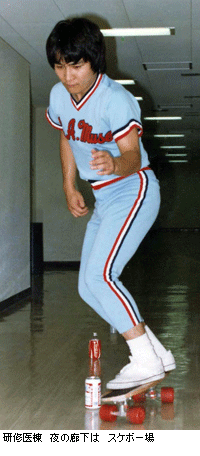 (2)初期研修終了後に,医局派遣で勤務した市中病院(既に閉院)が,私にとっての運命の出会いでした。それを境に流れが変わりました。決して,望んだわけでも探したわけでもなかったのですが,あの巡り合わせには感謝しています。よかった点を列挙してみます。
(2)初期研修終了後に,医局派遣で勤務した市中病院(既に閉院)が,私にとっての運命の出会いでした。それを境に流れが変わりました。決して,望んだわけでも探したわけでもなかったのですが,あの巡り合わせには感謝しています。よかった点を列挙してみます。
・200床と小回りのきく規模であった
・内科は臓器別になっていなかった
・救急外来と紹介救急入院が主体だった
・卒後2-6年次の研修医が診療の中心所帯であった
・限られた資源においても,教育提供を惜しまない指導医がいた
・研修医対象の症例検討会が毎日1-2回あった
・尊敬すべき指導医,上級医,同僚・後輩医師,看護師がたくさんいた
総合医の有用性を確信し,初期研修時代の迷いは完全に消え去りました。医師という職業にも充実感を感じ,生涯続ける覚悟がつきました。そこでの2年間の経験が,今までの自分を支えてくれています。「初期研修の2年が最も重要」という意見を聞くたびに,「簡単に決めつけるなよっ!」と声を張り上げて反論する根拠でもあります。
(3)ザ・フォーククルセダーズ,ビートルズ,吉田拓郎,ボブ・ディランに思春期の全エネルギーを奪われて以来今でも音楽家に憧れ続けており,折々に深く思い出す曲があったりするのですが,研修時代だけはまったく音楽の思い出がありません。病院の忘年会二次会で甲斐バンドの「HERO」を歌い,間奏のパフォーマンスで口に含んだアルコールを天井に向かって霧吹きのように撒き,大うけしたことだけが記憶に残っています。当時は,同席の妻も“狂喜”していたのに,今やると“兇器”が飛んできます。
(4)他人の価値観に踊らされ続けることは終わりにしましょう。自分自身の価値観を創り始めることです。それはそれで大変ですが,十分に行う価値のある行為です。(“人が幸せになるのを批判する権利など誰にもない♪”「ビートルズが教えてくれた」吉田拓郎)
快挙でなく暴挙? 2度目の米国研修
田中まゆみ(聖路加国際病院・内科) (1)最初の研修先は天理よろづ相談所病院で小児科を選択した。大学以外で研修を受けることに迷いはなかったが,当時小児科助教授だった三河春樹先生にも入局挨拶に行っていたのだから,われながら世間知らずもいいところである。
(1)最初の研修先は天理よろづ相談所病院で小児科を選択した。大学以外で研修を受けることに迷いはなかったが,当時小児科助教授だった三河春樹先生にも入局挨拶に行っていたのだから,われながら世間知らずもいいところである。
この後,三河先生には大変お世話になってしまうのだが,特に,産休交代要員のお願いに上がった折(女医というのは勝手に妊娠もできないことを先輩から聞いて初めて知り,慌てて参上したのであったが),帰りに「一緒にタクシーで帰ろうや」と父親のような優しい気遣いを見せてくださったことは一生忘れないだろう。女医にとってキャリア上の一大事である結婚と妊娠を研修時代に経験することは,「失敗」に限りなく近い無謀で必ずしもお勧めできないが,理解ある上司に恵まれた私は幸運であった。マンツーマンに教えていただいた天理の赤石強司部長には深く感謝している。
米国での2度目の研修も決して快挙ではなく暴挙に近い。そもそもマッチングの時に,制度改革の一項目を見逃したがために失格であることに気づき,面接を受けたハーバード内科小児科合同プログラム等5つのプログラムに辞退の手紙を出さざるをえない羽目になったのである。次の年まで急遽,以前から関心のあった公衆衛生大学院(SPH)に学ぶことにした。ハーバードSPHは締切が過ぎていたので諦め(これも事前準備不足による失敗),ボストン大学SPHに合格し,昼間は研究室で働き学費を稼ぎながら夜間コースで学んだ。Annas教授の医事法学の講義がすばらしく,2度目に挑戦したマッチングもうまくいって,「禍転じて福となる」1年となった。
しかし,予想されたことではあるが,中年になってからの2回目の研修は苦行であった。外国人研修医ばかりのプログラムで,一部米国人看護師の研修医いじめが横行していた。先輩からの忠告は「看護師を怒らせるな。看護師は研修医より強い」というものであった。むろん,私の性格であるから,問題看護師に面と向かって,「あなたが私にそういう態度をとるのは,何か個人的に恨みでもあるの?」とやった。
そのせいか,私の評価は,指導医によって真っ二つに分かれてしまうことになった。ある指導医は,4つの座標軸を描いてみせ,「研修医と指導医の組み合わせには4通りある。指導医も研修医も優秀なら右上,指導医が優秀で研修医が馬鹿なら右下,指導医も研修医も馬鹿なら左下,研修医が優秀で指導医が馬鹿なら左上,と,こうなる。君の場合は,どれか……わかるね」とウィンクして見せた。途中で交代した研修部長からも疎まれ,米国の医療制度への疑問も強まり,日本に帰ることにしたのであった。
(4)研修医の皆さん,失敗を恐れず「物言う研修医」になってください。そして,先輩の失敗の数々から大いに学んでください。失敗を未然に防ぐためにも,失敗しても「そのくらい大丈夫」と立ち直るためにも。
3年目の危機一髪
勝俣範之(国立がんセンター中央病院・腫瘍内科医長) (1)研修医時代を私は徳洲会病院で過ごした。元来なまけものであった私は,「どうせ研修をするのなら日本でいちばんハードなところでやろう」と思い,徳洲会病院の門を叩いた。と,いうと聞こえがよいのであるが,5年生の春休みに学生実習をした際に,「頭はいらない,体力と根性があればよい」ということを真に受けて,体力と根性だけは自信があった私は,周囲の反対(ほとんどの友人たちはその当時大学の医局に入局していた)を振り切って,徳洲会で研修を受けることにした。
(1)研修医時代を私は徳洲会病院で過ごした。元来なまけものであった私は,「どうせ研修をするのなら日本でいちばんハードなところでやろう」と思い,徳洲会病院の門を叩いた。と,いうと聞こえがよいのであるが,5年生の春休みに学生実習をした際に,「頭はいらない,体力と根性があればよい」ということを真に受けて,体力と根性だけは自信があった私は,周囲の反対(ほとんどの友人たちはその当時大学の医局に入局していた)を振り切って,徳洲会で研修を受けることにした。
茅ヶ崎徳洲会病院での研修医3年目の出来事である。研修医時代のいちばん危険な時期が,卒後2-3年目と言われている。研修医を2-3年もすると,たいていのプライマリケアがこなせるようになるし,救急車が来ても,あわてずトリアージ対応ができるようになる。言うなれば何でもできるような錯覚に陥るわけであるが,そのような時に,とんだしっぺ返しをくらうことが多いものである。
研修当時,茅ヶ崎徳洲会病院では当直の研修医が夕診といって,夕方5時から8時までの内科外来を担当していた。夕診は仕事帰りのサラリーマンが多く,風邪やじんましん,頭痛などがほとんどである。時には1日に20-30人近くの風邪の処方をすることもあった。風邪の診断と処方に辟易していたその頃の私は,何とか早く夕診を片づけてやろうとばかり思っていた。
そんな中で,40歳台の女性が,頭痛を主訴に来院した。型通りのhistory takingをやり,普段からストレスもたまっていて,肩こりもあり,最近になり時々頭痛がすると言う。おきまりの筋緊張性頭痛かと思い,アセトアミノフェンの処方箋を準備し始めた。型通りのphysical examinationをやって早く診療を終わらせようと思っていたが,神経学的所見をやっていたところ,右眼球が内転しないのに気づいた。他の神経学的所見は何も異常がないのだが,右眼球がどうしても内転しないのである。Historyをどう聞いても筋緊張性頭痛であるので,内心たまたま何かの拍子で目が動かないのであろうと思い,頭痛薬を処方して早く帰そう,と思う反面,目が動かないのがどうも気持ちが悪い。
 悩んでいるとどんどん患者がたまってくるので,どうしようかと思っているうち,ついに神経内科のスタッフ医師に電話をしようと思い立った。たまたま電話がつながり,「これこれの患者がいて,目の動きが悪いのですが,筋緊張性頭痛と思うので帰してもいいですか?」と30秒プレゼンをすると,「目が内転しないのはおかしい」とすぐに来てくださって,動眼神経麻痺と診断,すぐに緊急脳CTを撮ることになった。CT所見は,見事なくも膜下出血(SAH)であり,即入院。3日後には手術を受け,大事にいたることはなかった。
悩んでいるとどんどん患者がたまってくるので,どうしようかと思っているうち,ついに神経内科のスタッフ医師に電話をしようと思い立った。たまたま電話がつながり,「これこれの患者がいて,目の動きが悪いのですが,筋緊張性頭痛と思うので帰してもいいですか?」と30秒プレゼンをすると,「目が内転しないのはおかしい」とすぐに来てくださって,動眼神経麻痺と診断,すぐに緊急脳CTを撮ることになった。CT所見は,見事なくも膜下出血(SAH)であり,即入院。3日後には手術を受け,大事にいたることはなかった。
歩いて来院するようなSAHの患者を初めて経験した。「教科書どおりの患者は一人もいない」との言葉のごとく,まさに,「患者から学ぶ」とはこのことであるとしみじみと思ったものである。
(2)研修医時代に指導してくださったすべての指導医と患者さんたち,それと現在の妻と出会えたことですね。今でも研修医時代の患者サマリーは一人ひとりすべて保管してあります。
(4)研修医1年目の時は教科書を読むことすら禁じられました。「教科書読むひまがあったら,患者を診ろ!」と言われたものです。「患者から学ぶ」ということは,研修医というより,臨床医の原点というべきものですかね。
「おお,Akute Magendilation!」
大生定義(立教大教授/聖路加国際病院・内科) (1)私は,地元の北海道大学を卒業後,内科をオールラウンドに勉強したいと考え,聖路加国際病院内科レジデントとして入職した。1年目のころは,よく失敗をした。外科2か月・産婦人科・小児科各1か月ローテーションした後,ホームの内科病棟に戻ったが,新しい経験の連続,毎日毎日が失敗の連続であった。
(1)私は,地元の北海道大学を卒業後,内科をオールラウンドに勉強したいと考え,聖路加国際病院内科レジデントとして入職した。1年目のころは,よく失敗をした。外科2か月・産婦人科・小児科各1か月ローテーションした後,ホームの内科病棟に戻ったが,新しい経験の連続,毎日毎日が失敗の連続であった。
当時の聖路加国際病院は,内科当直医は一人で,病棟と救急室の患者を診ていた。最初は2年目の先輩レジデントについての見習い当直であった。その日は,現在都内の大学医学部で内科学教授となっている,当時2年目の先輩と一緒であった。
今でも名前は頭から離れない,70歳台後半くらいの女性が腹痛で,夜間遅く,救急室を受診してきた。当時は,自分たちでやるだけの簡単な血液検査しかできなかったが,炎症所見ははっきりせず,腹部エックス線も,非特異的な所見であった。腹部の触診でも腹膜刺激症状ははっきりせず,帰宅可能と判断した。先輩と「まあ,大丈夫だよね」と話し合いながら……。しかし翌日,胃穿孔で入院手術となった。幸い命はとりとめたが,本当にがっくりであった。
その先輩と一緒に急性腹症の患者を診察することが続いていた。今度は内科病棟に入院中の白内障術後(当時は入院期間が長く,安静も必要とされた)の高齢患者が腹痛を訴えてきた。先輩と一緒に診察,腹部の圧痛もあり,腹部エックス線で腸捻転に典型的なS状結腸の膨脹した腸管像がみられると判断し,外科医長にコンサルトした。外科も私たちの勢いに同意され,緊急開腹手術の体制をとり,手術室で準備を始めた。それではまず,胃管を挿入というわけで手術を開始しかけた,なんとその時に大量のガスが排出され,腹部膨満は改善。術者の医長は,「おお,Akute Magendilation!」と普段は英語の術語が多い医長がドイツ語で叫んだ。私たちが腸捻転と思い込んでいたのは,術後胃拡張だったのだ。
今から思うと大変思い込みが多い時期であった。まったく,医者の思い込みは患者には大変な迷惑になる。
(2)もちろん,数多くの先輩や患者さん,指導医からよい影響を受けたが,特に当時の循環器内科の医長に,決断の思い切りのよさを学んだ。医療の決断もさることながら,人生の決断もである。その先生はご自分で「教育病院の循環器責任者として活動性が落ちてきていると自覚するので,職を辞す」と明言され,開業医に転身されたのだ。もちろん転身されてからも,出版をはじめ,医学の仕事やご趣味も存分に楽しまれている。その後の私自身の身の処し方について影響を受けたと言える。他の高名な指導医からは「私=すべての出会った方々の総和」と,周囲の人々から学ぶ姿勢を説かれたことも印象に残っている。
(3)「サタディナイトフィーバー」。当時ジュニアレジデントは,先輩から大切な業務のひとつとして厳命され,病棟の親睦を深めるため,複数のナースたち(決して単独ではない,できるだけ多くの)と頻繁に飲み会に出かけていったものである。ディスコでよくこの音楽がかかっていた。
(4)医師は生涯研修医であると思います。自らが他の人の役に立つことができ,感謝してもらえるこの職業につくことができたということに思いを致し,この与えられた機会や自分の能力に感謝しながら,覚悟を持って仕事を進めてほしいと思います。特権意識ではなく誇りを持って,毎日研鑽していきましょう。
寛容を学んだ2つの事例
郡 義明(天理よろづ相談所病院・総合診療教育部長) (1)この類の話ならありすぎて困るが,とりあえず2つの出来事を紹介する。
(1)この類の話ならありすぎて困るが,とりあえず2つの出来事を紹介する。
天理での研修が始まった時,生涯の師,今中孝信先生に出会った。強烈な個性の先生だった。その先生が宴会でよく言う口ぐせが「暇な時に遊ぶやつはアホなやつ。忙しい時に遊ぶやつはスゴイやつ」。私も早速実行することに決めた。その頃私は陽明寮という病院の宿舎に住んでいた。2か月に1回,その宿舎に同期の研修医や病棟の看護師を呼んで,陽明分教会のお祭りと称して宴会を開いていた。集まれば,深夜2時,3時まで大騒ぎ。ついに度重なる騒音にたまりかねた近所の住民が病院に苦情を申し出た。てっきり大目玉を喰らうことを予想していたが,副院長からは笑顔で「もう少し静かにやるように」とだけ注意された。声高に言われれば反発して続けるつもりだったが,宴会はやめることにした。
研修3年目の時,全身倦怠で受診してきた60歳台の女性を診察した。貧血があり,Hb7.6(と見えた)。外来で検査をすることにして患者を帰した後,よくよくデータを見るとなんとHt7.6! あわてて自宅に電話して翌日入院。貧血の原因検索をすると,腹水と卵巣らしき腫瘍が見つかった。腹水穿刺を数度試みるも細胞診は陰性。ついに痺れを切らした私は,卵巣の腫瘍をエコーガイド下に穿刺することを思いついた(当時はまだエコーガイド下に穿刺をすることはほとんど行われていなかった)。技師さんに針先をエコーで確認してもらいながらなんとか穿刺に成功。ようやく腺癌の診断がついた。有頂天になったところに先輩医師から「腹水の細胞診が陽性に出ないということは腹腔内に腫瘍が浸潤していない証拠。もし,穿刺したところから癌細胞が腹腔内にこぼれたら,君はどうするつもりだった?」とやんわり諭され,全身から血の気が引いた。
人を諭すには寛容が必要だということを2つの事例から学んだはずだが,いまだに人に寛容になり切れない自分。しょせん生まれ持った人間の器が違うと,最近はいささか自嘲気味だ。
 |
| スイス・ツエルマットにて筆者近影。「自分が生きいきとしていなければ,患者さんに希望は与えられない。時には楽しいことをしてリフレッシュしよう」 |
ところで,医師としての技量は今のほうが明らかに上だが,むしろ,未熟だった駆け出しの頃のほうがこのような患者さんにはるかに多く出会うことができた。患者さんが未熟な私に心を開いてくれたのは,ひたむきさが伝わったのだと思う。最近,パッションが枯れてきたのかなと自戒する。
(3)シルベスタ・スターローン主演の映画「ロッキー」のテーマ曲“Gonna Fly Now”。研修医時代にくたくたになった時,とくにへこんだ時によく聴いていた。つらいトレーニングに耐え,試合では顔がゆがむほどのパンチを受けながら,それでも向かっていく主人公のロッキー。そして最後にはチャンピオンを倒す。そんなロッキーの姿を自分の姿に重ねていた。今でも聴くと元気が出る。
(4)「熱くなれ! 自分も含めて人を変えるのはパッションだ!」
サンタさん,早く連れて帰ってきて!
武田裕子(東京大学医学教育国際協力研究センター・助教授) (1)私は多分学年でいちばん惨めなインターンであった。誰よりも早く病院に行き,当直明けでも夜中まで残ってカルテを書いていた。箸を持ったまま眠り,風呂に入ってお湯が冷たくなって目が覚めたこともある。果たして自分は研修をやり遂げることができるのか不安でいっぱいだった。4日に一度の当直ではポケベルが鳴るたびに飛び上がっていた。
(1)私は多分学年でいちばん惨めなインターンであった。誰よりも早く病院に行き,当直明けでも夜中まで残ってカルテを書いていた。箸を持ったまま眠り,風呂に入ってお湯が冷たくなって目が覚めたこともある。果たして自分は研修をやり遂げることができるのか不安でいっぱいだった。4日に一度の当直ではポケベルが鳴るたびに飛び上がっていた。
ある夜のこと,老人ホームから低体温と意識障害の80歳近い女性が搬送されてきた。もともと認知症もある方で,尿路感染症から敗血症をきたしているのではないかと診断された。髄膜炎を除外するため腰椎穿刺が行われたが,かなりの肥満と腰椎圧迫骨折のあるこの患者さんへの手技は容易でなく,麻酔科の当直医が透視下で実施してくれることになった。レントゲンの台の上で薄い病衣をまとった患者さんとなかなか現れない麻酔科医を待ちながら私は怒っていた。可能性の低い鑑別診断にこだわる(とその時は思った)レジデントに,低体温の患者さんをこんな状態で深夜に待たせている麻酔科医に,慢性的に疲れている自分自身の能力のなさに。
この患者さん,いよいよ退院という日の前日に決まって熱を出した。当直明けで帰ろうという時に点滴が漏れた。次々と新たな疾患が見つかり,検査オーダーと専門医へのコンサルテーションに追われた。ある夜,またも点滴が漏れたと呼ばれた。午前2時である。穏やかな表情でこちらを見つめる患者さんを見下ろしながら,「She is an angel from the hell. She came to torture me.」とふと思った。
次の瞬間,われに返った私は,そんな考えを抱いた自分自身に驚愕した。そういえば,外来で不定愁訴の患者さんの訴えを聞きながら,考えていたのは自分のほうがよほど不幸せで不健康だということだった。ショックだった。患者さんに信頼されるよい医師をめざしていたはずなのに,患者さんが地獄の使者だと思えたのだ。よい医師であるためには,自分が惨めな状態であってはいけない。まず自分をケアしよう。つらい時には応援を求め,無理だと思ったら断ろう。効率よく仕事をして睡眠を確保しよう。そう心に誓った。
患者さんは間もなく退院し,私はインターン生活のドタバタを懐かしむ日が来るだろうと思えるようになった。実力のなさに泣きたくなって当直室に駆け込み,はっと気付くと泣き出す前に寝てしまっていた。そんな自分がおかしくて声を出して笑ってからは,何を深刻に悩んでいたのか思い出せなかった。そしてレジデントに進級した。
(2)外来主治医としてフォローしていた患者さんのなかに,その昔ジャマイカから移住して来られた陽気なお年寄りがいた。ある日,不整脈による失神発作で救急外来に搬送され循環器病棟に入院となってしまった。後から知って会いに行くと,「私の先生が来てくれた」といって大喜びされた。ご家族が,「先生は日本に帰ってしまったのか,と心配していたんですよ」と話してくださった。頑張る気持ちが湧いてきた。
(3)クリスマス・イブに当直をしていたら,夫から電話があり受話器からWilson姉妹の“Hey Santa!”が流れてきた。後になって,「クリスマスは一緒に過ごすって言ってたのにまだ帰ってこない。サンタさん,早く連れて帰ってきて!」という曲だと知った。この曲を聞くとハードだった研修医時代とずっと支えてくれた家族のサポートを思い出す。
(4)時には,頑張る自分をほめてあげてください。疲れたら休憩する,無理していると感じたら応援を頼むのもよい医療を提供するのに大切なことです。自分が生きいきと過ごすには何が必要か,立ち止まって考えてみませんか。
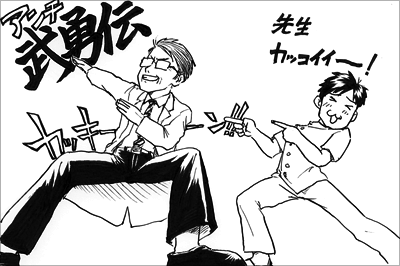
いま話題の記事
-
忙しい研修医のためのAIツールを活用したタイパ・コスパ重視の文献検索・管理法
寄稿 2023.09.11
-
人工呼吸器の使いかた(2) 初期設定と人工呼吸器モード(大野博司)
連載 2010.11.08
-
連載 2010.09.06
-
事例で学ぶくすりの落とし穴
[第7回] 薬物血中濃度モニタリングのタイミング連載 2021.01.25
-
寄稿 2016.03.07
最新の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]脆弱性骨盤骨折
『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第3回]わかりやすく2つの軸で分類して考えてみましょう
『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第1回]平坦な病変 (1)色調の変化があるもの
『内視鏡所見のよみ方と鑑別診断——上部消化管 第3版』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください
『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第1回]バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO)
『IVRマニュアル 第3版』より2024.04.26
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


