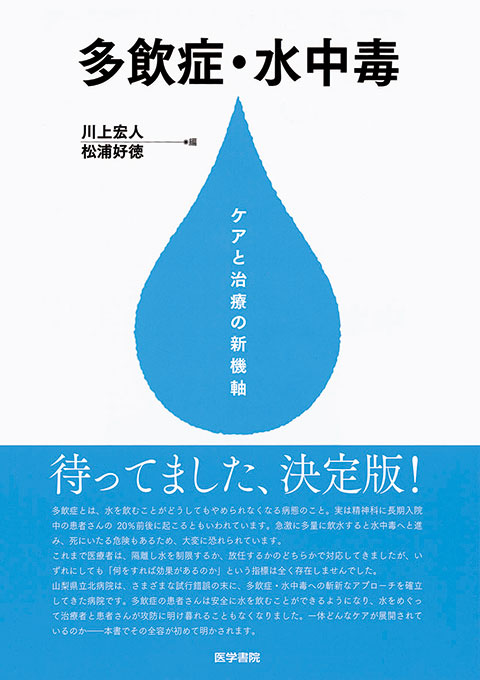多飲症・水中毒
ケアと治療の新機軸
初めて示される多飲症・水中毒治療の決定版!
もっと見る
多飲症・水中毒治療に初のスタンダード! 多飲症とは、水を飲むことがどうしてもやめられなくなる病態のこと。精神科に長期入院中の患者20%前後に起こるともいわれている。急激・多量な飲水は水中毒へと進み、死にいたる危険もあるため恐れられるが、これまでは「何をすれば効果があるのか」という指標は全く存在しなかった。本書は、試行錯誤の末に実効性ある斬新なアプローチを確立した山梨県立北病院のノウハウを初めて完全紹介する。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
推薦のことば(藤井康男)/本書の目的(川上宏人)
推薦のことば
この本の推薦文を書くことができることを、本当に嬉しく光栄に思うと共に、こんなにすばらしい著書を、川上宏人先生や松浦好徳看護師をはじめとする看護スタッフが完成させたことを、山梨県立北病院の院長として誇りに思います。
ここで少しだけ、昔話をさせてください。実は、山梨県立北病院で、最初に「水中毒(みずちゅうどく)」という診断をつけたのは私なのです。1983年の6月のことでした。当時、私が主治医として診ていた統合失調症の入院患者(男性)が、突然意識を失って倒れたかと思うと、大量の嘔吐、尿失禁、けいれん発作が出現し、慌てて臨床検査を行うと、108mEq/Lという著しい低ナトリウム血症が認められました。
今だったら誰でも「水」に着目すると思うのですが、その当時は多飲症や水中毒といった概念はほとんど知られておらず、かけだしの精神科医だった私には何が何だかわかりませんでした。ひょっとするとこれは命が助からないかもしれないと思い、年老いた両親を呼び寄せ、付き添ってもらいました。
幸い翌日には意識が戻り、3日ほどして回復したのですが、なぜこうなったのか、そしてどうして回復したのか、教科書を読んだり、先輩の先生に聞いても見当がつきません。しかしとにかく水を飲みすぎているのは間違いないので、半分は当てずっぽうで「水中毒」というキーワードで文献を調べてみると(当時はインターネットが発達していませんでしたから、文献検索も大変だったのですが)、精神病患者におけるwater intoxicationやpolydypsiaについての報告がいくつか手に入り、「これだ!」と膝を打ったのをよく覚えています。これが北病院で最初に確認された水中毒発作症例でした。
そのつもりで病棟の患者を観察すると、多くの入院患者が水道の蛇口に口をつけて、あおるように水を飲み続けていることに気がつきました。外来患者でも家族に聞くと、何リットルも水を飲んでいますという患者がいました。患者自身に聞くと、そんなに飲んでないと否定するのですが、隠れて大量に水飲みをしていることもあったのでした。
当時は抗精神病薬を投与中の統合失調症患者にけいれん発作が生じると、「薬物で発作閾値が低下したせいだ」とか「電気けいれん療法の副作用ではないか」などと考えて、抗てんかん薬が処方されることがよくありました。しかし実は、このようなけいれん発作の多くは多飲による低ナトリウム血症が原因だったのでしょう。
そこで、当時の北病院に勤めていた後輩の松田源一先生に、これを研究してみたらと勧めました。彼は多飲や水中毒を伴う患者について根気よく臨床観察を行った結果をまとめ、1988年に『精神医学』誌に載りました。この報告は、国内では必ず引用される重要な論文になりましたし、その後、この研究を発展させて彼の学位論文にもなったのです。
山梨県立北病院は1990年に全面改築されましたが、その後、多飲症患者への治療は、当病院でも大きな課題になりました。多飲症患者の個室施錠や保護室隔離は長期にわたるため、病院として救急・急性期患者が受け入れられないという支障が出ていたからです。そこで、1999年にアルコール病棟を改修して、多飲症専門病棟にしました。2000年には、稲垣中先生が、全多飲症患者に「NDWG」を指標にした包括的調査を行い、学位を授与されています。
しかし、整備された多飲症病棟でも、「患者の飲水を監視して管理する」ことを医療者の責務と考えて、患者へ管理的に接するということは続きました。けれどもこうした方法はなかなか患者の病状の改善には結びつかず、大胆な方針の見直しがはじまったのが2003年のことでした。
この2003年という年は、山梨県立北病院にとって、あらゆる点でターニングポイントだったといえるでしょう。この年から「開放病棟を1つ閉鎖し、病床を300床から200床に削減するなかで、援護寮(のちに退院支援施設になりました)を作り、デイケア・訪問看護を拡張し、スーパー救急病棟を開始し、医師やパラメディカルを増員する」という機能強化プランの検討が本格的に開始されたのです。当時、当病院ではどのような方向に進むべきかの議論がスタッフを巻き込んで展開されたのをよく覚えています。
大きな変革が進みつつある状況のなか、多飲症病棟でも新たな治療・看護方法の模索がはじまりました。多飲症病棟がある病棟は、重症・長期化した患者の受け入れ先であり、北病院のなかでも最もしんどい部分を受け持っている病棟です。このような病棟のなかで、この本に記されているような地道な努力が積み上げられ、重要な進歩が生み出されていったのです。
多飲症や水中毒は、精神症状が重く難治の患者に多く併発します。また精神症状の悪化とも関係があり、薬物を中断して再発した患者が、来院した時点で水中毒発作を併発しているということもあります。「水を飲め」というような幻覚がある患者もいますが、それよりも思考障害がひどく、認知機能が低下した患者に頻度が高いように思います。水を飲むという行為は、人間の根元的な欲動に根ざしていて、この調節機構の異常と統合失調症などの精神病症状とはどこかでつながっているにちがいないと私は思っています。
この本を作るという話が出てきたのは2006年10月に東京で行われた日本病院・地域精神医学会の「多飲症・水中毒をどうするか」というシンポジウムで、座長兼シンポジストとして、この本の著者である川上宏人先生と松浦好徳看護師がすばらしいプレゼンをしたことがきっかけだったと聞いています。そこから3年が経ちましたが、その間に熟成された知識・知恵・思いが、この本にはちりばめられています。この本が、多飲症・水中毒で悩む患者・家族・スタッフにとって、エビデンスを示した初のスタンダードとして役立っていくに違いないと私は確信しています。
山梨県立北病院・院長 藤井康男
本書の目的
本書は、多飲症と日々向き合っている患者やその家族、医療スタッフなどの方々が日ごろかかえている、「どのようにしたら安全に水を飲める環境を構築できるのか」という悩みや疑問を解決するためのヒントを提供することを目的としています。
本書の構成は、以下のように4部構成になっています。
第1部では、多飲症治療についての疑問やわかりにくい点、よくある質問などをQ&A形式で取り上げています。第2部は実践編です。山梨県立北病院(以下、北病院)の多飲症専門病棟において、看護師たちがこれまで試行錯誤を重ねながら作り上げ、現在一定の効果を示すまでに成熟した多飲症患者との「かかわり」や、体重管理のアプローチについて紹介しています。第3部は多飲症や水中毒についての知識をまとめた部分で、北病院で活用している、多飲症や水中毒に関する「とらえ方」や「重症度分類」の考え方を紹介しています。さらに、多飲症の原因、治療などについて、海外や日本国内において発表されてきた論文のレビューなどをまとめています。第4部は資料編で、北病院の多飲症専門病棟における看護計画、心理教育の患者用テキスト、スタッフ用マニュアルを紹介しています。
多飲症は精神科医療における一部の患者に限定された特別な病態であるように思わている感があります。しかし多飲症は統合失調症だけでなく、感情障害*1や精神発達遅滞*2,3,4,5、脳炎後や頭部外傷後などの器質的な脳疾患*6、神経性食思不振症*7、人格障害、認知症の患者などでも認められており、発症頻度は必ずしも少なくありません。
多飲症についてはいまだに多くのことが明らかになっていないため、治療的に正しく介入するのはとても難しいとされています。一見すると単純に思える治療の道筋は、実は複雑な迷路のように入り組んでおり、正しい進み方をしても出口に到達するまでには時間がかかり、間違いを重ねるほど抜け出しにくくなります。臨床現場においても統一された治療コンセプトや目標がなく、評価方法や診断基準も文献によってまちまちであるため、中等度以上の多飲症患者への対応は、スタッフの個人的努力や保護室・個室などのハード面に依存することになってしまいます。また、多飲症患者への処遇は、対応する人間と患者との関係性や、環境全体の雰囲気などにより大きく影響されるため、統一することが難しく、ややもすると介入の仕方が極端に過剰になるか、無関心になるかのどちらかになりやすいように思われます。
目の前で中等症以上の水中毒発作を一度でも見てしまうと、すべての飲水行為が怖く感じられてしまうこともあるでしょう。なんとかして水中毒への発展を制止しなくては、という切迫感からはじまる過剰な介入は、患者との間で不必要な摩擦を生み、さらなる多飲や問題行動の原因ともなり、結果として患者にも治療者にも、不必要な疲労感や不全感をもたらすだけの場合が少なくないのではないでしょうか。実際、荒川ら*8によると、多飲症患者にかかわった経験のある看護師の多くは、いつ発作が起こるかという不安や無力感、自責感を抱きやすい傾向にあり、鶴田による調査*9では、長期入院中の患者による暴力の4.5%は、水中毒が何らかのかたちで関与して起こったものでした。看護スタッフは荒れる患者と何もしない医師やその処方を憎み、医師は全くよくならない患者や看護スタッフの対応を憎み、患者はしつこい看護スタッフや自分を閉じ込める医師を憎む、という最悪の構造に陥ってしまうことがあり、こうなると絶望的です。
もうひとつの問題は、無関心や知識の欠如、正しくない「温情」などにより、危険な徴候を見逃してしまうことです。夕方になると患者の機嫌が悪くなり、幻聴の訴えや不眠、夜間の失禁が多くなっていれば、すでに軽症の水中毒であるとみなすべきです。ところが、見方しだいでは「そもそもの病状」や「薬物による副作用」とも受け取れます。けいれんなどの症状が出現するまで多飲症や水中毒に気づかないこともあるようです。確かに、それまでに多飲症によるさまざまな問題が起こっていれば、原疾患への治療方針は混乱させられ、正しい効果判定ができなくなってしまっているかもしれません。しかし、多飲症や水中毒の危険な徴候を見逃すと、結果としてその転帰を悪化させることにもなりかねません。さらには、長期間の多飲・多尿による身体への悪影響も見逃すことのできない問題です。
多飲症を合併しているということは、患者の予後を悪化させる可能性があり、さらには病棟運営にも深刻な影響を及ぼしかねないものです。では、そうならないためにはどうすればよいのでしょうか。
私も以前、総合病院の精神科病棟に勤務し、精神科患者の身体合併症治療に従事していた時期に、水中毒に続発した意識障害や重度の肺炎や呼吸不全、高度の横紋筋融解症による急性腎不全などを経験したことがあり、多飲症については厳重な行動管理が必須という印象をもっていました。2005年より北病院の多飲症専門病棟で勤務するようになったのですが、当初は、多飲症だからといって、特別なことが何もないことに驚いたものです。重度の多飲症患者に対応できるように工夫されている病床が5床(個室1、二人床2)ありますが、外見上の違いはそれらとほかの病室を区切るドアがあることと、その区画だけのトイレとリビングがある程度で、そのドアも施錠されていません。それ以外の違いといえば、体重を頻繁に測定することと、そのための体重計が病棟のリビングに置いてあることくらいです。
北病院において多飲症への対策を考えるきっかけとなったのは、1988年、当時北病院に勤務していた松田源一先生の多飲症患者に対する疫学研究*10でした。さらに松田は、多飲症患者の5年間にわたる長期経過についても研究*11しており、そのなかで、多飲症患者への治療的対応について、「とかく隔離拘束によって多飲行動を強制しようとする試みが行われる。しかし長期的な経過や転帰を見ると必ずしもよくない。隔離を必要とするようなより重症の精神症状を呈する例では多飲行動も治りにくいことが考えられる。このような例に対しては多大な労力を要するが、開放的処遇により人間的接触を多くすることが多飲行動を軽減するのに最も効果的であることがわかった」と述べています。現在の北病院における多飲症患者への治療的アプローチの原点はまさしくここにあるといえます。
とはいえ、北病院でも過去、多飲症患者に対してはやむを得ず恒常的な隔離に頼っていた時代があり、保護室や個室の多くが有効活用できない状態にあったことがあります。結果として病棟運営や精神科救急制度への対応にも影響するようになったため、1999年に多飲症専門病棟(閉鎖)を開設し、そこで多飲症患者に対して集団でかかわるための専門的な治療プログラムを立ち上げることになりました*12。さらに2003年からは、開放的な処遇に努めること、作業療法やレクリエーションを積極的に取り入れること、各スタッフが個人的に努力するのではなくチームとしてかかわること、が取り組まれ、「水中毒を防ぐ」ための対応から「安全に水を飲める」ための対応に向けてさまざまな試行錯誤がなされてきたのです。
現在、私たちの病棟では水を飲みすぎて意識を失ったり、けいれんを起こしたりする患者は見られません。また、多飲症の患者が少し多めに水を飲んでいても、それについて叱責したり無理やり静止する看護師もいません。入院中の患者で、以前に水中毒発作を起こしたり、多飲症に関連した問題行動を起こした経歴があっても、ほとんどは単独で院内外出を行うことができており、なかには単身生活をしながら外来に通院している人もいます。
私たちの多飲症を「よくする」方法は、多飲症を「なくす」ことではありません。多飲症病棟で日常的に行われていることに、特別なことはほとんどないのです。第一に原疾患の治療があり、それと並行して、多飲症の患者に対しては自らの健康や日常生活に支障をきたさないような水の飲み方を、その人なりの方法で確立するための援助が行われているだけなのです。特別な薬物も、特殊な教材も、厳密な管理法も用いていません。私たちは、10年近くの実践を通して、現在のかかわり方で多飲症の多くは改善させることができると考えるようになりました。
しかしそうはいっても、多飲症が原因で入院している患者の多くは退院のめどが立ちにくく、20床のうちいくつかは固定してしまっているのが現状です。今後、多飲症(の管理が難しいこと)が原因でなかなか退院させられないという状況をいかに打破していくかが私たちの課題であると考えています。
私たちの実践を、「閉鎖できる多飲症専門病棟があるからできるのだ」と考える方がいるかもしれません。しかし本書をよく読んでいただければ、私たちが閉鎖空間を治療の手段としてはほとんど用いていないことがわかっていただけると思います。ただ、私たちも、自分たちの方法が万全だとは思っていません。全く違う方法で良好な結果が得られている施設もあるかと思います。どのような点にせよ、本書が多飲症に困っている人たちにとって、何らかの助けになる部分があれば幸いです。
2010年1月
著者を代表して
川上宏人
本書で引用した文献は、以下の3つの方式で集めたものです。
1.MEDLINEを用いての検索、2.「医中誌」を用いての検索、3.上記でみつけ出した文献からの「孫引き」。
多飲症の治療についてのレビューでは、筆者の怠慢によりそのエビデンスレベルについての検証はしていないため、その内容については玉石混淆であることを事前にお断りしておきたいと思います。
また、参考にさせていただいた図書として、American Psychiatric Press社の「Progress in Psychiatry」(David Spiegel編集)というシリーズの中の一冊『Water balance in Schizophrenia』(David B. Schunur、Darrell G. Kirch編)、中外医学社の『より理解を深める! 体液電解質異常と輸液』(深川雅史監修、柴垣有吾著)の2冊を挙げておきます。
引用参考文献
1 小山田静枝: 精神科患者における多飲の臨床的研究. 精神医学 1998; 40(6):613-618
2 Bremner AJ, Regan A: Intoxicated by water. Polydipsia and water intoxication in a mental handicap hospital. Br J Psychiatry 1991; 158:244-250
3 Deb S, Bramble D, Drybala G, al e: Polydipsia amongst adults with a learning disability in an institution. J Intellect Disabil Res 1994; 38 ( Pt 4):359-367
4 Hayfron-Benjamin J, Peters CA, Woodhouse RA: Screening patients with mental retardation for polydipsia. Can J Psychiatry 1996; 41(8):523-527
5 及川克紀: 重症知的障害者の飲水行動について. 発達障害研究 2003; 25:110-116
6 Zafonte RD, Watanabe TK, Mann NR, al e: Psychogenic polydipsia after traumatic brain injury. Am J Phys Med Rehabil 1997; 76(3):246-248
7 Silber TJ: Seizures, water intoxiction in anorexia nervosa. Psychosomatics 1984; 25(9):705-706
8 荒川彌生, 美澄明子, 山本清人, 他: 精神障害者に見られる多飲水(水中毒)のケアの中で生じる看護者の陰性感情とその要因. 日本精神科看護学会誌 1999; 42(1):296-298
9 鶴田聡: 長期入院中の慢性精神分裂病患者の示す暴力行為について. 精神医学 2002; 44(1):33-38
10 松田源一: 精神障害者に発生する多飲の臨床的諸特性. 精神医学 1988; 30(2):169-176
11 松田源一: 入院精神障害者の多飲行動に関する臨床的研究―病的多飲の経過と転帰. 慶応医学 1992; 69(1):159-172
12 石部忠彦, 名取真, 稲垣中, 他: 多飲症治療病棟における飲水コントロールの試み. 病院・地域精神医学 2000; 43:249-250
推薦のことば
この本の推薦文を書くことができることを、本当に嬉しく光栄に思うと共に、こんなにすばらしい著書を、川上宏人先生や松浦好徳看護師をはじめとする看護スタッフが完成させたことを、山梨県立北病院の院長として誇りに思います。
ここで少しだけ、昔話をさせてください。実は、山梨県立北病院で、最初に「水中毒(みずちゅうどく)」という診断をつけたのは私なのです。1983年の6月のことでした。当時、私が主治医として診ていた統合失調症の入院患者(男性)が、突然意識を失って倒れたかと思うと、大量の嘔吐、尿失禁、けいれん発作が出現し、慌てて臨床検査を行うと、108mEq/Lという著しい低ナトリウム血症が認められました。
今だったら誰でも「水」に着目すると思うのですが、その当時は多飲症や水中毒といった概念はほとんど知られておらず、かけだしの精神科医だった私には何が何だかわかりませんでした。ひょっとするとこれは命が助からないかもしれないと思い、年老いた両親を呼び寄せ、付き添ってもらいました。
幸い翌日には意識が戻り、3日ほどして回復したのですが、なぜこうなったのか、そしてどうして回復したのか、教科書を読んだり、先輩の先生に聞いても見当がつきません。しかしとにかく水を飲みすぎているのは間違いないので、半分は当てずっぽうで「水中毒」というキーワードで文献を調べてみると(当時はインターネットが発達していませんでしたから、文献検索も大変だったのですが)、精神病患者におけるwater intoxicationやpolydypsiaについての報告がいくつか手に入り、「これだ!」と膝を打ったのをよく覚えています。これが北病院で最初に確認された水中毒発作症例でした。
そのつもりで病棟の患者を観察すると、多くの入院患者が水道の蛇口に口をつけて、あおるように水を飲み続けていることに気がつきました。外来患者でも家族に聞くと、何リットルも水を飲んでいますという患者がいました。患者自身に聞くと、そんなに飲んでないと否定するのですが、隠れて大量に水飲みをしていることもあったのでした。
当時は抗精神病薬を投与中の統合失調症患者にけいれん発作が生じると、「薬物で発作閾値が低下したせいだ」とか「電気けいれん療法の副作用ではないか」などと考えて、抗てんかん薬が処方されることがよくありました。しかし実は、このようなけいれん発作の多くは多飲による低ナトリウム血症が原因だったのでしょう。
そこで、当時の北病院に勤めていた後輩の松田源一先生に、これを研究してみたらと勧めました。彼は多飲や水中毒を伴う患者について根気よく臨床観察を行った結果をまとめ、1988年に『精神医学』誌に載りました。この報告は、国内では必ず引用される重要な論文になりましたし、その後、この研究を発展させて彼の学位論文にもなったのです。
山梨県立北病院は1990年に全面改築されましたが、その後、多飲症患者への治療は、当病院でも大きな課題になりました。多飲症患者の個室施錠や保護室隔離は長期にわたるため、病院として救急・急性期患者が受け入れられないという支障が出ていたからです。そこで、1999年にアルコール病棟を改修して、多飲症専門病棟にしました。2000年には、稲垣中先生が、全多飲症患者に「NDWG」を指標にした包括的調査を行い、学位を授与されています。
しかし、整備された多飲症病棟でも、「患者の飲水を監視して管理する」ことを医療者の責務と考えて、患者へ管理的に接するということは続きました。けれどもこうした方法はなかなか患者の病状の改善には結びつかず、大胆な方針の見直しがはじまったのが2003年のことでした。
この2003年という年は、山梨県立北病院にとって、あらゆる点でターニングポイントだったといえるでしょう。この年から「開放病棟を1つ閉鎖し、病床を300床から200床に削減するなかで、援護寮(のちに退院支援施設になりました)を作り、デイケア・訪問看護を拡張し、スーパー救急病棟を開始し、医師やパラメディカルを増員する」という機能強化プランの検討が本格的に開始されたのです。当時、当病院ではどのような方向に進むべきかの議論がスタッフを巻き込んで展開されたのをよく覚えています。
大きな変革が進みつつある状況のなか、多飲症病棟でも新たな治療・看護方法の模索がはじまりました。多飲症病棟がある病棟は、重症・長期化した患者の受け入れ先であり、北病院のなかでも最もしんどい部分を受け持っている病棟です。このような病棟のなかで、この本に記されているような地道な努力が積み上げられ、重要な進歩が生み出されていったのです。
多飲症や水中毒は、精神症状が重く難治の患者に多く併発します。また精神症状の悪化とも関係があり、薬物を中断して再発した患者が、来院した時点で水中毒発作を併発しているということもあります。「水を飲め」というような幻覚がある患者もいますが、それよりも思考障害がひどく、認知機能が低下した患者に頻度が高いように思います。水を飲むという行為は、人間の根元的な欲動に根ざしていて、この調節機構の異常と統合失調症などの精神病症状とはどこかでつながっているにちがいないと私は思っています。
この本を作るという話が出てきたのは2006年10月に東京で行われた日本病院・地域精神医学会の「多飲症・水中毒をどうするか」というシンポジウムで、座長兼シンポジストとして、この本の著者である川上宏人先生と松浦好徳看護師がすばらしいプレゼンをしたことがきっかけだったと聞いています。そこから3年が経ちましたが、その間に熟成された知識・知恵・思いが、この本にはちりばめられています。この本が、多飲症・水中毒で悩む患者・家族・スタッフにとって、エビデンスを示した初のスタンダードとして役立っていくに違いないと私は確信しています。
山梨県立北病院・院長 藤井康男
本書の目的
本書は、多飲症と日々向き合っている患者やその家族、医療スタッフなどの方々が日ごろかかえている、「どのようにしたら安全に水を飲める環境を構築できるのか」という悩みや疑問を解決するためのヒントを提供することを目的としています。
本書の構成は、以下のように4部構成になっています。
第1部では、多飲症治療についての疑問やわかりにくい点、よくある質問などをQ&A形式で取り上げています。第2部は実践編です。山梨県立北病院(以下、北病院)の多飲症専門病棟において、看護師たちがこれまで試行錯誤を重ねながら作り上げ、現在一定の効果を示すまでに成熟した多飲症患者との「かかわり」や、体重管理のアプローチについて紹介しています。第3部は多飲症や水中毒についての知識をまとめた部分で、北病院で活用している、多飲症や水中毒に関する「とらえ方」や「重症度分類」の考え方を紹介しています。さらに、多飲症の原因、治療などについて、海外や日本国内において発表されてきた論文のレビューなどをまとめています。第4部は資料編で、北病院の多飲症専門病棟における看護計画、心理教育の患者用テキスト、スタッフ用マニュアルを紹介しています。
多飲症は精神科医療における一部の患者に限定された特別な病態であるように思わている感があります。しかし多飲症は統合失調症だけでなく、感情障害*1や精神発達遅滞*2,3,4,5、脳炎後や頭部外傷後などの器質的な脳疾患*6、神経性食思不振症*7、人格障害、認知症の患者などでも認められており、発症頻度は必ずしも少なくありません。
多飲症についてはいまだに多くのことが明らかになっていないため、治療的に正しく介入するのはとても難しいとされています。一見すると単純に思える治療の道筋は、実は複雑な迷路のように入り組んでおり、正しい進み方をしても出口に到達するまでには時間がかかり、間違いを重ねるほど抜け出しにくくなります。臨床現場においても統一された治療コンセプトや目標がなく、評価方法や診断基準も文献によってまちまちであるため、中等度以上の多飲症患者への対応は、スタッフの個人的努力や保護室・個室などのハード面に依存することになってしまいます。また、多飲症患者への処遇は、対応する人間と患者との関係性や、環境全体の雰囲気などにより大きく影響されるため、統一することが難しく、ややもすると介入の仕方が極端に過剰になるか、無関心になるかのどちらかになりやすいように思われます。
目の前で中等症以上の水中毒発作を一度でも見てしまうと、すべての飲水行為が怖く感じられてしまうこともあるでしょう。なんとかして水中毒への発展を制止しなくては、という切迫感からはじまる過剰な介入は、患者との間で不必要な摩擦を生み、さらなる多飲や問題行動の原因ともなり、結果として患者にも治療者にも、不必要な疲労感や不全感をもたらすだけの場合が少なくないのではないでしょうか。実際、荒川ら*8によると、多飲症患者にかかわった経験のある看護師の多くは、いつ発作が起こるかという不安や無力感、自責感を抱きやすい傾向にあり、鶴田による調査*9では、長期入院中の患者による暴力の4.5%は、水中毒が何らかのかたちで関与して起こったものでした。看護スタッフは荒れる患者と何もしない医師やその処方を憎み、医師は全くよくならない患者や看護スタッフの対応を憎み、患者はしつこい看護スタッフや自分を閉じ込める医師を憎む、という最悪の構造に陥ってしまうことがあり、こうなると絶望的です。
もうひとつの問題は、無関心や知識の欠如、正しくない「温情」などにより、危険な徴候を見逃してしまうことです。夕方になると患者の機嫌が悪くなり、幻聴の訴えや不眠、夜間の失禁が多くなっていれば、すでに軽症の水中毒であるとみなすべきです。ところが、見方しだいでは「そもそもの病状」や「薬物による副作用」とも受け取れます。けいれんなどの症状が出現するまで多飲症や水中毒に気づかないこともあるようです。確かに、それまでに多飲症によるさまざまな問題が起こっていれば、原疾患への治療方針は混乱させられ、正しい効果判定ができなくなってしまっているかもしれません。しかし、多飲症や水中毒の危険な徴候を見逃すと、結果としてその転帰を悪化させることにもなりかねません。さらには、長期間の多飲・多尿による身体への悪影響も見逃すことのできない問題です。
多飲症を合併しているということは、患者の予後を悪化させる可能性があり、さらには病棟運営にも深刻な影響を及ぼしかねないものです。では、そうならないためにはどうすればよいのでしょうか。
私も以前、総合病院の精神科病棟に勤務し、精神科患者の身体合併症治療に従事していた時期に、水中毒に続発した意識障害や重度の肺炎や呼吸不全、高度の横紋筋融解症による急性腎不全などを経験したことがあり、多飲症については厳重な行動管理が必須という印象をもっていました。2005年より北病院の多飲症専門病棟で勤務するようになったのですが、当初は、多飲症だからといって、特別なことが何もないことに驚いたものです。重度の多飲症患者に対応できるように工夫されている病床が5床(個室1、二人床2)ありますが、外見上の違いはそれらとほかの病室を区切るドアがあることと、その区画だけのトイレとリビングがある程度で、そのドアも施錠されていません。それ以外の違いといえば、体重を頻繁に測定することと、そのための体重計が病棟のリビングに置いてあることくらいです。
北病院において多飲症への対策を考えるきっかけとなったのは、1988年、当時北病院に勤務していた松田源一先生の多飲症患者に対する疫学研究*10でした。さらに松田は、多飲症患者の5年間にわたる長期経過についても研究*11しており、そのなかで、多飲症患者への治療的対応について、「とかく隔離拘束によって多飲行動を強制しようとする試みが行われる。しかし長期的な経過や転帰を見ると必ずしもよくない。隔離を必要とするようなより重症の精神症状を呈する例では多飲行動も治りにくいことが考えられる。このような例に対しては多大な労力を要するが、開放的処遇により人間的接触を多くすることが多飲行動を軽減するのに最も効果的であることがわかった」と述べています。現在の北病院における多飲症患者への治療的アプローチの原点はまさしくここにあるといえます。
とはいえ、北病院でも過去、多飲症患者に対してはやむを得ず恒常的な隔離に頼っていた時代があり、保護室や個室の多くが有効活用できない状態にあったことがあります。結果として病棟運営や精神科救急制度への対応にも影響するようになったため、1999年に多飲症専門病棟(閉鎖)を開設し、そこで多飲症患者に対して集団でかかわるための専門的な治療プログラムを立ち上げることになりました*12。さらに2003年からは、開放的な処遇に努めること、作業療法やレクリエーションを積極的に取り入れること、各スタッフが個人的に努力するのではなくチームとしてかかわること、が取り組まれ、「水中毒を防ぐ」ための対応から「安全に水を飲める」ための対応に向けてさまざまな試行錯誤がなされてきたのです。
現在、私たちの病棟では水を飲みすぎて意識を失ったり、けいれんを起こしたりする患者は見られません。また、多飲症の患者が少し多めに水を飲んでいても、それについて叱責したり無理やり静止する看護師もいません。入院中の患者で、以前に水中毒発作を起こしたり、多飲症に関連した問題行動を起こした経歴があっても、ほとんどは単独で院内外出を行うことができており、なかには単身生活をしながら外来に通院している人もいます。
私たちの多飲症を「よくする」方法は、多飲症を「なくす」ことではありません。多飲症病棟で日常的に行われていることに、特別なことはほとんどないのです。第一に原疾患の治療があり、それと並行して、多飲症の患者に対しては自らの健康や日常生活に支障をきたさないような水の飲み方を、その人なりの方法で確立するための援助が行われているだけなのです。特別な薬物も、特殊な教材も、厳密な管理法も用いていません。私たちは、10年近くの実践を通して、現在のかかわり方で多飲症の多くは改善させることができると考えるようになりました。
しかしそうはいっても、多飲症が原因で入院している患者の多くは退院のめどが立ちにくく、20床のうちいくつかは固定してしまっているのが現状です。今後、多飲症(の管理が難しいこと)が原因でなかなか退院させられないという状況をいかに打破していくかが私たちの課題であると考えています。
私たちの実践を、「閉鎖できる多飲症専門病棟があるからできるのだ」と考える方がいるかもしれません。しかし本書をよく読んでいただければ、私たちが閉鎖空間を治療の手段としてはほとんど用いていないことがわかっていただけると思います。ただ、私たちも、自分たちの方法が万全だとは思っていません。全く違う方法で良好な結果が得られている施設もあるかと思います。どのような点にせよ、本書が多飲症に困っている人たちにとって、何らかの助けになる部分があれば幸いです。
2010年1月
著者を代表して
川上宏人
本書で引用した文献は、以下の3つの方式で集めたものです。
1.MEDLINEを用いての検索、2.「医中誌」を用いての検索、3.上記でみつけ出した文献からの「孫引き」。
多飲症の治療についてのレビューでは、筆者の怠慢によりそのエビデンスレベルについての検証はしていないため、その内容については玉石混淆であることを事前にお断りしておきたいと思います。
また、参考にさせていただいた図書として、American Psychiatric Press社の「Progress in Psychiatry」(David Spiegel編集)というシリーズの中の一冊『Water balance in Schizophrenia』(David B. Schunur、Darrell G. Kirch編)、中外医学社の『より理解を深める! 体液電解質異常と輸液』(深川雅史監修、柴垣有吾著)の2冊を挙げておきます。
引用参考文献
1 小山田静枝: 精神科患者における多飲の臨床的研究. 精神医学 1998; 40(6):613-618
2 Bremner AJ, Regan A: Intoxicated by water. Polydipsia and water intoxication in a mental handicap hospital. Br J Psychiatry 1991; 158:244-250
3 Deb S, Bramble D, Drybala G, al e: Polydipsia amongst adults with a learning disability in an institution. J Intellect Disabil Res 1994; 38 ( Pt 4):359-367
4 Hayfron-Benjamin J, Peters CA, Woodhouse RA: Screening patients with mental retardation for polydipsia. Can J Psychiatry 1996; 41(8):523-527
5 及川克紀: 重症知的障害者の飲水行動について. 発達障害研究 2003; 25:110-116
6 Zafonte RD, Watanabe TK, Mann NR, al e: Psychogenic polydipsia after traumatic brain injury. Am J Phys Med Rehabil 1997; 76(3):246-248
7 Silber TJ: Seizures, water intoxiction in anorexia nervosa. Psychosomatics 1984; 25(9):705-706
8 荒川彌生, 美澄明子, 山本清人, 他: 精神障害者に見られる多飲水(水中毒)のケアの中で生じる看護者の陰性感情とその要因. 日本精神科看護学会誌 1999; 42(1):296-298
9 鶴田聡: 長期入院中の慢性精神分裂病患者の示す暴力行為について. 精神医学 2002; 44(1):33-38
10 松田源一: 精神障害者に発生する多飲の臨床的諸特性. 精神医学 1988; 30(2):169-176
11 松田源一: 入院精神障害者の多飲行動に関する臨床的研究―病的多飲の経過と転帰. 慶応医学 1992; 69(1):159-172
12 石部忠彦, 名取真, 稲垣中, 他: 多飲症治療病棟における飲水コントロールの試み. 病院・地域精神医学 2000; 43:249-250
目次
開く
推薦のことば
本書の目的
第1部 多飲症・水中毒についてのQ&A
Q1 多飲症って何ですか?
Q2 多飲症と水中毒は違うのですか?
Q3 多飲症や水中毒には重症、軽症といった区別はあるのですか?
Q4 多飲症の原因は抗精神病薬などの薬物だと聞いたのですが、本当ですか?
Q5 多飲症は珍しい病態なのでしょうか?
Q6 多飲症の患者をみつけるためのよい方法はありますか?
Q7 多飲症は統合失調症の患者に特有なのでしょうか?
Q8 多飲症になりやすい人がいるのでしょうか?
Q9 水中毒を起こしにくくする飲み物はありますか?
Q10 保護室がすべて埋まっている場合、隔離の代わりに身体拘束を行ってもよいでしょうか?
Q11 多飲症患者のために夜間、病棟の水道を止めているので、ほかの患者から苦情がきて困ります。どうしたらよいでしょうか?
Q12 多飲症の患者が暴力的で困ります。どうしたらよいでしょうか?
Q13 多飲症について、患者に教育をしたいと思います。何かよい方法はありますか?
Q14 電気けいれん療法は多飲症に効くのでしょうか?
Q15 水中毒を繰り返す患者がいます。後遺症はあるのでしょうか?
Q16 保護室から出た途端に多飲水をする患者がいて困っています。
Q17 水中毒になった場合、積極的な治療が必要なのでしょうか?
Q18 どのくらい水を飲んでいると、多飲症になるのですか?
Q19 タバコやコーヒー、ビールは水中毒と関係がありますか?
Q20 水中毒の危険性を評価するために体重を測るのは、有効な方法ですか?
Q21 「軽度」の多飲症の人のベース体重の設定法は?
Q22 「中等度」の多飲症の人のベース体重の設定法は?
Q23 「重度」の多飲症の人のベース体重の設定法は?
Q24 もう何十年も多飲症が続いています。水中毒はないのですが、大丈夫でしょうか?
Q25 私たちの施設にいる多飲症患者は、絶対よくなるとは思えないのですが……。
第2部 実践編
1章 私たちも悩んでいた-北病院における多飲症看護の歴史
1 試行錯誤の時代
2 改革期
2章 スタッフの意識改革
1 「かかわり」の方法を確立
2 チーム全体の意思へ
3章 多飲症看護の具体的方法
1 行動観察
2 体重測定
3 行動制限(飲水制限)
4 血液検査と採尿
5 申告飲水
6 活動性を向上させる
4章 多飲症患者への教育
1 患者教育の必要性
2 「多飲症心理教育」への発展
3 講義の進め方
4 心理教育で見えてきたもの
5章 多飲症家族教室
1 家族への注目
2 家族教室の開催
第3部 知識編
1章 多飲症・水中毒とはどういう症状か
1 多飲症とは
2 水中毒とは
3 人体の水分バランス
2章 多飲症・水中毒の原因と治療
1 多飲症・水中毒の原因
2 多飲症・水中毒の治療
3章 多飲症患者の飲水行動を管理するための方法
1 早期発見する(あたりをつける)ための方法
2 多飲症の程度に合わせてNDWGを用いて管理する方法
3 外来でどうかかわるか
4章 多飲症治療の今後-開放的処遇に向けて
1 ハードとソフトの関係
2 長期入院中の患者に対する取り組み
3 長期化させないための取り組み
4 今後に向けて
第4部 資料編
1 多飲症看護計画
2 水中毒看護計画
3 多飲症心理教育 患者用テキスト
4 多飲症心理教育 スタッフ用マニュアル
おわりに
本書の目的
第1部 多飲症・水中毒についてのQ&A
Q1 多飲症って何ですか?
Q2 多飲症と水中毒は違うのですか?
Q3 多飲症や水中毒には重症、軽症といった区別はあるのですか?
Q4 多飲症の原因は抗精神病薬などの薬物だと聞いたのですが、本当ですか?
Q5 多飲症は珍しい病態なのでしょうか?
Q6 多飲症の患者をみつけるためのよい方法はありますか?
Q7 多飲症は統合失調症の患者に特有なのでしょうか?
Q8 多飲症になりやすい人がいるのでしょうか?
Q9 水中毒を起こしにくくする飲み物はありますか?
Q10 保護室がすべて埋まっている場合、隔離の代わりに身体拘束を行ってもよいでしょうか?
Q11 多飲症患者のために夜間、病棟の水道を止めているので、ほかの患者から苦情がきて困ります。どうしたらよいでしょうか?
Q12 多飲症の患者が暴力的で困ります。どうしたらよいでしょうか?
Q13 多飲症について、患者に教育をしたいと思います。何かよい方法はありますか?
Q14 電気けいれん療法は多飲症に効くのでしょうか?
Q15 水中毒を繰り返す患者がいます。後遺症はあるのでしょうか?
Q16 保護室から出た途端に多飲水をする患者がいて困っています。
Q17 水中毒になった場合、積極的な治療が必要なのでしょうか?
Q18 どのくらい水を飲んでいると、多飲症になるのですか?
Q19 タバコやコーヒー、ビールは水中毒と関係がありますか?
Q20 水中毒の危険性を評価するために体重を測るのは、有効な方法ですか?
Q21 「軽度」の多飲症の人のベース体重の設定法は?
Q22 「中等度」の多飲症の人のベース体重の設定法は?
Q23 「重度」の多飲症の人のベース体重の設定法は?
Q24 もう何十年も多飲症が続いています。水中毒はないのですが、大丈夫でしょうか?
Q25 私たちの施設にいる多飲症患者は、絶対よくなるとは思えないのですが……。
第2部 実践編
1章 私たちも悩んでいた-北病院における多飲症看護の歴史
1 試行錯誤の時代
2 改革期
2章 スタッフの意識改革
1 「かかわり」の方法を確立
2 チーム全体の意思へ
3章 多飲症看護の具体的方法
1 行動観察
2 体重測定
3 行動制限(飲水制限)
4 血液検査と採尿
5 申告飲水
6 活動性を向上させる
4章 多飲症患者への教育
1 患者教育の必要性
2 「多飲症心理教育」への発展
3 講義の進め方
4 心理教育で見えてきたもの
5章 多飲症家族教室
1 家族への注目
2 家族教室の開催
第3部 知識編
1章 多飲症・水中毒とはどういう症状か
1 多飲症とは
2 水中毒とは
3 人体の水分バランス
2章 多飲症・水中毒の原因と治療
1 多飲症・水中毒の原因
2 多飲症・水中毒の治療
3章 多飲症患者の飲水行動を管理するための方法
1 早期発見する(あたりをつける)ための方法
2 多飲症の程度に合わせてNDWGを用いて管理する方法
3 外来でどうかかわるか
4章 多飲症治療の今後-開放的処遇に向けて
1 ハードとソフトの関係
2 長期入院中の患者に対する取り組み
3 長期化させないための取り組み
4 今後に向けて
第4部 資料編
1 多飲症看護計画
2 水中毒看護計画
3 多飲症心理教育 患者用テキスト
4 多飲症心理教育 スタッフ用マニュアル
おわりに
書評
開く
「グルグル」と「爆発」をめぐる考察 (雑誌『精神看護』より)
書評者: 熊谷 晋一郎 (東京大学先端科学技術研究センター)
私は、今年で9年目になる小児科医である。出産時のトラブルによる後遺症で、脳性まひになった。それ以来、電動車いすに乗って生活をしている。トイレや、入浴、掃除洗濯など、身の回りのことの多くは一人ではできないため、ヘルパーさんなどに手伝ってもらいながら、生活を回している。
私には、精神科の臨床経験はない。だから、この本に書いてあるような精神科病棟の現場の厳しさを知らない。しかし、この本を読んでいくうちに、多飲症をめぐってのあれこれや、それに対する山梨県立北病院(北病院)の取り組みに対して、他人事ではない何かを感じた。
多飲症とは、水を飲むことがどうしてもやめられなくなり、日常生活にも支障をきたした状態のことだ。精神科では決して珍しいものではなく、長期入院中の患者の20%前後に起こるともいわれている。水といってもあなどれない。急激・多量な飲水をすれば水中毒へと進み、死にいたる危険もあるのだ。しかし、これまで多飲症に対してはっきりと治療方針が打ち立てられることはなかった。
看護師が患者の飲水をこまかく監視、管理しようとしても、なかなか患者の病状の改善には結びつかない。それどころか、飲水管理をめぐって暴力沙汰になることすらある。看護師の多くは、いつ水中毒が起こるかわからないという不安や、管理の努力が徒労に終わる無力感、自責感を抱きやすくなり、ひいては荒れる患者と何もしない医師を憎むようになる。一方、医師は、全くよくならない患者や看護師の対応を憎み、患者はしつこい看護師や自分を閉じ込める医師を憎む、という最悪の相互不信に陥ってしまうこともあるという。それに、飲水制限を徹底するためにやむなく行われる個室施錠や保護室隔離は長期にわたるため、病院として救急・急性期患者が受け入れられないという病棟運営上の支障も出てくる。
このように、多飲症という病態は、精神医療の現場を崩壊させうる大きな問題になっている。
◆心臓病の中学生にも水問題
過剰な監視が、かえって患者の様態を悪くするという経験は、私にも何度かある。その中でも特に印象に残っているのは、ある心臓病の中学生を担当した時のエピソードだ。
私はかつて一年間ほど、小児心臓病の専門病棟で働いていた。そこに入院してくる多くの子どもたちは、心臓が十分に動かなくなる、「心不全」と呼ばれる病態を患っていた。
心不全が起きると、全身にくまなく血液をいきわたらせるために必要な、高い血圧を維持できなくなる。それを補うために、レニン・アンギオテンシン系というホルモンシステムが作動し、体の中に通常よりもたくさんの塩分や水をため込むようになる。十分に動かない心臓の代わりに塩分や水をかさ増しして、血圧を正常化するのだ。この段階ではまだ、「血圧低下→水貯留→血圧正常化」という具合に恒常性が維持されているから、ある程度状態は安定している。
しかし、心不全が進んで塩分や水の貯留がある《一線》を越えると、心臓がそれ以上拡張できなくなるほど膨らんでしまい、かえって血圧が落ちてくる。こうなってくると、「血圧低下→水貯留→さらなる血圧低下→さらなる水貯留→…」という悪循環に陥ってしまう。このとき、塩分・水を貯留させるレニン・アンギオテンシン系のホルモンは振り切れるほど放出されているのだが、じつはこのホルモン自体がただでさえ傷んでいる心臓の筋肉に、追い打ちをかけるようにダメージを与える毒性をもっており、心不全の進行を早めるのである。
だが、この《一線》がどこなのかを見極めるのはとても難しい。それはきっと、多飲症が水中毒へと至る一線を見極める難しさと、共通する部分があるだろう。難しいからこそ、臨床家は常に不安を感じており、血圧や、体重や、尿量を何度も測定する。当時の私も、一線を越えないように厳しく水分摂取を制限し、越えたと判断したら急いで利尿剤を投与していた。それは、徹底した監視と管理の空間だと言える。
その重症心不全の中学生を担当した時、私も不安でいっぱいだった。見た目はわりと元気そうな様子なのだが、超音波検査で心臓の動きを見てみると、通常なら、大きく、ゆったりと、しなやかに強く動いているはずの心臓が、まるで小刻みな悪寒のように、小さく震えている。それを見た瞬間、私は自分のみぞおちの部分にも、ぎゅうと縮こまるような痛みを感じた。「一線はかなり近い」と思ったのだ。
実際に血液検査をしてみると、水貯留の程度を表す数値が跳ね上がっている。「間違いない、ぎりぎりだ!」と信じきった私は、すぐに厳しい水分制限と、ベッド上の絶対安静を指示した。体重増加や尿量減少の兆候があれば、すぐに利尿剤を打った。
することもなく終日、ベッドの上で過ごさせられる中学生のイライラは募る。口の渇きを紛らわすために、氷を長々と口の中で転がしながら、ふてくされた表情をしてヘッドフォンで音楽を聴いている。私はベッドサイドに行くたびに、彼から発せられるそのイライラを肌身にヒリヒリと感じ、申し訳なさを感じつつも、それをうまく受け止められなかった。私の目下の関心は、彼の今日の体重と、ここ数時間の尿量と、血圧と、心臓の動きと、血液データにこそあったのだ。私は、「実は彼の検査データにこそ興味がある」ということを彼に悟られないように、「何の音楽聴いてるの?」などと空虚な言葉を発する。一瞥をくれた後、彼は無視をする。私は黙って採血をし、ベッドから離れる。
厳しい管理を2週間くらい続けても、容態はよくなるどころかむしろ悪くなっていった。心臓の動きも相変わらずだし、利尿剤を打つ回数は増えていく。血液データも、わずかではあるが徐々に悪くなっていく。私は治療方針を見失った。「もはや、ペースメーカーの装着か、移植しかないのか」とさえ思うようになった。
◆監視からほどかれた心臓
同じ頃、彼のストレスも限界に達した。そして、外泊がしたいと言ってきた。私は、このような状態で外泊をするなんてとても無理だろうと思った。しかし、その時の私の上司は、なんと彼の外泊を認めたのである。私は上司の思惑が読めず、ますます混乱した。「大丈夫なんでしょうか」と上司に聞いても、「それはやってみないとわからない。ただ、入院する前まではそれなりに元気にやってたわけだし」という釈然としない返事を返してくる。
上司は、患者を見捨てたのだろうか? もしくは、危ない賭けに出たのだろうか? それとも、私にはない、経験的なカン、みたいなものがあったのだろうか? それはわからない。しかし、現在の治療方針が煮詰まっていることも、中学生のストレスが限界に達していることも、いまや明らかだったから、外泊することになった。
ところが信じられないことに、外泊から戻ってきた彼は、見違えるように元気になっていたのである。外泊中の様子をご両親に聞いてみると、なんと野球の素振りの練習をしたり、映画を見に行ったり、好きなものを食べたりと、自由で活動的な生活をしていたという。検査データも驚くほどの改善傾向を示しており、心臓の動きもよくなっていた。そして、ほどなく彼は退院していった。
入院中の彼は、基本的にとても「いい子」だった。入院中のほかの子どものなかには、自分のカルテを引きちぎったり、スタッフに罵声を浴びせたりする子もいる。彼は、むしろいい子であるがゆえに、監視・管理されるストレスを外へと放出する代わりに、内へ内へとため込んでしまうようなところがあったように思う。本書にも、ストレスがレニン・アンギオテンシン系、ひいては口渇感を引き起こすということが書いてあるが、私はこの経験を通して身をもって、監視されるストレスというものが、いかに人の心身を追い詰めていくかを知った。監視されて身動きがとれなくなっていた心臓は、自由を得て、力強く動き始めたのである。
◆「グルグル」と「爆発」のサイクル
北病院の実践も、当初から順風満帆なわけではなかったようだ。専門病棟での取り組みが始まったばかりの頃の状況が、本書には以下のように記載されている。
私は、物心ついたころから十代の半ばぐらいまで、毎日濃厚なリハビリを受けていた。そのリハビリというのは、「私の動きを、すこしでも健常な動きのイメージに近づけること」を目標にして行われた。私は、主に母親から、座り方やずりばいの仕方、お茶わんや鉛筆の持ち方など、日常生活の一挙手一投足を監視され続け、イメージから外れると厳しく修正された。
また、座位や膝立ち、片膝立ち、立位などの健常な姿勢パターンをなぞらせる訓練を、1回1時間半、1日に3回程度行っていた。母親は訓練中、しばしば激情的になって、イメージ通りにうまく動かない私に厳しく接した。エスカレートしたときには、バットでつつかれたりもして、文字どおりのスパルタだった。私は訓練中、懸命に、これまで見聞きしてきた健常な運動イメージを想起させながら、私自身が繰り出す運動を自己監視し続ける。
しかし、イメージを意識して監視すればするほど、私の体は緊張を強め、かえってイメージから外れた運動を繰り出してしまう。イメージと運動のギャップ→焦り→体の緊張→さらなるギャップ→さらなる焦り→…という悪循環によって、私は立ちすくんでしまい、運動が出せなくなる。そして、「自分を監視する自分を監視する自分を監視する……」というグルグルとした無限回路が、私の中に重く沈澱し、膨れ上がっていくのだ。
訓練が終わると、食事の時間だ。私は、我を忘れて食べた。食べている間は、グルグルを振り払うことができた。監視によってあらゆる運動をせき止められ、出口を失ったグルグルのエネルギーを、「食べる」という行為で発散している感覚だ。それは、怒りとも、喜びともつかない忘我の恍惚。きっと、多飲症の人が水を飲み続ける時というのは、同じような状態なんじゃないだろうか、と思う。食事中に茶碗の持ち方などを注意されると無性にイライラとし、ある時などは怒って茶碗をわざとひっくり返した。それに怒った父親が、私を抱えて暗い部屋にほおり投げ、私はそこで悔しさのあまり、大声で何時間も泣き続けた。
爆発的な過食をした後というのは、一気に正気に戻る。そして、またあの自己監視のグルグルが舞い戻ってくる。「みっともなく食べ散らかし、ぶくぶくと肥っていく自分」を責める自分が生まれるのだ。そしてそのグルグルが再び一線を越えると、今度は食べた物を残らず吐き出し始めるのである。
これが私の経験した過食嘔吐だ。私にとっての過食嘔吐は、自己を監視し続ける無限の「グルグル」と、それを衝動的な行動に転化する「爆発」の繰り返しだった。
◆竹細工のように
そんな頃、いつもの厳しい訓練中に、母が私をねじ伏せている現場を、偶然に通りかかった祖母(母の母親)が目撃した。母のすごい形相を見て、祖母は泣きながら母を諌めようとした。
「あんたの手はなあ……、堅すぎるんじゃ。竹細工でもなあ、乱暴にやりゃあぽきんと折れるじゃろう。ゆるりゆるりと、しなる竹をやさしゅうに曲げんにゃあいかん」
母は、今亡き祖母のこのセリフを思い出して口にするたびに、うっすらと涙ぐむ。
そう、母の思い描くイメージに沿わせるように、私の体に介入してくる母の手は、堅かった。切る感じ、押す感じ、弾く感じのする手だった。それは、私の体から発せられる情報を拾ってくれる手ではなかった。健常な動き、というイメージから流れ出してくる情報やエネルギーのようなものは、母の手を伝って私の体に流れてくる。そこには、「目指すべきイメージ→母の手→私の体」という一方通行の情報の流れがあって、下流にある私の体は今にも折れそうになっていた。
しかし、これは最近になって母から聞いたことなのだが、「そんなに厳しくしなくってもいいじゃない」という周囲のセリフと、「あなたがこの子をなんとかしなさい」という周囲の暗黙のメッセージの間で、当時の母自身も折れそうになっていたそうだ。そして、折れそうになるたびに、「自分が折れてしまったら、この子は誰からも見捨てられてしまう。どうか神様、私が折れないように見守っていてください」と、祈り続ける日々だったという。だからあの日の母は、諌める祖母のセリフに一瞬ひるみながらも、それを振り払って訓練を続けたのだ。
そういう意味では、母が唯一の加害者というわけではない。「健常な動き」「子どものために尽くす母」という規範的なイメージこそが、最上流に位置する加害者なのだ。規範的なイメージは、大人同士の相互監視によって維持されており、すべてはそこから流れ出す。つまり、「イメージ→母→母の手→私の体」という一方通行の情報やエネルギーの流れがあって、母自身もイメージから監視され、折れそうになっていたのである。
それにしても、祖母が使った竹細工のメタファーは、含蓄に富んでいる。竹細工を作るときには、あらかじめ「こんな作品を作ろう」という大まかなイメージがあるのは確かだろう。しかし素人のように、一足飛びにイメージ通りの形にしようと竹に無理な力を加えてしまうと、ぽきんと折れてしまう。竹のしなりや軋みを情報として受け止めながら、いたわるように力を加えていかなくてはならない。つまり、情報が「イメージ→手→竹」の一方通行に流れるのではなくて、「手⇔竹」のように相互に情報をやり取りしあいながら形を作っていかなくてはならないのだ。
その結果できあがる最終的な竹細工の形というものは、最初のイメージとは異なるものになる。しかし、それでよいのだ。確固たるイメージが最初からあるのではなく、「手⇔竹」という、手と竹の相互の情報のやり取りによって、想像していなかった新たな形=イメージが事後的に生み出されるのである。
◆監視され逆流する水
「こうあるべし」という確固たるイメージが現場を支配し、そこで監視される人々に軋みが生じるという構図は、かつての北病院にもあった。その当時の状況を、本書では次のように述べる。
しかし時に患者は、そのこもったグルグルのエネルギーを水にではなく、スタッフへと向け、こぶしを振り上げる。なぜならスタッフから、エネルギーを水へ向けてはならぬと脅されたからだ。しかし、「スタッフ→患者→水」という水路の方向に逆らったこの行為は、すぐさま患者自身に後悔と怯えの念を引き起こす。飲水する患者を制止しようとして、患者に殴られたスタッフによる記述を、本書から引用しよう。
一方では、スタッフの側も監視されているともいえる。
ここまで書いて誌面がつきてしまった。まだ書き足りなかったところがたくさんあるのだが、ここで筆を置くことにする。ここからいかに北病院が「安全に、おいしく水を飲んでもらえる病院」へと転身したかに興味をもった方はぜひ本を読んでみてほしい。きっとこの本は、多飲症ケアに直接関係ない人が読んでも、自らの臨床や日々の暮らしを振り返るきっかけになることと思う。
(『精神看護』第13巻 第4号,2010年7月,医学書院,111-118ページ掲載)
多飲症・水中毒ケアについてすべてを網羅した決定版 (雑誌『看護管理』より)
書評者: 橋本 茂 (四国大学看護学部看護学科精神看護学准教授/前徳島大学医学部附属病院副看護部長)
◆最もやっかいで,有効なケアができない無力感
「多飲症・水中毒」ケアは,精神科看護において最も厄介な対象の一つといっても過言ではないでしょう。
振り返ると,私は「多飲症・水中毒」について有効な看護ケアを実践したという経験は正直なところありません。私の場合,むしろ戦いでした。少しでもよいケアを提供したいと,専門書や研究文献を探してもそのほとんどが事例報告の類であり,根拠のあるケアを示したものはなかったように思います。このような状況ですから,いつも手探りの状態でした。そして,結果も“水との物理的隔離”と“対症療法”となり,看護ケアを提供したとは言い難く,最後には,屈辱と無力感ばかりが残るという有り様でした。
本書を手にとったとき,ほんとうに有効な実践書なのだろうかと半信半疑でした。また,「待ってました,決定版!」と帯にありましたが,少し大げさではないかというのが,正直な気持ちでした。それほど「多飲症・水中毒」ケアは難しいものであると考えていたからです。
◆これからのケアの標準に
ところが,読み込んでいくうちに,タイトルどおりの“決定版”と呼べるのではないかと思いました。なぜなら,現場で今すぐ,本書を活用したいという強い思いに駆られたからです。それほど衝撃的な内容でした。それまでの難しい問題に対する模範解答のような手引書であり,専門書といえる内容でありました。
第1部では,誰もが疑問に思う事柄が,Q&Aという形でしかも患者・家族も含めて理解できる内容となっています。
第2部では実践編として看護の実際を根拠に基づいて説明されています。第3部では知識編として医学的なしかもかなり高度な内容について述べられています。第4部では資料編として実際のプログラムを示されています。
本書が,水との物理的隔離つまり行動制限と対症療法という手段に頼りがちなケアを根本から変える「多飲症・水中毒」ケアの概念を変える1冊であると自信をもって勧めることができます。そして,全国の「多飲症・水中毒」ケアに携わる看護者にとって実際に活用できる内容であり,今後「多飲症・水中毒」ケアのスタンダードとなりえます。そして,何よりも「多飲症・水中毒」で苦しむ患者・家族にとってはQOLの大幅な向上が期待できます。
本書はこれからの「多飲症・水中毒」ケアの標準となるばかりでなく,これをもとに,研究が格段と進む予感がします。その意味でも本書の意義は非常に大きなものがあると考えます。著者である川上宏人先生,松浦好徳看護師長,山梨県立北病院の皆さんが「多飲症・水中毒」ケアに挑戦されたこと,ほんとうに素晴らしいと思います。
(『看護管理』2011年1月号掲載)
精神科勤務経験がなくても、「多飲症・水中毒」患者への「かかわり」がわかる本 (雑誌『看護学雑誌』より)
書評者: 藤野 智子 (聖マリアンナ医科大学病院 急性・重症患者看護専門看護師 集中ケア認定看護師)
「多飲症・水中毒」と聞いて、なにを考えるだろうか?
筆者は、救命救急センターで多くの水中毒の患者と接してきた。救急領域で遭遇する水中毒の患者は、意識障害を主訴として来院することが多く、血液データでは電解質異常を示す。数日間の輸液管理を受けて元気に退院、もしくは精神科病棟へ転棟していく姿は、救急領域で見る独特の光景かもしれない。
◆「多飲症」は特殊な病態ではない
本書のはじめに「推薦のことば」がある。この書籍の編者が所属する山梨県立北病院院長の藤井康男先生の「ことば」を読んでいて驚きを感じた。藤井先生は、「水中毒」を最初に診断した医師であり、かつその時期が1983年と、今からたった30年弱前であることも記述されていたからだ。そして、本書にも「多飲症は長期入院中の患者のうち20%前後に起こる(de Leon 1994)」(p26)、「多飲症患者の60~80%は統合失調症であるといわれています」(p29)と記述されているように、多くの患者が存在するであろう状況を、この30年弱の間に発見して、試行錯誤のうえに治療過程や看護展開を開発してきたことに敬服する。
前述のように、多飲症が慢性の統合失調症患者に多いとなると、精神科医療でも特別な病態と思われがちだが、感情障害や精神発達遅滞、脳炎後や頭部外傷後などの器質的な脳疾患、神経性食思不振、人格障害、認知症の患者などでも認められている(p11)ことから、決して特殊な病態ではないという理解が重要である。
◆読者が読みやすい個性的な構成
本書はユニークな構成となっている。筆者は精神科領域で働いたことはないが、とても読みやすい構成だった。臨床現場で患者と直に接する多くの読者にとっても同様だろう。
全体は4部構成になっており、第1部は25のQ&Aから始まる。一般的に、Q&Aは後付けの場合が多い印象があったが、はじめにQ&Aが入っていることで、とても読みやすくなっている。またAnswer部分には、しっかりとエビデンスや文献も盛り込まれているので、ここだけでも十分に学習できる。
第2部「実践編」では、1988年、松田源一医師の多飲症疫学研究を機に開始した、山梨市立北病院での多飲症患者への「かかわり」が記述されている。はじめは試行錯誤だったこと、隔離と開放の繰り返しだったこと、そこから対策チームが発足し、チーム一丸となって専門病棟ができあがっていったその足あとが克明に示されていた。はじめからうまくいっていたわけではなく、同じ志のもとにチームが結束し、スタッフ個々の意識が変わっていった結果、チーム全体の意思が統一されていったことが読み取れる。現在、同じように取り組んでいる方には、なんとも心強い内容ではないだろうか。そして、チーム医療が注目される現在では、見習うべき内容が数多く記述されていると痛感した。
◆多飲症専門病棟で働く看護師が築き上げた「かかわり」
第3~4部では、「知識編」「資料編」として文献レビューや編者の施設で使用している重症度分類などが示されている。多くの書籍では、この知識編がはじめに記述されているが、第3部に挿入しているのには深い意味があるのだろう。読者対象が看護師と限定されているわけではないだろうが、看護師が読みやすい入り口としたこと、病態ありきで対処するのではなく、「患者個々の声を聞く」というスタンス、「統一したかかわり」が必要であることを強調したいという意図が込められていると推測した。
この「かかわり」という言葉からも、編者たちの思いいれを感じる。山梨県立北病院では、患者への対応技術を「かかわり」と呼んでいる。この言葉には、「かかわり」は多飲症専門病棟で働く看護師が試行錯誤の末に築き上げたものであるという“誇り”が含まれているのだ。同じ看護師として、このように胸を張って自分たちの成果、誇りといえるほどがんばった努力に拍手を送りつつ、筆者らもがんばらねばと勇気をもらったような気持ちになる。
本書によって救急医療から見ていた水中毒の患者への看護とは違った角度から学ぶことができた。また、この書籍の表紙は、まさに「水」のしずくを綺麗な水色を使って表している。内容と同じく、とても分かりやすい。そして、「多飲症・水中毒」に特化した書籍はとても珍しく、目を引く。ぜひ、精神科領域のみならず、救急領域の看護師にも読んでもらいたい一冊である。
(『看護学雑誌』2010年7月号掲載)
優れて実践的で崇高な理念─精神科看護の最良部分
書評者: 黒木 俊秀 (肥前精神医療センター・精神科医)
わが国の精神科病棟において「水中毒」は厄介な症状として知られてきた。主に荒廃した慢性統合失調症の患者にみられる。「中毒」と呼ぶのは,あたかも「アルコール中毒(渇酒症)」のように,患者が水道栓の蛇口に口をつけて,あおるように水をがぶ飲みするからである。そのため,1日のうちに5~6kgもの体重増加を生じることがある。
患者の中には,けいれん発作や意識障害を起こす者もいる。採血すると著しい低ナトリウム血症が認められる。当然,飲水制限を行うが,患者はひどく抵抗し,隠れ飲みも減らない。仕方なしに保護室に隔離すると,患者はさらにいらだち,看護スタッフに怒りや敵意をあらわにする。保護室内のトイレの汚水まで飲もうとする患者さえおり,身体拘束まで考慮せざるを得なくなる。以上のように,「水中毒」は一見単純でありながら,ケアする側をはなはだ悩ませる。
こうした「水中毒」に対して,山梨県立北病院の医師と看護スタッフがまことに明快な治療と管理の指針を示したのが本書である。決定版と称してよいのではないだろうか。
第1部「多飲症・水中毒についてのQ&A」の冒頭において,著者らは「多飲症と水中毒は,はっきりと違うものとして考えるべき」とズバリ指摘する。すなわち,「多飲症=水中毒」という誤解が,その治療は「飲水制限」と決め込むあまり,患者の日常生活能力を過剰に管理してしまい,本来改善すべき不適切な飲水行動については無策のまま,セルフケア能力全体の劣化を招いてしまうのである。目標とすべきは,多飲症という行動 の改善であり,それができれば,水中毒は起きないという。
以下,多飲症と水中毒のそれぞれの重症度分類に応じた治療指針を示すとともに,「身体拘束は避けるべき」,「多飲症患者がオープンに飲水できる環境を作ることがよい」,「多飲症は飲水量のみで決めるべきではない(ベース体重の設定が重要)」等々,目から鱗が落ちるような提言が並ぶ。
続く,第2部「実践編」は看護スタッフによる多飲症患者への「かかわり」の報告であり,その具体的なケア方法の詳細を明らかにしている。コラム欄では,たった1杯のコーヒーを飲ませるかどうかで患者も看護師もともに傷ついた心痛む経験なども語られる。「かかわり」というキーワードを通して,わが国の精神科看護の最良の部分に触れる思いがする。多飲症の心理教育と家族教育はこれまで報告が少なかったが,巻末の心理教育用テキストをすぐに活用することができよう。
精神科医の川上宏人氏が執筆した第3部「知識編」は,多飲症・水中毒の病態と治療に関する精神医学の知見を網羅し,第1部をさらに詳しく解説したものである。結論として,多飲症の原因も治療も1つに特定することはできないが,その治療目標は,患者が「最も幸せに生活できる場所で,その人なりのケア能力に合った方法で自らの飲水行動をコントロールできれば」よしとする川上氏の臨床医としての見識に敬意を表したい。
著者らが掲げる「開放的処遇により人間的接触を多くする」という理念は,多飲症のみならず,喫煙やメタボリック症候群などの多くの問題行動を認める今日の重症精神障害者に対する「かかわり」にも普遍化し得るのではないだろうか。その意味で,本書は優れて実践の書であるとともに,崇高な理念の書でもある。
3部構成で紐解く,よりよい援助者のための画期的な良書 (雑誌『看護教育』より)
書評者: 岩井 眞弓 (熊本保健科学大学保健科学部看護学科)
家族や医療者は,患者が水道の蛇口から貪るように水を求める姿に「どうしてあんなに?」と心を痛めその安全を願いつつ,考えあぐねてきた。ここに,『多飲症・水中毒』という症状に苦しむ人々に向け,山梨県立北病院の精神医療スタッフによるケアの集大成が一冊の本にまとめられた。本書を読み終え確信したことは,人々は,自分で自分をコントロールしながら社会生活を送っていること,そして,日常の生活のなかで飲食ほどその人の意思によって量質ともにコントロール可能なものはないということである。
数年前,私は学生と精神看護の実習に臨んだ。その時出会った50歳代の女性は,娘が嫁いだ後,統合失調症の治療を受け,数年後水を飲み始めた。過剰な飲水が目立ち始めたのは一人家に残してきた夫が癌で手術を受けなければならない事態を知ってからであった。学生は日々の関わりのなかで何もできない自分に苛まれていたが,その女性が幻覚や妄想に苦しみ,夫に対する妻としての苦悩をも持ち合わせていることに気づいた。その後,朝は検温の後女性が告げる体重と前日の夥しい飲水量を淡々と記録し,ベッドを整え身支度や洗面をつかず離れず見守った。しばらくして,午後の治療がないときには趣味の絵画や全身マッサージを楽しみに娘のような学生を探す女性の姿があった。いつの間にか飲水量は減っていた。過剰な飲水という現象を是正するために患者の飲水行動をコントロールしようとしていた自分に気づいたこの学生は,現象の意味を日々のケアのなかから患者とともに探り当てていったのである。しかし,私は,その後再会した女性が個室の布団のなかでうずくまる日々を過ごしていたことを知り落胆した。今思えば,このとき本書のような良書に出会えていればと悔いが残る。
さて読者は,本書が他の多くの専門書とは全く逆の構成をもっていることに気づくであろう。第1部ではQ&Aとして,山梨県立北病院という一地域の中核病院から発信された書物でありながらも,臨床現場のどこにでもありうる疑問に的確に回答し読者を引き込む。第2部では実践編として,1980年以降の北病院治療史が述べられ,医療スタッフの意識改革が多飲症の改善につながった事実がコラムに語られ読者の多くが持つ体験と重なる。そして,多飲症患者教育および家族教室の必要性を2006年以降の実践を基に述べている。第3部では知識編として,これまで述べてきた内容と研究データを基に,あらためて『多飲症と水中毒』の原因および診断基準と重症度分類を疫学的に述べ,国内外の文献レビューを基に今後の治療の方向性に結びつけて紹介している。理論としては分かっていても具体的な表現がよりよい援助に結びつかず苦慮している医療スタッフ必読の一冊である。
(『看護教育』2010年7月号掲載)
やっと出た,多飲症ケアのスタンダード
書評者: 阪内 英世 (鶴が丘ガーデンホスピタル看護部長)
多飲症の患者ケアは,これまで隔離室で飲水を制限するか,監視ともいえるような観察体制で水中毒を予防するかのどちらかであった。これは看護師にとっては,その膨大な労力の割に無力感を強く感じさせるものであり,患者には不自由さと苦痛を与えるだけのものである。
しかし本書では,山梨県立北病院のスタッフが,それまでと異なる新しい多飲症患者の対応を紹介しており,行き詰まった患者ケアに希望をもたらすものとなっている。
本書の特筆すべき点をいくつかご紹介する。
まず第1に病気への理解を深めるため,病態としての多飲症,病状である水中毒がまったく別のものであることを明確に打ち出している点である。この2つを明確に分けて定義することにより,過剰な制限の必要性が否定され,多飲症患者のセルフケア能力に着目ができ,能力向上のための看護ケアが構築されるようになっている。
第2に膨大な臨床経験と実績に基づきスタンダードケアが確立されているということが挙げられる。今まで多飲症患者の臨床報告はその事例のみにあてはまる単発的なものが多く,このようにケアを行ったら予測される結果になったという報告型のものが多い。それに比べて県立北病院では,「この結果になったのは,ケアのこの部分が有効,または無効であったから」という検証型の報告になっているためその内容の信頼性が極めて高い。ましてやチームの意識や家族教育など,多飲症予防の側面にまで触れた報告は今までに無かったものである。
第3にハードウエアに依存しないという基本姿勢をとっている点が挙げられる。山梨県立北病院は多飲症治療専門病棟を持っている数少ない病院の一つであるが,その建物の構造を基盤としてケアが展開されていたなら,そのケアはほかの病院では使えないということになる。ハードに頼った飲水制限から「安全に水を飲んでもらう」ためのかかわりに切り替えていったからこそ,本書はすべての病院で使われ,参考にされる内容になっている。
第4は常に患者中心の視点で書かれているということである。われわれはともすると,多飲水の患者を受け持つのはつらい,やりがいがないなどの理由から,看護師が苦しくならないための多飲水患者のケアを確立しがちであり,安全重視の飲水量チェック,体重チェックや尿比重チェックなどにどうしても視点がいってしまう。これらは多飲水の傾向を見つけ水中毒を起こさないために行う対症的な方法ではあるが,多飲水を改善するためのケアではない。やはり患者中心であるならば,本書に書かれているように多飲症を引き起こす要因に対してのケアが充足されるべきである。
以上本書の特徴について述べてきたが,このほかにもリミット体重の算出方法,水中毒の治療,患者教育のテキストなど,参考になるものが多く掲載されている。
多飲症患者の対応を考える際や見直す際には,ぜひ一読いただきたい書籍である。
精神科治療者の真摯な姿勢を示す良書
書評者: 穴水 幸子 (慶大精神神経科)
水のような本である。『多飲症・水中毒-ケアと治療の新機軸』という題名の通り,至極当然のように水と身体のかかわりのことが書かれた本なのではあるが。ブルーと白の2色のシンプルな美しい装丁で飾られ,さっぱりとした筆致で書かれて大層読みやすい。しかし読者はその美しさに惑わされ,ふわりと読み流してしまってはいけない。この本には,多飲症に罹患した人々が示す,水への飽くなき要求と依存,あるいはその経過中におとずれる激しい消化器症状,失禁,低ナトリウム血症,神経症状,意識障害,けいれん発作,昏睡という身体症状が描かれている。本書は疾病に真正面から向かい合うタフでハードな治療記録でもある。
水中毒は精神科臨床医療では治療のなかで,身体管理上,もっとも苦慮する病態のひとつである。本書を紐説くと,ひとの身体における水の在り方をあらためて意識させられる。
第1部「多飲症・水中毒についてのQ&A」,第2部「実践編」,第3部「知識編」と3部構成になっており,水中毒の疾患を治療した経験のない医師やスタッフや医学生にも理解しやすい。たとえば,知識編にある人体と水のバランス,ヒトの体重の約60%が水分であり,さらにそのうちの3分の2が細胞内液で,3分の1が細胞外液である。そしてこの水分バランスを一定に保つために,浸透圧受容体と圧受容体の変化は神経伝達を介してモニターされ,随時調整が行われている。あらためてヒトの身体における水との切っても切れない睦まじい関係性をみるようなこころもちがする。しかし,いったんこの睦まじさが壊れたとき,水中毒という特殊な病態を呈するのである。
編者である川上宏人医師と松浦好徳看護師長らが勤務する山梨県立北病院以外でも,慢性期の統合失調症入院患者さんたちを治療している精神科病院においては,高い頻度で水中毒患者に遭遇する。深刻な水中毒の症状にスタッフはあわてふためき,「どう症状に対応し,介入し,治療していけばよいのか」と難渋するところである。編者らも水中毒治療に葛藤した時期もあったであろうと推察される。なにせ治療者が「水を飲むと倒れるぞ,飲み過ぎるな」と真剣に患者に諭し,水から脅迫的に遠ざけようとすればするほど,そうした人は水を求めるものだから。
編者らの山梨県立北病院では,患者らが看護室で水を飲むこと(申告飲水)を第一義的に重要な行動変容ととらえ,多少水を多く飲んでしまっても,見えないところで水を飲む(隠れ飲水)より病態経過は好転しているととらえている。治療における信頼関係がなによりも大切という視点をもつ。そして患者への心理教育,多飲症家族教室を地道に積み重ねる。さらに多飲症専門病棟までをも構築し,多飲症・水中毒という複雑な病態に向かいあう。このような精神科治療者の真摯な姿勢を示し得たことこそが,水の如き清楚な様態をもつ本書の最も本質的な美点である。
アルコール依存,薬物依存,摂食障害,また自身を傷つけるほど他者の愛情を惜しみなく求める人格障害など,ヒトの渇望と依存性から生まれるさまざまな精神疾患の治療書,指南書は世にあまたと存在する。しかし,水中毒という特殊な疾病において新たにこのような良書が生まれたのは初であり,その点が大変喜ばしい。
荘子いわく「君子の交わりは淡きこと水の如し」である。水中毒をふくめた依存性・中毒疾患をもつ患者と治療者間には,まずは穏やかな協力的潮流を作りあげていきたい。患者と治療者は,依存物質抑止のみを目的とした「水と油」の関係に決して陥ってはいけない。
命の危険の“前”と“あと”を考える
書評者: 阪本 奈美子 (国立病院機構東京医療センター救命救急センター・医師)
臨床医として仕事を始めて,もう10年以上になる。いろいろなことを,それなりにわかっていたつもりだった。しかし,本当は何もわかっていなかった。何かにガツンと頭をたたかれた,そんな一冊だ。
タイトルを見ると,専門書に思われた。あるいは教科書かとも。しかし,そうだとしても常識を覆す構成である。普通だったら,定義や解説から始まるだろう。本書はなんと「Q&A」から始まる。意外であったが,「なんとなく」知っている多飲症や水中毒に対する抵抗感が一気になくなったのは事実である。そしてのめりこんでいく自分に気づいた。平易な文章でつづられているため,入り込みやすい。それでいて内容の深さにどんどんとはまりつつ進んでいくのである。
読み進めていくうち,まず知ったのは自分の「無知」であった。私は水中毒を知っていたのではなく,低ナトリウム血症に伴うけいれんや意識障害の治療に当たっていただけであった。低ナトリウム血症を呈してけいれんを起こすような状態で患者さんが救急車で運ばれてくると,背景に精神疾患があり,飲水を制限できなかったゆえに「水中毒」に陥ったのだろう,という程度に考えていた。その状態,つまり命が危険な状態になる“前”のことや,そして元の鞘に収まった“あと”のことを気にかけたことはなかった。単に私は全身管理を行いながらけいれんを抑え,教科書通りのナトリウム補正をして,状態が安定したら,退院あるいは精神科依頼をして自分の手を離す,ということをやっていたのだ。そのことに思い至った。
Q&Aに続く第2部では,山梨県立北病院が水を安全に飲んでもらえるようになるまでの苦難の歴史が,さまざまなエピソードとともにつづられている。ふと気づくとコラムの「たった1杯の攻防」に目頭が熱くなっていた。誰だって(少なくとも私は)思い通りにならない患者の立ち居振る舞いに,陰性感情を抱いてしまう。「患者の飲水行動のみにとらわれ,その患者の人間性を尊重していない,スタッフ中心の看護であった」と反省の一文に象徴されるように,全身状態を悪化させる飲水行動を阻止することばかりにとらわれ,なぜ飲水するのかを考えていなかった。「飲みたい」という気持ちを受け入れ理解を示すことから始まる意識改革のくだりは,その行間に著者らの語りつくせぬ思いが詰まっているに違いない。
そして第3部ではその病因や合併症などが丁寧に解説されている。この一冊が出来上がるためには,実際には書かれていないものの,多くの汗と涙が流されたことだろう。そんな苦労をしてまでもやらなければいけないのか,と思われるかもしれないが,豊富な経験と膨大な文献資料に裏打ちされていたからこそ,越えられた山なのかもしれないと感じた。この本は,多飲症治療のマニュアルではない。「知る」ことだけではなく,何より大切な「考える」ことも教えてくれる本だ。
まあ,そこまで重くとらえないまでも,まずは手にとってページをめくってもらいたい。表紙のさわやかさもさることながら,その装丁の妙に気づくであろう。部ごとにはそれぞれ「水」にかかわる写真があり,ページ左下の欄外のランニングタイトルには蛇口が描かれている。心憎い演出が,やわらかな文体の奥に秘められた著者らの細やかな心配りと重なり,それに気づいた自分にほくそ笑んだものである。
確かに,多飲症・水中毒について詳しく述べられた書であるが,その向こうには普遍的な,患者と医師の関係,患者とナーススタッフとの関係,また医療スタッフ間の関係の持ち方が示されている。患者さんは何を思い,何を望んでいるのか。日々の診療の中で,病気だけをみてしまい,患者さんの気持ちや家族の思いを置き去りにしてしまってはいないだろうか。「流して」しまっていないだろうか。患者さんは一人ひとり顔も違うように考え方や感じ方が異なる。私でもできる小さなこと,「今日はお加減いかがですか?」そんなひと言から始めてみようと思う。
書評者: 熊谷 晋一郎 (東京大学先端科学技術研究センター)
私は、今年で9年目になる小児科医である。出産時のトラブルによる後遺症で、脳性まひになった。それ以来、電動車いすに乗って生活をしている。トイレや、入浴、掃除洗濯など、身の回りのことの多くは一人ではできないため、ヘルパーさんなどに手伝ってもらいながら、生活を回している。
私には、精神科の臨床経験はない。だから、この本に書いてあるような精神科病棟の現場の厳しさを知らない。しかし、この本を読んでいくうちに、多飲症をめぐってのあれこれや、それに対する山梨県立北病院(北病院)の取り組みに対して、他人事ではない何かを感じた。
多飲症とは、水を飲むことがどうしてもやめられなくなり、日常生活にも支障をきたした状態のことだ。精神科では決して珍しいものではなく、長期入院中の患者の20%前後に起こるともいわれている。水といってもあなどれない。急激・多量な飲水をすれば水中毒へと進み、死にいたる危険もあるのだ。しかし、これまで多飲症に対してはっきりと治療方針が打ち立てられることはなかった。
看護師が患者の飲水をこまかく監視、管理しようとしても、なかなか患者の病状の改善には結びつかない。それどころか、飲水管理をめぐって暴力沙汰になることすらある。看護師の多くは、いつ水中毒が起こるかわからないという不安や、管理の努力が徒労に終わる無力感、自責感を抱きやすくなり、ひいては荒れる患者と何もしない医師を憎むようになる。一方、医師は、全くよくならない患者や看護師の対応を憎み、患者はしつこい看護師や自分を閉じ込める医師を憎む、という最悪の相互不信に陥ってしまうこともあるという。それに、飲水制限を徹底するためにやむなく行われる個室施錠や保護室隔離は長期にわたるため、病院として救急・急性期患者が受け入れられないという病棟運営上の支障も出てくる。
このように、多飲症という病態は、精神医療の現場を崩壊させうる大きな問題になっている。
◆心臓病の中学生にも水問題
過剰な監視が、かえって患者の様態を悪くするという経験は、私にも何度かある。その中でも特に印象に残っているのは、ある心臓病の中学生を担当した時のエピソードだ。
私はかつて一年間ほど、小児心臓病の専門病棟で働いていた。そこに入院してくる多くの子どもたちは、心臓が十分に動かなくなる、「心不全」と呼ばれる病態を患っていた。
心不全が起きると、全身にくまなく血液をいきわたらせるために必要な、高い血圧を維持できなくなる。それを補うために、レニン・アンギオテンシン系というホルモンシステムが作動し、体の中に通常よりもたくさんの塩分や水をため込むようになる。十分に動かない心臓の代わりに塩分や水をかさ増しして、血圧を正常化するのだ。この段階ではまだ、「血圧低下→水貯留→血圧正常化」という具合に恒常性が維持されているから、ある程度状態は安定している。
しかし、心不全が進んで塩分や水の貯留がある《一線》を越えると、心臓がそれ以上拡張できなくなるほど膨らんでしまい、かえって血圧が落ちてくる。こうなってくると、「血圧低下→水貯留→さらなる血圧低下→さらなる水貯留→…」という悪循環に陥ってしまう。このとき、塩分・水を貯留させるレニン・アンギオテンシン系のホルモンは振り切れるほど放出されているのだが、じつはこのホルモン自体がただでさえ傷んでいる心臓の筋肉に、追い打ちをかけるようにダメージを与える毒性をもっており、心不全の進行を早めるのである。
だが、この《一線》がどこなのかを見極めるのはとても難しい。それはきっと、多飲症が水中毒へと至る一線を見極める難しさと、共通する部分があるだろう。難しいからこそ、臨床家は常に不安を感じており、血圧や、体重や、尿量を何度も測定する。当時の私も、一線を越えないように厳しく水分摂取を制限し、越えたと判断したら急いで利尿剤を投与していた。それは、徹底した監視と管理の空間だと言える。
その重症心不全の中学生を担当した時、私も不安でいっぱいだった。見た目はわりと元気そうな様子なのだが、超音波検査で心臓の動きを見てみると、通常なら、大きく、ゆったりと、しなやかに強く動いているはずの心臓が、まるで小刻みな悪寒のように、小さく震えている。それを見た瞬間、私は自分のみぞおちの部分にも、ぎゅうと縮こまるような痛みを感じた。「一線はかなり近い」と思ったのだ。
実際に血液検査をしてみると、水貯留の程度を表す数値が跳ね上がっている。「間違いない、ぎりぎりだ!」と信じきった私は、すぐに厳しい水分制限と、ベッド上の絶対安静を指示した。体重増加や尿量減少の兆候があれば、すぐに利尿剤を打った。
することもなく終日、ベッドの上で過ごさせられる中学生のイライラは募る。口の渇きを紛らわすために、氷を長々と口の中で転がしながら、ふてくされた表情をしてヘッドフォンで音楽を聴いている。私はベッドサイドに行くたびに、彼から発せられるそのイライラを肌身にヒリヒリと感じ、申し訳なさを感じつつも、それをうまく受け止められなかった。私の目下の関心は、彼の今日の体重と、ここ数時間の尿量と、血圧と、心臓の動きと、血液データにこそあったのだ。私は、「実は彼の検査データにこそ興味がある」ということを彼に悟られないように、「何の音楽聴いてるの?」などと空虚な言葉を発する。一瞥をくれた後、彼は無視をする。私は黙って採血をし、ベッドから離れる。
厳しい管理を2週間くらい続けても、容態はよくなるどころかむしろ悪くなっていった。心臓の動きも相変わらずだし、利尿剤を打つ回数は増えていく。血液データも、わずかではあるが徐々に悪くなっていく。私は治療方針を見失った。「もはや、ペースメーカーの装着か、移植しかないのか」とさえ思うようになった。
◆監視からほどかれた心臓
同じ頃、彼のストレスも限界に達した。そして、外泊がしたいと言ってきた。私は、このような状態で外泊をするなんてとても無理だろうと思った。しかし、その時の私の上司は、なんと彼の外泊を認めたのである。私は上司の思惑が読めず、ますます混乱した。「大丈夫なんでしょうか」と上司に聞いても、「それはやってみないとわからない。ただ、入院する前まではそれなりに元気にやってたわけだし」という釈然としない返事を返してくる。
上司は、患者を見捨てたのだろうか? もしくは、危ない賭けに出たのだろうか? それとも、私にはない、経験的なカン、みたいなものがあったのだろうか? それはわからない。しかし、現在の治療方針が煮詰まっていることも、中学生のストレスが限界に達していることも、いまや明らかだったから、外泊することになった。
ところが信じられないことに、外泊から戻ってきた彼は、見違えるように元気になっていたのである。外泊中の様子をご両親に聞いてみると、なんと野球の素振りの練習をしたり、映画を見に行ったり、好きなものを食べたりと、自由で活動的な生活をしていたという。検査データも驚くほどの改善傾向を示しており、心臓の動きもよくなっていた。そして、ほどなく彼は退院していった。
入院中の彼は、基本的にとても「いい子」だった。入院中のほかの子どものなかには、自分のカルテを引きちぎったり、スタッフに罵声を浴びせたりする子もいる。彼は、むしろいい子であるがゆえに、監視・管理されるストレスを外へと放出する代わりに、内へ内へとため込んでしまうようなところがあったように思う。本書にも、ストレスがレニン・アンギオテンシン系、ひいては口渇感を引き起こすということが書いてあるが、私はこの経験を通して身をもって、監視されるストレスというものが、いかに人の心身を追い詰めていくかを知った。監視されて身動きがとれなくなっていた心臓は、自由を得て、力強く動き始めたのである。
◆「グルグル」と「爆発」のサイクル
北病院の実践も、当初から順風満帆なわけではなかったようだ。専門病棟での取り組みが始まったばかりの頃の状況が、本書には以下のように記載されている。
隔離された患者の多くは施錠されている間は満足する量の水が飲めないために、開放処遇になると「今しかない」とばかりに飲水行動に走り、一気に大量飲水をしていました。そのために、再び隔離対応を受けるという「隔離→開放→隔離……」という悪循環が続いていました。(p.56)また、隔離期間が長くなることによる弊害についても述べられている。
隔離されればスタッフを含め、他者との接触が極めて少なくなります。長期にわたる隔離は、患者の精神症状を悪化させ、ADLの低下を招きます。それまでできていた挨拶や基本的な会話もできなくなり、身につけていた生活行動も失われます。そして終日ベッドに臥床して過ごし、周囲への関心が乏しい患者が生まれていきました。(p.56)隔離中の、「世界とのつながりが絶たれ、自分自身と向き合うほかにすることもない生活」と、開放された後の、水に向けられる「爆発的・衝動的・短期的な消費行動」とが延々と繰り返される日々──。私にもかつて、同じような経験がある。
私は、物心ついたころから十代の半ばぐらいまで、毎日濃厚なリハビリを受けていた。そのリハビリというのは、「私の動きを、すこしでも健常な動きのイメージに近づけること」を目標にして行われた。私は、主に母親から、座り方やずりばいの仕方、お茶わんや鉛筆の持ち方など、日常生活の一挙手一投足を監視され続け、イメージから外れると厳しく修正された。
また、座位や膝立ち、片膝立ち、立位などの健常な姿勢パターンをなぞらせる訓練を、1回1時間半、1日に3回程度行っていた。母親は訓練中、しばしば激情的になって、イメージ通りにうまく動かない私に厳しく接した。エスカレートしたときには、バットでつつかれたりもして、文字どおりのスパルタだった。私は訓練中、懸命に、これまで見聞きしてきた健常な運動イメージを想起させながら、私自身が繰り出す運動を自己監視し続ける。
しかし、イメージを意識して監視すればするほど、私の体は緊張を強め、かえってイメージから外れた運動を繰り出してしまう。イメージと運動のギャップ→焦り→体の緊張→さらなるギャップ→さらなる焦り→…という悪循環によって、私は立ちすくんでしまい、運動が出せなくなる。そして、「自分を監視する自分を監視する自分を監視する……」というグルグルとした無限回路が、私の中に重く沈澱し、膨れ上がっていくのだ。
訓練が終わると、食事の時間だ。私は、我を忘れて食べた。食べている間は、グルグルを振り払うことができた。監視によってあらゆる運動をせき止められ、出口を失ったグルグルのエネルギーを、「食べる」という行為で発散している感覚だ。それは、怒りとも、喜びともつかない忘我の恍惚。きっと、多飲症の人が水を飲み続ける時というのは、同じような状態なんじゃないだろうか、と思う。食事中に茶碗の持ち方などを注意されると無性にイライラとし、ある時などは怒って茶碗をわざとひっくり返した。それに怒った父親が、私を抱えて暗い部屋にほおり投げ、私はそこで悔しさのあまり、大声で何時間も泣き続けた。
爆発的な過食をした後というのは、一気に正気に戻る。そして、またあの自己監視のグルグルが舞い戻ってくる。「みっともなく食べ散らかし、ぶくぶくと肥っていく自分」を責める自分が生まれるのだ。そしてそのグルグルが再び一線を越えると、今度は食べた物を残らず吐き出し始めるのである。
これが私の経験した過食嘔吐だ。私にとっての過食嘔吐は、自己を監視し続ける無限の「グルグル」と、それを衝動的な行動に転化する「爆発」の繰り返しだった。
◆竹細工のように
そんな頃、いつもの厳しい訓練中に、母が私をねじ伏せている現場を、偶然に通りかかった祖母(母の母親)が目撃した。母のすごい形相を見て、祖母は泣きながら母を諌めようとした。
「あんたの手はなあ……、堅すぎるんじゃ。竹細工でもなあ、乱暴にやりゃあぽきんと折れるじゃろう。ゆるりゆるりと、しなる竹をやさしゅうに曲げんにゃあいかん」
母は、今亡き祖母のこのセリフを思い出して口にするたびに、うっすらと涙ぐむ。
そう、母の思い描くイメージに沿わせるように、私の体に介入してくる母の手は、堅かった。切る感じ、押す感じ、弾く感じのする手だった。それは、私の体から発せられる情報を拾ってくれる手ではなかった。健常な動き、というイメージから流れ出してくる情報やエネルギーのようなものは、母の手を伝って私の体に流れてくる。そこには、「目指すべきイメージ→母の手→私の体」という一方通行の情報の流れがあって、下流にある私の体は今にも折れそうになっていた。
しかし、これは最近になって母から聞いたことなのだが、「そんなに厳しくしなくってもいいじゃない」という周囲のセリフと、「あなたがこの子をなんとかしなさい」という周囲の暗黙のメッセージの間で、当時の母自身も折れそうになっていたそうだ。そして、折れそうになるたびに、「自分が折れてしまったら、この子は誰からも見捨てられてしまう。どうか神様、私が折れないように見守っていてください」と、祈り続ける日々だったという。だからあの日の母は、諌める祖母のセリフに一瞬ひるみながらも、それを振り払って訓練を続けたのだ。
そういう意味では、母が唯一の加害者というわけではない。「健常な動き」「子どものために尽くす母」という規範的なイメージこそが、最上流に位置する加害者なのだ。規範的なイメージは、大人同士の相互監視によって維持されており、すべてはそこから流れ出す。つまり、「イメージ→母→母の手→私の体」という一方通行の情報やエネルギーの流れがあって、母自身もイメージから監視され、折れそうになっていたのである。
それにしても、祖母が使った竹細工のメタファーは、含蓄に富んでいる。竹細工を作るときには、あらかじめ「こんな作品を作ろう」という大まかなイメージがあるのは確かだろう。しかし素人のように、一足飛びにイメージ通りの形にしようと竹に無理な力を加えてしまうと、ぽきんと折れてしまう。竹のしなりや軋みを情報として受け止めながら、いたわるように力を加えていかなくてはならない。つまり、情報が「イメージ→手→竹」の一方通行に流れるのではなくて、「手⇔竹」のように相互に情報をやり取りしあいながら形を作っていかなくてはならないのだ。
その結果できあがる最終的な竹細工の形というものは、最初のイメージとは異なるものになる。しかし、それでよいのだ。確固たるイメージが最初からあるのではなく、「手⇔竹」という、手と竹の相互の情報のやり取りによって、想像していなかった新たな形=イメージが事後的に生み出されるのである。
◆監視され逆流する水
「こうあるべし」という確固たるイメージが現場を支配し、そこで監視される人々に軋みが生じるという構図は、かつての北病院にもあった。その当時の状況を、本書では次のように述べる。
過度に批判的な対応、かかわりを密接にもとうとしすぎること、患者との関係が深くないにもかかわらず指導的になりすぎること、杓子定規すぎる対応、厳しすぎるルールなど、医療者側に行き過ぎがあることも少なくありません。(P.35)スタッフからの絶え間ない監視を一身に受け続けた患者は、リハビリを受けていた頃の私と同じように、自己監視のグルグルを膨らませていったに違いない。そして私の過食と同様に、そのグルグルを爆発的な飲水行動へと転化していったのではなかろうか。このような時、「厳しい飲水管理」という規範イメージからほとばしり出る情報やエネルギーは、「イメージ→スタッフ→患者→水」へと流れていく。
しかし時に患者は、そのこもったグルグルのエネルギーを水にではなく、スタッフへと向け、こぶしを振り上げる。なぜならスタッフから、エネルギーを水へ向けてはならぬと脅されたからだ。しかし、「スタッフ→患者→水」という水路の方向に逆らったこの行為は、すぐさま患者自身に後悔と怯えの念を引き起こす。飲水する患者を制止しようとして、患者に殴られたスタッフによる記述を、本書から引用しよう。
悔しい上に、「ああっ、殴ってしまった。怒られる」というような怯えた表情でした。つい思わず殴ってしまったのでしょう。そのときの私は、殴られたのに申し訳ない気持ちでいっぱいでした。(P.64)こうして行き場を失った患者のエネルギーは、グルグルと患者自身へと向かうことになる。
一方では、スタッフの側も監視されているともいえる。
スタッフの意識のなかには、「多飲症専門病棟に入院させているのに、患者が水中毒を起こして倒れたりしたら困る」「私の勤務帯に体重が増えたら困る」など、保身ともとれる思いがありました。(P.63)スタッフ間で共有された規範イメージを維持するため、スタッフ同士も互いに監視しあっており、「規範から外れた行動を自分がしないように」とびくびくしているのだ。それは、私にリハビリをしていた母親自身も、社会の相互監視の中に置かれていたのと同じだろう。そして、スタッフ同士が相互監視というエネルギーの交換をすることによって、規範的なイメージは拡大再生産的に肥大化していくとも言えるのである。
ここまで書いて誌面がつきてしまった。まだ書き足りなかったところがたくさんあるのだが、ここで筆を置くことにする。ここからいかに北病院が「安全に、おいしく水を飲んでもらえる病院」へと転身したかに興味をもった方はぜひ本を読んでみてほしい。きっとこの本は、多飲症ケアに直接関係ない人が読んでも、自らの臨床や日々の暮らしを振り返るきっかけになることと思う。
(『精神看護』第13巻 第4号,2010年7月,医学書院,111-118ページ掲載)
多飲症・水中毒ケアについてすべてを網羅した決定版 (雑誌『看護管理』より)
書評者: 橋本 茂 (四国大学看護学部看護学科精神看護学准教授/前徳島大学医学部附属病院副看護部長)
◆最もやっかいで,有効なケアができない無力感
「多飲症・水中毒」ケアは,精神科看護において最も厄介な対象の一つといっても過言ではないでしょう。
振り返ると,私は「多飲症・水中毒」について有効な看護ケアを実践したという経験は正直なところありません。私の場合,むしろ戦いでした。少しでもよいケアを提供したいと,専門書や研究文献を探してもそのほとんどが事例報告の類であり,根拠のあるケアを示したものはなかったように思います。このような状況ですから,いつも手探りの状態でした。そして,結果も“水との物理的隔離”と“対症療法”となり,看護ケアを提供したとは言い難く,最後には,屈辱と無力感ばかりが残るという有り様でした。
本書を手にとったとき,ほんとうに有効な実践書なのだろうかと半信半疑でした。また,「待ってました,決定版!」と帯にありましたが,少し大げさではないかというのが,正直な気持ちでした。それほど「多飲症・水中毒」ケアは難しいものであると考えていたからです。
◆これからのケアの標準に
ところが,読み込んでいくうちに,タイトルどおりの“決定版”と呼べるのではないかと思いました。なぜなら,現場で今すぐ,本書を活用したいという強い思いに駆られたからです。それほど衝撃的な内容でした。それまでの難しい問題に対する模範解答のような手引書であり,専門書といえる内容でありました。
第1部では,誰もが疑問に思う事柄が,Q&Aという形でしかも患者・家族も含めて理解できる内容となっています。
第2部では実践編として看護の実際を根拠に基づいて説明されています。第3部では知識編として医学的なしかもかなり高度な内容について述べられています。第4部では資料編として実際のプログラムを示されています。
本書が,水との物理的隔離つまり行動制限と対症療法という手段に頼りがちなケアを根本から変える「多飲症・水中毒」ケアの概念を変える1冊であると自信をもって勧めることができます。そして,全国の「多飲症・水中毒」ケアに携わる看護者にとって実際に活用できる内容であり,今後「多飲症・水中毒」ケアのスタンダードとなりえます。そして,何よりも「多飲症・水中毒」で苦しむ患者・家族にとってはQOLの大幅な向上が期待できます。
本書はこれからの「多飲症・水中毒」ケアの標準となるばかりでなく,これをもとに,研究が格段と進む予感がします。その意味でも本書の意義は非常に大きなものがあると考えます。著者である川上宏人先生,松浦好徳看護師長,山梨県立北病院の皆さんが「多飲症・水中毒」ケアに挑戦されたこと,ほんとうに素晴らしいと思います。
(『看護管理』2011年1月号掲載)
精神科勤務経験がなくても、「多飲症・水中毒」患者への「かかわり」がわかる本 (雑誌『看護学雑誌』より)
書評者: 藤野 智子 (聖マリアンナ医科大学病院 急性・重症患者看護専門看護師 集中ケア認定看護師)
「多飲症・水中毒」と聞いて、なにを考えるだろうか?
筆者は、救命救急センターで多くの水中毒の患者と接してきた。救急領域で遭遇する水中毒の患者は、意識障害を主訴として来院することが多く、血液データでは電解質異常を示す。数日間の輸液管理を受けて元気に退院、もしくは精神科病棟へ転棟していく姿は、救急領域で見る独特の光景かもしれない。
◆「多飲症」は特殊な病態ではない
本書のはじめに「推薦のことば」がある。この書籍の編者が所属する山梨県立北病院院長の藤井康男先生の「ことば」を読んでいて驚きを感じた。藤井先生は、「水中毒」を最初に診断した医師であり、かつその時期が1983年と、今からたった30年弱前であることも記述されていたからだ。そして、本書にも「多飲症は長期入院中の患者のうち20%前後に起こる(de Leon 1994)」(p26)、「多飲症患者の60~80%は統合失調症であるといわれています」(p29)と記述されているように、多くの患者が存在するであろう状況を、この30年弱の間に発見して、試行錯誤のうえに治療過程や看護展開を開発してきたことに敬服する。
前述のように、多飲症が慢性の統合失調症患者に多いとなると、精神科医療でも特別な病態と思われがちだが、感情障害や精神発達遅滞、脳炎後や頭部外傷後などの器質的な脳疾患、神経性食思不振、人格障害、認知症の患者などでも認められている(p11)ことから、決して特殊な病態ではないという理解が重要である。
◆読者が読みやすい個性的な構成
本書はユニークな構成となっている。筆者は精神科領域で働いたことはないが、とても読みやすい構成だった。臨床現場で患者と直に接する多くの読者にとっても同様だろう。
全体は4部構成になっており、第1部は25のQ&Aから始まる。一般的に、Q&Aは後付けの場合が多い印象があったが、はじめにQ&Aが入っていることで、とても読みやすくなっている。またAnswer部分には、しっかりとエビデンスや文献も盛り込まれているので、ここだけでも十分に学習できる。
第2部「実践編」では、1988年、松田源一医師の多飲症疫学研究を機に開始した、山梨市立北病院での多飲症患者への「かかわり」が記述されている。はじめは試行錯誤だったこと、隔離と開放の繰り返しだったこと、そこから対策チームが発足し、チーム一丸となって専門病棟ができあがっていったその足あとが克明に示されていた。はじめからうまくいっていたわけではなく、同じ志のもとにチームが結束し、スタッフ個々の意識が変わっていった結果、チーム全体の意思が統一されていったことが読み取れる。現在、同じように取り組んでいる方には、なんとも心強い内容ではないだろうか。そして、チーム医療が注目される現在では、見習うべき内容が数多く記述されていると痛感した。
◆多飲症専門病棟で働く看護師が築き上げた「かかわり」
第3~4部では、「知識編」「資料編」として文献レビューや編者の施設で使用している重症度分類などが示されている。多くの書籍では、この知識編がはじめに記述されているが、第3部に挿入しているのには深い意味があるのだろう。読者対象が看護師と限定されているわけではないだろうが、看護師が読みやすい入り口としたこと、病態ありきで対処するのではなく、「患者個々の声を聞く」というスタンス、「統一したかかわり」が必要であることを強調したいという意図が込められていると推測した。
この「かかわり」という言葉からも、編者たちの思いいれを感じる。山梨県立北病院では、患者への対応技術を「かかわり」と呼んでいる。この言葉には、「かかわり」は多飲症専門病棟で働く看護師が試行錯誤の末に築き上げたものであるという“誇り”が含まれているのだ。同じ看護師として、このように胸を張って自分たちの成果、誇りといえるほどがんばった努力に拍手を送りつつ、筆者らもがんばらねばと勇気をもらったような気持ちになる。
本書によって救急医療から見ていた水中毒の患者への看護とは違った角度から学ぶことができた。また、この書籍の表紙は、まさに「水」のしずくを綺麗な水色を使って表している。内容と同じく、とても分かりやすい。そして、「多飲症・水中毒」に特化した書籍はとても珍しく、目を引く。ぜひ、精神科領域のみならず、救急領域の看護師にも読んでもらいたい一冊である。
(『看護学雑誌』2010年7月号掲載)
優れて実践的で崇高な理念─精神科看護の最良部分
書評者: 黒木 俊秀 (肥前精神医療センター・精神科医)
わが国の精神科病棟において「水中毒」は厄介な症状として知られてきた。主に荒廃した慢性統合失調症の患者にみられる。「中毒」と呼ぶのは,あたかも「アルコール中毒(渇酒症)」のように,患者が水道栓の蛇口に口をつけて,あおるように水をがぶ飲みするからである。そのため,1日のうちに5~6kgもの体重増加を生じることがある。
患者の中には,けいれん発作や意識障害を起こす者もいる。採血すると著しい低ナトリウム血症が認められる。当然,飲水制限を行うが,患者はひどく抵抗し,隠れ飲みも減らない。仕方なしに保護室に隔離すると,患者はさらにいらだち,看護スタッフに怒りや敵意をあらわにする。保護室内のトイレの汚水まで飲もうとする患者さえおり,身体拘束まで考慮せざるを得なくなる。以上のように,「水中毒」は一見単純でありながら,ケアする側をはなはだ悩ませる。
こうした「水中毒」に対して,山梨県立北病院の医師と看護スタッフがまことに明快な治療と管理の指針を示したのが本書である。決定版と称してよいのではないだろうか。
第1部「多飲症・水中毒についてのQ&A」の冒頭において,著者らは「多飲症と水中毒は,はっきりと違うものとして考えるべき」とズバリ指摘する。すなわち,「多飲症=水中毒」という誤解が,その治療は「飲水制限」と決め込むあまり,患者の日常生活能力を過剰に管理してしまい,本来改善すべき不適切な飲水行動については無策のまま,セルフケア能力全体の劣化を招いてしまうのである。目標とすべきは,多飲症という行動 の改善であり,それができれば,水中毒は起きないという。
以下,多飲症と水中毒のそれぞれの重症度分類に応じた治療指針を示すとともに,「身体拘束は避けるべき」,「多飲症患者がオープンに飲水できる環境を作ることがよい」,「多飲症は飲水量のみで決めるべきではない(ベース体重の設定が重要)」等々,目から鱗が落ちるような提言が並ぶ。
続く,第2部「実践編」は看護スタッフによる多飲症患者への「かかわり」の報告であり,その具体的なケア方法の詳細を明らかにしている。コラム欄では,たった1杯のコーヒーを飲ませるかどうかで患者も看護師もともに傷ついた心痛む経験なども語られる。「かかわり」というキーワードを通して,わが国の精神科看護の最良の部分に触れる思いがする。多飲症の心理教育と家族教育はこれまで報告が少なかったが,巻末の心理教育用テキストをすぐに活用することができよう。
精神科医の川上宏人氏が執筆した第3部「知識編」は,多飲症・水中毒の病態と治療に関する精神医学の知見を網羅し,第1部をさらに詳しく解説したものである。結論として,多飲症の原因も治療も1つに特定することはできないが,その治療目標は,患者が「最も幸せに生活できる場所で,その人なりのケア能力に合った方法で自らの飲水行動をコントロールできれば」よしとする川上氏の臨床医としての見識に敬意を表したい。
著者らが掲げる「開放的処遇により人間的接触を多くする」という理念は,多飲症のみならず,喫煙やメタボリック症候群などの多くの問題行動を認める今日の重症精神障害者に対する「かかわり」にも普遍化し得るのではないだろうか。その意味で,本書は優れて実践の書であるとともに,崇高な理念の書でもある。
3部構成で紐解く,よりよい援助者のための画期的な良書 (雑誌『看護教育』より)
書評者: 岩井 眞弓 (熊本保健科学大学保健科学部看護学科)
家族や医療者は,患者が水道の蛇口から貪るように水を求める姿に「どうしてあんなに?」と心を痛めその安全を願いつつ,考えあぐねてきた。ここに,『多飲症・水中毒』という症状に苦しむ人々に向け,山梨県立北病院の精神医療スタッフによるケアの集大成が一冊の本にまとめられた。本書を読み終え確信したことは,人々は,自分で自分をコントロールしながら社会生活を送っていること,そして,日常の生活のなかで飲食ほどその人の意思によって量質ともにコントロール可能なものはないということである。
数年前,私は学生と精神看護の実習に臨んだ。その時出会った50歳代の女性は,娘が嫁いだ後,統合失調症の治療を受け,数年後水を飲み始めた。過剰な飲水が目立ち始めたのは一人家に残してきた夫が癌で手術を受けなければならない事態を知ってからであった。学生は日々の関わりのなかで何もできない自分に苛まれていたが,その女性が幻覚や妄想に苦しみ,夫に対する妻としての苦悩をも持ち合わせていることに気づいた。その後,朝は検温の後女性が告げる体重と前日の夥しい飲水量を淡々と記録し,ベッドを整え身支度や洗面をつかず離れず見守った。しばらくして,午後の治療がないときには趣味の絵画や全身マッサージを楽しみに娘のような学生を探す女性の姿があった。いつの間にか飲水量は減っていた。過剰な飲水という現象を是正するために患者の飲水行動をコントロールしようとしていた自分に気づいたこの学生は,現象の意味を日々のケアのなかから患者とともに探り当てていったのである。しかし,私は,その後再会した女性が個室の布団のなかでうずくまる日々を過ごしていたことを知り落胆した。今思えば,このとき本書のような良書に出会えていればと悔いが残る。
さて読者は,本書が他の多くの専門書とは全く逆の構成をもっていることに気づくであろう。第1部ではQ&Aとして,山梨県立北病院という一地域の中核病院から発信された書物でありながらも,臨床現場のどこにでもありうる疑問に的確に回答し読者を引き込む。第2部では実践編として,1980年以降の北病院治療史が述べられ,医療スタッフの意識改革が多飲症の改善につながった事実がコラムに語られ読者の多くが持つ体験と重なる。そして,多飲症患者教育および家族教室の必要性を2006年以降の実践を基に述べている。第3部では知識編として,これまで述べてきた内容と研究データを基に,あらためて『多飲症と水中毒』の原因および診断基準と重症度分類を疫学的に述べ,国内外の文献レビューを基に今後の治療の方向性に結びつけて紹介している。理論としては分かっていても具体的な表現がよりよい援助に結びつかず苦慮している医療スタッフ必読の一冊である。
(『看護教育』2010年7月号掲載)
やっと出た,多飲症ケアのスタンダード
書評者: 阪内 英世 (鶴が丘ガーデンホスピタル看護部長)
多飲症の患者ケアは,これまで隔離室で飲水を制限するか,監視ともいえるような観察体制で水中毒を予防するかのどちらかであった。これは看護師にとっては,その膨大な労力の割に無力感を強く感じさせるものであり,患者には不自由さと苦痛を与えるだけのものである。
しかし本書では,山梨県立北病院のスタッフが,それまでと異なる新しい多飲症患者の対応を紹介しており,行き詰まった患者ケアに希望をもたらすものとなっている。
本書の特筆すべき点をいくつかご紹介する。
まず第1に病気への理解を深めるため,病態としての多飲症,病状である水中毒がまったく別のものであることを明確に打ち出している点である。この2つを明確に分けて定義することにより,過剰な制限の必要性が否定され,多飲症患者のセルフケア能力に着目ができ,能力向上のための看護ケアが構築されるようになっている。
第2に膨大な臨床経験と実績に基づきスタンダードケアが確立されているということが挙げられる。今まで多飲症患者の臨床報告はその事例のみにあてはまる単発的なものが多く,このようにケアを行ったら予測される結果になったという報告型のものが多い。それに比べて県立北病院では,「この結果になったのは,ケアのこの部分が有効,または無効であったから」という検証型の報告になっているためその内容の信頼性が極めて高い。ましてやチームの意識や家族教育など,多飲症予防の側面にまで触れた報告は今までに無かったものである。
第3にハードウエアに依存しないという基本姿勢をとっている点が挙げられる。山梨県立北病院は多飲症治療専門病棟を持っている数少ない病院の一つであるが,その建物の構造を基盤としてケアが展開されていたなら,そのケアはほかの病院では使えないということになる。ハードに頼った飲水制限から「安全に水を飲んでもらう」ためのかかわりに切り替えていったからこそ,本書はすべての病院で使われ,参考にされる内容になっている。
第4は常に患者中心の視点で書かれているということである。われわれはともすると,多飲水の患者を受け持つのはつらい,やりがいがないなどの理由から,看護師が苦しくならないための多飲水患者のケアを確立しがちであり,安全重視の飲水量チェック,体重チェックや尿比重チェックなどにどうしても視点がいってしまう。これらは多飲水の傾向を見つけ水中毒を起こさないために行う対症的な方法ではあるが,多飲水を改善するためのケアではない。やはり患者中心であるならば,本書に書かれているように多飲症を引き起こす要因に対してのケアが充足されるべきである。
以上本書の特徴について述べてきたが,このほかにもリミット体重の算出方法,水中毒の治療,患者教育のテキストなど,参考になるものが多く掲載されている。
多飲症患者の対応を考える際や見直す際には,ぜひ一読いただきたい書籍である。
精神科治療者の真摯な姿勢を示す良書
書評者: 穴水 幸子 (慶大精神神経科)
水のような本である。『多飲症・水中毒-ケアと治療の新機軸』という題名の通り,至極当然のように水と身体のかかわりのことが書かれた本なのではあるが。ブルーと白の2色のシンプルな美しい装丁で飾られ,さっぱりとした筆致で書かれて大層読みやすい。しかし読者はその美しさに惑わされ,ふわりと読み流してしまってはいけない。この本には,多飲症に罹患した人々が示す,水への飽くなき要求と依存,あるいはその経過中におとずれる激しい消化器症状,失禁,低ナトリウム血症,神経症状,意識障害,けいれん発作,昏睡という身体症状が描かれている。本書は疾病に真正面から向かい合うタフでハードな治療記録でもある。
水中毒は精神科臨床医療では治療のなかで,身体管理上,もっとも苦慮する病態のひとつである。本書を紐説くと,ひとの身体における水の在り方をあらためて意識させられる。
第1部「多飲症・水中毒についてのQ&A」,第2部「実践編」,第3部「知識編」と3部構成になっており,水中毒の疾患を治療した経験のない医師やスタッフや医学生にも理解しやすい。たとえば,知識編にある人体と水のバランス,ヒトの体重の約60%が水分であり,さらにそのうちの3分の2が細胞内液で,3分の1が細胞外液である。そしてこの水分バランスを一定に保つために,浸透圧受容体と圧受容体の変化は神経伝達を介してモニターされ,随時調整が行われている。あらためてヒトの身体における水との切っても切れない睦まじい関係性をみるようなこころもちがする。しかし,いったんこの睦まじさが壊れたとき,水中毒という特殊な病態を呈するのである。
編者である川上宏人医師と松浦好徳看護師長らが勤務する山梨県立北病院以外でも,慢性期の統合失調症入院患者さんたちを治療している精神科病院においては,高い頻度で水中毒患者に遭遇する。深刻な水中毒の症状にスタッフはあわてふためき,「どう症状に対応し,介入し,治療していけばよいのか」と難渋するところである。編者らも水中毒治療に葛藤した時期もあったであろうと推察される。なにせ治療者が「水を飲むと倒れるぞ,飲み過ぎるな」と真剣に患者に諭し,水から脅迫的に遠ざけようとすればするほど,そうした人は水を求めるものだから。
編者らの山梨県立北病院では,患者らが看護室で水を飲むこと(申告飲水)を第一義的に重要な行動変容ととらえ,多少水を多く飲んでしまっても,見えないところで水を飲む(隠れ飲水)より病態経過は好転しているととらえている。治療における信頼関係がなによりも大切という視点をもつ。そして患者への心理教育,多飲症家族教室を地道に積み重ねる。さらに多飲症専門病棟までをも構築し,多飲症・水中毒という複雑な病態に向かいあう。このような精神科治療者の真摯な姿勢を示し得たことこそが,水の如き清楚な様態をもつ本書の最も本質的な美点である。
アルコール依存,薬物依存,摂食障害,また自身を傷つけるほど他者の愛情を惜しみなく求める人格障害など,ヒトの渇望と依存性から生まれるさまざまな精神疾患の治療書,指南書は世にあまたと存在する。しかし,水中毒という特殊な疾病において新たにこのような良書が生まれたのは初であり,その点が大変喜ばしい。
荘子いわく「君子の交わりは淡きこと水の如し」である。水中毒をふくめた依存性・中毒疾患をもつ患者と治療者間には,まずは穏やかな協力的潮流を作りあげていきたい。患者と治療者は,依存物質抑止のみを目的とした「水と油」の関係に決して陥ってはいけない。
命の危険の“前”と“あと”を考える
書評者: 阪本 奈美子 (国立病院機構東京医療センター救命救急センター・医師)
臨床医として仕事を始めて,もう10年以上になる。いろいろなことを,それなりにわかっていたつもりだった。しかし,本当は何もわかっていなかった。何かにガツンと頭をたたかれた,そんな一冊だ。
タイトルを見ると,専門書に思われた。あるいは教科書かとも。しかし,そうだとしても常識を覆す構成である。普通だったら,定義や解説から始まるだろう。本書はなんと「Q&A」から始まる。意外であったが,「なんとなく」知っている多飲症や水中毒に対する抵抗感が一気になくなったのは事実である。そしてのめりこんでいく自分に気づいた。平易な文章でつづられているため,入り込みやすい。それでいて内容の深さにどんどんとはまりつつ進んでいくのである。
読み進めていくうち,まず知ったのは自分の「無知」であった。私は水中毒を知っていたのではなく,低ナトリウム血症に伴うけいれんや意識障害の治療に当たっていただけであった。低ナトリウム血症を呈してけいれんを起こすような状態で患者さんが救急車で運ばれてくると,背景に精神疾患があり,飲水を制限できなかったゆえに「水中毒」に陥ったのだろう,という程度に考えていた。その状態,つまり命が危険な状態になる“前”のことや,そして元の鞘に収まった“あと”のことを気にかけたことはなかった。単に私は全身管理を行いながらけいれんを抑え,教科書通りのナトリウム補正をして,状態が安定したら,退院あるいは精神科依頼をして自分の手を離す,ということをやっていたのだ。そのことに思い至った。
Q&Aに続く第2部では,山梨県立北病院が水を安全に飲んでもらえるようになるまでの苦難の歴史が,さまざまなエピソードとともにつづられている。ふと気づくとコラムの「たった1杯の攻防」に目頭が熱くなっていた。誰だって(少なくとも私は)思い通りにならない患者の立ち居振る舞いに,陰性感情を抱いてしまう。「患者の飲水行動のみにとらわれ,その患者の人間性を尊重していない,スタッフ中心の看護であった」と反省の一文に象徴されるように,全身状態を悪化させる飲水行動を阻止することばかりにとらわれ,なぜ飲水するのかを考えていなかった。「飲みたい」という気持ちを受け入れ理解を示すことから始まる意識改革のくだりは,その行間に著者らの語りつくせぬ思いが詰まっているに違いない。
そして第3部ではその病因や合併症などが丁寧に解説されている。この一冊が出来上がるためには,実際には書かれていないものの,多くの汗と涙が流されたことだろう。そんな苦労をしてまでもやらなければいけないのか,と思われるかもしれないが,豊富な経験と膨大な文献資料に裏打ちされていたからこそ,越えられた山なのかもしれないと感じた。この本は,多飲症治療のマニュアルではない。「知る」ことだけではなく,何より大切な「考える」ことも教えてくれる本だ。
まあ,そこまで重くとらえないまでも,まずは手にとってページをめくってもらいたい。表紙のさわやかさもさることながら,その装丁の妙に気づくであろう。部ごとにはそれぞれ「水」にかかわる写真があり,ページ左下の欄外のランニングタイトルには蛇口が描かれている。心憎い演出が,やわらかな文体の奥に秘められた著者らの細やかな心配りと重なり,それに気づいた自分にほくそ笑んだものである。
確かに,多飲症・水中毒について詳しく述べられた書であるが,その向こうには普遍的な,患者と医師の関係,患者とナーススタッフとの関係,また医療スタッフ間の関係の持ち方が示されている。患者さんは何を思い,何を望んでいるのか。日々の診療の中で,病気だけをみてしまい,患者さんの気持ちや家族の思いを置き去りにしてしまってはいないだろうか。「流して」しまっていないだろうか。患者さんは一人ひとり顔も違うように考え方や感じ方が異なる。私でもできる小さなこと,「今日はお加減いかがですか?」そんなひと言から始めてみようと思う。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。