My Favorite Papers(赤石誠,清田雅智,植田真一郎,能登洋,内野滋彦,伊藤康太)
寄稿
2014.09.15
【寄稿特集】My Favorite Papersこれだから論文を読むのはやめられない |
 |
医学関連雑誌の国際的なデータベース「PubMed」には,約5700誌2300万件以上の学術論文が収録されているそうです。日々膨大なエビデンスが蓄積され圧倒されますが,「知の大海原」を航海することでしか得られない発見もあるのではないでしょうか。
そこで今回は,これまでの医師としてのキャリアのなかで出会った「お気に入り論文」を識者の方々に挙げていただきました。さあ明日から,知の愉悦を求めて大航海へ!
| 赤石 誠 能登 洋 |
清田 雅智 内野 滋彦 |
植田 真一郎 伊藤 康太 |
赤石 誠(北里大学北里研究所病院 臨床教授・副院長)
 (1)Henry WL, et al. Observations on the optimum time for operative intervention for aortic regurgitation. I. Evaluation of the results of aortic valve replacement in symptomatic patients. Circulation. 1980 ; 61(3) : 471-83. [PMID : 7353236]
(1)Henry WL, et al. Observations on the optimum time for operative intervention for aortic regurgitation. I. Evaluation of the results of aortic valve replacement in symptomatic patients. Circulation. 1980 ; 61(3) : 471-83. [PMID : 7353236]
Henry WL, et al. Observations on the optimum time for operative intervention for aortic regurgitation. II. Serial echocardiographic evaluation of asymptomatic patients. Circulation. 1980 ; 61(3) : 484-92. [PMID : 7353237]
(2)Braunwald E, et al. The stunned myocardium : prolonged, postischemic ventricular dysfunction. Circulation. 1982 ; 66(6) : 1146-9. [PMID : 6754130]
(3)Fuster V, et al. Atherosclerotic plaque rupture and thrombosis. Evolving concepts. Circulation. 1990 ; 82(3 Suppl) : II47-59. [PMID : 2203564]
35年以上の医師生活の中で,最も印象深い論文3つを挙げてほしいと依頼された。1か月くらい考えた揚げ句に選んだのがこの3つの論文である。
(1)は,大動脈弁閉鎖不全症の手術時期に関する論文である。この論文は,1980年にCirculation誌に掲載された。私は,そのとき医師になって3年目であった。それまでは,大動脈弁閉鎖不全症の手術適応は,Spagnuoloの論文[PMID : 4255488]がゴールドスタンダードであった。つまり,血圧,X線写真上の心拡大,心電図所見から自然歴を判断し,手術適応を考えていた時代である。そのとき,遭遇したのがこの論文だ。今まで駆出率が左室収縮機能の指標であると思っていたのに,収縮末期径がより優れた収縮機能の指標となるというメッセージだと受け取った。この論文で,著者らは,大動脈弁閉鎖不全において症状がある場合には,心エコー図の左室収縮末期径が55 mm以上になると予後が悪いので55 mmにならないうちに手術をしなくてはならないと結論している。さらに無症状でも心エコー図の左室収縮末期径が55 mmを超えたら左室機能が低下しているという論文が後に続いている。この収縮末期径が50-55 mmという考え方は,現代のガイドラインでもしっかり踏襲されている。30年前の概念がいまだにきちんと残っていることに,生理学に裏打ちされた論文のすごさを感じる。可変弾性体モデルにおいて,収縮末期の圧容積関係は唯一無二であり,あらゆる負荷条件には無関係であるという菅・佐川の理論(当時,私はこの心機能の理論に心酔していた)から見ると,逆流量が症例によりさまざまで,負荷条件が一定しない弁膜症において,収縮末期に注目したところがこの論文の素晴らしいところである。
(2)は,stunned myocardiumの論文である。最初にこの論文を読んだときには,何の目新しさも感じなかった。当時,私は心筋虚血の実験をしていて,冠動脈を結紮して局所心機能を超音波クリスタルで観察する毎日を送っていた。だから,結紮を解除して冠動脈血流を回復させたからといって,局所心機能がすぐに回復しないのは,当たり前のことであると思っていたし,そのことは既に多くの生理学者は常識として認識していたからである。この論文の著者はBraunwaldであるが,著者の実験データは何もない。実は,データは,さかのぼること4年前,Heyndrickxの論文[PMID : 665778]に示されているのである。しかし,この論文はあまり注目されなかった。Braunwaldがstunned myocardiumと命名することで,Heyndrickxの実験データに概念を与えたのである。このstunned myocardiumという概念がいかに重要であるかは,急性心筋梗塞の病態が解明され,再灌流療法が普及するにつれ徐々に明らかになっていった。
(3)は,臨床の現場にいて,なぜ狭窄した冠動脈が閉塞して心筋梗塞にならないのかと疑問を持っていた私に,「なるほど」という答えをくれた論文である。バイパス手術は心筋梗塞を予防しないという文献的常識と,今にも詰まりそうな血管はバイパスしないと大変だという直感的な危機感の間で,リアルワールドにいると狭窄はちっとも閉塞しないという事実を実感していた。狭いから詰まるという話は,事実ではないことを現場の医師たちは知っていたが,なぜなのかはわからなかったのである。そこへ,クリアカットにプラークの破綻という概念を与えたこの論文は,私にとっては目からうろこそのものであった。
*
論文とは,新しい事実を見つけたことを自慢するだけのものではない。論文とは,自分の考え方と概念を示す手段である。仮説を立てることは非常に大事で,ちょっとした思い付きだけの仮説は,検証するに当たらない。思い付きを,どこまで突き詰めて概念として確立していくか,そのために検証すべきは何かを明らかにしながら,論文は作られるべきではないだろうか。多くの症例を使って現象を観察することや,介入の結果を議論・検証する論文は,医学において重要であることは誰も否定しない。しかし,医学という学問の中で,ぞくぞくするような(いわゆる,鳥肌が立つような)感動を与える論文にはなり得ないと思っている。
清田 雅智(飯塚病院 総合診療科診療部長)
 (1)Wrenn KD, et al. The syndrome of alcoholic ketoacidosis. Am J Med. 1991 ; 91(2):119-28. [PMID : 1867237]
(1)Wrenn KD, et al. The syndrome of alcoholic ketoacidosis. Am J Med. 1991 ; 91(2):119-28. [PMID : 1867237]
(2)Schamroth L. Personal experience. S Afr Med J. 1976 ; 50(9):297-300. [PMID : 1265563]
(3)Osler WM. Remarks on Specialism. Boston Med Surg J. 1892 ; 126 : 457-9.
(1)私が最初に医師として読んだ英文の文献。1995年,研修医になって2か月目に,糖尿病のないケトアシドーシスの患者さんを担当した。日本語の教科書を手当たり次第調べても原因不明で,研修医の先輩も同様の症例を経験していたが,長らく謎とされていた疾患であった。当時PubMedはもちろんインターネットもなかったが,自らCD-ROMの文献検索装置Medlineで2時間くらいかけて調べ,この文献がヒットした。すぐに長崎大の友人に文献を送ってもらい,この文献を読むことで疑問が氷解した。研修開始4か月目にして日本内科学会九州地方会で発表デビューし,アルコール性ケトアシドーシス(AKA)の概念を当院で確立した。この文献のおかげで,研修医でもがんばれば新たな知見を見いだせること,英語の文献は情報量が多いこと,つらいながらもそれを読むことでしか得られない知識があることを痛感した。
(2)メイヨー・クリニック感染症科へ留学後の2006年に,院内に招聘されたMicheal Lamb医師(ピッツバーグ大)と回診を行った。Lamb先生には検査結果を隠して,感染性心内膜炎の患者さんを診察してもらったところ,僧帽弁逸脱を伴う僧帽弁逆流の雑音と見落としていたバチ指を身体所見のみで正診され,まさに“art”な回診の経験をした。そのときSchamroth’s signとその由来を教えていただいた。原文を確認し,当時Webcatで日本の図書館の蔵書情報を調べるもヒットせず途方に暮れていた。だが,いつか入手しようと思い文献入手リストに書き留めていた。2010年になり再度調べた際,SAMJ誌のHPの存在を知り,この文献をfree downloadできるという僥倖に恵まれた。初めてバチ指が治り得るものであることを知った。これは2012年刊行のMcGee『Evidence-Based Physical Diagnosis』最新版の主要変更点であった。文献を執念深く探すことの大事さを知った。
(3)2014年5月にACP Japanで凝固異常の講演を行い,若年発症の網膜中心静脈閉塞症の症例を提示した。その考察に,Lamb医師から紹介された,1981年刊行のLee C. Chumbleyの「Ophthalmology in Internal Medicine」を引いた。著者は米国の内科と眼科の二つの専門医資格を持っていて,一人でこの本を書き上げている。その本の序文にかのWilliams Osler医師が内科医のルーティンの身体診察として眼底鏡を使うことを推奨していたことが書かれており,なるほど米国でトレーニングを受けた医師が眼底鏡にこだわる起源を知ることができた。本の文中に該当の文献があり早速入手した。ちなみにこれは現在のNEJM誌であり,HPから簡単に入手可能であった。100年以上前の1890年代に,既にOsler医師はSpecialismの弊害を説いていたことを知った。これは私のGeneralistという立場を代弁しているように思えて,大いに勇気付けられた論文だった。
*
心に刻んだ文献を時系列で挙げたが,引用は逆に古いほうにさかのぼっていることに気付いた。最新の文献が良いのではなく,疑問を解決するものが良い文献である。オリジナルの文献に当たることで,深い知恵が得られる実感がありぜひお勧めしたい。
植田 真一郎(琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学教授/琉球大学医学部 附属病院臨床研究支援センター長)
 (1)Cocks TM, et al. Endothelium-dependent relaxation of coronary arteries by noradrenaline and serotonin. Nature. 1983 ; 305(5935):627-30.[PMID : 6621711]
(1)Cocks TM, et al. Endothelium-dependent relaxation of coronary arteries by noradrenaline and serotonin. Nature. 1983 ; 305(5935):627-30.[PMID : 6621711]
(2)van Harten J, et al. Negligible sublingual absorption of nifedipine. Lancet. 1987 ; 2(8572):1363-5.[PMID : 2890954]
(3)Roussel R, et al. Metformin use and mortality among patients with diabetes and atherothrombosis. Arch Intern Med. 2010 ; 170(21):1892-9.[PMID : 21098347]
(1)ヒトのからだはあまりにも精巧につくられている。
自分で臨床薬理学という領域を専攻していてこんなことを書くのは気が引けますが,特殊な疾患以外では,一つの薬がその病態を決定的に変えてしまう,あるいはその患者さんの予後を決定的に変えてしまうことはそんなに多くはありません。アスピリン,β遮断薬,スタチン,ACE阻害薬といった教科書を書き変えた薬剤にしても死亡率の低下は20%程度で,有効性を証明するためには大規模な臨床試験が必要でした。
この論文は,ヒトのからだが薬というある意味小ざかしいものをはるかに凌駕して精巧に作られ調節されていることを考えさせます。ここで報告されている実験は単純で,もしヒトの血管(平滑筋)を収縮させるような刺激を与えると,その作用を緩衝するために血管内皮細胞は血管を拡張させるような物質を生成,遊離するというものです。
当たり前かもしれませんが,そのような能力がからだの各部分に備わっているとすれば,薬によって一つの経路や遺伝子,受容体を抑制することで簡単に変えられるものではないでしょう。しかし,だからこそ臨床研究者にはある種の諦観が必要で生命に対して謙虚であるべきで,治療介入はその有効性・安全性を厳密に評価し過大評価やいいかげんな危険性の評価は慎むべきことを忘れてはいけません。
(2)その方法はホントに有効?
高血圧患者さんの血圧がコントロールできないとき,あるいは何らかの理由で急に上昇した際,脳血管障害を伴う高血圧などのときに,かつて「ニフェジピン(アダラート®)舌下」という投与法を教えられた時代があります。危険な方法ですし,そもそも一時的にコントロールしても意味はないので現在は用いられませんが,私が医師になったころはそのような指示がけっこうありました。10年くらい前までは救急のマニュアルに掲載されていたのを見たことがあります。
この論文では舌下投与でニフェジピンは全く吸収されていないことが示され,それで降圧作用を示したとしてもそれはかまずに飲み込んで効いていたのだろうと結論付けられています。飲み込まずに我慢した患者さんの血圧がちっとも下がらないことや舌下投与を行った臨床試験が存在しないことからこの方法を疑問に思った臨床医の功績です。たとえマニュアルのようなものに掲載されていてもその医療行為が本当に正しいのかどうか常に疑うことが必要で,それがよい臨床研究につながると気付かせてくれました。アウトカム評価が難しい救急の現場ではこのようなことはまだまだあるのではないかと思います。
(3)メトホルミンは「悪魔の薬」?
メトホルミンは日本で不当に評価の低い薬で,先進国中第一選択薬としていないのは日本だけだと思います。添付文書を見るといきなり「悪魔の薬」のような警告が出てきます。高齢者,少しでも腎機能の悪い患者さん,心不全の患者さんには使わないほうがいい,なんていう感じです。これは乳酸アシドーシスを危惧してのことなのですが実際どの程度発症しているのかははっきりしませんし,2-6/10万人・年という報告はありますが,そんな低い絶対リスクの中でこれらをどのように評価したのかもよくわかりません。もちろん腎機能の低下した患者さんには注意が必要ですが,そんな薬はたくさんありますね。
この論文は既に動脈硬化性疾患を有する患者さんを対象としたREACH registryという観察研究で,その中で糖尿病でメトホルミンをたまたま服用していた患者さんと服用していない患者さんの死亡率を比較したものです。コホート研究なので患者背景はかなり異なっており,多変量解析で補正していくわけですが,メトホルミン群における死亡リスクの低下は年齢・性の補正のみで33%,臨床的に重要と思われるさまざまな因子による補正を行った後も24%の低下があり,堅牢な結果といえると思います。
この論文でもうひとつ重要なのはサブグループ解析です。もともとサブグループ解析は,特別に効果のある集団を見つけることよりも,さまざまな患者背景を越えた結果の一貫性を証明することが目的です。この論文では腎機能の軽度低下(eGFR 30-60)や心不全,比較的高齢(65-80歳)でもメトホルミン使用は一貫して死亡率の低下と関連すると報告されています。もちろんRCTではありませんし,そのサブグループ解析ですから,同じ対象患者でのRCTでの結果よりは信頼性が落ちる可能性はあります。しかし,結局そのような患者を組み入れるRCTを実施することは困難であり,それまでに信頼性の高いRCTからの結果が存在すれば(メトホルミンではUKPDS研究),結果にバイアスが入るリスクを知った上でこの論文の結果を診療に用いることは可能だと考えます。
*
新薬が開発されると,さまざまな患者背景を持つ患者さんで有効性・安全性が評価され,結果として患者さんのアウトカムを改善するには多様なデザインの臨床研究が必要であり,結果はそれぞれの役割を考えて解釈すべきだと思います(図)。
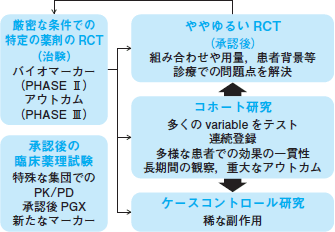 |
| 図 理想的な臨床研究の枠組みとその目的 |
能登 洋(聖路加国際病院内分泌代謝科医長/東京医科歯科大学医学部臨床教授)
 (1)Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease : the Scandinavian Simvastatin Survival Study(4S). Lancet. 1994 ; 344(8934) : 1383-9. [PMID : 7968073]
(1)Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease : the Scandinavian Simvastatin Survival Study(4S). Lancet. 1994 ; 344(8934) : 1383-9. [PMID : 7968073]
(2)Pitt B, et al. Randomised trial of losartan versus captopril in patients over 65 with heart failure(Evaluation of Losartan in the Elderly Study, ELITE). Lancet. 1997 ; 349(9054) : 747-52. [PMID : 9074572]
Pitt B, et al. Effect of losartan compared with captopril on mortality in patients with symptomatic heart failure : randomised trial-the Losartan Heart Failure Survival Study ELITE II. Lancet. 2000 ; 355 (9215) : 1582-7. [PMID : 10821361]
(3)Victor RG, et al. Effectiveness of a barber-based intervention for improving hypertension control in black men : the BARBER-1 study : a cluster randomized trial. Arch Intern Med. 2011 ; 171(4) : 342-50. [PMID : 20975012]
(1)4S⇒EBMの黎明
コレステロール高値の4444人を対象に,スタチン投与により総死亡と冠動脈疾患再発のリスクが有意に低下することを実証したRCTです。20年前にこのエビデンスが発表されるまでは大規模研究がなく,コレステロール値を下げると冠動脈疾患リスクは低下しても総死亡リスクは増加するという報告があり,治療意義が議論されていました。この研究は,臨床問題を解決する際にエビデンスという実証を重視することの意義を示した点で,EBM普及の起爆剤の一つとして歴史的に君臨します。
日本にEBMが浸透してまだ10年程度しか経ちませんが,この論文が発表された当時アメリカで臨床研修をしていた私は,この論文を活用してEBMの実践法やエビデンスの読み方を臨床の現場で習得し,日本でのEBM普及に力を入れました1)。
(2)ELITE/ELITE II⇒EBM商法への警鐘
ELITEは,心不全の標準治療薬であるアンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)と当時の新薬アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)の比較RCTで,一次エンドポイントの腎機能悪化に有意差はなかったものの二次エンドポイントの死亡率がARB群で有意に低いことが示されました。そこで同じ研究グループは,死亡率を一次エンドポイントとしたELITE IIをあらためて実施したところ,最終的に有意差はなくARBの優位性の期待は崩れ去りました。
このように,二次エンドポイントは仮説の提唱・探求のオマケにしかすぎません。一つの研究で検証できるのは一次エンドポイントだけです。二次エンドポイントを前面に出した薬の宣伝が氾濫していますので,騙されて朝三暮四とならないように警鐘を鳴らす論文セットです。
(3)床屋スタディ⇒エビデンスの創造
理容師によるサポートによってアメリカ黒人男性の血圧管理が有意に改善することを示した介入研究です。私が二度目に臨床留学した大学で実施されました。発想や研究法は感動的なほど独創的です。
アメリカの黒人男性にとって床屋は井戸端会議の場所として文化社会的な集会場です。医学生に床屋に血圧計を持って行かせ来客の血圧を測定させます。医学生は無給ですが論文に名前が載るため喜んで協力します(ここで人件費が浮きます)。血圧が高かった人のうち,研究に参加してくれた人には協力費として理髪代を研究費で支払いました。口コミで来客が増えるので床屋ももうかる上に,研究参加者も自動的に増え,誰もが得をする方策です。医療におけるコミュニティーの影響を体得しただけでなく,エビデンスの創り方の印象的な勉強になりました。
*
EBMは患者さんに始まり患者さんに帰着します。エビデンスを金科玉条として盲信するのではなく,鑑識眼と適材適所が重要であることも忘れないようにしましょう。また,これからは質の高いエビデンスを創り出していくことも大切です。日本から“赤提灯スタディ”が誕生することを楽しみにしています。

◆参考文献
1)週刊医学界新聞第2245号(1997年6月23日付)寄稿「ベスイスラエル病院での臨床疫学の実践」(能登洋)
内野 滋彦(東京慈恵会医科大学 麻酔科集中治療部)
(1)Bickell WH, et al. Immediate versus delayed fluid resuscitation for hypotensive patients with penetrating torso injuries. N Engl J Med. 1994 ; 331(17):1105-9.[PMID : 7935634]
(2)Warren BL, et al. Caring for the critically ill patient. High-dose antithrombin III in severe sepsis : a randomized controlled trial. JAMA. 2001 ; 286(15):1869-78.[PMID : 11597289]
(3)van den Berghe G, et al. Intensive insulin therapy in critically ill patients. N Engl J Med. 2001 ; 345(19):1359-67.[PMID : 11794168]
(1)常識とのギャップ
外傷による出血でショック状態となっている患者に対し,手術室に着くまで補液をしないほうが死亡率が低く,合併症も少ないことを示したRCTである。
単純に驚いた。出血性ショックの患者に補液をしないほうがいいとは。血が足りないのだから補液したほうが良いに決まっている,補液によって血圧が上がればそれは良いことに決まっている,という常識が覆された。今考えると,血圧はsurrogate markerであるとか,efficacyとeffectivenessの違いであるとか,そういう視点で見ればそれほどの内容でもないのだが,当時はそんな言葉を知る由もなく,単純に驚いた。
(2)日本と海外のギャップ
重症敗血症患者に対し,4日間で3万単位のアンチトロンビンIII(AT III)もしくはプラセボを投与し,両群で28日死亡率に差を認めなかったことを示したRCTである。
自分の専門を集中治療に決めた当時,集中治療系の日本の商業雑誌とCritical Care Medicine誌を勉強のために年間購読していつも鞄の中に入れておき,通勤途中に読んでいた(今考えると随分真面目だった)。この2つの雑誌の内容の違いは明白で,自分のやっていることは日本の商業雑誌の記載内容に近く(正確には,勉強のために読むくらいだから雑誌に書かれていることのほうがレベルが高いと思っていた),海外の人たちは本当にこんなことをしているのだろうかと素朴に疑問を感じていた。じゃあ見に行こう,それが留学しようと思った最大の理由だった(ちなみに2番目の理由はカジノに通うことだったが,これはオフレコでお願いしたい)。
日本と海外の違いの典型例がDICで,当時の日本では抗凝固薬の投与が基本であり,重症例ではAT IIIが当然のように投与されていた。しかし,DICの代表的な原因疾患である重症敗血症に対して,日本で使用されている数倍量のAT IIIを投与しても予後に影響せず,場合によっては出血を増やしてしまうという結果は,日本と海外のエビデンスに対する姿勢の違いを明確に印象付けられたし,根拠に基づく診療の重要性を認識させられた。
(3)学会発表と文献のギャップ
ICUで人工呼吸を必要とする患者に対し,intensive insulin therapy(IIT,血糖値を80-110 mgにコントロール)を行うか,通常の血糖コントロール(180-200 mg)を行うかで無作為に割り付け,IIT群でICU死亡率が有意に低下(4.6%対8.0%)することを示した一施設RCTである。
オーストラリア留学中にシドニーで集中治療の国際学会が開かれ,初めて海外の学会に参加した。そこでこの研究の筆頭著者がNEJM誌に掲載される前に研究結果を発表していて,ICU患者の死亡率をインスリンで半分にできるという結果に,海外の学会というのはこんなにすごい研究が発表されるものなのかと心から驚いた。この研究結果は聴衆全員にとって同じように驚きだったようで,発表終了後に文字通りのスタンディングオベーションが会場内に起こった。
しかし,その数週間後にNEJM誌に発表され,興奮を思い出しながら文献を実際に読んでみると,患者背景や治療内容などにいくつかの疑問点が浮かんだ。IITは世界中でしばらくの間ブームとなったが,その後複数の多施設研究により予後の改善効果は否定され(低血糖の副作用が多く発生),過去の治療となった。一施設研究におけるgeneralizabilityの限界や,学会発表のような部分的な情報だけで判断せず原文を読むことの重要性など,多くを学んだ文献だった。
*
暇を持て余しているわけでもないのに,自分はどうして論文を読み続けているのだろうか。その理由を考えてみると,
・患者を救うには知識が必要だと思い込んでいるから
・部内の勉強会の主催やブログ執筆のために必要だから
・自分の専門性を維持するために情報をアップデートする必要があるから
・研究のアイデアや参考文献が得られるから
・他人が知らないことを知ると優越感を感じるから
・単純に,面白いから
などが思い付く。最初の理由は,患者を救うには知識が必要だから,という意味ではない。読んだ文献の数と患者予後との関係は証明されてないはずだから。ちょっと自虐的だが,もしかしたら最大の理由は最後から2番目かもしれない。正確なところは自分でもわからないが,あまり細かいことは気にせず,これからも文献を読んでいきたいと思う。
伊藤 康太(ニューイングランド大学 医学部内科・老年医学)
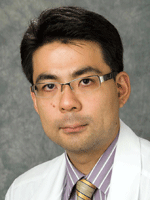 (1)Feinstein AR, et al. Problems in the “evidence” of “evidence-based medicine”. Am J Med. 1997 ; 103(6):529-35.[PMID : 9428837]
(1)Feinstein AR, et al. Problems in the “evidence” of “evidence-based medicine”. Am J Med. 1997 ; 103(6):529-35.[PMID : 9428837]
(2)Charlson ME, et al. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies : development and validation. J Chronic Dis. 1987 ; 40(5):373-83.[PMID : 3558716]
(3)Tosteson AN, et al. Cost effectiveness of screening perimenopausal white women for osteoporosis. Ann Intern Med. 1990 ; 113(8):594-603.[PMID : 2119161]
臨床疫学を学んでいた大学院在学中に影響を受けた3論文を挙げました。
(1)は,臨床疫学の父,故アルバン・ファインスタインが晩年に発表した論説で,かつての門下生デビッド・サケットらが巻き起こしたEBMムーブメントへの痛烈なアンチテーゼです。臨床判断を支えるべきエビデンスは,定量化されたソフトデータ(患者さんの主観や医療者の直観など)であり,病態生理であり,混沌としたリアル・ワールドを注意深く「観察」し思慮深く「分類」した研究です。ファインスタイン本来の臨床疫学を学んでいく過程で,EBMの方法論に縛られない研究観が培われました。
(2)は,ファインスタインの後継者であり,私自身が師事したメアリー・チャールソンのコホート研究です。ファインスタインが提唱した「併存疾患」の概念を具現化したチャールソン併存疾患指数は,あらゆる比較研究において交絡補正に欠かせない役割を担ってきました。内科研修医たちが観察したたった1か月分の入院患者さんの重症度分類が,発表から四半世紀を経た現在,史上最も引用されてきたとされる臨床系論文の原点です。
(3)は,骨粗鬆症検診の是非に関する古典的な費用対効果分析です。検診のRCTを遂行することが非現実的な状況で,最終アウトカム(骨折・死亡など)の検討が不十分であることを理由に検診を非推奨とするのが得策か,あるいは入手可能な代用アウトカムを存分に活用して患者さんにとって最善と信ずる選択肢を模索すべきか。いわゆる「不確実性下の意思決定」の数理モデル化は,その後の私の研究テーマになりました。
*
“Far better an approximate answer to the right question……than an exact answer to the wrong question” (Tukey JW)。論文を考察する際には,「的外れな設問への正確な解答より,的確な設問へのおおよその解答」を大切にしています。
いま話題の記事
-
忙しい研修医のためのAIツールを活用したタイパ・コスパ重視の文献検索・管理法
寄稿 2023.09.11
-
人工呼吸器の使いかた(2) 初期設定と人工呼吸器モード(大野博司)
連載 2010.11.08
-
連載 2010.09.06
-
事例で学ぶくすりの落とし穴
[第7回] 薬物血中濃度モニタリングのタイミング連載 2021.01.25
-
寄稿 2016.03.07
最新の記事
-
医学界新聞プラス
[第3回]人工骨頭術後ステム周囲骨折
『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』より連載 2024.04.19
-
医学界新聞プラス
[第2回]心理社会的プログラムを分類してみましょう
『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.19
-
医学界新聞プラス
[第5回]事例とエコー画像から病態を考えてみよう「腹部」
『フィジカルアセスメントに活かす 看護のためのはじめてのエコー』より連載 2024.04.12
-
医学界新聞プラス
[第3回]学会でのコミュニケーションを通して自分を売り込む!
『レジデントのためのビジネススキル・マナー――医師として成功の一歩を踏み出す仕事術55』より連載 2024.04.12
-
医学界新聞プラス
[第1回]心理社会的プログラムと精神障害リハビリテーションはどこが違うのでしょうか
『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.12
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


