MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


立岩 真也 著
《評 者》内藤 いづみ(ふじ内科クリニック院長・ホスピス医)
“死に傾く”医師たちへ
 医療倫理とは何だろう,といのちの現場でいつも考えさせられる。
医療倫理とは何だろう,といのちの現場でいつも考えさせられる。
立岩がこの本の序章で述べているように,いろいろな場面で同じ言葉が取り上げられると,なんだかもうわかっているような既視感を持つようになるらしい。
長いあいだ難病中の難病という烙印を押されてきたALSという病の現実をゆっくりと,詳しく学ばせてくれるこのぶ厚い本は,「わからない」ことは「わからない」という,当たり前のことを,格好をつけずに正直に認める勇気を与えてくれる。読む側にも体力が要求されるが(立岩という人物は体力のある人なのだろう),大量の参考文献と,実際の患者の声や主張を載せ,現在の可能性のある方向と著者の意見も文脈に沿って表してはいるが,結論を決めつけない手法に,私は安堵感(救いというべきか……)を覚えた。
私は,平均70日の在宅でのがん患者の生きる日々にかかわって,10年以上になる。本人と家族がどんな選択をしても,どんなケアや医療を私たちが提供しようとも,それで100パーセント絶対正解という確証はない。死に至る日々は,悩みと安堵と妥協が混ざり合い,揺れ動く心にみずからが折り合いをつけて,辛うじて,「これでよかった(はず)」とつぶやく結論に行き着くのではないかと感じている。
私のかかわる進行がん患者の死はほとんど避けられないものだが,ALS患者にとって,来たるべき時の人工呼吸器の装着の有無は,いのちの継続に決定的に関与するから大問題だ。
はずかしながら,私はこれほどの長期生存者がいらっしゃることを正確に知らなかった。そして,これらの患者の声をまとめて読ませてくれた,立岩の今回の仕事に感謝している。これは,医療現場の外にいる人だからこそできた仕事だと思う。
ALSは難病である,と私たちは教え込まれている。身体筋力能力は失われていくが,思考,知性,意識は保たれている状況を,最悪だと考える第三者の私たちがいる。そしてその第三者が,医療者としてALS患者にかかわった時に,“こんな状態では生きている価値がない”と潜在的に考え,人工呼吸器を着けないことを暗に勧め,その人がいのちを諦める方向に向かわせる力にもなっているかもしれないと気づかされた。医師は,患者の治癒不能という状況がとても苦手である。
私はこういう医師のアティテュード(態度)に対してずっと批判をしてきたつもりだった。中立ではなく,“生に傾く”医師として,ターミナルケアにかかわってきたつもりだった。甘かったかもしれないと反省している。
先日,余命1か月と告知を受けた食道がん患者にかかわった。退院時にその後の進行予想の説明はなく(食道が閉鎖すれば経口摂取できなくなり,生存の危機になるのに),週1回の抗がん剤治療に通院するように言われただけだったらしい。退院して,すぐに事態は急変した。飲み食いできなくなったのだ。ALS患者が急に呼吸困難になった状況と似て,くわしく知らされていなかったので,突然こういうことが起きて,本人も家族もかなりパニックになった。末梢静脈からの点滴だけでは体力がもたなくなり,中心静脈からの高カロリー輸液を検討した。
患者に説明すると「もう少し栄養を入れて,私は生きたい」とはっきり言ったのだ。そのためには外科的処置が必要になり,前医に再三依頼したが,「お気持ちはわかりますが(誰の気持ち?),処置のための空きベッドがありません。できません」という返事しかもらえなかった。ベッドが空くのを待つ余裕はこの患者には残されていなかった。私たちは追い詰められた。
私はそこに“死に傾く”医師たちの力のベクトルを感じた。それは大きな力である。ALS患者が,息が苦しければ,それを楽にする機械があるのと同じように,のどの乾きを癒し,いのちのエネルギーを与える方法があるのに,それを第三者の判断で,その選択肢を勝手に黙殺することが許されるのだろうか。
幸いに友人の外科医の協力で,留置ポートを着けることのできたこの患者は望みを叶え,生存のカロリーを得て,その後の20日間の人生を生き抜いた。
患者の「生きたい」という声を,医療者はくもりのない心で聴きとげるべきだと思う。


《標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野》
精神医学
第2版
奈良 勲,鎌倉 矩子 シリーズ監修
上野 武治 編
《評 者》冨岡 詔子(信州大教授・保健学科作業療法学)
知識の整理・確認にとどまらず, 精神医学の進歩がOT・PTに 及ぼす影響を俯瞰できる
 3年半前の初版本にも書評を書かせてもらった。「教科書としての標準的・中立的な立場を保持した過不足のない網羅的な内容」と「OTやPTに必要な項目の詳述とのバランスがとれた利用しやすい実用的な参考書」の2点を優れた特徴としてあげ,「治療とリハビリテーション関連事項の補強」を今後の改善への希望点としてあげた。今回の改訂では,こうした希望がかなえられ,初版本の持つ長所を生かしつつ,治療・ケア・援助・リハビリテーションに関連した記述が随所で補強された。特に,第19章は章タイトル自体が「精神障害の治療」から「精神障害の治療とリハビリテーション」に変更され,インフォームドコンセントや心理教育などの新たな項目を加えて,章全体が大幅に書きあらためられ,治療とリハビリテーションの全体像がより理解しやすくなった。
3年半前の初版本にも書評を書かせてもらった。「教科書としての標準的・中立的な立場を保持した過不足のない網羅的な内容」と「OTやPTに必要な項目の詳述とのバランスがとれた利用しやすい実用的な参考書」の2点を優れた特徴としてあげ,「治療とリハビリテーション関連事項の補強」を今後の改善への希望点としてあげた。今回の改訂では,こうした希望がかなえられ,初版本の持つ長所を生かしつつ,治療・ケア・援助・リハビリテーションに関連した記述が随所で補強された。特に,第19章は章タイトル自体が「精神障害の治療」から「精神障害の治療とリハビリテーション」に変更され,インフォームドコンセントや心理教育などの新たな項目を加えて,章全体が大幅に書きあらためられ,治療とリハビリテーションの全体像がより理解しやすくなった。
改訂版のきっかけとなる最新の動向や新知見の言及もタイムリーである。例えば国際生活機能分類(ICF)への言及(総論第1章),精神分裂病から「統合失調症」への呼称変更にあわせた関連用語の改定と項目内容の大幅な変更,および最新の生物学的成因論の記述(第9章「統合失調症およびその関連障害」),さらに老年期を「初老期」と「老年期」に区分した詳述(第18章の「ライフサイクルにおける精神医学」)など,現場のセラピストにとっても役に立つ内容が補充されている。
基礎教育のテキストには,伝統的・標準的な知見や定説といった過去から現在までの学問的蓄積をいかにわかりやすく伝えていくかという「保守的な側面」と,新たな仮説や知見をどのように伝えていくかという「進歩的な側面」の両面を持つことが常に要求されている。この両面のバランスのよさが本書の長所であり,作業療法の専門科目を教える教員にとっても,本書に対する「安心感と信頼感」の源泉になっている。
例えば,本書では,私自身が学生時代に教わったヤスパースの自我意識の概念やクレペリンやブロイラーの伝統的な分類概念から,最近の脆弱性―ストレスモデルや脳SPECTの知見までが含まれている。経験あるセラピストにとっても,本書の一読は必要な知識の整理や確認に役立つというだけでなく,学問(精神医学)の進歩がOT・PTにどのような影響を及ぼすかを俯瞰する機会になり,そうした視点で自分の実践(教育や臨床活動)を見直す道筋を提供してくれるのではないだろうか。その点,各章の最後にある「PT・OTとの関連事項」は,いずれ精神医学に関心のあるPT・OTの共同執筆者を求めることで,より明確なメッセージが伝達できるのではないかと期待している。
精神医学の教科書というと,「文字が多くてとっつきにくい」のが定番であったが,初版以来の基本方針である「百聞は一見にしかず」をより徹底し,図表・写真を多用し,レイアウトがさらにみやすくなった。また,重要な関連事項や用語を,NOTE・Advanced Studiesとして別個に記述して挿入する方法は,複雑な概念を整理しながら,自己学習を深めていくうえで,きわめて有用である。
本書の改訂にあたっては,「温故知新」を重視したとある。初版以来貫いている編集責任者の上野氏の方針は,テキスト出版の王道であり,厳しく骨の折れる仕事でもある。より使いやすくなった改訂版の出版に心から敬意を表したい。


《米国感染症学会ガイドライン》
成人市中肺炎管理ガイドライン
第2版
河野 茂 監訳
《評 者》松島 敏春(倉敷第一病院呼吸器センター長)
日本版ガイドラインへの 具体的提言も
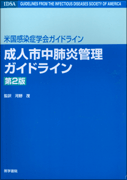 本書の訳者序にも述べられているように,肺炎は罹患率,死亡率共に高い重要な疾患であり,その診療ガイドラインは有益性が高いはずであると考えられた。本邦には日本呼吸器学会(JRS)の「成人市中肺炎診療ガイドライン」が存在するが,それを作成するに際して最も参考としたのは,1998年に公表されていたアメリカ感染症学会(IDSA)のガイドラインであった。それはすでに河野茂教授らが2000年に翻訳して,本書の第1版として刊行されている。その後IDSAガイドラインは2000年,2003年に改訂されたので,河野教授らは翻訳本の第2版として,このたび本書を刊行されたのである。
本書の訳者序にも述べられているように,肺炎は罹患率,死亡率共に高い重要な疾患であり,その診療ガイドラインは有益性が高いはずであると考えられた。本邦には日本呼吸器学会(JRS)の「成人市中肺炎診療ガイドライン」が存在するが,それを作成するに際して最も参考としたのは,1998年に公表されていたアメリカ感染症学会(IDSA)のガイドラインであった。それはすでに河野茂教授らが2000年に翻訳して,本書の第1版として刊行されている。その後IDSAガイドラインは2000年,2003年に改訂されたので,河野教授らは翻訳本の第2版として,このたび本書を刊行されたのである。
本書では,第I部として2000年に改訂されたガイドラインが詳細に翻訳され,肺炎の疫学,予後・リスクに基づいた治療の場の決定,診断法の評価,病原微生物ごとの肺炎に関する重要事項,抗菌薬の選択と各種抗菌薬に関する重要事項,治療期間・治療評価・治療に反応しない場合の対応,肺炎の予防,などが紹介されている。
第II部は初版,改訂版からさらに改定すべきこと,すなわち,治療場所の決定,推奨される抗菌薬,新しい検査法,SARS,ケトライド系薬などの新項目,菌血症を伴った肺炎球菌性肺炎の治療,ウイルス性肺炎などの特別項目,市中肺炎予防の改訂,などが紹介されている。
注目すべきは2003年のIDSAガイドラインとJRSのガイドラインの比較を試みていることであり,さらに,改訂IDSAガイドラインを参考として,“JRSガイドラインではどのような抗菌薬の選択をすべきか”を,具体的に示していることである。
現在JRSガイドラインは改定作業中であり,IDSAガイドラインを参考としていることも事実である。したがって本書が,2005年7月に発表予定のJRS「成人市中肺炎診療ガイドライン」を理解するのに有用であることはもとより,ガイドラインの目的である“肺炎治療の向上を図り,国民健康の増進に役立つ”ことは論をまたない。
監訳者の河野茂・長崎大学教授は,呼吸器感染症に関する研究では世界のトップランナーの1人であり,JRSガイドライン作成にあたっては最も精力的に仕事をされた。翻訳者の大野,東山,柳原長崎大学講師は,現在最も精力的に呼吸器感染症に関する研究を進めている方々である。初版に続く改訂版の翻訳のご苦労に感謝する。


清水 弘一 監修
米谷 新,森 圭介 編
《評 者》石橋 達朗(九大教授・眼科)
今後,どの眼科医にも 求められるであろうICGを用いた 診断技術の向上に役立つ
 あらゆる眼科疾患に関連深い脈絡膜循環
あらゆる眼科疾患に関連深い脈絡膜循環
脈絡膜。それは眼球の後方に位置するが故に,その生体内での循環動態や血管構築の詳細を知ることは困難であった。近年数々の診断機器の改良,すなわち造影剤を用いた検査により,その実態が解明されてきた。しかしながらフルオレセイン(FAG)蛍光眼底造影法では脈絡膜循環動態は捉えにくい。最もその血流動態の解明に寄与したのはインドシアニングリーン(ICG)蛍光眼底造影である。そしてさまざまな疾患の病態は脈絡膜の循環に関与していることが明らかになってきた。本著はICG蛍光装置の改良に携わった編者の10年間の経験の集大成とも言える多くのICG造影写真を掲載し,その所見をていねいに述べている。
2004年から厚生労働省に認可され,開始された光線力学療法は確実に多くの施設に普及している。施行に当たってはFAG造影検査の所見が中心となるが,ICG造影検査所見をも加味した正確な診断と適応の判断は必須である。本著でそれを再確認し,正確な治療適応の判断に役立てたい。
本著の編者によると「肩がこりそうなくらい大まじめな」書ということであるが,各疾患に対する解説には細やかな神経をもって枝葉末節にわたるまで手抜きを許さないという姿勢が随所から伝わってくる。脈絡膜循環に関するすべての分野を網羅しており,今後はどのような疾患を専門にする眼科医にも求められるであろうICGを用いた診断技術の向上に役立つと考えられる。ぜひ手元において,事あるごとに確認する書としたい。
詳しい疾患説明と美しい造影写真
本著は総論,各論から構成されている。
総論では編者による華麗ともいえる血管鋳型標本を配し,脈絡膜の血管構築(解剖学的特徴,生理学的特徴)について細かく説明している。それをはじまりとして,その美しい脈絡膜血管にいかにしてICGが流入していくか,加齢による変化,光る血管などについてページいっぱいのパノラマ造影写真を用いることによって,わかりやすく解説されている。
各論ではICGの臨床応用が活発化するきっかけとなった疾患,と編者が記している加齢黄斑変性を筆頭に,微妙にオーバーラップした網膜血管腫様増殖〔Rap〕,ポリープ状脈絡膜血管症〔PCV〕などとの鑑別についても言及している。また,ぶどう膜炎,遺伝性網膜変性,糖尿病網膜症などの疾患について,単に造影写真の所見の説明にとどまらず,その病態に関する疑問点や発症のメカニズムについても,さまざまな過去の報告を参照し,自験例との比較を行い細かく検討している。そういう意味でも,新しく眼科医師としてトレーニングを積む者だけでなく,すでに専門医となった医師にも十分読み応えがある内容である。

 ハーバード大学テキスト
ハーバード大学テキスト
心臓病の病態生理
第2版
Pathophysiology of Heart Disease:A Collaborative Project of Medical Students and Faculty, 3rd Edition
Leonard S. Lilly 編
川名 正敏,川名 陽子 訳
《評 者》島田 和幸(自治医大教授・循環器内科)
医学生と教官が 共同作業で作り上げた 循環病態生理学テキスト
本書は米国ハーバード大学の循環病態生理学のテキストであり,すでに国際的にも評価が確立されているが,特に「急性冠症候群」,「動脈硬化」を中心に旧版を大幅に改訂したものである。病態生理学を臨床家が執筆しており,問題の発想はあくまで臨床を起点としている。本書の最も適した対象は,わが国の医学教育課程の中では,基礎医学を勉強し終えて,臨床の系統講義を受けはじめた学生ではないだろうか。「基礎と臨床を科学という線で貫いた病態生理の概念」で構成されており,「循環」の講義シリーズが数週間あるとすれば,その間に通読すると,きっとその学生は循環器疾患のことがよくわかり,したがって深く興味を持つに違いないと想像する。もちろん研修医が循環器病棟をローテートする間に通読することも,すばらしい。実際の患者を経験しながら,1つひとつの症状・徴候・診断法・治療法にどのような病態生理上の概念が形成されているのかを知ることは,まさに科学としての医学をいきいきと実感できるに違いない。
本書のもう1人の主役はハーバード大学の医学生であるという。彼らが教官と共同作業でこのテキストを作り上げたと聞いて,米国の医学生の質の高さに驚嘆せざるを得ない。わが国でも,せめてどこかの医学校でこのような質の高い「学生と教官の共同作業」ができるような時代が来ないだろうかと夢見るばかりである。
本書はあえて難しい部分には立ち入らず,臨床をやっていくうえでこれくらいの知識でよいといったコンセンサスでレベルが統一されている。同時に,どうしてそういうことになるのかと,学生・研修医がいつも抱く疑問からは決して逃げていない。その理由を必ず答えてくれている。このあたり,学生が共同して作業した成果がまんまと出ていて,思わず読んでいてにんまりとしてしまう。川名正敏・陽子先生の訳も読みやすく,脚注はとても親切で,日本の読者にとってとても有用である。
