MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


悩みの多い間質性肺疾患に対する知見が日本語で集約
米国胸部学会ガイドライン間質性肺疾患診療ガイドライン
長井苑子,泉 孝英 監訳
《書 評》冨岡洋海(西神戸医療センター呼吸器科)
間質性肺疾患への対応に悩んできた日本
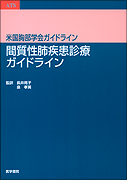 本書は米国胸部学会(ATS)が中心となって作成され,サルコイドーシス,特発性間質性肺炎(IIP),特発性肺線維症(IPF)の3つの最新ガイドラインについての翻訳を中心とし,その内容を日本に紹介した実にタイムリーなものである。これまで刊行されてきた疾患ガイドラインは,主にcommon diseaseを対象として,特に治療面での一定の方向性を示し,医療格差をなくすところに意義があったが,これらの間質性肺疾患については,多くの研究成果が蓄積されてきたものの,その病因,そして何よりも治療面での確立された見解に乏しい。よってその疾患概念の統一をはかり,比較的まれであるからこそ,多施設での病態,治療における知見の集約が急務であり,不完全ながら必然と生まれてきた経緯がある。
本書は米国胸部学会(ATS)が中心となって作成され,サルコイドーシス,特発性間質性肺炎(IIP),特発性肺線維症(IPF)の3つの最新ガイドラインについての翻訳を中心とし,その内容を日本に紹介した実にタイムリーなものである。これまで刊行されてきた疾患ガイドラインは,主にcommon diseaseを対象として,特に治療面での一定の方向性を示し,医療格差をなくすところに意義があったが,これらの間質性肺疾患については,多くの研究成果が蓄積されてきたものの,その病因,そして何よりも治療面での確立された見解に乏しい。よってその疾患概念の統一をはかり,比較的まれであるからこそ,多施設での病態,治療における知見の集約が急務であり,不完全ながら必然と生まれてきた経緯がある。
本書の意義は,やはり日本語で書かれていることで,広くわが国の医療関係者に読まれることが期待できる点にある。本書で扱われている疾患は厚生労働省特定疾患(難病)に指定され,その対応には難渋する場合が多い。実際,われわれも他の多くの医療機関から頻繁にこれらの間質性肺疾患についてのコンサルトを受けており,日常臨床の場で困惑している医師は多い。サルコイドーシスについては,わが国と欧米の研究者との交流からその疾患概念に大きな違いはみられない。ところが,長い間欧米との間で,その概念に解離がみられていたIIP,IPFについては,一般臨床医にとっては難解な印象がぬぐえなかったであろうが,この点についてもわかりやすく紹介している本書の意義は大きい。かつて日本のプロ野球でプレーし,「日本の『野球』と米国の『baseball』とは別のもの」と発言したメジャーリーガーがいたが,日本の「特発性間質性肺炎」と米国の「idiopathic pulmonary fibrosis」は,同じ疾患と考えていた日本の呼吸器科医は多かったはずである。
日本の臨床経験に根ざした訳注
さらに,本書の魅力はなんといってもその豊富な訳注にある。この訳注は,これらの領域でわが国をリードし,世界に向けてその研究成果を発信し続けてきた京都大学間質性肺疾患研究グループの豊富な経験があってはじめてできるものである。例えば,人種によってその臨床像,予後に違いがみられるサルコイドーシスにおいては,豊富な自験例998症例に基づいた適切な注釈(時には堂々と反論も交えながら)が,日本人であるわれわれの日常診療には大いに参考となる。また,IIP,IPFについても実際の臨床で直面する問題をガイドラインと照らし合わせながら適切に解説されている。本書が単なる訳本にとどまらず,ATSの原文以上の付加的価値があることを認識してほしい。役者(訳者)が違うのである。最後に,本文でも触れられているとおり,間質性肺炎の診療には臨床医,放射線科医,病理医の密接な連係が不可欠である。本書が,放射線科医,病理医の手元にもおかれ,これら難病のよりよい診療に役立てられることを期待したい。
B5・頁176 定価(本体5,000円+税)医学書院


確立された神経モニタリング法を図説した実用書
脳神経外科手術のための神経モニタリングアトラス片山容一,山本隆充 編集
《書 評》坪川孝志(前日大教授・脳神経外科)
「脳・神経手術モニタリング研究会」
 脳神経外科では手術の対象となる脳・神経は機能の局在があるうえに,再生能力が低い臓器であるため,手術に際して機能を有する脳・神経組織に侵襲が加わると機能障害が発生する危険がある。最近では,これに対処すべく顕微鏡下手術など術式の工夫に加えて,手術の支援法としてニューロナビゲーターや各種のモニター法が利用されている。
脳神経外科では手術の対象となる脳・神経は機能の局在があるうえに,再生能力が低い臓器であるため,手術に際して機能を有する脳・神経組織に侵襲が加わると機能障害が発生する危険がある。最近では,これに対処すべく顕微鏡下手術など術式の工夫に加えて,手術の支援法としてニューロナビゲーターや各種のモニター法が利用されている。
特に手術操作による機能障害発生に対する警告モニターとしては,以前より神経生理学的手法による神経モニタリング法が理論的にはもっとも信頼される方法とされながらも,手術室内での記録条件の劣化や施設間の方法の不統一といった問題のため信頼されるモニター法として確立されていなかった。こうした問題点の克服のために,編者の片山教授を中心に多くの脳神経外科医によって,平成11年より4年間にわたって,「脳・神経手術モニタリング研究会」を開催し,手術の内容別に,どの機能を守るために,どの電位をモニターするのか,また正確な記録のための条件などについて討議を重ねた結果,今日では手術中に発生する脳障害を防止するモニター法として,手術中の神経モニタリング法がもっとも信頼され,その価値も再評価されはじめた。
記録法や用語を統一し,モニターの信頼性を確保
こうした時期に,この「脳・神経手術モニタリング研究会」幹事の17人を中心にした分担執筆で完成したのが本書である。従来この分野は方法や用語が乱れていたが,本書では分担執筆であるにもかかわらず記録法や用語が統一され,常にモニターの信頼性の確保と実用性に視点を置いて解説されているのが特筆すべきことで,それが可能なのは4年間の「脳・神経モニタリング研究会」で指導的立場にある先生方の執筆によるためであろう。本書は177のよく選択された譜図をたどると,手術中の神経モニタリング法が身につくようにできているので,アトラスと題されているが,むしろ絵解き本ともいうべき特徴をもっている。
内容は,総論部分で手術中に利用される各種の神経モニタリング法の原理とモニターされた各基本電位が平易に図解されている。各論が本書の89%を占め,脳腫瘍の手術についても,従来の手術中神経モニタリング法の利用法とは異なり,中心溝の決定,運動や知覚機能の確保,言語領周辺手術,脳幹部手術・視神経周辺手術・聴神経周辺手術・頭蓋底手術など,手術の種類のみならず,手術の内容や目的によって,それぞれ何の神経機能保護に利用するモニター法を選択するかからはじまり,その電位変化の意義について,図を中心に解説されている。同じように,脳血管,脊椎・脊髄,機能的脳神経外科手術についても病態や手術法の違い,手術の各段階でのモニター法の選択とそれら電位変化の意義が図説されている点が,本書でなければできなかった特異点である。
本書は従来信頼性のなかった手術中の神経モニタリング法を,病態別,手術の内容別,さらには手術操作の段階別に,それぞれのモニター法を選択していくことで,モニターとしての信頼性が再確認できるよう構成され,またその利用法を図説した実用書である。脳神経外科の手術は徹底的かつ安全で,低侵襲でなければならない。こうした時代の脳神経外科医にとっては,必読の書となるにちがいない。
B5・頁192 定価(本体10,000円+税)医学書院


質問形式で整理されたクリティカルケア定番の1冊
重症患者管理シークレット 第2版Polly E. Parsons,Jeanine P. Wiener-Kronish 著/島崎修次,村田厚夫 監訳
《書 評》杉本 壽(阪大教授・生体機能調節医学)
本書は重症患者管理に必要な知識を質問形式で提示し,その解答を簡潔に記す形式を取っている。質問数は1973問にも及び,必須の知識はほぼ網羅されている。医療実務の中心的な担い手である主にassistant professorクラスの若手およそ100名が,それぞれの項目を分担執筆している。
知識の「幹」と「枝葉」を見分ける
医学領域の知識量は膨大であるが,医療実務に必要なコアとなる知識量はどの領域もそれほど多くはない。ところが初心者には「幹」と「枝葉」との区別がつかないため,それだけ無駄な苦労も多くなる。一般に学習効果がS状カーブを描き,初期の立ち上がりが遅いのはこのためである。本書では質問という形で重症患者管理に必要な知識の「幹」をあらかじめ示してくれているのではじめから効率良く知識が修得できる。本書の使い方としては,質問を読んで,すぐに解答を見るのではなく,まず自分なりの答えを考え出した後に解答と照らし合わせたほうが,学習効果は一層高まるであろう。医学は日進月歩とは言え,解決していない問題もまだまだ多い。これらの定説がない項目は,避けられるか,あるいは著者の意見に偏った取り扱いをされることが多いが,本書では論争という形でそれぞれの意見を公平な立場で紹介している。
倫理面にも重点をおいた内容
医療実務に医学知識や医療技術は必須ではあるが,それだけでは十分ではない。とりわけ重症患者管理の領域では倫理的な問題に遭遇することが多い。本書では倫理を大項目に別立てし,大きく取り扱っている。アメリカと日本では社会事情や法律が異なるため,日本ではそのまま当てはめることができない点もあるが,参考になる点も多い。最後に,本書の訳者10名はいずれもわが国の救急医療の中堅担い手であり,救急医療の実務に精通していることもあってか内容的にも的確であり,こなれた日本語表現が用いられている。翻訳書にありがちな読み取りにくさはない。
A5変・頁700 定価(本体8,200円+税)MEDSi


コンパクトにまとめられた症例で,精神科診断学を整理
DSM-IV-TRケースブックRobert L. Spitzer,他 原著
高橋三郎,染矢俊幸 訳
《書 評》武田雅俊(阪大教授/プロセシング異常疾患解析学)
 本書はDSM-IV-TRの改訂にあわせて出版された症例集である。成人145症例,小児及び青年期37症例,多軸評定のための症例10症例,世界各国からの21症例,歴史的22症例の合計235症例が記載されている。ご承知のように米国精神医学会は,1980年にDSM-III,1987年にDSM-III-R,そして1994年にDSM-IVを発表してきており,2000年にはDSM-IV-TRとしてテキストが改訂されたが,この改訂にあわせて出版された症例集が本書である。収められた235症例のうち42症例はDSM-IVの改訂時に加えられたものであり,本症例集で新たに加えられた症例はなく,考察が一部分改訂されている。
本書はDSM-IV-TRの改訂にあわせて出版された症例集である。成人145症例,小児及び青年期37症例,多軸評定のための症例10症例,世界各国からの21症例,歴史的22症例の合計235症例が記載されている。ご承知のように米国精神医学会は,1980年にDSM-III,1987年にDSM-III-R,そして1994年にDSM-IVを発表してきており,2000年にはDSM-IV-TRとしてテキストが改訂されたが,この改訂にあわせて出版された症例集が本書である。収められた235症例のうち42症例はDSM-IVの改訂時に加えられたものであり,本症例集で新たに加えられた症例はなく,考察が一部分改訂されている。
困難な精神科の症例をポイントを押さえて呈示
他の診療科と比べても精神科の症例呈示は難しい。必要十分な情報をコンパクトにまとめるという課題は時として困難であり,豊富な知識と十分な経験とがあって初めて可能となる。初学者の頃,症例を呈示する時に,どこまで詳しく記載するかを悩みながら,なかなかコンパクトにまとめることができなかったことを思い出す。コンパクトにまとめる作業は,「この部分を割愛しても大きな間違いが起こらない」との判断に基づいて行なうが,このような判断を下すためには,精神科の疾患全体についての包括的な知識と,同僚の精神科医のレベルについての理解とが必要である。このような条件を満たした症例呈示のモデルが本書には多数示されている。本書を通じて,症例呈示の仕方を学ぶことができる。1-2頁にコンパクトにまとめられた症例は,読者にもクイズを解く時のような知的作業を要求する。各症例について,自分なりのDSM-IVの診断を考えながら読み進み,考察で提示された診断と一致した時にはクイズを解き終えたような安堵感が広がる。また,解答に至るプロセスについての考察の筋道が,自分の考えの筋道と一致している時には,ある種の満足感を味わうことができる。
このような豊富な症例を通覧してみて非常に勉強になった。例えば,DSM-IVでは,小児・青年期に初めて診断される障害が一番に記載されており,その分類として,精神遅滞,学習障害,運動能力障害,コミュニケーション障害,広汎性発達障害,注意欠陥・破壊的行動障害,摂食障害,チック障害,排泄障害などに分類されていることはご承知のとおりである。広汎性発達障害の下位分類として,自閉性障害,レット障害,小児期崩壊性障害,アスペルガー障害などがあるが,小児崩壊性障害とは,3歳を過ぎてから出てくる自閉性障害に相当するものであり,その予後は自閉性障害と比較しても極めて悪いということを学んだ。症例とその考察を通読することにより知識が整理されてくる。
文化圏により異なる診断基準にも言及
筆者が特に興味深く思った症例は,世界各国からの症例と歴史的症例である。世界各国からの症例として,それぞれの文化圏に特徴的な病態を呈する症例が呈示されており,DSM-IVの診断基準として頻用される「その人の属する文化から期待されるものより著しく偏った」内容が,具体的に文化圏によりどのように異なるかが解説されている。日本からの症例は「対人恐怖症」であるが,やはり,多くの人が指摘するように,この病態はDSM-IVにはなじまないのであろう。考察で述べられているように,DSM-IVに当てはめようとすると,患者が有する「自分が他者に不快な感情を引き起こす原因になっている」との先入観が,妄想,優価観念,恐怖のいずれかをまず決めることになる。患者はこの根拠のない観念に確信を抱いているだけでなく,患者の行動に著しい影響を及ぼしていることから,妄想と考えざるを得ない。そして,妄想が唯一の精神症状であることから,その妄想が,属する文化圏においてまったく起こり得ない奇異な内容かどうかを考えてみる。すると,日本という文化圏では必ずしも奇異とは受け取られてはいないことから,統合失調症は除外され,妄想性障害,特定不能型の診断になるとしている。対人恐怖症を妄想性障害に位置づけることにはためらいが大きいが,このような観点から病態を見直していくと得られるものもあるかもしれない。診断体系の歴史的変遷も凝縮
この症例集のエッセンスを味わいたいと思われる読者には,まず歴史的症例22例を読まれることをお勧めする。自分がこれまで教科書などで見聞きしてきた代表的な症例についてのDSM-IVの診断名と,その診断に至る道筋が示されている。とくにEmil Kraepelinにより記載された11症例については,精神科診断学の黎明期から現在の診断体系に至るまでの歴史的変遷を凝集して味わうことができる。DSM-IV-TRは精神障害の分類のための診断基準の羅列であり,通読するという性質のものではないが,参照するたびに本書の症例をあわせて味わうことになり,DSM-IV診断体系が咀嚼され,読者の血となり肉となることが期待できる。A5・頁596 定価(本体8,500円+税)医学書院


消化器内科専門集団の経験を濃縮した,若手医師必携の書
消化器内科レジデントマニュアル東京大学消化器内科 編集
《書 評》藤原研司(埼玉医大教授・消化器・肝臓内科)
忙殺されている日本のレジデント
 医学・医療の進歩はめざましい。良質な最先端医療を受けることは誰もが望んでいる。しかし,わが国においては1ベッドあたりの医師や看護師数が米国の5分の1であるにもかかわらず欧米並の医療提供が求められるため,最近は医療者の労働過重が加速度的に強まっている。特に医療の最前線を担うレジデントは,現場での経験を通して学ぶ以外に時間的な余裕はほとんどない。加えて,わが国においては世界に誇る国民皆保険制度により,すべての国民は容易に希望する病院を受診できるため,大病院への患者集中が年々高まっている。このため医師の診療時間も限られ,レジデントにとってはマニュアルを手に診療することが効率的,実際的となる。
医学・医療の進歩はめざましい。良質な最先端医療を受けることは誰もが望んでいる。しかし,わが国においては1ベッドあたりの医師や看護師数が米国の5分の1であるにもかかわらず欧米並の医療提供が求められるため,最近は医療者の労働過重が加速度的に強まっている。特に医療の最前線を担うレジデントは,現場での経験を通して学ぶ以外に時間的な余裕はほとんどない。加えて,わが国においては世界に誇る国民皆保険制度により,すべての国民は容易に希望する病院を受診できるため,大病院への患者集中が年々高まっている。このため医師の診療時間も限られ,レジデントにとってはマニュアルを手に診療することが効率的,実際的となる。
日常診療において消化器系疾患はもっとも多い。全国の医療施設を10月のある1日に利用した患者の実態を推計した厚労省の調査によると,平成11年の患者数は入院148万人,外来684万人である。この両者につき15歳未満を除いて傷病別にみると,消化器系疾患は働き盛りである35-64歳の年齢層にもっとも頻度の高い疾患である。その内訳は,20歳代から増加傾向にある上部消化管疾患と肝疾患が35歳以降には次第に増え,また,それらの悪性腫瘍や下部消化管の悪性腫瘍が高齢となるにつれ増えている。平成11年の死亡者総数は98万人で,第1位の悪性腫瘍は全死亡者数の30%であり,そのうち消化器系疾患は全体の56%を占めている。しかも,悪性腫瘍以外の消化器系疾患として日常診療でもっとも頻繁に遭遇する胃潰瘍,十二指腸潰瘍,肝疾患,ヘルニア,腸閉塞のすべてが主要な死亡原因となっている。これらも含めると5人に1人が消化器系疾患で死亡していることになる。かくして消化器専門医には,高度の医学・医療の知識と技術面での手腕,さらには豊かな人間性がもっとも問われることになる。
豊富な診療経験にもとづいた実際的な内容
この度出版された『消化器内科レジデントマニュアル』は,東大消化器内科で現在活躍中の専門医が中心となって執筆されたものである。東大消化器内科では,1つの基本理念を掲げていると聞いている。常に患者の立場を守り,肉親の思いを抱いて,ともに病魔に闘いを挑むことを信条とする専門集団をめざしているのである。しかも,いまだ難治とされる疾患における最先端治療,特に肝細胞癌の経皮的治療や消化管・胆膵系悪性腫瘍に対する内視鏡的治療などは,おそらく世界的にももっとも数多くの症例において行なわれている施設の1つである。本書には,これらの豊富な診療経験をもとに,わが国において注目されているすべての消化器系疾患にかかわる診断の実際と手技や留意点,症候と診察面での要点,各種消化器系疾患の特徴や治療におけるポイントが重点的に網羅されている。事項によって,特に新しい検査・治療法についての患者への説明方法も,膨大なデータからのエビデンスをもとに記載されている。また,索引を充実させ,欧文の略語にはフルスペルが併記されていることも本書の特徴である。いわば生きた現場の経験が詰まった,若手医師必携の書である。
B6変・頁412 定価(本体4,500円+税)医学書院
