【座談会】
表情を読む
チャールズ・ベルとチャールズ・ダーウィンの表情研究
 岡本 保 (富坂診療所・神経内科) |  長野 敬 (自治医科大学名誉教授) |  山鳥 重<司会> (東北大学教授・ 高次機能障害学) |
『表情を解剖する』刊行の意義
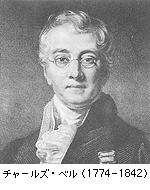 山鳥<司会> この度,「神経心理学コレクション」のシリーズとしてチャールズ・ベルの『表情を解剖する』(医学書院刊)が発刊されました。まず最初に,翻訳に当たられた岡本先生からその経緯をお話しいただけますか。
山鳥<司会> この度,「神経心理学コレクション」のシリーズとしてチャールズ・ベルの『表情を解剖する』(医学書院刊)が発刊されました。まず最初に,翻訳に当たられた岡本先生からその経緯をお話しいただけますか。
岡本 きっかけは,このシリーズの編者のお1人である河村満先生(昭和大)が,「非常に古いけれどもおもしろい本がある」と教えてくださったことでした。
読んでみると,表情というものが医学という科学と芸術を接点とした領域で描かれており,ベル自身の絵も素晴らしくて,見るだけでも楽しい本でした。河村先生から日本語になればとお勧めいただき,どこまでできるかわからないけれどもやってみようと思ったわけです。
河村先生からお借りした第4版は1847年にイギリスのマレー社から出版されたものです。初版本と比較してみますと図は同じものもありますが,別の形で綺麗になって増えているものも多々ありまして,それを比較するだけでも興味深いものでした。
山鳥 初版は1806年で,その間に内容も変わり,量も増えていますし,絵も変わっています。ベルが力を入れていたことがよくわかります。
岡本 ベルは1804年にエジンバラからロンドンへ居を移していますので,エジンバラ時代にベルが蓄積してきた仕事や経験が初版に集約されていると思います。第2版が1824年に出版されていますが,題名も変えられています。初版は「Essays on the Anatomy of Expression in Paintings」ですが,第2版から「Philosophy」という語を加え,そのニュアンスを加えています。
内容を比べますと,第3版を出版する前の1840年に,ベルは長年希望していた南イタリアへ旅行しており,芸術的な要素や趣向が加わっています。絵はもちろんですが,本書の注の中にもイタリアの論文からの引用をつけ加えています。その意味で初版から抱いてきた思いを,半世紀かけて組み上げたと言ってよいと思います。
山鳥 訳し終えて,科学史上大切なポイントはどういう点だとお考えでしょうか。
岡本 最も感銘を受けた点は,医学と芸術・美術との接点です。ベル自身が偉大な芸術家であったことを示す絵がたくさんあります。それを見ながら文章を読むことで,どの筋肉がどういう動きをして表情が生まれるのかが手にとるようにわかります。しかも複雑で深い内容の情動までも含めて記載しています。
さらには,例えばシェイクスピアなどを引用しながら,医学・芸術・美術・文学のすべてを含めた大作になっています。
山鳥 こういう見方は,最近はなくなっているのが残念ですね。
ダーウィンとベル
山鳥 長野先生にこの本をご校閲いただいたわけですが,ご感想はいかがでしょうか。長野 ベルと言えば,科学史では「ベル現象」にとどまらず,「前根後根論争」というベル=マジャンディ(Bell vs Magendie)の論争はよく知られているわけですが,この機会がなければ,ベルのこういう側面は知らずにすぎてしまったと思います。
後ほど話が出ると思いますが,ダーウィンも表情の本を書いています。そこでは率直に,「これまでいろいろな本を読んだけれども,昔のものはほとんど役に立たない。本格的なのは……」とベルのことを高く評価しています。ただし,そこには立場の違いがあるわけで,それはまたおもしろいのですが,ダーウィンの仕事のほうでも,表情の本は異例と言えると思います。
ダーウィンと言うと『種の起原』が代表的で,表情の本はあまり取り上げられません。今回通読し,ベルとダーウィンを比べることで教えられるところがありました。
山鳥 ベルとダーウィンは対照的なところがあると思います。先生がおっしゃったように,ダーウィンはベルに刺激を受けていますね。
例えば『The Descent of Man』(『人間の由来』)のイントロにはベルの仕事を紹介して,「この素晴らしい解剖学者は,人はある種の筋肉をただ情動表現の目的のためにのみ与えられていると主張する。この考えは人が下等な動物から進化したという考えに反するので,後に表情についての別の本で取り上げたい」と書いています。
長野 そうですね。『人間の由来』という本そのものが進化論の一環で,自然淘汰の話などがあって,アプローチもだいぶ違います。そこからスピンオフして別の1冊になったのが『人間と動物の情動表情』という感じですね。
ベルの本についてダーウィンは,「第2版より大幅によくなった第3版を参考にした」と言っています。
山鳥 進化論的な観点から,根本的な違いはどこにあるのでしょうか。
長野 ひと口で言うと,系統発生ということです。ダーウィンの場合は動物との連続性が基本テーゼになっています。ベルの場合は,人間と動物はずいぶん違い,ある意味で表情というのは人間にしかない。動物の場合にはただ気分の反映というものが出てくるだけです。連続させながら峻別しているところがある。それをダーウィンはあくまでつながったものとして理解したい。それが違うところですね。
「神のデザイン」
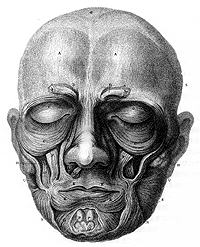 山鳥 岡本先生も注意深く訳されていますが,ベルのキーワードの1つに「デザイン」という言葉があります。これは「God's design」ということです。ヒトというのは神に近い。つまり,きわめて完璧に近いレベルに作られており,そのデザインにあわせて筋肉や表情が創られると言っている。そういう意味で「神のデザイン」というものがあって,いろいろなものが創造されてきている。その意味で,ダーウィンとはまったく逆です。
山鳥 岡本先生も注意深く訳されていますが,ベルのキーワードの1つに「デザイン」という言葉があります。これは「God's design」ということです。ヒトというのは神に近い。つまり,きわめて完璧に近いレベルに作られており,そのデザインにあわせて筋肉や表情が創られると言っている。そういう意味で「神のデザイン」というものがあって,いろいろなものが創造されてきている。その意味で,ダーウィンとはまったく逆です。
長野 ダーウィンにとって,「デザイン」という言葉は反語的なキーワードで,科学史ではペイリー(Paley)が『自然神学』に書いた有名な話があります。
「野原に時計が落ちていた。こういう精巧なデザインがヒトの手によってできるものではなくて創り手がいる。時計よりもはるかに精巧な生物,まして人間はデザインなしには創られない。デザインを行なったのは創造主である」。そういう言い方で,創造主とデザインというものがつながっていて,ダーウィンはそれに非常に反発を覚えて『種の起原』を書いたのだと思います。
山鳥 ベルも,ペイリーを最初のほうで引用していますが,どちらかというとペイリーの考えに従う立場をとっています。そういう点でもダーウィンとは違う。観察はどちらも鋭いのですが,つながりをどこにみるかとなると,ベルは「ゴッド」で,ダーウィンは「細胞」から始まっているとするわけです。つまりダーウィンにはコペルニクス的転回があるということですよね。
長野 2人の科学史的な役割をみますと,ベルは生理学者,解剖学者として有名です。そういう立場とこの本との質的なつながりもあるし,違いもあると思います。ダーウィンの場合にもそれがあります。ベルの場合にはどうでしょう?
チャールズ・ベルの表情研究
岡本 「ベルの表情論」というと,突拍子もない印象を持たれるかもしれませんが,彼の研究の流れとして必然的に生まれてきた要素があると思います。と言うのも,初版が出て間もない1811年に,「新しい脳解剖に関する概念」という論文を発表しています。それは,今までは1つの神経が2つの役割,例えば運動も感覚も司るという通説に対して,ちょうどハーヴェイ(Harvey)の血液循環論が従来の概念をひっくり返したのと同様に,ベルは1つの神経は1つの役割を果たすものだと主張します。
1本の神経は運動神経か感覚神経のどちらかだと言います。ベルは神経系に関して生理学と解剖学を駆使して業績を残しましたが,1821年には解剖学的な立場から後に「ベル神経」と呼ばれる「内呼吸神経」と「外呼吸神経」について述べています。内呼吸神経は今で言う横隔神経,外呼吸神経は前鋸筋のほうへいって呼吸を支配するものですが,それを正しく解剖学的に追求しました。
同じ1821年に末梢性の顔面神経麻痺=ベル麻痺を記載して,脳神経,特に顔面神経に関する詳しい解剖学を残しています。それ以前は,第 V 脳神経と第 VII 脳神経が非常に曖昧に使われていたのを明確に区別し,呼吸・表情に関するものは顔面神経の仕事だと述べています。
その後1823年に,先ほど話が出た「神」との関係だと思いますが,人が祈る時には目は天蓋を向き,眼球は上転して白目が見えることに関連づけて,後の「ベル現象」の元になるものを発表しています。
そういう一連の流れがあって,呼吸について長年研究してきたわけで,没後出版になってしまったものに,アレキサンダー・ショウ(Shaw)という親戚にあたる人がその後を継いで,ベルが追究していた神経について補充しています。その中で「呼吸神経論」というのを述べていまして,進化論とも結びつく点かもしれません。
第1の神経を「原始系神経」と呼び,移動や把握,ものを食べるとかで脊髄神経が主に働き,人間でなくても,それ以下の動物にも共通しているものとしてまとめています。第2番目として非常に特徴的なものが「呼吸系神経」であって,呼吸や発話,言葉に関係し,それが人間に特徴的であると述べています。
そういう一連の流れの中で,ベルの言う呼吸系神経が,表情を司る大切な神経系だということがわかったために,この第4版で集大成したのだと思います。
| ●ベル冠名用語と主要業績(『表情を解剖する』より)
◆ベルの法則(脊髄神経の前根は運動性で,後根は感覚性)
|
「マインド」について
長野 ベルの関心は確かに神経ですが,むしろ基本には脳の機能への興味から出発したという気がしますが,いかがでしょうか。山鳥 おっしゃるように,『表情を解剖する』の中では,表情は「マインド(mind)」がその内容を外へ向けて表出する道具として存在する,と考えられているようです。
「マインド」という,「神に近いものを翻訳するためのシステムとしての表情」という発想があるように思ったのですが,いかがでしょうか。
岡本 おっしゃるとおりだと思います。直接的には表現されていませんが,行間にかなりそのニュアンスが伝わってきます。その点で神を,彼自身もこの中で表現していたと思います。
長野 一般生物学で言いますと,脳ではなく脊髄が前根後根で運動と感覚を受け持っているということになりますが,そういう形で出てきたわけではなく,むしろ運動のほうははっきりしているけれども,脊髄で言えば後根の役目は,ベルにとってはあまりはっきりしていないわけです。
そのあたりで,マジャンディが出てくるわけで,彼は別にベルを否定しているわけではなく,むしろベルのほうが気にしていたのではなかったかと思います。
岡本 ベルは,後根は小脳のほうに入っているのであって,感覚に関係ないと言っていますね。
山鳥 呼吸神経という考え方はおもしろいし,神経の走行を発見したのはすごいです。呼吸というものが表情と関係している。表情を翻訳する前段階に呼吸があると考えていますね。
マインドがあり,呼吸があり,表情がある。そういう意味で,呼吸を精神と表情の媒介項として重視して研究しているところがあります。そういう発想もおもしろいと思います。現在でいうと神経系を媒介にして,ソマティック(somatic)な運動神経へ翻訳するというステップを考えていることになるのかもしれないですね。
岡本 顔を赤らめたり,青ざめたりするのもやはり呼吸器系・循環器系に関係する表現であるとベルは言っていますね。
山鳥 間に呼吸というものを置いて,表情を全身的な表現の一部と捉えていることがおもしろいと思います。それが最もよく出ているのが「瀕死の剣闘士」の彫刻についての解説です。グラディエイターが右手で地面に自分の身体を支えて,腕を突っ張ってすごく苦しい表情をしている。これを呼吸系の生理からみごとに説明しています。苦しい時に息をつくためには頑張って胸郭を張らなければならない。胸郭を膨らませるためには,腕の支えがないと駄目だ。だからそこに力が入る。瀕死の人にそんな力が出るのかと疑問に思う人がいるかもしれないけれども,それが自然だということでしょう。
全身から表情を捉えているという立場がすごいですね。今の生理学は,むしろ表情というと顔だけを問題にしている。ベルの場合は,全身を視野に入れて変化を研究しているわけで,その見方においてずっとすぐれているような気がします。
「イクスプレッション」と「フレーム」
長野 イクスプレッション(expression)を「表情」と訳すと,おっしゃるようにだいたい顔になるのですが,expressは「情」が「表出」されるのですから,全身のどこに出てきてもよい。ダーウィンも顔だけではなく,全身的な捉え方をしていますね。ただ,エソロジー(ethology=動物行動学・行動生物学)の立場から言うと,人間に焦点を当ててしまったから顔が中心になっている。人間のように顔つきがはっきりしている場合には,確かに顔が大事になってきます。その点が特に強調されたのが,ふつうに世間で言う表情だと思います。
山鳥 大変正確なご指摘だと思います。ベルもダーウィンもイクスプレッションであって,facial expressionとは言っていません。イクスプレッションに相当する日本語は「全身表現」ですね。
岡本先生はこの本の中で,「ベルはマインドに対してフレーム(frame)という言葉を使う」と言われています。このフレームの訳語にもいろいろ工夫されています。フレームというのはマインド以外のもの,禅宗でいう「袋」です。「汚い皮袋」という禅宗の言い方がありますが,それをフレームという言葉で表わして,そのフレームが表わすものがイクスプレッションということですね。
ベルに関して見落としてならないことは,ヒトと他の動物との間に距離をおいていることです。根本的にヒトとヒト以外という概念が牢固としてあると思います。
特に押さえておかなければいけないのは,黒人,特にAfricanをwhiteとは違う存在として見ているところで,これはダーウィンとは決定的に違います。おもしろいのは,われわれ東洋人はベルの考え方のどこにもないということです(笑)。そもそも存在しない。whiteといわゆるnegro(black)だけで,アジア的存在はほとんど視野に入っていません。
長野 科学史には必ず出てくることですが,ダーウィンはその点で当時としては進んでいたと思います。ビーグル号で南米へ行った時にフェゴ島あたりで,原住民が海岸で裸で踊っているのを見て,「やはり違う人種だ」というような印象を持ったりしますが,これはしかたがないことですね。
翻訳上の問題点
山鳥 200年前の英語を訳すのは大変だったと思いますが,そのあたりの苦労話を少しお聞かせいただけますか。例えば,先ほどのフレームという語はどのように訳されましたか。
岡本 いろいろ言い換えました。先ほど山鳥先生がおっしゃったように,「外郭」というのがありますし,具体的に「骨格」や「筋肉」と訳したところもあって,2-3変えたところがあります。
山鳥 「デザイン」はどうでしたか?
岡本 先ほど先生がおっしゃったように神様が人間を創る時という意味もありますし,画家が使う絵のもとになるものという意味で「図案」としたところもありますし,もう少し高尚に「何か訴えるもの」という意味を持たせて工夫したものもあります。
山鳥 今は現代の心理学に侵されていますから,表情と言ってもせいぜい6つぐらいのパターンに限ってしまい,かなり荒っぽく考えています。ところがベルは,「恐怖」ということ1つにしても,「fear」「terror」「horror」ときっちり分けて,その表情はすべて違うとしています。明らかに心理状態としては違うわけです。
長野 ダーウィンのアプローチは,「表情は習慣が固定して,それが反復されると遺伝する」というわけです。現代の言葉で言えば,獲得形質の遺伝ということになります。これは『種の起原』でも,その立場を認めていないわけではないですね。
ただ,『種の起原』ではそれは副次的な要素で,やはり競争によって生物は種が変わっていくし,枝分かれすることをメインテーマにしていますが,彼の表情の本には,淘汰のメカニズムのことはほとんどなく,ごく自然に,くり返された表情が遺伝するようになって,後は生まれつき出てくるという言い方になります。
ダーウィンの表情論
山鳥 ダーウィンの表情論に入りたいと思います。ダーウィンの表情論では,進化論の考えで言う,「セレクション(selection)」ということがあまり出ていないとおっしゃったわけですが,私の持っている1965年の再版では,コンラッド・ローレンツ(Lorenz)がイントロを書いています。ローレンツは「ダーウィンはエソロジーの父だ」と言って,「ビヘイビアー(behavior)もオーガン(organ)と同じように遺伝するという考えは大事だ」という評価をしています。そのへんはどうですか。
長野 その通りだと思います。ただ,そのビヘイビアーが遺伝するようなものとして,いわば生物の身についてきたメカニズムですね。ローレンツはそのメカニズムを気にしないで,エソロジーのレベルで論じています。そういう意味では,ダーウィンの本はぴったりです。要するにヒューマン・エソロジーの源流だと評価している例はたくさんありますね。
山鳥 行動自体が遺伝するというのは,夏目漱石のエッセイにそういう話がありましたね。どこかの骨董屋の親父が座っている。何十年か経ってそこを通ると同じ親父が座っている。考えてみれば,同じなわけはないので,息子が座っているというわけです(笑)。行動が遺伝するというのは,新鮮な気がしたのです。進化論では,そういうものは遺伝しないということですね。
 |  |  |
「エソロジー」について
長野 エソロジーとの関係ですが,ローレンツと一緒にノーベル賞を受賞したティンバーゲン(Tinbergen)はローレンツよりも少し実験的なアプローチをしました。例えば,親鳥が戻ってきた時に雛鳥が突っつくのは,親鳥を認識しているのではなく,嘴のある模様を認識して,それを突っつくと自動的に餌がもらえるからだとデータを取って解析したのです。親鳥の先に何か模様がついているということ自体が1つのイクスプレッションだということです。それに対して雛鳥が反応するというふうに,個体と個体との間の広い意味の行動的な関係がエソロジーだというわけです。
山鳥 ビヘイビアーからどのくらいマインドが想像できるかということですね。
長野 相手の「マインド」あるいは状況を窺い,それに対してこちらが反応するための窓口として,全身のイクスプレッションの中でも,表情というのは非常に大事だということです。こういうことを初めて科学的に扱った1人が,ベルということになるでしょうね。
「ダーウィンの感情表現」について
山鳥 そのベルの表情研究を土台に,自分の進化論の立場から表情を分析したわけですが,行動進化論の視点で見たのがダーウィンの画期的なところだと思います。長野 確かにそうです。ダーウィンというとすぐに分子遺伝学に通ずる「ネオ・ダーウィニズム」がクローズアップされますが,意外に注目されていない点ですね。大変大事な本だということを改めて感じました。
山鳥 「神経心理学コレクション」のシリーズに本書を入れたのは,神経心理学という,「人間の心というのは基本的に脳表現である」という立場から見ると,心を表現するものとして,姿勢や表情は言語などと同じくらい大事だからです。そういうものをトータルに扱う方法論の1つとして,進化論的な方法論というのは今も大事だと思います。むしろ最近はこういう点が見落されているという気がします。
長野 入江重吉さんが書かれた『ダーウィニズムの人間論』(昭和堂)は,ダーウィンの感情表現に関する一般原理は「(1)有用な連合性習慣の原理」,「(2)対照の原理」,「(3)最初より意思から独立な,またある程度まで習慣から独立な神経系の構造による動作の原理」とまとめています。
第1の原理は一定の心の状態のもとで,それを満足させるような動作や,顔つきといったものが起こって,それが身についていき習慣が遺伝で固まる。
第2の原理は,それと反対の感情,心の動きが起こった時は,顔つきや動作そのものには意味がなくても,赤と黒,プラスとマイナスのように反対の動作が起こる。思いつきですけれども,例えば怒る時に拳を振り上げるのは,ダーウィン的に言えば動物が飛び掛かる時の姿勢なので(第1の原理),なだめる時に,「ナアナア」と言って腕を水平に「セーフ」の形に広げるのはその逆の第2の原理から出てくることになります。
山鳥 ダーウィンは,イヌなどの攻撃の表情とサブミッション(submission)と言って,負けた時の動きが正反対であることをうまく捉えていますね。
長野 それが相反の原理ですね。それから第3の原理はもう少し神経生理学的な整理の仕方ですね。
山鳥 そうですね。岡本先生が最後の解説のところで紹介されておられますが,この3つの原理はよく考えられていると思います。ただ,先生がおっしゃるように,こういう流れで行動を見ることが,その後出ていないのではないでしょうか。
長野 ただ,心理学の分野ではけっこうあります。この本にも紹介されていますが,エックマン(Eckmann)は「普遍性のテーゼ」で,いまのような見方でいろいろなパターンが全部説明できるとダーウィンを高く評価しています。
ところが,J.ラッセル(Russell)という人は,例えば文化的・社会的なコンテクストで,同じ感情でも表出のされ方はずいぶん違ってくるというようなところがあまりカバーされていないので,普遍的と言うには限界があると言っています。
山鳥 ダーウィンの書いていることは伝わってはいるわけですね。
『ダーウィン・ウォーズ』について
山鳥 長野先生は最近『ダーウィン・ウォーズ』(青土社)という本をお訳しになられましたが,最近の進化論の状況についてお話しいただけますか。長野 ダーウィンの表情の話は生物学の主流には乗らずに,自然選択という部分がクローズアップされてきたわけです。遺伝子がわかる以前から,とにかく「遺伝質」の変化によって進化していくという筋書きができ,生物学者はそれを信じるようになってしまったわけです。
最大のネックは遺伝子でした。遺伝子はメンデル以来,形式的な伝わり方は解析されてきたのですが,正体がわからない。それが,「DNAの二重らせん」という実体がわかり,その塩基の変化が突然変異であると言えるようになったわけです。
最初は突然変異の対象となるのは,フィジカルなものとして捉えられる,身体的な変化だけだったわけです。しかしそれが広がって,いろいろな行動が動物ではわかってきた。また,それと人間とのつながりについては,基本的に動物と人間に変わりはないことが,分子遺伝学が進むにつれて強調されて,モノー(Monod)に言わせると,「大腸菌で真実であることは象でも真実である」ということになる。
これは少し言いすぎだと思いますが,それをさらに伸ばせば,象で真実であることは人間で真実だということになってくるわけで,広い意味では人間までカバーできる,という一般観念があるわけです。そこにもう1つ,先ほどのエソロジーが近代化してきて,行動は形質であって遺伝するというのはローレンツも言ったわけですけれども,遺伝するのだったら,やはり遺伝子で決まるだろうという一種の観念主義的な発想が強力になって,そこに「利己的遺伝子」というドーキンス(Dawkins)のキーワードが合流することになりました。
ダーウィン的な競争の世界で生物がせめぎあって生きているとすれば,自分に損になるようなことを生物はするはずがない。ある個体が遠慮深い行動をしたとすれば,その個体が持っている遺伝子は,その個体と一緒に子孫を残さずに断絶してしまうのだから,その観念を遺伝子までもっていって,実際にある行動を,動物,さらには人間に取らせているのは遺伝子であるというものです。
山鳥 ドーキンスのキーワードの1つは,「個体は遺伝子の乗り物である」。つまり,今残っているものは,勝ち残ったのであって,そうでないものは消えてしまうということですね。利己的なものだけがいま残っているのだということですよね。
長野 これはよく攻撃される言い回しですね。ドーキンスの使った「利己性」というのは,確率的に遺伝子が次の世代まで残るストラテジーが伝わりやすいからというだけのことですが,個体の行動としての利己主義とか博愛といったレベルと,遺伝子のレベルの話がどうしても混乱するのです。
山鳥 それは大事なところで,利己的というとindividualに還元して一般に考えられていますが,彼の言う「利己的」というのは,遺伝子部分が可能性としてそれを今に残しているものが利己的だということですね。そこに誤解が生じるもとがあるのでしょうか。
長野 それは,ドーキンスに言わせると誤解だというのですが,ああいう言葉を選択したということは,やはり罪の半分はドーキンスにあると思います。いわば,必然的に落ちるような落とし穴をしかけておいて,「落ちたほうが悪い」と言っているような感じがします。
山鳥 グールド(Gould)とドーキンスは,『ダーウィン・ウォーズ』では対極のように記載されていますが。
長野 この本の著者ブラウンは,グールドに対しての批判が少し強いですけれどもね。ドーキンスのほうは,自分の学説が目立たなければ生き残れないですから,最初は極端に遺伝子が中心であって,個体はそれに操られる乗り物であると強調しました。そうすると,個々の行動パターンも遺伝子で決まることになって,これは人間性の解体である,ということになる。人間の場合にはもっと全体的に見なければいけないというのはその通りですね。
これはいわば昔,社会ダーウィニズムとして否定されたものと同じようになる。この限りではブラウンも,グールドや,さらにその盟友でもっと立場のはっきりしているルウォンティン(R.C.Lewontin)に一理あることを認めています。
山鳥 そうですね。そっちへつながっていく危険性はありますね。
グールドは遺伝子中心以外のプリンシプルを主張しているのですか。グールドも基本的には遺伝子ですね。
長野 定向進化など,合理的な説明のつかないものに対しても,持ち出しているわけではありません。
例えば,「スパンドレル」という有名な概念があります。これはアーチ建築で,丸屋根と縦の柱の間にできる三角の隙間のことです。それはただ丸と棒の隙間に出てきたものだけれども,次第に装飾の上でなくてはならないものになったわけです。初めから設計されたように思われるけれども,いわば偶然の産物で,それが後から役に立つということになったものです。
山鳥 と言うことは,遺伝子だけが重要なのではなくて,フェノタイプ(phenotype)も重要だということになるのでしょうか。
長野 いまのスパンドレルの話は,建物ができなければ存在しないわけです。ですから,フェノタイプが組み合わさってできあがったシステムというものが大事だから,あくまでも個体レベルで見なければならないというわけです。
山鳥 全体としてのシステムが大事で,遺伝子だけというのはおかしい。そういう違いがあるのですね。
長野 そうです。ドーキンスも頭のよい人ですから,最近は方向転換しています。個々の遺伝子が利己的だと言って頑張って自分だけ勝手なことをすれば,遺伝子がシステムをアンバランスにして破壊してしまう。これは自殺行為で,利己性にならないから,お互いに仲よくしましょうというのが利己性であると,詭弁みたいですが,そう言っています。そこまでいくと,グールドとほとんど変わらなくなってしまいます。
山鳥 鮮明に方法論的に違うかというと,あまりよくわからないですね。
長野 ええ。進化のユニットとしては,個体がなくなって受け渡されるのは,生殖細胞の遺伝子だけだと言えばその通りですが,だから進化で支配的なのは遺伝子だけと言ってよいかという問題ですね。やはり,持ち主である個体全体を進化の単位としてみるか,というところで論争があったのですね。
さらに上のレベルで,ダーウィンも気にしていましたが,集団で生きている生物,例えばハチのような集団が進化の単位になり得るかという話が出てきて,これは理論的に否定され,個体が主だということになったのですが,今でもまだ尾を引いていますね。
それをもう一段下へずらすと,個体も遺伝子の集団だから,個体を丸ごとというだけの捉え方は粗雑で科学的でない。やはり伝わるのは遺伝子であるというもう1つの主張が出てきて,最後の対立はそこですね。ですが,ドーキンスのほうが戦略を変えて,「私は個々の遺伝子が勝手なことをするなどとは言っていない。それは誤解だ」と言う。そういうふうに開き直られると,その限りでは差が縮まってきたわけです。
そうなると,残った対立点は理論的というより,例えば「個体,ことに人間の場合に,個人をばらして考えるのはけしからん」という一種の理念ですね。「ヒューマニズムというものがある」,「それは思い込みであって科学的でない」とか,「結果として出てくるのならよいけれども,最初から観念を科学理論にかぶせるのは認められない」というところに対立点が移っています。
「ハーヴェイの血液循環論」との関係
山鳥 ところで,ハーヴェイの血液循環論がベルの表情論に影響を与えたのですか。岡本 先ほど申しましたように,ハーヴェイが「血液は体循環する」という画期的な概念を発表しましてから100年後の1811年にベルが,「新しい脳解剖に関する概念」と題した論文を公にしました。
それをハーヴェイに喩えたのはロンベルク(Romberg)という神経内科医です。彼は「ベルは,ちょうど200年前のハーヴェイと同様の人であり,その発見は同様の発見だ」と言ったということです。彼はベルを高く評価して,表情の本を含めていくつか翻訳しています。
ベルには生理学に多くの貢献がありますが,その中で筋感覚=muscle sense,第六感覚と言いますか,それを言ったのもベルが最初で,筋肉自体からフィードバックとして感覚が戻ってくる,筋肉にも自分自身を知る能力があると言いました。ロンベルクは最初それに目をつけて,臨床的にロンベルクの名をとって「ロンベルグ試験」というような,深部感覚を調べる試験法を初めて行なっています。いろいろな意味で,ロンベルクとのつながりがあったということです。
ベルは脳解剖や脳生理などの基礎的なことを19世紀前半にやっていたのですが,シャルコー(Charcot)も19世紀の半ば以降から神経学に取り組み,ロンベルクも後に神経学に貢献していて,臨床的な診療手技として得られるさまざまな方法を考え出すきっかけを与えたのがベルということになります。そういう意味で,表情のこととは別としても,神経学や神経生理学に与えた影響は大きいと思います。
長野 筋肉からのレポートというのは,今の言葉で言えば,筋紡錘からインパルスがくるという情報の流れを掴んでいたのですね。
山鳥 この本の岡本先生の解説の中に,ベルがお兄さんにあてた手紙などが紹介されていますが,目の神経は光を運び,耳の神経は音を運ぶ。舌の神経は味を運ぶ。心臓の神経は血圧の動きを運ぶ。そういう意味で,筋肉も当然筋肉独特の動きを運ぶであろう,という原理的な考えでいろいろ発見しているところで,そこがおもしろいです。やはり天才ですね。
「イタリア紀行」がもたらしたもの
編集部 ところで,第4版が決定的に違うのは,暗いエジンバラで育ったベルが,イタリアへ行ったことで引用に出てくる詩歌,それから図版,特に古代美術の点は異なることですが,その点についてはいかがでしょうか。岡本 若い頃から,彼は南方に憧れる気持ちが強かったようです。
当時,ヴィンケルマン(Winckelman)という新古典主義の歴史家が,「美術と風土と地理というものが非常に密接な関係にある」と言ったのです。北の寒風にさらされた地域では忍耐強く,宗教的に言えば,教会で黙々と祈る姿が思い描かれる。それに対して,南は開放的で,陽気で,裸で海辺にたわむれている人たちを見るだけで絵になると言う。教会の石段に倒れている乞食でさえも,彼が小さい頃から憧れてきたイタリアを象徴するような雰囲気をかもしだしています。
ベルは芸術家としても名高いわけですが,「スコットランドのホガース(Hogarth)」と呼ばれていた,イタリアで研修を積んだディヴィッド・アラン(Allan)と小さい頃から親交があり,絵に親しんでいたことが,イタリアへ行きたいという気持ちにさせた1つの要因かと思います。
イタリアの芸術や美術の中で,彼が最も感銘を受けたのは,ミケランジェロの彫像だったようです。「あれは解剖学的な知識がなければ絶対にできない仕事だ。姿勢にしても,動きにしても,筋肉の解剖をきちんと押さえていないと,実際にああいう力強い形で彫刻に現わすことはできなかっただろう」と言っています。自分が解剖学や生理学で学んできたことを,この芸術に接して再認識することが,ベルにとって大きな意味があったと思います。
それが最終的に第3版や第4版が内容的に豊富なものになったことに関係があると思います。また,南と北の気質,風土とその取り組み方の違いというものが,エジンバラで育ったベルだからこそ,なおさら心を南に向かわせて,そこでの吸収力にもつながったのだと思います。
長野 ダ・ヴィンチにはあまり注目してないですね。
岡本 ダ・ヴィンチについては,あまり重きを置いていないようですね。
山鳥 僕もミケランジェロが好きですが,ベルは解剖学的に,どの筋肉がどれだけ盛り上がっているとか,肩甲骨がどれだけ上がっているかということをきちんと見ているわけです。そして,その全体のバランスの取り方がノーマルよりも,あるところを強調しているからよけいに自然に見える,というような理詰めの観賞をしています。それがすごいですね。
おもしろいのは,「ダヴィデ像が口を閉じているのは変だ」と言うのです。ミケランジェロを崇拝していますが,「あの像はおかしい」と指摘しているわけです。「口をあけていないと,力は出ないのではないか」というわけですね(笑)。
しかし,本当に絵がうまいですね。
長野 みんながこの程度には描いたのですかね。
山鳥 ベルを読んでいると,ギリシャ時代の人も解剖を勉強していた可能性を感じますね。200年前にこのような本が出ていたことは驚きです。「Since Darwin」という考え方はありますが,「Before Darwin」というものはありません。そこから半世紀遡ったところで,ベルがこういうことを書いていたのは衝撃的です。
日本は明治維新の時より前に成立していた思想にはブラインドです。そういう点でも,この本を紹介するのは意味のあることだと思います。
(おわり)
