第9回日本消化器関連学会週間
DDW-Japan2001開催
「21世紀の消化器病学;継承と飛躍」をテーマに
 DDW-Japan2001(第9回日本消化器関連学会週間)が,さる10月17日-20日の4日間,京都市の国立京都国際会館,他において開催された。
DDW-Japan2001(第9回日本消化器関連学会週間)が,さる10月17日-20日の4日間,京都市の国立京都国際会館,他において開催された。
「21世紀の消化器病学;継承と飛躍」をメイン・テーマに掲げた今回は,第32回消化吸収学会(阪医大・勝 健一氏),第62回消化器内視鏡学会(慶大・北島政樹氏),第43回消化器病学会(滋賀医大・馬場忠雄氏),第39回消化器集団検診学会(早期胃癌検診協会・丸山雅一氏),第5回肝臓学会(国立病院長崎医療センター・矢野右人氏)の5学会が参加(いずれも,「日本」は略。カッコ内は会長)。DDW合同企画として,「生活習慣病と消化器」「消化器疾患におけるクリニカルパス」「医療事故-今問われているもの」「遺伝子診断の倫理的,社会的,法律的側面」,また特別企画として「ITが変える消化器病学」など多彩なプログラムが組まれた。

●ITが変える消化器病学
ブロードバンド時代のコミュニケーション
 |  |
総務省(旧:総務庁,自治省,郵政省)編「情報通信白書」(旧:「通信白書」)平成13年版は,「加速するIT革命-ブロードバンドがもたらすITルネッサンス」を特集し,「e-Japan戦略」や「e-Japan重点戦略」などを概説しているが,今回のDDWでは,「総合コンセプト“From Office/OR to Desk Top”」と謳い,「特別企画:ITが変える消化器病学」(司会=山梨医大・藤野雅之氏,慶大・森川康英氏)というかつてないユニークな試みが行なわれた。
「80年代後半に幕を開けたコンピュータ技術による通信革命は21世紀に入って第3段階を迎え,ブロードバンド化による圧倒的な通信速度の獲得と情報量の増大をもたらした。この特別企画ではブロードバンド時代を迎えたITによる社会の変貌とコミュニケーションのあり方を消化器病と言う切り口から概観する」という企画主旨のもとに,武藤佳恭氏(慶大環境情報学)の基調講演「ブロードバンド時代のコミュニケーション」に続き,第2部「IT技術と消化器診断」として,(1)患者・医師から見た医療情報とInternet(東京都済生会中央病院・鈴木吉彦氏),(2)ブロードバンド時代の内視鏡画像の共有化/Medical Town(オリンパス光学・檜山慶一氏),(3)マイクロコスモ技術による仮想生命に向けて(昭和大横浜市北部病院・井上晴洋氏),(4)CT・MRIの開く新しい世界(東海大・今井裕氏)などが発表された。
また第3部では,フランス・ストラスブルール大学とドイツ・チュービンゲン大学を結んで「ピクチャーテルによる日欧カンファレンス」が実演された。
武藤氏はその基調講演の中で,「ようやく日本もブロードバンド時代に突入し,個人が家庭から安価に高速インターネットにアクセスできるようになった。あらゆる人がブロードバンド技術を使って,“情報”という武器を操れるのである。しかし,医師にとっては,厳しい時代に入ったと思ってよい」と指摘。
さらに,「すべての技術には光と影があるように,ブロードバンド技術やITも例外ではない。それではブロードバンド時代に医療機関は現在,何をなすべきなのか」と問いかけ,医療の情報インフラHL-7(health level seven)の速やかな導入を強調し,コミュニケーションを図るための最新のITgadgetsを紹介した。
●消化器癌の分子標的治療
 近年,「分子標的治療」が癌治療法として注目されているが,消化器病学会パネルディスカッション「消化器癌の分子標的治療」(司会=京都府立医大・山岸久一氏,金沢大・高橋豊氏)では,食道癌,胃癌,大腸癌,家族性大腸腺腫症,肝臓癌,膵癌などに対する分子標的治療が検討された。
近年,「分子標的治療」が癌治療法として注目されているが,消化器病学会パネルディスカッション「消化器癌の分子標的治療」(司会=京都府立医大・山岸久一氏,金沢大・高橋豊氏)では,食道癌,胃癌,大腸癌,家族性大腸腺腫症,肝臓癌,膵癌などに対する分子標的治療が検討された。
p53遺伝子を中心とした食道癌への分子標的治療
食道癌治療は,進行例,再発例を中心にいまだ満足できるものではなく,さらなる集学的治療の展開として新たな治療の開発が必須とされている。松原久裕氏(千葉大)は,細胞周期の調節,アポトーシス,DNAの損傷において重要な役割を演じているp53を食道癌の分子標的と考え,p53遺伝子を食道癌細胞導入,その直接増殖抑制効果,抗癌・放射線に対する感受性の増強強化について報告。さらに,消化器癌では日本で初めての遺伝子治療となった,「進行食道癌に対するp53遺伝子を用いた遺伝子治療臨床研究プロトコール」に関しても報告した。大腸癌に対する抗VEGF抗体による血管新生治療
また,北方秀一氏(金沢大)は,大腸癌において臨床試験が進みつつある「抗VEGF(vascular endothelial growth factor)抗体による血管新生治療」について,(1)VEGF産生能の高低で効果の差があるか(症例を選ぶ必要があるか),(2)抗VEGFに抗体の投与によって,他の血管新生因子の発現が亢進しないかを検討。北方氏は,「抗VEGF抗体による治療は,VEGF高発現の腫瘍を対象とすることが効率的であり,臨床応用に際しては何らかの方法で症例を選択すべきであり,また本治療によりVEGF産生や他の血管新生因子に変化がないことから,長期間継続治療が可能であると考えられる」と報告した。
●“脳-腸相関”の基礎と臨床
-神経消化器病学のめざすもの
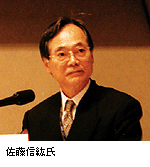 「脳」・「神経」・「免疫」という,一見異なる世界の間に成立した「クロストーク」から,さまざまな成果がもたらされたことは周知の通りである。
「脳」・「神経」・「免疫」という,一見異なる世界の間に成立した「クロストーク」から,さまざまな成果がもたらされたことは周知の通りである。
今回のDDWでは,これをさらに具体化して,消化器病学会ワークショップ「“脳-腸相関”の基礎と臨床-神経消化器病学のめざすもの」(司会=順大・佐藤信紘氏)が企画され,「神経消化器病学」という新たな概念が提起され,討議の対象となった。
カハールのもう1つの発見-「カハール介在細胞」
 討論に先立って行なわれた基調講演「Brain-Gut-Immune:消化管運動と神経と免疫系-消化管研究の新しいアプローチ」で唐木英明氏(東大・獣医薬理学)は,まず,
「カハールとゴルジの論争」を紹介した。
討論に先立って行なわれた基調講演「Brain-Gut-Immune:消化管運動と神経と免疫系-消化管研究の新しいアプローチ」で唐木英明氏(東大・獣医薬理学)は,まず,
「カハールとゴルジの論争」を紹介した。
神経学者ゴルジと組織学者カハールは,1906年に同時にノーベル賞を受賞したが,両者の見解は異なっていた。ゴルジは「網状説」(神経細胞どうしが突起によってつながり,ネットワークを作る),一方カハールは「ニューロン説」(それぞれの細胞は独立し,直接つながっていない)である。
1906年当時はどちらが正しいのか明らかではなかったが,1932年の電子顕微鏡の発明によって,カハールの「ニューロン説」が正しいことが証明された。
唐木氏は科学史上有名なこの論争とともに,「カハールのもう1つの発見」として,消化管のほとんどの部位にあって,c-Kitタンパク質を持つ「カハール介在細胞(ICC:Interstitial cells of Cajal)」を紹介し,その「消化管研究の新しいアプローチ」を次のように解説した。
「消化管研究の新しいアプローチ」
「脳-腸相関」の研究は,両者の組織において作用する共通の生理活性物質の研究から始まり,消化管運動,分泌,血流などの面で研究が進んできた。一方,神経-免疫相関の研究でも,例えば,脳においては感染やさまざまなストレスによって単球由来のミクログリアやアストロサイトなどが種々の炎症性サイトカインを産生し,神経機能に影響していることが明らかになっている。また,ある種のサイトカインは神経成長因子または分化制御因子としての機能もはたしている。その一方で,消化管内腔は常に外界からの異物の直接的な侵入にさらされているため,免疫機能が高度に発達しており,免疫系細胞が多数分布している。特に,粘膜層には多数のマクロファージが存在し,粘膜バリアー機構の要として機能していることはよく知られている。
「神経-免疫-消化管」の3者間のクロストーク
そして,「神経-免疫-消化管」の3者の間のクロストークも明らかにされつつある。消化管の免疫機能は粘膜系がはたすものと考えられてきたが,1985年,Mikkelsenによって,筋層にもマクロファージが常在することが初めて明らかにされた。特に,消化管縦走筋と輪走筋の間にはマクロファージがネットワーク状に規則正しく分布することが示されて注目された。この位置には蠕動運動指令の中枢であるアウエルバッハ神経叢とペースメーカー機能を担うとされるカハール介在細胞があり,マクロファージはこれらの細胞と近接している。これらの解剖学的知見から,この常在型マクロファージが運動系を担う神経細胞やペースメーカー細胞とクロストークしていることが容易に想像される。以上のような唐木氏の基調講演に引き続いて行なわれたワークショップでは,「ガラニン,エンテロスタティンによる接食行動,消化管運動熱産生の調節と脳-腸相関関係」「脳-胃サーキットにおけるTRH(thyrotropin-releasing hormone)の重要性」「小腸粘膜の形態維持機構と生理機能に対する中枢神経系の関与」「過敏性腸症候群の病態生理からみた脳-腸相関」「肝におけるBrain-Gut Axis(脳-腸相関)に対する脳内の内因性神経ペプチドの関与」など,各種の消化器の「脳-腸相関」が論じられた。
