連載 MGHのクリニカル・クラークシップ
第13回
カルテの電子化
田中まゆみ(イエール大学ブリッジポート病院・内科小児科レジデント)急ピッチで進むコンピュータ化
こと電子カルテに関しては,マサチューセッツ総合病院(MGH)は決して最先端を走っているほうではない。かといって遅れているほうでもない。筆者がクラークシップをしていた1999年夏の時点で,すべての患者の検査データ・退院サマリーに病院中どこからでもアクセスできた。CTやMRIについては,もともとコンピュータ画像であるから,単純X線写真(胸部・腹部など)がまだフィルムを探し回らなければならないのとは対照的に,病棟から簡単にコンピュータアクセス可能となっており,画像を見ながら診断のディクテーション(口述録音)も聞けるようになっていた。薬剤などの指示もICUではすでにすべてがコンピュータ入力であった。のちに述べる理由から,医師の指示のコンピュータ化は急ピッチで進んでおり,MGHのみならず米国中の病院で近年中に全病棟がコンピュータ指示入力方式になっていくことと思われる。コンピュータから患者へ
患者からコンピュータへ
クラークシップでは,医学生も研修先の病院のコンピュータの訓練を受けて修了時に暗証番号を受け取り,それをフルに使って臨床実習を行なう。病院によってコンピュータシステムが違うので,学生同士,どっちのシステムのどこがいいの悪いのと,比べあっていた。システムのよし悪しで仕事の効率やストレスは相当違ってくるから,こういう情報交換は研修先を決めるのにも微妙に影響するようだ。
実際,コンピュータなしには研修医の仕事は回らない。朝の回診は,当直医がプリントアウトしたチームの担当患者全員の申し送り表を各自が手にして書き込みながら進む。回診前にはコンピュータに向かって自分の受け持ち患者の検査結果をすべて調べておかねばならない。「さっき調べたらまだ結果が出ていませんでした」と回診中に報告しても,重要な検査だと,「もう出ているかもしれない,誰かもう一度調べて」と教官やチームリーダーが示唆するや,誰かがさっとコンピュータに駆け寄ってキイを叩き,「まだ結果は出ていません」とか「トロポニンの2回目は0.01,ジゴキシン血中濃度は0.9です」などと報告する。すべてがライブで進行している感じの目まぐるしさだ。検査結果によって即退院が決定することもあるから,入院日数を半日でも減らしベッドの回転を早くしたい病院にとっては,間髪を入れず結果が伝達されるコンピュータは,スピードアップのためになくてはならないシステムである。
医学生も研修医も看護婦も,コンピュータから患者へ,患者からコンピュータへと飛び回りながら働くといっても過言ではない。朝の定時採血で送られた検査については午後1時頃には結果が出揃うので,またコンピュータに向かってチェックし,申し送り表とカルテに書き込む。こうしたコンピュータデータチェックは,時間に追われる身には無味乾燥な日常業務だが,例えばクレアチニン値の変化をその場でグラフにして見ることもできるし,培養結果が陽性だと可愛い黴菌マークが付くので「何が生えたかな?」とクリックする時,思わずわくわくするという楽しみもある(患者にとっては悪いニュースなのだから,心ならずも,と言うべきであろうが)。
新患が入ると,まずコンピュータに向かって,過去の退院サマリーや検査結果(救急外来での検査結果[CBC等]や過去の重要な検査結果[CT,心エコー,胃カメラ,腎機能,肝機能等])を調べ,会う前にどんな患者かほぼ把握しておいてから問診・診察に入るのが常道で,この事前検索のおかげで問診や診察が非常にスムーズに運ぶ。以前は古いカルテを取り寄せてページをめくりながら確認していたのだから,効率の差は明らかである。
新患の問診・診察結果をコンピュータにタイプ入力し,検査結果はコピー&ペーストでそっくり写し,プリントアウトしたものをそのまま入院時カルテにする研修医も増えてきた(写真)。いわば「自主電子カルテ」で,これを院内E-mailで送付しあえば,研修医同士の引き継ぎ業務もクリック1つで終了してしまう。ついでに,疑われる病気についての教科書(インターネットでアクセスできるハリソン内科書やMDconsultなど)や文献もコピー&ペーストして添えておけば,お互いに議論が共有できて患者のケアに役立つ。これをするのにパーム(手のひら)型のコンピュータを持ち歩いている研修医もいるが,もし医師全員が病院のコンピュータと連結したシステムのパームコンピュータを持ち歩けば,病棟のコンピュータに依存せずにいつでもどこでも患者データを入力したり交信したりできる。そのようなシステムを真剣に検討している教育病院は多く,そのうち医師が出先や自宅から自分の患者のデータをチェックし指示を送ることができる日も遠からずやってくるだろう。
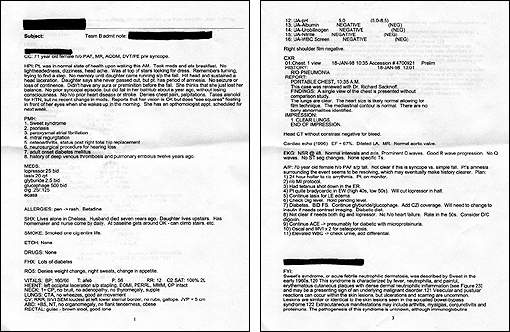 |
| 写真 研修医がプリントアウトした「自主電子カルテ」(全3頁。2頁目は病院のコンピュータからコピー&ペーストした検査値がずらり並ぶだけなので省略)。最後にこの患者ではないが同時期に入院した患者の「Sweet Syndrome」についてインターネット教科書からコピー&ペーストしてある。同僚から頼まれて参考文献として添付したものだ。これらをすべて同僚に院内E-mailで送れば,引継ぎは終了する。正式カルテとしては,最後の「Sweet Syndrome」のところを削除してプリントアウトし,カルテにファイルして,できあがり。 |
医療過誤防止のためのコンピュータ化
病院がコンピュータ化を急ぐのには,実は効率化以外にも理由がある。患者の安全(=医療過誤防止)である。1999年に発表されたIOM(Institute of Medicine)の報告書 “To Error is Human” は,Leapeらの研究(註1)に基づいて,医療過誤での死者は肺炎による死者に次いで多く,交通事故による死者よりも多い,とし,その数を半減させることを目標として掲げたが,そのためのアプローチの1つとして薬剤の指示をコンピュータ化することを提案している。これを受けて,最近,大手の企業が,従業員の健康保険の契約を結ぶのに,指示をコンピュータ化した病院を優先する方針を打ち出したため,病院にとってはコンピュータ化がお得意様を確保するための死活問題になってきたのである。初めは患者や保険会社への請求事務のため会計部門に導入されたコンピュータシステムだったが,検査部門,そして薬剤部門,さらに医師業務のすべてへと拡大・統合化されていっているわけである。
カルテの電子化は,理想的にいけば,読みやすく統一された書式で医療情報が瞬時に多数の医療者に伝達されることにより,医療ミスは減り,ケアの質が向上することが期待される。タイプは慣れさえすれば手書きよりはるかに時間が節約できるので,その分医療は効率化され,患者との触れ合いにもっと時間がかけられるようになるはずだ。
コンピュータ化=非人間的医療か?
しかし,コンピュータ経験者なら誰でも感じるように,コンピュータで節約した時間を他のことに有効に使う,というのは意外と難しい。むしろ,テクノストレスや,インターネットであちこちのサイトに行って遊んでしまうことによる生産性ロスも考慮に入れなければならない。さらに,検査データなど,コンピュータと向かい合って得られる情報についつい「溺れて」しまい,生身の患者とのコミュニケーションが損なわれるのでは,との危惧もある。この点,米国では,もともと医学部の教育で問診・診察を重視してきた歴史が長く,また,小学校からコンピュータを使いこなしているのでテクノストレスも低いせいか,「コンピュータ化=非人間的医療」という短絡は必ずしもあてはまらないように見える。「コンピュータおたく」に見える研修医も,患者の前に立てば,手抜きせず丁寧にてきぱきと問診・診察をこなし,患者や家族の意向に気を使う。そういう基本的訓練の徹底と,コンピュータを「使いこなす」態度には一日の長を感じさせられる。
むしろ問題なのは,医療者側と患者側の受け止め方のギャップではなかろうか。医療者が「コンピュータ化したからミスはチェックされるはず」とテクノロジーに依存する傾向があるのに対し,米国の患者は,銀行やカード会社の請求ミスなどで日常的に「コンピュータ化されてもミスはしょっちゅう起こる」体験を積んでいるから,おいそれとはコンピュータ(=を使う人間)を信用しないのである。コンピュータ化さえ怠ってきた医療界が,「電子化したからミスは減るはず」と言っても,その先をすでに経験している消費者(患者)にとっては,「何を今さら」ということになる。コンピュータ入力ミスをどこまでチェックできるか,言い古された結論で恐縮だが,結局は使う人間の問題に帰着するのだから。
電子カルテのアキレス腱
そして,電子カルテの最大のアキレス腱は,情報の漏洩であろう。病院のコンピュータシステムにはログイン記号と暗証番号を使って入るわけだが,ほとんどの暗証番号は姓名の一部や誕生日を使うなど,簡単に推量できるようなものだと言われる。決して他人に暗証番号を貸さない,スクリーンを開いたままで席をはずさない,終了したら必ずログアウトする,等と指導され,また,暗証番号は半年ごとに変えるなどの防衛策も取られるが,ハッカーがその気になれば侵入はたやすいことと思われる。個人情報の秘密保持に敏感な患者のために,患者が希望すれば誰がその患者の情報にアクセスしたかをすべてチェックして本人に知らせるというシステムもある。主治医でもないのにアクセスした場合,すべて記録に残るので,「何の目的で私の検査結果を知りたかったのか」と患者にあとで質問される可能性がある,ということである。その場合,もしアクセスした者がハッカーだったりしたら,使われた暗証番号の持ち主や病院は大変な迷惑をこうむることになる。その危惧が的中したのが最近報道されたワシントン大学病院患者情報漏洩問題である。患者情報の買い手は,製薬会社や保険会社などいくらでもある。病院から情報が漏れたと判明すれば,個人情報の保護に手落ちがあったとして訴えられかねないが,プロのハッカー相手に防衛するのはきわめて困難と言われるだけに,病院関係者は頭を痛めている。
必要なのは患者中心の視点
また,言うまでもないことだが,コンピュータシステムの開発・維持には莫大な費用がかかる。鳴り物入りで喧伝されたスタンフォード大学とUCSF(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)の合併があえなく挫折したのも,両者のコンピュータシステムの統合に予想以上にお金がかかり採算がとれなくなったことが原因と言われている。その点,MGHとブリガム&ウィメンズ病院との合併では情報システムには手をつけず,規模の大きさで保険者との交渉力を強めるという本来の目的に徹した,ゆるやかな連合としたことは賢明であった(註2)。ベス・イスラエル・ディーコネス病院では,いち早く患者のためのコンピュータ情報センターを設置するなど,患者中心の情報システムでは定評があるが,今では患者が自宅のコンピュータから自分の検査結果を検索できるようになっており,非常に好評である。患者が自分の検査結果を知るためにいちいち医療機関に出向いたり医療者にお伺いをたてたりしなければならないストレスの大きさは,少しでも想像力のはたらく者ならすぐに理解できるから,この方式は実に画期的と言える。「コンピュータ,コンピュータ」と情報産業に振り回されるのでなく,医療者自身が患者中心の視点から確固たる信念とコンセプトをもってMedical Informaticsのあるべき姿を提示することがいかに重要かがわかる(註3)。
臨床の基礎訓練がますます大切に
電子カルテの功罪は論じ尽くされた感があるが,その流れはもはや止めようがない。使いやすく,間違いにくく,ミスをチェックしやすいシステムが普及すれば医療の質向上に貢献する。患者自身が医療情報にアクセスして,それをもとに医師と議論できれば,患者-医師関係は格段に良好なものとなろう。また,へき地医療では画像診断が遠隔地からアドバイスでき,地域格差解消に大きな威力を発揮するだろう。一方で,もし臨床の基礎訓練ができていないと安易なマニュアル医療がはびこることになり,患者の疎外感を強めることになろう。プライバシーの保護もますます重大問題になっていくことと思われる。医療者にとっては,「馬鹿とコンピュータは使いよう」という時代になっていく。MGHでも医学生や研修医のほうが教官よりコンピュータをはるかに使いこなしていたが,ではそれでよりよい医療を提供しているかと問われれば,やはり教官にはかなわないというのが正直な感想であった。コンピュータ世代の医師が経験を重ねていった時,医療の質が向上し患者がより満足しているような,そんなプログラミングの開発のために,患者と医療者はもっともっと協力し合わなければならない。
(この項つづく)
註1:New Engl J Med(1991)324:370,377
註2:ブリガム&ウィメンズ病院はMGHよりはるかに電子化が進んでおり,その薬剤指示システムは,過誤を減らしただけでなく,望ましい(=同じ効力でより安価な;米国のDRG/PPSシステムのもとでは,医師が入院患者に安い薬剤を処方するほど病院は儲かる)薬剤の処方へと医師を正しく誘導する役割をも果たし,医療の質の向上に貢献し,経済的効果も上がったと報告している。しかし,経験に乏しい医師がコンピュータに誘導されるままに処方することが教育的かどうかという議論もある(Arch Intern Med. 2000;160:2741-2747)。
註3:この意味で,島根県立中央病院のコンピュータシステムの開発と実践は患者と医師が同じコンピュータ画面を見ながら協力してインプットするなど,実に斬新である(瀬戸山元一著『(ホントニ)患者さん中心にしたら病院はこうなった』〔医療タイムス社〕)。
