連載 MGHのクリニカル・クラークシップ
第11回
MGH流カルテの書き方
田中まゆみ(イエール大学ブリッジポート病院・内科小児科レジデント)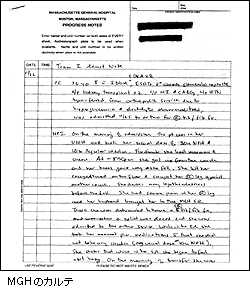 「MGH(マサチューセッツ総合病院,ハーバード大学医学部の教育病院)ではどんなカルテ用紙を使っているのか」,「MGHの入院時カルテの書式を教えてほしい」と,よく聞かれる。これには困る。上部に患者のIDカードをスタンプする欄があるだけで,あとは罫線が引いてあるだけのものだからだ。要するに,白紙である。
「MGH(マサチューセッツ総合病院,ハーバード大学医学部の教育病院)ではどんなカルテ用紙を使っているのか」,「MGHの入院時カルテの書式を教えてほしい」と,よく聞かれる。これには困る。上部に患者のIDカードをスタンプする欄があるだけで,あとは罫線が引いてあるだけのものだからだ。要するに,白紙である。
では,どんなカルテを書いてもいいのかというと,決してそうではない。主訴も診断も多様にわたる多数のカルテを読んできたが,勝手に書いていいどころか,すべて一定の様式を厳守しており,誰が読んでもどこに何が書いてあるかほぼ見当がつくように書かれている。
医学生は,何度も下書きを見せて研修医の指導を受けながら,正しいカルテの書き方に習熟していく。研修医は,3-4日おきの当直ごとに1晩に5人の入院カルテを仕上げなければならないという日常を送っているから手慣れたもので,流れるように,一定形式で書きあげていく。
患者情報の伝達手段としての伝統的なカルテの形式がルールとして厳然とあり,何を書いてもよいというのは,その手法を守った上でのことにすぎないのである。カルテの中で高度な医学的議論をするにも,必ず基本的な情報をきちんと丁寧に押さえてから検討に入る。医学生・研修医・フェロー・教官・各専門科コンサルタント・看護婦・理学療法士・栄養士たちがそれぞれの立場から毎日書き連ねていくカルテの,あっという間に増していく厚みは,そのまま医療の厚みを反映しているかのようであった。
なぜカルテの記載に力が入るのか
なぜ一生懸命カルテを書くのか。カルテを読めばその医師の実力がわかる,と言われる。MGHのような,誇り高い医師の集まった競争の激しい病院で,カルテ書きが一種の示威手段となるのは当然であろう。非常に水準が高いので手抜きは一目瞭然だし,それぞれに何か「光る」ものを残したいと,医学生から教官までレベルこそ違え力が入るのである。しかし,医療水準もさることながら,それ以前の問題として,カルテは患者・医療機関・社会にとってそれぞれ重大な意味と機能を持つ公的文書であるという認識がゆきわたっていることも事実である。記録者には,カルテの法的倫理的な基盤を十分に理解して,その責を果たさなければならない義務があるのである。
まず,カルテには患者の健康に関する個人情報が詰まっているわけだから,患者は当然その情報を確認し,誤りがあれば訂正する権利がある。また,第3者がみだりにカルテを見ることを許さない権利もある。これらは,基本的人権である個人のプライバシー権に基づく権利である。1995年の世界医師会において採択された「患者の権利に関する訂正リスボン宣言」でも,患者が自分の医療情報を知る権利は明記されており(日本医師会は唯一棄権したが),もはやグローバルスタンダードと言ってよいであろう。
つまり,医療者は,対象者である患者自身が読むという前提でカルテを書かねばならないし,その内容は他人に漏らさないという守秘義務を遵守しなければならないのである。
患者はなぜカルテを読みたいのか
では,患者が自分のカルテを読む時,どんなことを知りたいと思うだろうか。まず自分の医療情報が正しく把握整理され,それに基づいた的確な判断が下され,さらには迅速な処置が取られたかどうかということを知りたいに違いない。カルテの主訴や現病歴が自分の言った通りの言葉で書いてあれば,「この医者は自分の言うことをその通り受け止めてくれた」と思うだろうし,患者にとっては重要と思われ詳しく述べたことがまったく記載されていなければ,がっかりするであろうし医師への信頼もゆらぎかねない。
だから,たとえ医学的には関係ないと思われても,「患者は,……が……と関係があるのではと心配している」などという中立的な書き方で記録しておくとよい。患者への質問に答える時にも役立つし,実は重要な意味を持っていた情報であったことが後で判明したりすることも少なくないからである。つまり,患者からの情報は,できるだけありのまま,漏らさず記録することが大切なのだ。これは身体所見についても同様で,頭のてっぺんから爪先まで一通り記載することはもちろんだが,痛みなどの訴えのある箇所は必ず重点的に診察し詳細に記載するなど,つねに患者本位でなければならない。
プロが行なう誠実な記載とは
その日の検査結果はその日のうちに記載しておくことも当然である。検査データはカルテの別の場所に集められているが,それとは別に,医師がちゃんと結果に目を通して正常か異常かを認識しているということが医師記録に記されていなければ意味がないのである。さらに,それらの診察や検査の結果を正しく解釈して迅速かつ適切な処置が講じられていなければ,「何のために診察したのか。何のために採血や検査をしたのか。結果が治療にどう活かされたのか」ということになる。これは,医師記録とともに,指示記録にも二重に残して,ただ考えただけでなく実際に指示が下され実行に移されたということを証明しなければならない。また,ICUや熱傷病棟などでは時々刻々と患者の容態が変わるから,記録には必ず時刻が添えられていなければならない。普通病棟で容態が急変したときも時刻の記載は必須である。そして,すべての記述・指示にはサインがなければならない(電話での指示もすべて後でサインする)。自分に関する医療情報がこのように克明に記載されていれば,患者としても安心できるし,万一事故が起きて何が起こったか知りたい時にも納得できるというものである。
患者として次に気になるのは,果たして医療者が自分を偏見なく誠実に診てくれているだろうか,ということではなかろうか。もし不用意に「わがまま」などと書き残したりしたら,それを読んだ患者や家族はどう思うだろう。こういう主観的な記載は,客人である患者に失礼千万であるばかりか,反論できない患者に対してフェアでなく,また,臨床心理学を無視したもので,医療のプロであることを放棄しているとさえ言える。痛みやだるさ,病気の進行や人生の前途への不安やいらだちを抱えた患者の心理をまったく理解していない,ということだからだ。医療者も人間であるから内心はどう思おうと自由だが,公式記録であるカルテには,中立的な事実(患者が実際にどういう要求をしたか等)のみを記載し,non-judgmentalでなければならない。
一方,人種・性別・年齢・職業・性的嗜好・婚姻状態・経済状態・保険に対する差別的書き方もあってはならない。人種により疾患の頻度や治療薬の効果も異なるので人種は記録したほうがよいが,“Black”と書かず“African-American”と書くのがより好ましい表現とされる。カルテの記載に患者の人格や人種などへの偏見が感じられれば患者や家族は医療者に対する信頼を瞬時に失ってしまうだろうし,抗議するとともにその部分の訂正や削除を求めてくるだろう。患者や家族が訴訟がらみでカルテを請求した場合にそのような表現が見つかったりしたら,医療機関側がどんなに不利になるかは明らかであろう。
MGHのカルテには,書き出しが
“Mr. ....is a most pleasant 76 year-old African-American gentleman with a history of....”“John is a most adorable 18 month-old white boy with cystic fibrosis ...”などと,患者がどんなに好人物かとか可愛らしいかとかいう記述から始まるものが多い。医師が患者を他の医療者に親しみをこめて紹介しているという感じで,患者や家族がこれを読めば悪い気はしないに違いない。
透明性の確保,検証責任の実践
医療記録は患者に帰属するというのがグローバルスタンダードだが,米国では所有権は形の上では医療機関に属している。しかし,法律で30年間という長期の保管義務が定められており,病院の病歴室は図書館並みかそれ以上の人員を擁し,マイクロフィルムを駆使して,カルテの長期保存に腐心している。高齢者向け公的保険メディケア指定病院(教育病院はほとんどすべてメディケア指定)では,メディケア患者の受ける医療の質を厳しく審査するJCAHO(医療機関合同審査機構)の基準を満たすため,大変な人手をかけてカルテ内容を詳細にチェックしている(註)。また,医療訴訟の多い米国では,カルテの不備は医療機関にとって命取りになりかねないという現実もある。カルテの記載もれをチェックする病歴部は,医師にとっては絶対逆らえないお目付け役。研修医や教官は,毎日毎日カルテ書きに膨大な時間を割いたうえに,病歴部から,退院患者のカルテについての「ここにサインが抜けている」,「指導医の記述がない」,「退院時サマリーがまだ口述されていない」等々という通知に追われながら暮らしているといっても過言ではない。
医療機関や医師にとって,カルテは,自らの医療行為が正しかったと証明してくれる唯一の証拠文書であるから,完璧な記録を残すために必死なのである。うがった見方をすれば,患者や家族や弁護士や裁判官が後からアラ捜しをするであろうという前提のもとで,カルテを整備しなければならないのだ。改ざんについては特別神経質で(改ざん即敗訴と言ってよいため),ホワイト修正液は絶対使用禁止。単純なミスでも黒く塗りつぶしてはならず,必ず線で消して,“error”と書きサインを添えたうえで書き直す。何ももみ消そうとしていませんよ,と,疑惑を抱かれないように必死なのである。
それもこれも,過去に医療機関がミスを隠蔽してきたことで完全に信用を失墜してしまったからで,医療のtransparency(透明性:誰にも明らかで,隠し事がないこと)とaccountability(検証責任:自分の行なった行為を正当化する根拠を持つこと)を証明するために,カルテの重要性は高まる一方と言ってよい。
よいカルテは読み手に訴える
こう書くと,そのような,いわば自己防衛・義務としてのカルテ書きはさぞ苦痛であろうと思われるかもしれないが,幸いなことに,そこで終わってしまわないのもまた医のすばらしさである。医療訴訟など滅多に起こされない日本でも,見事なカルテを読んで感嘆した経験は誰にでもあることと思う。医師がよいカルテを書くのは,法的規制や訴訟こわさゆえでは断じてない(法的規制や訴訟の脅威が,水準を高めるのに大いに寄与することは否定できないが)。訴訟王国アメリカでも,よいカルテというのは,法的レベルを越えて,読み手に訴えるものを持つ。先輩たちや教官がカルテを書く姿勢を見,彼らの書いたカルテを読んで,「ああ,こんなカルテが書けるようになりたい」と溜め息をつきながら,「今度こそは」と,学生も研修医もせっせとカルテ書きに励むのである。次回は,そのカルテの内容を詳しく述べよう。
(註)1998年,名門ペンシルバニア大学病院を含む2教育病院で,教官が研修医の医療内容を毎日把握・指導している旨を担当患者のカルテに逐一記載していなかったという理由で多額の保険金返還を命じられるという,全米の教育病院を震撼させた事件が起こった。以後,どの教育病院もいつ監査が入ってもいいように,戦々恐々教官のカルテ記載を徹底している。
