インタビュー
21世紀の外科学の進むべき方向性
第100回日本外科学会開催にあたって
北島政樹氏(慶應義塾大学医学部附属病院長,教授・外科学/第100回日本外科学会会長)
外科学の最新の動向
 きたる4月12-14日,記念すべき第100回を迎える日本外科学会総会が「未来のための今-Act now for the future」をテーマに,東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催される。本紙では開催に先駆け,今学会の大会長を務められる北島政樹氏(慶大教授)にお話をうかがう機会を得た。
きたる4月12-14日,記念すべき第100回を迎える日本外科学会総会が「未来のための今-Act now for the future」をテーマに,東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催される。本紙では開催に先駆け,今学会の大会長を務められる北島政樹氏(慶大教授)にお話をうかがう機会を得た。
北島氏には,最近の外科学の動向から第100回総会のハイライト,21世紀における外科医像など,大いに語っていただいた。
患者のQOLを重視した手術-患者を中心とする医療をめざして
北島 近代外科学の確立は約400年前,フランスのアンブロアズ・パレ(註1)から始まりました。一方日本においては,最初に薬草「通仙散」を全身麻酔に用いた華岡青洲から始まり,歴史は200年にあまるほどです。その後ご存知のように,麻酔科学の発達,抗生物質の発見などから,外科学はさらに発達していきました。かつて外科学は「great surgeon,great incision」との言葉のように,侵襲性の高い手術が当然のように行なわれ,われわれもそのような時代背景で育ってきました。手術は患者さんの立場よりもむしろ,外科医の立場を優先に行なわれてきた感は否めないと思います。
しかしここ数年,患者さんのQOLを第1に考えて,いかに機能的な外科治療ができるかに意識がシフトしていきました。その象徴的な出来事となるのが1987年にフランスのMouretが最初に行なった腹腔鏡下胆嚢摘出術です。そこから,患者さんにいかにやさしい手術・治療ができるかが真剣に考えられるようになり,これが内視鏡外科手術の発展に結びつきます。
内視鏡下手術が登場した当初は,私自身も前述の「great surgeon」の時代に育っていましたから,「果たして外科医がやるべきなのか」と抵抗感を持っていました。14-5年前のオーストラリア国際消化器病学会で,内視鏡下における胆嚢手術のビデオを見た時にも,半分は興味を,もう半分は違和感を感じていました。
しかし1990年頃から,内視鏡下手術では患者さんのQOLが非常によいことが明らかになってきました。当時,川崎市立病院の大上正裕先生(現慶大外科)たちがいち早く内視鏡下手術を導入されていて,先生にお願いして医局員を連れて見にいきました。その時に大上先生が目を輝かせて「患者さんに痛みもほとんどなく,とてもやさしい手術です」と私に説明してくれたのが印象的でした。
医学と工学の融合
北島 私が慶應大に戻り,内視鏡下手術を導入したばかりの1991年頃,「内視鏡下手術は将来ロボット化される」ことを表現した漫画を医局員に書いてもらい,京都の国際学会での講演で発表しました。その絵はロボットがロボット自身を操作するもので,現状とは少しイメージが違っています。学会でこのことを提言したのは,私自身が1975-77年にかけて米国ボストンのマサチューセッツ総合病院(MGH)に留学時の経験に端を発しています。MGHは,チャールズ川をはさんだ向い側にマサチューセッツ工科大学(MIT)が位置しており,両者は頻繁に交流しています。つまり,医学と工学の融合がごくごく自然になされているのです。例えば,私のボスのジョン・バーク先生は外傷の専門家ですが,熱傷に利用される人工皮膚をMITと共同開発し,現在は商品化されています。このように米国では,工学と医学の融合が非常に盛んで,しかも大きな成果をあげていることを目の当たりにしました。
その時に,「日本の医学部も工学部と共同でやらなくてはだめだ」と痛感し,日本に戻り工学部の先生たちと一緒に研究を始めました。慶大では現在,ロボットなどを用いた内視鏡の周辺医療機器の開発に挑戦しています。まだよちよち歩きですが。しかし工学部が有する技術はこちらが驚くほどすばらしく,これに医学の視点とをドッキングさせれば,1プラス1は2でなく5くらい大きくなると期待しています。
内視鏡下手術支援ロボットシステム
――先生方が開発されている内視鏡下手術の医療機械をご紹介いただけますか。北島 内視鏡下手術は,手術時間は長いのですが退院や社会復帰も早く,また傷も小さいので,患者さんにとっては非常にやさしい手術です。しかし外科医にとっては制約の多い,きつい手術です。1つには直接臓器を触ることができない点,2つ目は術野を直接見ずにモニターを通して手術を行なうという2つの欠点があります。これらの外科医の負担を軽減しなくてはいけないと,先ほど述べたような医学と工学の融合を展開し,周辺医療機器の開発に取り組み始めました。
最初に,手術野を高画質の3次元画像化する試みから,島津製作所と共同で「ヘッドマウントディスプレイ(HMD)」(本紙11面参照)を開発しました。さらに内視鏡自体を3次元画像にする試みも開始しています。それから,手術中は助手が内視鏡を動かしますが,この場合,助手との息が合わないと手術がやりにくくなります。そこで,ロボットを使って術者が内視鏡も動かせないかと,米国NASA出身の技術者によるベンチャー企業「Computer Motion社」と共同で,内視鏡下手術支援ロボットシステム「AESOP(Automated Endoscopic System for Optimal Positioning)2000」を導入しました(本紙2面参照)。
当初は,足元のペダルでロボットを動かしていたのですが,目と手と足を同時に駆使するとなると,外科医にとてもきついものです。最近では,術者があらかじめ自分の声を登録し,その声にのみ反応するというボイスコントロールシステムを導入して,自分の見たい視野を助手なしでも抽出することが可能になりました。
1996年の日本内視鏡外科学会(会場=東京・京王プラザホテル)の会長を務めた際に,慶大手術室と会場をつないで,AESOP2000のライブデモンストレーションを行ないました。そこで司会者がロボットをコントロールして動かした時には,今まで日本で内視鏡下手術を勉強されてきた人たちにもエポックメイキングだったようで,皆とても驚かれ,当時は,「この学会が日本の内視鏡外科学を変えた」という言葉をいただきました。
da Vinciの登場
一昨年,米『ライフ』誌に「メディカルミラクル」と題した,心臓手術にロボット手術が導入されるという記事が組まれました(The Cutting Edge, Heart Surgery Enters the Age of Robotics, LIFE Magazine Special Issue Medical Miracles for the Next Millennium, 1998)。そこに「da Vinci」(本紙1,2面参照)という手術用ロボットが紹介され,とても大きなショックを受けました。当時,教室でも工学部との共同研究で内視鏡下手術支援装置を開発しておりましたが,まさか実用化された商品が出現するとは思ってもいませんでした。まさに先を越されたと感じました。「da Vinci」はコンピュータ制御により内視鏡下手術を支援するための装置であり,術者側コンソールと患者側マニピュレータで構成されます。患者側マニピュレータを電気的に接続された術者側コンソールにおいて術者が操作することで,術者は低侵襲な内視鏡下手術を開腹手術のような操作感覚で行なうことができます。コンソールは高解像度3次元画像で,操作を5分の1あるいは3分の1に縮小できますし,遠隔操作も可能です。これは現時点での究極の手術ロボットだと思います。
この存在を知ってすぐに,開発元の米国「Intuitive Surgical社」に,消化器外科と心臓外科,小児外科の医師たちに渡米してもらったところ,非常に高い評価を得ました。そこで,これを日本に導入したい,その時には自分たちの手でやってみたいということで,現在,厚生省に治験を申請しています。それが許可されれば,いつでも開始できる状態です。これで日本に初めてロボット手術が導入されることになります。
現在,手術用ロボットに触覚を付ける研究を進めています。MIT大学院生だったトーマス・マーシー氏によって「Sensable Technology社」が開発した,触覚を伝達可能な「PHANToM」(本紙2面参照)を購入しました。現在,慶大理工学部と共同でPHANToMシステムの内鏡視下手術への応用を研究しています。このような触覚伝達能はまだda Vinciにも搭載されておりません。将来的にはmaster-slave manipulator(master-slaveによってコントロールされるロボット)に,触覚を伝達できるロボットシステムによる内視鏡下手術が可能になるでしょう。
――学会でもda Vinciを用いたセッションが用意されているそうですね。
北島 今学会では,ハイビジョンを用いて「da Vinci」による手術のライブデモンストレーションを行なおうと準備しています。学会場である東京国際フォーラムと,慶大,米国・マウントサイナイ医療センター(以下,マウントサイナイ),川崎市立川崎病院とを4元中継して,国際カンファレンスと遠隔手術指導(本紙11面参照)を行なう予定です。
マウントサイナイからは,米国の腹腔鏡手術のトップであるMichel Gagner先生と,アメリカの腹腔鏡下大腸切除術の第一人者Jeffrey Milsom先生に参加いただきます。実は,彼らは私の親友なのです。ただ,現在マウントサイナイでは「da Vinci」ではなく,別のロボットを使っているので,それをプレゼンテーションして議論に加わってもらいます。
一方,川崎市立川崎病院と慶大とは昨年12月から,遠隔手術指導を開始しました。慶大からsuperimposerを使って,画面に自由に線を書きこめるなど双方対話式の手術指導を開始しています(本紙11面参照)。ライブデモの時にこの遠隔手術指導もお見せしたいと考えています。
また,このような遠隔コミュニケーションが可能になってから,独・ミュンヘン工科大学のJorg R. Siewert教授とも,定期的にカンファレンスを行なっています。前回は「食道がんのadjuvant chemotherapy」をテーマに,両方からデータを出し合ってカンファレンスを行ないました。医局員にもよい刺激になっていると思います。ISDN3回線を用いて1時間3-4万円ほどで可能です。タイムディレイもほとんどなく,効率のいいカンファレンスが可能となりました。画像圧縮装置には「Picture Tell社」の製品を使っています。
外科学の大きな変革を前になすべきこと
世間に頓着せず,未来を見据える
――その他に,今学会にはどのような企画が用意されているのでしょうか。北島 その前に,今学会のメインテーマに「未来のための今」という言葉を据えた理由からお話しましょう。この言葉には,20世紀から21世紀のブレイクスルーをめざし,新たな外科学の確立という基本理念が含まれています。今学会には20世紀から21世紀の架け橋であることの重さ,また過去100年を振り返って次世紀を展望する重さがあります。そこでメインテーマに「21世紀の展開」や「展望」という言葉を据えただけでは,何か足りないのではないかと考えていました。そこでずっと暖めていた言葉が「未来のための今」でした。
このメインテーマは福沢諭吉先生の言葉に由来しています。1858年に慶應義塾が設立され(現在の聖路加国際病院の構内),その10年後の1868年(慶応4年)に,上野で官軍と彰義隊の戦争が起こりました。そこから6-7km離れている慶應義塾では,大砲の音がこだまする中,福沢先生は塾生に対してウェーランド経済学書の講義をされ,そこで「世間の動きに頓着するな,未来を見据えよ。今ではなくて『未来のための今』なのだ」と説いたそうです。この言葉が第100回総会のメインテーマになっています。
福沢先生は医学にも精通しておられ,緒方洪庵の大阪・適塾の塾長を22-23歳で務められました。さらに外国へ行っては医学をみて,1883年に「将来,内視鏡を使って胃の中や子宮の裏が見られる」と予言されています。また,「医学は外科より始まるものなり」と記されておられます。
一方,慶大初代医学部長である北里柴三郎先生が,福沢先生より初代学部長の任を託された時に,「今までの国立病院,国立大学は科毎の独立意識が強かったが,そのような隔壁をなくして一家族のごとく」,このような医学部を作りたいとおっしゃっています。ですから今学会では,福沢先生の「未来のための今」と,北里先生の「隔壁をはずして一家族のごとく」という理念を反映させたいと考えています。
外科学会に課された使命
北島 また今学会には,大きい使命がいくつかあると考えております。それは,先ほどから述べておりますように「外科学の最先端技術を提示する」に加えて,「日本の高度の技術を示す」,「国際化で若い人をエンカレッジする」,「海外の若い医師に日本の外科の姿を知ってもらう」,などがあげられます。先に述べたような最先端技術を駆使した外科学が,21世紀の外科学の姿になるでしょう。そこで,現時点における外科学の最高の技術を示して,若い人に「このハードルを越えなさい」と言いたい,今学会を目標として,それを越える努力をしてもらいたい思います。
今回,外科学の歴史に名前を残すような一流の外科医約40名が来日されることから,この学会は日本の外科学の力を示すよいチャンスであるととらえています。また,学会ホームページも初めて英語版を作り,世界へ向けてリアルタイムな情報発信を行なっております。それと同時に,海外の若手医師に対するトラベラーズグラントを用意して,学会参加を呼びかけました。これらは日本外科学会の国際化をめざすことを目的としております。これには10数か国から140名ほどの応募があり,そのうち80名ほどが来日することから,今学会の議論は英語で行なわれます。これは日本の若い外科医も国際舞台へ出なさいというメッセージでもあるのです。
20世紀を検証し,新たな世紀を展望する
北島 新しいものを追うだけなく,古きよきものを見つけ,それを新しいものに求めるというのが私の理念でもあります。この意味から,Centennial Symposium「外科学-新たなる夜明け」を企画しました。これはテーマである「未来のための今」を具体化することであり,すばらしい実績を残した海外の外科医を日本にお呼びして,20世紀の外科学を語ってもらい,21世紀のブレイクスルーを展望するというものです。これは,私自身が聴きたいと思っています。同時通訳されますので,医学生にも聞いてもらいたいものです。特に外科志望の学生には貴重なチャンスになります。よく「外科医は3K」と言われ,学生に外科学が誤解されているように思えます。そこで,外科学にはこれだけ夢があることを医学生に見てほしいですね。学会では,医学生とコメディカルの参加は無料としました。臓器移植,バイオマテリアル
北島 FK506などの免疫抑制剤が日本で作られ,さらに移植医療も進んできました。しかし,日本ではこれまで脳死移植は4例しか行なわれていませんし,2歳児がアメリカで心臓移植手術を受けて帰国したというニュースをみるなど,まだ日本における移植はさまざま問題点を抱えています。移植医療もそうですが,私自身も勉強したいと思うtissue engineeringの発達も目覚しく,細胞培養から臓器を作りそれを患者さんに使う可能性が出てきました。そのあたりも含めて,日本に臓器移植の現状を,外国と日本とで比較したり,移植先進国からの意見を聞けるシンポジウムを予定しています。
がん治療への新しい視座
北島 長年外科医をやっておりまして,がんに対する敗北感を感じています。早期がんはともかく,進行がんを治療できないのは,外科医にとっては非常に悔しいことです。20世紀になり,がんの診断や発生については,分子生物学の台頭からがんの原因究明が可能になってきました。90年代にはがん遺伝子治療が登場しましたが,これは今世紀の課題だと考えています。アメリカで遺伝子治療を最初に開始した人が,「今までの治療で効果のない場合には,それに代わる何かドラスティックな治療をしなければ患者さんは救えない」という言葉を残しています。私どもも現在,遺伝子治療の研究を進めています。1つは,アデノウイルスにIL-1受容体拮抗物質を入れて移植前の肝臓に導入すると,免疫拒絶やプライマリーグラフトノファンクション,虚血再灌流障害の予防が可能になります。それから,がん局所に抗がん剤を入れたベクターウイルスの注入した際の実験データが集まってきています。
今学会では「がんの遺伝子治療」は大きなテーマです。しかしがん治療としての遺伝子治療は,がんが多数の遺伝子によるものである以上,今すぐ効果は出ないでしょう。そこでがんとの共栄共存を考え,「tumor dormancy」という概念が登場してきました。これは簡単に言うと,がん細胞を眠らせて一緒に生きていくということです。それには血管新生を抑え,がんの間質の進展を抑える「anti-angiogenetic factor」,「MMB inhibitor」などを用いて,がんを発症させずにがんとともに生活していくという概念が,21世紀には必要になると思います。学会ではがん治療の新たなストラテジーを議論したいですね。
がん低侵襲手術の方向性
北島 これまで,正常なリンパ節はホメオスタシスを保つ機能を有するにもかかわらず,がんが発見されればリンパ節は大部分が郭清されてきました。しかし外科医が,この正常のリンパ節まで切除してよいのかという疑問を投げかけられたら,それに十分に答えられるでしょうか。がんから最初に転移するリンパ節を「sentinel node」と言いますが,最近,このような前哨リンパ節を探してそれだけを切除するという手法に,大きな効果が認められてきました。それを「Sentinel Node Navigation Surgery」と言います。今回シンポジウムのテーマの1つに選びました。
12-3年前,アメリカ放射線学会で,モノクローナル抗体を用いたこのナビゲーション手術が報告されたのを機に,悪性黒色腫や乳がんで施行され,その成果が報告されるようになりました。昨年から慶大でも消化管への応用を開始しています。内視鏡を使ってラジオアイソトープ,テクネシウム-スズコロイドをがんの周辺に打ちます。そのスズコロイドが,いわゆる「sentinel node」に届きますが,それを内視鏡で発見するγディテクターを開発しました。これを昨年の日本消化器外科学会で発表したところ,立ち見になるほど関心が高いようでした。
そこで昨年11月に,「sentinel node navigation surgery研究会」を設立し,第1回研究会には予想をはるかに越える参加者が集まりました。学問に興味のある人たちがこれだけたくさんいて,テーマによっては人が集まることを実感しました。第2回は金沢市で開催予定です。これは今後,がん治療における大きなテーマの1つになると思います。
「果たして外科医は生き残れるか」
――今回,鼎談「21世紀外科医のあり方を探る-果たして外科医は生き残れるのか」という,ユニークな企画があるそうですね。北島 この問いには,今まで私が話したことを若い外科医や,これから外科医になる医学生たちがきちんと受け取めてくれると,外科医は生き残ると答えられます。
この鼎談には,第94回の日本外科学会会長を務められた三島好雄先生(東医歯大)と,読売新聞「医療ルネサンス」取材班統括責任者の大谷克哉氏の2人を司会に,比企能樹先生(北里大),広瀬輝夫先生(元ニューヨーク医科大),梅園明先生(済生界宇都宮病院),真栄城優夫先生(沖縄県立中部病院)という組み合わせで,お話いただく予定になりました。このような先生方に20世紀を回顧していただき,医学教育の中で21世紀を展望していただいて,それをわれわれ第一線の場で教育に取り組む外科医や,若手外科医がどのように受け止めるか,という反応が非常に大事だと思います。
――学術集会に加えて,記念式典や展示,市民公開講座なども充実した企画が用意されているそうですが。
北島 これまであげた最先端のトピックスはすべて,「患者さんにやさしい低侵襲手術」をいかに提供できるかにつながると思います。そこで,同様のタイトルで市民公開講座「患者にやさしい外科治療」を開催する予定です。
また4月11日に記念式典を行ないます。ここでは慶大脳外科出身の小森昭弘氏に作曲していただいた「式典序曲」を,小森先生の指揮でメトロポリタン管弦楽団に演奏いただきます。記念講演では,慶大心臓外科出身の向井千秋氏にご登場いただくことになりました。そして特別講演には鳥居泰彦慶應塾長に「福沢諭吉と慶應医学」というテーマでご講演いただきます。また今学会の開催にちなんで記念切手が発行されることになりました。
21世紀の外科学
――外科医にとって21世紀はどのような時代になるとお考えでしょうか。北島 この答えは,外科医または施設長が持っているビジョンによって,その受け止め方が違ってくると思います。将来,外科医が何をめざしているか,何をやりたいかという明確なビジョンのもとには,外科学をめざす若い医師は絶えないでしょう。外科医は十分に生き残ると考えています。
先ほど述べた手術用ロボットの出現によって「外科医は失業しますね」という愚問を投げかける人がいます。しかし,ロボットだけで手術をすべて行なうなんてことはあり得ません。それを操作する資格があるのは,解剖・生理学に熟知した外科医だけです。外科学は今後,ハイテク技術を駆使する時代になると思いますが,そこでは患者さんのより高いQOLを求める外科医が登場してくると考えています。
他科の医師・コメディカルとの壁と取り除く
――臨床の場で接点のある他科の医師やコメディカルに対して,外科医はどのように対するべきでしょうか北島 今学会では,シンポジウムにも多数の内科系の教授にご参画をお願いし,外科と内科の治療の接点について考えてみたいと思います。内科治療をするのか外科治療をするのか,まだまだ議論が足りません。例えば,劇症肝炎を内科的治療をするか移植するかで,いつももめてしまいます。炎症性腸疾患においても,保存的にいくのか外科治療するのかについても同様です。そのあたりのコンセンサスを出そうということで,内科系の先生方にご参加いただきます。
同時に,今まで述べたように外科領域でハイテクが使われてきますと,看護職もメディカル・エンジニアリングなどに興味のある人でないと務められないでしょう。看護職が単に医師のオーダーを聞いて,それに忠実に従うという時代ではありません。看護職も医療に積極的に参加する時代です。かの「ナイチンゲール精神」にも,「外科学と看護学は車の両輪のごとく」とあり,外科医が,あるいは看護職が勉強しないと,この車が倒れると書かれています。まさにその通りです。
患者さんと心をともにする外科医の育成
――外科医の教育についてどのようなビジョンをお持ちですか。北島 今後ますますハイテクを駆使した外科教育が可能になるでしょう。これは,バーチャルリアリティ(VR)を使った周辺機器の開発から,VRを利用したトレーニング,という方向に進むと考えています。実際にアメリカでは,小学校の授業にVRを取り入れた教育が施行されています。先ほどお話した4年前の日本内視鏡外科学会で,米国ロボット手術のトップクラスであるRichard Savata先生から,小学生の理科授業はVRで行なわれ,カエルの解剖もVRで,映像のカエルを解剖して縫合し,終わるとカエルが飛ぶ絵が出てくる,という話を聞きました。今後はこのようなVRを駆使した外科教育が登場するでしょう。そうなれば若手医師の教育は変化してくると思います。
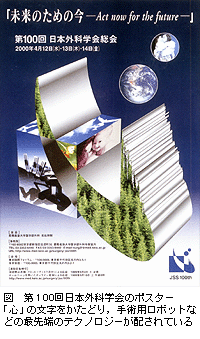 しかし,いくら医学や技術が進歩しても,外科学とはアートとサイエンスが強調される領域です。アートは技術,サイエンスは臨床にフィードバックできる学問・研究をさします。しかし,人にメスを入れる外科医とは,内科系の教育とは少し意味が違うと思っています。私は医局員には「外科医である前に人であれ」と強調しています。外科医も慣れてくると,メスを入れることをなんとも思わなくなる場合もあります。いくら歳を経て熟練した外科医であっても,人の体にメスを入れるということがどれほど大変なことかは,一生覚えていなくてはいけません。そしてこれはどんなに時代が進んでも守り続けなくてはいけないことです。そこで今学会のポスターには「心」という文字を配して,外科医にとってヒューマニティが一番重要であることを示したつもりです。それが今度の外科学会の理念です(図参照)。
しかし,いくら医学や技術が進歩しても,外科学とはアートとサイエンスが強調される領域です。アートは技術,サイエンスは臨床にフィードバックできる学問・研究をさします。しかし,人にメスを入れる外科医とは,内科系の教育とは少し意味が違うと思っています。私は医局員には「外科医である前に人であれ」と強調しています。外科医も慣れてくると,メスを入れることをなんとも思わなくなる場合もあります。いくら歳を経て熟練した外科医であっても,人の体にメスを入れるということがどれほど大変なことかは,一生覚えていなくてはいけません。そしてこれはどんなに時代が進んでも守り続けなくてはいけないことです。そこで今学会のポスターには「心」という文字を配して,外科医にとってヒューマニティが一番重要であることを示したつもりです。それが今度の外科学会の理念です(図参照)。
――いちばん最初に入れたメスの感触を覚えていらっしゃいますか。
北島 はい。胃の手術を最初に行なったのが昭和44年1月30日で,外科医になって2年目のことです。私は第1助手でした。胃の出血の患者さんでしたが,部長に「代われ」と言われた時には本当にびっくりしました。その時どうやったかはあまり覚えていません。手術が終わった時には腰も砕けるぐらい疲れていました。
患者さんの術後をみるにも,昔はレスピレータに良いものがなく,例えば食道がんの手術だとわれわれ病棟医は,ボストンバックに4-5日の下着類を詰め込んで病院に泊り込み,交代でバックを押しているんです。皆で飲んでいても,「そろそろ交代だぞ」と病院に戻って,という時代を過ごしました。今とはずいぶん異なりますね。だからと言って「自分たちはこんなに大変だったのだから,同じことをやれ」と押しつけることはできません。時代は変わりますし,機械も進化していきます。ですが,患者さんと心をともにすることだけはいつまでも忘れずにいてほしいですね。
――本日はお忙しい中,ありがとうございました。
(註1)アンブロアズ・パレ
「近代外科の父」と呼ばれるフランスが生んだルネッサンス期の外科医。世界で初めて四肢切断術に成功し「私が処置をし,神がこれを癒したもうた」との名言を残す。江戸時代の外科教科書ともいうべき「紅夷外科宗伝」における図譜のほとんどはパレの記した「外科全集」による


