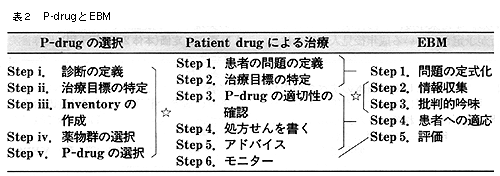P-drugを学び教えるということ
津谷喜一郎 東京医歯大助教授・難治疾患研究所情報医学研究部門(臨床薬理学)

私は昨年(1998年)8月12-21日にかけて,オランダ・フローニンゲン大学で行なわれたP-drug(Personal drug)の教師養成のためのコース「5th International Course on Teaching Rational Drug Therapy」に参加した。その後の日本での動き,Evidence-based Medicine(EBM)との関係を含めて報告したい。
コースの概要
このコースは今回が第5回で,毎年夏に行なわれている。例年約20人の参加者で,昨年は少し多く31人だった。参加者を国別でみると,ヨーロッパではブルガリア,クロアチア,ポーランドなど東欧が多く,アジアは日本とインドネシア,トルコから,そのほか南米,アフリカからの参加があった。参加者は発展途上国の人が多く,先進国からは今回,日本とドイツのみであったが,日本は医薬品の合理的使用については途上国なので,ちょうどよいと思った。コースの参加者は多様で,一般の薬理学者,臨床薬理学者,一般内科医もいる。
P-drug教師養成コース

コースは全体で10日間だ。3つのパートに分かれ,「モデュール」と称している。最初の4日間は,参加者が学生としてP-drugについて学ぶ。週末をはさんだ次の3日間は,今度は教師となり,模擬学生にP-drugについて実際に教え,最後に試験とまとめがある。
問題解決型の臨床薬理学
本コースの実際の進行は,5-6人の小グループに分かれて,別々の部屋で行なわれる。私のグループは,アフリカ・ブルキナファソ,スペイン,トルコから2人と私の5人で,それにロシア人のファシリテーターが1人ついた。初日に,各自に「高血圧」の診断のもとに作成するようにとの表が与えられる。これには,「efficacy」(有効性),「safety」(安全性),「suitability」(適合性),「cost」(費用)の4項目に対して,自分が知る薬物群ついて空欄に記入せよというものだ。
しかし,ただ表を埋めよと言われても,降圧利尿剤もあれば,βブロッカー,ACE阻害薬,Ca拮抗薬など種々あるので,具体的に何を書いてよいのか悩むことになる。参加者全員には“British National Formulary”(BNF)が配られているが,手元にはこれしかなく,「efficacy」といっても血圧降下作用なのか,死亡率を下げるのかわからず混乱する。しかし,この混乱するところがポイントで,自分で考えて,またグループで議論を進めて,それでも足らなければ,図書館やインターネットで実際に自分たちで調べることが目的なのだ。
つぎに,高血圧に対してベストの薬物群から自分のP-drugを選択する。ここで薬剤名だけでなく,どのようなdosage formで,1日何回,何日間処方するかまで含めて,自分のパターンを決める。それがP-drugなのだ。
Practicalな教育法
2日目は,具体的な症例が提示されて,ある特定の患者に対する薬の選択を行なう。特定の患者に対して選択した薬については“Patient drug”と呼んでいる。ここではpersonal drugの「suitability」(適合性)が重要になる。他の薬物との相互作用や,禁忌,あるいは1日に何回投与する,といったことにも考慮しながら,自分が持っているP-drugがこの特定の患者のPatient drugになるかを,議論して決めていく。
3日目は,実際に処方箋を書く段になる。この日から模擬患者となる学生が参加する。彼らはフローニンゲン大学医学部の学生が主で,一部薬学部の学生もいた。1年生から6年生まで約15人だ。彼らを目の前に,問題の同定から始めて,ステップにしたがってその患者にとって最適な薬を決めて,いろいろな指示を与えるところまで行なう。実際には4人の学生が1人ずつ部屋に入り,参加者の1人が対応しているのを他のメンバーがみて,後ほどその内容について議論するという方法をとる。
4人目への対応が終わり,やれやれと思っていると,急にその部屋に電話がかかってきて,パニック風の患者が「高血圧で頭が痛くてしようがない,どうしたらいいんだ」と訴えてきた。それに対してどう答えるか。「電話では状態がよくわからないから,指示はできない」と言うと,その患者がすぐ部屋に来てしまう。模擬患者だから部屋の近くにいるわけだ。またそれに対応しなければならないので,参加者には大きなストレスがかかる。学生たちは楽しんでやっている。彼らにとっては世界各国からの参加者を相手に病人のふりをするのはおもしろいのだろう。まったく“practical”な教育法だ。
4日目は,これまでの3日間の成果,つまり本当にP-drugについて教育されたかどうかをテストされる。小部屋が8つほどあり,その中の3つの小部屋に順々に入っていき,3人の模擬患者を相手に実際にP-drugのコンセプトを用いて,最終的に処方箋を書くところまでをテストされる。部屋の奥がマジックミラーになっていて,ファシリテーターは参加者がどのような対応をしているのかをそこから見て採点する。その際には,「OSCE」(objective structured clinical examination)により各項目に,0-5までの6段階のスケールを用いて採点する(表1)。
P-drugを教える
モデュール2では,今度は参加者が教える側,ファシリテーター役になる。生徒役であるフローニンゲン大学の医学生4人を相手に,実際にP-drugとはどういうものかを教えるという形をとる。ここでは実際の教育方法を自分で考えて実践する。例えば,同じグループになった薬理学を教えているというスペインの女医は,トルコ人の参加者を模擬患者にみたて,その対応を学生たちに見せて,P-drugを教えるという形をとった。翌日,ブルキナファソから参加した神経内科の医師は,学生同士に医師側と模擬患者側の役割をさせて教えるという方法をとった。テーブルの配置を改善したり,話しやすい席順にしたりと,グループのメンバーにはいろいろアイディアがわいてくるものだ。
グループの参加者の1人が,教師役の参加者が4人の学生それぞれと,または学生全体に何回話をしたかをカウントする。ここでの教育法はproblem orientedで,学生に自ら考えさせて,議論させるのがゴールだ。したがって,教師役が多く話すのはよくない,学生間の議論が多いのがよい,ということになる。
また,参加者はそれぞれ他の参加者が教師役としてどのようにふるまっているかを評価する。3つの項目から成り立ち,以下に示す後ろのステップまで達していれば評価が高いということになる。
(1)Learning Objectives:教える目的をはっきり伝えた,コースのその日の目的が達成されたかどうかを話した,学生にこの目的をよりよく達成するにはどうしたらいいかを聞いた
(2)Problem-Solving:疑問があった時にすぐ答えた,しばらく答えずに後になって答えた,いつこの答えが必要なのかを伝えた,学生に自分で回答をみつけるように話した
(3)Process:議論が混乱した時に何もしなかった,議論が混乱した時に介入した,議論をうまく刺激した,本当の問題解決型まで導いた,
モデュール2の4日目は,今度は参加者が学生を採点する側になる。そこでは参加者の1人が模擬患者になって,教育された学生が具体的に患者から問題を聞き出して,自分のP-drugから,Patient drugを選び出し,患者とのコミュニケーションをとって,処方箋まで書いたかを,先ほどと同じOSCEを使って評価する。
自国でコースの成果を展開する
全体のまとめに入る前にポスターセッションがある。ここでは,本コースで学んだことを自分の国でどう生かすかについて,プランを各自書くものだ。そしてお互いに批判し合う。各国によって状況が大きく異なり,ここで大事なことは,コースで学んだことをいかに自国に帰って展開するかということだ。例えば,先進国からはドイツと日本からの参加があったが,ドイツでは学生時代に3回,進級のための国家試験があり,特定の大学だけでこのようなコースを取り入れるのは難しいとのことだ。つまり先進国の間でも状況は異なる。そこにどう取り入れるかが重要なのだ。私が書いたプランは,日本でP-drugのワークショップを行なうことだ。これは具体的には浜松医大臨床薬理学の大橋京一教授に協力をお願いし,浜名湖臨床薬理セミナーの翌日に,1日間のワークショップを,昨年12月に開催した。この時にはDr. H. V. Hogezeil(WHO Drug Action Program担当医官)にファシリテーターとして来てもらった。次いで,日本でP-drug普及のためのネットワークを作ることを示した。日本における臨床薬理学関係のカンファレンスは,浜名湖セミナー以外に,富士五湖カンファレンス,日光カンファレンス,阿蘇九重カンファレンスとある。これらの各代表の方,また東大薬剤部の折井孝男氏,P-drugマニュアル訳者の1人の別府宏國氏(都府中療育センター副院長)に参画いただき,P-NET-Jを作った。
(昨年に引き続き,P-drugワークショップを主催,今年8月27-29日の3日間行なう予定)
P-drugとEBMの関係
ここで「P-drug」とは何か,またEBMとの関係について解説しておく。P-drugのPとは「Personal」の略だ。これは医師側,医療従事者側の“Personal”という意味であり,患者側ではない。P-drugの選択にはStep i-vまでの5つのステップがある。表2の左のカラムに示す。
臨床現場でP-drugをどう使うか
つぎの作業として,P-drugを実際に臨床現場の患者にどう使うかである。特定の患者に最も適切な薬はPatient Drugとも呼ばれる。これにはStep 1-6までの6つのStepがある。表2の中央のカラムに示す。このように,P-drugの選択の場面と,臨床現場での使用場面との2つのセットに分け,それぞれ明確でロジカルなステップに分けたことがポイントだ。P-drugのオリジナルテキストができたのは80年代後半で,その後少しずつバージョンアップして改善されながら教育に使われてきた。いわゆるEBMの動きというのは90年代に入ってから起こったもので,P-drugのほうが先行していたと言える。一般に私たちはEBMのほうがなじみは深い。そこでP-drugとEBMとの関係を述べると次のようになる。
表2の右のカラムはEBMの5つのStepを示す。EBMはStep1として目の前の患者の問題の定式化から始まるが,これはPatient drugによる治療のStep1と2に対応する。同じくEBMのStep4はPatient drugのStep3,4,5に,EBMのStep5はPatient drutgのStep6に対応する。 さて,EBMで残ったStep2の情報収集とStep3の批判的吟味に対応するのがP-drugの選択のStep i-vだ。
自分の診るすべての患者にそれぞれEBMを実践するのは物理的に不可能である。そこで自分が診る可能性のある典型的,一般的な診断名に対して,あらかじめP-drugを選択しておくというわけだ。WHOの必須医薬品が国家レベルの限定されたリストならば,P-drugは,医師個人レベルの限定されたリストとも言える。P-drugはEBMのうち薬物による治療に特化しており,P-drugの選択には薬物群なるコンセプトを使う。また,Patient drugによる治療では,処方箋,アドバイスといったところがEBMよりも,より細分化された形になっているのである。
●本コースのホームページ
http://coo.med.rug.nl/summerschools/index.htm
| I 問題解決のステップ
1. 問題(診断)を明らかにし,P-drugないしP-treatmentを用いる 2. 目前の患者へのP-drugの適切性をチェックする a. 禁忌 b. 相互作用 c. 利便性 3. 薬物治療の選択を行なう a. 薬剤 b. 剤形 c. 投与量 d. 治療期間 e. 非薬物療法 4. 処方せんをしっかりと書く (医師の名前と住所,期日,一般名,濃度・力価,投薬方法,総量,1回分の量,指示,警告,サイン,患者の名前と住所) 5. 情報,指示,警告 a. 効果(どういう効果がある,いつ効果が起こる,どのくらい効果が続く) b. 副作用(どのような,何をすべきか) c. 指示(服用法,容量,投薬間隔,投薬期間,ケアのポイント) d. 警告(最大量,相互作用,逆作用,投薬中止) e. 次回の約束(時間,どんな時に早めにくるか) II コミュニケーションのスタイル a. クリアでわかりやすい b. 会話の構成力 c. 患者(またはその配偶者)に言いたいことを言ってもらう,または質問しやすい時間を与える d. 患者(またはその配偶者)が指示を理解したかの確認 e. 患者にもう1度指示を復唱させる |