苦闘の米国面接旅行記
岡 真由美(Lemuel Shattuck病院 内科レジデント)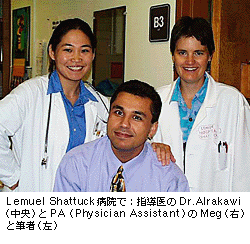 34便。今回の就職活動のために乗った飛行機の便数である。1997年9月野口医学研究所のプログラムに参加しトーマス・ジェファーソン大学での外科研修,続いて10月にマイアミ大学での肝移植見学,一旦帰国後1月には面接旅行のため渡米,そして3月,だめ押しだが結果発表の際のスクランブルに備え再び米国の土を踏む,と計3回の渡米で乗った飛行機の数が上記の数字である。改めてみてみると結構すごい数だ。そして日本と米国の近さに驚く。
34便。今回の就職活動のために乗った飛行機の便数である。1997年9月野口医学研究所のプログラムに参加しトーマス・ジェファーソン大学での外科研修,続いて10月にマイアミ大学での肝移植見学,一旦帰国後1月には面接旅行のため渡米,そして3月,だめ押しだが結果発表の際のスクランブルに備え再び米国の土を踏む,と計3回の渡米で乗った飛行機の数が上記の数字である。改めてみてみると結構すごい数だ。そして日本と米国の近さに驚く。
この4週間に渡って苦闘した面接旅行について思うところを書いてみようと思う。
97年の10月に応募書類を送り11月中旬からぽつぽつと面接しましょうという返事が返ってきた。結局,年内に外科2か所,放射線科4か所,Transitional Year(註)1か所の計7か所からの誘いがあり,昨年との違いに驚きながら,そして期待に胸膨らませながら,年が明けた1月7日にフィラデルフィアへと飛んだ。
外科は2か所とも面接日を指定してきており,1000人前後の応募者(6ポジション)の中から選ばれた100人強を2日に分けて面接するという形を取っていた。放射線科は小人数で面接する所がほとんどだったためこちらの都合が通るようであった。
〈註〉Transitional Year:眼科,放射線科,麻酔科などは専門研修に入る前に1年間のインターンを義務づけており,そのためのプログラムである。一般医療を経験するのが目的であるため,たくさんの科をローテーションするようになっている。
初面接
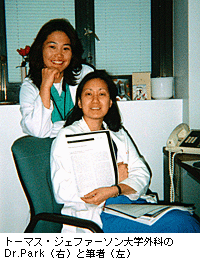 まず1月10日。初面接はフィラデルフィアのAllegheny大学病院の外科であった。フィラデルフィアの中心地にある古い病院で最近Allegheny 大学に買収された。米国の病院はこういうことがしょっちゅう起こり,ここも最近の10年間で3回以上は経営者が変わっているという話。学生も慣れたもので,プログラムの存亡に対する危惧や,内容の変更,関連病院へのローテーションがそのまま継続するのかなど手厳しい質問をぶつける。日本でも教授交替の時,入局者が減るのと同じことだろうか。
まず1月10日。初面接はフィラデルフィアのAllegheny大学病院の外科であった。フィラデルフィアの中心地にある古い病院で最近Allegheny 大学に買収された。米国の病院はこういうことがしょっちゅう起こり,ここも最近の10年間で3回以上は経営者が変わっているという話。学生も慣れたもので,プログラムの存亡に対する危惧や,内容の変更,関連病院へのローテーションがそのまま継続するのかなど手厳しい質問をぶつける。日本でも教授交替の時,入局者が減るのと同じことだろうか。
ここでもすべてがコンピュータ化されており,CT・MRIの画像は画面上でチェック,検査結果の照会,食事・検査のオーダーもコンピュータで行なう。驚いたのはすべての病室(病棟ではない!)にコンピュータが備えつけられていたことだ。
チーフ・レジデントとアテンディング・ドクターの2人組による15分ほどの面接が2回,これは翌週行なったトーマス・ジェファーソン大学の外科と同じやり方であった。質問はほとんど予想しうるものばかりだった。
例えば,
「どうして外科を選んだのか?」
「日本の外科研修を途中でやめて米国にくる必然性,メリットは?」
「米国で研修後の予定計画は?」
「休日は何をしているのか?」
など快調に答えていったのだが,最後に“What makes a good surgical resident?”と聞かれた時は予想外であったため,しどろもどろの返答しかできなかった。アドリブに弱い自分が非常に情けなかった。
また面接の際,推薦状を書いてくれたトーマス・ジェファソン大学のDr.Parkの話も何度か出,彼女のおかげで面接までこぎつけたという事実を強く再認識した。
いろいろな意味で厳しい外科
私以外はほとんどが米国の医学生のようであった。みんな実習の合間を縫って20か所以上で面接を受け,すでに面接のプロとなっていた。1人外国の医学部を卒業したという米国女性と話したが,彼女にとっても外科は非常に厳しいらしく,5-6か所しか受けられそうにない,とこぼしていた。インタビューの翌週,見学の申し出をすると快く承諾してくれ,チーフ・レジデントを紹介してくれた。彼に電話すると,「じゃあ6時にオペ場で会おう」と言われたときには,「ああこれが外科医の生活なのね」と思い,めまいがした。
放射線科の面接
翌週1月13日。Nassau Countyメディカル・センター放射線科の面接を受けた。マンハッタンからロングアイランドレールロードに1時間乗ると,すっかり田舎という感じの町に降り立つ。この静かな町にどーんとそびえるかなり大きなメディカル・センターである。放射線科の研修プログラムはのんびりしており,1日2回のカンファレンス(11:30AM,3:30PM)があり,午後のカンファレンス前にはレジデント等の仕事は大体終わっているという話だった。応募者は3人で皆FMG(Foreign Medical Graduates;米国以外の医学校卒業生)であった。1人はNYの大学の眼科で研究しており,既に永住権を獲得しているという韓国人,もう1人は放射線科医とし本国でバリバリやっているといった感じのインド人であった。彼は自国の設備と比べ,この病院に来る意味はないとはっきり言いきっていた。確かに苦労して研修しても,達成感は半減だろうというような病院であった。パソコンは必須のアイテム
今回の旅行にはパソコンを持参した。米国の就職活動には必須のアイテムである。まず応募についても,放射線科・産婦人科・Transitional year program他,数科はすべてE-mailで応募,連絡を行なうことになっている。ERAS(Erectric Residency Application Service;応募書類,推薦状などの書類を米国医学校の在籍者は大学の事務に,私たちFMGの場合はECFMG〔Educational Commission for FMG〕に集め,そこから応募者それぞれの希望の病院に送信してくれるというシステム)のおかげで,推薦状を何十通も頼まなくてもいいし,日本から送ることを考えると馬鹿にならない郵便代だって助かる。最初はいいことずくめだと思ったが11月第1週に申し込んだにもかかわらず,1月になっても病院から書類の不備を指摘されたり,書類が揃っていないため選考の対象から外されていたりしたことが後になって判明した。話がそれたがパソコンの用途としては,他に“Thanks Letter”の作成があげられる。面接の後,各面接官にお礼状を書くのが普通のようで,私も面接の夜に1日を思い出しながら作り翌日フロッピーに入れたのを大抵はKINKO'S(コンピュータの時間レンタルショップ)でプリントし郵送するようにしていた(もちろん店で作っても構わないのだが,時間がかかり,その分高くついてしまうので作っていったほうがお得)。そして,何といっても日本との連絡が取りやすいのが最大の利点である。1か月も1人で旅行していると,どうでもいいようなことを話す相手に飢えており,そんな時日本の友人とつまらないことを話す(mailし合う)のがとてもいい気分転換になった。また心配してくださっている医局の先生にもE-mailで随時報告ができ,その点でも非常に役立った。
本命での面接
その週の1月17日。本命のトーマス・ジェファーソン大外科の面接に臨んだ。面接は朝の9時から始まった。応募者46人が一堂に会したところで面接,病院ツアー,そしプログラム・ディレクターとの集団会見など1人ひとりに予定表が配られる。面接はアテンディング1人,レジデント1人の組み合わせに2回会うという形式だった。おもしろいのは1組は応募書類の中でPersonal Statementしか見せてもらっておらず,本人に一から自分のことを説明させるというblind interviewという方法をとっていたことだ。これは応募者にとって有利にも不利にもなり得るやり方で,自分のアピールしたいことを話し続けることができるという利点もあるが,その表現力がなければ非常にマイナスポイントの高くなるこわい形式だ。私の場合,ある程度Personal Statementの内容を話した時点でいろいろ質問をしてくれたので,何とか話が途切れなかった。
もう1組はアテンディングが乳癌専門の女医さんで,彼女の質問にも冷や汗をかいた。「外科医として命を助けられない患者に対してどういう気持ちを抱き,それを自分の中でどう処理していくのか?」といった内容だったと思うが,うまく答えられなかった。後で自分なりに考えた答えを“Thanks Letter"として送った。
面接では必ず最後に「質問は?」と聞いてくる。何か尋ねないと消極的であるとか興味を持っていないとか,とにかくネガティブな印象を与えてしまう。名著!?“GETTING INTO A RESIDENCY-A Guide for Medical Students”(K.V.Iserson著,Galen Press刊)の中でも,質問の内容で応募者の質を判断すると言っているぐらいだ。しかし,プログラム・ディレクターと応募者7-8人とのグループセッションでは,ざっくばらんに話そうという雰囲気にも関わらず,いい質問が浮かばず,結局私を含め2人が質問をしなかった。まあ皆大した質問はしてなかったのだが,しないよりしたほうがいいのが米国なのだ。
そんなこんなで,本命と気合を入れていた割に散々な出来で帰った私を野口医学研究所の面々が「また明日からがんばれ」とキムチとビールで気合を入れてくれた。本当にありがたかった。
ハードな1週間の始まり
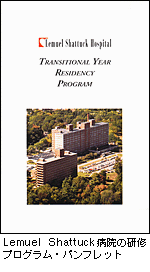 翌週はとにかく忙しかった。まず月曜日はロチェスター大学放射線科で面接。ディレクターとの面接中,ここにも日本人がいるんだよと紹介していただいたのが沼口ユウジ先生だ。神経放射線科の教授をされており,突然の訪問者にも親切にアドバイスをしてくださった。
翌週はとにかく忙しかった。まず月曜日はロチェスター大学放射線科で面接。ディレクターとの面接中,ここにも日本人がいるんだよと紹介していただいたのが沼口ユウジ先生だ。神経放射線科の教授をされており,突然の訪問者にも親切にアドバイスをしてくださった。
プログラムはとてもしっかりしており,教育熱心なプログラム・ディレクター,Dr.Skucasのもとでone to one teachingを基本とした,実践的でありかつアカデミックな研修が行なわれていた。話をした女医さんによれば教育熱が短所でもあるという,それは研修医が与えられることに慣れすぎてしまい積極的に学ぶ姿勢をなくすからということだ。
米国のトレーニングは実に繰り返しの連続であり,ある意味では日本の小学校教育に似ている。ばかばかしいとまで思える基本的知識を反芻させることで忘れられないものとしている。私たちがいくつになっても“九九”を忘れないように,彼らは医学生的教科書的知識を本当によく覚えている。
1月20日。次の目的地ボストンへ。翌日面接を受けたLemuel Shattuck 病院はタフツ大学の関連病院の1つで,ボストン市内から地下鉄で約20分ほどのところにある。無保険者や州立刑務所の囚人が対象の上,病院内にアル中,薬中のリハビリ施設があるため,患者層が興味深かった。
“ER”の元ネタ
1月22日木曜日,朝の便でシカゴへ。12時から面接予定。ホテルにチェックインし,病院へ。シカゴは米国の他の大都市にたがわず,9つの医学校を有し-大medical societyを築いている。Cook County 病院は市の中心部から少し離れた所にある。Rush大学病院,Presbyterian子ども病院が隣接してそびえ建っており,お茶の水を思わせる雰囲気である。両隣が高いため小さく見えるがどっしりした古い造りの病院だ。ドラマ“ER”の元ネタになっただけあり,周囲の環境はよろしくない。プログラムは非常に実践的で救急外傷が多くInterventional Radiologyの出番が多い,にもかかわらずフェローシップ・プログラムがないこと,公立病院で患者に無保険者が多いことからか,当直時の診断手技はレジデントのみでやってしまうらしい。銃創からの出血に対してembolizationで止血など,この地域特有の手技もマスターできそうだ。
目についたのは東南アジア人系の多さだ。アテンディングしかり,レジデントしかり,応募者しかりである。ここは面接日を3日に絞り4つのポジションのために100人近くを面接する。その日も午前午後15人ずつぐらい面接を行なっており,ランチの時間に午前午後組の両方が重なったのだが,20人近くがインド,パキスタン,バングラデシュ系の顔立ちであった。外国人研修医を伝統的によく採用する病院らしい。
General medicineを重視した最近の政策のため,放射線科への応募者が最近2年で激減した。以前といってもつい3年前までは最も優秀な米国人医学生が集まる科であったのにだ。放射線科などの専門的科の就職状況は確かに昔ほどよくないらしいが,だからといって職にあぶれるといったことはなく,学生たちもそれに気づいたのか,すでに今年は去年の2-3倍の応募者があったらしい。麻酔科は依然FMGに頼らざるを得ない状況らしいが,問題は1年目必須の内科研修をどうするかなのだ。私も放射線科では5か所から面接の申し込みがあったがTransitional Year programは結局1か所のみという厳しい状況であった。FMGの場合は,USMLEの得点で85点以上またひどい所では90点以上といってくる。これから米国臨床留学をめざす人は満を持して試験に臨んでもらいたい。
プログラムの長所と短所
一泊しNY経由で翌々日デトロイト到着。1月27日水曜日,William Beaumont 病院はデトロイトの郊外に位置する非常に大きく豪華な私立病院で,病床数は929,年間入院数は約4万(全米で6位),救急患者は約8万,総外科手術患者数は約3万2,000とVolumeでは全米でも上位の病院である。今年からレベル3の救急病院に認定されたということで,ERがさらに忙しくなることは間違いない。
放射線科はというとCT5台,MRI3台にPET scannerも備えており立派なものである。中でも3年前にできたという外来患者専用の画像センターは素晴らしく美しい。1日の症例数の例をあげると消化管透視30例,マンモグラフィー150例とかなり多い。画像センターの隣に駐車場がありマンモグラフィーの患者などは車を停めてから受付し,検査を終え,支払いを済ませ,車に戻るまで約30分だそうだ。
私はこの面接旅行の途中から必ずプログラムの長所と短所を尋ねるようにしていた。相手を考えさせる場合もあれば,そこから新たな質問が生まれることもあり,短所を聞くのは私の場合有効であった。ここではそのどちらもVolumeであるという返事が返ってきた。
Volumeといえば驚かされるのが医師の数である。1200人の医師に加え300人を超す研修医が929床のために働いている。いくら専門化が進んでいるとはいえ,日本とはあまりに違う。彼らには勉強する時間,そして教育をする時間が仕事の一部として与えられているのだ。われらが日本の医師の頑張りを誉めてあげたくなった。
最後の面接へ
そして2月4日,とうとう最後の面接。もうこの頃には緊張感などなくなっていた。そのせいかどうか,2日前から風邪をひいてしまった。長期の面接旅行は気合を持続させるのが大変だ。同じ質問を何度も繰り返し聞かれ,それに対して同じ答えを繰り返す,だれてしまうのが人間だろう。目的は面接ではない,米国で研修を受けることなのだ。そう言い聞かせ自分を奮い立たせる,これが3週間しか続かなかった。デラウェア・メディカル・センターはフィラデルフィアから30分,Wilmingtonという街にあるデラウェア州唯一の公立病院である。患者の数は先に述べたWilliam Beaumont 病院より少し少ない程度。しかし放射線科のレジデントの数は先の7人に対し4人と少ない。当直の回数も多くレジデントはなかなか忙しそうだった。
プログラム・ディレクターは女性で,この人も教育熱心でプログラムを改善しようと奮闘していることがみてとれた。ここには2年目の研修医に伊藤宏彦先生という日本の先生がおられたので,事前に少し話を聞くことができた。
面接自体はとてもあっさりしたもので,私の体調が悪かったせいもあるのだが,ほとんどの時間を私から質問することに費やし,つまり相手にしゃべらせて自分の宣伝をするのを忘れてしまっていた。やはり万全の体調で望むべきと反省した。
ランキングとマッチング
以上で全面接過程を終了。しかし最も大事なそしてやっかいなランキングという作業が待っていた。自分の気に入った順に受けた所を並べるという,ただそれだけなのだが,これが難しい。やはり外科は上に置きたい,しかしPreliminary(1年あるいは2年限定の研修,上にあがれることは稀)はやりたくない。また放射線科の中でも迷う。アカデミックな大学病院にするか実践力の公立病院か,それとも美しい私立病院を選ぼうか,とかデトロイトは日本からの直行便があっていいけど,シカゴの文化的側面も見逃せないとか,判断基準が実にプロプロフェッショナルではないのだが,人生の中で5年間を過ごす場所をこんなサイコロを振るかのようにして決めるのだから,いろいろな要素を絡ませて考えてしまう。結局外科を上位に,次いでTransitional yearを含む5年間プログラムの放射線科をランクした。そして3月16日,インターネット上でロチェスター大学放射線科,そして1年目はボストンのLemuel Shattuck病院にマッチしたことを知った。私の米国臨床留学への道がようやく拓かれたのだ。
なぜ米国へ行きたいのか
どうしてこんなにしてまで米国に行きたいのか何度も自分に問いかけ,また米国で頑張っておられる先生方にも聞いてみた。面接のために必然的に自分の適性や将来の目標,医師としてあるいは1人の人間としてどう生きたいのかなどを文章としてまとめなければならなかったのだが,これが自分の考えを明確にするのに役立ったのみならず,今まで過ごしてきた人生の何分の一かを見直すいい機会となった。結局いまだにはっきりした答えはないのだが,自分を試してみたいというのが一番の理由だろうと思う。この国の研修システムの素晴らしさに魅せられたのがきっかけではあったが,“自分はどれだけ強くなれるのだろうか? 困難に出会ったとき私はどこまで頑張れるだろうか?”そんな少しいたずらめいた気持ちが,数年後の自分をまったく想像できない,そんな位置に私自身を置いてみたくなった一番の動機だろうと思う。
この辺で終わりとしたいが,最後にフィラデルフィアでの滞在中のみならず面接旅行で飛び回っている間,お世話になった津田武先生,青山剛和先生,佐藤隆美先生をはじめとする野口医学研究所の皆様,私のわがままを認めてくださった徳島大学第一外科田代征記教授および医局の皆様に深い謝意を表したい。
