MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


日本におけるペプシノゲン法の最新最高の報告書
ペプシノゲン法 三木一正 編集《書 評》久道 茂(東北大医学部長)
胃がん検診の現状
 1998年4月,厚生省の「がん検診の有効性評価に関する調査研究事業」研究班(総括委員長:久道茂)の報告書が公表された。わが国の老人保健法の保健事業の中に取り入れられている5種目のがん検診について,内外の学術雑誌や報告書を精査し,がん死亡率減少効果を示す確かな科学的根拠があるかどうか,その証拠の質の程度はいかほどか,などについて調査した。最終的に,わが国のがん検診についての「勧告」まで行なった。
1998年4月,厚生省の「がん検診の有効性評価に関する調査研究事業」研究班(総括委員長:久道茂)の報告書が公表された。わが国の老人保健法の保健事業の中に取り入れられている5種目のがん検診について,内外の学術雑誌や報告書を精査し,がん死亡率減少効果を示す確かな科学的根拠があるかどうか,その証拠の質の程度はいかほどか,などについて調査した。最終的に,わが国のがん検診についての「勧告」まで行なった。
その中で,胃がん検診については,「逐年のX線検査を用いた胃がん検診受診を勧奨する証拠がかなりある。ただし,検査の限界に関する十分な説明を事前に行なうべきである」とまとめた。これまでの胃がん検診の有効性を評価する種々の研究,例えば,症例対照研究,時系列研究,地域相関研究,非無作為化コホート研究,生存率比較研究など,RCT(無作為比較対照試験)以外の多くの研究で,いずれも胃がん検診は胃がん死亡率を減少させる証拠がかなりあるという判断をしたのである。
しかし,現行の胃がん検診には限界があることも確かである。関係者なら承知のことだが,間接胃X線撮影法は,粘膜変化を伴う胃後壁陥凹性病変や小弯線付近の場合は小病変でも抜群の診断能を発揮するが,前壁病変,小隆起性病変,平坦型早期胃がんの場合は,どうしても限界がある。これは,集団を対象とした検診の効率化のため,直接胃X線撮影法で行なっている圧迫法を採用していないことや,前壁病変に対する撮影方法と枚数に制限があるからである。
このような状況が続いていた中で,10年ほど前から新しい胃がんのスクリーニング法の開発に没頭していた東邦大学医学部の三木一正教授は,ペプシノゲン法を考案し,その基礎的実験,臨床での応用,アメリカや中国,UICCの研究機関等との共同研究,日本消化器集団検診学会附置研究会の発足,そして厚生省がん研究助成金による研究班の設置まで,ほとんど1人で努力され,忍耐強く,着実に成果を上げてこられたのである。その間,内外の消化器病研究者は,次第に関心を示すようになり,こぞってペプシノゲン法に関する研究を行なった。疫学研究,診断能の臨床研究,病理学的研究,そして集団を対象とした胃がん検診の実際へと研究が進んできた。
ペプシノゲン法の全体を網羅
本書は,近年注目されている胃がん検診におけるペプシノゲン法に焦点をあて,その疫学,基礎的・臨床的研究,実際の集検での成績など全体を網羅したものである。執筆者も総勢100名近くにのぼる,現在わが国における最新最高の報告書といえよう。しかも,編者はペプシノゲン法の長所だけでなく,限界にも触れている論文を公平に編集している。今後,本法のさらなる研究の発展のためには,本書の役割はきわめて大きなものになると信じる。いい著書である。関係者は必読すべきものとぜひ推薦したい。B5・頁288 定価(本体3,000円+税) 医学書院


最新の赤血球の情報が豊富に満載
赤血球 三輪史朗 監修《書 評》谷口直之(阪大大学院教授・生化学)
最新のトピックスを網羅
 言うまでもなく,われわれヒトの生化学を専門とするものにとっては,最も入手しやすい材料が血液であろう。戦後まもなく,物資も実験器具もない頃に,わが国の多くの生化学者が,その実験対象を血液,中でも赤血球を選んだのも必然であったと思われる。そして,その成分の分析から,国際的な独創性のある研究が生まれたのである。山川民夫先生により発見されたグロボシドなどは,その代表といえよう。研究費が豊富になり,研究環境の整った最近でも,生体膜の研究,ヘモグロビンなどに代表される多くのタンパク質の研究対象として,やはり赤血球の重要性はかわらない。生化学,分子生物学,血液学,免疫学などの専門家の研究対象である。本書は,最新の赤血球の細胞生物学,分子生物学,生化学が網羅されている。
言うまでもなく,われわれヒトの生化学を専門とするものにとっては,最も入手しやすい材料が血液であろう。戦後まもなく,物資も実験器具もない頃に,わが国の多くの生化学者が,その実験対象を血液,中でも赤血球を選んだのも必然であったと思われる。そして,その成分の分析から,国際的な独創性のある研究が生まれたのである。山川民夫先生により発見されたグロボシドなどは,その代表といえよう。研究費が豊富になり,研究環境の整った最近でも,生体膜の研究,ヘモグロビンなどに代表される多くのタンパク質の研究対象として,やはり赤血球の重要性はかわらない。生化学,分子生物学,血液学,免疫学などの専門家の研究対象である。本書は,最新の赤血球の細胞生物学,分子生物学,生化学が網羅されている。
これまでわが国には,臨床血液学の優れた本はみられたが,総合的に赤血球を扱った単行本は必ずしも多くない。1974年に,東大出版会から刊行されたCellular and Molecular Biology of Erythrocytes(H. Yoshikawa and S. M. Rapprot)は当時として画期的な,しかも,わが国の代表的な研究者が執筆しており,座右の書として,随分参考にさせていただいたものである。
事実この書の中で,山川民夫先生は,論文のabstractに“In studies of animal-cell membranes, red cellsare frequently used as experimental material since they are readidly available.”と記載されておられる。時代をよく反映した記述である。
「赤血球フォーラム」のメンバーを中心に
さて本書は,17章からなり,最新の赤血球の細胞生物学,分子生物学,生化学が網羅されている。つまり,最新の赤血球の情報が豊富に満載されているといえよう。毎年「赤血球フォーラム」という小さな会が本書の監修者である三輪史朗先生を中心に,日本生化学会の期間中に開催されており,そのメンバーの中心である専門家の方々が執筆されている。編集者の藤井寿一,高桑雄一両氏はそれぞれ,ピルビン酸キナーゼとサイトスケルトンの専門家であるが,編集者の専門に偏ることなく,全般をよく網羅しており,監修者と編集者の企画が行き届いている点に敬服する。特に,幹細胞から,転写制御調節など,現在の分子生物学,細胞生物学のトピックスを十分網羅しているだけでなく,レオロジー,加齢変化の問題なども扱っている。基礎と臨床の接点
また,自己免疫性溶血貧血や,発作性夜間ヘモグロビン尿症など,病気の発症の分子機構にせまる記述など,基礎医学と臨床医学との接点ともいえる内容が記載されており,これから,基礎研究や臨床研究をめざす方々にも,大いに参考になろう。挿入図も大変わかりやすく,学生の講義の資料などに利用させていただくには大変好都合である。赤血球を扱っていない研究者にも大いに参考になる記述が多い。もちろんトピックスが網羅されているだけに内容はやや高度であることはやむを得ないが,欲を言えば,専門外の研究者や学生のために用語説明などがついていると,もっと理解しやすかったと思われる。座右の書としての価値は十分ある。
B5・頁268 定価(本体9,000円+税) 医学書院


日常臨床を視野においた呼吸器の病態生理のテキスト
呼吸の病態生理 第3版ジョン・B・ウエスト 著/堀江孝至 訳
《書 評》佐々木英忠(東北大教授・老年・呼吸器内科)
ジョン・B・ウエスト教授は呼吸の病態生理学の世界の第一人者であるが,本書は真にそのエッセンスが凝縮されて掲載されているというのが一読した第一印象である。そのエッセンスをさらに高めて,われわれ日本人にもわかりやすく翻訳していただいた堀江孝至教授も,この分野の第一人者であるため,車の両輪のごとく相乗効果となり,本書に表われている。
従来,この領域では数式やほとんど日常用いられていない末梢のことまで細かに述べられていて,本筋がどこかへいってしまう例が多かったが,本書は,本筋をはずさないで,しかも,日常われわれが遭遇する呼吸器疾患の病態生理をわかりやすく解説している。そのため,教科書を読むというわずらわしさはなく,むしろ,楽しんで読めるという感がする。
病理組織を頭でイメージできる
その理由の1つは,実際の組織図を随所に入れて,次に模式図で解説し,病態を示すという一貫した流れからきているため,あたかも日常臨床の基本である病理組織を頭にイメージしながら,何の抵抗もなく受け入れられるところにあると考えられた。呼吸器疾患に限らず,疾患を把握するためには第1に病態生理が基本であるが,本書では各疾患の病態生理まで追及しており,単なる生理学ではもうとうなく,それこそ,日常臨床を視野においた病態生理である点が本書の第2の特質であろう。ここにも堀江孝至教授の日頃の考え方が導入されてすぐれた内容となっている。
ジョン・B・ウエスト教授は,日本人が好きでしばしば来日されているが,本書はすでに第5版を重ねるという全世界に好評の書である。そして堀江孝至教授によって,日本語版でも第3版と版を重ね,そのたびごとに改良,改筆を加えられすばらしい内容に仕上がっており,しかも,頁数は224頁と適量になっている。いかに,むだなくエッセンスを盛り込んであるかの証拠である。
医師,医学生の必読の書
医学部の学生の必読の書であることはもちろんのこと,呼吸器専門医をめざす医師,また麻酔科医,外科医など,すべての領域の医師にとっても必ず役立つものと確信するため,ここに推薦のことばを書かせていただいた。A5変・頁224 定価(本体3,800円+税) 医学書院MYW


呼吸器疾患の分子生物学の最前線を網羅
呼吸器疾患の分子生物学 川上義和,他 編集《書 評》北村 諭(自治医大教授・呼吸器内科学)
呼吸器疾患研究の大きな流れ
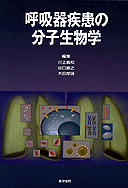 筆者は,昭和30年代の後半に大学病院の医局に入局し,呼吸器病学の臨床と研究を開始した。当時の東大第3内科第5研究室(呼吸器グループ)には,長沢潤(元天皇侍医),三上理一郎(元奈良医大教授),原澤道美(東大名誉教授),吉田清一(埼玉がんセンター名誉総長),吉良技郎(順大名誉教授),福島保喜(東邦大名誉教授),村尾裕史(日本イーライリリー相談役)といった錚々たるメンバーがいた。
筆者は,昭和30年代の後半に大学病院の医局に入局し,呼吸器病学の臨床と研究を開始した。当時の東大第3内科第5研究室(呼吸器グループ)には,長沢潤(元天皇侍医),三上理一郎(元奈良医大教授),原澤道美(東大名誉教授),吉田清一(埼玉がんセンター名誉総長),吉良技郎(順大名誉教授),福島保喜(東邦大名誉教授),村尾裕史(日本イーライリリー相談役)といった錚々たるメンバーがいた。
呼吸器の患者としては,肺結核,肺炎,慢性気管支炎,気管支喘息,肺気腫,閉塞性肺炎は稀であった。当時の呼吸器の臨床は,1枚の胸部X線写真を試し透かして読影し,それに断層写真,気管支造影写真を加えるくらいであった。肺癌症例が増加し始め,坪井式の擦過細胞診用ゾンデが開発されたのは,それからしばらくしてであった。したがって,当時の研究は,剖検所見を臨床経過と組み合わせた,いわゆる,臨床病理学的研究というテーマが大部分を占めていた。
その後,米国やヨーロッパで,肺機能・肺生理学の研究をしてきた医師が続々と帰国し,日本の呼吸器病学は,肺機能・肺生理学の全盛時代となった。また,肺循環や肺表面活性物質の研究もさかんに行なわれるようになった。
1970年代後半になり,螺良英郎先生(当時徳島大教授),広瀬隆士先生(当時九大胸研),筆者らを中心として,肺の代謝機能すなわち生化学的アプローチによる肺機能の研究が行なわれるようになった。
日本の医学界全体の研究も,cyclic AMP,cyclic GMPをめぐる研究がさかんとなり,次いで,プロスタグランジンに関する研究が一世を風靡した。当時は2年に1回,主としてイタリアのフィレンツェ市でプロスタグランジン国際会議が開催された。その頃にカロリンスカ研究所のSammuelsson教授がSRS-Aがleukotriene C4,D4であることを解明し,ノーベル医学生理学賞を受賞し,次いで,J.R. Vaneがプロスタサイクリンの発見で,ノーベル賞を受賞した。
今から8年前にはRMCB(Respiratory molecular cell biology)研究会が発足し,分子生物学的手法を取り入れた研究がさかんに行なわれるようになった。
呼吸器疾患の多方面にわたって記述
このような時期に医学書院から,『呼吸器疾患の分子生物学』という単行本が出版された。本書は,大きく,呼吸器疾患と分子生物学の接点,呼吸器疾患における分子生物学の基礎とその臨床応用,分子生物学の基本手技,インターネットを利用した新しい情報の入手方法の4章よりなる。執筆者は90名であるが,そのうち40%は基礎部門の研究者である。呼吸器領域においても分子生物学的・遺伝子学的手法による研究は年ごとに増加しているが,まだまだその研究者の人数が欧米に比較すると極端に少ないのが現状と言えよう。
本書は450頁ほどのモノグラフであるが,その内容は,呼吸器病学の多方面にわたっており,非常にすぐれたものである。
これから,呼吸器疾患の分子生物学を志す若い学徒にとって,必読の入門書になるものと確信する次第である。
B5・頁468定価 (本体16,000円+税) 医学書院


著者の経験が熟成された実践手術書
緑内障から見たIOL手術 近藤武久 著《書 評》根木 昭(熊本大教授・眼科)
緑内障の有病率は40歳以上の3.5%でその数,約200万人。一方,白内障手術件数は年間60万件と言われる。両手術とも強角膜輪部を切開創とするため,それぞれの手術が相互に術式や効果に影響を及ぼす。近年,白内障分野では小切開手術や結膜を消費しない角膜切開手術が普及し,緑内障分野では,合併症をかかえながらもマイトマイシン併用手術が目標眼圧達成成績の向上を招いたことで,従来の白内障緑内障同時手術の適応に大きな変化をもたらした。現在,緑内障患者はその2割しか治療されていないといわれるが,正常眼圧緑内障の頻度の高さに対する眼科医の関心の高まりは緑内障患者の新規発掘をうながし,今後両者を併発する患者数は急激に増大すると予測される。白内障手術をする時は必ず緑内障に留意し,緑内障手術をする時には必ず将来の白内障を考慮せねばならない時代である。
実践に徹したリズム感のある記述
本書はこのような状況を踏まえた実にタイムリーな出版である。まず美しい写真に見入ってしまうが,文章が簡潔で理解しやすいのが特徴である。実際の手技がカラーで図示されているのもよい。そしてなんといっても内容が実践に徹しているのでリズム感がありどんどん読み進むことができる。“私のノウハウ”や“ワンポイントアドバイス”には著者の経験が濃縮されており,明日からすぐにでも使えて大変実用的である。最近は共同執筆による著書が多いので同時手術のような意見の分かれるところでは結論がぼかされ後味が悪いが,本著は単独執筆だけに同時手術では“レンズ全長が短く,ハプチクスの弱いレンズ(アクリルレンズ MA30BAなど)は回避したほうがよい”とかneedlingはV-Lanceナイフが“通常の注射針よりはるかに操作性がよくて,安全である”など著者の豊富な経験から断定してあり説得力がありすっきりとした読後感がある。私事で恐縮だが,私は著者のもとで初期研修を受けた。当時大学では眼内レンズは扱っておらず,研修病院で初めてみた手技は粘弾性物質もなくまさに神業であった。わが国でも有数の多忙な病院であったが,著者の日常は実に淡々とし何事があろうと術前後でつねに変わらず平静であった。しかし本著の“忘れ得ぬケース”には生きた心地がしなかった,残念であった等の著者の心情がてらいもなく吐露されており大変感銘を受けた。この項を読むだけでもいろいろな歴史が頭をよぎる読者も多いことだろう。あたらしい手技に臨む姿勢があらためて正される気がした。
手術前夜に手に取る1冊
題名は“緑内障からみたIOL手術”であるが,内容的には白内障手術全般,また緑内障手術単独をもカバーしたものである。B5サイズで持ち歩きができ,活字が見やすいため通勤やベッドのなかでも読むことができる。合併症対策が豊富で後嚢破損や硝子体脱出,切開線の亀裂など目次を見るだけで簡単に目的頁を捜すことができ,まさに手術前夜に手に取る1冊といえる。著者の長年の経験が熟成された誠に味わい深い実践手術書である。B5・頁140 定価(本体8,000円+税) 医学書院
