<新春インタビュー>
1999年の臓器移植
田中紘一氏(京大教授・移植免疫医学)に聞く
 |
| 田中紘一氏
1942年,大分県生まれ。1966年京大外科入局。島根県立中央病院勤務,京大第2外科研究室助教授などを経て,1996年12月より京大大学院医学研究科移植免疫医学講座教授。 1990年より臨床生体肝移植に取り組み,これまでに400例以上を手がける。また,生体小腸移植を唯一手がけている |
移植医療の現状
―――臓器移植法施行から400日以上が経過しました。移植医療の現状とは?田中 日本では,腎臓以外の臓器移植は海外に行って受けざるを得ない時代が長く続き,1昨年の10月16日にようやく臓器移植法が施行されました。この1年間,1例も脳死移植はなかったものの,日本における移植医療の確立へ向けて一歩も二歩も前進したことは間違いありません。法律の中身については厳しすぎるという受け取り方もありますが,逆にいえば,日本における移植医療の歴史的背景からそのような法律となったことも確かで,当面はそのことを尊重し,臓器移植法の精神に則って進んでいくべきだと考えています。
もちろん,(脳死移植を)待っている患者さんには,1日も早くという切実さがあり,現在も大変苦しい時を送っています。しかし,欧米のような移植医療の先進国の歴史を振り返ってみても,一朝一夕に今日の医療を実現しているわけではありません。日本における現在とは,臓器移植法の精神に則って,さまざまな分野の方が,移植医療の確立のために地道な努力を重ねている段階だという認識です。
―――臓器移植に関わる医療者として取り組んでいくべきことは?
田中 私たちも地道な努力を続けるしかありません。具体的に言えば,脳死移植が実施できない以上,取り組むのは生体移植ですが,その移植医療を受けた人たちをできるだけ健康な体にして生活の場へ戻すということです。そして,その方たちがいろいろなところで活躍する。あるいは学校で楽しい生活を送る。そういう人たちが増えれば増えるほど,社会の移植医療に対する理解は深まっていくのだと思います。
移植現場の課題
―――いまだに1例も脳死移植が行なわれないということによって生じている移植医療の現場での問題は?田中 いくつかの難しい問題があります。まず,脳死肝移植の待機患者として実際に登録をした人たちの「移植を待つ思い」と直接の関わり合いを持たねばなりません。悩みを抱える患者さんをいかにサポートしていくかという問題です。
また,待機している患者さんたちをいつの時点で生体肝移植に切り替えるか,ということにも常に注意を払っていなければなりません。このタイミングの見極めも非常に難しいことです。脳死移植を待ち続けた末に,その限界のところで生体肝移植に切り替えた場合,手術成績は悪くなってしまいますから。
生体肝移植の成果がある程度期待できる状態の患者さんに対して,病状の悪化を心配する一方で,「脳死移植を待つ」という患者さんの思いも大切にしなければなりません。これが難しいところです。
全国初の「臓器移植医療部」
―――京大病院には全国初の「臓器移植医療部」設置が予定されていますが,その意義は?田中 脳死臨調以来,「オープン(情報公開),フェア(移植機会の公平・公正),ベスト(最善の医療体制)」ということが言われるようになり,一昨年の臓器移植法の施行により国家的プロジェクトとして,それをめざした移植医療の基盤整備がされつつあります。臓器の斡旋組織としては日本臓器移植ネットワークを全国7ブロックに分け,公平・公正な臓器の配分システムが確立されました。一方これに基づく,移植施設の確立と整備(ベストな医療体制)が今後の課題となっています。
移植医療は,臓器の置換のために臓器提供が必要であると同時に,自分以外の臓器 を受け入れるのに必要な免疫抑制療法が欠かせません。この2つが,これまでの医療とは大きく異なる点であり,すべての臓器移植に共通することです。そして,移植成績向上のためには移植技術よりもさらに重要なことでもあります。
このような特性を持つ臓器移植を円滑に推進するためには,各臓器に共通する免疫抑制療法の調節,感染症対策等の組織的患者管理,移植のための医療機器の運用と管理,拒絶反応診断のための病理組織の作成と診断が常時行なえる組織とともに,患者および家族の精神面でのケアを行なう移植コーディネーター職や,外来ケア,長期管理への対応など,現行の移植医療ではカバーできていない新たな患者管理まで行なえる総合的な組織が必要です。
また,免疫学やウイルス学などの先進的な基礎研究の成果を臨床の場へ応用していくための作業を組織的に組み立てていくことも大切です。臓器移植医療部はこれらを総合的・効率的に推進するためのものです。本年4月の開設を予定しています。
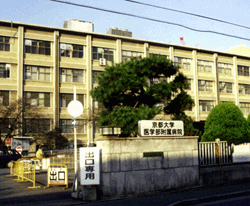 |
| 京都大学医学部附属病院
現在,肝臓と肺の脳死移植実施施設として選定されている。同院の移植外科は,年間90件を超える生体肝移植を行なうと同時に,国内他施設や外国での移植も50例近く支援しており,生体肝移植の世界的なセンターとして知られる。また,生体小腸移植も手がける唯一の施設である |
臓器の垣根を越えた組織
―――京大病院として取り組む臓器移植領域拡大への展望は?田中 すでに肝臓と肺については,脳死移植実施施設として選定されていますが,小腸および膵臓についても早期移植が実現するように積極的に推進していきます。肝・腎の生体移植とともに関与していく臓器移植医療の領域は確実に拡大していくでしょう。そのためにも,心臓外科での心臓移植,呼吸器外科での肺移植,泌尿器科での腎移植,移植外科での肝・小腸・膵移植後に,各科と協力して患者さんを集中的に専門集団で管理し,状態の安定をもって各科へ転科できるような,臓器の境界を超えた新たな組織としての臓器移植医療部がぜひ必要なのです。また,当院にそれを設置することにより,他の施設でも同様の組織が作られることが期待できます。
―――臓器移植医療部の設置によってどのような成果が期待できますか?
田中 まず,第1に患者さんにとっては,より信頼できる医療を受けられること。第2に,基礎的な研究の臨床への応用が進むということ。そして第3に,日本で培われた臓器移植医療の成果がより海外へ発信できるようになることです。すでに,約30か国の人が京大に生体肝移植を見学に来ています。日本で培われたいろいろな成果が,今度はさらに海外へ貢献する。特にアジアの人たちに大きな貢献ができるのではないかと考えています。
特異的免疫抑制剤の開発
免疫寛容の探究
―――本年度の田中先生ご自身の臨床・研究の中での課題は?
田中 臓器移植の歴史は免疫抑制剤の進歩と深く関わっています。
現在の免疫抑制剤の効果は非特異的免疫抑制であるために,移植された臓器以外の外敵に対する抵抗力も落ちてしまうという問題があります。それに対して,例えば肝臓を移植したら,肝臓だけ攻撃する拒絶反応を抑えて,他の生体防御は全部維持してくれるような「特異的免疫抑制剤」の開発が模索されています。たくさんの方が取り組まれていますが,私たちにとっても大きな目標です。まだ何とも言えないところですが,ここには分子生物学の進歩も貢献するかもしれません。
もう1つは,移植した後に拒絶反応を起こさずに,移植した臓器を自分の中に受け入れるという「免疫寛容」を,より導入するという方向での治療の追究です。現在の移植医療は免疫抑制剤を使いすぎている可能性が高く,免疫抑制剤の減量・離脱への取り組みも大切だと考えています。現に当院の生体肝移植では,すでに15人ほどの患者さんが免疫抑制剤をまったく飲んでいません。それぞれの患者さんについて,何が免疫寛容をもたらしたのか。あるいは,より免疫寛容を導入するにはどうしたらいいのか,という探究を続けたいと思います。
地道な努力が道を開く
―――最後に,日本社会における移植医療の展望をお聞かせください。田中 これはかなり難しい話になります。移植医療とは,海外での歴史をみても,臓器移植法の精神から考えても,「自分たちはどう生きるか」そして,「自分たちはどう死ぬか」という,「自己決定」の上に立脚したものです。ですから,臓器移植医療とは,他人まかせでは決してできません。自分たちでいろいろなことを決めていく中で初めてできるものなのです。そのような意味では,社会のあり方やそれを構成する人々の意識のあり方と深く関わっています。
また,臓器移植とは大きな「連帯」であるという側面があります。「連帯」は「思いやり」に通じるものであり,社会の財産としてそれを育てていかなくてはなりません。ですから,教育の果たす役割は非常に大きく,これを教育の場から着実に普及させていくという地道な努力が大切です。
日本人には元来,人を思いやる心も知恵もあります。1つひとつの地道な努力の積み重ねが大きなバックグラウンドを作り,理解が広がっていけば,いつか必ず道が開けると信じています。
―――ありがとうございました。
