第57回日本癌学会総会より
癌の転移,悪性化のメカニズム
-日本癌学会教育講演より
第57回日本癌学会総会(参照)の最終日には教育講演が企画され,気鋭の研究者・臨床家が,癌の研究や診断,治療の最前線を紹介。本号では広橋説雄氏(国立がんセンター研)による「病理学からみた癌の個性」,中村祐輔氏(東大医科研)による「遺伝子研究の臨床への応用」を報告する。


細胞接着機能の不活性化
癌の9割は人体の上皮組織に発生し,進行すると上皮組織の基底膜を破り周辺組織に浸潤し,リンパ節などを介して転移する。広橋氏は,「細胞間の相互作用の結果である転移には不明な点が多いが,増殖した癌細胞がばらばらになりやすい」ことに注目,細胞間接着分子であるカドヘリンに遺伝子変異が起こる結果,癌細胞は原発巣から分離して転移につながることを証明した。まず広橋氏は,「癌細胞における細胞接着機能の不活性化にはカドヘリンおよびその細胞内結合蛋白であるカテニンの遺伝子変異,転写調節領域のメチル化などの多様な機構が存在する」ことを示し,「カドヘリン,βカテニン,αカテニン細胞接着装置が,癌の増殖因子によるシグナル伝達によって異常が起きる」と指摘。また,「家族性大腸ポリポーシス症の原因遺伝子であるAPCもβカテニンと結合・分解する働きに関与しているということがわかってきた。分解されるといいのだが,分解されなかった場合,βカテニンが蓄積し,核内に移って別な細胞の増殖などに関わる遺伝子群の発現を調節することで,癌化へ進む」との知見を披露した。
さらに広橋氏は,「癌の浸潤の先端では,癌細胞がばらばらになると同時に周囲を分解する酵素,その他,いろいろな遺伝子の発現がハーモニーをともない浸潤する。そして本当の転移というものが起こる。その仕組みに構造異形からの研究により迫ることができた」と述べ,病理形態学が分子科学と結びつくことによる,癌本態の理解への貢献を強調し,多分野からの癌というものの理解に癌の形態の情報を合わせ,癌の個性を診断していくことの重要性を説いた。
共通の遺伝子異常をターゲットに
一方,中村氏は1991年に氏自身が単離したことで知られるAPC遺伝子およびそれに結合するβカテニンをめぐる最近の研究成果を報告した。中村氏は,大腸癌の発現機構におけるβカテニンの働きに注目。APC,あるいはβカテニンに異常を起こすことによって,大腸の粘膜細胞にポリープが発生することから,βカテニンの癌への関与を探索。解析の過程で80-90%の大腸癌および一部の肝臓癌においてもβカテニンの異常が非常に多いことが明らかになったと報告。さらに,「βカテニンが異常を起こすと細胞を悪性化させるのであれば,大腸癌,あるいは一部の肝癌においてはβカテニンの経路を遮断することによって,治療への糸口を見つけることができるのではないか」との戦略から,βカテニンそのものが細胞を悪性化することの可能性を調べた結果,「通常では,細胞は増殖の限界に達すると死に至るが,変異型βカテニンを導入すると死というプロセスを経ず,上に積み重なるように細胞は増殖するという研究結果が得られた。それに対して,栄養状態の悪いDOXという物質を入れ,変異型βカテニンの発現を抑えると増殖は抑えられた。また,悪性転化した細胞において異常なβカテニンの経路を遮断すると腫瘍細胞を正常化させる可能性がある」と報告した。そして中村氏は,「βカテニンが異常になった段階でどのような経路で細胞が悪性転化するか,また,どのような変化が細胞の中で起こって腫瘍化につながっているのか,その経路の解明,あるいはβカテニンそのものをターゲットにした新しい治療法の開発につなげたい」と意欲を見せた。
さらに中村氏は,関連する欧米での遺伝子研究とその臨床応用の現状に触れ,「それぞれの癌において共通している異常をターゲットにした新しい治療の開発が急速に進んでいる。乳腺の場合には,Rb2という遺伝子の研究成果から,それを利用して癌細胞の増殖を抑えようという研究がなされ臨床応用されつつあり,また,人の癌でみつかったras遺伝子の異常,あるいはp53遺伝子の異常を標的としてこれを元に戻す,あるいは抑える治療法が開発されている」とその活況を紹介するとともに,日本での研究,臨床応用の遅れを指摘し,「癌細胞の研究をするということは敵の本体を知ることだ。癌における遺伝子の異常を探すことが癌の治療につながっていることは欧米が実証している」と強調した。
癌の個性診断
中村氏は最後に,癌の個性診断について言及。「同じ臓器に生じた癌であっても,個々の癌の性質はまったく同一であるということはない。したがって,薬剤や放射線療法等の治療に対する患者個々の感受性などは当然異なってくる。分子レベルでの知見をもとに患者個々の,または個々の癌の個性を的確に把握して,その患者にとって最も適切な治療法を選択していくことが,今後の癌の診療にとってきわめて重要」と指摘し,講演を終えた。21世紀の放射線治療への道
-キュリー夫妻ラジウム発見から100年

学会のシンポジウム企画として開催された「キュリー夫妻ラジウム発見100周年記念シンポジウム」(司会=癌研 伊藤彬氏,国立がんセンター 佐々木康人氏)では,キュリー夫妻がラジウムを発見した歴史的意義から21世紀に向けた放射線治療の方向性を探ることを目的に,司会の両氏を含め7人が登壇し,議論を深めた。
物理,工学的視点から
司会を務めた伊藤氏は,最初に「キュリー夫妻ラジウム発見の意味するもの」を口演。「ラジウムの発見は,物理学,化学,生物学,医学等の自然科学にインパクトを与え,20世紀の“核の医学”革命をもたらす直接のきっかけとなった」と位置づけ,ラジウム治療線源の研究について解説。1914年にパリにラジウム研究所が設立されたこと,また同研究所からキュリー夫人が亡くなった1934年に,日本の癌研究会癌研究所にラジウム(5g)が寄付され,日本の放射線治療が始まったことなどを報告した。またその後,ラジウムに代わる放射線源の開発は,放射性同位元素の医学診断への応用など,無限の可能性と発展性を持っていることを強調した。次いで,尾内能夫氏(癌研)は「ラジウム研究とラジウム治療の歴史的意義」について解説。ラジウムのα線からは中性子の発生,ウランの核分裂の発見(1936年),原子炉製作(1942年)につながったことや,β線からの陽電子発見はポジトロン,PETの開発につながったことなどが報告された。また,「各種ラジウム療法の開発が,現在の放射線治療の基礎になっている」と述べる一方,ラジウムは放射性ガス汚染などの欠点があることから医療に用いることの危険性が指摘され,1981年には国際放射線防護委員会が使用中止を勧告しているが,尾内氏は「誕生83年にして引退せざるを得なかったが,ラジウムは本当に危険なのか」との疑義も呈した。
医学,臨床の視点から
また,佐々木正夫氏(京大)は「放射線感受性の解析:ATM遺伝子を中心に」を,大野典也氏(慈恵医大)は「放射線感受性プロモーターを用いた遺伝子治療」で,放射線治療と遺伝子治療の併用,さらに薬剤を含めた治療法の開発について報告した。臨床の立場からは山下孝氏(癌研)が,「皮膚癌の治療から始まった日本の放射線治療は,その後頭頸部癌や子宮癌へと範囲は広がっていったが,ラジウムの危険性が指摘されたために最近ではイリジウムに置き換えられた治療となり,適応範囲も拡大した」と述べた。その上で,外陰部癌や軟部組織への照射により組織温存が可能になったこと,普通病棟での治療が可能になったこと,乳癌再発後の組織照射により生存率が向上したことなどの成果を報告。また,「イリジウム小線源治療はコバルト照射と同様の効果がある」と述べ,その治療方針などを提示した。
池田恢氏(国立がんセンター東病院)は,「高齢者の放射線治療」について考察。「65歳以上の癌患者が1/3を占めるようになった現在,超高齢患者でも治療を受けたいと希望する者が多い」と述べ,がんセンター8施設での90歳以上の新患者に対する放射線治療の集計結果を報告した。それによると,放射線治療の完遂度は75%であり,外科手術よりも侵襲が少ないことから,「年齢は大きな予後因子ではない。高齢者への優しい治療である」と結論づけた。
最後に司会の佐々木氏が,「放射線治療の新方向」と題し口演。ガンマナイフ治療の症例数などを報告するとともに,C-アーム式集光照射装置などの新しい器械も紹介,術中照射も可能になったことを述べた。
その後の総合討論は,「21世紀の放射線治療の道」をテーマに,(1)キュリー夫妻によるラジウム発見の意義,(2)放射線治療の物理・工学的課題,(3)放射線治療の医学・生物学的課題,(4)放射線治療の臨床的・社会的課題の側面から意見交換が行なわれた。その中で,「キュリー婦人は施設内放射線被爆による白血病で死亡したとされているが,ラジウム汚染ではなく,X線装置を乗せた自動車での移動の際の被爆が原因」との新解釈も報告された。また,尾内氏は「放射線をかけすぎると悪いのはなぜか」との疑義を出すなど,ラジウム発見から100年が経過した現在,ラジウムの見直しの必要性が示唆されたシンポジウムとなった。
吉田賞は黒木登志夫氏,長与賞は市川平三郎氏
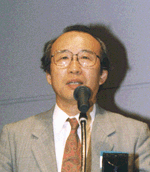

日本癌学会は,癌研究者吉田富三および学会創始者である長与又郎を記念し,癌研究の業績に対して吉田富三賞を,主に臨床,社会医学に関する業績に対しては長与又郎賞を設け,優れた癌研究者に授与してきた。第7回を迎えた吉田賞は,試験管内発癌研究,シグナル伝達研究を通じた業績が評価され,黒木登志夫氏(昭和大教授,写真左)。第3回長与賞は胃の2重X線造影法の開発と普及を通じた業績が評価された市川平三郎氏(国立がんセンター名誉総長,写真右)がそれぞれ受賞した。


