【座談会】これからの薬物治療はどうあるべきか | |
| 上野文昭氏 大船中央病院内科(司会) |
石岡忠夫氏 仁生社江戸川病院高砂分院副院長 |
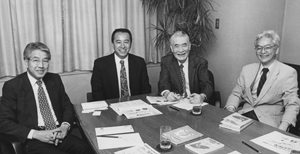 | |
| 北原光夫氏 東京都済生会中央病院副院長 | 津谷喜一郎氏 東医歯大助教授・臨床薬理学 |
日本の薬物治療の問題点
上野 医療に対して厳しい批判的な目が向けられている今日この頃ですが,本日お話いただく薬物治療も,例外ではありません。日本は何事によらず技術開発がさかんで,医薬品に関しても次々と新しい製品が開発され,市販されています。もちろんその中にも有益な薬もたくさんありますが,問題は実際の薬の使い方です。つまり,せっかくよい薬剤が出てきても,患者の利益として還元されていないのではないかと考えられます。
本日は,この問題を見直して,これからの薬物治療に関する正しい方向づけをご討論いただきたいと思います。
医師を取り巻く薬の問題
上野 まずはじめに,日本の薬物治療の問題点を具体的に整理していただきたいと思います。最初に,海外と日本の内科臨床を比較する目をお持ちの北原先生にお話しをうかがいたいと思います。
 北原 1つは,日本の中で数多くの抗生物質が作られて,そのことに批判がありましたが,問題なのはその使い方であり,決して効かないような薬剤はありませんでした。使い方さえ間違えなければきちんとした医療が行なえるはずです。
北原 1つは,日本の中で数多くの抗生物質が作られて,そのことに批判がありましたが,問題なのはその使い方であり,決して効かないような薬剤はありませんでした。使い方さえ間違えなければきちんとした医療が行なえるはずです。
もう1つは,欧米ではまったく評価されていない,あるいは効かない薬が,日本では相変わらず使用され続けていることがあげられます。例えばある種の癌に使われているものや,消炎酵素剤のように小腸で全部分解・吸収されて単なるアミノ酸に変わってしまう薬もあります。同様に止血薬が依然と使われているのが現状です。このあたりの問題は指導者の立場の人間を教育しないと,相変わらず効かない薬が使われ続けることになります。
さらに,医師のデータの読み方の能力があげられます。最近,厚生省から発売中止となった脳循環代謝改善薬がその例です。
これには,インフラストラクチャーをきちんとしなければいけないし,それを見きわめる医師の能力も問われるのではないかと感じております。
上野 大きく3通りのご指摘をいただきました。いずれも臨床医の見識があれば回避可能なようですね。
津谷 日本で「適正使用」という場合,現場で医師が「クリティカル・アプレイザル」(批判的吟味)をしっかりやればよいという考えがあります。しかし,個人の臨床医のできることは限られていますね。効かない薬,危険な薬が市場にあるというシステムそのものに問題がある場合,そのシステムそのものが変わるべきだという点をあげておきたいと思います。
もう1点は,日本は世界でも有数の長命国で,国際的に比較してもかなりよいヘルスステイタスをエンジョイしていると思います。そのステイタスのうちのどのくらいが医薬品によるものかを明確に言うのは難しいのですが,私はそれほど高くない気がします。衛生状態や日本が持つヘルスシステムのよさが効いているのであり,薬物自体はわれわれの健康管理にそれほどは役立っていないかもしれないことを振り返ってみるといいのではないでしょうか。
日本人の国民性と薬物治療
上野 石岡先生は臨床だけでなく,臨床薬理や統計にも造詣が深いのですが,先生の目から見たわが国の薬物治療の問題点はどのようなものでしょうか。石岡 日本の国民性あるいは医療の歴史を考えますと,「医師」という言葉より先に「薬師」(くすし)という言葉が出て,薬をくれるものが医療だという連綿たる歴史があると思います。薬師如来が繁盛するような状況で,正確な診断より「薬を出すもの・もらうもの」という考えが,日本の国民性の中に定着しています。
明治以降になると,これは有名な言葉で,「治療は診断に付随する」とあります。きちんとした診断ができれば,それに伴って自動的に治療は決まってくるという考えがありました。一方,治療が自由になると,薬を軽視する傾向が医学教育でもあり,現在,後輩たちの状況を見ても,臨床薬理学的な側面から見た治療学の教育はまったくなされていません。そのギャップが,現実の場に出てきているのではないでしょうか。
医学教育における薬物治療学
上野 日本の医学部では,薬物治療を1つの診療技術として教えてはいないように思います。当然,卒後教育でも同様で,内科に限らずすべての科で,薬物治療を技術としたはっきりとした形での教育をしているとは思えません。その点については津谷先生,いかがでしょうか。津谷 私は臨床薬理学の分野におりますが,今の教育には問題があると考えています。
私は臨床薬理学を薬理学の枠組みの中で,東医歯大と東大で3年と4年生に教えています。内容は基本的には臨床試験の方法論と倫理です。しかしそれだけでは決して十分ではありません。私が臨床薬理学を教えている大学に限らず,日本の医学部には,薬の使い方をきちんと教育しているところはほとんどないようです。また,それをどのタイミングで教育すべきなのかを,日本の状況も考えた上で探っていく必要があると思います。
上野 臨床薬理学を医学部低学年に教えても,確かに彼らは興味は湧かないと思います。実際に臨床に相当浸ってからでないと,薬物治療の重要性はわからないという問題点があると思います。
北原先生は,初期研修医にどのような形で薬物治療を教育されているのですか。
北原 臨床薬理学とは,なかなか日本では教えにくいものですね。われわれの病院でも,きちんとレジデント教育を行なっているつもりですが,それは治療や診断の面であり,薬の使い方や機序に関しては,なかなか教えられません。教える側の医師にそういった素養が積まれていないと,難しい点があると思います。
先輩の処方を盗むことの功罪
上野 石岡先生,かつては薬が治療そのものだったのが,次第に診断重視,薬軽視に変わってきたとのことでしたが,この傾向は今後どうなるでしょうか。石岡 正確な診断に正確な治療がついてくるのは確実なことで,どちらが主か従かといえば,診断に比重がかかってくるのは内科医として当たり前だと思います。
私の病院には,ある大学から研修医が来ていますが,みな薬の処方をどうしていいのかわからないと言います。私たちが医師としてのスタートをきった時には,先輩の処方を盗もうと,当直の時にカルテを見て,この疾患にはこの薬を使っている,これはどのぐらい使うもの,としていたように覚えています。
上野 先輩や教授の処方を盗むことですが,その盗んだ相手が正しいかどうかの保証はありません。科学的根拠を持たずに,ただ専門家や先輩に追従するのは,わが国の薬物治療をだめにした最大の原因の1つではないかと思っています。
津谷 私も医師になって,薬の処方をどうしていいのかわかりませんでした。結局,見よう見まねで自分の病院,あるいは今考えるとナンセンスなことをやっていたなと思いますが,パート先の約束処方まで自分の手帳に書きとめて,これでやっと処方ができると安心した覚えがあります。
結局,教育されない限りは,誰しも同じようになってしまうのではないのですか。
氾濫する医薬品情報
MRとどう付き合うか
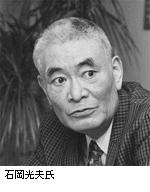 石岡 薬の情報を得るのに,プロパー,今で言うMRからいろいろ聞きました。MRの影響力は絶大で,現在でも新薬の動機づけの最大の因子がMRです。
石岡 薬の情報を得るのに,プロパー,今で言うMRからいろいろ聞きました。MRの影響力は絶大で,現在でも新薬の動機づけの最大の因子がMRです。
上野 実は,私自身はMRから流される情報を鵜呑みにすることが,大きな問題ではないかと思っています。MRが自社の製品を売り込むのは彼らの正当な仕事ですので,臨床医はそれを批判的に見る目が必要ではないかと思います。
津谷 確かにMRからの影響は非常に強いと思います。先日,オーストラリアからMRとの付き合い方に関するビデオを送ってもらいました。この中で,「MRとの会話の場を自分でコントロールしろ」と言っています。向こうから言われることを一方的に聞くのではなく,こちらから聞けということです。しかし,具体的にどうしたらいいのかは,よくわからないですね。
そこで,本校の臨床薬理学の選択実習で,学生をMRに同行させて,MRの立場から医師がどのように見えるのかという実習を行なってみようかと考えています。
私がハーバード大にいた時にMGH(マサチューセッツ総合病院)で,メルク社のMRと1日一緒に過ごしたことがあります。あれはとてもよい勉強になりました。つまり,MRがどう医師を見て,どういう具合にアプローチしているか,つまり彼らの考え方がわかるのです。それをモデルにしたいと考えています。
上野 MRの質は高くなってきていると思います。ですから,彼らとどう接するかが,臨床の立場からは重要になると思います。
病院によっては,MRを医局に出入り禁止するところがあります。それは若手の医師の保護という名目ですが,場合によってはMRも貴重な情報源になり得ます。それは医師がしっかりしていれば,という前提ですが。
石岡 MRから情報を引き出すのも,こちらがある程度,基礎知識を持っていなければ引き出すものがありません。やはり医師がある程度,副作用の細かいことまで聞けるだけの素養がないと,うまく使い切れないような気がしますね。
医療品情報を整理する技術
上野 わが国では数多くの医薬品が市販されていて,医薬品に関する情報も膨大です。雑誌や教科書も多くなりますと,氾濫する情報を整理する技術が必要になります。特に若手の医師や多忙な臨床医に,実際的な,効率のよい方法を教えていただければと思います。石岡 私のところはベッド数100の小さな病院ですが,整理しようと思っても,内服薬335,注射140,外用137,その他50と,私が処方するのにも全部の薬剤を覚えられるわけではありません。
研修医にはよく,「基本的な処方だけ覚えろ」と言っています。例えば高血圧なら,「Ca拮抗剤,ACEインヒビター,それからαブロッカー,βブロッカー,サイアザイドと,そのぐらい覚えて,その中で特徴のあるものを2つぐらい選べばいい。βブロッカーなら,選択性の高いISAのないものと,ISAがあって歯止めが効くものと,2つぐらいを覚えておく。細かいことを各メーカーが言ってくるけども,現実に臨床で証明するデータがなければ信用しないでいい」と話しています。
自分の口で言うのもなんですが,私はわりと処方はうまいほうだと思っているのですが,それでも薬剤の数はせいぜい80から100で済みます。厚い本を買うよりも,若い先生だったら基本的な薬を50から100を覚えて,あとはどの組み合わせでうまくやっていけるかがわかればよいのではないかと思います。診断がきちんとしていれば,多くの薬を機関銃を打つみたいに出す必要はないような気がして,そういう教育を私は研修医にしているつもりです。
上野 北原先生のお考えはいかがでしょうか。
北原 「診断がつくまでは治療をするな」が私の原則です。日本の先生方は対症療法に走りすぎて,熱があれば抗生物質,痛ければ痛み止めと……。痛いのはお気の毒ですからなんとかしなくていけませんが,診断を急いでつけて,それに合った治療を行なうことが,まず最初でなければいけないと思います。
それから,本当に薬を投与しなければならないのかどうかも,きちんと決めなくてはいけません。例えば高血圧の場合,ほんのわずかに血圧の高い人をすぐに治療を始める必要はなく,食事療法や減量を試みて,3―4か月ごとに血圧を測定するなど,きちんと見きわめる必要があります。
それから,処方した薬がきちんと投与されているかどうかも問題があります。例えば抗生物質なら,保険診療で量が左右されてしまって,投与量がきちんとしていない場合もありますし,それから看護婦さんあるいは医師自身が面倒臭がって,8時間ごとに投与すべきものを12時間ごとにしか投与していないということもあります。
正しい医療情報を収集する
北原 アメリカでは,インターネットなどを使って誰でもさまざまな情報が得られます。例えば,NCI(National Cancer Institute)から,一般向けの白血病やホジキン病の治療のパンフレットが出て,どのように薬が使われるべきかがきちんと書いてあります。ところが日本では,そういった治療方法よりも,医師がその施設独自の治療を始めるという問題があります。例えばホジキン病の患者さんが関西地方に引っ越しをされた時,「こういう治療でやってきたので,その後はよろしくお願いします」と,ある大学病院に紹介しました。しかし,そこでは大学独自の治療を行なっていて,世界的に認められているホジキン病の治療は行なっていない,という返事がきました。日本では大学で自分たちのやりたいようにやり,世界で認められたものを行なわない風土があり,本当に情報を得ているのかどうかが疑問になることが多いと思います。
上野 普遍的な治療に関する情報の話がでましたが,津谷先生,薬物治療に限らず,臨床医学に必要な情報を集める方法について解説いただけますか。
津谷 現在は,情報過剰なところがありますね。情報の質はさまざまで玉石混交です。最近では,クオリティのレベルが高いことを,「エビデンスがある」という言い方をするようにもなりました。しかし,そこを見きわめる能力やトレーニングを医師が受けていない,また受けていても情報が多すぎることが基本的な問題だと思います。
EBM(Evidence-Based Medicine)と絡めてお話しすると,EBMの1つの特徴に,「プレ・アプレイズド・レビュー」(あらかじめ吟味したレビュー)を用いることがあります。個々の臨床医があふれかえる情報からいいものを見出すのが理想ですが,今の状況はそれが不可能なレベルに達していると思います。そこで,しかるべき人間や機関が予めレビューした情報を使うのが1つのやり方だと思います。それが例えばコクラン共同計画から出ている「コクランライブラリー」であったり,エビデンスに基づくガイドラインであるのですが,日本でもそういった動きがここ数年で動き始めていますので,期待をしています。
薬は本当に「効いている」のか
津谷 北原先生のお話で,「診断がつくまではとりあえず治療を始めない」ことについて,私はとても正しいことだと思いますが,2つコメントがあります。1つは,患者の満足度です。患者のほうが病気と薬について一定の情報を知っていて,患者からある治療を要求することがあります。また患者は薬を出してくれる医師をいいと思ってしまうこともあります。
もう1つは,コクラン共同計画でプラセボに関するグループがあり,そこでよくディスカッションされるのですが,世の中には正しい診断というのは半分ぐらいしかないのではないか,それでも何らかの治療をして,よくなっているのではないか。ノンスペシフィック(非特異的)な治療効果というのは,結構高いのではないかというわけです。そこでいま世界的にプラセボに関する関心が高まってきています。これは病気にもよるでしょう。日常的な疾患の場合と,専門医がある特定の領域で診断をつける場合とは違う局面があるのではないかと思います。こうしたことを北原先生はどのようにお考えになりますか。
北原 それは患者との対話できちんと説明すれば,十分だと思います。
1つの典型例として,3-4週間熱が続いている不明熱の患者に,いきなり抗生物質を始めてしまうことがよくあります。不明熱だからこそ,抗生物質が効くような病気ではないことが大部分なのに,同じような状況があるのです。
そうすると患者自身は,「これで治療が始まってよくなる」と間違った幸福感にひたるし,医師は「薬を出しているので,これでもう大丈夫」と,自分の思考能力,医師としての能力を高めることを止めてしまうことがあります。
津谷 治療は薬物によるだけではなく,コミュニケーション能力も含めて薬物療法があるということですね。
北原 そうです。その点は少し違った立場のインフォームド・コンセントになるのでしょう。説明をしない限りは,患者さんは納得しないと思います。
津谷 コミュニケーションが大事であることはよくわかります。しかし,現実に限られた時間の中でたくさんの患者さんをみようと思うと,コミュニケーションよりも薬をシンボリックに出すことに流れやすい状況もあるのではないかという気がします。
上野 確かに薬物治療だけが独立した治療ではないと思います。
津谷先生はプラセボのことをおっしゃいましたが,同じ薬を出しても医師によって効く場合,効かない場合はいくらでもあると思います。
津谷 北原先生,上野先生には,本書(『内科医の薬100』第2版)が改版される時には,ぜひプラセボを加えてもらいたいと思います。
オランダの「Farmaco-therapeutish Kompas」という,米国のPDR(Physician's Desk Reference)に相当する本の中には,プラセボが入っています。カプセル剤と液剤があり,さまざまな色や味のものがあり,患者の状態に合わせた処方ができます。日本ではビタミン剤などをプラセボ代わりにすることはあっても,プラセボが薬物療法の本にのることはありません。しかし公定書に載っている国もあるのです。
プラセボというと,日本人はなんとなくネガティブなイメージがあるようです。それはおそらく「偽薬」という訳からで,「I shall please」という本来のポジティブな意味が抜けているからでしょう。プラセボをうまく使えるようになると,日本の医療費もずいぶん減少するのではないかと思います。
上野 薬物治療中の患者の具合がよくなっていく場合に,これは明らかにプラセボ効果であろうという判断ができる例は多いと思います。ある程度患者をきちんと見ていればわかるはずで,それを薬が効いたと思って脳天気になっている医師が多いことが問題だと思いますね。
津谷 それは習練によってわかるということですね。
上野 そう思います。臨床現場ではそういう判断をしております。
患者との対話が大切だということですが,実際外来を受診された患者とよくお話すれば,ただ薬をもらいたい人なのか,あるいはまずはっきり診断をつけてほしいのかがわかります。後者のように患者にやたら処方するわけにはいきません。
薬を限定すること
上野 北原先生が以前に,「臨床医の能力と処方する薬の数は反比例する」とおっしゃっていたのを覚えています。津谷 本書(『内科医の薬100』)の初版の序文の中で,お二人の先生方は,大事なのは「常用する薬剤の種類を制限することだ」とお書きになっていますね。
先ほど石岡先生は,日本人の持つ「薬師観」について話されました。私は日本を含めてアジアは多様性をよしとする文化を持っていると思います。日本の文化がいくらアメリカナイズされても,「多様な薬を使える」のはよいことで,限定することは何か悪い,ネガティブなことのように受け取られてしまいます。そんな文化の中でお二人の先生はよく「大事なのは限定することだ」と言い切って書いたものだと思います。
上野 北原先生もそうでしょうが,私もアメリカで臨床教育を受けてから帰国した時,日本には驚くほど薬が多くて,とても覚えきれませんでした。そこで,基本的な薬剤だけをきちんと押さえればいいだろうと考えたのです。結局は石岡先生とまったく同じ意見になりました。
石岡 私のところは高齢の方をお預かりしていて,痴呆の方がほとんどなので,患者さんと話し合うことが不可能な病院です。そうすると,ますますこちらが責任を持って診断をしなくてはいけません。そうすると,薬を出すことが逆に恐くなってきます。そういう環境のもとで仕事をするのもいい訓練になるのではと,研修医をお迎えしています。
EBMを薬物治療に反映させる
上野 医薬品や医薬品情報が氾濫しても,基本的な線をおさえれば,多過ぎはしないということに尽きると思います。あとは,日常の診療に頻繁に使うものは別として,稀なもの,たまに使うものの情報収集をどうしたらいいかという問題が出てきますが,それに関しては系統だった情報収集が必要になると思います。最近の流行りでもあるEBMを,薬物治療の上でどのように活かしていくかについて,EBM推進者の1人である津谷先生のお考えをお聞きしたいと思います。
津谷 いわゆるEBMは,薬物治療だけに限らず,他の治療法あるいは検査や診断などさまざまな分野をすべて含めての話だと思います。しかし,中身は特に目新しいものではないですね。最近東大で衛星を使い何校かの大学で共通して受講する医療情報学の講義が始まり,そこで私は,EBMとコクラン共同計画のことを90分ほど話をしました。その後,学生から「今日の講義のポイントは何ですか」と質問を受けました。そこで考えてみると,ポイントも何もなくて,当たり前のことを教えたわけです。
上野 逆に言うと,当たり前じゃないことがずいぶんなされているということにはなりませんか。
津谷 そういうことですね。「エビデンス」の逆の言葉はおそらく「バイアス」ではないかと思います。バイアスがなるべく入っていない,入る可能性の低い情報を使うことだと思います。EBMはキャッフレーズとして,またムーブメントとしてはとてもよいのではないでしょうか。Clinical epidemiologyも「臨床疫学」とすると,「疫学」という古い倉庫から引っ張り出したような言葉ですし。EBMはある意味では,いろいろなことを変える1つのキーワードにはなると思います。
上野 信頼できる証拠を求める能力ですね。これも早いうちから医学教育の中に取り入れなくてはいけませんが,学生が興味を持ってくれるのがどの時期かという問題になると思います。
津谷 そうですね。私はWHOから出ている『Guide to Good Prescribing』を『P-drugマニュアル』(医学書院)として訳しました。この本を紹介した論文に「早めに教育することは非合理的薬物使用に対する予防接種だ」と書いてありました。大変よい言葉で,それこそエビデンスの高い「予防接種」を,早めに行なえばよいのですね。
正しい薬物治療を行なうために
上野 日本の薬物治療について,従来の問題点,多過ぎる医薬品の情報をどう乗り切るかとか,EBMの話などお聞きしました。これらを踏まえて,今後正しい薬物医療はどうあるべきかという点につき,お話しいただきたいと思います。石岡 トゲのある発言とは思いますが,勉強しない先生が薬を増やしていくという印象を持っています。例えば利尿剤を1種類使えばいい時に,日本だけで使われている強心剤,あるいはビタミン薬を加えていくのは,結局何回も繰り返されているように,その薬の本質や作用を知らないからです。
また,構造式が同じなのに,薬品名が違うから違う薬だと思っていたとか,そのような基本的な知識を加えていけば,効かない薬,ちょっと疑問がある薬はもう一度見直してみようと思うのでないですか。知れば知るほど使う薬は減って,本当に必要な薬だけになるとと思います。
上野 また使う薬が減れば,その薬について詳しいことも勉強できますしね。
石岡 新しい薬を使わなくてはならない時に,もう1度,文献等を読んでこれを加えたらどうなるか,副作用,相互作用,相乗作用が出てくることが,最近はそのような情報が豊富になってきていいと思います。
上野 自信のない臨床医は,いろいろな薬を知らないと不安になる,という気もします。堂々と「そんな薬は知らない」と言えばいいと思います。ほかの医師が知らない薬を投与していた患者を引き継ぐ場合も,調べれば済むことであって,すべてを知っている必要もないと思います。
石岡 まだ日本では,医師同士で患者の情報を伝達することが十分行なわれていませんし,薬歴もほとんど伝達されません。そういう面もこれから反省しなくてはいけないと思います。
P-drugの考え方
上野 津谷先生は,これから若い臨床医が薬物治療を学んでいく上で,臨床薬理学的な面からのアドバイスをお聞かせください。 津谷 具体的な改善策としては,私はさきほど述べた「P-drug」(本紙2272号参照)というコンセプトを日本に広めようと思っています。
津谷 具体的な改善策としては,私はさきほど述べた「P-drug」(本紙2272号参照)というコンセプトを日本に広めようと思っています。
「P-drug」はpersonal drugの略で,ここでpersonalというのは医師のことです。つまり医師が使う薬のリスト,昔の言い方で言いますと「自家薬籠中の薬」をまず正しく形成する,(1)診断,(2)治療目的の特定,(3)inventoryの作成,(4)クライテリアに従った薬物群の選択,(5)P‐drugの選択,という5つのステップを取ります。次いで,それを実際の患者の治療に適用するのです。ここでは,(1)患者の問題の定義,(2)治療目的の特定,(3)P‐drugの適切性の確認,(4)処方箋を書く,(5)情報を与える,(6)治療をモニターする,の6つのステップを取ります。これを問題解決型(problem‐based solving)で教えていくのです。
新しいコンセプトを広めるにはいろいろなやり方があると思います。今考えているのは「ティーチング・ザ・ティーチャー・コース」で,教える人を育てる場を設けることです。浜松医大の臨床薬理学教室(大橋京一教授)が中心となって,毎年12月,浜松で臨床の場を主体にした「浜名湖臨床薬理セミナー」を12月に開いています。今年は12月5日(土)にあり,それと関連して翌6日(日)に,「P-drug教師用ワークショップ」を行なう予定です(事務局=コントローラー委員会〔担当・清野〕:TEL03-3791-0202/FAX03-3791-0191)。これを各地で続けようと思っています。
医学部や病院で核となる人材が,そこでトレーニングを受けて,次いでエコースタイルでいろいろな場所で教える,というようなことができればと考えています。
上野 教育者の育成に関しては,北原先生からも,実際にきちんと教えてくれる人がいないのが問題だとご指摘いただきました。今後は,津谷先生にリーダーシップを取って広めていただければと思います。
津谷 まず仲間を増やそうと思っています。
賢い医師になる
 上野 北原先生,これからの薬物治療の方向性をおまとめいただきたいと思います。
上野 北原先生,これからの薬物治療の方向性をおまとめいただきたいと思います。
北原 私が受けてきた医学教育では,「さじ加減」といった,本当にエビデンスのない治療方法を教わってきました。今後はEBMの観点からみた薬の使い方が重要だと思います。すべての治療方法がEBMにのっとっていませんので,EBMのデータのない治療を行なうには,きちんとした施設できちんとした人が書いているものを見て臨床に活かすことが必要です。
一方,欧米のEBMで出されたデータを 100%日本に移せるかという問題が,どこにでも絡んでくると思います。例えば,抗癌剤の投与量にしても,アメリカでは100mg/m2が癌に効く量であったものを,日本でそれを75mg/m2と,適当に翻訳して使い始めているんですね。そのあたりの問題は,やはり臨床薬理学の方々に責任の一端があるのではないかと思います。今はどうしても欧米のデータを日本にスライドさせているのが現状ですが,それが本当に日本に正しく伝わっているかは疑問であると思っています。
教育に関しては,私たちの病院では,若手の医師に『ワシントンマニュアル』に加えて,4-6頁の小冊子である『メディカルレターズ』を読むことを勧めています。これは新しい薬が市販されると,今までの薬との効力の有効性の比較に加えて,最後に必ず経済性についてもコメントされます。市販の抗生物質と新しく売り出された抗生物質を7日間使った場合に,どれだけ値段が違うかという表が必ず記事になります。今後は,新しい薬が市販された場合には,治療という側面だけでなく経済性という点も考えて,賢い治療を行なっていける医師になってほしいと思います。
上野 北原先生が『ワシントンマニュアル』や『メディカルレター』をお勧めになるのは,多忙な研修医が自分でクリティカル・アプレイザルを行なう時間がなければ,信頼できる誰かが流している情報を信頼するということですね。先ほどの津谷先生のお話と共通すると思います。
本日はいろいろと立場の違う先生方にお集まりいただき,多岐にわたるお話をいただきました。ありがとうございました。


