第35回日本リハビリテーション医学会開催
「21世紀におけるリハ医療の位置づけ」をテーマに
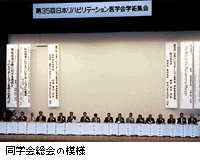 超高齢社会の到来を目前にし,2000年からの公的介護保険の実施など,医療は財政策を含めた変革が迫られ,リハビリテーション(以下,リハ)医療も,これまでの施設内リハから,在宅へ向けた対応が求められるようになった。それを裏づけるように,訪問看護事業などにもリハ担当者が参画しはじめている。
超高齢社会の到来を目前にし,2000年からの公的介護保険の実施など,医療は財政策を含めた変革が迫られ,リハビリテーション(以下,リハ)医療も,これまでの施設内リハから,在宅へ向けた対応が求められるようになった。それを裏づけるように,訪問看護事業などにもリハ担当者が参画しはじめている。
そのような中,第35回日本リハビリテーション医学会が,さる5月28-30日の3日間,「21世紀におけるリハ医療の位置づけ」をテーマに,福田道隆会長(弘前大教授)のもと,青森の青森市民会館や青森厚生年金会館などを会場に開催された。
本学会では,特別企画として海外からの4名の招待講演,会長講演「脳性障害におけるリハの展望-脳性麻痺・脳卒中を中心として」,シンポジウム(1)脊髄損傷治療における現状とリハ医療の位置づけ,(2)高次脳機能障害(失語症)治療における現状とリハ医療の位置づけ,パネルディスカッション(1)脳性麻痺治療における現状とリハ医療の位置づけ,(2)脳卒中治療における現状とリハ医療の位置づけ,(3)介護保険とリハ医学の他,6題のセミナー,4題の研修セミナー,さらには青森市制100周年を記念する一般市民を対象とした医学公開講座も行なわれた。本紙ではこれらの中から,シンポジウム(1)および会長講演を取り上げ報告する。
脊髄損傷とリハ医療
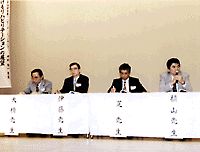 同学会のシンポジウム(1)「脊髄損傷治療におけるリハ医療の位置づけ」(座長=弘前大 原田征行氏,横浜市大 安藤徳彦氏)では,整形外科医,リハ医ら4名が登壇し,治療や患者支援システムについて,それぞれの考えを述べた。
同学会のシンポジウム(1)「脊髄損傷治療におけるリハ医療の位置づけ」(座長=弘前大 原田征行氏,横浜市大 安藤徳彦氏)では,整形外科医,リハ医ら4名が登壇し,治療や患者支援システムについて,それぞれの考えを述べた。
手術治療の成績
まず,植山和正氏(弘前大・整形)は,同大学病院の1978年以降に入院治療した59名の頸椎および頸髄損傷(以下頸損)患者(12-82歳,平均年齢;男47.5歳,女性53.5歳)について検討。受傷原因では,「交通事故21例(35.6%),転落事故(高所転落)16例(30.0%),転倒,スポーツ受傷等であり,受傷部位ではC3/4レベル20例と最も多く,手術施行45例では受傷から手術までの日数は平均48日,術後からリハ開始までが平均9.5日(39例),術後から座位に至るまでが23.1日であった」と報告。また「手術はあくまで整復固定を前提としており,社会復帰をめざし早期リハを開始しているが,肺炎などの合併症を起こすことも多く,現状では自宅退院は20.3%にすぎない。患者は転院がほとんどで,施設間の連絡を密にするなどの社会的受け入れ体制の構築が望まれる」と述べた。芝啓一郎氏(総合脊損センター・整形)は,「胸椎・腰椎損傷に対する手術的治療の目的は,損傷脊椎の構築学的再建と強固な内固定を行なうことによって,簡易な外固定での早期離床とリハを促進すること」として,「急性期胸椎・腰椎損傷治療の変遷と現況」を報告。
芝氏は,急性期患者のヘリコプターによる搬送が増えてきた事実を語るともに,2次損傷の予防,早期離床を目的に治療を行なった結果,75%の症例(平均37歳)が4週以内に離床を可能にしていることを述べた。また内固定法の変遷として,1979年のハリントンシステムや,1986年からのtrans-pedicular fixationの導入経過や問題点を述べ,ハリントンインストルメンテーションの有用性を解説。1995年からは,リハ医の指示により,手術翌日からベッドサイドでリハを開始することで,11-12週で院内自立歩行が可能になっていることも報告し,「慢性期のリハ治療の促進や患者のコミュニケーションの向上に,また急性期の評価や治療法の改善,進歩に有用であった」とまとめた。
脊損患者の生活支援へ向けて
一方,伊藤利之氏(横浜市総合リハセンター・リハ)は,「頸損のような高位脊髄損傷(以下脊損)患者の受け入れは,一般医療機関ではなく労災病院や総合リハセンターなどの専門病院に限られている。その原因としては,専門医の不足,看護体制の不備,医療の不採算性などが考えられる」として,10年間のデータを基に,主に在宅生活をしている頸損患者(114人,平均44歳,完全麻痺60%,リハ経験あり86%)の生活上の問題点,必要なサービス,効果的なリハのあり方などを検討した。伊藤氏は,「50歳以上の頸損患者は45%であり,高年齢患者のほうが死亡率が低いというデータ結果であったが,医療機関で受けられるサービスを受けないまま在宅生活を余儀なくされている高齢在宅患者もいた。急性期での看護,介護手段も重要だが,在宅支援へ向けた地域リハの充実は緊急焦眉の課題。年々変わる患者の状態への対応には訪問看護ステーションの活用,リハ医の協力,連携が必要。在宅リハサービスの充実を図るには,高齢化,核家族への対応も考慮したシステムの構築が重要」と述べ,公的介護保険制度をにらんだ対策がリハ医療に必要と強調した。
最後に登壇した大橋正洋氏(神奈川県総合リハセンター・リハ)は口演の中で,「アメリカでは,1995-2000年のモデル事業として,全土18か所の脊損センターで,リハ医が主体的に脊損治療にかかわる事業を展開している」とテキサスリハセンターの例を紹介。また,脊損患者の現状として「褥瘡や泌尿器疾患などの他臓器におよぶ多種合併症を起こすことや高齢化が問題になっている」と指摘。その対策として,「脊損病棟やリハ医だけで解決できる問題ではなく,患者のQOLに沿った医療の展開にはチームワークが不可欠。リハ医はその要となる必要があり,データベースの構築から他科へ訴えかけることも重要。複数のリハ関連職が,患者が必要とする時に的確なサービスを提供できる包括的なシステムの形成が期待される」と述べた。
高齢化する患者と在宅リハで論議
また,総合ディスカッションの場では,「65歳以上の人工呼吸器をつけた頸損患者でも,リハを行なうことで気分転換が図れることが大切。看護職,セラピストらの協力が必要だが,合併症があってもリハはすべきであろう」(芝氏)
「アメリカでは,合併症がある患者だけでなく,若年者を積極的に救おうということから,各施設間でデータ構築へ向けた連携を取り合っている」(大橋氏)
「脊損だけではく,他の患者も引き受けざるを得ないシステムも問題だが,看護体制の不備が問題。量的な解決策が最重要課題である」(伊藤氏)
「大学病院では,他科からの来診は難しい」(植山氏)などの問題に関して論議されるとともに,これからの在宅リハが話題になった。
地域で在宅リハを実践している伊藤氏は,「介護なしの在宅は考えられない。また在宅は医療だけで支えられるものではなく,医療・福祉の連携が必要。看護職,介護職がどれだけ脊損などを理解しているかが問題だが,バックとしてのリハ医の存在が重要。リハセンター,脊損センターは訪問看護ステーションの前線基地として活用されるようになるのが望ましい」と述べた。
EBMを基本としたリハ医学の構築を
福田会長は,大学病院でのリスクベビーおよび脳性麻痺児558名,発作直後から入院し機能訓練を受けた脳卒中患者1092名の調査結果に基づき,(1)大学病院でのリスクベビー,脳性麻痺の初診時および経過中の問題点,(2)関連病院での脳卒中リハの現況と問題点,(3)将来展望について,(4)システムとしての医療の4視点からの「脳性障害の治療の現状と将来展望」について分析,その考察を会長講演の内容とした。講演の中で福田氏は(1)に関し,初診時に脳性麻痺との診断がついた症例は558例中81例であり,最終診察時には四肢麻痺35名,片麻痺19名,両麻痺19名,対麻痺4名,アテトーゼ6名の83名(14.8%)であったと報告。これらの症例のリスクや因子および臨床所見との関連を検討,「脳室周囲白質軟化が低出生体重児の脳性麻痺の大きな要因になっている」と指摘した。さらに,呼吸障害などの合併症を持つ超低出生体重児の症例を紹介し,高ビリルビン血症,仮死などの出血性脳室拡大発症後の危険因子と予後についても解説を加えた。
(2)では,脳卒中の発症時の平均年齢および入院日数が1978-85年で64.7歳,272.6日,以降69.7歳,179.7日(86-89年),69.4歳,96.0日(90-93年),71.6歳,88.2日(94-97年)と,発症年齢と反比例し入院日数が減少,現在28日までになったと報告。なお,初回発作から再発までの期間は平均で5.2か月だが,「再発作における尿失禁は32%,体幹バランス障害23%,心疾患が22%あり,言語障害と併せて再発作時の特徴になっている」と指摘した。
(3)に関連しては,脳性麻痺児の早期療育の意義,保育の役割,健康に対するチェック項目について述べるとともに,「(1)疾病の特徴を正確に把握し,将来の見通しと限界を知り,適切な治療の選択をする,(2)病的パターン化した動きを軽減し,変化のある動きを与える,(3)摂食,易感染,てんかん,睡眠リズム,呼吸,遊びや言語発達に関連する認知障害などを考慮する,(4)両親に十分な情報の提供を行ない,よけいな不安を親に与えない,(5)廃用・誤用・過用症候群は障害児にも存在することを考慮する,(6)一時的な効果よりは長期的展望に立った効果を期待する」などを脳性麻痺治療において考慮すべきことにあげた。また,急性期,回復期,維持期の時間的経過としての3相構造に対応する機能回復過程として,自然回復,身体・心理的回復,QOLの維持期の3段階変換機転をあげ,「この3段階の回復過程は年齢,疾患の重症度,合併症の数により異なり,3相構造とは必ずしも一致しない。そのための個別的な早期集中リハ治療,間歇的頻回リハ治療などのプログラム設定が重要」と示唆した。
(4)では,「脳障害のリハは,単に運動障害のみならず,認知障害,失語・失行・失認,痴呆などの高次機能障害,精神機能障害を合併することが多い。21世紀を迎えるにあたり,リハ医師は国民や他の診療科のスタッフから何を期待され,保健・医療・福祉の中でどのような位置づけをすべきかについてしっかりとした基本理念を持つべきである」と述べ,「日本ではDRGなどの定額医療費支払い制度が検討されているが,リハ医はこれらの動きをもっと重大なこととしてとらえなければならない。また,患者の失われた機能とQOLを考えて問題解決にあたらなければならない」と指摘。さらに,「科学としてのリハ医療,応用技術としてのリハ医療の相乗効果を図るリハ医学の構築のためには,EBMを基本とした脳科学研究が必要」と結んだ。
