アメリカ家庭医療学専門医として考えること
寄稿神保真人 First Health of Carolinas Family Care Center Medical Director
 私は,現在アメリカで家庭医療学専門医として5年目を迎えている。小学校から高校卒業までをアメリカで過ごし,帰国後,医学部および卒後内科研修を慶應大学で修了した私は,1993年より機会を得て,アメリカ・フィラデルフィアのトーマス・ジェファーソン大学病院で家庭医療学(Family Practice)研修医となった。3年間の研修を最終年度はチーフレジデントとして1996年に修了し,専門医の資格をとり,今日に至っている。
私は,現在アメリカで家庭医療学専門医として5年目を迎えている。小学校から高校卒業までをアメリカで過ごし,帰国後,医学部および卒後内科研修を慶應大学で修了した私は,1993年より機会を得て,アメリカ・フィラデルフィアのトーマス・ジェファーソン大学病院で家庭医療学(Family Practice)研修医となった。3年間の研修を最終年度はチーフレジデントとして1996年に修了し,専門医の資格をとり,今日に至っている。
押し寄せる医療市場自由化の波
現在,J-1ビザを持つ外国人医師が米国の永住権を取るのは,非常に困難である。だが,いくつか抜け道は残されていて,私の場合,ノース・キャロライナ州の医療過疎地域で3年間医療従事する条件で,永住権取得が約束されている。これは,アメリカ人医師が,医学生時代に負った多額の学資ローンを政府に肩代わりしてもらう際にもよく使われる方法である。興味深いのは,このような地域でも近年,医療市場自由化の波が押し寄せ,病院や診療所の吸収・合併が盛んに行なわれていることである。現に,私が昨年より勤めているモントゴメリー郡診療所も2年前にファースト・ヘルスという非営利医療組織に吸収された。この組織は,私の診療所より東方45キロに位置するゴルフで有名なパインハーストに本部を構え,2病院,11診療所,2老人ホーム,1ホスピスを抱え,なお拡張中という一大グループである。
感銘を受けたインタビュー
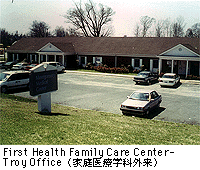 さて,日常の診療であるが,病院と老人ホーム入院患者の回診以外は,1日の大半を外来で過ごす。年齢や性別に関係なく,プライマリ・ケアを実践する家庭医療学では,実際,多種多様の患者を診る。例えば,4か月乳児の検診の次は74歳の肺気腫患者,次は職場の事故による裂傷の急患,という具合である。
さて,日常の診療であるが,病院と老人ホーム入院患者の回診以外は,1日の大半を外来で過ごす。年齢や性別に関係なく,プライマリ・ケアを実践する家庭医療学では,実際,多種多様の患者を診る。例えば,4か月乳児の検診の次は74歳の肺気腫患者,次は職場の事故による裂傷の急患,という具合である。
ここで私がいつも考えるのは,僻地医療の面白さ,難しさもさることながら,臨床現場での家庭医療学とはどういうものか,ということである。もともと内科専門医であった私は,1991年トーマス・ジェファーソン大学病院で家庭医療学を見学した際,幅広い患者層のみならず,患者の訴えを生物医学的立場からだけでなく,心理社会学的な立場からじっくり聞いていく姿勢に感銘を受けた。それは,自分が知っていた内科や精神科のアプローチとは異なるもので,より柔軟性に富み,患者の訴えを枠に当てはめることなく検討していくため,むしろ見落としが少ない印象を受けた。研修中も,患者の本当の受診目的は何か,患者に安心感を与えるにはどうすればよいか等,具体的なコミュニケーション改善の訓練を受けた。お陰で,研修2年目に,歩行困難を訴えて受診した若い黒人男性にエイズの宣告をした時など,相手の心の痛みに共感するとともに,より強い信頼感を得ることができたと思っている。
効率性の重視へシフト
ひるがえって,現在はどうか。まず時間的余裕がない。医療市場自由化は,効率性を重視するため,再診患者は15分,初診患者でも30分以内に診ることが要求される。いわゆるBottom Line(最低診療限度の徹底)であり,研修医時代にかけていたような診療時間の長さでは,あっという間に遅れをとってしまう。もっとも,日本の外来の殺人的な混雑からすれば,ずっとゆったりしていると思われるであろう。しかし,患者の期待度が違う。高血圧患者の場合,通常3-6か月に1度の受診であるが,問診,理学的所見に加え,処方箋と薬副作用の確認,食事や運動内容,喫煙の有無,職場や家庭でのストレス,コレステロールや他の冠動脈疾患危険因子について指導していくと15分はたちまち過ぎてしまう。
さらに終わりに近くなって,「先生,実は最近めまいがするんだがね」と聞かれるともういけない。(これを予め察知するためにも,研修医時代は,「他に何かありませんか」と問診終了時には必ず聞け,と教えられた)。また日本では保健所,学校,職場等で行なわれる予防接種,定期検診,癌スクリーニング,人間ドック等が,アメリカでは個人レベルで診療所がほぼ一手に引き受けるため,かなりの予防医学や公衆衛生の知識を要求される。1日で30人を診た後などは,30ないしそれ以上(付き添ってくる家族も問題を抱えてくることもあるので,家族療法になるようなこともある)の異なった人生と関わった疲労感が,ぐっと肩にのしかかってくる。
多様な人生に深く関わる
しかし,多種多様の人生に深く関わるところに家庭医療学の醍醐味もあるのだと思う。ある76歳の白人の女性。動悸,めまい,ふるえを訴え,当診療所を受診した。明らかな理学的異常所見はみられず,心電図も正常。さらに詳しい問診で,本人が長年使っていたベンゾジアゼピン系安定剤を,前医が突然中止したことが判明。再び少量より開始し,徐々に減らしていくことに成功。血液検査も正常で,再診時には,本人も以前の自分に戻った気がすると言った。そのとき,なぜ安定剤を使っていたのか聞いてみた。本人は不眠症のためだと言う。さらに聞くと,どうもうつ病の症状のようである。「自殺を考えたことはありませんか?」黙って頷く。「……これまで他人に話したことは?」「ありません。先生が初めてです。You are the only one who asked.」
現在,彼女は定期的に抗うつ剤の処方箋とカウンセリングを受けにやってくる。精神科・心理カウンセリグも勧めてみたが,現在のところは他に行く気がしないと言い,最近は笑顔もよく見られる。
全患者が彼女のようにうまくいくわけではないし,どの段階で専門家に紹介するか,いまだに悩むことも多い。しかし,これを会得するのも医学のアートの1つだと思い,日夜診療に励む今日この頃である。6つの診療所を統括するメディカル・ディレクターの仕事や,今秋仕事と並行して学生として始めるノース・キャロライナ大学チャペルヒルの公衆衛生学修士(Master of Public Health)プログラム(テレメディアやインターネットを通じて学べる3年プログラム)については,再び紙面をお借りして紹介できたらと思っている。
